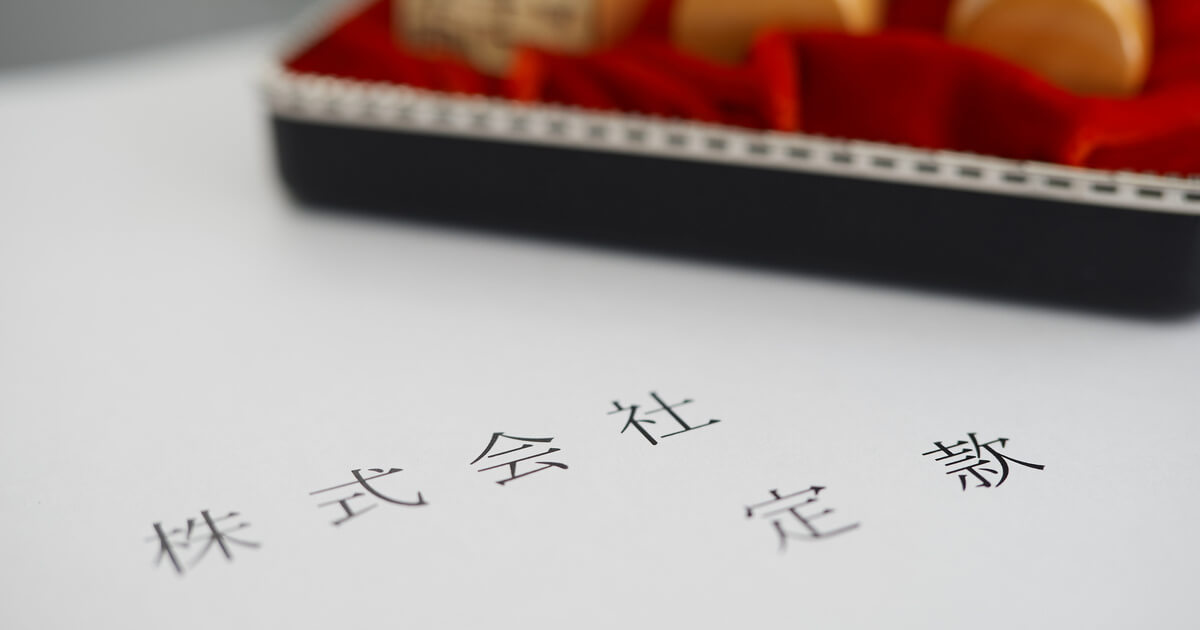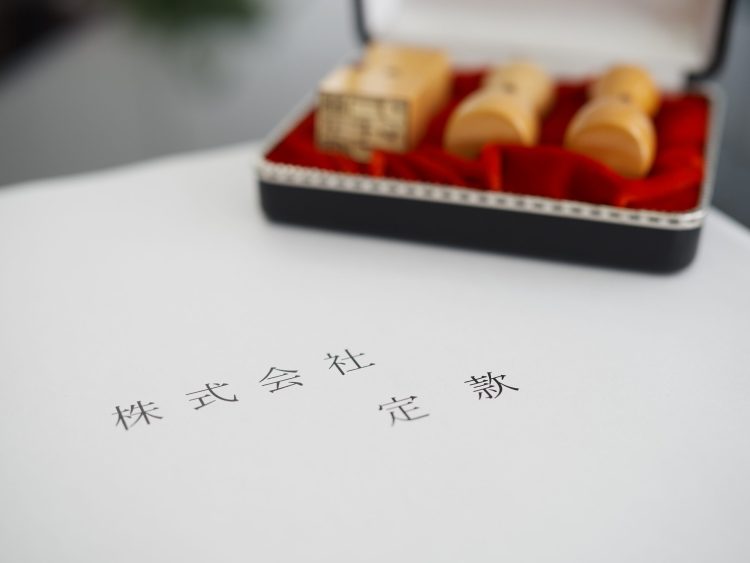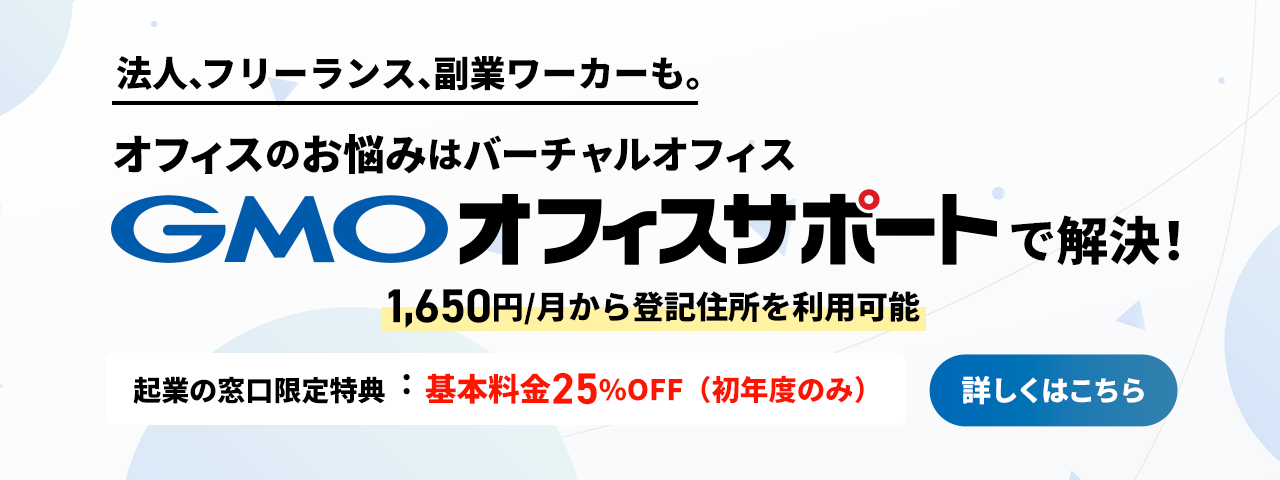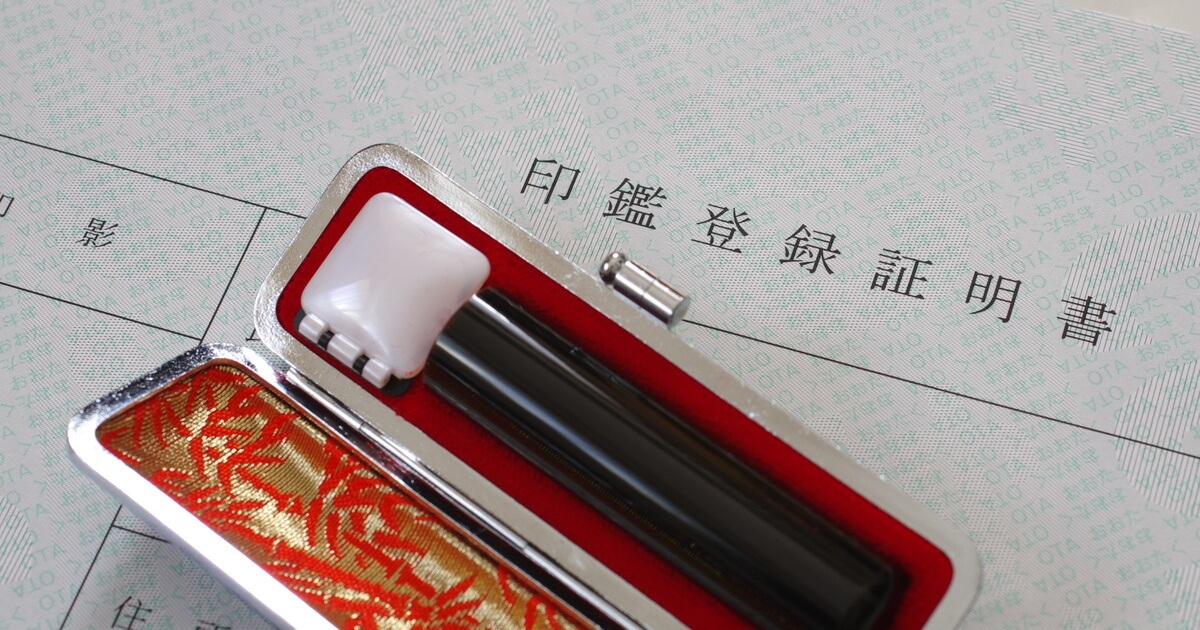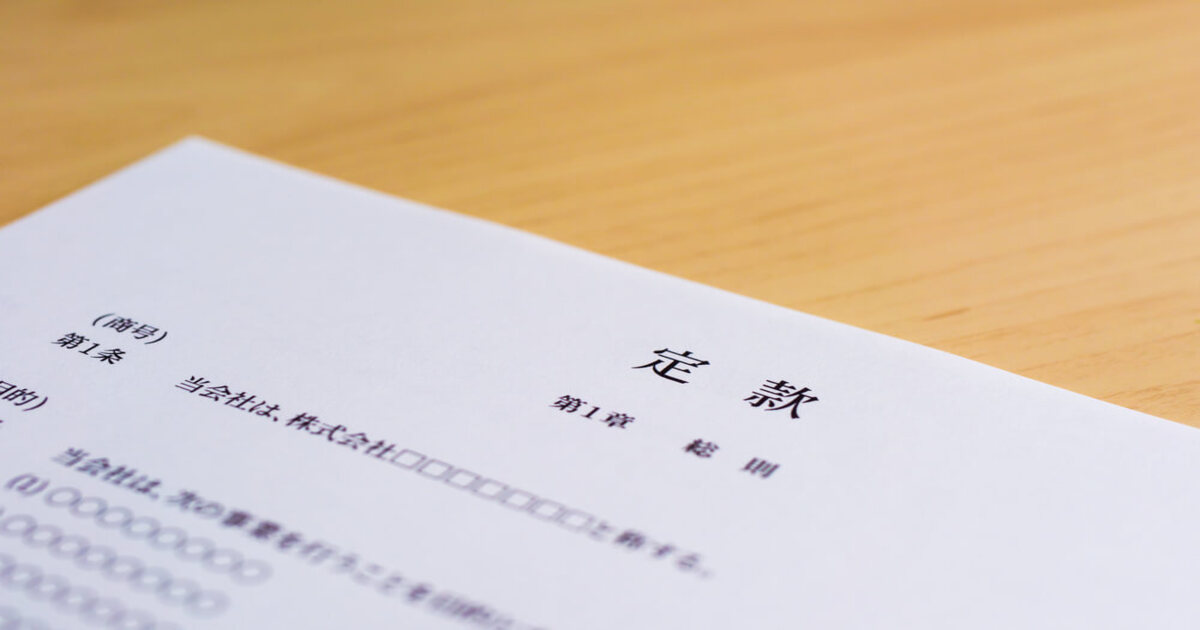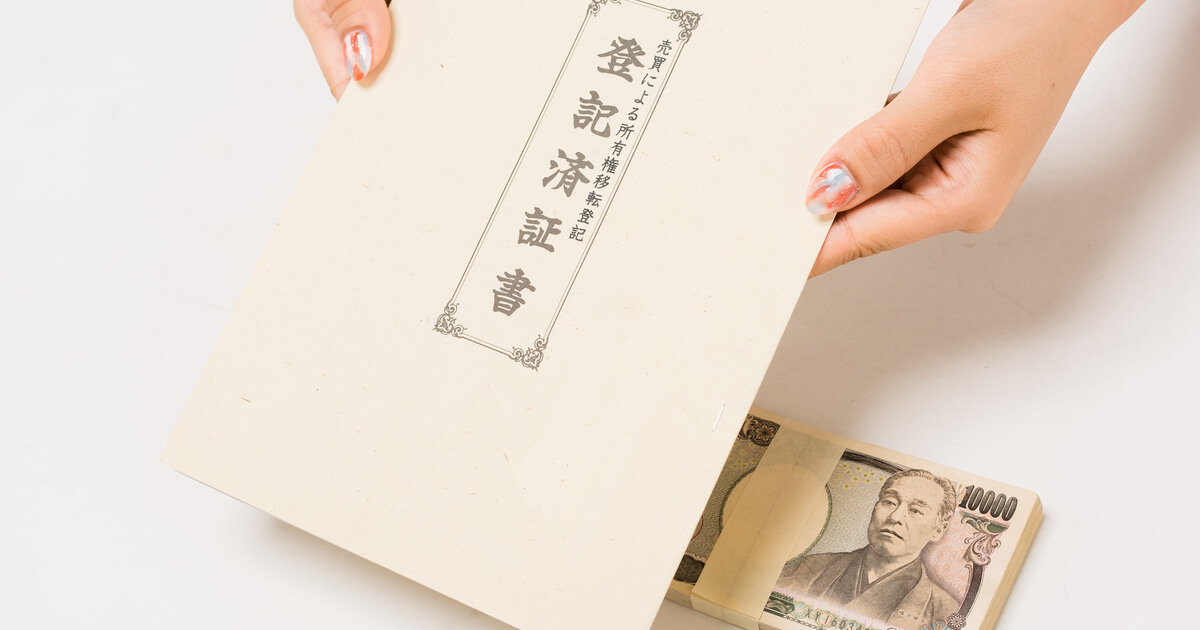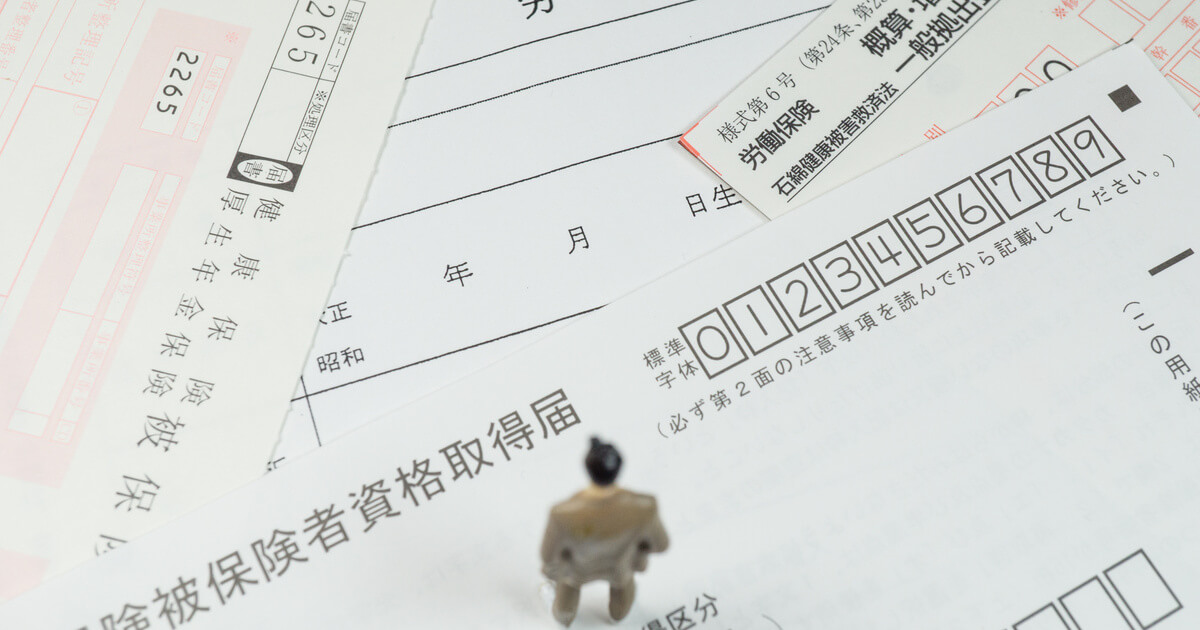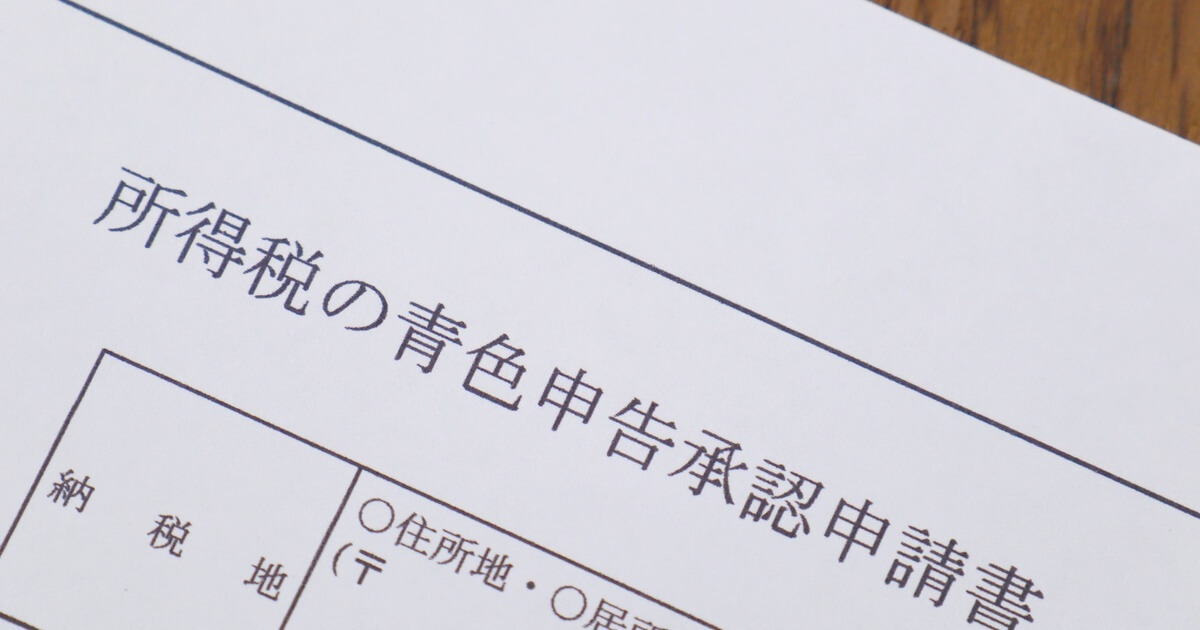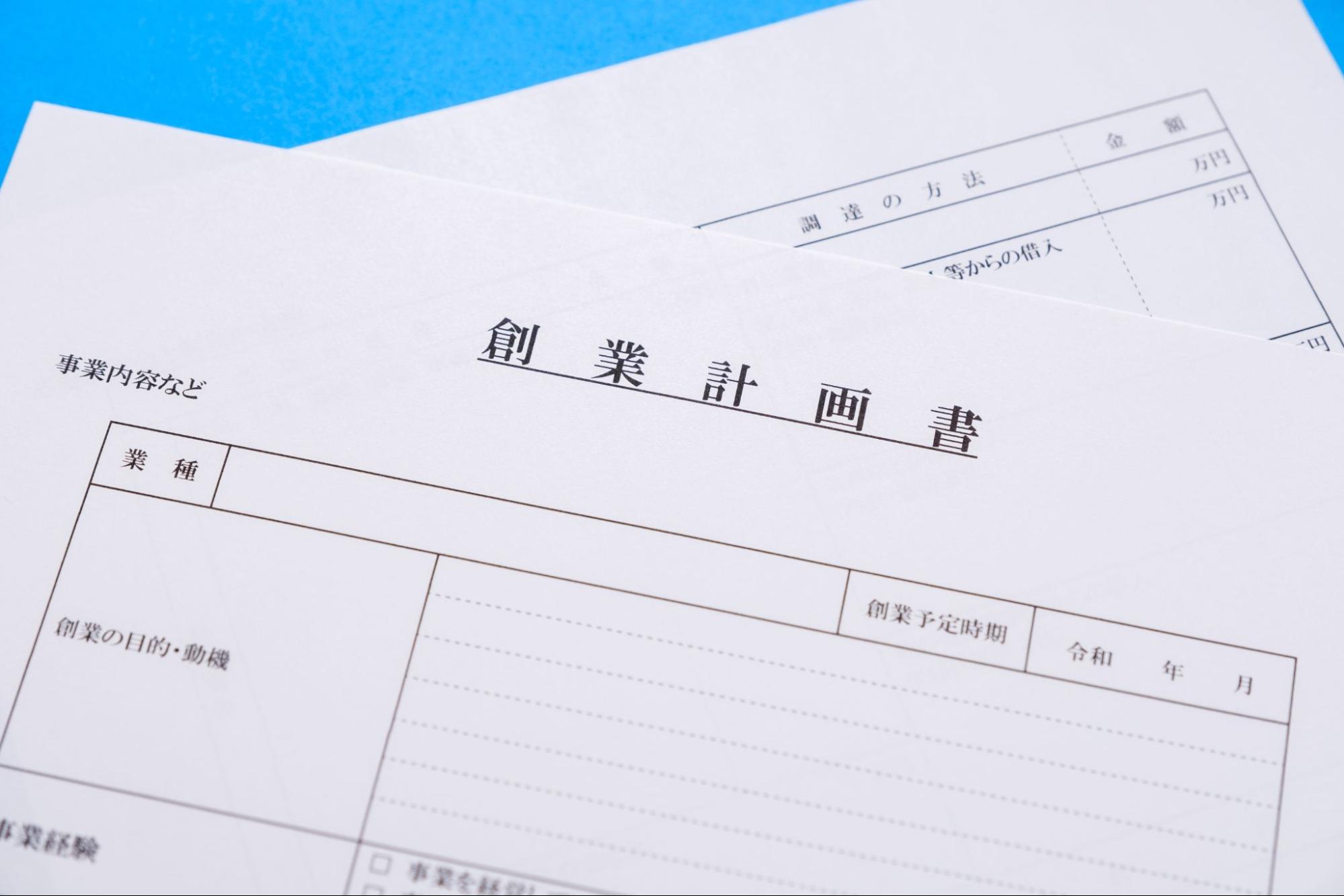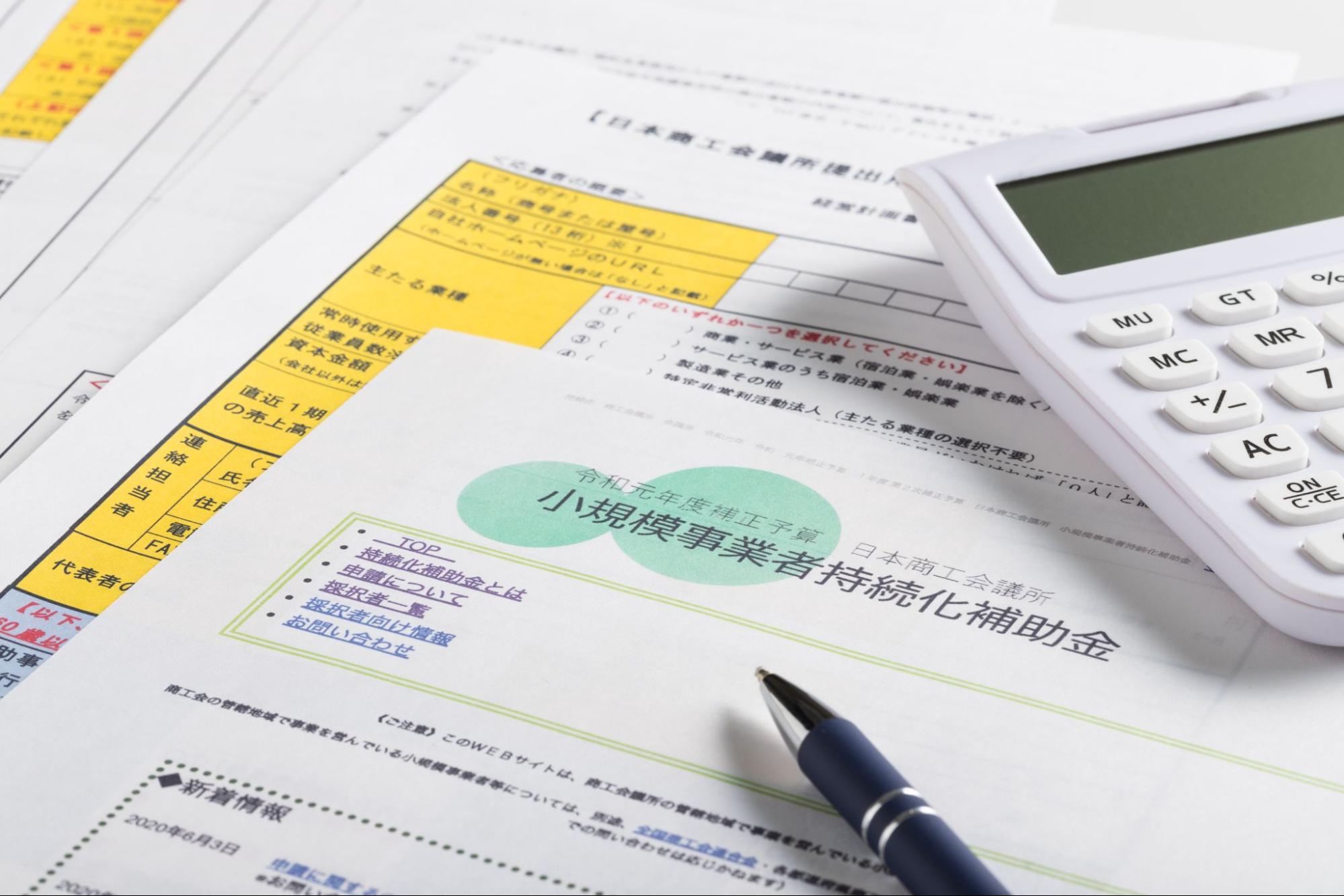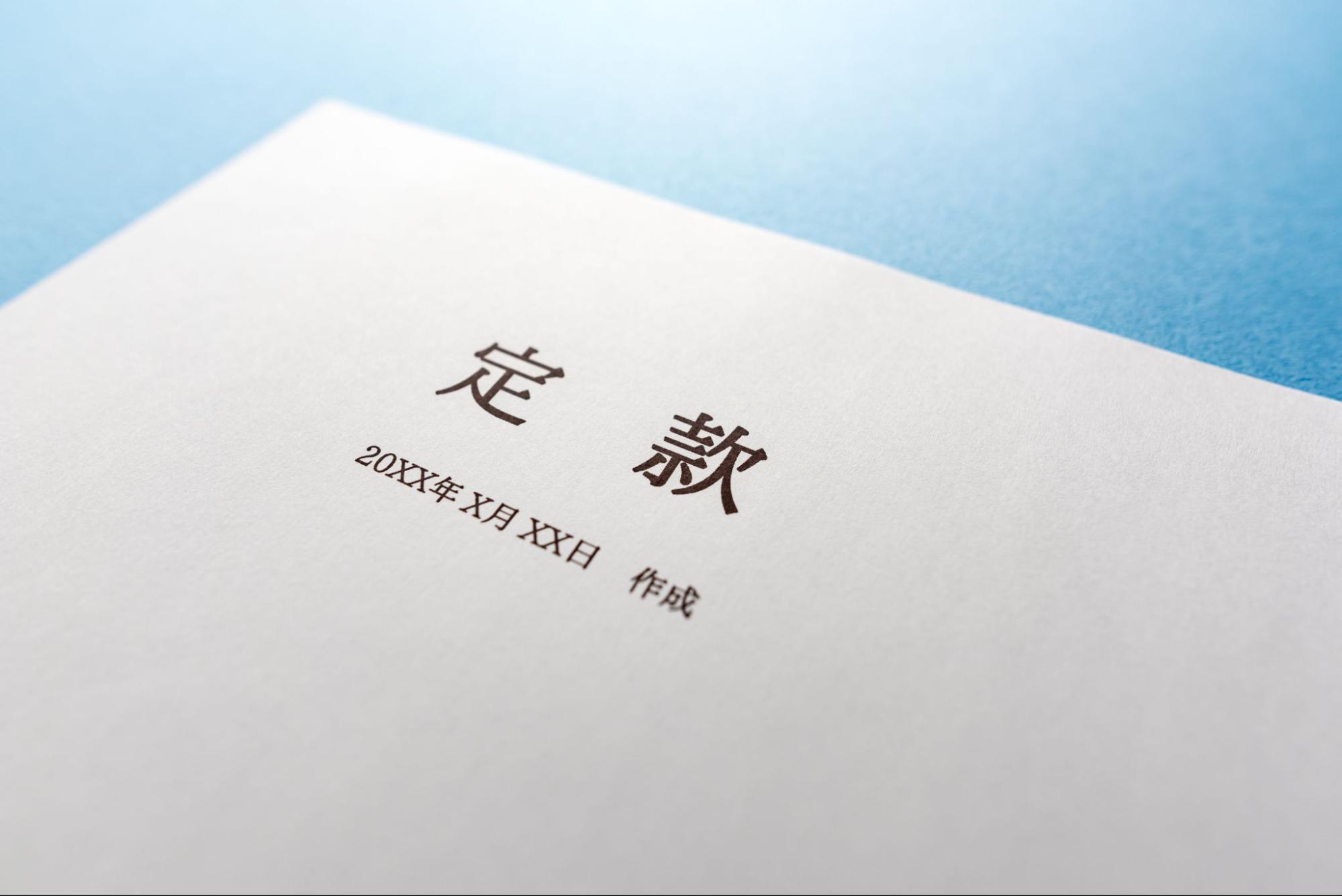会社設立のやり方を徹底解説!準備から手続き・補助金・設立後までわかりやすく解説
会社を設立するには必要な手続きがさまざまあるほか、流れに沿う必要があります。
この記事では、会社設立ための基本的な流れと手順について紹介します。また、会社設立に関するメリット・デメリットについても解説しますので、スムーズに起業するためにぜひ役立ててみてください。
- 【この記事のまとめ】
- 「会社設立」とは法務局に登記申請を行い法人を設立することで、節税や事業継承の利点があり、社会的信用を得て大規模な契約も可能にします。
- 会社設立の際には、やることや準備すべき書類がたくさんあるので、事前に知識を身に付けておくとスムーズです。
- 会社設立自体は自分ひとりでも可能ですが、設立の内容次第では、後々、許認可や借入に悪影響を与える可能性もあるため、一度専門家に相談することがオススメです。会社設立の必要性があるのかも含めて、慎重に検討してみましょう。

会社設立の流れ
会社設立には一般的な流れがあるため、事前にやることを把握しておくとスムーズです。まずは設立の流れについて見ていきましょう。
- 【会社設立の流れ】
最初に「社名」「本社の所在地」「事業の目的」「資本金」「発起人」といった会社の基礎となる情報を定め、社用の印鑑も用意します。
また、資本金を準備する際は、「初期費用+3~6ヶ月間収益がなくても事業継続できる額」に設定するのが一般的です。続いて、会社の規則を定めた定款を作成した後、株式会社の場合は認証を受けます。
資本金の払い込みを行い、法務局での会社設立登記申請後、問題がなければ10日ほどで手続きは完了です。登記事項証明書を取得して無事に会社が設立できたことを確認し、印鑑カードの交付を受けてください。
国税や地方税の確認、社会保険の加入など事業開始前に必要なことも漏らさずに行うことも大切です。
会社の設立とは

そもそも「会社設立」とは、法務局に登記申請を行い、法人を設立することです。会社を設立することで節税対策や事業継承をしやすくなるなどの利点があります。また、事業の規模が大きくなり、個人事業主では責任を負いきれなくなった場合も会社を設立することで社会的な信用を得やすくなるでしょう。
さらに、法人格を持つことで個人事業主では受けられなかった大きな事業の契約を履行できる場合もあります。会社の設立は、事業をさらに大きくしていくために必要な手続きだといえるでしょう。
創業と設立の違い
創業とは新しい事業を起こすことを指し、会社ではなく個人事業主でも新規事業をスタートすれば「創業した」と表せます。
一方で、設立は法人登記を行う必要があり、申請が通れば会社として公的に認められるのが特徴です。登記を申請した日が「会社の設立日」になります。
株式会社と合同会社の違い
「株式会社」とは、「株式を発行することで事業に必要な資金を調達する形態の会社」のことを指します。会社に資金を提供した者が株主であり、会社の経営者は株主が集う株主総会によって定められるのが基本です。
一方「合同会社」とは、「会社の経営者と資金の提供者が同一である会社」のことで、資金を出した全社員に会社の意思を決める権利があります。2006年の会社法施行から新たに設けられた形態です。
株式会社と合同会社の違いは、「意思の決定方法」が挙げられます。株式会社は株主に意思決定の権利がある一方で、合同会社は定款に別段の定めがない限り全ての社員の同意が必要です。
また、株式会社は役員の任期が最長で10年と定められているのに対し、合同会社には任期の定めがありません。その他、株式会社は決算公告や定款の認証が必要ですが、合同会社は不要であることも両者の違いです。
法人と個人事業主の違い
「個人事業主」とは、個人で事業を行っている人のことです。法人は会社設立の際に登記申請を行うのに対し、個人事業主は税務署に開業届を提出して事業をスタートします。また、個人事業主は事業開始に伴う費用が発生しませんが、法人は登記の手続きに関わる法定費用と資本金が必要です。
会社設立に必要な費用

前述の通り、会社設立にあたっては登記手続き費用と資本金が必要となり、事前に準備しておかなければなりません。株式会社と合同会社とでは費用が異なるため、確認しておくことが大切です。ここからは、どの程度の費用がかかるのか、具体的に解説します。
株式会社の設立に必要な費用
株式会社の登記申請費用の具体的な項目と一般的な金額の目安は、以下の通りです。
| 【項目】 | 【目安】 |
|---|---|
| 収入印紙代(定款) | 4万円(電子定款は不要) |
| 認証手数料(定款) | 資本金300万円以上:5万円
資本金100万円~300万円未満:4万円 資本金100万円未満:3万円 |
| 謄本手数料(定款) | 1ページあたり250円 |
| 登録免許税 | 資本金×0.7%もしくは15万円のどちらか高い金額 |
この他に、会社用の印鑑作成費用や印鑑登録手数料など、登記申請以外の費用がかかり、全体としては25万円以上必要となるケースが多いです。
合同会社の設立に必要な費用
合同会社の登記申請費用の具体的な項目と一般的な金額の目安は、以下の通りです。
| 【項目】 | 【目安】 |
|---|---|
| 収入印紙代(定款) | 4万円(電子定款は不要) |
| 認証手数料(定款) | 0円 |
| 謄本手数料(定款) | 0円 |
| 登録免許税 | 資本金×0.7%もしくは6万円のどちらか高い金額 |
株式会社と同様に、会社用の印鑑作成費用や印鑑登録手数料など登記申請以外の費用がかかり、11万円以上必要となるケースが多いです。
自分で手続きする場合と専門家に依頼する場合の違い
会社設立の登記申請は自分でやることも可能ですが、専門家に依頼するのもひとつの方法です。専門家へ依頼した場合は、自分で行う場合と比べて専門家への報酬がかかります。ただし、専門家に代行してもらえば、通常は電子定款を作成してもらえるので紙の定款に貼る4万円分の収入印紙代は必要なくなります。
設立費用を抑えるためのポイント
会社設立時の費用を抑えるには、いくつかの実践的な方法があります。特に初期段階では無駄な支出を避け、本当に必要な部分にだけコストをかけることが重要です。
具体的なコスト削減策として、以下の方法が挙げられます。
- 定款を電子定款で作成することで、収入印紙代4万円を節約できる
- オフィスはバーチャルオフィスや自宅を活用し、賃料を抑える
- 事務用品や設備は中古品やリースを利用し、初期投資を最小限にする
- 会社設立の手続きや事務作業をできる限り自分で行う
- 国や自治体の特定創業支援等事業(特定創業支援事業)を活用する
これらの工夫を組み合わせれば、会社設立時の初期費用を大きく抑えることができます。特に電子定款や公的支援の活用は、節約効果が高いです。
資本金の目安と考え方
資本金の設定は、会社設立後の安定した経営に直結するため慎重な検討が求められます。資本金は、100万円〜300万円で設立するケースが一般的です。
また、業種や事業規模によっても必要額は変わります。例えば、建設業許可なら500万円以上、人材派遣業許可なら2,000万円以上が必要です。
資本金が1,000万円未満であれば、設立から最大2年間は消費税が免除されるメリットもあります。
資本金を決める際は、融資や他の資金調達手段と合わせて初期費用と3~6カ月分の運転資金を目安にし、事業計画や許認可要件も考慮しましょう。
資本金が少なすぎると資金繰りが厳しくなり、逆に多すぎると税負担が増えるため、無理のない範囲で100万円~500万円程度を目安に設定するのが現実的です。
会社設立に必要な手続き一覧

会社設立に必要な手続きは、設立準備から登記、設立後の各種申請まで多岐にわたります。
スムーズに会社設立を進めるためには、各手続きの流れや必要書類、提出先を事前に把握しておくことが大切です。
ここでは、会社設立に必要な主な手続きと、その際に準備すべき書類や取得方法についてわかりやすく解説します。
会社設立に必要な書類一覧と取得方法
会社設立には多くの書類が必要となり、準備や取得方法を正しく理解することが重要です。特に株式会社の場合、必要書類は10種類以上に及びます。
下記の表は主な必要書類とその概要、取得方法をまとめたものです。
| 手続き | 手続きの場所 | 必要書類 | |
|---|---|---|---|
| 登記前 | 定款認証 | 公証役場 |
|
| 登記時 | 登記申請 | 法務局 |
|
| 会社印登録 | 法務局 |
|
|
| 登記後 | 印鑑カードの取得 | 法務局 |
|
| 印鑑証明書交付申請 | 法務局 |
|
|
| 登記事項証明書交付申請 | 法務局 |
|
これらの書類は、法務局の窓口や郵送、オンライン申請で提出できます。提出方法や書類の綴じ方は管轄の法務局によって異なるため、事前に確認すると安心です。
電子定款と紙定款の違い
会社設立時に作成する定款には、電子定款と紙定款の2種類があります。どちらを選ぶかによって、費用や手続きの手間が大きく異なります。
以下の表で主な違いをまとめます。
| 項目 | 電子定款 | 紙定款 |
|---|---|---|
| 形式 | PDFファイル(電子データ) | 紙の文書 |
| 印紙税 | 不要(0円) | 必要(4万円) |
| 作成方法 | パソコンで作成し電子署名を付与 | パソコンや手書きで作成 |
| 認証方法 | オンラインで公証役場に送信 | 公証役場に直接持参 |
| 必要機材 | ICカードリーダー、PDFソフトなど | 特になし |
| データ修正 | 申請後は再申請が必要 | その場で修正可能 |
電子定款は印紙税が不要なため費用を抑えられますが、専用ソフトや機器の準備が必要です。一方、紙定款は手続きがシンプルで機材も不要ですが、印紙税4万円がかかります。
費用重視なら電子定款、手軽さやパソコン操作に不安がある場合は紙定款が適しています。自社の状況や優先事項に合わせて選択しましょう。
会社設立の手順

会社設立を行うにあたっての具体的な手順は、以下の通りです。手順に合わせてスケジュールを組み、滞りなく済ませるようにしましょう。
- 会社概要の決定
- 定款作成
- 資本金の払い込み
- 登記申請書類作成
- 登記登録申請
1.会社概要の決定
まずは、どういった会社を設立するのか、具体的な概要を決める必要があります。具体的な内容は、以下の通りです。
- 【最初に決めるべきこと】
-
- 事業の目的
- 商号
- 資本金の額
- 本店の所在地
- 出資者(発起人)
- 各発起人の出資額
- 発行可能株式の総数
- 設立時に発行する株式の枚数
- 株式譲渡制限を設けるか否か
- 事業年度
- 公告を行う方法
- 会社設立時の代表取締役
- 会社設立時の取締役
2.定款作成
上記で定めた会社の概要をまとめ、「定款」を作成します。定款は会社の基本原則をまとめたもので、会社と公証役場に1部ずつ保管されるのが原則です。以前は紙の定款が基本でしたが、近年は収入印紙代がかからない電子定款が取り入れられることも増えています。
定款の記載例については日本公証人連合会で具体的に記されているため、参考にしてください。
参考:日本公証人連合会
3.資本金の払い込み
資本金払込の手順は、以下の通りです。
- 発起人代表の銀行口座を用意する
- 用意した口座に資本金を払い込む
- 払込明細を用意する
※通常の銀行の場合:通帳の表紙、表紙の裏、払込内容が記帳されたページのコピー
※ネットバンクの場合:銀行名、支店名、預金種別、口座番号、口座名義人の氏名、振り込み内容が記載されたページをプリントアウト - 払込証明書を作る
※記載事項:払込金額、株数1株あたりの払込金額、本店所在地、商号、代表取締役氏名、日付
※会社代表印:代表取締役氏名の右側と払込証明書の左上にそれぞれひとつずつ - 払込証明書と通帳コピーを綴じてそれぞれのページに契印する
4.登記申請書類作成
登記申請書類のテンプレートは、法務局のサイトのサイトで公開されています。申請書作成にあたって記載する事項は、以下の通りです。
- 商号、本店の所在地:会社名と住所
- 登記の事由:登記する理由(「令和×年×月×日発起設立の手続き終了」と記載するのが一般的)
- 登記すべき事項:別途書類を添付し「別紙記載の通り」もしくは「別添CD-Rに記載の通り」と記載
- 課税標準の金額:資本金のこと(「金○○万円」と記載する)
- 登録免許税の額:支払う登録免許税の額
- 添付書類:印鑑証明書や定款などの添付書類を記載
- 申請の年月日:法務局に申請する年月日を記載
- 登記所の表示:管轄法務局の名前を記載
「登記すべき事項」の具体的な内容は、「目的」「商号」「本店の所在場所」「資本金額」「株式の譲渡制限の定め」「発行可能株式総数」「発行済株式の総数」「役員に関する事項」「公告の方法」です。必要事項を記載後、申請書に会社代表印を2ヵ所入れ、添付書類をホチキスで綴じます。最後に契印を入れたら完了です。
5.登記登録申請
- 【窓口の場合】
-
管轄の法務局へ行き、窓口で登記申請書と添付書類を提出してください。問題がなければ、1週間から10日ほどで手続きが完了します。
- 【郵送の場合】
-
必要書類を一式揃え、管轄法務局に郵送して申請できます。特定記録郵便や簡易書留を利用するのがおすすめです。問題がなければ、1週間から10日ほどで手続きが完了します。
- 【オンラインの場合】
-
法務局のオンラインシステム「登記ねっと 供託ねっと」からの申請も可能です。専用のソフトをダウンロードする他、電子証明書が必要となります。
なお、これから新たに会社を設立する方だけでなく、個人事業主として活動してきた方が「法人成り(法人化)」するケースも増えています。
法人成りについては、以下の記事で詳しく解説しています。
会社設立後にやること

会社設立後は、登記が完了しただけで終わりではなく、事業を円滑にスタートさせるために多くの手続きが必要です。
ここでは、会社設立後に必要な主な手続きや届出について、項目ごとに分かりやすく解説します。
税務署・都道府県税事務所・市町村への届出
会社設立後は、税務署や都道府県税事務所への各種届出が不可欠です。
特に「法人設立届出書」や「給与支払事務所等の開設届出書」など、提出期限が決まっている書類が多いため、早めの準備が求められます。
主な提出書類と提出期限、提出先は以下の通りです。
| 提出書類 | 提出期限 | 提出先 |
|---|---|---|
| 法人設立届出書 | 設立日から2か月以内 | 税務署・都道府県税事務所 |
| 給与支払事務所等の開設届出書 | 開設日から1か月以内 | 税務署 |
| 青色申告の承認申請書 | 最初の事業年度終了日の前日まで | 税務署 |
| 減価償却資産の償却方法の届出書 | 最初の確定申告書提出期限まで | 税務署 |
これらの届出を怠ると、税制上の優遇措置が受けられない場合や、後々の手続きが煩雑になるリスクがあります。
提出方法や必要書類は各自治体や税務署で若干異なるため、事前に公式サイトで確認し、不備のないように進めましょう。
年金事務所・労働基準監督署・ハローワークへの届出
従業員を雇用する場合は、年金事務所や労働基準監督署、ハローワークへの届出も必要です。社会保険や労働保険の加入手続きは義務となるため、期限を守って対応しましょう。
主な手続きと提出先は下記の通りです。
| 手続き内容 | 提出期限 | 提出先 |
|---|---|---|
| 健康保険・厚生年金保険新規適用届 | 設立日から5日以内 | 年金事務所 |
| 労働保険保険関係成立届 | 雇用日から10日以内 | 労働基準監督署 |
| 雇用保険適用事業所設置届 | 設置日から10日以内 | ハローワーク |
| 雇用保険被保険者資格取得届 | 資格取得日の翌月10日まで | ハローワーク |
期限を過ぎると罰則や保険給付の遅延につながるため、設立直後からスケジュールを立てて対応することが大切です。
手続きの詳細や必要書類は各機関の公式サイトで確認し、不明点は専門家に相談すると良いでしょう。
社会保険と労働保険の手続き
会社設立後は、社会保険(健康保険・厚生年金保険)と労働保険(労災保険・雇用保険)への加入が原則義務となります。加入手続きの流れやポイントを整理すると、以下のようになります。
| 保険の種類 | 加入義務の有無 | 手続き先 | 主な提出書類 |
|---|---|---|---|
| 健康保険 | 役員・従業員がいる場合 | 年金事務所 |
|
| 厚生年金保険 | 役員・従業員がいる場合 | 年金事務所 |
|
| 労災保険 | 従業員が1人でもいる場合 | 労働基準監督署 |
|
| 雇用保険 | 雇用条件を満たす場合 | ハローワーク |
|
社会保険料や労働保険料は、会社と従業員で分担して納付します。手続きを怠ると罰則や給付遅延のリスクがあるため、設立直後から速やかに対応しましょう。
会計ソフトや顧問税理士の選定
会社設立後の経理体制は、会計ソフトの導入や顧問税理士の選定だけでなく、複数の選択肢を組み合わせて最適化できます。
例えば、日常の記帳や仕訳はクラウド型会計ソフトで自社管理し、決算や税務申告は税理士に依頼する運用も一般的です。下記の表で主な選択肢を比較します。
| 選択肢 | 特徴・メリット |
|---|---|
| クラウド会計ソフトのみ |
|
| 顧問税理士のみ |
|
| ソフト+税理士併用 |
|
| 経理代行サービス活用 |
|
会計ソフトは機能や料金、サポート体制を比較し、自社の規模や業務内容に合うものを選びましょう。税理士を選ぶ際は、クラウド会計に強いか、IT知識や導入実績が豊富かも重要なポイントです。
経理業務の負担やコスト、将来の事業拡大も見据え、最適な組み合わせを検討することが経営の安定につながります。
創業時に利用できる助成金や補助金

補助金は、主に経済産業省の管轄で、事業者の新規事業や研究開発など、事業経費に対する補助を目的としています。
一方の助成金は、ヒト(従業員)に対して支払われるお金といえます。多くが厚生労働省の管轄で、事業者の雇用や従業員の労働環境整備・改善の支援が目的です。
創業時には、これらの補助金や助成金を活用することで、資金面の負担を大きく軽減できます。ここでは、創業時に利用できる主な補助金・助成金と、自治体独自の支援制度について解説します。
小規模事業者持続化補助金
小規模事業者持続化補助金は、創業間もない事業者向けの補助金で、販路開拓や業務効率化の取り組みを支援します。創業枠を活用すれば、最大250万円の補助を受けられる点が大きな魅力です。
主な補助対象は下記の通りです。
- チラシやホームページの作成費用
- 販促イベントの実施費用
- 業務効率化のための設備投資
申請には「特定創業支援等事業」の証明書が必要となるため、まずは自治体で証明書を取得しましょう。販路拡大や事業基盤強化を目指す創業者に最適な制度です。
キャリアアップ助成金
キャリアアップ助成金は、非正規雇用から正社員化を進める企業を支援する助成金です。主に有期雇用やパート、派遣社員を正規雇用に転換した場合に活用できます。
主なメリットは以下の通りです。
- 正社員化1人あたり最大80万円の助成
- 派遣社員の直接雇用や母子・父子家庭の雇用で加算あり
- 1事業所あたり年間20人まで申請可能
雇用保険の適用事業所であることや就業規則の整備、正社員化の前にキャリアアップ計画の提出など、一定の要件を満たす必要があります。人材の定着や働き方改革を進めたい企業におすすめです。
自治体ごとの支援制度をチェックする方法
創業時には、国の制度だけでなく、自治体独自の補助金や助成金も活用できます。効率的に情報を収集するには、以下の方法がおすすめです。
- 自治体の公式ホームページを確認する
- 商工会議所や商工会の窓口で相談する
- 中小企業支援機関の情報サイトを活用する
自治体によって支援内容や申請条件が異なるため、最新情報をこまめにチェックしましょう。地域ごとの制度を活用することで、設立時の負担をさらに軽減できます。
補助金・助成金の違いについて、さらに詳しく知りたい場合は、こちらの記事をご覧ください。
会社設立のメリット

会社設立には、主に次のようなメリットがあります。
社会的信用の向上
会社を設立する際には、商号(社名)、住所、資本金などの情報を法務局に提出し、登記しなければなりません。この登記内容は誰でも閲覧できるため、法人としての責任が発生し、社会的な信用力が向上します。
取引先や仕入先の中には、法人でなければ契約を結ばない企業や、個人事業主とは大規模な取引を行わない企業もあります。
このように社会的な信用を得やすくなることで、資金調達も容易になります。個人事業主でも資金調達は可能ですが、事業拡大などで大口の融資が必要な場合、法人の方が資金調達の選択肢が広がります。
節税のメリット
個人事業主と法人では課税される税金の仕組みが異なります。個人事業主には所得税が、法人には法人税がかかります。個人事業主の所得税は累進課税であり、所得が増えると税率が段階的に上がり、最大で45%に達します。
一方、法人税は資本金1億円以下の法人であれば、所得が800万円を超える部分に23.20%、800万円以下の部分に15%の税率が適用されます。所得が増えるほど、会社設立による節税効果が高まります。
さらに、会社を設立すると、経営者は給料を役員報酬として受け取ります。法人では、役員報酬は定期同額給与などの要件を満たすことで経費として認められ、法人税の対象外となります。
また、法人では経費の範囲が広いことや、青色申告書を提出すれば欠損金(赤字)を10年間繰り越すことができる点も、節税のメリットと言えます。
決算月の自由な設定
個人事業主の場合、事業年度は1月から12月と法律で定められており、決算月は12月です。一方、法人では事業年度の決算月を自由に設定できます。会社の繁忙期と決算月が重ならないように調整するなど、都合に合わせて決算月を設定できるのがメリットです。
有限責任
個人事業主は事業上の責任をすべて自分で負わなければなりません。経営が悪化した際の未払い金や借入金、滞納した税金も個人の負債として負担する必要があります。これを「無限責任」と言います。
一方、株式会社や合同会社の場合、責任は「有限責任」となり、代表者個人がすべての責任を負う必要はありません。個人保証による借入を除き、責任の上限は出資金の範囲内に留まります。
つまり、出資額以上の支払い義務は発生せず、個人の資産は保護されます。万が一の際にリスクを最小限に抑えることができるため、大きなメリットと言えるでしょう。
会社設立のデメリットとリスク

会社設立に関する手続きは、個人事業主の開業届より手間と費用がかかるところがデメリットです。登記申請の際には電子定款を採用して収入印紙代を節約したり、専門家に依頼して手間を減らしたりといった工夫が必要でしょう。
また、個人事業主より厳密な会計処理が必要となる点も注意してください。顧問税理士と契約するなどして、専門家の意見を聞くことが大切です。
設立後のランニングコストや税金の負担など、事前に知っておくべき点を把握しておくことで、より現実的な経営判断が可能になります。
ここでは、会社設立のデメリットとリスクについて詳しく解説します。
設立後の維持コスト(会計・税務・社会保険)
会社設立後は、個人事業主と比べてさまざまな維持コストが発生します。主な固定費として、以下の項目が挙げられます。
- 法人住民税(均等割):赤字でも最低7万円が発生
- 社会保険料:健康保険や厚生年金保険などの会社負担分
- 税理士報酬:会計や税務処理のための顧問料(年間30万~50万円が目安)
これらの費用は、会社の規模や従業員数に応じて増加します。特に社会保険料は従業員の給与に連動して負担が大きくなりやすく、税理士報酬も業務量によって変動します。
設立後のランニングコストを事前に把握し、無理のない資金計画を立てることが経営安定の鍵です。
赤字でも法人住民税が発生する
会社は赤字決算の場合でも、法人住民税の均等割を必ず納付しなければなりません。
均等割は利益の有無にかかわらず、資本金や従業員数に応じて課税されるため、最低でも年間7万円程度が必要です。
- 資本金1千万円以下・従業員50人以下の場合:最低7万円
- 資本金や従業員数が増えると金額も上昇
この税金は、会社の規模や所在地によって異なる場合があります。赤字でも免除されないため、資金繰りが厳しい時期でも必ず発生する固定費となります。
設立前にこのリスクを十分に理解し、経営計画に反映させることが重要です。
会社設立を検討する際のポイント

会社を設立するかどうかを検討する際には、ポイントを踏まえた上でしっかり吟味することが重要です。ここでは、検討時に参考になるポイントについて解説します。
事業拡大を視野に入れているか
会社設立を検討する際は、将来的な事業拡大の可能性を見据えておくことが重要です。法人化することで、組織体制の強化や信用力の向上、大型取引への参入など、成長の選択肢が広がります。
特に、複数の事業展開や支店開設を計画している場合は、法人格を持つことで柔軟な経営判断が可能となります。
今後のビジネス展開を考えたとき、個人事業主のままでは限界が生じやすいため、事業拡大を目指すなら会社設立を前向きに検討しましょう。
多くの人員や専門知識を持つ人材が必要か
事業運営において多くの人員や専門知識を持つ人材が必要な場合、法人化は有効な選択肢です。法人であれば、優秀な人材の採用や外部パートナーとの連携がしやすくなり、組織力を高められます。
具体的には、以下の点がポイントです。
- 社会保険の整備による雇用環境の向上
- 専門性の高い業務の分担や外部委託
- 人材育成や研修体制の構築
専門知識や人材の確保が経営の成否を左右する場合は、会社設立による組織強化を検討しましょう。
出資が必要か
事業の成長や新規プロジェクトの立ち上げには、十分な資金調達が欠かせません。会社設立により、出資を受けやすくなる点は大きなメリットです。
主な出資方法には以下があります。
- 複数の投資家からの資金調達
- 金銭以外の現物出資(不動産や有価証券など)
- 株式発行による資本増強(株式会社の場合)
出資を受けることで事業資金を確保できる一方、議決権や経営方針への影響も生じるため、出資の必要性や条件を慎重に検討しましょう。
融資や補助金を活用したい場合に設立時期は最適か
融資や補助金の活用を考えている場合、会社設立のタイミングが重要です。設立直後は「創業融資」や「創業期限定の補助金」など、起業家向けの優遇制度が利用できるケースが多くなります。
具体的なポイントは以下の通りです。
- 日本政策金融公庫や地方自治体による創業融資制度
- 創業期限定の補助金や助成金
- 申請時期や要件の確認が必要
設立時期によって利用できる制度が変わるため、資金調達や補助金申請の計画と合わせて、最適な設立タイミングを見極めましょう。
会社設立に関するよくある質問

ここからは、会社設立に関する「よくある質問」について具体的に答えていきます。
株式会社と合同会社はどちらを選ぶべき?
株式会社は、対外的な信用をより高めたい人に向いています。また、資金調達の幅が広いため、巨額の投資が必要となるスタートアップ企業にも最適です。
一方で、合同会社は、対外的にそれほど法人名が重要でない業種で、設立費用を抑えたい人に向いています。
会社設立は自分ひとりでもできる?
会社設立自体は自分ひとりでも可能です。ただ、設立の内容次第では、後々、許認可や借入に悪影響を与える可能性もあるため、一度専門家に相談することをオススメします。自分で登記する場合は定款の作成や登記申請書類の作成、必要書類の準備などが必要となるため、あらかじめ十分な知識を身に付けて申請するようにしましょう。
会社設立にかかる期間・日数は?
会社設立にかかる期間は、株式会社で3週間程度、合同会社で2週間程度と言われています。手続きの主なスケジュールは、以下の通りです。
- 設立前の事前準備(商号や事業目的などを決める)
- 定款の作成と認証
- 資本金の払い込み
- 登記の申請
会社設立に条件はある?
会社設立の主な条件は、以下の通りです。
- 資本金の条件:1円から設立が可能
- 設立人数の条件:1人から設立が可能
- 株式の条件:株式の譲渡制限・発行可能株式総数の上限を定める必要がある
- 商号の条件:使えない文字・記号があるため事前に確認
- 本店所在地の条件:同じ住所に同名の会社名は登記できない
会社設立をするなら「GMOオフィスサポート」を活用しよう!

会社設立とは、法務局への登記を通じて法人を作ることを指し、社会的信用や節税など多くのメリットがあります。
設立には定款作成や登記などの手続きが必要で、株式会社・合同会社によって費用も異なります。設立後は税務・保険の届出や助成金の活用も重要です。
ただし、不安な点がある場合は専門家に任せるのがおすすめです。会社設立の必要性があるのかも含めて、慎重に検討してみてください。
GMOオフィスサポートでは、会社設立時に必要な代表印や銀行印などの印鑑セットを販売しております。最短で2営業日以内に発送しますので、急いで作りたい方にもおすすめです。
会社の銀行口座(法人口座)はGMOあおぞらネット銀行がおすすめ!

画像引用元:GMOあおぞらネット銀行
会社設立時にネットバンクで銀行口座を開設するなら、GMOあおぞらネット銀行がおすすめです。
手間なくスピーディーに口座開設できる点が強みで、口座開設手続きは印鑑レス・ペーパーレス・郵送レスで行うことができます。また、条件を満たせば最短即日で口座を開設できます。
振込手数料は同行宛て無料に加え、他行宛てでも一律143円/件(税込)(※)と低価格で、さらに設立1年未満のお客さまであれば、他行宛て振込手数料が月20回まで無料です。
創業期のお悩みを解決するため、外部企業と提携してさまざまなサービスを紹介するビジネスサポートも行っており、会社運営の面でも強い味方になるでしょう。ぜひGMOあおぞらネット銀行をご利用ください。
(※)2025年8月1日より
起業や独立を考えている方に朗報
起業・経営のプロ監修のオリジナル冊子『会社設立完全ガイド』を無料でプレゼント!
「起業の窓口」では、起業に必要なノウハウや成功者のインタビュー、経理や会計の基礎知識など、さまざまなコンテンツを完全無料で提供しています。また、GMOインターネットグループが展開するビジネスの立ち上げや拡大に役立つ各種サービスをおトクな特典付きでご紹介しています。
会社設立や資金調達などのノウハウが詰まった『会社設立完全ガイド』をGETして、夢の実現への一歩を踏み出してみませんか?
GMOインターネットグループ株式会社はGMOあおぞらネット銀行株式会社を所属銀行とする銀行代理業として、円普通預金の受入れを内容とする契約の締結の媒介を行います。
銀行代理業許可番号:関東財務局長(銀代)第335号
- 記事監修
-
- 中野 裕哲 HIROAKI NAKANO
- 起業コンサルタント(R)、経営コンサルタント、税理士、特定社会保険労務士、行政書士、サーティファイドファイナンシャルプランナー・CFP(R)、1 級FP 技能士。 V-Spiritsグループ創業者。東京池袋を本拠に全国の起業家・経営者さんを応援!「あの起業本」の著者。著書16冊、累計20万部超。経済産業 省後援「DREAMGATE」で11年連続相談件数日本一。
- ※本記事は、起業の窓口編集部が専門家の監修または独自調査(アンケート)に基づいて制作したものです。
- ※掲載している情報は、記事公開時点の法令・税制・商品・サービス等に基づくものであり、将来的に変更される可能性があります。
- ※アンケート調査に関する記述は、特定の調査対象者からの回答結果および編集部の見解を含んでおり、内容の正確性・完全性を保証するものではありません。
- ※記事の内容は一般的な情報提供を目的としており、すべての方に当てはまるものではありません。個人の状況に応じた具体的な助言が必要な場合は、専門家にご相談ください。
- ※情報の利用や判断、実施については、ご自身の責任で行っていただきますようお願いいたします。
- ※本記事に掲載された内容の転載・複製はご遠慮いただき、引用の際は必ず出典をご明記ください。



 シェア
シェア