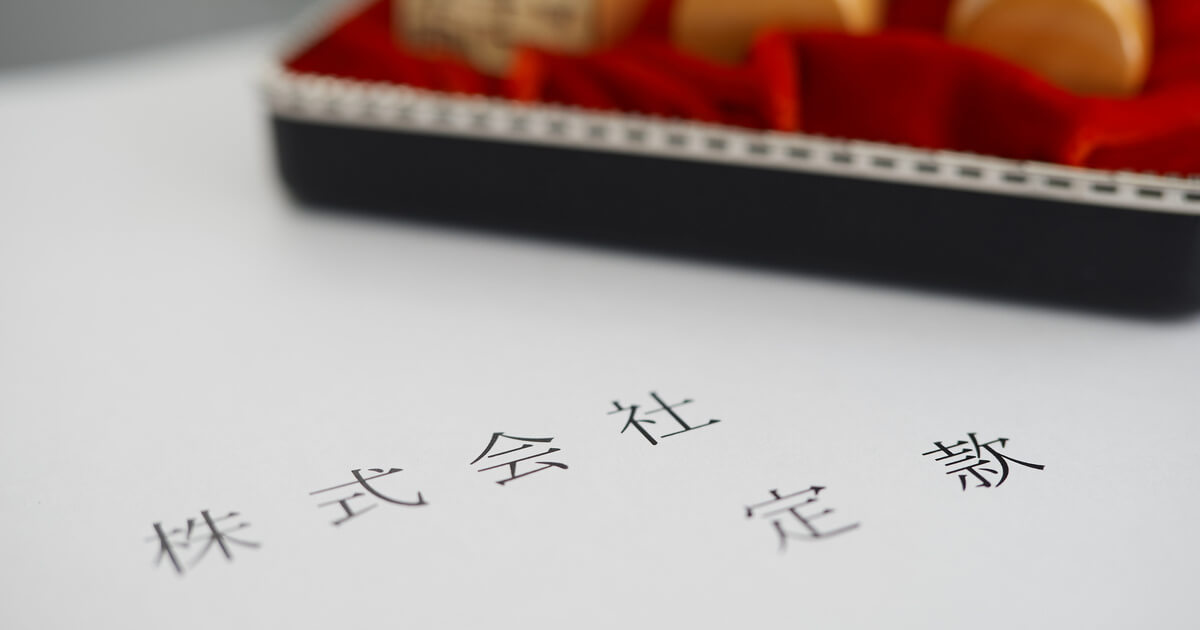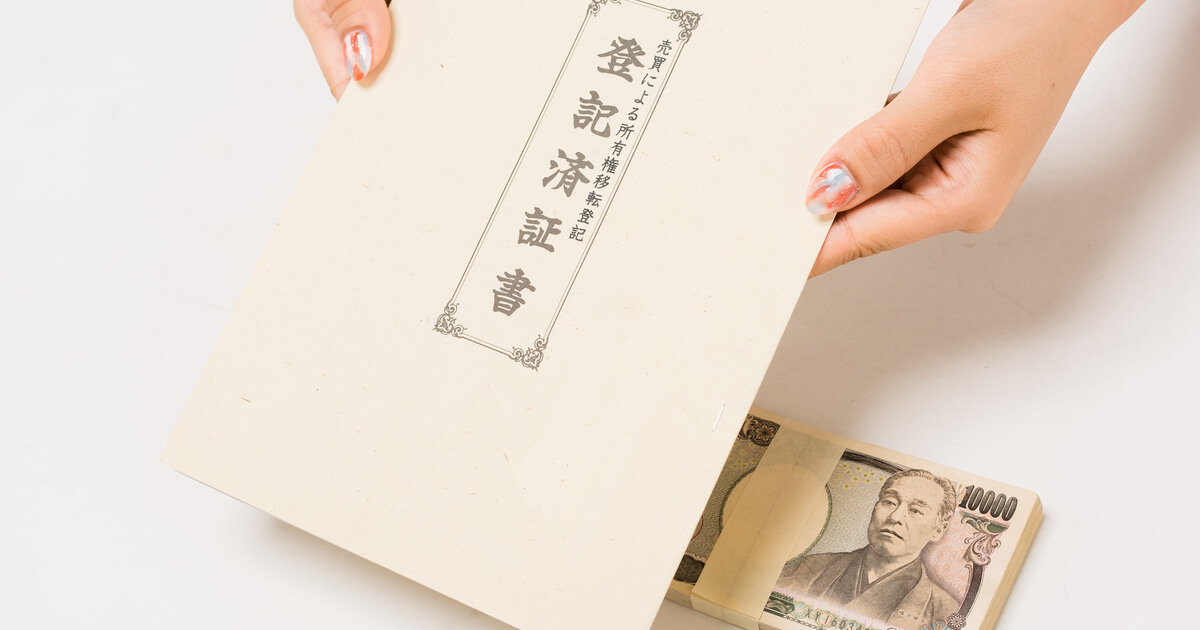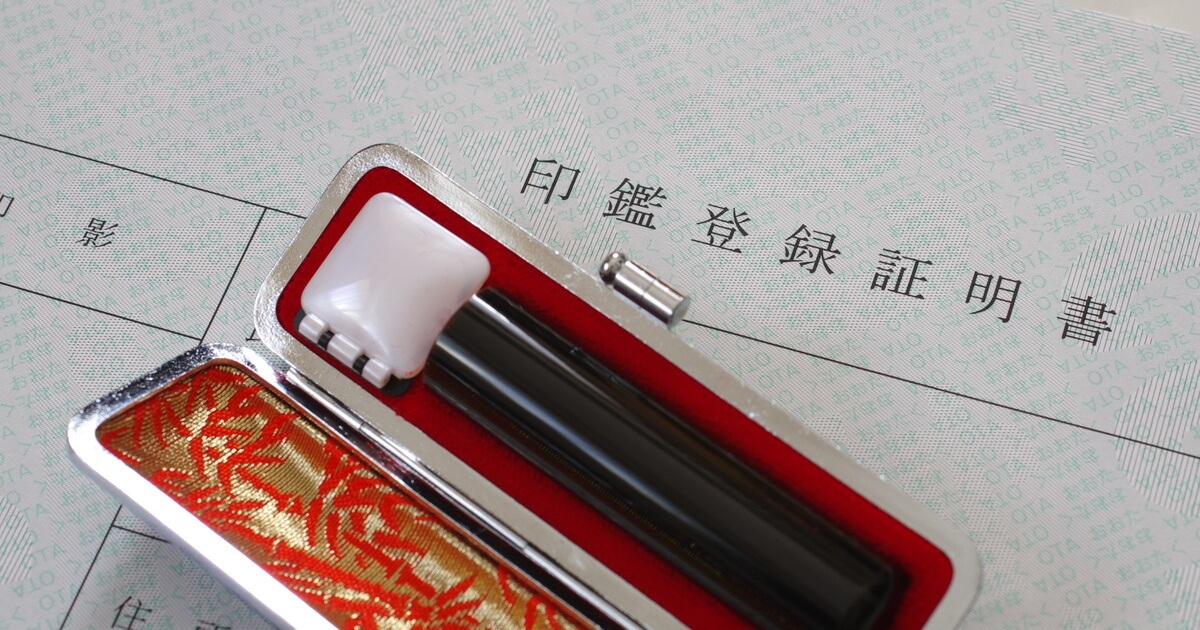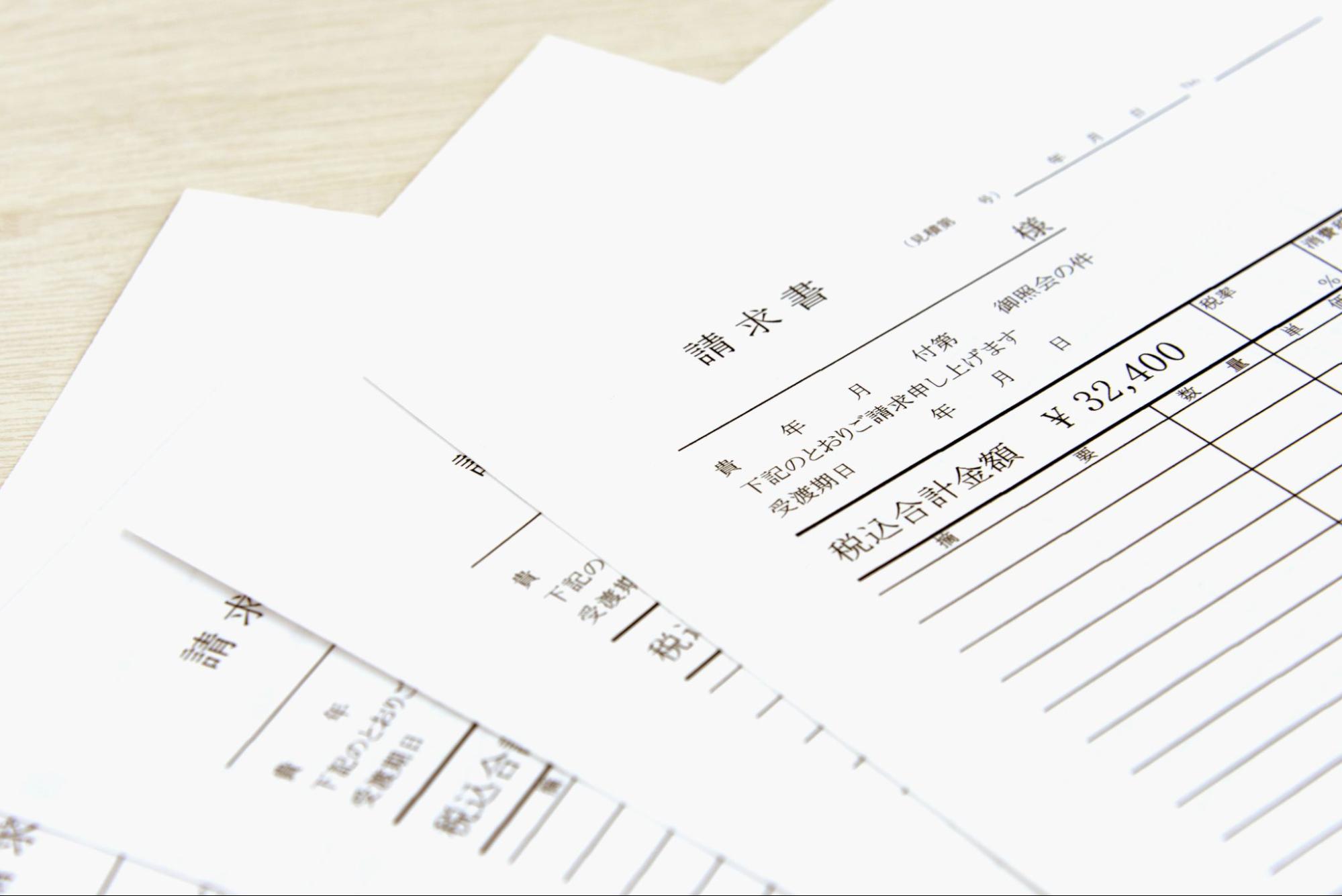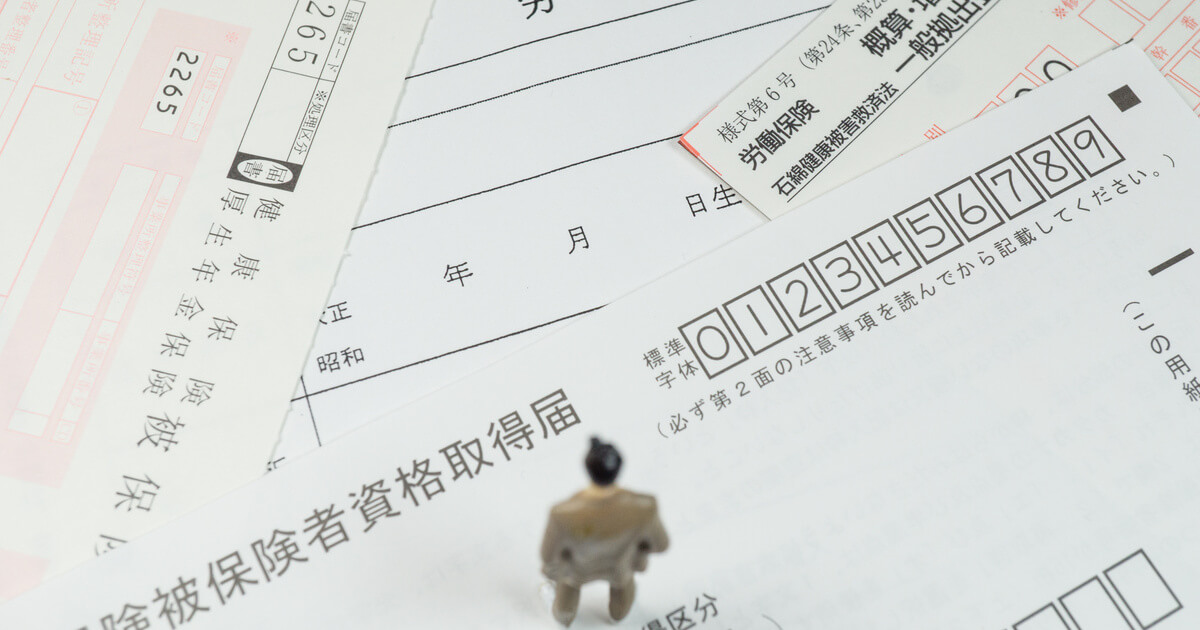起業資金はいくらかかる?会社設立に必要な費用一覧

起業するためには、設備資金と運転資金の2種類の起業資金が必要です。
「2023年度新規事業開業実態調査」によると、起業に必要な開業費用の平均値は1,027万円です。しかし、開業費用の分布をみると、500万円未満で起業する方が40%以上と最も多いことが明らかとなりました。
個人事業主として起業するのか、それとも法人化するのかによって、必要な開業資金は変わってきます。いずれにしても、事業を続けていくうえで起業資金の確保はマストであるため、自分に必要な開業資金を把握しなくてはなりません。起業を決めた段階で起業資金を算出すれば、自分に合った資金調達の方法が見えてくるはずです。
本記事では、起業するうえで具体的な必要資金や算出方法、具体的な調達方法について解説します。起業において必要な資金調達の基礎知識やノウハウを正しく理解して、スムーズかつ計画的な起業を目指しましょう。
- 【この記事のまとめ】
- 会社設立から運営までの費用相場は約1,027万円で、年々低資金での開業が増加しています。テレワークの普及やフリーランスの増加が要因とされています。
- 株式会社設立には、法定費用、資本金、その他の費用が必要です。法定費用の内訳には認証手数料や登録免許税が含まれ、資本金は社会的信用を考慮し十分に準備することが重要です。
- 法人設立にかかる費用は300~400万円が目安ですが、個人事業主は200万円程度を準備すると良いでしょう。運転資金も考慮し、事業が軌道に乗るまでの資金計画が必要です。
「起業の窓口」では、AIインフルエンサーの茶圓氏とコラボをおこない、AIを活用してビジネスの効率化を図るための貴重な知識を提供しています。
特集ページ「AI×起業」では、最新のAI技術やツールを使った実践的なアプローチを紹介しており、起業家や個人事業主の業務をよりスマートにサポートします。
AIの力で業務の負担を軽減し、ビジネスの成長を加速させたい方に最適な情報が満載です。ぜひご覧ください。
「起業の窓口」の特集ページ「起業家インタビュー」では、実際に成功を収めた起業家たちの貴重なインタビューが充実しています。リアルな体験や苦労、成功までの道のりを通じて、これから起業を目指す方々に向けた実践的なアドバイスを提供しています。
さまざまな分野で活躍する起業家の声を通して、ビジネスのヒントやインスピレーションを得られるコンテンツが満載です。ぜひインタビューを参考にして、自分のビジネスに活かしてみてください。
会社設立から運営までにかかる費用相場は約1,027万円

会社設立には、定款作成、登記申請などを始めとするさまざまな手続きが必要です。
「2023年度新規事業開業実態調査」調べによると、会社設立から運営までにかかる費用相場は約1,027万円と言われています。
しかし、開業費用として1,000万円以上を用意する割合は年々減少傾向ですあり、低資金から事業を始める起業家が増加していると言えます。これらの要因は、テレワークの普及によるオフィスの縮小を進める企業や、自宅やカフェなどで働けるフリーランスとして起業する方が増加しているのも当てはまるでしょう。
株式会社を設立する場合は、定款作成、登記申請が必要です。ビジネスによっては事務所や店舗開設だけではなく、人件費や広告宣伝費などのさまざまなコストが発生します。店舗を持つ場合や人を雇って大きくビジネスをしていこうとする場合には、会社設立から運営までの費用として1,000万円以上は準備する必要があると言えます。
株式会社を設立するときにかかる費用相場
株式会社を設立する際にかかる費用は、主に下記の3つにカテゴライズされます。
- 法定費用…法定費用とは、会社設立時に公証役場や法務局に支払う必要のある費用
- 資本金…資本金とは、会社を運営するための元手となる資金。会社設立時に募った資金や、経営者の自己資金で構成される
- そのほか費用…設備投資や事業所の契約にかかる初期費用、広告費や雑費などが当てはまる
続いて、上記3つの内訳において必要となる費用相場を一つひとつ解説していきます。
株式会社の設立にかかる法定費用
株式会社を設立する際に必要となる法的費用の内訳は、以下のとおりです。
| 認証手数料 | 30,000円~50,000円 |
|---|---|
| 収入印紙代 | 40,000円(電子定款では不要) |
| 定款謄本手数料 | 約2,000円 |
| 登録免許税 | 150,000円または資本金額×0.7%どちらか高い方 |
- 印紙代…紙の定款に貼付する収入印紙代として、4万円が必要です。電子定款であれば印紙代は不要となります。
- 認証手数料…株式会社の場合、作成した定款を公証人役場で認証してもらう必要があります。認証手数料は3万円から5万円で、資本金によって変動します。資本金が100万円未満の場合は3万円、資本金の額等が100万円以上~300万円未満の場合は4万円、その他の場合は5万円です。
- 定款謄本手数料…登記申請時に必要な定款の謄本を作成するため、謄本手数料がかかります。謄本手数料は平均2,000円程度です。謄本の枚数によって費用が変わるので、詳細は公証役場へ確認しましょう。
費用を抑えるポイントは、電子定款を利用すれば、印紙代4万円を節約できます。
なお、定款作成を司法書士などの専門家に依頼すると、別途費用がかかります。自分で作成すれば費用を抑えられますが、内容に不備などがある場合、登記申請が却下される可能性があるため、注意が必要です。
株式会社の設立に必要な資本金
会社法においては、1円からでも株式会社の設立は可能です。
しかし、資本金が極端に少ない場合、以下のようなデメリットがあります。
- 信用力を示せない
- 融資を受けにくい
- 賃貸契約が不利になる
- 取引先との契約が不利になる
- 事業を継続させることが難しい
このように、資本金が少なすぎる場合は、事業を円滑に進められないさまざまなデメリットが発生します。
目安としては、初期費用に運転資金3ヵ月分を足した金額を資本金として用意しておくことをおすすめします。
株式会社の設立に必要なそのほかの費用
株式会社を設立する際は、法定費用や資本金の他にも、下記のような費用が発生します。
- 印鑑代…印鑑代とは、会社の実印を作成するための費用です。多くの場合は、実印とセットで、法人口座の開設に用いる銀行印と、請求書などに押印する角印も作成します。
- 印鑑証明書代…印鑑証明書代とは、会社設立時に必要な個人の印鑑証明書を取得するための費用です。印鑑証明書は、銀行との契約締結や法人の銀行口座開設をおこなう際に必要となるケースがあります。
- 登記簿謄本の発行費用…登記簿謄本の発行費用とは、新しい会社の登記簿謄本を発行するための費用です。登記簿謄本は、銀行との契約締結や法人の銀行口座開設を進める際に複数枚必要となる場合があります。
合同会社を設立するときにかかる費用相場
合同会社を設立する際にかかる費用は、主に下記の3つにカテゴライズされます。
- 法定費用…合同会社が準備する法定費用の内訳は、収入印紙代と登録免許税の2つ
- 資本金…合同会社の資本金を集める際は、 合同会社の出資者が払い込む必要がある
- そのほか費用…設備投資や事業所の契約にかかる初期費用、広告費や雑費などが挙げられる
合同会社の設立にかかる法定費用
合同会社を設立する際に必要となる法的費用の内訳は、以下のとおりです。
| 認証手数料 | 不要 |
|---|---|
| 収入印紙代 | 40,000円(電子定款では不要) |
| 定款謄本手数料 | 不要 |
| 登録免許税 | 60,000円または資本金額×0.7%どちらか高い方 |
- 印紙代…紙の定款に貼付する収入印紙代として、4万円が必要です。電子定款であれば印紙代はかかりません。
- 認証手数料…合同会社を設立する際は、定款の公証役場での認証が必要ないため、認証手数料はかかりません。
- 定款謄本手数料…合同会社を設立する際は、定款の認証は不要であるため、謄本手数料は必要ありません。
- 費用を抑えるポイント…株式会社の設立時と同様に、電子定款を利用すれば、印紙代4万円を節約できます。そのため、実質的には登録免許税の60,000円さえ用意すれば、合同会社を設立できます。
合同会社の設立に必要な資本金
合同会社を含む全ての会社形態において、会社設立に必要な資本金は最低1円以上と定められています。
一方で、旅行業や有料職業紹介業などの許認可が必要な事業においては、資本金の最低金額が定められています。
- 旅行業:100万円〜
- 有料職業紹介業:500万円〜
設立する合同会社の事業内容がいずれかに当てはまる場合は、上記の最低金額を準備しなくてはなりません。
合同会社の設立に必要なそのほかの費用
合同会社を設立する際は、法定費用や資本金の他にも、下記のような費用が発生します。
- 印鑑代
- 印鑑証明書代
- 登記簿謄本の発行費用
法人と個人事業主では起業に必要な費用や手続きが異なる

法人と個人事業主では、起業に必要な費用や手続きが異なります。
ここでは、個人事業主が法人化するかどうかで迷った場合の判断方法についても触れるので、参考にしてみてください。
法人の目安
法人を設立する場合の資金は、事業内容などによって異なりますが、300~400万円程度が目安となります。
法人を設立する際、初期費用として株式会社の場合は20万円以上、合同会社の場合は6万円以上ほどのコストがかかります。司法書士などに依頼した場合、プラス5~20万円程度の費用がかかるため、手続き代として11万円~40万円ほどは必要と捉えておくべきです。
さらに、会社設立時は「資本金」も必要です。資本金1円から会社の設立は可能ですが、社会的信用をふまえると、ある程度の金額を積んでおく必要があります。会社設立時の資本金の平均は、およそ300万円程度といわれています。
会社設立費用も含む初期費用や資本金、運転資金をふまえて、トータル400万円程度は準備することをおすすめします。
個人事業主の目安
個人事業主が起業する場合の資金は、事業内容などによって異なりますが、200万円程度を目安に準備するとよいでしょう。
たとえ低資金で始められる事業であっても、事業が軌道に乗るまでの運転資金は十分に貯めておく必要があります。目安である200万円は、設備資金などを含めない、事業を続けていくために使用する運転資金のみの目安となります。
開業時に必要な運転資金は、事業内容や規模、売掛金の回収サイト、事業計画などを考慮して算出する必要があります。少なくとも3ヵ月分の支払いができる程度の金額を用意しておくと安心ですが、事業を軌道に乗せるために時間がかかりそうな場合は、6ヵ月分の資金を準備しておくことをおすすめします。
「起業の窓口」の特集ページ「AI×起業」では、AIを活用して事業計画書を簡単に作成する方法を紹介!
詳しくは「【できるのか?】ChatGPTを使ってたった1時間で事業計画書を書くアラフォー起業家。《小説「AI起業」シリーズ#01》」をご覧ください。
会社設立の手続き後にかかる費用

そもそも起業資金とは、どんなお金をさすのでしょうか?起業資金とは、その名の通り、起業するために必要なお金のことです。
起業資金には、次の2種類があります。
- 開業費
- 維持費
開業費の相場
まずは、開業費の相場と内訳を紹介していきます。開業費とは、事業を始めるために必要な費用です。
設備費用
設備費用は、事業開始に必要となる設備・備品の購入費用です。
具体的には、以下のようなものが挙げられます。
| 事務所・店舗の設備 |
|
|---|---|
| 事業用車両 |
|
| その他 |
|
オフィスの契約
オフィスの契約費用は、開業費の中でも大きな割合を占める重要な項目です。
主に以下の費用が含まれます。
| 賃料 | オフィスの広さや立地、設備によって大きく変動する。一般的な目安としては、敷地面積1坪あたり月額1万円~2万円程度 |
|---|---|
| 敷金・礼金 | 敷金は家主に預けるお金。礼金は家主への謝礼金です。敷金は賃料の1~10ヶ月分、礼金は賃料の1ヶ月分が目安 |
| 仲介手数料 | オフィス探しを不動産会社に依頼した場合、賃料の1ヶ月分+消費税が上限 |
| 前家賃 | 契約開始月から翌月末までの家賃を前払いする |
| 共益費 | 建物全体の維持管理に必要な費用。賃料の10~20%程度が目安 |
| 火災保険料 | オフィスや店舗などが火災などによって損害が出た場合に支払われる保険 |
| その他 | 登記費用、事務所開設届費用、引っ越し費用、インターネット回線工事費用など、オフィス開設に伴う各種費用も含まれる |
契約前にしっかりと確認し、慎重に検討することが大切です。
広告費
広告費用とは、事業の周知や顧客獲得のために支出する費用です。
広告費用の例としては、以下のようなものが挙げられます。
- チラシやパンフレット、ポスター等の印刷費
- ウェブサイトやSNS広告の制作費
- 広告代理店への手数料
- メディアへの掲載料
- イベント開催費用
- 開業セレモニー費用
開業費として計上された広告費用は、繰延資産として処理されます。繰延資産とは、開業当初にまとめて計上した費用を、任意の事業年度で費用として計上できるようにするものです。
名刺作成費
開業費とは事業を始めるために必要な費用を指すため、実際に事業が稼働する前から営業などで必要になる名刺の製作費も含めることができます。
維持費
続いて、維持費の内訳を見ていきましょう。維持費とは、事業を運営していくため必要な運転資金のことです。
各種税金
起業時の維持費に含まれる税金は、大きく分けて以下の5つです。
| 法人税 | 法人が得た利益に対して課される税金。利益がなければ法人税はかからない |
|---|---|
| 法人住民税 | 法人が所在地とする市町村に納める税金。法人税の額に一定税率を乗じて計算される法人税割と法人であれば等しく払う義務のある均等割がある |
| 所得税 | 個人が得た所得に対して課される税金。事業所得は、所得税の課税対象となる |
| 消費税 | 商品やサービスの販売などでお客さまから預かっている税金。基準期間の課税売上高が1,000万円を超える場合やインボイス登録を行った事業者の場合、消費税の納税義務が発生する |
| 固定資産税 | 土地や建物、一定価額を超える設備などの固定資産に対して課される税金。法人が所有する固定資産は、固定資産税の課税対象となる |
また、上記以外にも行う取引や手続きによって登録免許税、印紙税、不動産取得税などがかかってきます。
社会保険料
起業したら、会社と従業員はそれぞれ社会保険料を負担する必要があります。社会保険料は、健康保険、厚生年金保険、雇用保険、介護保険の4つで構成されています。
社会保険料は、標準報酬月額に基づいて計算されます。標準報酬月額は、給与や賞与などの報酬額をもとに算定されるもので、加入する健康保険組合や都道府県などによって異なります。
また社会保険料の負担割合は、会社と従業員でそれぞれ半額ずつ負担します。
事業所・店舗の賃貸費
起業したら事業所・店舗の賃貸費は、事業内容、立地、広さ、設備などによって大きく異なります。
具体的な例は下表のとおりです。
| SOHO | 自宅の一室を事業所として利用。費用は月額数万円程度 |
|---|---|
| レンタルオフィス | 都市部の広さ10坪ほどで月額10万円程度~ |
| 賃貸物件 | 駅前立地の広さ20坪ほどで月額20万円程度~ |
※SOHO…「Small Office Home Office」の略で、一般的には受託した委託業務を自宅や小さなオフィスで行う働き方
※参考:アットホーム:貸事務所
※参考:レンタルオフィス スペイシー
設備費
設備費は、設備の種類、規模、使用頻度、保守管理方法などによって大きく異なります。
一般的な設備費の目安は下表のとおりです。
| オフィス機器 |
|
|---|---|
| 通信設備 |
|
事前にしっかりと計画を立て、予算に合った設備を導入することが重要です。
通信費
通信費は、事業内容、利用する通信回線、データ使用量、契約プランなどによって異なります。
一般的な通信費の目安は下表のとおりです。
| 固定回線 |
|
|---|---|
| モバイル回線 |
|
| その他 |
|
予算に合わせて、通信回線やプランを選択しましょう。
専門家への依頼料
専門家への依頼料は、専門家の種類、経験、依頼内容、作業量などによって異なります。
一般的な専門家への依頼料の目安は下表のとおりです。
| 税理士・会計士 |
|
|---|---|
| 弁護士 |
|
| コンサルタント |
|
専門家への依頼料は、事業の成長に伴い増加していく可能性があります。定期的に専門家への依頼内容を見直しましょう。
人件費
人件費は、事業規模や業種、雇用形態、従業員の給与水準などによって変わります。
一般的には、人件費は売上高の30~50%程度と言われています。しかし、これはあくまでも目安であり、業種や企業規模によって大きく異なります。
起業に必要な資金を調達する方法5選

起業資金を自己資金だけで準備するのは大変であるため、複数の方法を組み合わせて資金調達するのが一般的です。
起業資金の集め方としては、大きく分けて5つの方法があります。
| 資金調達方法 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 自己資金を使う |
|
|
| 出資を受ける |
|
|
| 家族や知人から借入する |
|
|
| 金融機関から融資を受ける |
|
|
| 補助金や助成金を申請する |
|
|
補助金・助成金の違いについては、次の記事をご覧ください。
自己資金を使う
自分で貯めたお金(自己資金)を元手に起業することは、基本的な資金調達の方法だと言えます。
自らが出資者となるため、経営の自由度が高くなるのがメリットです。もちろん金利の負担を気にする必要もなく、トラブルが起こるリスクもありません。ただし、基本的に資金には限りがあるため、万が一事業が成功しなかったときには個人資産を失ってしまうというデメリットがあります。
出資を受ける
資金調達の方法には、他企業やエンジェル投資家から出資を受けたり、クラウドファンディングで出資を募ったりする方法もあります。
出資を受けるメリットは、返済が不要だという点です。また、投資家や起業家からのアドバイスを受けることができるほか、投資家同士のネットワークにより人脈も広がります。ただし、出資比率や投資契約の内容によっては、経営権を握られてしまうケースがあるほか、制約を受ける可能性がある点がデメリットです。
出資元には、主に以下のような種類があります。
- 【出資者の種類】
-
- ベンチャーキャピタル(ファンド)
- クラウドファンディングの会員
- エンジェル投資家
- 他企業
家族や知人から借入する
家族や友人、知人などから個人的な借入をして資金調達する方法もあります。親族や友人、知人からの個人的な借入なら審査が必要なく、借入条件を自由に決められるため、融通が利きやすいというメリットがあります。
その反面、近しい存在だからこそ曖昧な約束になってしまったり、後でトラブルになったりする可能性があるなど、デメリットも大きいのが難点です。
金融機関から融資を受ける
資金調達の方法として、日本政策金融公庫や金融機関からの融資がよく利用されています。日本政策金融公庫からの創業融資は、融資を受けるまでの期間が短いのがメリットです。金融機関からの融資は審査が比較的厳しく、融資までにある程度時間を要します。融資は出資や個人的な借入とは違い、経営への介入や人間関係のしがらみがないというメリットがあります。
ただし、出資や補助金・助成金などと違い、いずれも金利負担や返済義務があるのがデメリットです。起業資金として利用される融資には、次のようなものがあります。
- 【融資の種類】
-
- 日本政策金融公庫の創業融資・・・「新規開業資金」「女性、若者/シニア起業家支援資金」等
- 民間金融機関からの融資・・・自治体の制度融資、銀行や信用金庫からの融資等
補助金や助成金を申請する
資金調達の方法としては、補助金や助成金を申請するという方法もあります。 補助金や助成金は、返済しなくてもよいのが最大のメリットですが、申請手続きに手間がかかる上に要件が厳しいため、すぐに受け取れないというデメリットがあります。
とはいえ、支払った費用を後から支給するという仕組みが基本であるため、当面の資金は必要となります、そのため、補助金や助成金があるからといって、自己資金の準備は怠らないよう注意しましょう。
補助金・助成金の例としては、以下のようなものがあります。また、自治体独自に設けている制度もあるため、各自治体のホームページを確認しましょう。
- 【補助金や助成金の種類】
-
- 経済産業省の「ものづくり補助金」「小規模事業者持続化補助金」等
- 厚生労働省の「キャリアアップ助成金」「人材確保等支援助成金」「中途採用等支援助成金」等
- 東京都の「創業助成事業」、大阪府の「大阪起業家グローイングアップ事業」等
起業資金に関するよくある質問
ここでは、起業資金に関する「よくある質問」に回答します。
起業家への支援制度はどこで情報収集できる?
「経済産業省」や「独立行政法人中小企業基盤整備機構」といった公的機関が、積極的に起業家の支援を行っています。そのため、起業家への支援制度については、これらの公式サイトで情報収集することをおすすめします。
また、それぞれの自治体でも、起業家へ独自の支援制度を設けているところがあります。都道府県や市町村の広報サイトなども、こまめにチェックすると情報収集できるでしょう。公的機関以外にも株式会社プロジェクトニッポンが運営する「DREAM GATE」などで起業家支援に関する情報収集が可能です。
- 【起業家への支援制度の例】
-
- 女性、若者/シニア起業家支援資金・・・日本政策金融公庫による、女性の方、35歳未満または55歳以上の方の創業者に融資する制度
- 起業支援ファンド・・・ベンチャー企業が新事業等に取り組む際の、ファンドによる資金提供・経営支援
- エンジェル税制・・・ベンチャー企業へ投資を行った個人投資家に対して、税制上の優遇措置を行う制度
開業するのに最低いくら必要?
開業資金は、業種や規模、立地などによって大きく異なるため、一概にいくらとは言えません。
日本政策金融公庫の調査によると、2023年度の新規開業実態調査における開業費用の平均は1,027万円でした。ただしこれはあくまでも平均値であり、中央値は550万円となっており、長期的に見ると少額化している傾向です。
自分に合った調達方法を選ぶことが重要
本記事では、起業時に必要な開業費用や開業費用の集め方、会社設立後にかかる費用などについて解説しました。
起業資金とは、起業する時に必要な設備資金と運転資金をトータルした資金のことです。必要な起業資金は事業内容や企業規模によって異なるため、各必要経費の支出項目を具体的にリストアップするところから始めてみてください。
また、起業資金の調達方法にはさまざまな方法が存在します。近年は、起業にかかわる補助金や助成金なども数多く存在し、多くの方々が起業しやすい時代と言えるでしょう。しかし、調達方法によってメリット・デメリットも異なるため、あなたに合った調達方法を選ぶことが重要です。
起業の窓口では、起業に関するさまざまなサポートを受けることができます。スムーズに起業を進めたい方や、起業後に後悔したくない方は、ぜひ活用してみてください。
会社の銀行口座(法人口座)はGMOあおぞらネット銀行がおすすめ!

画像引用元:GMOあおぞらネット銀行
会社設立時にネットバンクで銀行口座を開設するなら、GMOあおぞらネット銀行がおすすめです。
手間なくスピーディーに口座開設できる点が強みで、口座開設手続きは印鑑レス・ペーパーレス・郵送レスで行うことができます。また、条件を満たせば最短即日で口座を開設できます。
振込手数料は同行宛て無料に加え、他行宛てでも一律145円/件(税込)と低価格で、さらに設立1年未満のお客さまであれば、他行宛て振込手数料が月20回まで無料です。
創業期のお悩みを解決するため、外部企業と提携してさまざまなサービスを紹介するビジネスサポートも行っており、会社運営の面でも強い味方になるでしょう。ぜひGMOあおぞらネット銀行をご利用ください。
起業や開業、独立に興味を持ったら、まずは「起業の窓口」に登録してみよう!
「起業の窓口」では、起業に必要なノウハウや成功者のインタビューなど、さまざまなコンテンツを完全無料で提供しています。
会員特典として、起業・経営支援のプロ「V-Spirits」が監修するオリジナル冊子『会社設立完全ガイド』を無料プレゼント。さらに、V-Spritsによる1時間の無料起業相談や、GMOインターネットグループが展開するビジネスの立ち上げや拡大に役立つ各種サービスをおトクな特典付きでご紹介します。
あなたの夢の実現を全力でサポートします!
- 記事監修
-
- 中野 裕哲 HIROAKI NAKANO
- 起業コンサルタント(R)、経営コンサルタント、税理士、特定社会保険労務士、行政書士、サーティファイドファイナンシャルプランナー・CFP(R)、1 級FP 技能士。 V-Spiritsグループ創業者。東京池袋を本拠に全国の起業家・経営者さんを応援!「あの起業本」の著者。著書16冊、累計20万部超。経済産業 省後援「DREAMGATE」で11年連続相談件数日本一。
GMOインターネットグループ株式会社はGMOあおぞらネット銀行株式会社を所属銀行とする銀行代理業として、円普通預金の受入れを内容とする契約の締結の媒介を行います。
銀行代理業許可番号:関東財務局長(銀代)第335号
- ※本記事は、起業の窓口編集部が専門家の監修のもとに制作したものです。
- ※掲載している情報は、記事の公開・更新時点における商品・サービス、法令、税制に基づいており、将来これらは変更される可能性があります。
- ※記事内容の利用・実施については、ご自身の責任と判断でお願いいたします。
- ※本記事は一般的な情報提供を目的としております。個人の状況に応じた具体的な助言が必要な場合は、専門家にご相談ください。
関連記事
- 起業・創業の新着記事
- 起業・創業の人気記事ランキング
- タグリスト
- AI×起業
- AI×起業特集はこちら
- 起業家インタビュー
- 起業家インタビュー一覧はこちら
- 監修者・執筆者一覧
- 監修者・執筆者一覧はこちら



 シェア
シェア