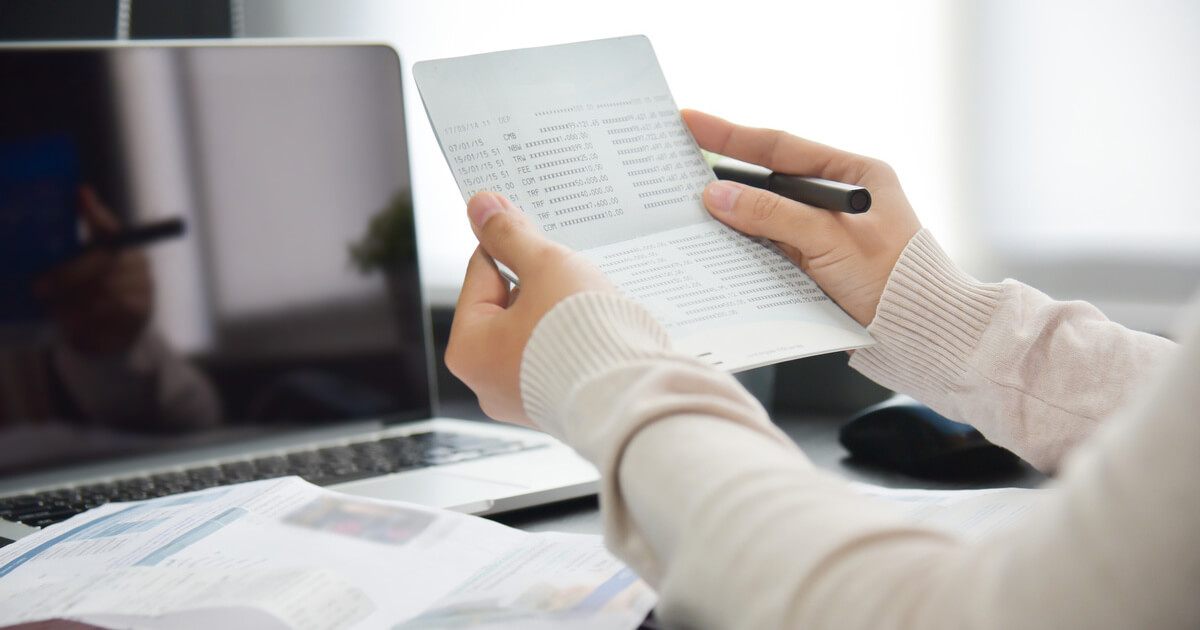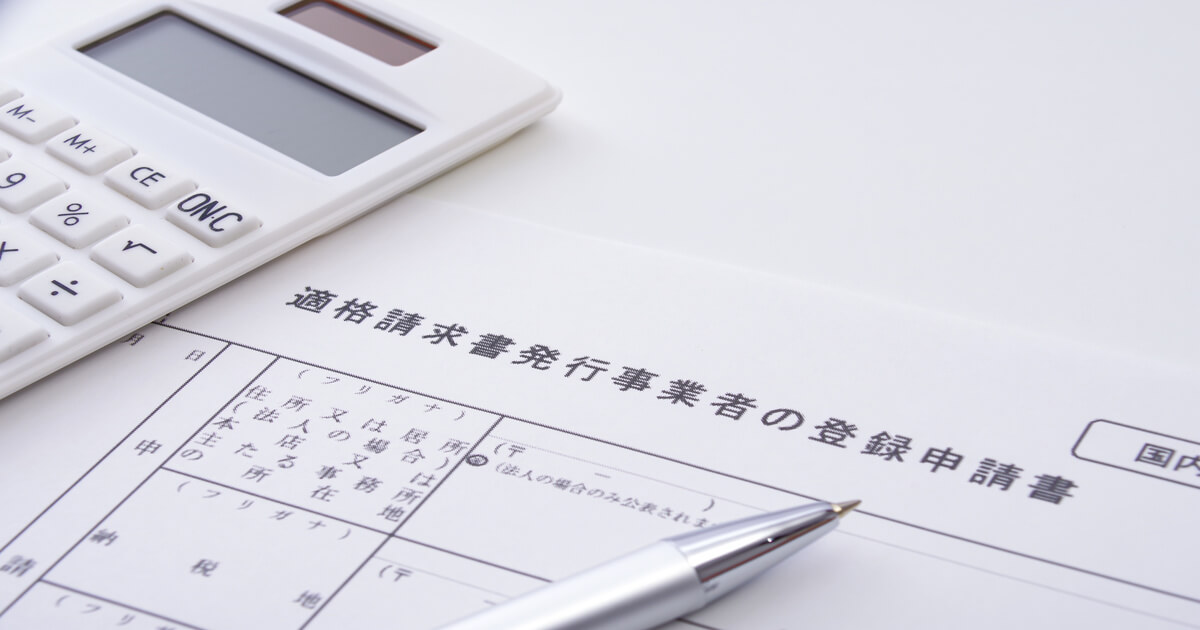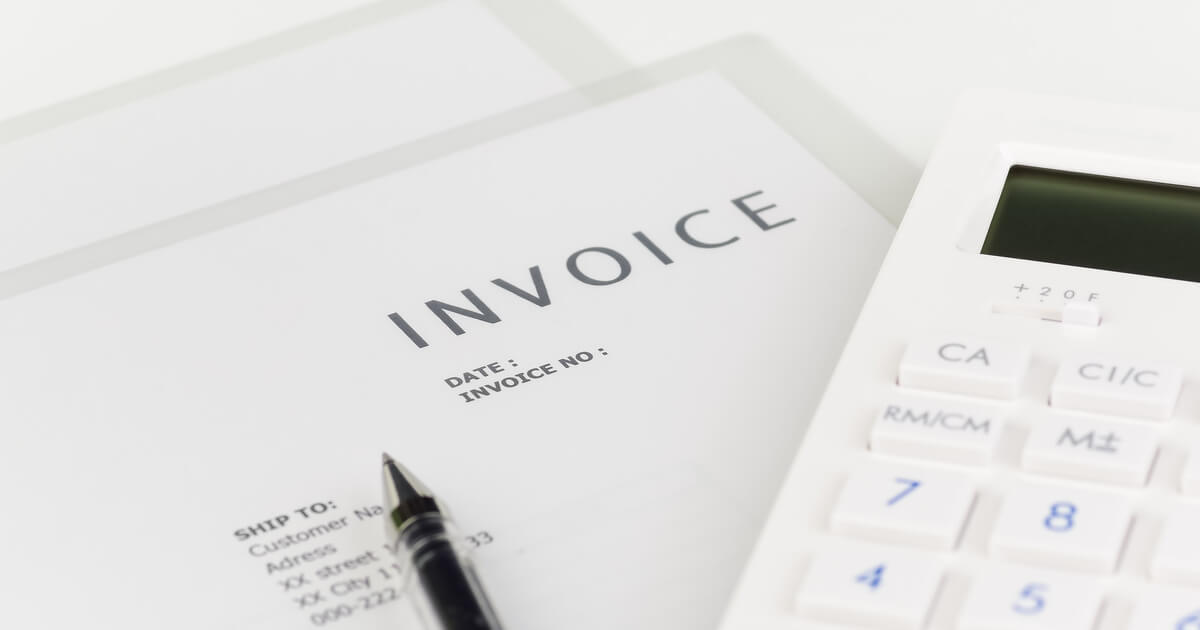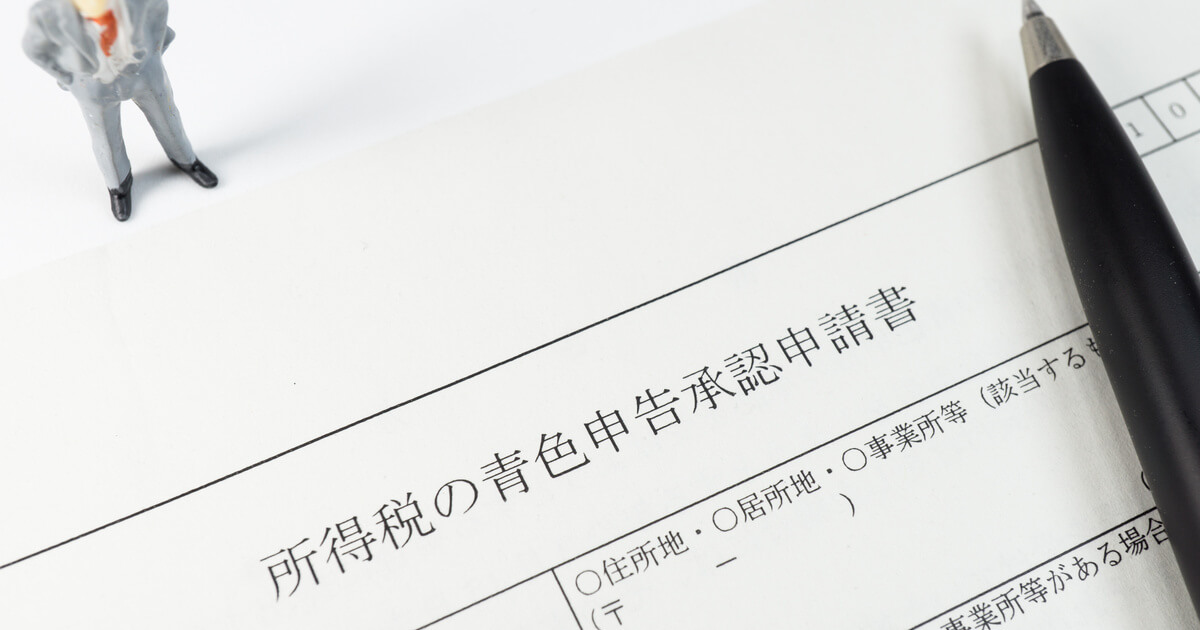個人事業主にかかる税金の種類と計算方法|節税対策や控除の種類も解説
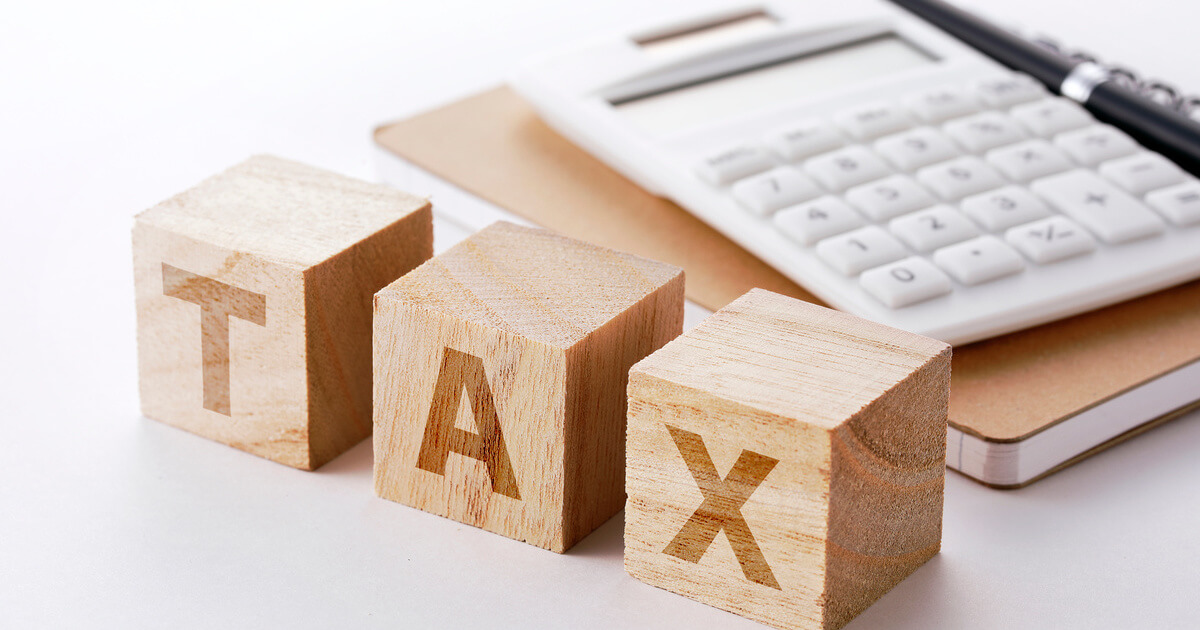
個人事業主には所得税、住民税、個人事業税、消費税などさまざまな税金が課され、それぞれ計算方法や納付時期が異なります。
青色申告特別控除や小規模企業共済等掛金控除など、適切な節税対策を活用すれば税負担を軽減することも可能です。
ただし、申告漏れや納税遅延があった場合には、延滞税や加算税などの重いペナルティが課される場合があります。
この記事では、個人事業主にかかる税金の種類と計算方法、効果的な節税対策、申告漏れなどで生じるペナルティ、控除の活用法について解説します。
- 【この記事のまとめ】
- 個人事業主が支払う税金には、所得税・住民税・消費税・個人事業税があります。各税金の納税方法は、インターネットバンクやクレジットカードなど、便利な手段が用意されています。
- 所得税は事業所得やその他の所得に基づき課税され、復興特別所得税も併せて納付します。税率は所得金額によって異なり、計算方法も明確に定められています。
- 住民税は住所地の自治体に納め、均等割と所得割が含まれます。消費税は売上に基づき、特定の売上を超えた事業主に課され、計算方法は2とおりあります。
2024年分(令和6年分)の所得税等の確定申告期間は2025年2月17日(月)から3月17日(月)です。
「起業の窓口」では、確定申告の方法、青色申告や白色申告の基礎知識、手続きの流れ、節税のコツなどを詳しく解説しています。
ぜひ、「確定申告」に関する他の記事もご覧ください。
2024年11月1日より、フリーランス保護法が施行されます。
組織に所属せずに働くフリーランスが安心して働ける環境を整備するために、フリーランスと企業などとの発注事業者間の取引の適正化(契約書等により取引条件を明示する)が主な目的です。
詳しくは次の記事をご覧ください。フリーランス保護法の概要、制定された背景や具体的な内容などを解説しています。
個人事業主にかかる税金の種類

個人事業主が支払う税金には、以下のような種類があります。
| 税金の種類 | 内容 | 納税方法 | 対象者 |
|---|---|---|---|
| 所得税・復興特別所得税 | 所得税:1年間の課税所得に対する税金 復興特別所得税:東日本大震災の復興に必要な財源を確保するための所得税 |
インターネットバンク・クレジットカード・ダイレクト納付・税務署や金融機関での納付 | 事業所得やその他の所得を得た個人事業主 |
| 住民税 | 住所地の都道府県・市町村に納める税金 | 納付書を基に一括または4期分割で現金納付(インターネットバンクやクレジットカード、銀行引き落としなどに対応している自治体もある) | 1月1日時点で市町村内に住所がある個人事業主、住所はないものの事務所や事業所がある個人事業主 |
| 消費税 | 商品やサービスの消費に対して発生する税金 | インターネットバンク・クレジットカード・ダイレクト納付・コンビニ納付・税務署や金融機関での納付 | 前々年の課税売上高が1,000万円を超えた個人事業主 インボイス発行事業者となった個人事業主 |
| 個人事業税 | 各都道府県ごとに定められた一定の業種に対する税金 | クレジットカード・口座振替・コンビニ納付・金融機関での税金納付 | 各都道府県ごとに定められた業種に当てはまる個人事業主 |
個人事業主が支払う税金は、大きく分けて所得税・復興特別所得税、住民税、消費税、個人事業税の4つです。
確実に納税するためにも、まずは支払う税金の種類やその内容、対象者を把握しておきましょう。
所得税・復興特別所得税
所得税は、個人事業主については1年間の収入から経費や控除分を差し引いた事業所得やその他の所得に発生する税金を指します。
復興特別所得税は、東日本大震災の復興に必要な財源を確保するために創設された所得税です。
主な納税方法はインターネットバンク・クレジットカード・ダイレクト納付・税務署や金融機関での現金納付です。また、課税事業所得金額によって所得税の税率や控除額が変わります。
| 課税所得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 195万円未満 | 5% | 0円 |
| 195万円~330万円未満 | 10% | 97,500円 |
| 330万円~695万円未満 | 20% | 42万7,500円 |
| 695万円~900万円未満 | 23% | 63万6,000円 |
| 900万円~1,800万円未満 | 33% | 153万6,000円 |
| 1,800万円~4,000万円未満 | 40% | 279万6,000円 |
| 4,000万円超 | 45% | 479万6,000円 |
所得税・復興特別所得税の計算方法
所得税と復興特別所得税の計算式は、以下のとおりです。
- 【計算式】
-
- 所得税:課税事業所得×税率-税額控除額
- 復興特別所得税:所得税額×2.1%
- 【課税事業所得600万円の場合の計算例】
-
- 所得税:600万円×20%-42万7,500円=77万2,500円
- 復興特別所得税:77万2,500円×2.1%=1万6,200円(100円未満切り捨て)
住民税
住民税とは、住所地の都道府県・市区町村に納める税金のことです。納付書を基に一括または4期分割で現金納付できるほか、自治体によってはインターネットバンクやクレジットカード、銀行引き落としなどで支払いが可能な場合もあります。
対象者は、1月1日時点で市町村内に住所がある個人事業主、住所はないものの事務所や事業所を有する個人事業主です。均等割と所得割の2種類があり、これらを合算した額を住民税として納付することになります。
均等割
所得額に関わらず、全ての人に対して均等に発生する税金額のことです。市町村民税3,500円、都道府県民税1,500円で合計5,000円が課せられます。
所得割
所得に対して発生する税金額のことです。税率は、都道府県民税4%+市町村民税6%=10%と一律で定められています。(政令指定都市は都道府県税2%、市町村民税8%)
住民税の計算方法
均等割は同じ額が課されますが、所得割は以下の計算式を用いて算出します。
- 【計算式】
-
- 所得割:事業所得×10%(都道府県民税4%+市町村民税6%)
- 【事業所得600万円の場合の計算例】
-
- 所得割:600万円×10%=6万円
- 所得割+均等割:6万円+5,000円=6万5,000円
消費税
商品やサービスの消費に対して発生する税金のことを指します。インターネットバンク・クレジットカード・ダイレクト納付・コンビニ納付・税務署や金融機関での納付を選択でき、対象者は前々年の課税売上高が1,000万円を超えた個人事業主です。
ただし、2023年10月からインボイス制度が始まり、インボイス登録をしている方については、前々年の課税売上高が1,000万円を超えていない場合でも消費税を納税する必要があります。
消費税の計算方法
消費税の計算は、原則課税方式と簡易課税方式の2種類があります。原則課税方式は計算方法が複雑なため、基準期間の売上額が5,000万円以下の場合は簡易課税方式の選択が可能です。ここでは、簡易課税方式の計算方法を紹介します。
- 【計算式】
-
- 簡易課税方式:(1年間の売上金額(税抜)×消費税率)- {(1年間の売上額(税抜)×消費税率)×みなし税率}
みなし税率は、業種によって変わります。
| 業種 | みなし税率 |
|---|---|
| 第1種事業(卸売業) | 90% |
| 第2種事業(小売業) | 80% |
| 第3種事業(農業、漁業等) | 70% |
| 第4種事業(飲食店業等) | 60% |
| 第5種事業(運輸業、金融業等) | 50% |
| 第6種事業(不動産業) | 40% |
- 【売上税抜600万円の場合の計算例(卸売業の場合)】
-
(600万円×10%)- {(600万円×10%)×90%}=6万円
個人事業税
都道府県ごとに定められた一定の業種に対する税金です。納税方法は、クレジットカード・口座振替・コンビニ納付・税務署や金融機関での税金納付があります。
各都道府県指定の業種に当てはまる個人事業主が対象です。地域によって各業種の税率は変わりますが、こちらでは東京都のケースを確認しましょう。
| 区分 | 税率 | 事業の種類 |
|---|---|---|
| 第1種事業 | 5% | 物販販売業、保険業、飲食店業等 |
| 第2種事業 | 4% | 畜産業、水産業等 |
| 第3種事業 | 5% | 医業、士業、デザイン業等 |
| 3% | マッサージ・指圧などその他の医業に類する事業 |
個人事業税の計算方法
個人事業税には、所得に関わらず290万円の控除があります。そのため、事業所得(青色申告特別控除の適用前)が290万円以下なら個人事業税を払う必要はありません。
- 【計算式】
-
個人事業税:(事業所得-290万円)×税率
- 【青色申告特別控除前の事業所得600万円の計算例(飲食店業の場合)】
-
(600万円-290万円)×5%=15万5,000円
【例】個人事業主が支払う税金のシミュレーション
個人事業主が支払う税金の種類を解説しましたが、「実際どの程度支払うのか想像できない」という方も多いのではないでしょうか。
ここでは、個人事業主が支払う税金のシミュレーションを行い、支払い金額の目安を算出します。
- 【前提条件】
-
- 個人事業主で年間収入:600万円
- 事業で取り扱う全ての消費税率:10%
- 年間の必要経費:200万円
- 基礎控除額:48万円(年間)
- 青色申告特別控除額:65万円
- 40歳・独身・配偶者や扶養家族なし
- 社会保険料は考慮しない
- 予定納付や源泉徴収はなし
- インボイス登録なし
- 【年収600万円の課税所得】
-
- 所得:600万円-200万円=400万円
- 課税所得:400万円-48万円-65万円=287万円
これらの情報を用いて、年収600万円の所得税・住民税・個人事業税・消費税を算出します。
- 【年収600万円の各種税金額】
-
- 所得税額:287万円×10%-9万7,500円=18万9,500円
- 住民税額(およそ10%):287万円×10%+5,000円=29万2,000円
- 個人事業税額:0円
- 消費税額:0円
- 税金の合計:18万9,500円+29万2,000円=48万1,500円
合計所得金額が290万円を下回る場合、個人事業税は発生しません。
また、消費税はインボイス登録しておらず、2年前の課税売上高が1,000万円以下であれば、個人事業税額と同様に免除されます。
したがって、年間収入600万円、必要経費200万円、基礎控除額48万円の個人事業主の場合、所得税、住民税、個人事業税、消費税を合わせて48万1,500円の納税が見込まれます。
ただし、これはあくまで一例です。実際の納税額は、収入や経費の額、控除の利用状況に応じて大きく変動します。
税理士などの専門家に相談しながら、適切な申告と納税を行いましょう。
個人事業主の年収別の手取り早見表
個人事業主の手取りは、年間の収入によって大きく異なります。手取りを計算するうえでは、単純な収入だけでなく、累進課税や青色申告の有無を考慮して計算します。
- 【前提知識】
-
- 所得税:課税所得に5〜45%の税率を乗じる
- 住民税:所得割は課税所得に10%を乗じる
- 個人事業税:課税標準額に暫定的に5%の税率を乗じる
- 消費税:(売上に係る税額 – 仕入れに係る税額)×10%
- 事業所得:事業収入-必要経費
- 【前提条件】
-
- 消費税は原則課税
- 原価率:40%
- 国民年金保険料と国民健康保険料を加える
前提条件を踏まえた場合、個人事業主の年収別の手取りは以下のようになります。
| 事業所得 | 手取り(青色申告) | 手取り(白色申告) |
|---|---|---|
| 300万円 | 232万1,000円 | 221万7,000円 |
| 400万円 | 301万7,000円 | 288万5,000円 |
| 500万円 | 368万5,000円 | 349万6,000円 |
| 600万円 | 367万円 | 347万3,000円 |
| 700万円 | 414万7,000円 | 394万9,000円 |
| 800万円 | 462万3,000円 | 442万5,000円 |
| 900万円 | 509万9,000円 | 488万6,000円 |
| 1,000万円 | 559万7,000円 | 537万9,000円 |
累進課税により、事業所得が上がれば上がるほど所得税の税率も上がるため、事業所得に比べて手取りが少なくなります。
また、青色申告と白色申告では、どの事業所得を比べても手取りに差が生まれます。
個人事業主で手取りを増やすためには、適用できる控除を適切に活用し、青色申告で必要経費をもれなく計上することが大切です。
【重要】個人事業主ができる節税対策

個人事業主として事業を行う際には、節税対策を考えることも大切です。ここでは、個人事業主ができる効果的な節税対策を6つ紹介します。
青色申告をする
青色申告とは、確定申告の申告方法のひとつです。税務署に所定の期限までに「個人事業主の開業・廃業等届出書」と「所得税の青色申告承認申請書」を提出すれば、青色申告対象事業者として認められます。
青色申告の特徴は、最大65万円の控除を受けられることです。また、通常は個人事業主が家族に払った給与は経費計上できませんが、青色事業専従者給与制度を利用すれば家族に払った給与を経費として計上できます。
さらに、1年間の赤字分を翌年以降3年間繰り越せるのに加え、前年に繰り戻せるのも嬉しいポイントです。青色申告対象事業者となることは、大きな節税に繋がるといえるでしょう。
確定申告を楽にしたいと悩む方へ

質問に答えていくだけで、経理の作業がはじめての方でも簡単に確定申告の書類作成をすることができます!
確定申告を楽にサクッとおこないたい方は、freeeがおすすめです!
控除を利用する
控除とは収入や税金から差し引く金額のことで、所得控除と税額控除の2タイプがあります。どちらの控除もうまく利用することで節税効果を得られるでしょう。
所得控除は、課税対象所得を減額できる制度のことです。控除額が大きければ課税対象所得が減り、税額も下がります。
たとえば、所得控除40万円で所得税率20%となった場合、単純計算で40万円×20%=8万円の節税に繋がるのが基本的な考え方です。
税額控除は、支払う税金自体を減らせる制度です。所得税が40万円の場合、税額控除が30万円であるならば40万円-30万円=10万円へと税金が減額されます。なお、控除の主な例は以下のとおりです。
- 【控除の例】
-
- 所得控除:医療費控除、社会保険料控除、生命保険料控除、小規模企業共済等掛金控除など
- 税額控除:住宅借入金等特別控除、配当控除など
経費を見直す
経費とは、事業運営のために使用した費用のことです。事業所得は1年間の収入から経費と控除を差し引いた額になるため、必要な経費を計上することも節税に繋がります。主な経費の事例は以下のとおりです。
- 【経費の例】
-
- 消耗品費:事務所で使うペンやメモ帳の備品代
- 旅費交通費:タクシー代、電車代
- 接待交際費:取引先との飲食代
- 通信費:事業用携帯電話の通信費やプロバイダー費
- 水道光熱費:事務所や店舗の電気代、水道代、ガス代
- 地代家賃:事務所や店舗の賃料
なお、自宅兼事務所で水道光熱費や通信費、地代家賃などが発生した場合は、仕事で使用した分だけ家事按分として計上できます。本来経費として計上できる費用に抜け漏れがあるとその分所得が増え税率も高くなるため、経費となるものは全て把握するようにしてください。
ふるさと納税を利用する
ふるさと納税は、生まれ育った故郷や応援したい自治体に寄附をする制度です。
寄附金額のほとんどが所得税と住民税から控除されるため、ふるさと納税の特典を踏まえると、大きな節税効果が得られる可能性があります。
自治体のホームページなどで、寄附金の使途や特典を確認し、納得できる自治体を選ぶことが大切です。
手続き方法は自治体によって異なるため、選んだ自治体のホームページを確認するか、各自治体に直接問い合わせることをおすすめします。
ふるさと納税を活用することで、地域に貢献しながら確実に節税できるでしょう。
iDeCo(確定拠出年金)を活用する
iDeCoは、自営業者や専業主婦など、幅広い方が加入できる私的年金制度です。掛金は全額所得控除の対象となるため、所得税や住民税の負担を減らせます。
拠出限度額は、自営業者の場合は月額6万8,000円、専業主婦の場合は月額2万3,000円など、加入者の区分により異なります。
運営管理機関が提示する投資信託や保険商品などから運用商品を選択し、自身で運用するのが特徴です。
60歳以降に年金または一時金で受け取れますが、受給開始時期は加入期間によって異なるため注意が必要です。
iDeCoを賢く活用すれば、税負担を抑えつつ、ゆとりある老後資金を準備できます。
法人化を検討する
所得税の税率は所得金額に応じて5%から45%まで7段階に分かれていますが、法人税率は一定の所得金額までは一律です。
例えば、課税所得が800万円の場合、所得税の税率は23%ですが、法人税率は15%に抑えられます。
法人化には設立費用や煩雑な手続きが伴いますが、節税メリットは大きいといえるでしょう。
また、法人の場合は家事按分が不要で、事業に必要な支出は全て経費として計上できるため、仕訳作業がシンプルになります。
さらに、役員報酬を支払えば給与所得控除も活用できます。一定以上の所得がある個人事業主は、法人化を視野に入れた税務対策を検討してみてください。
個人事業主が利用できる控除の主な種類
ここでは、個人事業主が利用できる主な税額控除について解説します。
配偶者控除
配偶者控除は、納税者に所得税法上の控除対象配偶者がいる場合に受けられる所得控除です。
控除額は、納税者本人の合計所得金額と控除対象配偶者の年齢により異なります。
| 控除を受ける納税者本人の合計所得金額 | 控除額 | |
|---|---|---|
| 一般の控除対象配偶者 | 老人控除対象配偶者 | |
| 900万円以下 | 38万円 | 48万円 |
| 900万円超950万円以下 | 26万円 | 32万円 |
| 950万円超1,000万円以下 | 13万円 | 16万円 |
個人事業主にとっては、配偶者の収入が控除対象配偶者の条件を満たすかどうかを確認することが重要です。
配偶者の収入が増えて控除の対象外になった場合、想定外の増税となってしまうため、配偶者の収入状況に注意しましょう。
医療費控除
医療費控除は、納税者本人や生計を共にする家族のために支払った医療費が一定額を超えた場合に受けられる所得控除です。
控除額は、支払った医療費の合計額から保険金等で補填される金額と、10万円(総所得金額等が200万円未満の場合は総所得金額等の5%)を差し引いた金額になります。
- 【控除額の計算式】
-
(支払った医療費の合計額 – 保険金等で補填される金額)-10万円(または総所得金額等の5%)
個人事業主の場合、事業専従者である家族の健康管理にかかる費用も、一定の条件を満たせば医療費控除の対象となります。
領収書の保管を徹底し、確定申告時に控除を受けられるよう備えておくことが大切です。医療費控除の上限額は200万円であることも覚えておきましょう。
社会保険料控除
社会保険料控除は、納税者本人や生計を共にする家族の負担すべき社会保険料を支払った場合に受けられる所得控除です。
控除の対象となる社会保険料は以下のとおりです。支払った金額または給与等から差し引かれた金額の全額が控除額となります。
- 【社会保険料控除の対象】
-
- 健康保険料、国民年金保険料、厚生年金保険料
- 国民健康保険料、介護保険料
- 国民年金基金の掛金など
個人事業主は、自身で国民年金保険料を支払っている方が多いため、確定申告時に社会保険料控除を適用できます。
また、従業員を雇用している場合は、従業員の社会保険料も含めて事業主負担分を支払っている可能性があります。
これらの支払額も社会保険料控除の対象になるため、漏れなく申告しましょう。
保険料は事業を継続するうえで欠かせない経費ですが、社会保険料控除を活用することで、納税額を抑える効果が期待できます。
生命保険料控除
生命保険料控除は、個人事業主が生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料を支払った場合に受けられる所得控除です。
控除額は支払った保険料の種類や年額に応じて、下表のように計算されます。
- 【新契約(平成24年1月1日以後締結)の場合】
-
年間の支払保険料等 控除額 20,000円以下 支払保険料等の全額 20,000円超 40,000円以下 支払額×1/2+10,000円 40,000円超 80,000円以下 支払額×1/4+20,000円 80,000円超 一律40,000円
個人事業主の場合、節税対策として生命保険料控除を有効活用することをおすすめします。
ただし、保険期間が5年未満の一部の保険は控除対象外なので注意が必要です。
生命保険料控除の適用を受けるには、確定申告時に保険料の支払証明書などを添付する必要があります。
小規模企業共済等掛金控除
小規模企業共済等掛金控除は、個人事業主が小規模企業共済制度などに加入し、掛金を支払った場合に受けられる所得控除です。
控除の対象となる制度と掛金は以下のとおりで、支払った掛金全額が所得から控除されます。
- 小規模企業共済制度の掛金
- 確定拠出年金の企業型年金や個人型年金の掛金
- 地方公共団体が条例で定める心身障害者扶養共済制度の掛金
小規模企業共済制度は、廃業時や事業継続が困難になったときの生活の安定を図ることを目的とした国の共済制度です。
掛金は全額所得控除でき、共済金の受取時も一時所得として低い税率で課税されるため、節税メリットが大きいのが特徴です。
個人事業主にとって、将来のリスクに備えつつ所得税の負担を減らせる点は、大変魅力的だといえるでしょう。
なお、小規模企業共済等掛金控除の適用には、確定申告の際に共済契約証書や掛金の領収証などの提示・添付が必要です。
住宅借入金等特別控除
住宅借入金等特別控除とは、個人が住宅ローンを利用して住宅を新築または購入した場合、一定の要件のもと、ローン残高に応じた所得税額の控除が受けられる制度のことです。
控除期間は10年または13年で、控除額は以下のように計算されます。
| 居住開始年 | 控除期間 | 各年の控除限度額 |
|---|---|---|
| 令和3年1月1日から令和4年12月31日まで | 13年 |
[住宅の取得等特別特例取得または特例特例取得に該当する場合] 【1~10年目】 年末残高等×1%(50万円) 【11~13年目】次のいずれか少ない額が適用 1. 年末残高等×0.7%(上限5,000万円) 2. (住宅取得等対価の8% – 消費税等)(上限5,000万円)×2% ÷ 3 |
| 令和4年1月1日から令和5年12月31日まで | 13年 |
[認定住宅に該当する場合] 年末残高等(上限5,000万円)×0.7% [特定エネルギー消費性能向上住宅に該当する場合] 年末残高等(上限4,500万円)×0.7% [エネルギー消費性能向上住宅に該当する場合] 年末残高等(上限4,000万円)×0.7% |
| 令和6年1月1日から令和7年12月31日まで | 13年 |
[認定住宅に該当する場合] 年末残高等(上限5,000万円)×0.7% [特定エネルギー消費性能向上住宅に該当する場合] 年末残高等(上限4,500万円)×0.7% [エネルギー消費性能向上住宅に該当する場合] 年末残高等(上限4,000万円)×0.7% |
引用:No.1213 認定住宅の新築等をした場合(住宅借入金等特別控除)|国税庁
事務所兼住宅を取得する際に、この制度の適用を検討してみるのもよいでしょう。
住宅部分については、床面積の2分の1以上を居住用に充てる必要がある点には注意が必要です。
確定申告を楽にしたいと悩む方へ

質問に答えていくだけで、経理の作業がはじめての方でも簡単に確定申告の書類作成をすることができます!
確定申告を楽にサクッとおこないたい方は、freeeがおすすめです!
【注意】納税遅延や申告漏れなどで生じるペナルティ

個人事業主が税金の納付を遅延したり、申告を怠ったりした場合には、税務署から厳しいペナルティが課される場合があります。以下、発生するペナルティの例を紹介します。
延滞税が課される
税金の納付期限を過ぎると、延滞した期間に応じて延滞税が発生します。
延滞税の計算方法は、納付までの期間により2つのパターンに分かれており、期限後2ヵ月以内と2ヵ月超で適用される税率が異なります。
- 【納付期限後2ヵ月以内に完納する場合】
-
- 延滞税額=本税額×延滞税率×延滞日数÷365日
- 適用税率:年7.3%または「延滞税特例基準割合+1%」の低い方
- 【納付期限後2ヵ月を超えて完納する場合】
-
- 延滞税額=本税額×延滞税率×延滞日数÷365日
- 適用税率:年14.6%または「延滞税特例基準割合+7.3%」の低い方
2ヵ月を超えると税率が大幅に上昇するため、早期納付が重要となります。また、延滞税特例基準割合は毎年見直されるため、実際の計算時は最新の税率を確認する必要があります。
各種加算税が課される
確定申告の期限を過ぎたり申告内容に誤りがあった場合は、本来の税額に加えて各種加算税が課される可能性があります。
加算税には過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税、重加算税の4種類が存在します。
| 種類 | 税率 |
|---|---|
| 過少申告加算税 | 期限内申告で税額が少なかった場合に10%(期限内申告税額と50万円のいずれか多い額を超える部分は15%) |
| 無申告加算税 | 法定申告期限後に申告をした場合、原則として次の税率が適用 納付すべき税額のうち 50万円までの部分:15% 納付すべき税額のうち 50万円を超える部分:20% ただし、税務署から調査の事前通知を受ける前に自主的に申告した場合には、加算税は一律 5% に軽減さ また、悪質な無申告を繰り返している場合などは、加重税率(最高30%)が適用されることがある(2024年改正) |
| 不納付加算税 | 源泉徴収税を期限内に納付しなかった場合に5%(税務署の指摘を受けた場合は10%) |
| 重加算税 | 隠蔽や仮装があった場合に過少申告は35%、無申告は40%の懲罰的税率 |
正当な理由がある場合や、税務調査前に自主的に修正申告を行えば、加算税が免除または軽減される可能性があります。
申告ミスが悪質と判断されないよう、日頃から適切な記帳と申告を心がけることが重要です。
青色申告が取り消される
2年連続で期限内申告を怠ったり帳簿書類の備付けが不十分だったりする場合、青色申告の承認が取り消されるリスクがあります。一度取り消されると再申請しても1年間は承認されません。
最大65万円の特別控除が受けられなくなり、税負担が増加してしまいます。
また、赤字の繰越控除や青色事業専従者給与など、個人事業主にとって重要な税制優遇措置も全て利用できなくなるため注意が必要です。
刑事責任を問われる可能性がある
故意に税金を免れようとする脱税行為は重大な犯罪であり、刑事責任を問われる可能性があります。所得税法違反では、10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金が科されます。
脱税で有罪となれば社会的信用を完全に失う他、取引先との契約解除や金融機関からの融資停止など、事業継続が困難になるケースも珍しくありません。
売上の除外や架空経費の計上、二重帳簿の作成など、明らかに悪質な行為は厳しく処罰される対象となるため絶対にやってはいけません。
個人事業主が税金を払っていない場合の対処法

税金の未納や申告漏れに気付いた場合は、放置せずに速やかに対処することでペナルティを最小限に抑えられます。ここでは、税金を払っていない場合の対処法を3つ紹介します。
過去分の税金を払う
未納の税金がある場合は過去の申告内容を確認し、正確な納税額を計算したうえで速やかに納付手続きを進めることが最優先です。修正申告書を作成して本税と延滞税を合わせて納付します。
自主的に修正申告を行った場合、無申告加算税や過少申告加算税が軽減される可能性があります。
納付資金が不足している場合は分割納付の相談も可能です。過去5年分まで遡って申告できるため、複数年分の未納がある場合はまとめて処理することをおすすめします。
税務署に相談する
納税に関する不安や疑問がある場合は、税務署の相談窓口を積極的に活用しましょう。電話相談や来署相談は無料で、匿名での相談も可能です。
納付が困難な場合の分割納付や猶予制度についても、税務署の職員が現実的な解決策を一緒に検討してくれます。事前に相談内容を整理して必要書類を準備しておくとスムーズです。
相談記録を残しておくことで、後日のトラブル防止にも繋がるため、メモを取りながら相談することが重要となります。
税理士に相談する
複雑な税務処理や過去の申告に不安がある場合は、税理士への相談で専門的なアドバイスと適切なサポートを受けられます。
修正申告書の作成や税務調査への対応など、専門知識が必要な業務も代行してもらえるため、心強い味方となるでしょう。
初回相談は無料の事務所も多く、相談だけでも問題解決の糸口が見つかる可能性があります。
継続的な解決にはある程度の費用が発生しますが、ペナルティの軽減や適正な節税により、結果的にコストパフォーマンスがよくなるパターンもあるため、不安がある場合は検討してみてください。
個人事業主と法人の税金の違い

個人事業主が法人化を検討する際、税金の仕組みがどのように変わるのかを理解することは重要な判断材料となります。以下、個人事業主と法人の税金の違いについて詳しく解説します。
法人税
法人税は法人の所得に対して課される国税で、個人事業主の所得税に相当する税金です。税率は原則23.2%の固定税率が適用されるのが特徴です。
資本金1億円以下の中小法人については、年800万円以下の所得部分に15%の軽減税率が適用され、税負担の軽減が図られています。
個人事業主の所得税は累進課税で最高45%まで上昇するのに対し、法人税は一定税率である点が大きな違いです。
所得が高額になるほど法人化による節税効果が大きくなるため、年間所得が800万円を超えるあたりから法人化を検討する価値があります。
法人住民税
法人住民税は都道府県と市町村に納める地方税で、法人税額に連動する「法人税割」と所得に関係なく課される「均等割」で構成されています。
法人税額を課税標準として計算され、法人税額に自治体ごとの税率を乗じて算出します。
標準税率は都道府県民税が1.0%、市町村民税が6.0%ですが、大都市では超過税率が適用される場合があるため注意が必要です。
東京23区では合計10.4%の超過税率が適用され、資本金や法人税額により税率が変動することもあります。
一方、均等割は資本金等の額と従業員数により税額が決定される固定的な税金です。赤字でも必ず納付義務が生じ、最も低い区分でも年額7万円の負担があります。
法人事業税
法人事業税は都道府県に納める地方税で、法人の所得や収入、資本金等に応じて課税される仕組みです。税率は業種や所得金額により異なり、普通法人では3.5%〜7%程度が適用されます。
| 年間所得 | 税率 |
|---|---|
| 400万円以下の部分 | 3.5% |
| 400万円超800万円以下の部分 | 5.3% |
| 800万円超の部分 | 7% |
資本金1億円超の法人には外形標準課税が適用され、所得だけでなく付加価値や資本金等も課税対象となるのが特徴です。
所得が増加すると税率も段階的に上昇するため、事業計画を立てる際は税負担も考慮する必要があります。
特別法人事業税
特別法人事業税は2019年10月から導入された国税で、法人事業税と併せて都道府県に申告納付する税金です。法人事業税額に対して37%〜260%の税率を乗じて計算されます。
この税金は地域間の税収格差を是正する目的で創設され、国が徴収した後に地方に配分される仕組みとなっています。
個人事業主には存在しない税金であり、法人化により新たに負担することになる税金のひとつです。実質的には法人事業税の一部として扱われるため、申告や納付は法人事業税と同時に行います。
消費税及び地方消費税
消費税は、売上に含まれる消費税から仕入等で支払った消費税を差し引いて納付する税金で、個人事業主も法人も同じ仕組みが適用されます。
法人化のメリットとして、新設法人は最大2年間の免税期間を受けられる可能性があります。ただし、資本金1,000万円以上の法人は設立初年度から課税事業者となるため注意が必要です。
簡易課税制度やインボイス制度への対応など、消費税の取り扱いは複雑化しています。
個人事業主から法人化する際は、消費税の免税期間を最大限活用できるタイミングを検討することが節税のポイントとなります。
個人事業主の税金に関するよくある質問

個人事業主として活動する中で生じるよくある疑問を5つ紹介します。正しい知識を身につけることで、適切な税務処理と節税対策が可能となります。
副業から個人事業主になった場合、税金はどう変わる?
副業から個人事業主として独立すると、給与所得から事業所得への切り替えにより税金の計算方法が変わります。
青色申告を選択すれば、最大65万円の特別控除が受けられるようになります。
また、必要経費の範囲が広がり、事業に関連する支出を経費として計上できるため、課税所得を効果的に圧縮することが可能です。
ただし、源泉徴収がなくなるため、ご自身で税金を計算して納付する必要があります。
国民健康保険や国民年金への切り替えも必要となり、社会保険料の負担が増加する可能性もあるため、個人事業主への変更は総合的な検討が必要です。
開業初年度の税金で注意すべきポイントは?
開業初年度は売上が不安定な一方で初期投資がかさむため、適切な税務処理により税負担を軽減することが重要となります。
特にポイントとなるのが、青色申告承認申請書の提出です。青色申告承認申請書は開業から2ヵ月以内に提出しなければ、初年度から適用を受けられません。
青色申告は最大65万円の特別控除を受けられる他、事業で赤字が出た場合の最大3年間の繰り越しも可能となるため、個人事業主として本格的に活動するなら積極的に活用したい制度のひとつです。
また、個人事業主になった後は領収書や請求書の保管を徹底し、事業用とプライベートの支出を明確に区分することが大切です。
経費として認められるものと認められないものの基準は?
経費として認められるかどうかは、事業との関連性と必要性が判断基準となります。仕入原価、家賃、通信費、広告宣伝費などは典型的な必要経費です。
自宅兼事務所の場合は、事業使用割合に応じて家賃や光熱費を按分計上できます。その一方で、個人的な支出や家事費は経費にならず、スーツ代や散髪代なども原則として認められません。
判断に迷う場合は税理士に相談し、税務調査でも説明できる合理的な根拠を準備しておきましょう。
確定申告の期限に間に合わない場合はどうすればよい?
確定申告の期限である3月15日に間に合わない場合でも、できるだけ早く申告することでペナルティを最小限に抑えられます。
期限後申告となりますが、税務署から指摘される前に自主的に申告すれば、無申告加算税を軽減できます。
災害や病気など正当な理由がある場合は、期限延長の申請により認められる可能性があります。
税務署に足を運べない場合は、電子申告(e-Tax)の利用がおすすめです。e-Taxを利用すれば24時間いつでも申告でき、税務署の窓口に並ぶ必要もありません。
どうしても間に合わない場合は、概算でも期限内に申告し、後日修正申告する方法も検討すべきです。
収入が少ない年でも税金は払う必要がある?
収入が少なくても基礎控除48万円を超える所得があれば所得税の納税義務が発生し、住民税は所得に関わらず均等割が課されます。事業所得が赤字でも他の所得と通算できない場合があるのです。
国民健康保険料は前年の所得を基準に計算されるため、収入が減っても高額な保険料負担が続く可能性があります。
収入が激減した場合は、納税の猶予制度や減免制度の活用も検討できるため、税務署や自治体に相談することをおすすめします。
【まとめ】個人事業主は税金の仕組みを理解して賢く節税しよう!
この記事では、個人事業主にかかる税金の種類と計算方法、節税対策、控除の活用法について解説しました。
個人事業主は所得税、住民税、個人事業税、消費税など複数の税金を適切に管理し、期限内に納付することが重要です。
年間収入によって支払う税額は大きく変わるため、早見表などを活用し、おおよその目安を立てておくとよいでしょう。
青色申告特別控除や各種所得控除を最大限活用すれば、税負担を合法的に軽減できます。
税務処理に不安がある場合は、専門的な知識を持つ税理士のサポートを受けることで、適切な申告と効果的な節税対策を実現できます。
起業や開業、独立に興味を持ったら、まずは「起業の窓口」に登録してみよう!
「起業の窓口」では、起業に必要なノウハウや成功者のインタビューなど、さまざまなコンテンツを完全無料で提供しています。
会員特典として、起業・経営支援のプロ「V-Spirits」が監修するオリジナル冊子『会社設立完全ガイド』を無料プレゼント。さらに、V-Spritsによる1時間の無料起業相談や、GMOインターネットグループが展開するビジネスの立ち上げや拡大に役立つ各種サービスをおトクな特典付きでご紹介します。
あなたの夢の実現を全力でサポートします!
- 記事監修
-
- 中野 裕哲 HIROAKI NAKANO
- 起業コンサルタント(R)、経営コンサルタント、税理士、特定社会保険労務士、行政書士、サーティファイドファイナンシャルプランナー・CFP(R)、1 級FP 技能士。 V-Spiritsグループ創業者。東京池袋を本拠に全国の起業家・経営者さんを応援!「あの起業本」の著者。著書16冊、累計20万部超。経済産業 省後援「DREAMGATE」で11年連続相談件数日本一。
- ※本記事は、起業の窓口編集部が専門家の監修または独自調査(アンケート)に基づいて制作したものです。
- ※掲載している情報は、記事公開時点の法令・税制・商品・サービス等に基づくものであり、将来的に変更される可能性があります。
- ※アンケート調査に関する記述は、特定の調査対象者からの回答結果および編集部の見解を含んでおり、内容の正確性・完全性を保証するものではありません。
- ※記事の内容は一般的な情報提供を目的としており、すべての方に当てはまるものではありません。個人の状況に応じた具体的な助言が必要な場合は、専門家にご相談ください。
- ※情報の利用や判断、実施については、ご自身の責任で行っていただきますようお願いいたします。
- ※本記事に掲載された内容の転載・複製はご遠慮いただき、引用の際は必ず出典をご明記ください。
関連記事
30秒で簡単登録
厳選サービスを特典付きでご紹介



 シェア
シェア