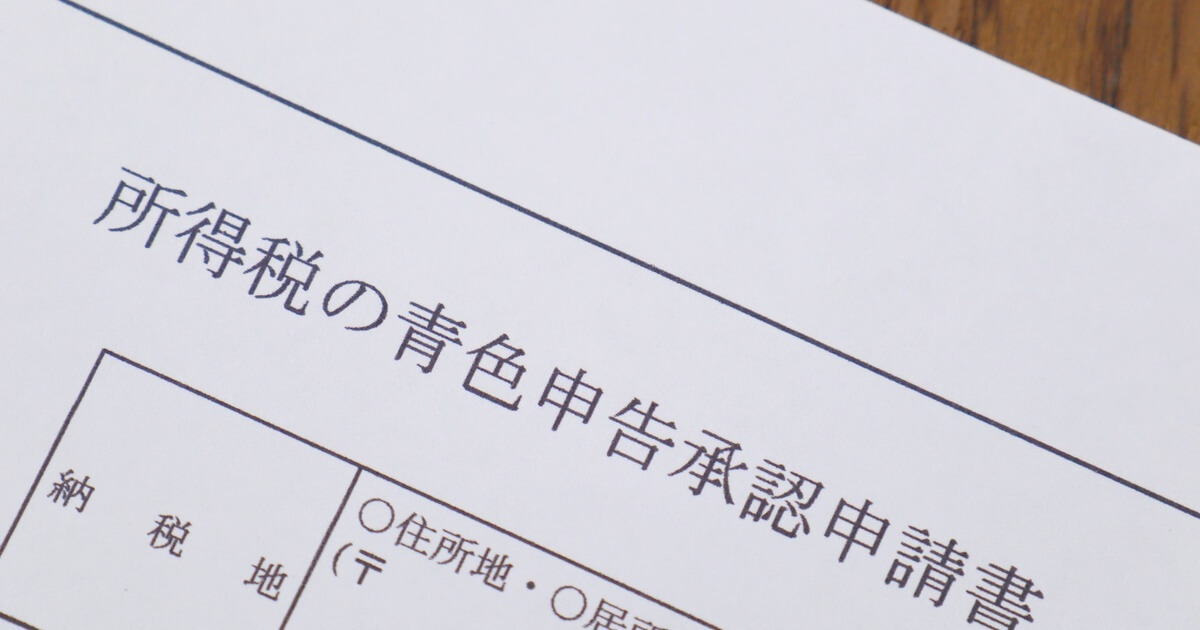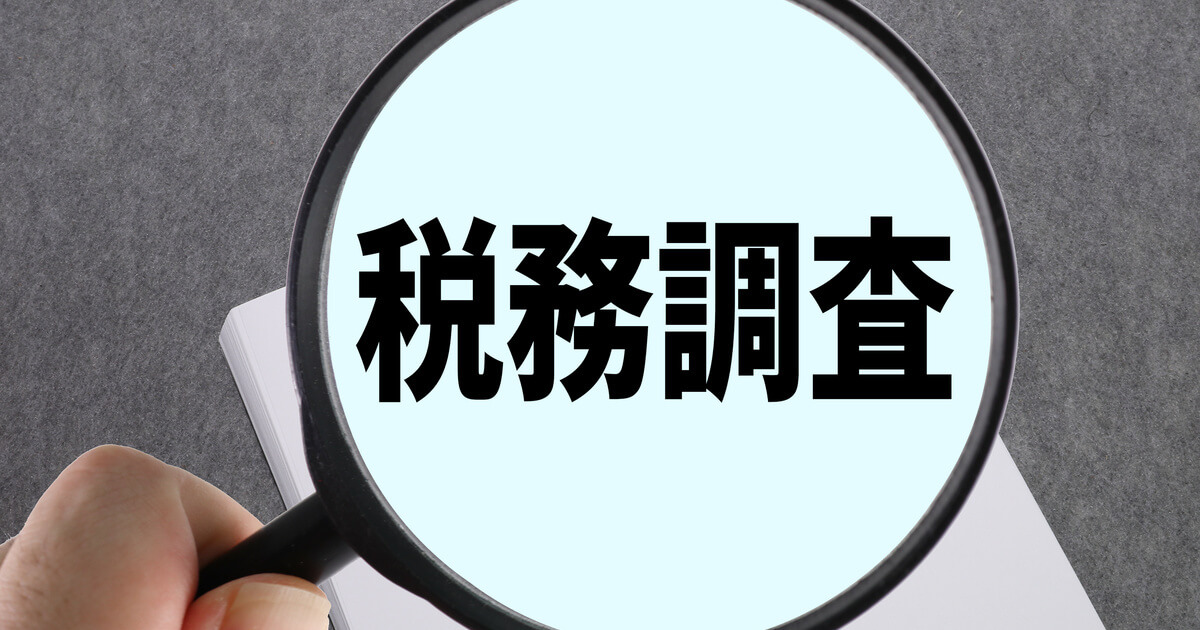【税理士監修】個人事業主の家事按分を徹底解説!節税効果と正しい計算方法

しかし、その計算方法や税務上の注意点を誤ると、税務調査で指摘を受けるリスクもあります。この記事では、税理士監修のもと、家事按分の基本から具体的な計算例、そして税務調査で困らないための正しい方法まで、個人事業主が知っておくべき全てを分かりやすく解説します。
- 【この記事のまとめ】
- 家事按分で経費にできる費用の種類と、その具体的な計算方法
- 青色申告と白色申告での家事按分の違いと、記帳のポイント
- 税務調査で指摘されないための注意点と、根拠の残し方
- 家事按分(かじあんぶん)とは?個人事業主が知るべき基本と節税メリット
- 家事按分(かじあんぶん)の定義は事業とプライベートの費用を分けること
- どうして家事按分が必要なの?個人事業主の節税効果が狙えるからです!
- 適切に家事按分しないとどうなりますか?隠れたリスクあり
- 家事按分の対象となる費用と具体的な計算方法
- 個人事業主が経費にできる割合と計算方法
- 家賃
- 水道光熱費
- 通信費
- 自動車関連費
- その他の家事按分対象費用
- 確定申告における家事按分:青色申告と白色申告の違いと記帳方法
- 青色申告の場合:合理的な根拠があれば按分比率に制限なし
- 白色申告の場合:「業務の主たる部分」の厳格な解釈
- 家事按分した費用の記帳方法:勘定科目と事業主貸
- 税務調査で指摘されないための家事按分ルールと対策
- 「合理的な根拠」の重要性:あいまいな按分はNG
- 按分比率の根拠となる書類の保管
- 一度決めた按分比率の変更と注意点
- 会計ソフトを導入して効率的に管理・根拠を明確化
- よくある質問:個人事業主の家事按分Q&A
- Q.シェアオフィスやバーチャルオフィスの費用は家事按分できますか?
- Q.実家で事業をしている場合、家賃は按分できますか?
- Q.引っ越した場合、按分比率は見直すべきですか?
- Q.按分比率の根拠が不足している場合、どうすればいいですか?
- まとめ:正しい家事按分で安心して事業に集中しよう
2024年分(令和6年分)の所得税等の確定申告期間は2025年2月17日(月)から3月17日(月)です。
「起業の窓口」では、確定申告の方法、青色申告や白色申告の基礎知識、手続きの流れ、節税のコツなどを詳しく解説しています。
ぜひ、「確定申告」に関する他の記事もご覧ください。
2024年11月1日より、フリーランス保護法が施行されます。
組織に所属せずに働くフリーランスが安心して働ける環境を整備するために、フリーランスと企業などとの発注事業者間の取引の適正化(契約書等により取引条件を明示する)が主な目的です。
詳しくは次の記事をご覧ください。フリーランス保護法の概要、制定された背景や具体的な内容などを解説しています。
家事按分(かじあんぶん)とは?個人事業主が知るべき基本と節税メリット

ここでは、家事按分の基本的な意味から、なぜ個人事業主にこの作業が不可欠なのか、そしてそこから得られる節税効果について解説します。家事按分の全体像を掴むことで、その重要性を理解し、後の具体的な計算方法へとスムーズに進めるでしょう。
家事按分(かじあんぶん)の定義は事業とプライベートの費用を分けること
家事按分とは、個人事業主やフリーランスが、事業とプライベートの両方で使用している費用を、事業で使用した割合に応じて経費として計上する会計処理のことです。例えば、自宅で仕事をしている場合、家賃や電気代、インターネット料金など、事業でも私用でも使う費用が発生します。
これらの費用は「家事関連費」と呼ばれ、全額を経費とすることはできません。家事按分を行うことで、事業に合理的に関連する部分だけを経費計上することが可能になります。
どうして家事按分が必要なの?個人事業主の節税効果が狙えるからです!
家事按分は、個人事業主にとって合法的な節税策として非常に有効です。事業に必要な出費を経費として計上すればするほど、事業の利益(所得)が減り、その結果として納めるべき所得税や住民税の金額を抑えることができます。
また、課税事業者であれば、消費税の納税額にも影響し、消費税の還付を受けられる可能性も出てきます。適切に家事按分を行うことは、個人事業主のキャッシュフローを改善し、事業の成長を支援する基盤となります。
適切に家事按分しないとどうなりますか?隠れたリスクあり
家事按分を怠ると、節税できるはずの費用を経費計上できず、本来よりも多くの税金を支払うことになります。これは、事業の利益を圧迫し、資金繰りにも影響を与えかねません。さらに、不適切な家事按分(例えば、事業と私用の区別が曖昧なまま全額経費とするなど)は、税務調査の際に指摘される大きなリスクとなり得ます。
もし税務署から按分率の妥当性を問われた際に、合理的な根拠を示すことができなければ、経費が否認され、追加で税金を支払うことになるだけでなく、延滞税などのペナルティが発生する可能性もあります。
【中野先生からのアドバイス】
家事按分は、個人事業主が節税をする上で非常に重要なテクニックです。ただし、税務署は事業と私用の区別が曖昧な費用に対しては厳しくチェックします。ご自身の事業の実態に合った『合理的な按分率』を設定し、その根拠をしっかりと残しておくことが、安心して事業を続けるためのカギとなります。不安な場合は、必ず税理士にご相談ください。
家事按分の対象となる費用と具体的な計算方法

家事按分のやり方には、以下の4つの方法が挙げられます。
| 面積按分 | 自宅のうち事業用に使用している部分の面積に基づいて按分する方法 |
|---|---|
| 時間按分 | 1日のうち事業用に使用している時間に基づいて按分する方法 |
| 売上按分 | 事業の売上に基づいて按分する方法。事業活動の割合に応じて経費を配分 |
| 定額按分 | 定額で一定の割合を経費として計上する方法 |
面積按分は自宅の一部をオフィススペースとして使用するケース、時間按分は自宅で作業する時間が明確に区別できるケースで適しています。
売上按分は事業の売上が総収入に対して大きな割合を占めるケース、定額按分は簡便に経費を計上したい、基準が定められているケースに向いています。
個人事業主が経費にできる割合と計算方法

家事按分による経費計上でのトラブルを未然に防ぐためにも、経費にできる割合と計算方法を事前に把握しておくことが大切です。
家事按分の対象となりやすい家賃、水道光熱費、通信費、自動車関連費の4つの支出について経費にできる割合と計算方法を見ていきましょう。
家賃
個人事業主が自宅を事業所として使っていれば、家賃の一部を事業経費として扱うことができます。この際、事業用と生活用のスペースを明確に区分し、合理的な方法で按分しなくてはなりません。
例えば、100㎡の自宅で、そのうち20㎡を事業用として使用しているとしましょう。この場合、使用面積で按分すると、20%を経費として扱うことができます。仮に月額家賃が10万円の場合は2万円が経費です。
また、毎日8時間事業用として使用しているとしましょう。この場合、使用時間で按分すると、24時間のうち8時間、つまり3分の1を経費として扱うことができます。仮に月額家賃が10万円の場合は約3万3,000円が経費です。
家賃の経費計上について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
水道光熱費
個人事業主が自宅を事業所として使用している場合、水道光熱費の一部も事業経費として計上することが可能です。これには、電気代、水道代、ガス代などが含まれます。事業用と生活用の使用部分を明確に区分し、合理的な方法で按分することが重要です。
例えば、100㎡の自宅で、そのうち20㎡を事業用として使用しているとしましょう。この場合、使用面積で按分すると、20%を経費として扱うことができます。仮に月額水道光熱費が1万円の場合は2,000円が経費です。
また、毎日8時間事業用として使用しているとしましょう。この場合、使用時間で按分すると、24時間のうち8時間、つまり3分の1を経費として扱うことができます。仮に月額水道光熱費が1万円の場合は約3,300円が経費です。
通信費
個人事業主が自宅を事業所として使っていれば、通信費の一部についても事業経費に計上することが可能です。通信費にはインターネット料金や電話料金などが含まれます。事業用と生活用の使用部分を明確に区分し、合理的な方法で按分しなくてはなりません。
例えば、1日のうち8時間を事業用としてインターネットを使用しているとしましょう。この場合、使用時間で按分すると、24時間のうち8時間、つまり3分の1を経費に計上できます。仮に月額のインターネット料金が6,000円の場合は2,000円が経費です。
また、1か月のうち、事業用の電話使用が全体の40%を占めているとしましょう。この場合、使用頻度で按分すると、40%を経費として扱うことができます。仮に月額電話料金が5,000円の場合は2,000円が経費です。
自動車関連費
個人事業主が自動車を事業用と私用で兼用しているということも少なくありません。この場合、自動車関連費の一部を事業経費として扱うことができます。自動車関連費にはガソリン代、保険料、修理費用、駐車場代が含まれます。事業用と私用の使用割合を明確に区分し、合理的な方法で按分する必要があります。
例えば、1か月の走行距離が1,000km、そのうち事業用が600kmとしましょう。この場合、走行距離で按分すると、60%を経費として扱うことができます。仮に月額のガソリン代が2万円の場合は1万2,000円が経費です。
また、1日あたりで4時間を事業用として使用しているとしましょう。この場合、使用時間で按分すると、24時間のうち6時間、つまり4分の1を経費に計上できます。仮に月額の保険料が1万円の場合は約1,666円が経費です。
その他の家事按分対象費用
上記の主要な費目以外にも、以下のような費用が家事按分の対象となる場合があります。
- 減価償却費: 事業と私用で兼用しているPCや業務用家具など、高額な資産については、その利用割合に応じて減価償却費を按分し、経費として計上できます。
- 消耗品費: 事業で使う文房具やプリンターのインク、事業用清掃用品など、事業と私用が混在する消耗品も対象です。
- 新聞図書費: 事業に関連する新聞や雑誌、書籍なども、事業と私用の利用度合いに応じて按分できます。
重要な点は、どのような費用であっても「事業に関連していること」、そして「按分率に合理的な根拠があること」です。
【中野先生からのアドバイス】
水道光熱費の按分において税務署が特に注目するのは、その『合理性』です。電気代は事業用機器の使用時間や事業スペースの面積で按分しやすいですが、ガス代や水道代は、事業内容によっては私用の割合が非常に高いことが多いです。
単なる生活費の一部と見なされないよう、事業への関連性を具体的に説明できる根拠を持つことが肝要です。
例えば、料理教室を自宅で開いているなら水道代の按分も合理的ですが、デスクワークが主であれば、事業でどれだけ水を使うのかを客観的に示すのは難しいでしょう。
確定申告における家事按分:青色申告と白色申告の違いと記帳方法

家事按分は、確定申告の種類によって扱いが異なります。特に青色申告と白色申告では、按分できる範囲に違いがあるため、ご自身の申告方法に合わせた理解が不可欠です。ここでは、税務上の違いと、実際の記帳方法について解説します。
青色申告の場合:合理的な根拠があれば按分比率に制限なし
青色申告を選択している個人事業主は、家事関連費のうち事業に必要な部分を経費にできます。青色申告では、白色申告のような厳格な「主な支出(50%超)」という制限がありません。
ただし、「業務遂行上必要であったことが明らかに区分できる場合」に限られます。つまり、事業のために使った分であるという合理的な根拠が明確に示せる限り、按分比率が 50% 未満であっても経費計上が可能です。これは青色申告の大きなメリットの一つであり、より柔軟な節税が期待できます。
白色申告の場合:「業務の主たる部分」の厳格な解釈
一方で、白色申告を選んでいる個人事業主の場合、家事関連費の按分には制限があります。原則として、その費用が事業の主な部分(事業での利用が 50% を超える割合)として使われている場合に限り、按分して経費計上が認められます。
この「主な部分」という解釈は厳しく、税務署は事業と私用の境界が曖昧な費用に対しては、経費として認めないケースもあります。ただし、自宅兼事務所で、事業用スペースと私用スペースが物理的に完全に仕切られているなど、明確に区分できる場合は、按分が認められることもあります。白色申告の方は、按分の基準と根拠をより一層明確にする必要があります。
【中野先生からのアドバイス】
青色申告と白色申告における家事按分の『主たる部分』の解釈は、税務調査で最も問われやすい点の一つです。
白色申告の場合、50% 未満の按分は原則として認められにくいと理解しておきましょう。
青色申告であれば柔軟性はありますが、それでも按分率の『合理的な根拠』は必須です。事業の実態とかけ離れた按分率は、税務署から経費を否認される原因となりますので、ご自身の事業内容と照らし合わせて慎重に設定してください。
家事按分した費用の記帳方法:勘定科目と事業主貸
家事按分した費用を記帳する際は、事業用とプライベート用の部分を明確に区別して勘定科目を振り分けます。事業用部分は通常の経費の勘定科目(例:地代家賃、水道光熱費、通信費、車両費など)で記帳し、プライベート用部分は「事業主貸《じぎょうぬしか》」という勘定科目を使用します。
事業主貸とは、個人事業主が事業の資金から私用の支払いを行った場合や、私用の資産を事業で使用した場合などに用いる勘定科目です。家事按分においては、私用分の費用を事業主貸として処理することで、事業の経費と私用の支出が混同するのを防ぎます。
【記帳例: 月の家賃 10万円、事業割合 30% の場合】
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 勘定科目 | 金額 | 勘定科目 | 金額 |
| 地代家賃 | 30,000円 | 普通預金 | 100,000円 |
| 事業主貸 | 70,000円 | ||
この仕訳により、事業に必要な家賃分のみが「地代家賃」として経費計上され、残りの私用分は「事業主貸」として処理されます。
また、主要な家事按分対象費用の勘定科目は以下のとおりです。
【主要な家事按分対象費用の勘定科目一覧】
| 費目 | 主な勘定科目 | 按分基準例 |
|---|---|---|
| 家賃・地代 | 地代家賃 | 面積比、時間比 |
| 電気代 | 水道光熱費 | 面積比、時間比 |
| ガス代・水道代 | 水道光熱費 | 使用実態(事業内容による) |
| インターネット | 通信費 | 時間比、利用回線数 |
| 携帯電話料金 | 通信費 | 通話時間比、利用明細 |
| ガソリン代 | 車両費 | 走行距離比 |
| 自動車保険料 | 保険料 | 走行距離比 |
| PC・業務用家具 | 減価償却費 | 使用時間比、利用頻度 |
税務調査で指摘されないための家事按分ルールと対策

家事按分は節税に有効な手段ですが、その按分率が恣意的であったり、根拠が不明確だと税務調査の際に経費を否認されるリスクがあります。ここでは、税務調査で指摘を受けないために、どのような家事按分ルールを意識し、どのような対策を講じるべきかを解説します。
「合理的な根拠」の重要性:あいまいな按分はNG
税務署が家事按分の妥当性を判断する上で最も重視するのは「合理的な根拠」があるかどうかです。漠然と「半分くらい事業で使っているから 50%」といったあいまいな按分率は、税務調査の対象になりやすく、経費を否認される可能性が高まります。
「合理的な根拠」とは、誰が見てもその按分率が事業の実態に即していると客観的に判断できる基準と資料のことです。例えば、事業専用の部屋の面積を明確にしている、事業で使用する時間帯を記録している、車の走行距離を記録している、といった具体的で客観的な事実に基づいた根拠が求められます。
【中野先生からのアドバイス】
税務調査で按分比率を否認される典型的なケースは、事業の実態と按分率がかけ離れている場合、そして何よりも「根拠がない」場合です。
例えば、自宅のワンルームで作業しているのに家賃の 80% を経費にしている、休日は一切事業をしていないのに電気代を「時間按分」で 50% にしている、といったケースは税務署から「本当に事業でそこまで使っているのか?」と疑問視されがちです。明確な根拠があれば、税務署も納得せざるを得ません。
按分比率の根拠となる書類の保管
税務調査に備え、設定した按分比率の根拠となる書類をきちんと保管しておくことが極めて重要です。
| 按分基準 | 証明方法の例 |
|---|---|
| 面積を示すもの |
・自宅の間取り図、賃貸契約書に添付されている図面 ・事業用スペースの写真(撮影日付きで保管) ・簡易な測量アプリなどで測定した記録 |
| 時間を示すもの |
・日々の業務日報やタイムスケジュール(事業時間と私用時間を記録) ・業務管理ツールやカレンダーアプリの業務ログ |
| 走行距離を示すもの |
・車両運行記録簿(日時・行き先・走行距離・事業目的など) ・Googleマップ等の移動履歴(事業利用分をスクリーンショット等で保管) |
| 通信記録 |
・携帯電話の通話明細やデータ利用明細(事業利用が明確な場合) ・インターネット利用時間のデータ(プロバイダから提供される場合) |
【按分比率の根拠となる主な書類と具体的な保管方法】
| 費目 | 主な根拠書類 | 保管方法 |
|---|---|---|
| 家賃・地代 | 間取り図、写真、賃貸契約書 | PDF化してクラウド保存、紙媒体で保管 |
| 水道光熱費 | 月ごとの請求書、業務記録 | PDF化してクラウド保存、紙媒体で保管 |
| 通信費 | 月ごとの請求書、通話/利用明細 | PDF化してクラウド保存、紙媒体で保管 |
| 車両費 | 走行距離記録簿、ガソリン領収書 | Excel/スプレッドシートで記録、領収書保管 |
| 減価償却費 | 購入時の領収書、利用記録 | PDF化してクラウド保存、紙媒体で保管 |
一度決めた按分比率の変更と注意点
一度決めた按分比率は、原則として継続して適用することが求められます。しかし、事業の状況が変化した場合(例:事業拡大で事業専用スペースが増えた、引っ越して自宅兼事務所の間取りが変わった、事業での車の使用頻度が大幅に増えたなど)は、新しい実態に合わせて按分比率を見直す必要があります。
ただし、安易に、あるいは節税のためだけに頻繁に按分率を変更すると、税務署から不自然な按分として見なされ、指摘を受ける可能性が高まります。按分率を変更する際は、その変更が必要となった具体的な理由を記録し、新しい按分率の根拠も明確に残しておきましょう。
会計ソフトを導入して効率的に管理・根拠を明確化
家事按分の複雑な計算や記帳、そして根拠となる書類の管理は、会計ソフトを導入することで大幅に効率化できます。多くの会計ソフトには家事按分機能が搭載されており、一度按分率を設定すれば、毎月の家賃や光熱費などを入力する際に自動で事業用と私用に振り分けてくれます。
また、領収書やレシートをスキャンしてデータ化し、仕訳に紐づけて保管する機能を持つ会計ソフトも多く、これが税務調査時の強力な根拠となります。日々の記帳の手間が省けるだけでなく、正確な経費計上と税務調査対策にも繋がるため、個人事業主であればぜひ導入を検討すべきツールです。
よくある質問:個人事業主の家事按分Q&A
ここでは、個人事業主が家事按分に関してよく抱く疑問と、その簡潔な回答をまとめました。具体的な疑問を素早く解消し、家事按分への理解を深めましょう。
Q.シェアオフィスやバーチャルオフィスの費用は家事按分できますか?
シェアオフィスやバーチャルオフィスの費用は、基本的に家事按分の必要はありません。これらのサービスは、事業目的で契約しているため、支払い全額を「地代家賃」や「賃借料」などの勘定科目で経費として計上できます。自宅の家賃などと混同しないように注意しましょう。
Q.実家で事業をしている場合、家賃は按分できますか?
実家で事業をしている場合でも、親に家賃を支払っており、それが客観的に証明できる(賃貸契約書、振込履歴など)のであれば、自宅の家賃と同様に家事按分が可能です。ただし、無償で自宅スペースを使わせてもらっている場合は、実際に金銭の支払いがないため経費にはできません。
Q.引っ越した場合、按分比率は見直すべきですか?
はい、引っ越して自宅兼事務所の環境が変わった場合は、必ず按分比率を見直す必要があります。例えば、新しい家屋の面積が変わったり、事業専用スペースが設けられたりした場合は、それまでの按分率は合理的な根拠を失います。新しい実態に合わせて按分率を再計算し、その根拠も記録に残しておきましょう。
Q.按分比率の根拠が不足している場合、どうすればいいですか?
按分比率の根拠が不足している、あるいは按分率の設定に不安がある場合は、無理な経費計上は避けるべきです。最も安全なのは、税理士に相談し、ご自身の事業内容と実態に合わせた適切なアドバイスを受けることです。税理士は、税務調査で指摘を受けないための按分率設定や根拠資料の準備について、具体的な指導をしてくれます。
まとめ:正しい家事按分で安心して事業に集中しよう
家事按分は、個人事業主が自宅兼事務所などの家事関連費を経費として計上し、合法的に節税するための重要なスキルです。その意味や対象となる費用、具体的な計算方法、そして青色申告・白色申告それぞれの違いを理解することは、確定申告を正しく行い、税務調査で指摘を受けないためにも不可欠です。
この記事で解説したポイントを参考に、ご自身の事業の実態に合わせた「合理的な按分率」を設定し、その根拠となる書類をしっかりと保管しましょう。これにより、節税効果を最大限に享受しつつ、安心して事業に集中できる環境を整えることができるはずです。
確定申告を楽にしたいと悩む方へ

質問に答えていくだけで、経理の作業がはじめての方でも簡単に確定申告の書類作成をすることができます!
確定申告を楽にサクッとおこないたい方は、freeeがおすすめです!
「起業の窓口」では、個人事業主の方々に向けて、業務効率化のヒントや成功事例、最新のビジネス情報など、お役立ち情報を提供しています。
ぜひ、「個人事業主」に関する他の記事もご覧ください。
起業や開業、独立に興味を持ったら、まずは「起業の窓口」に登録してみよう!
「起業の窓口」では、起業に必要なノウハウや成功者のインタビューなど、さまざまなコンテンツを完全無料で提供しています。
会員特典として、起業・経営支援のプロ「V-Spirits」が監修するオリジナル冊子『会社設立完全ガイド』を無料プレゼント。さらに、V-Spritsによる1時間の無料起業相談や、GMOインターネットグループが展開するビジネスの立ち上げや拡大に役立つ各種サービスをおトクな特典付きでご紹介します。
あなたの夢の実現を全力でサポートします!
- 記事監修
-
- 中野 裕哲 HIROAKI NAKANO
- 起業コンサルタント(R)、経営コンサルタント、税理士、特定社会保険労務士、行政書士、サーティファイドファイナンシャルプランナー・CFP(R)、1 級FP 技能士。 V-Spiritsグループ創業者。東京池袋を本拠に全国の起業家・経営者さんを応援!「あの起業本」の著者。著書16冊、累計20万部超。経済産業 省後援「DREAMGATE」で11年連続相談件数日本一。
- ※本記事は、起業の窓口編集部が専門家の監修のもとに制作したものです。
- ※掲載している情報は、記事の公開・更新時点における商品・サービス、法令、税制に基づいており、将来これらは変更される可能性があります。
- ※記事内容の利用・実施については、ご自身の責任と判断でお願いいたします。
- ※本記事は一般的な情報提供を目的としております。個人の状況に応じた具体的な助言が必要な場合は、専門家にご相談ください。



 シェア
シェア