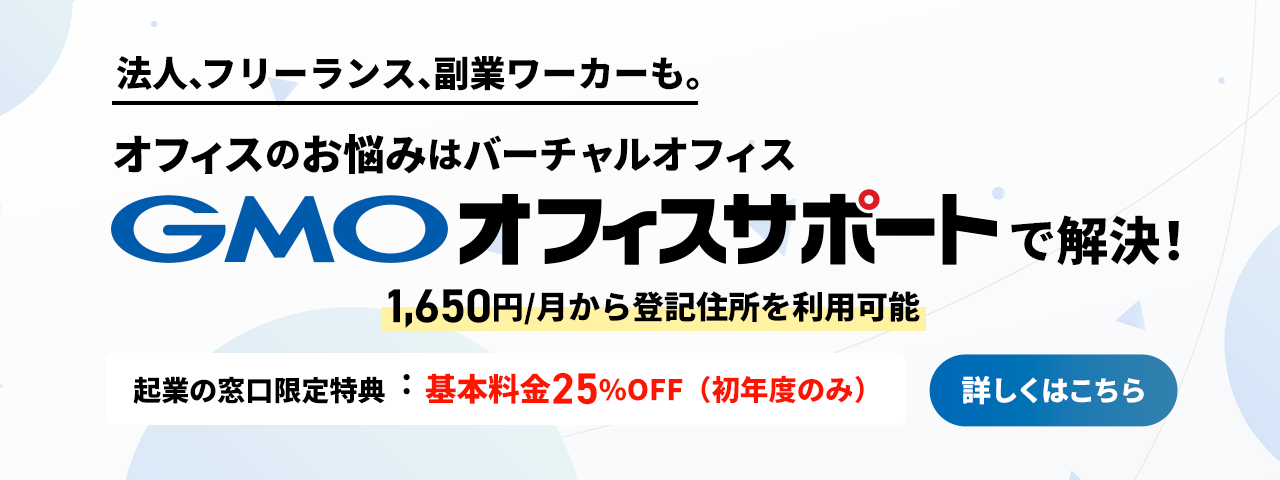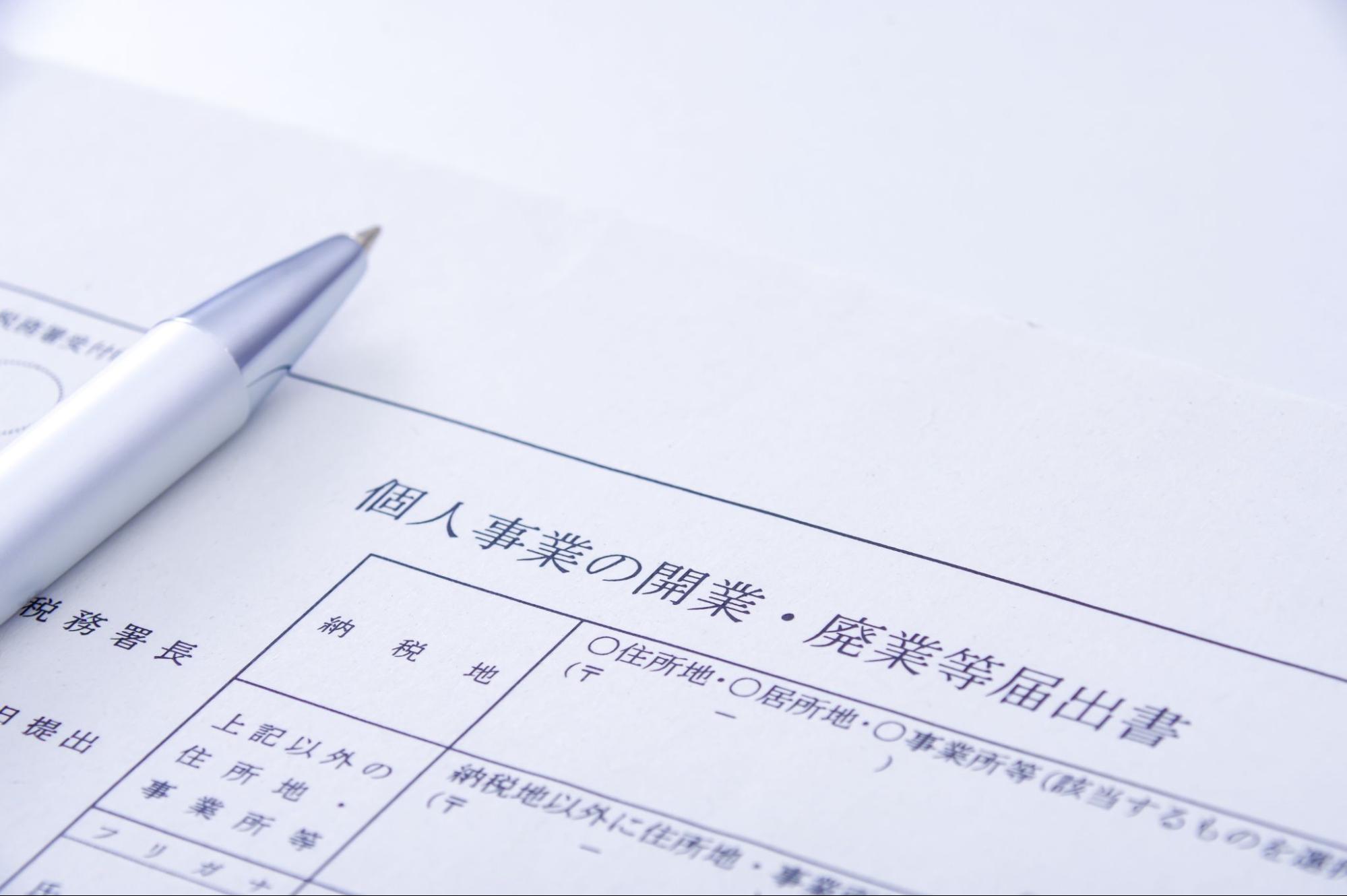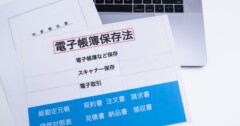バーチャルオフィスで起業はできる?メリット・よくある質問を解説

バーチャルオフィスとは、実態のあるオフィスではなく住所のみを貸し出すサービスのことを指します。言葉は聞いたことがあっても、バーチャルオフィスの具体的なサービス内容やメリットなどについて把握していない方も多いのではないでしょうか。
そこで、こちらではバーチャルオフィスについて詳しく解説します。バーチャルオフィスの利用を検討している方に役立つ情報を紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
- 【この記事のまとめ】
- バーチャルオフィスでの起業は可能ですが、法人登記の住所に使用することができ、事業運営に必要な住所を借りることができます。実際の仕事は別の場所で行います。
- バーチャルオフィスを利用できない職業もあり、人材派遣業や士業など、実態のある事務所が必要な職種には不適切です。適切なオフィス選びが重要です。
- バーチャルオフィスのメリットは、低コストで迅速に住所を取得でき、プライバシーの保護にも役立ちます。月額料金が低く、サービス内容も充実しています。
「起業の窓口」では、AIインフルエンサーの茶圓氏とコラボをおこない、AIを活用してビジネスの効率化を図るための貴重な知識を提供しています。
特集ページ「AI×起業」では、最新のAI技術やツールを使った実践的なアプローチを紹介しており、起業家や個人事業主の業務をよりスマートにサポートします。
AIの力で業務の負担を軽減し、ビジネスの成長を加速させたい方に最適な情報が満載です。ぜひご覧ください。
「起業の窓口」の特集ページ「起業家インタビュー」では、実際に成功を収めた起業家たちの貴重なインタビューが充実しています。リアルな体験や苦労、成功までの道のりを通じて、これから起業を目指す方々に向けた実践的なアドバイスを提供しています。
さまざまな分野で活躍する起業家の声を通して、ビジネスのヒントやインスピレーションを得られるコンテンツが満載です。ぜひインタビューを参考にして、自分のビジネスに活かしてみてください。
バーチャルオフィスで起業はできる?【結論】可能です

バーチャルオフィスを使った起業は可能です。そもそも起業とは、個人事業主や株式会社などの形態を問わず新しく事業を起こすことを指し、会社として起業する場合は法人の設立登記が必要になります。
設立登記は設立する法人情報を法務局に登録し、企業として活動できる状態にすることが目的であり、商業登記法上では本店所在地の住所に関する制限がありません。そのため、バーチャルオフィスのように実態のない場所を住所地として記載しても問題はないとされています。
バーチャルオフィスとは

バーチャルオフィスとは、事業に必要な住所を貸し出すサービスを指します。住所はあっても実態は伴わないため、実際に仕事をする場所は別に用意しなければなりません。例えば、自宅をワークスペースとして使いつつ、登記上はバーチャルオフィスの住所を登録するといった使い方ができます。
バーチャルオフィスを利用できない職種
基本的にバーチャルオフィスを使った起業は可能ですが、中には利用できない職種も存在します。
主な職種は、以下の通りです。
- 人材派遣業・有料職業紹介業:事業の認可に実態のある事業所が必要
- 士業:弁護士会や税理士会などに事務所を登録する場合に実態のある事務所が必要
- 不動産業:宅地建物取引業免許の取得に実態のある事務所が必要
このように、事業を運営するための条件として実態のある事務所が掲げられている職種は、バーチャルオフィスで起業しても許認可等を取得することができません。起業予定の事業内容を確認し、適切なオフィスを選ぶようにしてください。
バーチャルオフィスとレンタルオフィスの違い
レンタルオフィスとは、デスクや電話、インターネット環境など事業運営に必要な設備が整った貸しスペースのことです。オフィス用品を自分で準備する必要はなく、契約したらすぐに事業拠点として活用できます。バーチャルオフィスは住所のみを貸し出すのに対して、レンタルオフィスは仕事を行うためのスペースも貸し出しているのが両者の違いです。
バーチャルオフィスのサービス内容

バーチャルオフィスのサービス内容は、主に以下の4項目があります。
- 住所の貸し出し
- 固定電話番号の貸し出し
- 郵送物の転送
- その他のオプション
いずれも起業時に役立つサービスばかりです。各項目の詳細を確認して、事業運営に役立ててみましょう。
住所の貸し出し
住所の貸し出しは、法人の拠点となる住所をレンタルできるサービスです。レンタルした住所は法人登記で使えるだけでなく、ホームページや名刺などにも記載できます。ただし、バーチャルオフィスによっては法人登記の住所利用にオプション料金がかかることもありますので、あらかじめ確認してください。
法人登記やその手続の流れについて、下記の記事で詳しく解説しています。
固定電話番号の貸し出し
市外局番から始まる固定電話番号を借りられるサービスです。固定電話番号に連絡があった場合、事前登録した携帯電話などに転送するサービスもあります。携帯電話番号より社会的信用度が高いため、バーチャルオフィス契約時に固定電話番号もレンタルする場合が多いです。
郵送物の転送
バーチャルオフィスに届いた郵送物を指定の場所へ転送してくれるサービスです。郵送物が届くたびに取りに行く必要はないため、起業直後で忙しい時期も郵送物の取りこぼしが防げるでしょう。なお、転送料や転送の頻度は各社で異なりますので事前の確認が必要です。
その他のオプション
取引先との打ち合わせがある場合、バーチャルオフィスの会議室オプションを利用できます。少人数用の会議室からセミナーにも使える大規模会議室まで、会議室の規模は会社によってさまざまです。会議室の広さや備品の有無などをあらかじめ確認しておくとよいでしょう。
その他には、法人登記代行オプションや経理のサポートオプションなど、専門家への依頼・相談ができるサービスもあります。必要に応じて活用してみてください。
バーチャルオフィスの費用はどのくらい?

バーチャルオフィスの利用費用は、月1,000円~1万円ほどです。基本料金が月額1,000円のケースでは、一等地ではなく地方の住所を貸し出す場合や、住所貸し出し以外のサービスが別料金になる場合があります。「専用市外局番の取得」「ワーキングスペースの利用」といったオプションが基本料金に含まれることになれば、月額料金も上がっていくでしょう。
月1万円以上のバーチャルオフィスでは、受付が来客の対応をしてくれたり、備え付けのロッカーを使えたり、さまざまな面で充実したサービスを受けられます。どのようなサービスが必要なのか確かめて、予算を検討することが大切です。
バーチャルオフィスで起業するメリット

起業や事業運営の課題となる拠点の確保を解決してくれる存在が、バーチャルオフィスです。
起業する際の拠点選びには選択肢がありますが、そのなかでバーチャルオフィスを利用するメリットは、以下の通りです。
- コストの削減が可能
- プライバシーの保護につながる
- ブランディングになる
- 利用開始までがスピーディー
ここでは、バーチャルオフィスで起業する4つのメリットを詳しく解説します。
コストの削減が可能
バーチャルオフィスの最大のメリットは、起業にかかるコストの削減が可能な点です。
本来、法人登記や手続きをする際に拠点となる住所が必要となり、それらを準備するのにも敷金や礼金、保証金、さらには毎月の賃料などのコストが必要です。
一方、バーチャルオフィスの場合、登記に必要な住所を借りる場合であっても、初期費用がほとんどかからず、ランニングコストも月額1,000円~1万円ほどで済ませられます。
特に起業初期は、売り上げが安定しないことが多いため、バーチャルオフィスの利用によって初期コストとランニングコストを抑えれば、広告宣伝や商品開発など本業に資金を集中しやすくなります。
起業初期はバーチャルオフィスで運営し、見込みが立ったらオフィスの賃貸を検討するのもおすすめです。
プライバシーの保護につながる
自宅住所を事業の連絡先として公開したくない場合、バーチャルオフィスはプライバシーの保護に効果を発揮します。
法人登記の際の住所として利用できるため、Webサイトや名刺に自宅住所を記載する必要がなくなります。これにより、自宅への訪問やプライベート領域の侵害を防げるでしょう。
特に女性の起業家は、住所公開がリスクになるため、バーチャルオフィスの利用がおすすめです。
ブランディングになる
バーチャルオフィスで利用できる住所の多くは、都心の一等地や有名エリアです。
これらの住所を活用することで、高級感や信頼感を持って事業を展開できるため、ブランディング効果を期待できます。
特に新規顧客や取引先に対しての第一印象を高め、競合と差別化を図る際に有利です。また、Webサイトや名刺に記載するオフィスの住所が良い立地だと、イメージアップにもつながりビジネスチャンスを広げるキッカケにもなります。
少ないコストで企業のイメージアップができるのは、バーチャルオフィスならではの強みです。
利用開始までがスピーディー
バーチャルオフィスは、契約から利用開始までが非常にスピーディーです。
例えば、物理的なオフィスを賃貸する場合、物件選びや内覧、審査など実際に契約に至るまでにも手続きがあり、1ヶ月~2ヶ月ほどの期間が必要でした。
しかし、バーチャルオフィスは最短即日から数日で住所を利用することが可能です。
また、物理的な内装・設備工事を必要としないため、利用開始までの時間を大幅に短縮できます。
そのため、すぐにでも起業したい人にとっては便利なサービスです。契約もオンライン上で完結するケースが多く、手間がかかる心配もありません。
【注意】バーチャルオフィスで起業するデメリット
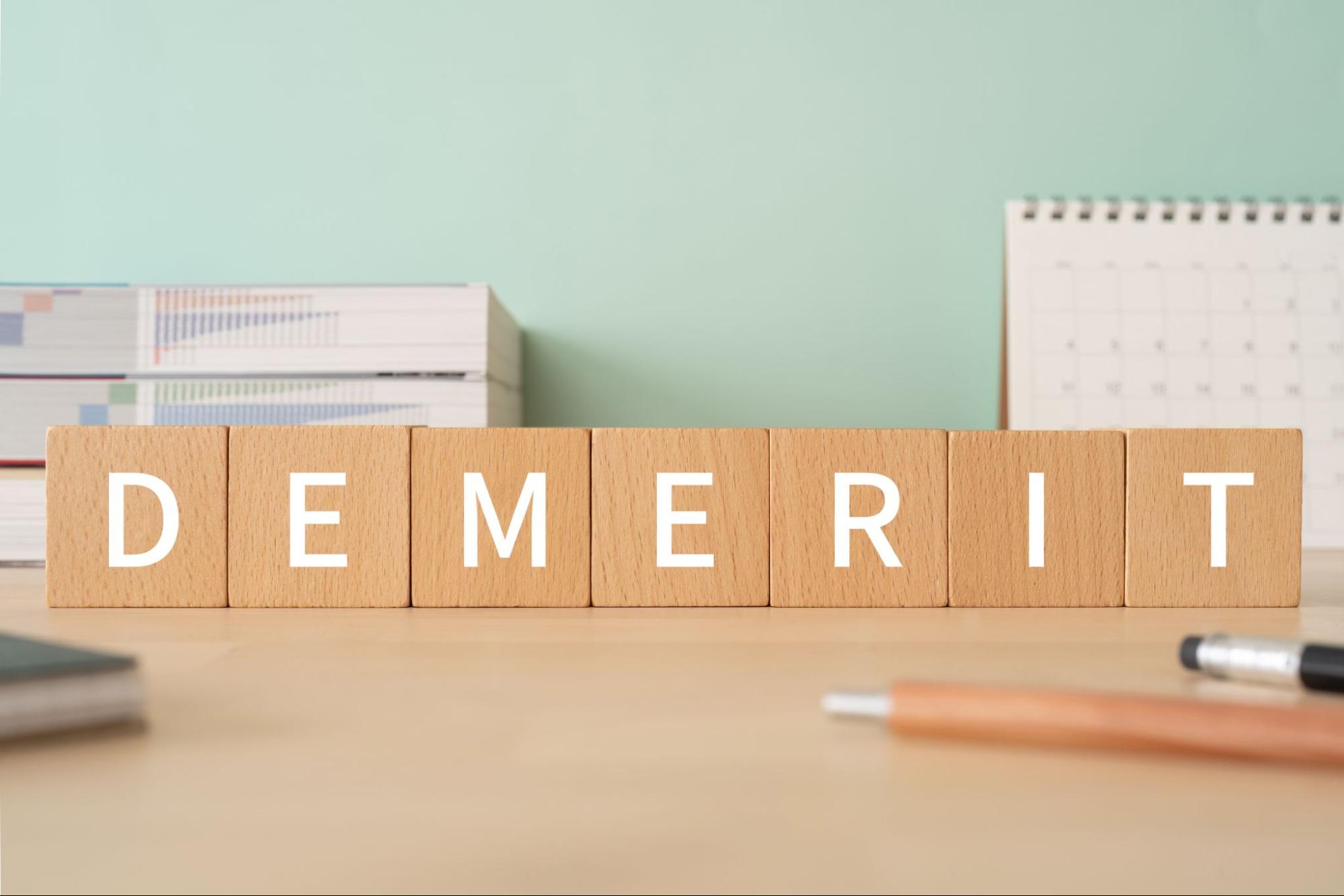
バーチャルオフィスは、手軽に起業の拠点となる住所を利用できる便利なサービスですが、利用にあたってはデメリットも存在します。
バーチャルオフィスで起業する主なデメリットは、以下の通りです。
- 許認可が取れないケースがある
- 他社と住所が同じになる可能性がある
- 法人口座の開設や融資の審査で問題になるケースがある
- 実務を行う場所を他に用意する必要がある
- 運営会社の倒産によって住所が利用できなくなる
ここでは、バーチャルオフィスで起業する5つのデメリットを詳しく解説します。
許認可が取れないケースがある
バーチャルオフィスを利用する場合、業種によって必要な許認可が取れないケースがあります。
必要な許認可を取れないと、事業を開始できないため、バーチャルオフィス以外の選択肢を考えなければいけません。
特に許認可のなかでも、事務所の実在が要件に含まれているケースでは注意が必要です。バーチャルオフィスは住所を借りるサービスとなるため、要件として事務所の実在が含まれている許認可は取得できません。
バーチャルオフィスで許認可の取得が難しい業種は、以下の通りです。
- 古物商
- 不動産業
- 建設業
- 士業(税理士、司法書士、弁護士など)
- 探偵業
- 不動産業
- 職業紹介業
- 人材派遣業
該当する業種は、実在する事務所の存在が要件を満たすために必要です。
許認可を取得せずに業務を開始した場合、罰則やペナルティを受ける可能性があるため注意してください。
他社と住所が同じになる可能性がある
バーチャルオフィスで提供される住所は、複数の利用者が同時に使用します。
そのため、他社と住所が同じになる可能性は避けられません。
特に同一住所で多数の会社が登記されている場合、取引先や顧客からの信用に影響を与えたり、印象が悪くなる可能性があります。相手から不信感を持たれないためにも、バーチャルオフィスを利用していることを事前に知らせておきましょう。
法人口座の開設や融資の審査で問題になるケースがある
法人口座の開設や融資の審査時に、バーチャルオフィスの利用が問題になるケースがあります。
例えば、バーチャルオフィスの住所を本店所在地として登記した場合、「実体のあるオフィスがない」として信用面でマイナスに評価される可能性があります。これは、マネーロンダリングや詐欺などの犯罪を防止するために、実地確認や登記住所の証明を厳格に行っているためです。
ただし、金融機関によって審査基準が異なるため、バーチャルオフィスの利用を伝えたうえで法人口座の開設や融資の審査を申し込みましょう。
実務を行う場所を他に用意する必要がある
バーチャルオフィスは、あくまで住所のみを貸し出すサービスです。
サービスによっては、郵便物や電話の転送サービスが提供されているものの、実務を行うスペースや作業場は含まれていません。
そのため、会議や打ち合わせ、商品の保管、発送作業、事務作業などの実務を行う場所が別途必要です。例えば、本店所在地の住所にバーチャルオフィスの住所を使い、自宅やレンタルオフィスで実務を行う場合もありますが、さらなるコストが発生してしまいます。
業務形態や利用目的に応じて、実務スペースの必要性を明確にしてから利用を判断しましょう。
運営会社の倒産によって住所が利用できなくなる
バーチャルオフィスには、運営会社の倒産によって住所が利用できなくなるリスクがあります。
例えば、運営会社が経営難に陥り倒産した場合、住所の利用ができなくなってしまいます。その場合、新たなオフィスの契約とともに、登記簿謄本の変更、Webサイトや名刺の修正、取引先への連絡など、多くのコストと手間が必要になるでしょう。
そのため、契約時には運営会社の実績や信頼性を十分に確認し、万が一の事態の備えた計画を用意しておくことをおすすめします。
【手順】バーチャルオフィスで起業する流れ

バーチャルオフィスで法人として起業する際、通常利用よりも若干の手間がかかります。
具体的な流れは、以下の通りです。
- 個人名義で利用契約を結ぶ
- 定款の作成および認証
- 必要書類を用意のうえ法務局へ提出
- 登記簿謄本を提出して個人名義から法人名義へ変更
ここでは、バーチャルオフィスで起業する流れをステップごとに解説します。
1.個人名義で利用契約を結ぶ
バーチャルオフィスで法人として起業したい場合、まずは個人名義で利用契約を結びます。
契約後でないとバーチャルオフィスの住所を登記に利用できないため、個人名義の契約によって使用できる状態にしてください。
多くのバーチャルオフィスは、法人設立前の準備段階での契約も受け付けているため、その旨を伝えたうえで契約を進めましょう。
2.定款の作成および認証
個人名義で契約後は、まずは会社設立にあたって定款を作成します。
定款には、以下3つの分類された項目を明記します。
| 絶対的記載事項 |
|
| 相対的記載事項 |
|
| 任意的記載事項 |
|
定款の所在地の項目には、利用可能になったバーチャルオフィスの住所を明記してください。
また、定款は公証役場での認証が必要です。公証人によって、内容の正当性が確認されます。
ただし、定款認証が必要なのは、株式会社、一般社団法人や一般財団法人、弁護士法人などに限られ、合同会社や合資会社、合名会社の場合は不要です。
3.必要書類を用意のうえ法務局へ提出
定款認証後は、登記を行うために以下の必要書類を揃えます。
- 登記簿申請書
- 定款
- 登録免許税納付用台紙
- 発起人決定書
- 代表取締役の就任承諾書
- 取締役の就任承諾書
- 取締役の印鑑証明書
- 資本金の払込証明書
- 印鑑届書
- 登記すべき事項を記録した書面や記録媒体
すべての書類が揃ったら、管轄の法務局に提出してください。
また、設立する法人の種類によっても要件が異なるケースもあるため、書類の不備がないよう注意し、提出前に専門家にチェックしてもらうとスムーズです。
4.登記簿謄本を提出して個人名義から法人名義へ変更
会社設立後は、バーチャルオフィスの契約名義を個人から法人に変更します。その際、法務局で取得できる登記事項証明書の提出を求められるケースがあります。。
また、名義変更時には登記簿謄本の提出を求められるケースがあるため、事前に準備しておきましょう。
名義変更が完了すれば、バーチャルオフィスの住所で正式な事業運営ができます。
【重要】起業の際に利用するバーチャルオフィス選びのポイント
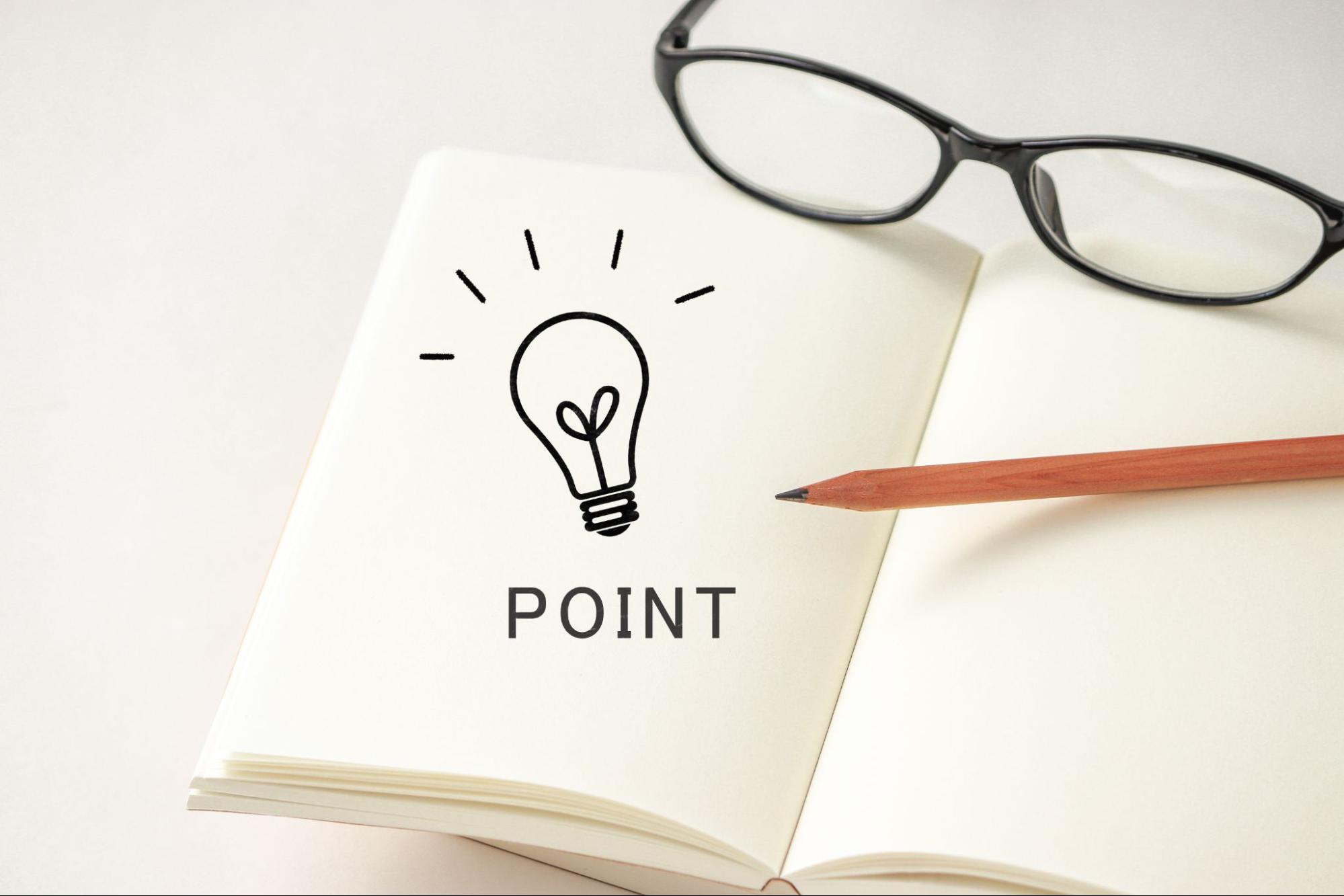
バーチャルオフィスは起業や事業運営において、コストを抑えつつ信頼性の高い住所を確保できる便利なサービスです。
しかし、選び方によっては運営上のトラブルが生じるため、慎重な検討が必要です。
バーチャルオフィスの利用を検討する際は、以下6つのポイントに注目しましょう。
- 【ポイント①】法人登記の可否
- 【ポイント②】機能やオプション、料金
- 【ポイント③】契約内容や縛りなど
- 【ポイント④】立地
- 【ポイント⑤】住所や電話番号に問題がないか
- 【ポイント⑥】同一名の法人はないか
ここでは、起業の際に利用するバーチャルオフィス選びのポイントを詳しく解説します。
【ポイント①】法人登記の可否
バーチャルオフィス選びの基本となる重要なポイントが、法人登記の可否です。
バーチャルオフィスは住所を貸し出すサービスですが、すべてのサービスが本店所在地として利用できるわけではありません。なかには、登記に住所が利用できないサービスもあります。
特に法人として起業を考えている場合や将来的な法人化を検討している人は、必ず確認してください。
【ポイント②】機能やオプション、料金
バーチャルオフィスの機能やオプションは、サービスによって異なります。
住所貸しが基本のサービスとなり、固定電話番号の貸し出し、郵便物や電話の転送などはオプションとなるのが一般的です。オプションの追加にはコストが発生するものの、これらが充実していると事業運営がスムーズになります。
そのため、自分の事業スタイルに合った機能やオプションを利用できるかどうかを確認しておきましょう。
また、同一の機能であっても、サービスごとに料金が異なるため、比較検討するのをおすすめします。
【ポイント③】契約内容や縛りなど
バーチャルオフィスの契約時には、契約期間の縛りや解約条件などの契約内容を細かくチェックしましょう。
例えば、最低利用期間が長く設定されている場合、解約時に高額な違約金が発生するケースがあります。また、契約の自動更新などの通知も行われるかどうかも確認してください。
契約内容に不明点があれば、事前に問い合わせておくとよいでしょう。
【ポイント④】立地
バーチャルオフィスで借りられる住所の立地は、事業の印象や信頼度に大きく影響します。
都心の一等地や知名度の高いエリアの住所であれば、ブランディング効果を期待できるでしょう。しかし、利用料金が安いからといった理由でサービスを選んでしまうと、有名エリアから外れた住所を貸し出され、バーチャルオフィスのメリットの恩恵を受けられなくなってしまいます。
また、立地の良さとともに、該当する住所の建物も確認しておくとよいでしょう。事業イメージに合ったビルなのか、古すぎるビルではないかなどがチェックすべきポイントです。
>$
【ポイント⑤】
住所や電話番号に問題がないか
貸し出される住所や電話番号に問題がないかどうかも、バーチャルオフィス選びで重要なポイントです。
例えば、過去に詐欺で悪用されていたり、悪評がある住所は避けたほうが無難です。
取引先がその事実を知っていた場合、信用面でのリスクがあるかもしれません。
【ポイント⑥】同一名の法人はないか
新たに設立する法人名と同一の会社がないかも確認すべきポイントです。
特に法人を設立する場合、同一商号同一本店の禁止が会社法で定められているため、同一名の法人があると希望の法人名で設立できなくなってしまいます。
また、似た名称の会社が存在する場合、取引先や顧客の混乱を招く可能性があります。
法人名の独自性はブランドイメージにも直結するため、登記前に国税庁 法人番号公表サイトなどで類似する法人がないかをチェックしておきましょう。
バーチャルオフィスで起業する際の注意点

銀行によって異なりますが、バーチャルオフィスだと法人口座の開設審査基準を満たせない可能性もあります。過去にバーチャルオフィスの住所を悪用した犯罪が発生した事例があるため、銀行側も慎重になっている可能性があります。バーチャルオフィスの契約前に、法人口座も問題なく開設できるか確認してください。
バーチャルオフィスでの起業に関するよくある質問

バーチャルオフィスを初めて利用する場合、さまざまな面で疑問に思うこともあるのではないでしょうか。そこで、ここからはよくある質問と回答を紹介します。バーチャルオフィスに関する疑問を解消し、起業に役立てるための参考にしてください。
Q.バーチャルオフィスは違法にならない?
A.バーチャルオフィスで起業しても違法にはなりません。ただし前述の通り、人材派遣業や士業などバーチャルオフィスの利用が向いていない職種もあるため注意してください。
Q.個人事業主でもバーチャルオフィスは利用できる?
A.バーチャルオフィスは、法人だけでなく個人事業主も利用できます。「自宅の住所は公開したくないので、事業用の住所が欲しい」といった理由でバーチャルオフィスを利用する個人事業主は少なくありません。
バーチャルオフィスなら低コストで利用できるため、小規模事業を行う個人事業主でも取り入れやすいでしょう。
Q.バーチャルオフィスを利用する場合、納税地はどこになる?
A.個人事業主の場合、原則自宅住所地が納税地となります。法人の場合はバーチャルオフィスが本店所在地となっていれば、バーチャルオフィスの住所地が納税地となります。
Q.バーチャルオフィスの費用は経費になる?
A.バーチャルオフィスの利用料金やオプション料金は経費として計上できます。バーチャルオフィスの基本料金に該当する部分は「支払手数料」として仕訳されるケースが多いです。
会議室のレンタルやロッカーの利用などのオプションは、各項目の内容に合わせて仕訳を行ってください。なお、バーチャルオフィスは実態を伴わないため、仕訳の勘定科目として「賃貸料」を使うのは不適切とされています。
Q.バーチャルオフィスで社会保険や雇用保険に加入できる?
A.バーチャルオフィスでも社会保険や雇用保険に加入できます。加入の申請は、通常のオフィスを利用している場合と同様です。厚生年金保険や健康保険といった社会保険は年金事務所へ、雇用保険は公共職業安定所(ハローワーク)へ必要書類を提出しましょう。
【まとめ】バーチャルオフィスならGMOオフィスサポート!

画像引用元:GMOオフィスサポート株式会社
使い勝手のよいバーチャルオフィスをお探しの場合は、GMOオフィスサポートがおすすめです。月額660円から利用できます。
各種銀行にて法人口座開設の実績があるのに加え、GMOあおぞらネット銀行なら情報連携により口座開設時の手間を省けるのも嬉しいポイントです。郵便物等の到着・発送をLINEで知らせてくれたり、法人設立登記代行などのビジネス支援を利用できたり、サービス内容も充実しています。
リーズナブルな価格でバーチャルオフィスを利用したい場合は、ぜひ検討してみてください。
バーチャルオフィスは、オフィスを構えるコストを削減したいときや、自宅の住所を公表したくないときに役立ちます。住所の貸し出しだけでなく固定電話番号の貸し出しや郵送物の転送などのサービスも揃っており、スムーズな事業運営に繋げられるのが魅力です。便利なバーチャルオフィスを選んで、起業に活用してみてはいかがでしょうか。
会社の銀行口座(法人口座)はGMOあおぞらネット銀行がおすすめ!

画像引用元:GMOあおぞらネット銀行
会社設立時にネットバンクで銀行口座を開設するなら、GMOあおぞらネット銀行がおすすめです。
手間なくスピーディーに口座開設できる点が強みで、口座開設手続きは印鑑レス・ペーパーレス・郵送レスで行うことができます。また、条件を満たせば最短即日で口座を開設できます。
振込手数料は同行宛て無料に加え、他行宛てでも一律143円/件(税込)(※)と低価格で、さらに設立1年未満のお客さまであれば、他行宛て振込手数料が月20回まで無料です。
創業期のお悩みを解決するため、外部企業と提携してさまざまなサービスを紹介するビジネスサポートも行っており、会社運営の面でも強い味方になるでしょう。ぜひGMOあおぞらネット銀行をご利用ください。
(※)2025年8月1日より
起業や開業、独立に興味を持ったら、まずは「起業の窓口」に登録してみよう!
「起業の窓口」では、起業に必要なノウハウや成功者のインタビューなど、さまざまなコンテンツを完全無料で提供しています。
会員特典として、起業・経営支援のプロ「V-Spirits」が監修するオリジナル冊子『会社設立完全ガイド』を無料プレゼント。さらに、V-Spritsによる1時間の無料起業相談や、GMOインターネットグループが展開するビジネスの立ち上げや拡大に役立つ各種サービスをおトクな特典付きでご紹介します。
あなたの夢の実現を全力でサポートします!
- 記事監修
-
- 中野 裕哲 HIROAKI NAKANO
- 起業コンサルタント(R)、経営コンサルタント、税理士、特定社会保険労務士、行政書士、サーティファイドファイナンシャルプランナー・CFP(R)、1 級FP 技能士。 V-Spiritsグループ創業者。東京池袋を本拠に全国の起業家・経営者さんを応援!「あの起業本」の著者。著書16冊、累計20万部超。経済産業 省後援「DREAMGATE」で11年連続相談件数日本一。
GMOインターネットグループ株式会社はGMOあおぞらネット銀行株式会社を所属銀行とする銀行代理業として、円普通預金の受入れを内容とする契約の締結の媒介を行います。
銀行代理業許可番号:関東財務局長(銀代)第335号
- ※本記事は、起業の窓口編集部が専門家の監修または独自調査(アンケート)に基づいて制作したものです。
- ※掲載している情報は、記事公開時点の法令・税制・商品・サービス等に基づくものであり、将来的に変更される可能性があります。
- ※アンケート調査に関する記述は、特定の調査対象者からの回答結果および編集部の見解を含んでおり、内容の正確性・完全性を保証するものではありません。
- ※記事の内容は一般的な情報提供を目的としており、すべての方に当てはまるものではありません。個人の状況に応じた具体的な助言が必要な場合は、専門家にご相談ください。
- ※情報の利用や判断、実施については、ご自身の責任で行っていただきますようお願いいたします。
- ※本記事に掲載された内容の転載・複製はご遠慮いただき、引用の際は必ず出典をご明記ください。



 シェア
シェア