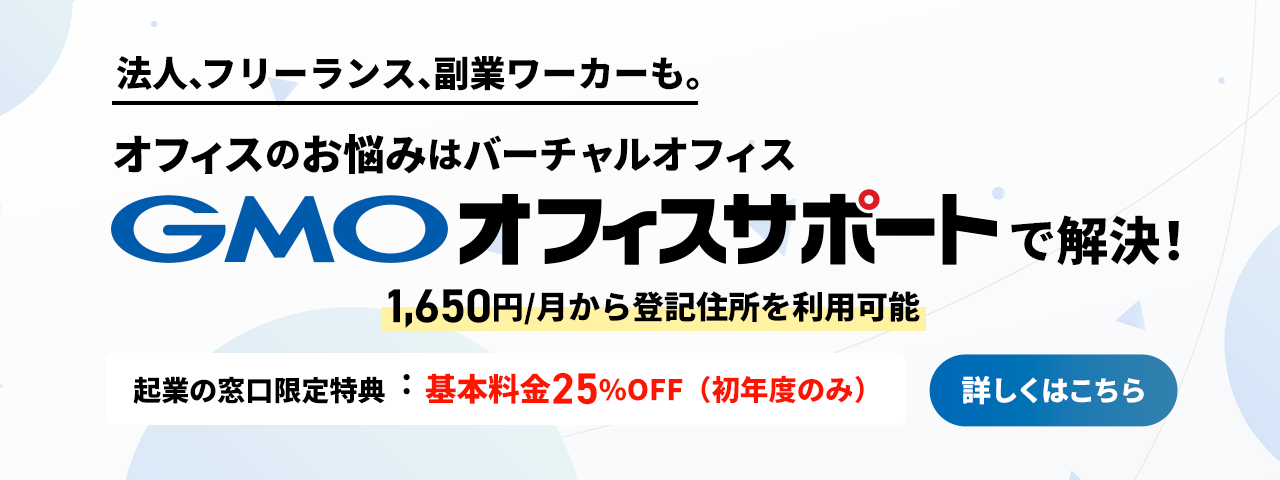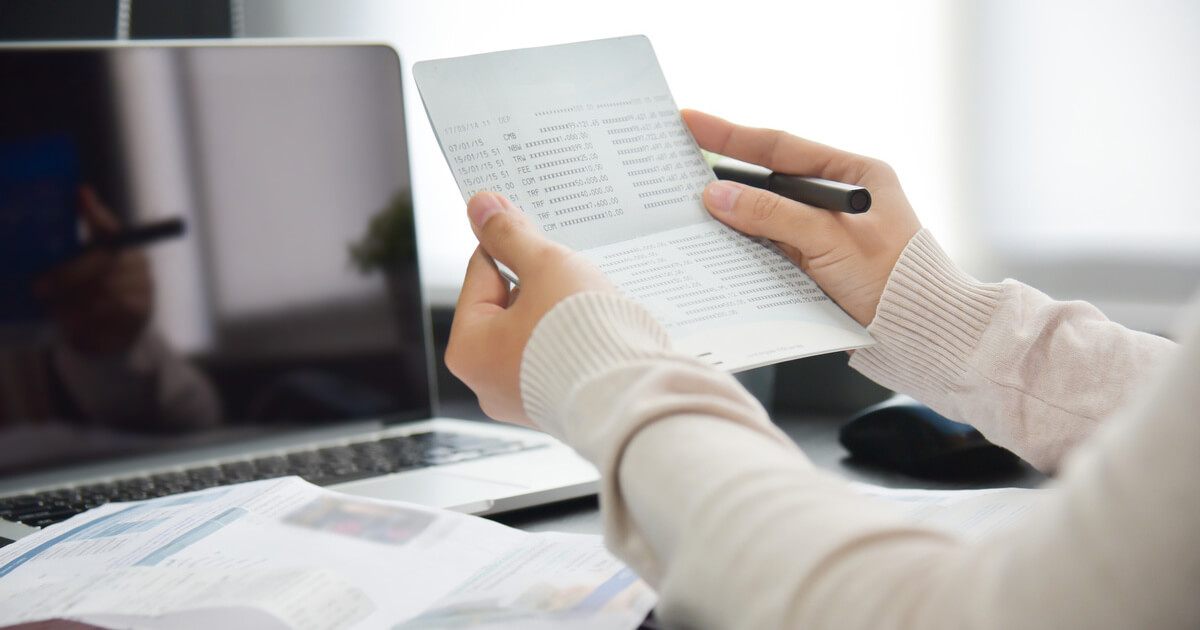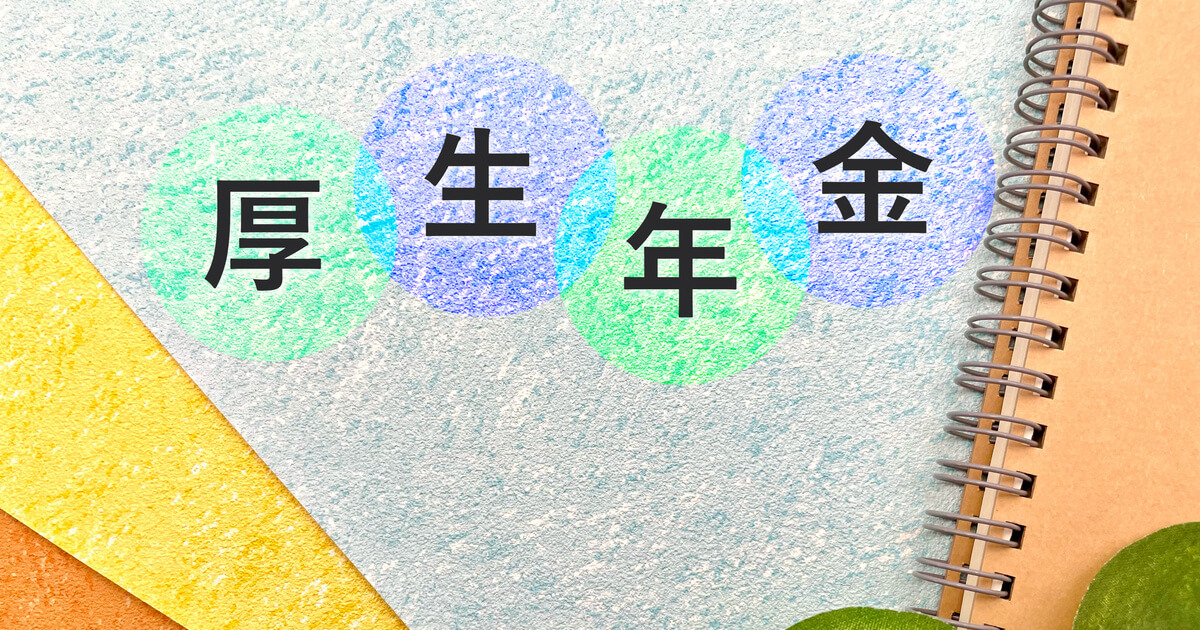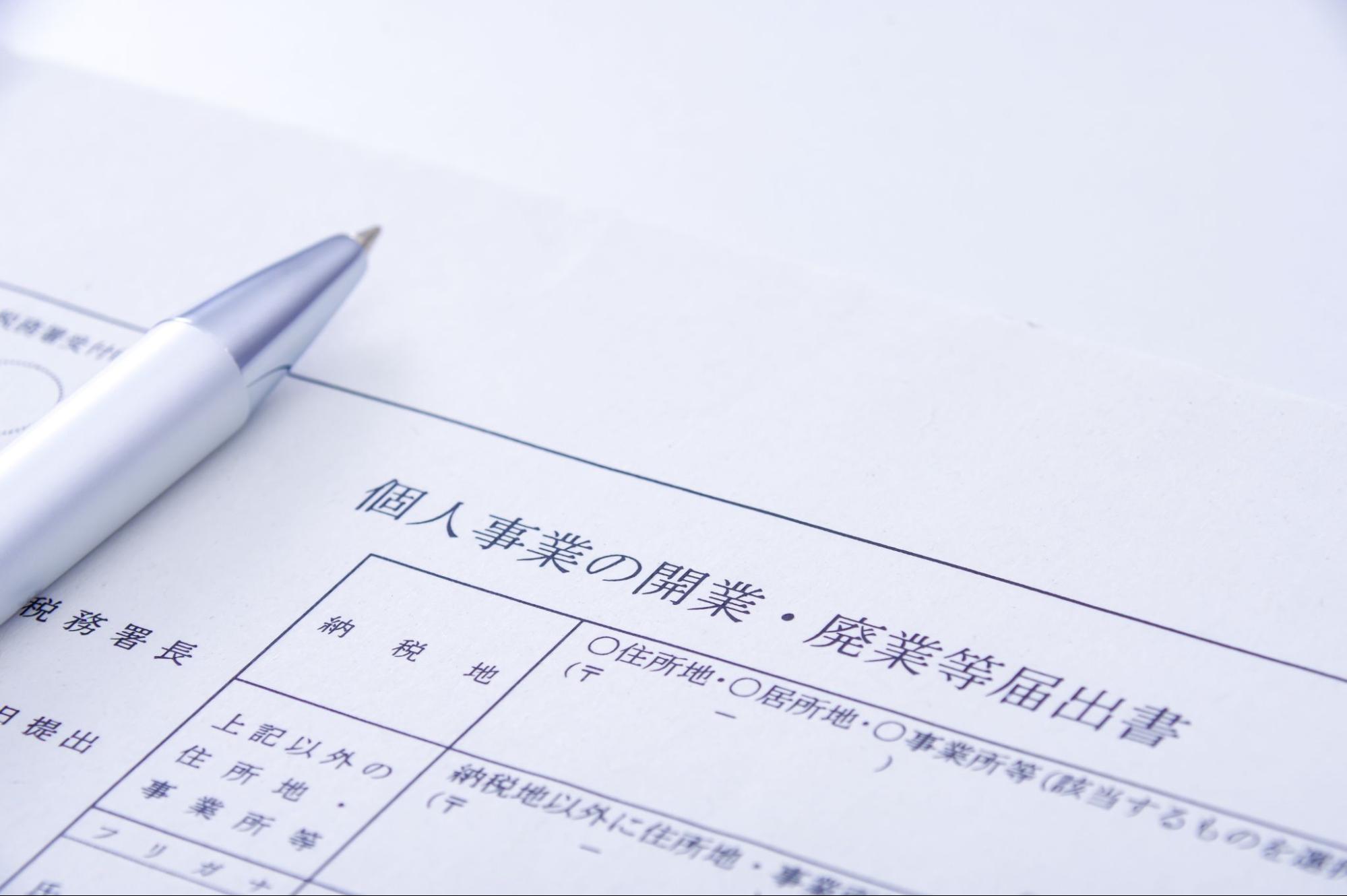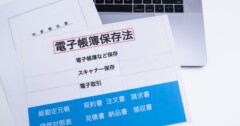個人事業主がバーチャルオフィスで開業するメリット7選!納税地や選び方も解説

本記事では、個人事業主がバーチャルオフィスを利用するメリットや、利用した場合の納税地の書き方などについて解説します。
- 【この記事のまとめ】
- バーチャルオフィスは、住所を提供するだけでなく、事業の信頼性を高めるため、特に都心の一等地住所が個人事業主に人気です。また、プライバシーも保護できます。
- バーチャルオフィスを利用する場合、開業届にその住所を記載しても問題ありません。納税地として自宅や事業所の住所も選択できるため、使い分けが可能です。
- バーチャルオフィスは経費削減に有効で、会議室や電話サービスも利用できるため、初期コストを抑えつつ、事業運営を効率化できます。
2024年11月1日より、フリーランス保護法が施行されます。
組織に所属せずに働くフリーランスが安心して働ける環境を整備するために、フリーランスと企業などとの発注事業者間の取引の適正化(契約書等により取引条件を明示する)が主な目的です。
詳しくは次の記事をご覧ください。フリーランス保護法の概要、制定された背景や具体的な内容などを解説しています。
開業届の納税地にバーチャルオフィスの住所を書いていい?【結論】住所地・居住地・事業所から選択可能

冒頭で触れたように、バーチャルオフィスは従来のオフィスとは異なり、物理的なオフィス スペースがないビジネス向けのサービスです。そのため、個人事業主がバーチャルオフィスを利用した場合、開業届の納税地にはどこの住所を書けばいいのか迷う人もいるでしょう。
個人事業主は、「住所地」「居住地」「事業所」のいずれかから納税地を選択できます。
バーチャルオフィスを個人事業主におすすめする7つの理由

個人事業主にバーチャルオフィスがおすすめである理由は、主に以下の7つです。
- 事業の信頼性を担保できる
- 商用利用できない賃貸物件に住んでいても起業できる
- プライバシーを確保できる
- 経費削減ができる
- 会議室や電話番号などのサービスを利用できる
- 住所変更を申請する手間がかからない
- 申込後は利用開始までの期間が短い
それぞれ詳しく解説していきます。
事業の信頼性を担保できる
バーチャルオフィスを利用することで、事業の信頼性を高める効果があります。
都心一等地などの好立地の住所をオフィスの住所として利用できるので、企業イメージを向上させることができ、顧客や取引先などから信頼感を得ることに繋がるでしょう。
商用利用できない賃貸物件に住んでいても起業できる
バーチャルオフィスは、商用利用できない賃貸物件に住んでいても起業が可能になるメリットがあります。
賃貸物件のなかには、契約時に商用利用が禁止されていることがあります。自宅の住所を事業の所在地として使用できず、起業の際の大きな障壁になるケースも少なくありません。
一方、バーチャルオフィスでは、契約内容の制約を受けず、住所を利用できます。例えば、ネットショップを運営する際に必要な特定商取引法に基づく表記にも使用可能です。
また、自宅住所を公開せずに事業を運営できるため、プライバシーを守れます。特に自宅に家族がいる人や女性にとっては大きなメリットです。ビジネスとプライベートをしっかりと切り分けながら、事業を展開できます。
プライバシーを確保できる
バーチャルオフィスの住所を使えば、自宅の住所を公開する必要がありません。これにより、プライバシーを保護できます。また、情報漏洩などのリスクを軽減できるので、セキュリティ対策にもなります。
特定商取引法などの表記で自宅を公開するのはトラブルになった際などリスクがあるため、バーチャルオフィスの住所を使った方が安全です。
経費を削減できる
実際のオフィススペースを借りるコストと比較して、バーチャルオフィスは大幅な経費削減が可能です。家賃や設備費といった初期費用や固定費用が抑えられるので、経済的に大きなメリットがあります。
また、都内でオフィスを構えようとすると、マンションの一室を借りるのにも家賃だけで10万円以上はかかるものです。家賃がかからないだけでも、経費を大きく削減できるでしょう。
会議室や電話番号などのサービスを利用できる
バーチャルオフィスでは、会議室のレンタルや電話番号の利用、郵便物の管理サービスなど、多様なビジネスニーズに応じたサービスを受けられます。
会議室や応接室は必要に応じて利用できるため、固定費を抑えられるでしょう。また、電話対応や郵便物の転送などは秘書サービスを利用できるので、オフィスに自分の身を置かなくても問題なく仕事を進められます。
住所変更を申請する手間がかからない
引っ越しをしても、バーチャルオフィスの住所は変わらないため、住所変更の申請やその手間を省くことができます。自宅の住所を納税地に記載していた場合は、自宅住所が変更になったタイミングで税務署への住所変更申請が必要です。
申込後は利用開始までの期間が短い
申込後は利用開始までの期間が短いのも、バーチャルオフィスならではの特徴です。
起業する際、事務所やオフィスの確保に時間がかかると、スタートが遅れ、ビジネスチャンスを逃すことにもなりかねません。例えば、実体のある事務所やオフィスを賃貸する場合、内覧・審査・契約といった手続きで1ヶ月~2ヶ月ほどの期間が必要です。
一方、バーチャルオフィスは申し込みから利用開始まで、早くて即日最短、一般的に数日以内には利用開始が可能です。また、オンライン上での申し込みを受け付けているケースが多いため、忙しい起業準備の妨げになる心配もありません。
バーチャルオフィスの利用が適している個人事業主の業種

バーチャルオフィスは、物理的なスペースを借りることなく、事業用住所を利用できるサービスです。
起業初期のコスト削減やプライバシー保護など多くのメリットがあります。特に以下の業種を営む個人事業主に適しています。
- ネットショップ・ECサイト
- Web関連事業
- 動画配信者
- 出張・訪問ビジネス
- オンライン講師
- アフィリエイター
ここでは、それぞれの業種でバーチャルオフィスがどのように適しているのかを解説します。
ネットショップ・ECサイト
ネットショップやECサイトを運営する場合、自宅や別の作業スペースで商品の仕入れや管理、梱包や発送を行いながらも、ビジネス上の住所や連絡先が必要です。
特定商取引法において、インターネットでの通信販売を行う際は事業者の住所の記載が義務付けられています。そのため、バーチャルオフィスで借りられる住所の利用は重宝します。
特に自宅住所を公開しないことで、顧客からの直接的なクレームを防止できるため、安全面の観点からも活用すべきです。
また、Webサイト上に記載する住所の立地が一等地だったり、有名なエリアであると顧客や取引先からの信用度が上がります。その結果、販売促進にもつながり、売上アップにも貢献するでしょう。
Web関連事業
Web関連事業を営む個人事業主には、バーチャルオフィスの利用が適しています。
理由の一つがコスト面です。Webデザイン、システム開発、SEOコンサルタントなど、Web関連事業には複数の業種がありますが、実作業はパソコンとインターネット環境があれば完結するケースがほとんどです。そのため、物理的なオフィスを持つ必要がなく、バーチャルオフィスの利用によってコストを削減できます。
また、自宅住所ではなく、バーチャルオフィスの住所を利用することによって、クライアントからの信用度が高まり、受注できる可能性も高めてくれます。
動画配信者
YouTubeやTikTok、Instagramなどの動画配信者にもバーチャルオフィスの利用がおすすめです。
自宅などで制作活動を行いながらも、ビジネスとしての住所を持つことが信頼獲得につながります。例えば、企業とのタイアップやスポンサー契約時にバーチャルオフィスの住所を構えていると、案件獲得の可能性を高めるかもしれません。
また、バーチャルオフィスの郵便物転送サービスは、ファンとの交流時にも役立ちます。例えば、ファンからのプレゼントを受け取る場合に自宅の住所を公開しなくてもよいため、安全面で有効です。また、動画の企画でファンにプレゼントを送る場合でも、発送先の住所としてバーチャルオフィスの住所を記載できるため、プライバシーの確保が可能です。
出張・訪問ビジネス
訪問介護、ハウスクリーニング、家事代行など、顧客のもとでサービスを提供するビジネスは、バーチャルオフィスの利用が向いています。
これらの業種は、一般的に固定店舗を持たない場合が多い傾向です。しかし、その場合はWebサイト上などに自宅住所を記載しなければならず、プライバシーの観点からもリスクがあります。
一方、バーチャルオフィスを利用すれば、Webサイトや名刺、チラシなどに借りた住所を記載できるため、プライバシーを守れます。
特に自宅を拠点にしながら、コストを抑えたい人にとってバーチャルオフィスはピッタリのサービスです。
オンライン講師
オンラインスクールやオンラインセミナーの講師は、業務する場所が問われないため、バーチャルオフィスでの起業が適しています。
オンライン講師がバーチャルオフィスの住所を利用することで、受講生や取引先に安心感を与え、信頼を高められます。
また、オンライン講師はインターネット上で受講生と顔を合わせるシーンもありますが、それに合わせて自宅住所を公開するとリスクが高まります。例えば、女性講師の自宅住所へ受講生が突然訪れてくるといった危険に遭遇する可能性もあるでしょう。
そのため、特に女性のオンライン講師は、自宅の住所を公開せず、バーチャルオフィスの住所を利用してプライバシーを守りましょう。
アフィリエイター
ブログやSNSで広告を得るアフィリエイターは、事務所やオフィスを持たず、自宅で活動することがほとんどです。
広告主から自宅以外の住所を求められるケースは稀ですが、事業拡大のために作業の外注化などを検討する場合には、バーチャルオフィスの住所が役立ちます。
例えば、外部のフリーランスと業務委託契約を結ぶ場合、住所を知らせる必要がありますが、自宅で活動しているアフィリエイターは自宅住所を公開しなければいけません。
しかし、自宅の住所公開は、プライバシーや安全の観点からもおすすめできません。
一方、バーチャルオフィスを使用すれば、業務委託契約書に借りている住所を記載できるため、プライバシーの保護につながります。
【手順】個人事業主がバーチャルオフィスで開業するにはどうすればいい?

バーチャルオフィスで開業するには、以下の手順を踏む必要があります。
- バーチャルオフィスのサービスを選び、契約する
- バーチャルオフィスの住所を開業届に記入する
- 納税地を住所地、居住地、事業所のいずれかに選ぶ
- 青色申告承認申請書を提出する
- 銀行口座を開設する
利用を希望するサービスを選んだら、まずは申込みましょう。事前に疑問点を問い合わせてみたり、現地へ内覧に行ってみたりするのもおすすめです。
バーチャルオフィスへ申し込む際は、一般的に写真付き身分証明書のほか、個人事業主であれば住民票などが必要になります。書類をもとに審査が行われ、おおよそ1週間程度で結果が通知されます。サービスの性質上、不正な目的で利用される可能性も秘めているため、どこのサービスでも基本的には審査が設けられています。審査に通過したら入会金などの初期費用を支払い、契約できます。
契約が完了すれば、開業届にバーチャルオフィスの住所を事業所として記載しても問題ありません。
【重要】個人事業主がバーチャルオフィスを利用する際の選び方

個人事業主がバーチャルオフィスを選ぶ際は、以下のポイントに注目しましょう。
- 初期費用やランニングコストから選ぶ
- 郵便物・電話転送の有無をチェック
- 会議室やコワーキングスペースは使えるか
- 最低契約期間のチェック
- 住所の立地や信頼性をチェック
- 法人登記が可能かどうか
- 信頼できる企業が運営しているか
ここでは、個人事業主がバーチャルオフィスを利用する際の選び方を解説します。
初期費用やランニングコストから選ぶ
バーチャルオフィスで起業する際は、まず初期費用やランニングコストに注目します。
契約時にかかる費用と月額費用、オプション費用などを加味したうえで計算しましょう。
バーチャルオフィスは、物理的なオフィスを賃貸するよりもコストを抑えられるものの、起業初期は資金に限りがあることが多いため、無理のない料金設定のサービス選びが重要です。
特に月額料金は1,000円~1万円ほどと広い範囲が相場となるため、経営に影響が出ない範囲で検討しましょう。
また、不要なオプションを省略できる場合は、カットしてコスト削減を図るのもよいでしょう。
郵便物・電話転送の有無をチェック
バーチャルオフィスの代表的なオプションとして、郵便物や電話転送のサービスが提供されています。
しかし、すべてのバーチャルオフィスでこれらのサービスが含まれているわけではありません。郵便物や電話転送を利用したい人は、事前にチェックしておきましょう。
また、郵便物の取り扱い方法、電話転送の仕組みは業者ごとに異なるため、内容を確認しておくと安心です。特に電話転送が可能な時間帯、郵便物の保管期間や転送にかかる費用は注目すべきポイントです。
会議室やコワーキングスペースは使えるか
バーチャルオフィスのなかには、会議室やコワーキングスペースの利用が可能な場合があります。
顧客や取引先との打ち合わせに活用したい場合は、設備の有無と利用方法、料金体系を確認しておきましょう。
また、頻繁に利用する予定があれば、空き具合や施設へのアクセス面も確認すべきポイントです。
最低契約期間のチェック
バーチャルオフィスによっては、契約内容に最低契約期間が設けられている場合があります。
最低契約期間内に解約した場合、高額な違約金が発生するケースがあるため注意が必要です。特に事業所の変更や事業規模の拡大が早期で予想される場合は、短期契約や縛りのないプランを提供するバーチャルオフィスを選ぶとよいでしょう。
また、契約内容によっては、通知なく自動更新が行われるケースもあるため、契約満了日は必ず覚えておいてください。
住所の立地や信頼性をチェック
バーチャルオフィスの住所は、事業のイメージとして顧客や取引先の信用に関わります。
都心の一等地やオフィス街に住所が構えられていれば、事業のブランディング効果も期待できるでしょう。
ただし、過去に特殊詐欺などの犯罪で使用されたバーチャルオフィスも少なからず存在します。このような住所は、顧客や取引先に悪いイメージを与えるため注意が必要です。
また、好立地の住所ほどコストが高くなる傾向があるため、料金とブランディング効果を比較しつつ、検討しましょう。
法人登記が可能かどうか
バーチャルオフィスの住所が法人登記可能かどうかも、重要なポイントです。
個人事業主であれば登記は必要ありませんが、将来的に法人設立を検討している場合は、事前に確認しておく必要があります。
例えば、個人事業主としてバーチャルオフィスの住所を使い、事業拡大にともない法人設立を検討したとします。バーチャルオフィスの住所が法人登記に対応していない場合、新たにオフィスを借りたり、法人登記が可能なサービスへの移行を検討しなければならないため、費用と手間がかかります。
後々の手間とコストを減らすためにも、最初から法人登記可能なバーチャルオフィスの利用をおすすめします。
信頼できる企業が運営しているか
バーチャルオフィスを長く安心して使うためには、企業の信頼性や実績が重要です。
例えば、料金体系が安いからと、実績のない企業が運営するバーチャルオフィスを利用した場合、倒産のリスクが懸念されます。もし運営会社が倒産した場合、利用していた住所は使用できないほか、新たな住所の確保、関係各所への連絡、住所変更手続きなど、多くの手間とコストがかかってしまうでしょう。
そのため、数年以上の運営歴を持ち、利用者の評判や口コミの高いバーチャルオフィスの利用がおすすめです。
【注意】個人事業主がバーチャルオフィスを利用する際の注意点

バーチャルオフィスを利用する際の注意点は、以下の6つです。
- 郵便物の受取りが面倒くさい
- 業種によってはバーチャルオフィスを利用できない場合がある
- バーチャルオフィスを納税地にすると税率の違いで負担が増えるケースがある
- 他社と住所が重複するケースがある
- 実務を行う場所が別途必要
- 運営会社が廃業した場合は住所を使えない
郵便物の受け取りが面倒くさい
バーチャルオフィスでは郵便物の管理サービスが提供されているものの、直接的な郵便物の受け取りには制限があります。
必要に応じて、郵便物の転送サービスを利用することが可能です。基本的には、バーチャルオフィスを運営している企業のもとへ郵便物が届き、そのあとバーチャルオフィスの運営会社から利用者に郵便物が転送される仕組みです。
また、郵便物の転送にはタイムラグが発生する点にも注意しなければいけません。一度バーチャルオフィスの住所に荷物が送られてから自分の元へ届くため、通常の配送よりも時間がかかります。
そのため、重要な書類や急を要する荷物には不向きです。
業種によってはバーチャルオフィスを利用できない場合がある
一部の業種では、バーチャルオフィスの利用が認められていないことがあります。建設業や有料職業紹介業など許認可が必要な業種では、バーチャルオフィスを事業所として使用することが難しい可能性が高いです。
代表例は以下の通りです。
- 建設業
- 不動産業
- 一部の士業
- 人材派遣業
- 探偵業
- 廃棄物処理業
- 古物業
バーチャルオフィスを納税地にすると税率の違いで負担が増えるケースがある
バーチャルオフィスを納税地にする場合、税率の違いの理解が必要です。
特に市町村民税は地方自治体によって設定されており、財源確保や環境対策の目的で超過課税が含まれる場合があります。例えば、地方税の超過課税は自治体により異なります。例えば、神奈川県では「水源環境保全税」、愛知県では「あいち森と緑づくり税」が県民税に上乗せされています。
これらの違いによって税負担が変わるため、納税地を選択する場合は税率を比較したうえで検討しましょう。
他社と住所が重複するケースがある
バーチャルオフィスは、利用者が同一の住所を使用しています。
そのため、他社と住所が重複するケースは避けられません。特に人気の高いバーチャルオフィスは、複数の法人や個人事業主が同じ住所を使っています。
住所の重複自体は法律に触れないものの、取引先や顧客からの信用に影響を与える場合があるため、事前に告知しておくほうがよいでしょう。
実務を行う場所が別途必要
バーチャルオフィスは、住所のみを貸し出すサービスです。
実際の業務を行う場所は含まれていないため、実務を行うスペースの確保が別途必要です。例えば、ネットショップ運営にあたっては、商品の保管や管理、発送準備などの実務を行うスペースが必要になるでしょう。
自宅での実務を予定していない場合は、バーチャルオフィスとは別の場所の確保を忘れずに行ってください。
運営会社が廃業した場合は住所を使えない
バーチャルオフィスの運営会社が廃業すると、今まで使っていた住所が使えなくなります。
個人事業主であれば、新たなオフィスの確保とともに、税務署へ個人事業の開業・廃業等届出書の提出(住所変更)、Webサイトや名刺の修正、利用するサービスの住所変更、取引先への連絡など、多くの手間が発生します。
運営会社の廃業は予測できない事態ですが、信頼性の確認とともに、万が一の対応策も考えておきましょう。
バーチャルオフィスについてよくある質問

バーチャルオフィスを初めて利用する場合、さまざまな面で疑問に思うこともあるのではないでしょうか。そこで、ここからはよくある質問と回答を紹介します。バーチャルオフィスに関する疑問を解消し、事業を始めるための参考にしてください。
Q.バーチャルオフィスは違法にならない?
A.バーチャルオフィスで起業しても違法にはなりません。ただし前述の通り、人材派遣業や士業などバーチャルオフィスの利用が向いていない職種もあるため注意してください。
Q.個人事業主でもバーチャルオフィスは利用できる?
A.バーチャルオフィスは、法人だけでなく個人事業主も利用できます。「自宅の住所は公開したくないので、事業用の住所が欲しい」といった理由でバーチャルオフィスを利用する個人事業主は少なくありません。
バーチャルオフィスなら低コストで利用できるため、小規模事業を行う個人事業主でも取り入れやすいでしょう。
Q.バーチャルオフィスを利用する場合、納税地はどこになる?
A.個人事業主の場合、納税地は「住所地」「居所」「事業所」から選択可能です。法人の場合は、本店所在地として登記した住所が納税地となります。
Q.バーチャルオフィスの費用は経費になる?
A.バーチャルオフィスの利用料金やオプション料金は経費として計上できます。バーチャルオフィスの基本料金に該当する部分は「支払手数料」として仕訳されるケースが多いです。
会議室のレンタルやロッカーの利用などのオプションは、各項目の内容に合わせて仕訳を行ってください。なお、バーチャルオフィスは実態を伴わないため、仕訳の勘定科目として「賃貸料」を使うのは不適切とされています。
Q.バーチャルオフィスで社会保険や雇用保険に加入できる?
A.バーチャルオフィスでも社会保険や雇用保険に加入できます。加入の申請は、通常のオフィスを利用している場合と同様です。厚生年金保険や健康保険といった社会保険は年金事務所へ、雇用保険は公共職業安定所(ハローワーク)へ必要書類を提出しましょう。
Q.バーチャルオフィスに住民税はかかる?
A.個人住民税(均等割)は、住民票のある住所地の市区町村で課税されます。そのため、バーチャルオフィスの住所が課税対象になることはありません。
【まとめ】個人事業主がバーチャルオフィスの住所を納税地として書いても問題ない
今回は、バーチャルオフィスが個人事業主におすすめの理由や注意するポイントについて解説しました。個人事業主がバーチャルオフィスを利用して開業する場合、開業届に記載する納税地はどこの住所を書けばよいか迷ってしまうものです。バーチャルオフィスの住所を書いても問題ありません。
GMOオフィスサポート バーチャルオフィスでは、初期費用0円、月額660円からサービスを提供しています。渋谷や新宿、銀座などの人気エリアにある一等地のビルの住所を使うことが可能です。郵便物の転送や銀行への連携のサポートなども充実しているので、バーチャルオフィスを検討している方はぜひ選択肢に入れてみてはいかがでしょうか。
「起業の窓口」では、個人事業主の方々に向けて、業務効率化のヒントや成功事例、最新のビジネス情報など、お役立ち情報を提供しています。
ぜひ、「個人事業主」に関する他の記事もご覧ください。
起業や開業、独立に興味を持ったら、まずは「起業の窓口」に登録してみよう!
「起業の窓口」では、起業に必要なノウハウや成功者のインタビューなど、さまざまなコンテンツを完全無料で提供しています。
会員特典として、起業・経営支援のプロ「V-Spirits」が監修するオリジナル冊子『会社設立完全ガイド』を無料プレゼント。さらに、V-Spritsによる1時間の無料起業相談や、GMOインターネットグループが展開するビジネスの立ち上げや拡大に役立つ各種サービスをおトクな特典付きでご紹介します。
あなたの夢の実現を全力でサポートします!
- 記事監修
-
- 中野 裕哲 HIROAKI NAKANO
- 起業コンサルタント(R)、経営コンサルタント、税理士、特定社会保険労務士、行政書士、サーティファイドファイナンシャルプランナー・CFP(R)、1 級FP 技能士。 V-Spiritsグループ創業者。東京池袋を本拠に全国の起業家・経営者さんを応援!「あの起業本」の著者。著書16冊、累計20万部超。経済産業 省後援「DREAMGATE」で11年連続相談件数日本一。
- ※本記事は、起業の窓口編集部が専門家の監修または独自調査(アンケート)に基づいて制作したものです。
- ※掲載している情報は、記事公開時点の法令・税制・商品・サービス等に基づくものであり、将来的に変更される可能性があります。
- ※アンケート調査に関する記述は、特定の調査対象者からの回答結果および編集部の見解を含んでおり、内容の正確性・完全性を保証するものではありません。
- ※記事の内容は一般的な情報提供を目的としており、すべての方に当てはまるものではありません。個人の状況に応じた具体的な助言が必要な場合は、専門家にご相談ください。
- ※情報の利用や判断、実施については、ご自身の責任で行っていただきますようお願いいたします。
- ※本記事に掲載された内容の転載・複製はご遠慮いただき、引用の際は必ず出典をご明記ください。



 シェア
シェア