個人事業主が受けられる融資制度|融資審査のポイントや注意点を解説

個人事業主でも、確定申告書による所得証明や事業計画書の提出により、さまざまな融資制度を利用できます。
日本政策金融公庫や銀行、信用金庫、地方自治体、ノンバンクなどが挙げられます。
融資を受けることで、事業を拡大しやすくなる他、「融資を受けた」という実績を作れる点もメリットの1つです。
しかし、利息負担や返済義務という重い責任も伴うため、資金繰りへの影響を慎重に検討する必要があります。
この記事では、個人事業主が受けられる融資制度の種類や融資審査のポイント、条件とタイミング、メリット・デメリットについて解説します。
- 【この記事のまとめ】
- 個人事業主向けに、日本政策金融公庫は「新規開業資金」など複数の融資制度を提供しています。無担保での借り入れが可能で、創業から7年以内の方に適しています。
- 地方自治体や信用金庫は地域密着型で柔軟な融資を提供しています。金利はやや高い傾向がありますが、地域特有の支援が受けられる点が特徴です。
- 個人事業主の融資審査では、事業計画、自己資金、信用情報が重視されます。事業状況に応じた適切な融資額を設定し、無理のない返済計画が求められます。
2024年11月1日より、フリーランス保護法が施行されます。
組織に所属せずに働くフリーランスが安心して働ける環境を整備するために、フリーランスと企業などとの発注事業者間の取引の適正化(契約書等により取引条件を明示する)が主な目的です。
詳しくは次の記事をご覧ください。フリーランス保護法の概要、制定された背景や具体的な内容などを解説しています。
「起業の窓口」では、AIインフルエンサーの茶圓氏とコラボをおこない、AIを活用してビジネスの効率化を図るための貴重な知識を提供しています。
特集ページ「AI×起業」では、最新のAI技術やツールを使った実践的なアプローチを紹介しており、起業家や個人事業主の業務をよりスマートにサポートします。
AIの力で業務の負担を軽減し、ビジネスの成長を加速させたい方に最適な情報が満載です。ぜひご覧ください。
【結論】個人事業主が受けられる融資制度

個人事業主が利用できる融資制度には、いくつかの選択肢があります。
日本政策金融公庫の融資
日本政策金融公庫とは、日本政府が100%出資する金融機関です。
日本政策金融公庫は、個人事業主が利用できる融資制度を複数用意しています。中でも代表的なものが「新規開業資金」です。
「新規開業資金」は、新たに事業を始める方または事業開始後おおむね7年以内の方を対象とした融資制度であり、原則として無担保で融資を受けられます。
日本政策金融公庫は小規模事業者への融資に積極的な点が大きな特徴です。
銀行融資
銀行でも、個人事業主向けの融資を行っています。
銀行から融資を受けたい場合は、普段から付き合いのある担当者に相談するか、融資窓口に直接問い合わせましょう。
長期の借り入れが可能で、比較的大きな金額を借りられる場合がありますが、融資審査は比較的厳しい傾向にあります。
事業の収益性や返済能力などが重視されるため、創業間もない個人事業主には難しい場合もあるでしょう。一般に銀行が個人事業主に融資を行う場合は後述する地方自治体の融資制度を活用します。
信用金庫の融資
信用金庫は地域密着型の金融機関であり、個人事業主向けの融資にも積極的です。
地元の中小企業や個人事業主を支援するため、融資審査も比較的柔軟な傾向にあります。
また、その地域に密着したサポートを受けられるのも特徴です。日本政策金融公庫に比べると金利が高い傾向にありますが、それでも選択肢の1つに入るでしょう。一般に信用金庫が個人事業主に融資を行う場合は後述する地方自治体の融資制度を活用します。
地方自治体の融資制度
地方自治体によっては、個人事業主も利用できる融資制度を設けている場合があります。
たとえば、東京都では「東京都中小企業制度融資『創業』」があり、個人事業主も利用できる制度の1つです。
「お住いの都道府県・市区町村名+融資」といった検索ワードで調べてみると、業種や用途ごとにさまざまな融資制度が出てくるでしょう。
融資制度の条件や金額は自治体によって大きく異なるため、申し込み前にしっかりと確認することが大切です。
また、融資とは異なり、補助金や助成金は返済不要です。返済の負担がない分、資金繰りが楽になるという利点があります。ただし、申請には補助金や助成金の目的に事業内容が合致していることが求められます。詳しくは次の記事をご覧ください。
ノンバンクの融資
ノンバンクとは、預金業務を行わないお金を貸すことに特化した金融機関のことです。
個人事業主向けの融資を行っているところが多く、審査がスピーディーで、銀行や公的機関と比べて融資までの時間が短いのがメリットです。
また、担保が不要なところもあるため、資金調達の選択肢の1つとなるでしょう。
ただし、金利が比較的高めである点が難点です。他の金融機関に比べて金利が高いことから、返済負担が大きくなる可能性があります。
ノンバンクによって信頼性も異なるため、利用する際は慎重な選択が必要です。
融資のほかに、クラウドファンディングも資金調達の方法としては有効です。詳しくは次の記事をご覧ください。
個人事業主が融資を受けるための基礎知識

個人事業主が融資を受ける際には、いくつかの基礎知識を理解しておく必要があります。
融資を受けるための条件
個人事業主が融資を受けるためには、事業の収益性や返済能力、信用情報などの条件を満たす必要があります。
融資制度を利用する際は審査が発生し、その審査に通らなければ融資を受けることはできません。
事業計画が明確で、安定した収入が見込めることが重要です。
また、過去の借入履歴や延滞の有無などの信用情報も確認されることもあるため、普段から信用情報を良好に保っておくことが大切です。
融資を受けるタイミング
個人事業主が融資を受けるタイミングは、主に事業の立ち上げ時の創業資金と事業が軌道に乗った後の運転資金や設備資金が必要なときの2つのケースが考えられます。
事業の立ち上げ時は、開業資金や設備費用などの初期投資にかかる資金を調達するために、金融機関から融資を受けるケースが多いです。
一方、事業が軌道に乗った後も、運転資金が不足する場合や設備投資が必要な場合に融資を検討することがあります。
事業が安定していない状態での融資は難しい場合が多いため、融資の申し込みタイミングには注意が必要です。
融資を受ける際は事業の状況や資金需要を十分に見極め、事業計画を立てることが重要です。
融資を受けられる金額
融資を受けられる金額は事業内容や返済能力、担保の有無などを総合的に判断して個別に決定されます。そのため、融資の金額を一概に算出することはできません。
日本政策金融公庫の新創業融資制度では最大3,000万円まで借入可能となっていますが、必ずしも限度額まで借りられるとは限らず、場合によっては融資を承認されないケースもあります。
初回融資では、300万円から500万円程度の少額から始まることがほとんどです。
確実に返済実績を積み重ねていくことで、次回以降の融資枠が段階的に拡大していく仕組みになっています。
担保提供により融資額を増やすことも可能ですが、万が一返済不能となった場合のリスクも十分に考慮する必要があります。
個人事業主が融資を受けるメリット

事業発展のチャンスを掴むためには、適切なタイミングでの資金調達が欠かせません。以下、融資を受けることで得られる具体的なメリットについて解説します。
事業を拡大しやすくなる
手元資金が潤沢になることで、これまで資金不足で見送っていた投資案件にも積極的にチャレンジできるようになります。
最新設備の導入により生産性は飛躍的に向上し、品質改善やコスト削減にも繋がるため、市場での競争力を大幅に強化できるでしょう。
また、在庫を充実させることで販売機会の損失を防ぎ、顧客の要望に即座に応えられる体制を構築できます。優秀な人材を採用して組織力を強化したり、広告宣伝に投資してブランド認知度を高めたりすることも可能です。
ただし、無計画な拡大は失敗のリスクも高めるため、投資効果を慎重に見極めながら、段階的に事業を成長させていくことが重要です。
「融資を受けた」という実績を作れる
金融機関からの融資実績は、事業者としての信用力を高める重要な要素となります。
返済実績があることで、次回以降の融資審査では「信頼できる取引先」として評価され、審査期間の短縮や金利優遇などのメリットを受けられる可能性が高まるのです。
他の金融機関からも信頼されやすくなり、複数の資金調達ルートを確保できます。
取引先や仕入先からの評価も向上し、掛け取引の条件改善や取引額の拡大に繋がることもあります。
ローン利息を経費として扱える
事業資金として借り入れた融資の利息は必要経費として計上できます。課税所得を減らすことで実質的な節税効果が期待できるため、資金調達コストの軽減に繋がります。
たとえば、年間50万円の利息を支払った場合、所得税率が30%なら15万円の節税となり、実質的な金利負担は表面金利よりも低くなる計算です。
ただし、元金返済分は経費にならない点に注意が必要です。
また、プライベート目的で使用している支払利息についても経費として認められないため、経費として計上したい場合は、必ず事業目的で借り入れするようにしましょう。
個人事業主が融資を受けるデメリット

融資を受けることは事業成長の起爆剤となる一方で、返済義務という重い責任が伴います。リスクや負担についても十分に理解したうえで融資の利用を検討してください。
ローン利息の負担が増える
融資を受けると元金に加えて利息の支払いが発生します。売上が計画通りに伸びなかった場合でも返済は待ってくれません。
たとえば、金利3%で500万円を5年返済する場合、総利息は約39万円にもなるため、資金繰りへの影響を慎重に検討する必要があります。
毎月の固定費として重くのしかかり、経営を圧迫する要因となってしまうこともあるでしょう。
返済期間が長期になるほど総利息額は増加していくため、可能な限り早期返済を目指すことが、トータルコストを抑える重要なポイントとなります。
管理や手続きの手間が増える
融資を受けると返済管理はもちろん、決算書の定期提出や業況報告など、これまでなかった事務作業が発生し、本業に割ける時間が減少する可能性があります。
金融機関からは四半期ごとの試算表提出を求められることもあり、経理処理を常に最新の状態に保つ必要が生じます。
複数の金融機関から借入がある場合、それぞれ異なる報告の対応や提出期限の管理など、事務負担はさらに増大してしまうでしょう。
返済が滞ると督促対応に追われることになり、精神的なストレスも大きくなります。
将来の審査に影響することがある
現在の借入状況は将来の融資審査に影響するため、安易な借入は新たな資金調達の障害となる可能性があります。
複数の借入により返済比率が高くなると、追加融資を受けにくくなります。
また、一度でも返済遅延があるとその記録は信用情報機関に5年間残り、他の金融機関での審査にも悪影響を及ぼすため、信用回復には長い時間が必要です。
住宅ローンや自動車ローンなど個人的な借入の審査にも影響し、プライベートでの資金計画に制約が生じることもあります。
【重要】個人事業主に対する融資審査のポイント

金融機関が個人事業主に対して融資審査を行う際には、一般的に以下のようなポイントを考慮します。
資金使途
融資審査では、借入金の使途が事業目的に合致しているかが重要なポイントとなります。事業の運転資金や設備投資など、明確な資金使途であることが求められます。
また、資金使途が事業計画と整合性があるかどうかも審査されるため、説得力のある説明が必要です。
資金使途が不明確だったり、事業目的と関係なかったりする場合は、融資が認められない可能性が高くなるでしょう。
事業計画
個人事業主の事業計画は、融資審査の重要な判断材料の1つです。
事業の収益性や成長性、市場性などが評価されるため、説得力のある事業計画を作成する必要があります。
また、事業計画が実現可能かどうかも審査のポイントとなります。計画が甘く、根拠が乏しい事業計画を立ててしまうと、審査に通りづらくなるため入念な準備が必要です。
自己資金
個人事業主が融資を受ける際は、自己資金が十分にあると審査が有利に進みます。
自己資金が十分にあることは、事業に対する経営者の意欲や準備の表れと見なされ、返済リスクを低く評価する材料となるのです。
一般的に、自己資金は30%以上あることが望ましいとされていますが、事業内容や融資金額によって異なるため、自己資金の基準は一概にはいえません。しかし利用する融資制度によっては自己資金の割合が明確に示されている場合もあります。
自己資金の割合は、事業の実情に合わせて適切に設定することが重要です。
経営状態
個人事業主の経営状態も、審査時の重要ポイントの1つです。
売上高や利益率、資金繰りなどの財務状況が評価の対象となり、事業の安定性や将来性、競合他社との比較なども考慮されます。
経営状態が良好で、返済の可能性が高いと判断されれば、融資が認められる可能性が高くなります。
一方、財務内容が悪化している場合や事業の先行きが不透明な場合は、融資審査が通りづらくなるため注意が必要です。
融資希望額
融資希望額は、事業規模や資金使途に見合った適切な金額であるかが評価されます。
融資希望額が事業計画や返済能力に対して過大である場合、返済リスクの観点から、融資が認められない可能性が高くなります。
余裕を持って経営を進めるために融資希望額を高くしてしまいがちですが、融資を断られるリスクもあるため、事業規模に見合った金額を設定しましょう。
返済能力
個人事業主の返済能力は、融資審査の重要な判断基準の1つです。事業からの売上や費用、利益などを基に、返済能力が評価されます。
返済能力が十分でないと判断されると、審査に通らず、融資を受けられない可能性が高くなります。
また、返済期間や返済方法なども審査のポイントとなるため、無理のない返済計画を立て、確実に返済できる見通しを示すことが重要です。
ご自身の返済能力を確認する方法の詳細を確認したい場合は税理士などのプロに相談するとよいでしょう。
信用情報
個人事業主の信用情報は、融資審査に大きな影響を与えます。個人の借入履歴や延滞の有無、クレジットカードの未払いなどが確認されます。
信用情報に問題がある場合、融資が認められない可能性が高くなるため、日頃から信用情報を良好に保つように努めることが大切です。
【注意】個人事業主が融資を受ける際の注意点
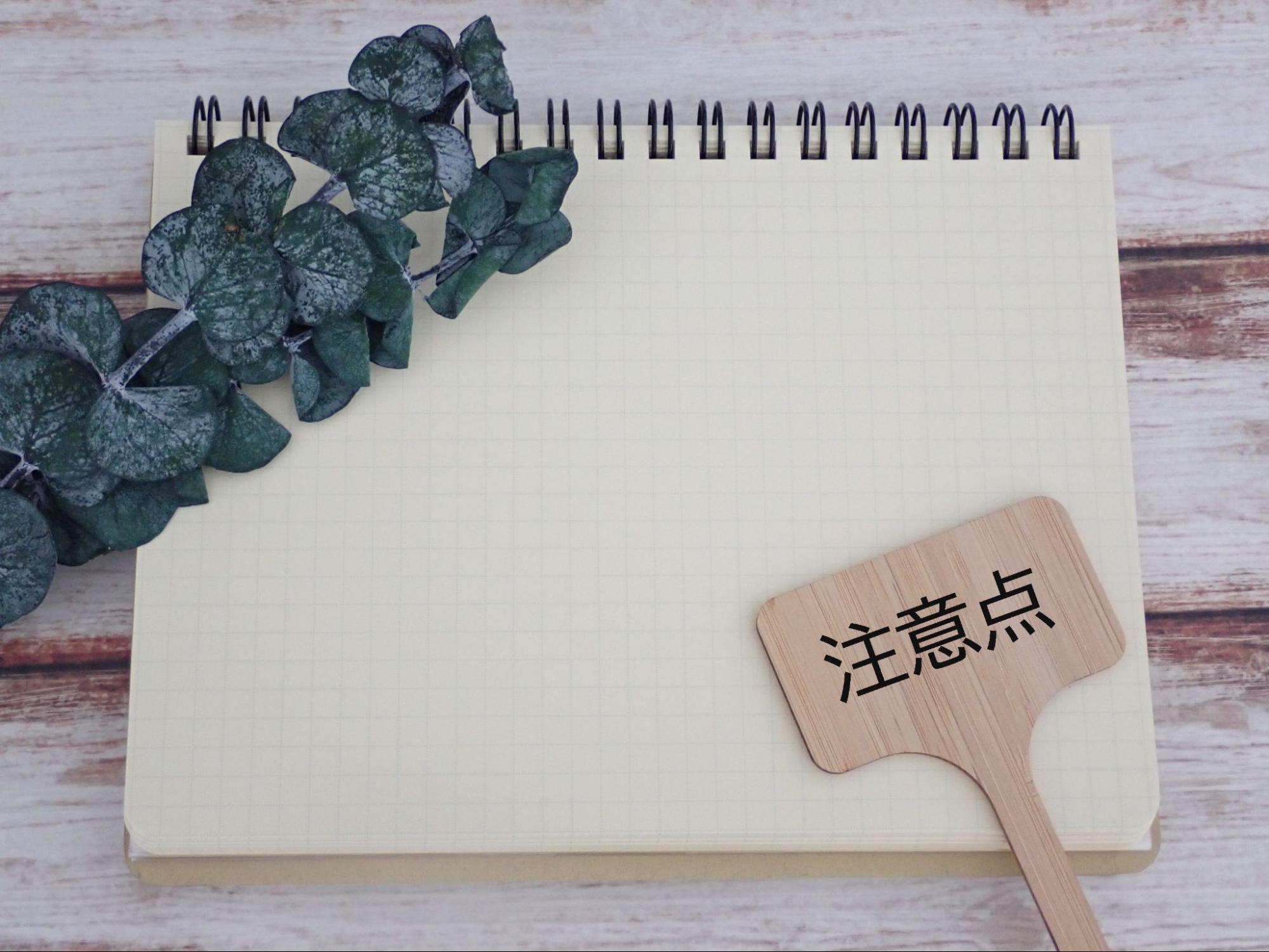
ここでは、個人事業主が融資を受けるときに注意すべきポイントについて解説します。
自己資金が0だと難易度が上がる
自己資金が全くない状態では、事業に対する経営者のコミットメントが低いと見なされ、融資が認められない可能性が高くなります。
また、自己資金がない場合、返済リスクが高いと判断される可能性もあるため、融資審査の難易度が上がります。
自己資金は事業の実情に合わせて、できる限り準備しておくことが望ましいといえるでしょう。
資金がショートする前に融資を検討する
資金繰りに困ってから融資を検討するのは得策ではありません。
資金がショートした状態では、事業の継続性が危ぶまれるため、融資審査に通過しにくくなります。
そのため、資金需要を予測し、余裕を持って融資を検討することが重要です。計画的に資金調達を行うことで、より有利な条件で融資を受けられる可能性があります。
必要書類はもれなく準備する
融資審査では、各金融機関が定める書類を提出する必要があります。主に以下のような書類の提出が求められます。
- 【提出が求められる書類の一例】
これらの書類準備に不備があると、審査が進まず、融資が遅れる可能性があります。
信用力を低下させる要因にもなるため、必要書類はもれなく準備することが大切です。
「起業の窓口」の特集ページ「AI×起業」では、AIを活用して事業計画書を簡単に作成する方法を紹介!
詳しくは「【できるのか?】ChatGPTを使ってたった1時間で事業計画書を書くアラフォー起業家。《小説「AI起業」シリーズ#01》」をご覧ください。
私的流用は絶対に行わない
融資金はあくまでも事業目的で使用するものであり、私的流用は厳禁です。
融資金を個人的な用途に使用した場合、資金使途違反とみなされ、今後の融資が受けられなくなる可能性があります。場合によっては、一括返済を求められることもあるでしょう。
そのため、融資金の使途は事業計画に沿ったものに限定し、適切に管理することが求められます。
融資金の私的流用は、個人事業主にとって致命的なリスクとなりうるため、絶対に避けなければなりません。
個人事業主の融資に関するよくある質問

融資申請を検討している個人事業主から寄せられる疑問や不安について、実務的な観点から詳しく解説します。
開業したばかりでも融資を受けられる?
開業直後でも借入制度によっては融資を受けることが可能です。
たとえば、日本政策金融公庫の「新規開業・スタートアップ支援資金」であれば、新規事業者でもまとまった融資を受けられる可能性があります。
条件は「新たに事業を始める方または事業開始後おおむね7年以内の方」となっており、最大7,200万円(うち運転資金4,800万円)まで借入可能です。
ただし、申請すれば必ず融資を受けられるとは限らず、事業計画書の完成度が審査の鍵を握ります。
市場分析や競合調査、売上予測の根拠などを具体的に示し、事業の実現可能性を証明することが求められるため、入念な準備が欠かせません。
個人事業主が利用できるローンの種類は?
個人事業主が利用できる融資制度は多岐にわたり、それぞれ特徴や条件が異なるため、事業の状況に応じて最適な選択をすることが重要です。
日本政策金融公庫の「一般貸付」が最も一般的で、金利も低く設定されています。融資限度額は最大7,200万円と大きく、返済期間も最大20年以内と長く設定されているのが特徴です。
一方、ビジネスローンは審査が早く手続きも簡単ですが、金利が高めに設定されているため、短期的な資金需要に適しています。
各制度の特徴を理解し、金利や返済期間、必要書類などを比較検討したうえで申請することが重要です。
個人事業主の融資に担保や保証人は必要?
融資の種類や金額により担保・保証人の要否は変わりますが、最近は無担保・無保証の融資制度も増えています。
先ほど紹介した日本政策金融公庫の「新規開業・スタートアップ支援資金」は、担保や保証人が原則不要で、担当者に希望を詳細に伝えることができます。
担保や保証人不要で融資を受けたい場合、まずは「新規開業・スタートアップ支援資金」の利用を検討してみるとよいでしょう。
ただし、融資額が大きくなると、不動産担保や連帯保証人を求められることが一般的です。
担保提供により金利が優遇されるメリットもあるため、リスクとメリットを天秤にかけて判断する必要があります。
融資の審査にはどのくらい時間がかかる?
融資審査の期間は、一般的に申し込みから実行まで3週間から1ヵ月半程度を見込んでおく必要があります。日本政策金融公庫なら面談から2週間程度で結果が出ることが多いです。
民間金融機関の場合、信用保証協会の審査も含めると1ヵ月以上かかることもあり、急ぎの資金需要には対応が難しいケースもあります。
ビジネスローンなら最短即日から3営業日程度で融資実行される商品もあるため、緊急時には有効な選択肢となるでしょう。
なお、融資の審査は書類に不備があると止まってしまうため、事前確認を徹底することが期間短縮のポイントです。決算期や年度末は申し込みが集中し、通常より時間がかかる傾向にあります。
複数の金融機関に同時に融資を申し込んでも大丈夫?
複数の金融機関への同時申込は可能ですが、複数申込は審査落ちのリスクを上げる可能性があるため、本命の金融機関を1つに決めて申し込むのが賢明です。
同時申込により審査期間を短縮し、より良い条件の融資を選択できるメリットがある一方で、「資金繰りが相当厳しいのでは」という印象を与えるリスクがあります。
多くても2〜3行程度に留め、本命の金融機関を明確にしておくことが重要です。
複数申込を行う場合は、正直に他行への申込状況を伝えることが信頼関係構築の基本となります。隠していても信用情報機関への照会で判明するため、虚偽申告は信用失墜に繋がります。
確定申告書の赤字が続いていても融資は受けられる?
赤字の理由や今後の改善見込みを明確に説明できれば、融資を受けられる可能性はゼロではありません。既に改善傾向が見られる場合は、前向きに検討してもらえることがあるのです。
事業計画書で黒字転換への具体的な道筋を示し、月次試算表で直近の業績改善を証明することが重要です。
不動産などの十分な担保があれば、民間金融機関でも融資を受けられる可能性が高まります。ただし、金利は高めに設定され、返済期間も短くなることが一般的です。
個人事業主が融資以外で資金を調達する方法

融資以外にも個人事業主が活用できる資金調達手段は複数存在します。ここでは、代表的な資金調達方法を4つ紹介します。
自治体の補助金・助成金制度
各自治体が実施する補助金・助成金は返済不要の資金として魅力的で、創業支援から販路開拓、設備投資まで幅広い用途に活用できる制度が用意されています。
ただし、申請期間が限定されており、競争率も高いのが実情です。
採択されるためには、事業の社会貢献性や地域経済への波及効果を明確にアピールする必要があり、申請書類の作成には相当の労力が必要となります。
採択後も実績報告や会計検査への対応など、事務負担は決して軽くありませんが、資金面でのメリットは大きいといえるでしょう。
クラウドファンディング
不特定多数から資金を募るクラウドファンディングは、資金調達と同時にマーケティング効果も期待できる新しい手法として注目されています。
購入型なら支援者へのリターンは商品やサービスで済むため、借入のような返済負担がありません。また、SNSでの拡散により、新規顧客の獲得やファン作りにも繋がります。
ただし、目標額に達しない場合は1円も受け取れないAll or Nothing方式が一般的で、プラットフォーム手数料として集めた金額の10〜20%が差し引かれます。
リターンの発送や支援者への報告など、プロジェクト終了後の対応も重要です。
ファクタリング
ファクタリングとは、企業が持つ売掛債権をファクタリング事業者に買い取ってもらい、手数料が差し引かれた金額を期日前に受け取れるサービスのことです。
融資とは異なり借入にならないため、信用情報機関への影響を避けながら資金調達できる点が大きなメリットです。
審査は売掛先の信用力が重視されるため、赤字決算でも利用可能です。最短即日での現金化も可能で、急な資金需要にも対応できる即効性の高さが魅力となっています。
ただし、手数料は売掛金額の2〜20%と高めに設定されており、継続的に利用すると利益を圧迫する要因となりかねません。
また、悪質な業者も存在するため、利用する際は契約内容を十分に確認することが大切です。
家族や知人からの借り入れ
金利負担が少なく柔軟な返済条件で資金調達できる方法として、家族や知人からの借り入れが挙げられます。審査もなく迅速に資金を得られる点が大きなメリットです。
しかし、金銭トラブルが人間関係の破綻に繋がるリスクもあるため、たとえ身内でも借用書を作成し、返済条件を明確にすることが不可欠となります。
贈与税の対象とならないよう、金利を設定して返済実績を残すことも重要です。
年間110万円を超える借入は贈与とみなされる可能性があるため、税務上の取り扱いにも注意が必要となります。
【まとめ】個人事業主の融資活用は準備と計画が成功への鍵!
個人事業主は、日本政策金融公庫や銀行、信用金庫、ノンバンクなどで融資を受けることができます。
融資を活用すれば事業拡大や設備投資が可能となり、返済実績により信用力も向上しますが、利息負担や管理の手間、将来の審査への影響などデメリットも存在します。
融資以外にも補助金・助成金、クラウドファンディング、ファクタリングなど多様な資金調達手段があるため、ご自身の事業状況に合わせて最適な方法を選択することが重要です。
個人事業主向けの融資をお探しの場合は、日本政策金融公庫や地域の金融機関への相談をご検討ください。
「起業の窓口」では、個人事業主の方々に向けて、業務効率化のヒントや成功事例、最新のビジネス情報など、お役立ち情報を提供しています。
ぜひ、「個人事業主」に関する他の記事もご覧ください。
起業や開業、独立に興味を持ったら、まずは「起業の窓口」に登録してみよう!
「起業の窓口」では、起業に必要なノウハウや成功者のインタビューなど、さまざまなコンテンツを完全無料で提供しています。
会員特典として、起業・経営支援のプロ「V-Spirits」が監修するオリジナル冊子『会社設立完全ガイド』を無料プレゼント。さらに、V-Spritsによる1時間の無料起業相談や、GMOインターネットグループが展開するビジネスの立ち上げや拡大に役立つ各種サービスをおトクな特典付きでご紹介します。
あなたの夢の実現を全力でサポートします!
- 記事監修
-
- 中野 裕哲 HIROAKI NAKANO
- 起業コンサルタント(R)、経営コンサルタント、税理士、特定社会保険労務士、行政書士、サーティファイドファイナンシャルプランナー・CFP(R)、1 級FP 技能士。 V-Spiritsグループ創業者。東京池袋を本拠に全国の起業家・経営者さんを応援!「あの起業本」の著者。著書16冊、累計20万部超。経済産業 省後援「DREAMGATE」で11年連続相談件数日本一。
- ※本記事は、起業の窓口編集部が専門家の監修または独自調査(アンケート)に基づいて制作したものです。
- ※掲載している情報は、記事公開時点の法令・税制・商品・サービス等に基づくものであり、将来的に変更される可能性があります。
- ※アンケート調査に関する記述は、特定の調査対象者からの回答結果および編集部の見解を含んでおり、内容の正確性・完全性を保証するものではありません。
- ※記事の内容は一般的な情報提供を目的としており、すべての方に当てはまるものではありません。個人の状況に応じた具体的な助言が必要な場合は、専門家にご相談ください。
- ※情報の利用や判断、実施については、ご自身の責任で行っていただきますようお願いいたします。
- ※本記事に掲載された内容の転載・複製はご遠慮いただき、引用の際は必ず出典をご明記ください。



 シェア
シェア





























