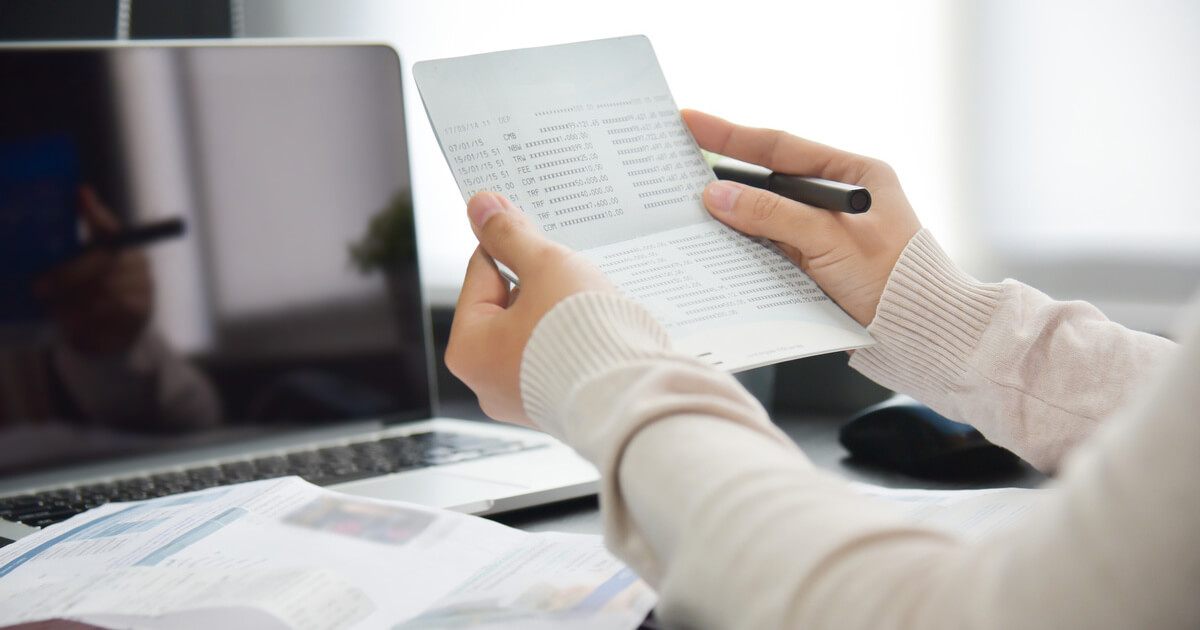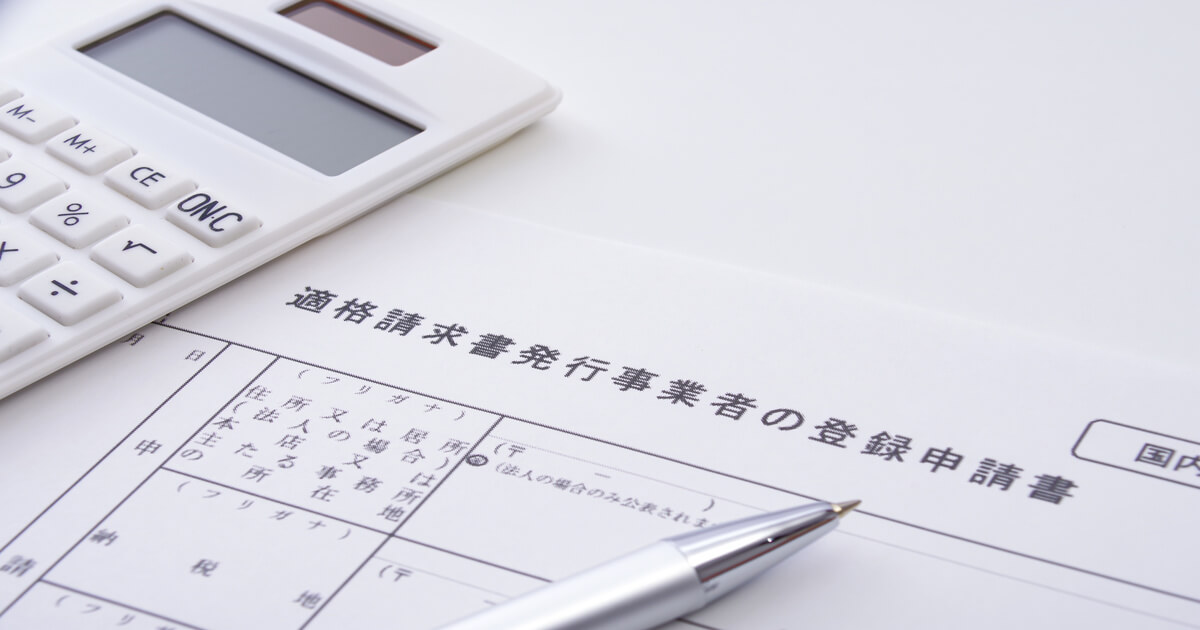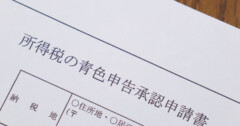個人事業税は経費として計上できる?経費計上時の勘定科目や計算方法、納付方法を解説

個人事業税は、事業所得が290万円を超える個人事業主に課税される地方税の1つです。対象業種や税率は法定業種によって異なり、計算方法も定められています。
個人事業税は経費として計上でき、適切な勘定科目で処理する必要があります。
節税のためには、家事按分や経費とプライベート支出の明確な区分など、きめ細やかな支出管理が欠かせません。
申告は原則不要ですが、納付方法は納付書や口座振替、クレジットカードなど、いくつかの選択肢があります。
この記事では、個人事業税の概要や計算方法、経費計上時の留意点、節税に繋がる支出管理のコツ、納付方法について詳しく解説します。
- 【この記事のまとめ】
- 個人事業税は、事業所得が290万円を超える個人事業主に課される地方税です。70種類の法定業種が対象で、業種区分に応じて税率が異なります。
- 個人事業税は租税公課として経費計上が可能です。節税には、家事按分の適切な実施や経費とプライベート支出の明確な区分が欠かせません。
- 納付方法は、納付書や口座振替、クレジットカード、電子納付など複数の選択肢があり、一定の条件を満たせば、控除や減免が適用される場合もあります。
個人事業税とは

個人事業税は地方税の1つに分類される税金で、各都道府県に対して納付します。事業をするうえで、行政サービスを利用することから、その経費を負担するために作られた税金です。
全ての個人事業主に納税義務があるわけでなく、法定業種や事業所得金額が290万円を超える個人事業主が対象になった税金です。
法定業種の70業種には、多くの業種が含まれており、業種ごとに区分や税率も異なります。
対象業種に該当しない場合は、事業税の課税はない
個人事業税が対象になる業種は、法律で70業種に分類された法定業種があり、個人事業主のほとんどが対象になるといわれています。
70業種に区別されない事業者は、個人事業税を支払う必要はありません。
また、個人事業税に対しては青色申告であっても青色申告特別控除が適用されません。ただし、事業主控除の290万円があるため、原則所得が290万円を超えない限り、納税義務は発生しないことになってます。
個人事業税の課税対象となる法定業種と税率
法定業種の70業種と区分、税率は以下の通りです。
| 区分 | 税率 | 法定業種の種類 |
|---|---|---|
| 第1種事業
(37業種) |
5% | 物品販売業、運送取扱業、料理店業、遊覧所業、保険業、船舶定係場業、飲食店業、商品取引業、金銭貸付業、倉庫業、周旋業、不動産売買業、物品貸付業、駐車場業、代理業、広告業、不動産貸付業、請負業、仲立業、興信所業、製造業、印刷業、問屋業、案内業、電気供給業、出版業、両替業、冠婚葬祭業、土石採取業、写真業、公衆浴場業(むし風呂等)、電気通信事業、席貸業、演劇興行業、運送業、旅館業、遊技場業 |
| 第2種事業
(3業種) |
4% | 畜産業、水産業、薪炭製造業 |
| 第3種事業
(30業種) |
5% | 医業、公証人業、設計監督者業、公衆浴場業(銭湯)、歯科医業、弁理士業、不動産鑑定業、歯科衛生士業、薬剤師業、税理士業、デザイン業、歯科技工士業、獣医業、公認会計士業、諸芸師匠業、測量士業、弁護士業、計理士業、理容業、土地家屋調査士業、司法書士業、社会保険労務士業、美容業、海事代理士業、行政書士業、コンサルタント業、クリーニング業、印刷製版業 |
| 3% | あんま・マッサージ又は指圧・はり・きゅう・柔道整復、その他の医業に類する事業、装蹄師業 |
税務署にて、個人事業主の開業届を提出した際の事業内容によって業種が決定します。
第1種事業(37業種)・第2種(3業種)・第3種(30業種)に分類され、多くの個人事業主が適合します。ただし、例外として漫画家・作家・執筆業(ライター)などは法定業種に該当しません。
もし、開業した業種が不明だったり、業種が70業種の中になかったりする場合は、管轄の都道府県にある都道府県税事務所に確認しましょう。
個人事業税の計算方法
個人事業税の計算式は以下の通りです。
1月1日〜12月31日の1年間で得た、事業所得および不動産所得の合計から計算します。
また、確定申告の内容によっては、雑所得も対象になる場合があります。雑所得が加算される場合や計算が難しい場合は、管轄の都道府県税事務所に相談して正確な金額を納税するようにしてください。
個人事業税は経費として計上できる

個人事業税は事業を営むうえで必要な出費になるため、経費計上が可能です。
経費計上をする前に、自分が営む業種は法定業種にあたるかどうか、その場合の税率は何%か、事前にチェックするようにしましょう。
個人事業税の仕訳と勘定科目
確定申告時に個人事業税の仕訳は、租税公課と普通預金もしくは現金で計上します。
仕訳は借方勘定に租税公課と納税金額、貸方勘定に普通預金(現金)と納税金額です。
| 借方勘定 | 貸方勘定 | ||
|---|---|---|---|
| 勘定科目 | 金額 | 勘定科目 | 金額 |
| 租税公課 | 150,000 | 普通預金 | 150,000 |
※納税金額を150,000円と仮定
この記載方法はあくまで一例であり、支払い方法に合わせて勘定科目を正しく変更する必要があります。
個人事業税の節税に重要となる支出管理のやり方

必要以上の納税を避けるためには、 個人事業税の計算を正しく行う必要があります。ここでは、個人事業税の節税に重要となる支出管理の方法について解説します。
適切に家事按分する
自宅の一部を事務所として利用している個人事業主は、家賃や光熱費などの支出を適切に按分し、事業で使用した分のみを経費計上する必要があります。これを家事按分といいます。
家事按分には明確なルールはありませんが、合理的で客観性のある基準を設けることが重要です。
つまり、第三者が見て納得できる理由や根拠を示す必要があるのです。
例えば、家賃10万円の3LDK(約80㎡)の自宅で、8畳(約13㎡)の部屋を仕事用として使用する場合、家賃全体の約16%(13÷80)にあたる1万6,000円を事業用経費として計上します。
適正な家事按分は、個人事業税の節税に繋がるだけでなく、経理の透明性を高めるうえでも非常に重要です。自宅のどの部分をどの程度事業に使用しているか、日頃から意識しておくとよいでしょう。
なお、家事按分の詳細については以下の記事で解説しています。
経費とプライベート支出を明確に分ける
個人事業主が経費として認められるのは、あくまで事業に関連した支出のみです。私的な支出を経費に混在させると、帳簿が混乱し、確定申告でのトラブルにも繋がりかねません。
「可能な限り節税対策を行いたい」という考え方は大切ですが、経費とプライベート支出を明確に分け、適切に支出管理する必要があります。
経費とプライベートの支出を分けるには、事業専用の口座やクレジットカードを用意するのが効果的です。
例えば、事業用のクレジットカードを作り、業務に関する支払いは全てそのカードで行うように徹底すれば、支出管理が容易になります。
一方で、現金払いの場合、プライベートな支出と混同しやすいというデメリットがあります。支出管理の手間を省くためにも、経費の支払いはなるべく法人カードを活用するとよいでしょう。
経費計上の際には、支払い金額を証明する領収書やレシートなどの書類が必要です。
支払い時に受け取った領収書等は、記載内容に不備がないかその場で確認し、必要な情報が不足している場合はすぐに追記しておきます。これにより、後の帳簿付けがスムーズになります。
個人事業税の申告方法と申告時期
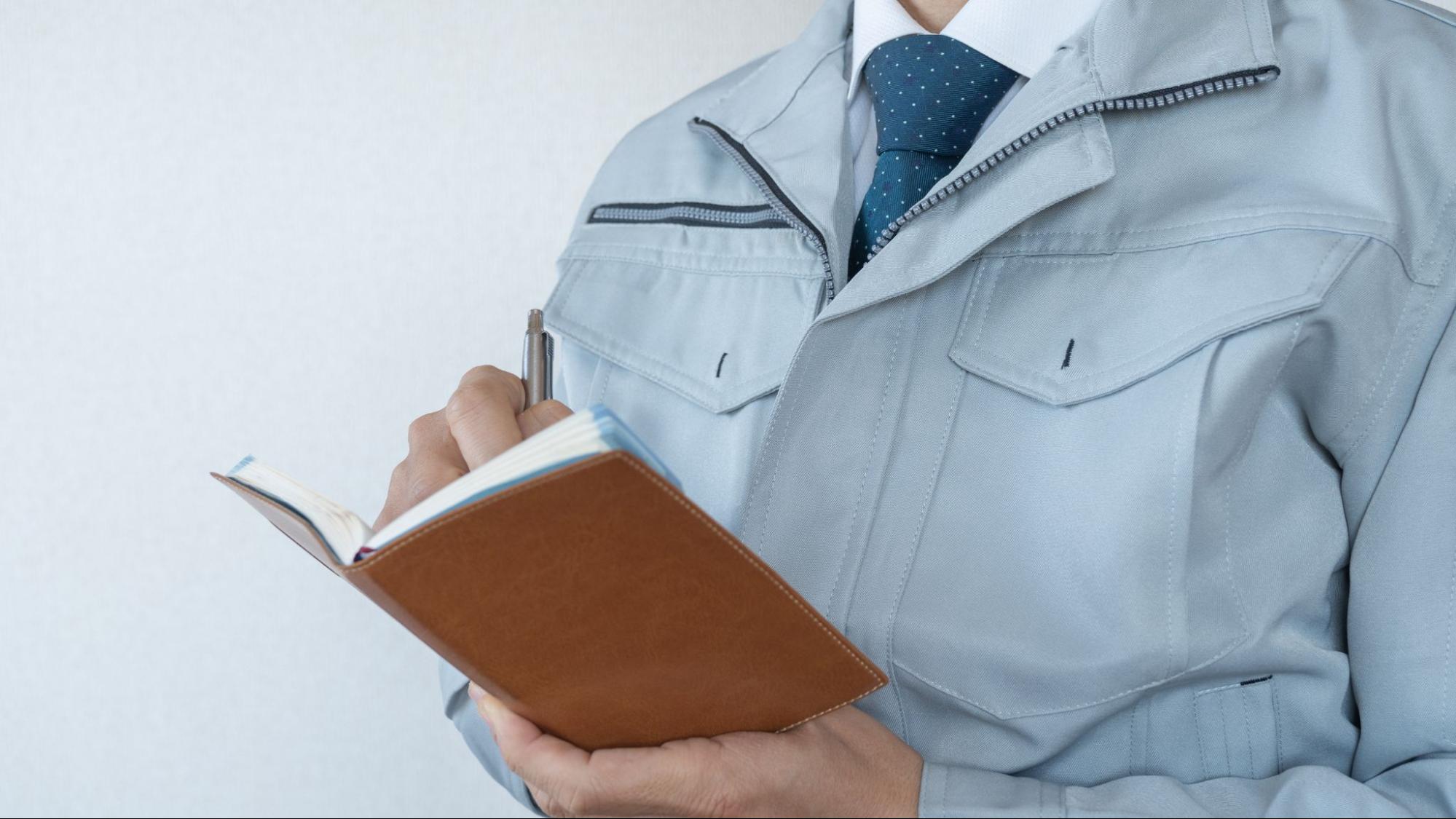
原則、個人事業主で確定申告をした方は、別途個人事業税の申告の必要はありません。
一方、確定申告をしていない個人事業主は、毎年3月15日までに前年の事業所得などを、事業所所在地の都道府県税事務所に申告する義務があります。
年の途中で事業を廃止した場合は、所得税の確定申告とは別に、廃止日から1ヶ月以内(死亡による廃止の場合は4ヶ月以内)に個人事業税の申告が必要です。
申告の際は、所定の申告書に必要事項を記入し、都道府県税事務所に提出します。
確定申告または個人事業税の申告を行うと、通常8月に税額を記載した納税通知書が送付されます。ただし、課税対象外の業種や所得金額が290万円以下で納税の必要がない場合は、通知されません。
個人事業税の申告は、事業主ご自身で行うことが基本ですが、税理士に依頼することもできます。申告手続きに不安がある場合は、専門家に相談するのも1つの方法です。
個人事業税の納付方法

個人事業税の支払いは確定申告後に送付される納付書や、口座振替、クレジットカード、電子納付などで納税が可能です。
個人事業税の納付時期は、原則8月と11月の年2回です。
各都道府県によって納付書の発行タイミングには多少の誤差があるため、納付書が届かない場合は役所に確認しましょう。ここでは、個人事業税の納付方法を解説します。
| 納付方法 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 納付書と現金 |
|
|
| 口座振替 |
|
|
| クレジットカード |
|
|
| 電子納付 |
|
|
| 窓口 |
|
|
| 決済アプリ |
|
|
1:納付書と現金で支払う
確定申告後に送付される納付書を使って現金で支払うのが、一般的な支払い方法です。
個人事業税の支払い対象者であれば、8月頃に各都道府県から納付書が送られてきます。
納付書はコンビニエンスストアや金融機関の窓口で支払えるようになっているため、納付書と現金を用意して支払ってください。
ただし、コンビニエンスストアの場合、納税額が30万円以下でなければ支払いができません。必ず金額を確かめたうえで、納付書の利用を検討しましょう。
2:口座振替で支払う
口座振替は、指定の口座から自動で納付する方法です。
自身が引き落としを希望する銀行へ行き、口座振替依頼書(自動払込利用申込書)に必要事項の記入と押印のうえ、銀行もしくは最寄りの県税事務所で提出してください。
各都道府県によって対応している銀行が異なるため、県内の取扱金融機関の各店舗や郵便局、県税事務所などで口座振替依頼書(自動払込利用申込書)を受け取ってください。
支払い忘れが起こりづらいのがメリットではありますが、残高不足だと未納になる恐れがあります。
気付かないうちに延滞金が発生する可能性もあるため、必ず引き落としが完了したかどうかを確認しましょう。
3:クレジットカードで支払う
個人事業税はクレジットカードでも支払うことが可能です。
ただし、個人事業税は国税ではなく地方税になるため、各都道府県の自治体によっては対応していない場合や使用するクレジットカード会社に制限がある場合があります。
例えば、東京都で利用できるカードブランドは、VISA・MasterCard・JCB・AmericanExpress・Diners Club.TS CUBIC CARDです。
クレジットカード払いのメリットは24時間支払い可能で、締め日によっては支払いを遅らせることが可能な点です。
デメリットは納税できる金額は100万円未満のみという制限があり、手数料がかかります。
4:電子納付で支払う
地方税を支払う専用サイトeLTAX(エルタックス)を利用すれば、ダイレクト納付・インターネットバンキングを利用して、個人事業税を納付することが可能です。
eLTAXとは、地方税の申告や納税をインターネット上で行えるポータルシステムのことです。
「electronic(電子)」と「Local(地方)」の頭文字にTAX(税金)を合わせた造語で、申告手続きと関連性の高い申請・届出手続き、納付手続きなど、さまざまな処理を行えます。
eLTAXからのダイレクト納付では、口座振替になるため手数料がかからないメリットがあります。
一方で、事前に利用届出が必要であったり、納税用口座の登録が必要であったりとデメリットもあるため注意が必要です。
もし興味のある方はeLTAX(エルタックス)公式サイトをご確認ください。
5:窓口で直接支払う
個人事業税を窓口で直接支払う方法は、わかりやすいのが特徴です。行政窓口に直接出向き、その場で現金で納付します。
納付書を持参し、窓口で手続きを行うだけなので、操作に不安がある方でも安心して納付できるでしょう。
ただし、支払いのたびに行政窓口まで足を運ばなければなりません。時間的な拘束や移動の手間を考慮する必要があるため、忙しい個人事業主にとっては若干の負担になるでしょう。
また、現金での支払いになるため、多額の現金を用意したり、支払い後の手元資金が一時的に減ったりするデメリットもあります。
窓口での直接支払いは、納付方法として一般的な選択肢ですが、オンラインで完了する他の手段よりも利便性は低いです。
6:決済アプリで支払う
スマートフォンの決済アプリを使って個人事業税を支払う方法もあります。時間と手間を大幅に省けるのが魅力です。
個人事業税の納付書にはバーコードが記載されており、このバーコードを決済アプリで読み込むことで納付が完了します。
決済手数料も発生しないため、クレジットカード払いと比べてコストを抑えられるのもポイントです。
ただし、納付書を利用した支払いは、原則30万円以下とされています。一部の自治体では10万円超の支払いにも対応していないケースがあるため、高額納付の際は特に注意が必要です。
また、決済アプリを利用した場合、領収書が発行されません。個人事業税を経費として計上する際は、納付の事実を証明する書類が必要になるため、別途、納税証明書などを取得する必要があります。
決済アプリでの支払いは、手軽で効率的な反面、高額納付への対応や証明書類の取得など、一定の制約があることを理解しておきましょう。
個人事業税が控除となる4つのケース

ここでは、個人事業税が控除もしくは該当しない場合について解説します。
法定業種以外の業種に該当する場合
法定業種の70種以外の業種に該当する場合、個人事業税の対象にはなりません。
例えば、漫画家・作家・執筆業(ライター)・システムエンジニア・プログラマーなどが個人事業税の対象外です。ただし、業務内容によっては請負業と判断され、課税されてしまうケースもあります。
また、漫画家などの場合、デザイン業の要素が業務に含まれると、課税対象になる場合もあるため、管轄の都税事務所や県税事務所で法定業種の確認をしておきましょう。
事業所得が290万円以下の場合
個人事業主には、290万円の事業主控除があるため、原則所得が290万円を超えない限り納税義務はありません。
また、営業開始から1年未満の場合は月割額で控除されます。期間ごとの事業主控除額は以下の通りです。
| 期間 | 事業主控除額 |
|---|---|
| 1ヶ月 | 24万2,000円 |
| 2ヶ月 | 48万4,000円 |
| 3ヶ月 | 72万5,000円 |
| 4ヶ月 | 96万7,000円 |
| 5ヶ月 | 120万9,000円 |
| 6ヶ月 | 145万円 |
| 7ヶ月 | 169万2,000円 |
| 8ヶ月 | 193万4,000円 |
| 9ヶ月 | 217万5,000円 |
| 10ヶ月 | 241万7,000円 |
| 11ヶ月 | 265万9,000円 |
| 12ヶ月 | 290万円 |
過去3年の赤字の繰り越しがある場合
過去3年の赤字繰り越しがある場合、赤字分が所得の控除となります。
個人事業主は、事業所得が純損失で赤字経営になった場合、翌年以降3年間は繰越控除が可能です。本年度が黒字経営だったとしても、前年度が赤字経営であれば、純利益分を相殺して収入を下げることができます。
結果的に、利益を相殺して収入が290万円以下になれば個人事業税の納税義務がなくなります。
その他の繰越控除がある場合
被災事業用資産の損失の繰越控除がある場合も、損失の金額を所得から控除可能です。
白色申告事業者は、自然災害(震災・水害・風害・火災など)によって生じた、事業用資産の破損や故障による損失金額を翌年以降3年間は繰越控除可能です。
また、直接事業の用に供する資産(土地、家屋などを除く、機械、装置、車両など)を譲渡したことによって被った損失に対する譲渡損失の控除と繰越控除もあります。
こちらは青色申告をしている人が対象で、翌年以降3年間は繰越控除可能です。
減免が受けられる個人事業税減免制度とは?

個人事業主の方で、障がいを持つ事業主や扶養家族に障がい者がいる場合に、個人事業税減免制度を受けられます。
ここでは、減免が受けられる個人事業税減免制度の詳細を解説します。
自治体によって条件が異なる
個人事業税減免制度は、各都道府県の自治体によって金額や内容が異なります。
身体的障がいだけでなく、精神障がいの場合、免税額が大幅に増えるだけでなく、条件次第で2つの制度を併用できるケースもあります。
例えば、東京都の場合、障がい者1人につき5,000円の減税対象です。詳しい要件については管轄の都道府県税事務所にご確認ください。
個人事業税減免制度の対象となる主なケース
個人事業税には、各都道府県の自治体が定める一定条件や自然災害によって被害を被った被災者を対象とした個人事業税減免制度が制定されています。
自然災害の場合は、災害の規模や被害を受けた程度によって内容が異なるため、管轄の都道府県税事務所に確認してください。
災害などで損害を受けた場合
例えば熊本県では、台風等の災害の影響で被災者の復興を支援する目的から免税処置が設けられています。
前年の事業所得が1,000万円以下であり、災害により事業用資産にその価格の2分の1以上の損害を受けた場合が対象です。
免税額は事業所得の金額ごとに区別され、500万以下の場合100%減免・500万超え750万円以下の場合50%減免・750万超え1,000万円以下の場合25%減免と制定されました。
自然災害等で事業継続が困難な場合は、各都道府県の減免措置を確認しましょう。
生活保護法による生活扶助を受けている場合
例えば神奈川県では、生活保護法の規定により生活扶助を受けている場合、税額の全額が減免されます。
また、富山県でも生活保護法の規定により生活扶助を受けている方は、申請により個人事業税が減免される場合があります。
この申請には、減免申請書と福祉事務所の長が発行する生活扶助を受けている証明書が必要です。
納税者または扶養親族が障害者の場合
減免制度が対象になるケースは以下の通りです。
- 1年間の合計所得金額が一定額(300万から400万円)以下であること
- 納税者、または扶養親族等が障がいのある人であること
原則、障がい者手帳が1級〜4級になる人が対象ですが、精神障がいや知的障がいの場合には各都道府県で判断も変わってきます。
対象となる人は、公的に障がい者を証明する資格を取得している人がほとんどです。
その他の場合
神奈川県では、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に規定する生活支援給付を受けている場合には、全額の減免が認められています。
中国残留邦人等とは、日本が戦争中に中国に住んでいた中国人が戦後の混乱の中で幼くして肉親と離別し、身元を知らないまま成長したり、生活手段を失い中国に留まったりして中国で生活してきた人たちを指します。
まとめ
この記事では、個人事業税の概要や計算方法、経費計上時の留意点、納付方法について詳しく解説しました。
個人事業税は、事業所得が290万円を超える個人事業主に課される地方税です。70種の法定業種が対象となり、業種区分によって税率が異なります。
個人事業税は租税公課として経費計上が可能であり、節税のためには家事按分の適切な実施や、経費とプライベート支出の明確な区分が重要となります。
原則、確定申告をすれば個人事業税の申告は不要です。納付方法には、納付書や口座振替、クレジットカード、電子納付など複数の選択肢があります。
個人事業税には、一定の要件を満たせば控除や減免を受けられるケースもあります。制度の詳細は自治体によって異なるため、管轄の都道府県税事務所に確認しましょう。
「起業の窓口」では、個人事業主の方々に向けて、業務効率化のヒントや成功事例、最新のビジネス情報など、お役立ち情報を提供しています。
ぜひ、「個人事業主」に関する他の記事もご覧ください。
起業や開業、独立に興味を持ったら、まずは「起業の窓口」に登録してみよう!
「起業の窓口」では、起業に必要なノウハウや成功者のインタビューなど、さまざまなコンテンツを完全無料で提供しています。
会員特典として、起業・経営支援のプロ「V-Spirits」が監修するオリジナル冊子『会社設立完全ガイド』を無料プレゼント。さらに、V-Spritsによる1時間の無料起業相談や、GMOインターネットグループが展開するビジネスの立ち上げや拡大に役立つ各種サービスをおトクな特典付きでご紹介します。
あなたの夢の実現を全力でサポートします!
- 記事監修
-
- 中野 裕哲 HIROAKI NAKANO
- 起業コンサルタント(R)、経営コンサルタント、税理士、特定社会保険労務士、行政書士、サーティファイドファイナンシャルプランナー・CFP(R)、1 級FP 技能士。 V-Spiritsグループ創業者。東京池袋を本拠に全国の起業家・経営者さんを応援!「あの起業本」の著者。著書16冊、累計20万部超。経済産業 省後援「DREAMGATE」で11年連続相談件数日本一。
- ※本記事は、起業の窓口編集部が専門家の監修または独自調査(アンケート)に基づいて制作したものです。
- ※掲載している情報は、記事公開時点の法令・税制・商品・サービス等に基づくものであり、将来的に変更される可能性があります。
- ※アンケート調査に関する記述は、特定の調査対象者からの回答結果および編集部の見解を含んでおり、内容の正確性・完全性を保証するものではありません。
- ※記事の内容は一般的な情報提供を目的としており、すべての方に当てはまるものではありません。個人の状況に応じた具体的な助言が必要な場合は、専門家にご相談ください。
- ※情報の利用や判断、実施については、ご自身の責任で行っていただきますようお願いいたします。
- ※本記事に掲載された内容の転載・複製はご遠慮いただき、引用の際は必ず出典をご明記ください。



 シェア
シェア