免税事業者のインボイス制度【完全ガイド2025】影響・やるべきこと・損しない対策を税理士が徹底解説!

結論として、インボイス制度は免税事業者のあなたに大きな影響を与えますが、制度を正しく理解し、ご自身の状況に合わせて適切な対策を講じれば、不利になることなく事業を継続できます。
この記事では、制度の基本から具体的な対応策、そして賢く活用できる有利な選択肢まで、専門用語をできるだけ使わずに分かりやすく解説します。
- 【この記事のまとめ】
- インボイス制度が免税事業者に与える具体的な影響と、今すぐ確認すべきこと
- 「課税事業者になるべきか?」「免税のままか?」あなたの状況に合わせた最適な選択肢
- 負担を軽減する「2割特例」や「経過措置」の活用法と、正しい請求書の書き方
- インボイス制度とは?免税事業者に何が変わるの?
- インボイス制度のキホン:「適格請求書」って何?なぜ必要なの?
- 免税事業者が直面する3つの大きな変化
- 「適格請求書発行事業者」の登録は必須?メリット・デメリットは?
- 【最重要】免税事業者の2つの選択肢:課税事業者になるか、免税のままでいるか
- パターン1:思い切って「課税事業者」になる!メリット・デメリットと判断基準
- パターン2:これまで通り「免税事業者」を続ける!メリット・デメリットと注意点
- 【ケーススタディ】私はどっちを選ぶべき?あなたの状況に合わせた選択シミュレーション
- 賢く活用!免税事業者が使えるインボイス制度の負担軽減策
- 仕入税額控除の「経過措置」とは?いつまで使える?
- 【大注目!】「2割特例」で納税額を大幅カット!対象者・期間・計算方法を徹底解説
- その他の支援策・補助金はある?(2025年最新情報)
- インボイス制度開始後の請求書はどう変わる?免税事業者のための請求書作成ガイド
- パターン1:課税事業者になった場合の「適格請求書(インボイス)」の書き方
- パターン2:免税事業者のままの場合の請求書の書き方と取引先への伝え方
- 【独自視点】免税事業者がインボイス制度で本当に注意すべき3つのポイント
- ポイント1:取引先との関係維持:価格交渉や契約見直しの可能性と対策
- ポイント2:意外と見落としがち?独占禁止法・下請法との関連
- ポイント3:最新情報を常にキャッチアップ!制度変更や解釈の確認方法
- 【Q&A】免税事業者のインボイス制度に関するよくある質問
- Q. 売上が1000万円以下でも課税事業者になるべき?
- Q. 適格請求書発行事業者の登録申請はいつまでに、どうやってすればいい?
- Q. 取引先からインボイス対応のために値下げを要求されたら、どうすればいい?
- Q. インボイス制度に対応できるおすすめの会計ソフトは?
- Q. 免税事業者のままでも、消費税を請求書に書いていいの?
- まとめ:インボイス制度は怖くない!正しい知識で賢く対応しよう
- 【おさらい】免税事業者がインボイス制度で押さえるべき最重要ポイント
- 不安な場合は一人で悩まず専門家へ相談を
「確定申告」の期間は毎年2月16日から3月15日です。
「起業の窓口」では、確定申告の方法、青色申告や白色申告の基礎知識、手続きの流れ、節税のコツなどを詳しく解説しています。
ぜひ、「確定申告」に関する他の記事もご覧ください。
2024年11月1日より、フリーランス保護法が施行されます。
組織に所属せずに働くフリーランスが安心して働ける環境を整備するために、フリーランスと企業などとの発注事業者間の取引の適正化(契約書等により取引条件を明示する)が主な目的です。
詳しくは次の記事をご覧ください。フリーランス保護法の概要、制定された背景や具体的な内容などを解説しています。
確定申告を楽にしたいと悩む方へ
インボイス制度とは?免税事業者に何が変わるの?

「インボイス制度って、結局何なの?」
まずは、この基本的な疑問から解消していきましょう。このセクションでは、インボイス制度の概要と、特に私たち免税事業者にどのような影響があるのか、ポイントを絞って分かりやすくご説明します。難しく考えず、まずは全体像を掴んでいきましょう。
インボイス制度のキホン:「適格請求書」って何?なぜ必要なの?
インボイス制度とは、正式には「適格請求書等保存方式(てきかくせいきゅうしょとうほぞんほうしき)」と言います。2023年10月1日から開始された、消費税の仕入税額控除に関する新しいルールです。
これまで、事業者が支払った消費税分を、受け取った消費税から差し引いて納税する「仕入税額控除」を受けるためには、区分記載請求書などの保存が必要でした。しかし、インボイス制度導入後は、原則として「適格請求書(インボイス)」と呼ばれる特定の要件を満たした請求書や領収書がなければ、買い手側は仕入税額控除を受けられなくなります。
なぜこのような制度が導入されたかというと、主に2019年10月から導入された消費税の軽減税率(8%と10%)への対応が背景にあります。複数の税率が存在することで、正確な消費税額の把握と計算が複雑になったため、より厳格な管理方法としてインボイス制度が導入されたのです。
❝ 適格請求書(インボイス)とは、売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。❞
インボイス制度の概要 – 国税庁
つまり、あなたが取引先(買い手)に対して発行する請求書が「適格請求書」でなければ、その取引先は消費税の仕入税額控除を受けられない、ということになります。これが免税事業者にとって大きなポイントとなるのです。
免税事業者が直面する3つの大きな変化
では、インボイス制度によって、私たち免税事業者には具体的にどのような変化が起こるのでしょうか?主に以下の3つの変化が考えられます。
- 取引先(課税事業者)が仕入税額控除を受けにくくなる可能性
- 取引継続や新規取引への影響
- 自身の納税義務や事務負担の発生(課税事業者になった場合)
あなたが免税事業者のままで、適格請求書を発行できない場合、あなたの取引先(課税事業者)は、あなたへの支払いにかかる消費税額を仕入税額控除できなくなります。これは、取引先にとって実質的なコスト増につながる可能性があります。
上記の理由から、取引先が仕入税額控除を重視する場合、適格請求書を発行できない免税事業者との取引を見直したり、新規の取引を控えたりする可能性が出てきます。
適格請求書を発行するためには、「適格請求書発行事業者」として登録し、課税事業者になる必要があります。課税事業者になると、消費税の申告・納税義務が生じ、経理処理や事務作業も増えることになります。
これらの変化を理解することが、今後の対応を考える上での第一歩です。
「適格請求書発行事業者」の登録は必須?メリット・デメリットは?
「それなら、すぐに適格請求書発行事業者に登録すべきなの?」と考える方もいらっしゃるでしょう。
まず、適格請求書発行事業者の登録は任意です。法律で強制されるものではありません。しかし、登録しない場合、前述の通り取引に影響が出る可能性があります。
登録する(つまり課税事業者になる)ことの主なメリットは以下の通りです。
- 【課税事業者になることの主なメリット】
-
- 取引先(課税事業者)が仕入税額控除を受けられるため、取引を継続しやすくなったり、新規の課税事業者との取引が獲得しやすくなったりする可能性があります。
- 一定の条件を満たせば、支払った消費税の方が多い場合に還付を受けられる「消費税の還付申告」が可能になります(輸出業など特定のケースのみ)。
- 【課税事業者になることの主なデメリット】
-
- 消費税の納税義務が発生します。これまで免税だった分の税負担が増えることになります。
- 消費税の計算や申告、適格請求書の作成・保存など、経理や事務の負担が増加します。
- 【課税事業者になるメリット】
-
- 取引の維持・拡大: 最大のメリットは、取引先(特に課税事業者)が仕入税額控除を受けられるため、既存の取引を継続しやすくなる点です。また、インボイス発行を求める新規の課税事業者との取引チャンスも広がります。
- 消費税還付の可能性: 輸出取引が多い場合や、大きな設備投資などで支払った消費税額が受け取った消費税額を上回る場合、消費税の還付を受けられる可能性があります。
- 【課税事業者になるデメリット】
-
- 消費税の納税義務: これまで免除されていた消費税の納税義務が発生します。売上にかかる消費税から仕入れにかかる消費税を差し引いた額を納付する必要があり、資金繰りにも影響が出ます。
- 経理・事務負担の増加: 消費税の計算、帳簿付け、適格請求書の作成・保存、消費税申告書の作成・提出など、経理業務が複雑化し、事務負担が増えます。
- 【課税事業者になるかどうかの判断基準】
-
- 主要な取引先は課税事業者か? 取引先が課税事業者で、インボイスを求めている場合は、登録を検討する余地が大きいです。
- 売上規模はどの程度か? 売上が1,000万円を超えていなくても、取引先の意向で登録を選択するケースは多いです。
- 今後の事業拡大の意向はあるか? 新規に企業との取引を増やしたい場合、登録が有利に働くことがあります。
- 事務処理能力やリソースはどうか? 増加する事務負担に対応できるか、または税理士に依頼するコストも考慮に入れましょう。
- 【免税事業者を続けることの主なメリット】
-
- 消費税の納税義務なし: 引き続き消費税の納税は免除されます。これが最大のメリットと言えるでしょう。
- 事務負担の現状維持: 消費税に関する新たな経理処理や申告業務は発生しません。
- 【免税事業者を続ける主なデメリット】
-
- 取引先からの値下げ交渉や取引停止のリスク: あなたの取引先(課税事業者)は、あなたへの支払いについて仕入税額控除が受けられないため、その分を価格交渉で調整しようとしたり、インボイスを発行できる他の事業者へ乗り換えたりする可能性があります。
- 新規取引先の獲得が難しくなる可能性: 新たに取引を開始しようとする課税事業者が、インボイス発行を条件とする場合があります。
- 【免税事業者を続ける主なデメリット】
-
- 取引先への丁寧な説明: 免税事業者のままでいることを選択した場合、取引先(特に課税事業者)には、なぜその選択をしたのか、そしてインボイスを発行できない旨を丁寧に説明し、理解を求める努力が必要です。
- 価格交渉への備え: 取引先から値下げを要求される可能性も考慮し、自社の提供価値を再確認したり、価格設定を見直したりする必要が出てくるかもしれません。
- 独占禁止法・下請法への意識: 優越的な地位にある取引先から、一方的な取引条件の変更や不当な値下げを強要された場合は、独占禁止法や下請法に抵触する可能性があります。
- フリーランスデザイナーAさん
- 個人向けオンラインレッスンのBさん
- 複数の小規模店舗に商品を卸しているCさん
- この経過措置の適用を受けるためには、以下の対応が必要です。
- 区分記載請求書等と同様の事項が記載された請求書等の保存。
- 経過措置の適用を受ける旨(80%控除対象など)を記載した帳簿の保存。
- インボイスを機に免税事業者からインボイス発行事業者(課税事業者)になった方
- 基準期間(前々事業年度)の課税売上が1,000万円以下の要件を満たす小規模事業者
- 免税事業者がインボイス発行事業者の登録を受けて課税事業者となった場合。
- 課税事業者選択届出書を提出して課税事業者となった場合で、登録日が令和5年10月1日~令和9年9月30日までの日の属する課税期間中である場合など、いくつかのパターンがあります。詳細は国税庁の情報を確認してください。
- 通常(本則課税)の場合:
売上消費税50万円 – 仕入消費税(仮に20万円) = 納税額30万円 - 2割特例の場合:
売上消費税50万円 × 20% = 納税額10万円 - 【適格請求書の記載必須項目】
-
- 適格請求書発行事業者の登録番号 (T + 13桁の法人番号または数字)
- 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称
- 課税資産の譲渡等を行った年月日
- 課税資産の譲渡等に係る資産または役務の内容(軽減税率の対象品目である旨)
- 課税資産の譲渡等の税抜価額または税込価額を税率ごとに区分して合計した金額及び適用税率
- 税率ごとに区分した消費税額等(端数処理は一請求書あたり、税率ごとに1回ずつ)
- 【免税事業者の請求書のポイント】
-
- 登録番号は記載しない(できない)。
- 消費税額の記載について:「消費税」として明確に区分して記載すると、取引先が仕入税額控除できると誤認する可能性があるため、「税込価格」として総額表示するか、あるいは内訳として「(うち消費税等相当額〇〇円)」と参考程度に記載するなどの工夫が考えられます。国税庁は、免税事業者が消費税や地方消費税の額を請求書に記載してはならないとはしていませんが、適格請求書と誤認されないような記載が望ましいとしています。
- 請求書に「当方は免税事業者です」や「適格請求書発行事業者登録番号はございません」といった一文を添えることで、取引先の理解を助けることができます。
- 【対策として考えられること】
-
- 早めのコミュニケーション: まずは、主要な取引先に、自身がインボイス発行事業者になるのか、ならないのかの方針を早めに伝え、相談することが大切です。「どうしようかな……」と迷っている間に、取引先が他の事業者を探し始めてしまうかもしれません。
- 提供価値の再確認とアピール: 価格だけでなく、あなたの提供するサービスや商品の品質、専門性、納期遵守といった付加価値を改めて取引先に伝え、理解を求めましょう。
- 柔軟な価格設定の検討: 状況によっては、一部価格を見直すことも検討材料の一つかもしれません。ただし、一方的な値下げ要求に応じる必要はありません。
- 契約内容の確認: 既存の契約書に、インボイス制度に関する取り決めや、価格変更に関する条項がないか確認しておきましょう。
- 【注意すべき行為の例】
-
- 仕入税額控除ができないことを理由に、一方的に取引価格を引き下げる。
- インボイス発行事業者になることを強要し、応じない場合に取引を打ち切る。
- 商品やサービスの対価とは別に、「協力金」などの名目で金銭負担を要求する。
- 【情報収集のポイント】
-
- 国税庁のウェブサイトを定期的に確認する: 最も信頼できる一次情報は国税庁のウェブサイトです。「インボイス制度特設サイト」はブックマークしておくと良いでしょう。インボイス制度特設サイト – 国税庁
- 信頼できる専門家の情報を参考にする: 税理士や会計事務所が発信する情報も参考になりますが、発信元が信頼できるか、情報が最新かを確認しましょう。
- セミナーや説明会に参加する: 自治体や商工会議所、税理士会などが開催するセミナーも、最新情報を得る良い機会です。
- 提出方法: e-Tax(電子申請)または郵送で提出できます。e-Taxが便利でおすすめです。
- 登録希望日からの登録: 原則として、登録申請書を提出してから登録通知が来るまで一定期間(e-Taxで約3週間、書面で約1.5か月 ※執筆時点の目安)かかります。特定の課税期間の初日から登録を受けたい場合は、その課税期間の初日から起算して1か月前の日までに提出する必要がありますが、困難な事情がある場合は柔軟な対応がされることもあります。/li>
- 最新情報確認: 手続きや期間については変更される可能性もあるため、必ず国税庁の[手続名]適格請求書発行事業者の登録申請手続 – 国税庁で最新情報を確認してください。
- 交渉の余地を探る: まずは取引先と話し合いの場を持ち、あなたの状況や提供している価値を説明し、理解を求めましょう。経過措置についても説明し、段階的な対応を提案するのも一つの方法です。
- 不当な要求には屈しない: 明らかに一方的で不当な要求であれば、安易に応じる必要はありません。/li>
- 専門家や相談窓口へ: 交渉が難しい場合や、不当な圧力を感じる場合は、公正取引委員会や中小企業庁の相談窓口、弁護士や税理士に相談することを検討してください。
- freee会計: クラウド会計ソフトの代表格で、銀行口座やクレジットカードとの連携機能が強力です。
- 弥生会計 オンライン / やよいの青色申告 オンライン: 老舗の会計ソフトで、信頼性が高く、サポートも充実しています。/li>
- マネーフォワード クラウド確定申告: freee会計と同様に人気のクラウド会計ソフトで、使いやすさに定評があります。
- 税込価格で総額表示する(例:デザイン料 110,000円(税込))
- どうしても内訳を示したい場合は、「(うち消費税等相当額 10,000円)」のように、あくまで参考情報であることが分かるように記載する
- 請求書に「当方は免税事業者です」と明記する といった対応が望ましいでしょう。最も安全なのは、税抜金額と税込総額のみを記載し、「消費税」という項目を設けないことです。
- あなたの事業内容や取引先の状況に合わせた、オーダーメイドのアドバイスが受けられること。
- 複雑な制度の解釈や、煩雑な事務作業をサポートしてもらえること。
- 税務に関する最新情報を常に提供してもらえること。 など、多岐にわたります。
- 記事監修
-
- 中野 裕哲 HIROAKI NAKANO
- 起業コンサルタント(R)、経営コンサルタント、税理士、特定社会保険労務士、行政書士、サーティファイドファイナンシャルプランナー・CFP(R)、1 級FP 技能士。 V-Spiritsグループ創業者。東京池袋を本拠に全国の起業家・経営者さんを応援!「あの起業本」の著者。著書16冊、累計20万部超。経済産業 省後援「DREAMGATE」で11年連続相談件数日本一。
- ※本記事は、起業の窓口編集部が専門家の監修または独自調査(アンケート)に基づいて制作したものです。
- ※掲載している情報は、記事公開時点の法令・税制・商品・サービス等に基づくものであり、将来的に変更される可能性があります。
- ※アンケート調査に関する記述は、特定の調査対象者からの回答結果および編集部の見解を含んでおり、内容の正確性・完全性を保証するものではありません。
- ※記事の内容は一般的な情報提供を目的としており、すべての方に当てはまるものではありません。個人の状況に応じた具体的な助言が必要な場合は、専門家にご相談ください。
- ※情報の利用や判断、実施については、ご自身の責任で行っていただきますようお願いいたします。
- ※本記事に掲載された内容の転載・複製はご遠慮いただき、引用の際は必ず出典をご明記ください。
一方、デメリットとしては、以下の内容が考えられます。
登録するか否かは、ご自身の事業の状況、取引先の意向、そして後述する負担軽減措置などを総合的に考慮して判断する必要があります。
以前、ウェブデザイナーのお客様から「クライアントのほとんどが企業なので、登録しないと仕事が減るのでは……」というご相談を受けました。その方とは、クライアントへの影響度合いや、課税事業者になった場合のシミュレーションを一緒に行い、最終的に登録を選択されました。このように、個々の状況に応じた判断が大切です。
【最重要】免税事業者の2つの選択肢:課税事業者になるか、免税のままでいるか
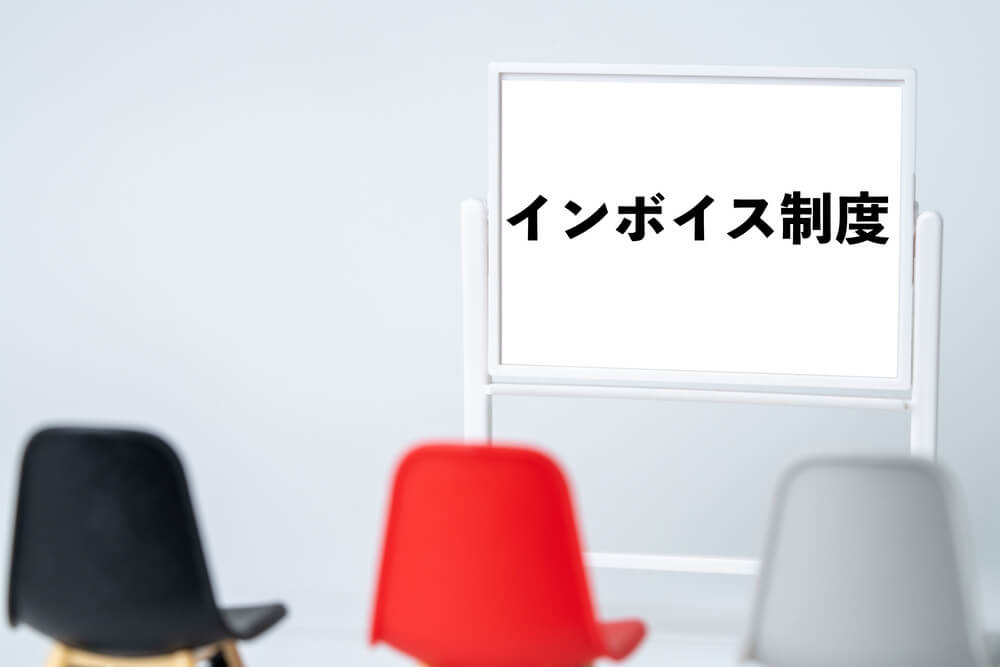
インボイス制度導入にあたり、私たち免税事業者が直面する最大の岐路は、「課税事業者になるか」それとも「免税事業者のままでいるか」という選択です。どちらの道を選ぶかによって、今後の事業運営や税負担が大きく変わってきます。
このセクションでは、それぞれの選択肢のメリット・デメリット、そしてご自身の状況に合わせた判断ポイントを具体的に見ていきましょう。感情的にならず、冷静に比較検討することが重要です。
パターン1:思い切って「課税事業者」になる!メリット・デメリットと判断基準
まず、適格請求書発行事業者の登録を行い、課税事業者になる選択肢です。
【課税事業者になるメリット・デメリット】
| 項目 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 取引関係 | 課税事業者の取引先が仕入税額控除可能、取引の維持・拡大に繋がりやすい | ‐ |
| 税金 | 消費税還付の可能性(条件あり) | 消費税の納税義務が発生 |
| 事務面 | ‐ | 適格請求書の作成・保存、消費税申告業務の発生、経理処理の複雑化と負担増 |
| その他 | 社会的信用の若干の向上(見方による) | ‐ |
パターン2:これまで通り「免税事業者」を続ける!メリット・デメリットと注意点
次に、適格請求書発行事業者の登録をせず、免税事業者のままでいる選択肢です。
【免税事業者を続けるメリット・デメリット】
| 項目 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 取引関係 | ‐ | 課税事業者の取引先が仕入税額控除不可。取引継続の交渉が必要になる場合がある。新規の課税事業者との取引が難しい場合がある。 |
| 税金面 | 消費税の納税義務なし | ‐ |
| 事務面 | 経理・事務負担は現状維持 | ‐ |
| その他 | 取引先への説明や価格交渉が必要になる可能性あり | ‐ |
【ケーススタディ】私はどっちを選ぶべき?あなたの状況に合わせた選択シミュレーション
「結局、私にはどちらが良いの?」と迷われる方も多いと思います。そこで、いくつかのケーススタディを通して、判断のヒントを探ってみましょう。
【状況】
主な取引先は大手企業(課税事業者)で、継続的な案件が多い。取引先からはインボイス発行を求められている。
【考えられる選択】
この場合、取引の継続を最優先に考えるなら、課税事業者になることを検討するのが現実的でしょう。後述する「2割特例」などの負担軽減策も活用できます。
【状況】
生徒はすべて一般消費者(BtoC)。事業者間取引はほとんどない。
【考えられる選択】
主な顧客が一般消費者であれば、インボイスの発行を求められることは基本的にありません。この場合は、免税事業者のままでいるメリットが大きいと考えられます。
【状況】
取引先は小規模な個人商店(免税事業者も課税事業者も混在)。一部の課税事業者からはインボイスを求められているが、強くはない。
【考えられる選択】
このケースは判断が難しいです。あなたの各取引先の意向を丁寧にヒアリングし、インボイス発行を求める取引先の売上構成比、今後の事業方針などを総合的に話し合うことをオススメします。
例えば、「2割特例」が使えるうちは課税事業者になり、状況を見て再度判断していくなど。このように、一つ一つの取引関係や将来性を見極めることが重要です。
ご自身の状況をこれらのケースに当てはめてみたりして、じっくり考えてみてください。もちろん、最終的な判断に迷う場合は、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。
賢く活用!免税事業者が使えるインボイス制度の負担軽減策

「課税事業者になると税負担が増えるのは困る……」そう思われる方も多いのではないでしょうか。ご安心ください。インボイス制度への移行に伴い、特に免税事業者から課税事業者になった方の負担を和らげるための特例措置が用意されています。
このセクションでは、これらの負担軽減策について、対象者、期間、具体的な内容を分かりやすく解説します。これらを賢く活用することが、損をしない対策の鍵となります。
仕入税額控除の「経過措置」とは?いつまで使える?
インボイス制度が始まっても、すぐにすべての取引で厳格なインボイスが求められるわけではありません。特に、免税事業者からの仕入れについては、急激な変化を緩和するための経過措置が設けられています。これは、買い手側(課税事業者)の負担を軽減する措置ですが、結果として免税事業者との取引継続にも繋がりうるものです。
| 概要 | |
|---|---|
| 内容 | 免税事業者など、適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れについても、制度開始から一定期間は、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額として控除できます。 |
| 期間と控除割合 | |
| 期間 | 控除割合 |
| 2023年10月1日 〜2026年9月30日 |
仕入税額相当額の80%控除可能 |
| 2026年10月1日 〜2029年9月30日 |
仕入税額相当額の50%控除可能 |
| 必要な対応 | |
| 対応事項 |
|
【大注目!】「2割特例」で納税額を大幅カット!対象者・期間・計算方法を徹底解説
免税事業者からインボイス発行事業者になった方にとって、最も注目すべき負担軽減策が「2割特例」です。これは、消費税の納税額を売上税額の2割に軽減できるという、非常に有利な制度です。
| 2割特例とは | |
|---|---|
| 概要 | インボイス発行事業者となった免税事業者の税負担・事務負担を軽減するための、売上税額の2割を納税額とできる特例措置です。事前の届出は不要で、消費税の申告書に2割特例の適用を受ける旨を付記することで適用を受けられます。 |
| 対象者 |
▼2割特例の詳しい対象者要件 |
| 適用期間 | 2023年10月1日から2026年9月30日までの日を含む各課税期間です。個人事業主の場合、2023年10月~12月分、2024年分、2025年分、2026年分の申告が対象となり得ます。 |
| 計算方法 | 非常にシンプルで、売上にかかる消費税額 × 20% = 納税額となります。仕入れにかかる消費税額を計算する必要がないため、事務負担も大幅に軽減されます。 |
| 具体例 | |
|
年間売上高が550万円(うち消費税50万円)のフリーランスデザイナーが課税事業者になった場合。 この例では、納税額が20万円も軽減されます。 |
|
その他の支援策・補助金はある?(2025年最新情報)
インボイス制度への対応を支援するための直接的な補助金は、制度開始当初に比べて少なくなっていますが、中小企業や小規模事業者がITツールを導入する際に利用できるIT導入補助金などが、間接的にインボイス対応に役立つ場合があります。
IT導入補助金では、会計ソフトや受発注ソフト、決済ソフトなどが対象となることがあり、インボイス制度に対応した機能を持つツールも含まれることがあります。
❝ IT導入補助金は、中小企業・小規模事業者等のみなさまが自社の課題やニーズに合ったITツールを導入する経費の一部を補助することで、みなさまの業務効率化・売上アップをサポートするものです。❞
IT導入補助金2024(サービス等生産性向上IT導入支援事業)公式サイト
公募要領や対象となるITツールは毎年変わる可能性があるため、常に最新情報を確認することが重要です。補助金の活用を検討される場合は、お近くの商工会議所や中小企業支援機関、または税理士にご相談いただくのが良いでしょう。
インボイス制度開始後の請求書はどう変わる?免税事業者のための請求書作成ガイド
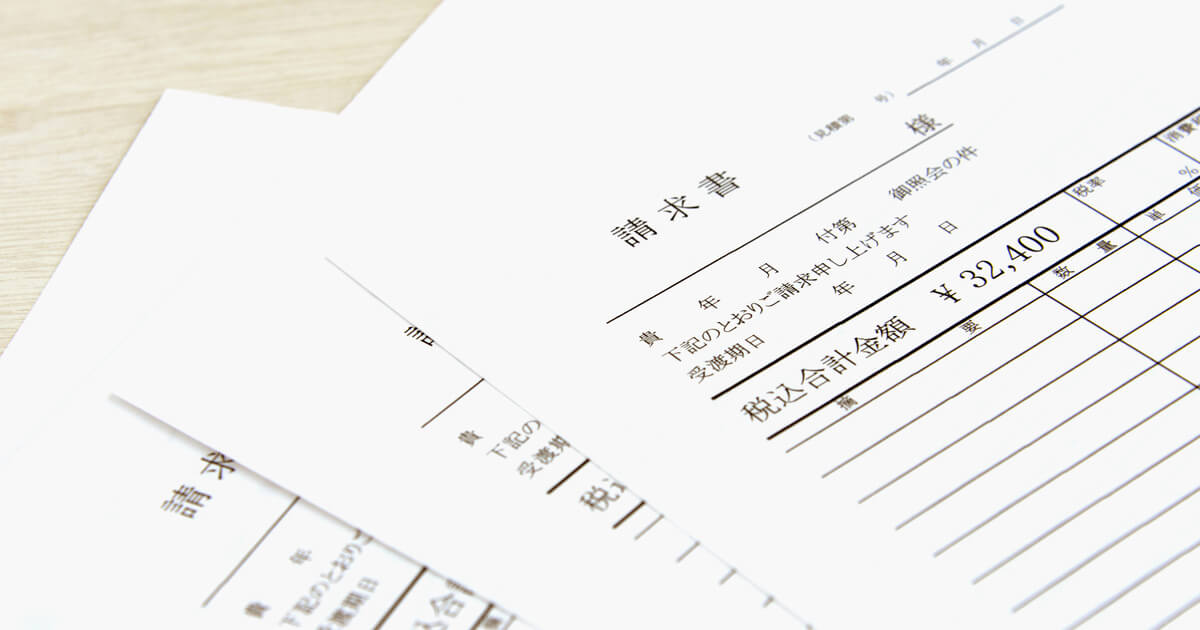
インボイス制度に対応する上で、最も実務的な変化が「請求書の書き方」です。特にフリーランスの方にとっては、「クライアントに迷惑をかけない、正しい請求書を発行したい」というニーズは非常に高いでしょう。
このセクションでは、課税事業者になった場合と免税事業者のままでいる場合、それぞれの請求書の書き方と注意点を、具体的な記載例を交えながら解説します。
パターン1:課税事業者になった場合の「適格請求書(インボイス)」の書き方
適格請求書発行事業者として登録し、課税事業者になった場合は、「適格請求書(インボイス)」を発行する必要があります。従来の請求書に加えて、いくつかの項目を記載しなければなりません。
特に、登録番号、適用税率、税率ごとの消費税額等の記載が重要です。
例えば「登録番号は載せたけど、消費税額をまとめて書いてしまった」というご相談がありました。この場合、厳密には適格請求書の要件を満たしていないことになります。税率ごとに区分して消費税額を記載する点に注意しましょう。
多くの会計ソフトでは、これらの要件を満たした請求書フォーマットが用意されていますので、活用すると便利です。
パターン2:免税事業者のままの場合の請求書の書き方と取引先への伝え方
免税事業者のままでいることを選択した場合、あなたは適格請求書発行事業者ではないため、適格請求書(インボイス)を発行することはできません。 登録番号もありません。
この場合、請求書の書き方自体は、インボイス制度導入前と大きく変わる必要はありません。従来の「区分記載請求書」と同様の記載で問題ありませんが、取引先に誤解を与えないための配慮が大切です。
【取引先への説明例文】
いつもお世話になっております。〇〇(自社名/屋号)です。 インボイス制度開始に伴い、当方の方針についてご連絡申し上げます。 検討の結果、当面の間、免税事業者として事業を継続することといたしました。 つきましては、当方からの請求書は適格請求書(インボイス)の要件を満たさないものとなります。
ご迷惑をおかけし恐縮ですが、何卒ご理解いただけますようお願い申し上げます。 引き続き、より良いサービス提供に努めてまいりますので、今後とも変わらぬお引き立てを賜りますようお願い申し上げます。
このような丁寧なコミュニケーションが、良好な取引関係を維持するために重要です。
【独自視点】免税事業者がインボイス制度で本当に注意すべき3つのポイント

インボイス制度については、制度の概要や手続き面での情報が多く発信されています。しかし、私たちフリーランスや小規模事業者が、実務上「本当に気をつけるべきこと」は、もう少し深い部分にあるかもしれません。
このセクションでは、税理士の観点から、特に免税事業者の皆さまに注意していただきたい3つのポイントを、独自視点を交えて解説します。
ポイント1:取引先との関係維持:価格交渉や契約見直しの可能性と対策
インボイス制度の影響で、最も心配されるのが取引先との関係です。あなたが免税事業者のままでいる場合、課税事業者の取引先は仕入税額控除が受けられない分、コスト増となります。そのため、取引先から価格の引き下げを要求されたり、最悪の場合、取引の見直しを検討されたりする可能性はゼロではありません。
小規模な製造業の事業者が、大手取引先からインボイス発行を強く求められ、対応に苦慮していた事例があります。この場面では、単に発行できない旨を伝えるのではなく、自社の技術力や短納期対応といった強みを再度訴求し、あわせて経過措置期間中は一部価格面で協力するなどの代替案を提示しながら交渉が行われました。
その結果、直ちに取引停止とはならず、継続に向けた交渉の余地が生まれています。こうした対応からも、状況に応じた丁寧なコミュニケーションの重要性がうかがえます。
ポイント2:意外と見落としがち?独占禁止法・下請法との関連
インボイス制度への移行に乗じて、取引上の優越的な地位にある事業者が、免税事業者に対して不当な不利益を与える行為は、独占禁止法や下請法に違反する可能性があります。
❝ 免税事業者との取引に関して、仕入税額控除ができないことを理由として、取引価格の引下げを要請する場合には、転嫁の程度や価格交渉の経緯等を総合的に勘案して、それが「買いたたき」に該当しないかどうかが問題となります。❞
インボイス制度後の免税事業者との取引に係る下請法上の考え方 – 公正取引委員会
もし、取引先からこのような不当な要求を受けたと感じた場合は、一人で抱え込まず、公正取引委員会や中小企業庁が開設している相談窓口、または弁護士や税理士などの専門家に相談しましょう。
インボイスQ&A(公正取引委員会)より抜粋
Q: 免税事業者に対し、インボイス発行事業者への登録を要請することは問題となりますか。
A: 登録を要請すること自体が直ちに問題となるものではありませんが、登録しない場合に取引価格を引き下げたり、取引を打ち切ったりするなど、一方的に不利益を与える場合は、独占禁止法上又は下請法上問題となるおそれがあります。
このように、公的機関も注意喚起を行っています。ご自身の権利を守るためにも、正しい知識を持つことが大切です。
ポイント3:最新情報を常にキャッチアップ!制度変更や解釈の確認方法
インボイス制度は比較的新しい制度であり、今後も関連する通達やQ&Aが更新されたり、新たな解釈が示されたりする可能性があります。また、2割特例や経過措置には適用期間が定められています。
税理士は、常に最新の税制改正情報や国税庁からの通達をチェックし、クライアントの皆様に正確な情報をお伝えできるよう努めています。情報が氾濫する時代だからこそ、信頼できる情報源を見極めることが重要です。ご自身での情報収集に不安がある場合は、顧問税理士に確認するのが最も確実です。
【Q&A】免税事業者のインボイス制度に関するよくある質問

ここまでインボイス制度について詳しく見てきましたが、それでもまだ個別の疑問点や不安が残っているかもしれません。このセクションでは、特に免税事業者の方からよく寄せられる質問とその回答をまとめました。あなたの疑問解消の一助となれば幸いです。
Q. 売上が1000万円以下でも課税事業者になるべき?
必ずしもそうとは限りません。売上が1000万円以下であれば、原則として消費税の納税義務は免除されます(免税事業者)。しかし、インボイス制度では、あなたの取引先(特に課税事業者)が仕入税額控除を受けるために、あなたにインボイス(適格請求書)の発行を求める場合があります。 その場合、取引先の意向や、インボイスを発行できないことによる事業への影響度、そして「2割特例」などの負担軽減措置のメリットを総合的に考慮して判断する必要があります。一律に「なるべき」または「ならなくてよい」とは言えないため、ご自身の状況をよく分析することが大切です。
Q. 適格請求書発行事業者の登録申請はいつまでに、どうやってすればいい?
適格請求書発行事業者の登録を受けるためには、「適格請求書発行事業者の登録申請書」を納税地を所轄する税務署長に提出する必要があります。
「いつから登録したいか」を明確にし、早めに準備を進めることが肝心です。
Q. 取引先からインボイス対応のために値下げを要求されたら、どうすればいい?
まず、冷静に状況を把握しましょう。取引先が仕入税額控除できない分を、一方的にあなたに負担させようとする値下げ要求は、場合によっては独占禁止法や下請法に抵触する可能性があります。ポイントは次のとおりです。
Q. インボイス制度に対応できるおすすめの会計ソフトは?
インボイス制度に対応した会計ソフトは、請求書発行や消費税計算の事務負担を軽減する上で非常に役立ちます。多くのフリーランスや個人事業主の方に利用されている代表的な会計ソフトには、以下のようなものがあります。
これらのソフトは、適格請求書の作成、税率ごとの集計、消費税申告書の作成支援など、インボイス制度に必要な機能を備えています。多くの場合、無料プランやお試し期間が用意されているので、ご自身の業務スタイルや予算に合わせて比較検討してみるのが良いでしょう。 操作性や機能にはそれぞれ特徴がありますので、実際に触ってみるのが一番です。
Q. 免税事業者のままでも、消費税を請求書に書いていいの?
免税事業者は、消費税の納税義務が免除されているため、取引先から消費税を「預かる」という立場にはありません。そのため、請求書に「消費税額 〇〇円」と明確に区分して記載することは、取引先に誤解を与え、適格請求書と誤認させてしまう可能性があります。
国税庁のQ&Aでは、「免税事業者が、その取引に係る消費税額や地方消費税額に相当する額について、請求書等に『消費税額等』や『消費税額等相当額』等として、別途明確に区分して表示することは、消費税法上、問題となるものではありません」とされていますが、同時に「適格請求書等と誤認されるおそれのないように表示する」ことも求められています。
トラブルを避けるためには、下記のポイントを押さえましょう。
まとめ:インボイス制度は怖くない!正しい知識で賢く対応しよう

ここまで、免税事業者の皆さまがインボイス制度にどう向き合い、対応していくべきか、様々な角度から解説してきました。多くの情報に触れ、少し頭が混乱しているかもしれませんね。
最後に、インボイス制度は確かに変化をもたらしますが、正しい知識を身につけ、ご自身の状況に合わせて賢く対応すれば、決して怖いものではありません。むしろ、これを機にご自身の事業や取引先との関係を見直し、事業を成長させるための土台を築くチャンスと捉えることもできるはずです。
【おさらい】免税事業者がインボイス制度で押さえるべき最重要ポイント
このチェックリストを活用して、ご自身の対応状況を再確認してみてください。
【インボイス制度対応 最重要チェックリスト】
| チェック項目 | 確認ポイント | 対策・行動 |
|---|---|---|
| 1. 制度の基本理解 | インボイス制度とは何か、なぜ導入されたか理解したか?適格請求書発行事業者とは何か、登録の任意性を理解したか? | 国税庁の資料等で再確認。不明点は専門家へ。 |
| 2. 自社への影響把握 | 主な取引先は課税事業者か、免税事業者か?取引先からインボイス発行を求められているか、または求められそうか? | 取引先へのヒアリング、アンケート実施。 |
| 3. 対応方針の決定 | 課税事業者になるか、免税事業者のままでいるか、メリット・デメリットを比較検討したか?自身の事業規模、将来性、事務処理能力を考慮したか? | ケーススタディやフローチャートを参考に熟考。必要ならシミュレーションを実施。 |
| 4. 負担軽減策の理解と活用 | 「2割特例」の対象となるか、適用期間、計算方法を理解したか?「経過措置」の内容と期間を理解したか? | 自身が対象となるか確認。有利な方を選択できるよう準備。 |
| 5. 請求書様式の準備 | 課税事業者になる場合、適格請求書の記載事項を理解し、対応できるか?免税事業者のままの場合、取引先に誤解を与えない請求書の書き方を理解したか? | 会計ソフトの導入検討、請求書テンプレートの準備。 |
| 6. 取引先とのコミュニケーション | 自社の方針を取引先に説明する準備はできているか?価格交渉や契約見直しが発生した場合の対応を考えているか? | 事前に説明内容を整理。不当な要求には専門家へ相談。 |
| 7. 会計・申告体制の整備 | 課税事業者になる場合、消費税の申告・納税の準備はできているか?帳簿付けや経理処理の変更に対応できるか? | 会計ソフトの選定・導入、税理士への相談検討。 |
| 8. 最新情報のキャッチアップ | 国税庁のウェブサイトなど、信頼できる情報源を定期的に確認する習慣があるか? | 定期的な情報収集の習慣化。 |
不安な場合は一人で悩まず専門家へ相談を
インボイス制度は複雑で、個々の状況によって最適な対応が異なります。もし、この記事を読んでもまだ不安が残る、自分の場合はどうすれば良いか具体的に知りたい、という方は、決して一人で悩まず、税理士などの専門家にご相談ください。
専門家に相談するメリットは、以下のとおりです。
多くの税理士事務所では、初回相談を無料で行っているところもあります。まずは気軽に問い合わせてみてはいかがでしょうか。
起業や開業、独立に興味を持ったら、まずは「起業の窓口」に登録してみよう!
「起業の窓口」では、起業に必要なノウハウや成功者のインタビューなど、さまざまなコンテンツを完全無料で提供しています。
会員特典として、起業・経営支援のプロ「V-Spirits」が監修するオリジナル冊子『会社設立完全ガイド』を無料プレゼント。さらに、V-Spritsによる1時間の無料起業相談や、GMOインターネットグループが展開するビジネスの立ち上げや拡大に役立つ各種サービスをおトクな特典付きでご紹介します。
あなたの夢の実現を全力でサポートします!
関連記事
30秒で簡単登録
厳選サービスを特典付きでご紹介



 シェア
シェア



















