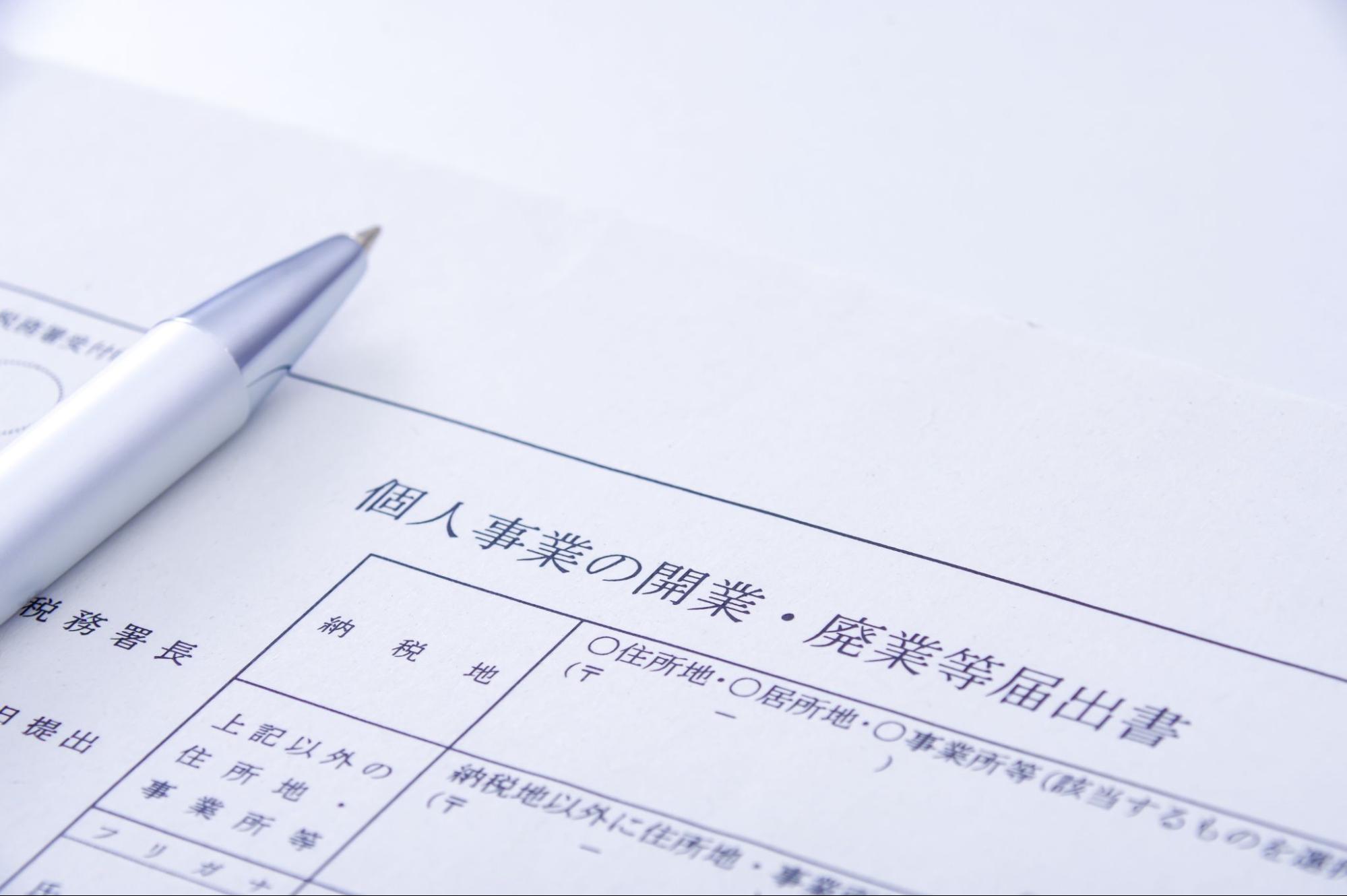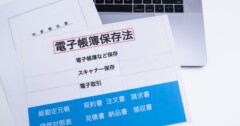起業時に受けられる融資一覧|自己資金なしでも起業できるのか解説

起業を検討しているものの、「資金が足りない」「一度廃業してしまい資金が少ない」といった悩みを抱えている人はいませんか。
起業資金が少ない方は、新規開業・スタートアップ支援資金などの融資を受けることで、起業に必要な資金を集められる可能性があります。とはいえ、どんな制度なのか詳しく知ってからでないと利用を検討しづらいと感じる方もいるでしょう。
本記事では、起業時に利用できる融資や融資の際に気をつけるポイントについて解説します。自己資金が足りなくて起業できない方や一度廃業した方でも、今回紹介する融資に通ることで、起業ができるようになります。ぜひご一読ください。
- 【この記事のまとめ】
- 新規開業・スタートアップ支援資金など、起業時の資金不足に対応するための融資制度を解説します。各制度は担保不要や低金利で利用しやすく、起業家を支援します。
- 女性やシニア向け制度、再挑戦支援資金、地方自治体の制度融資など、起業状況や個別のニーズに応じた融資制度が豊富に用意されています。各自に適した制度を選びましょう。
- 起業時の融資を申請する際、事業計画や資金使途の明確化が重要です。明確な計画があることで、審査通過の可能性が上がり、スムーズな資金調達が期待できます。
「起業の窓口」では、AIインフルエンサーの茶圓氏とコラボをおこない、AIを活用してビジネスの効率化を図るための貴重な知識を提供しています。
特集ページ「AI×起業」では、最新のAI技術やツールを使った実践的なアプローチを紹介しており、起業家や個人事業主の業務をよりスマートにサポートします。
AIの力で業務の負担を軽減し、ビジネスの成長を加速させたい方に最適な情報が満載です。ぜひご覧ください。
「起業の窓口」の特集ページ「起業家インタビュー」では、実際に成功を収めた起業家たちの貴重なインタビューが充実しています。リアルな体験や苦労、成功までの道のりを通じて、これから起業を目指す方々に向けた実践的なアドバイスを提供しています。
さまざまな分野で活躍する起業家の声を通して、ビジネスのヒントやインスピレーションを得られるコンテンツが満載です。ぜひインタビューを参考にして、自分のビジネスに活かしてみてください。
起業時に受けられる融資一覧

起業する際に、資金面の問題を抱えている事業者は多いでしょう。起業する際には、開業資金や商品の購入費などが必要になります。
起業する際に資金不足などお金の問題を抱えないためにも、今回紹介する以下8つの融資を活用してください。
- 新規開業・スタートアップ支援資金
- 新規開業・スタートアップ支援資金(女性、若者/シニア起業家支援関連)
- 新規開業・スタートアップ支援資金(再挑戦支援関連)
- 生活衛生新企業育成資金(新企業育成・事業安定等貸付)
- 挑戦支援資本強化特別貸付(資本性ローン)
- 新事業活動促進資金
- 地方自治体の制度融資
それでは、順番に解説します。
新規開業・スタートアップ支援資金
新規開業・スタートアップ支援資金は、日本政策金融公庫が新規開業者のために設けている融資制度です。新規開業・スタートアップ支援資金は、事業をはじめるために必要な備品の購入費用や事業を継続するために必要な資金に使えます。
無担保・無保証人で融資を受けられるため、初めて起業する方におすすめの制度です。
| 対象者 | 新たに事業を始める方または事業開始後おおむね7年以内の方 |
|---|---|
| 資金の使用用途 | 新たに事業を始めるため、または事業開始後に必要とする設備資金および運転資金 |
| 融資限度額 | 7,200万円(うち運転資金4,800万円) |
| 金利 | 基準利率 2.8~4.2%程度(最新の金利は日本政策金融公庫の公式ページを確認) |
| 返済期間 | 設備資金:20年以内<うち据置期間5年以内> 運転資金:10年以内<うち据置期間5年以内> |
利用がおすすめの人の特徴は以下の通りです。
- 新たに事業を始める人
- 事業を継続するために資金が必要な人
新規開業・スタートアップ支援資金(女性、若者/シニア起業家支援関連)
新規開業・スタートアップ支援資金(女性、若者/シニア起業家支援関連)は、女性または35歳未満か55歳以上の方向けの日本政策金融公庫の融資制度です。設備資金が20年以内と返済期間が長く金利が安いです。
無担保・無保証人で融資を受けられるため、女性、若者、シニアに該当する方にはおすすめの制度です。
| 対象者 | 新たに事業を始める方または事業開始後おおむね7年以内の方のうち、女性または35歳未満か55歳以上の方 |
|---|---|
| 資金の使用用途 | 新たに事業を始めるため、または事業開始後に必要とする設備資金および運転資金 |
| 融資限度額 | 7,200万円(うち運転資金4,800万円) |
| 金利 | 特別利率A 2.0~3.8%程度(令和7年10月時点。最新は公式サイト参照) |
| 返済期間 | 設備資金:20年以内<うち据置期間5年以内> 運転資金:10年以内<うち据置期間5年以内> |
利用がおすすめの人の特徴は以下の通りです。
- 新たに事業を始める人のうち女性、若者、シニアに該当する人
- 事業を継続するために資金が必要な人
新規開業・スタートアップ支援資金(再挑戦支援関連)
新規開業・スタートアップ支援資金(再挑戦支援関連)は、一度廃業した人や再起を図りたい人が利用できる融資です。事業を立ち上げて失敗した人が再度チャレンジできるような資金制度であるため、魅力的ですが、一度廃業していることから、審査のハードルは高くなります。
また、新規開業・スタートアップ支援資金(再挑戦支援関連)を利用できる人は、廃業した経験が必要です。申し込む際は、担保や保証人が必要となる場合があるため、事前に検討しておきましょう。
| 対象者 | 新たに事業を始める方または事業開始後おおむね7年以内の方のうち、 下記のすべてに該当する方
|
|---|---|
| 資金の使用用途 | 新たに事業を始めるため、または事業開始後に必要とする設備資金および運転資金(前事業に係る債務を返済するために必要な資金を含みます。) |
| 融資限度額 | 7,200万円(うち運転資金4,800万円) |
| 金利 | 基準利率2.80~4.20%(令和7年10月1日現在、年利%) |
| 返済期間 | 設備資金:20年以内<うち据置期間5年以内> 運転資金:15年以内<うち据置期間5年以内> |
利用がおすすめの人の特徴は以下の通りです。
- 廃業歴がある人
- 再起を図りたい人
生活衛生新企業育成資金(新企業育成・事業安定等貸付)
生活衛生新企業育成資金(新企業育成・事業安定等貸付)は、日本政策金融公庫が生活衛生関連事業を創業する方のために設けている融資制度です。
飲食店や美容室、食肉販売業、クリーニング業のような衛生関係の事業を始める際に必要な設備資金、運転資金の融資を受けられます。
振興計画認定組合の組合員は、振興事業に係る資金証明書など、その他の人は都道府県知事の推薦書が必要になりますが、設備資金は最大7億2,000万円、運転資金は最大5,700万円と高額な融資を受けられる可能性のある制度です。
| 振興計画認定組合の組合員 | その他の人 | |
|---|---|---|
| 対象者 | 生活衛生関係の事業を創業する方又は創業後おおむね7年以内の方 | |
| 資金の使用用途 | 設備資金および運転資金 | 設備資金 |
| 融資限度額 | 設備資金は1億5000万円~7億2,000万円、運転資金は最大5,700万円 | 設備資金 7,200万円~4億8,000万円 |
| 金利 | 基準利率:2.80~4.20% 特別利率A:2.40~3.80% 特別利率B:2.1~3.5% 特別利率C:1.90~3.30% ※令和7年10月1日現在 |
基準利率:2.80~4.20% 特別利率A:2.40~3.80% 特別利率B:2.15~3.5% 特別利率C:1.90~3.30% ※令和7年10月1日現在 |
| 返済期間 | 設備資金:20年以内<うち据置期間5年以内> 運転資金:10年以内<うち据置期間5年以内> |
設備資金:20年以内<うち据置期間5年以内> |
出典:日本政策金融公庫(生活衛生新企業育成資金(新企業育成・事業安定等貸付)<特例貸付>)
利用がおすすめの人の特徴は以下の通りです。
- 該当する事業を新たに始める人
- 高額な融資を受けたい人
挑戦支援資本強化特別貸付(資本性ローン)
挑戦支援資本強化特別貸付は、スタートアップや新事業の展開、海外展開、事業再生に取り組む企業に向けた財務体質強化を目的にした制度です。
通常の融資とは異なり、挑戦支援資本強化特別貸付は資本性ローンに該当され、自己資本とみなすことができます。
つまり、挑戦支援資本強化特別貸付によって受けた融資によって、自己資金比率の増加とともに金融機関からの評価が高まるため、追加融資の可能性も高まります。
| 対象者 | 次のいずれかを満たす法人または個人企業
次のすべてを満たす方
|
|---|---|
| 資金の使用用途 | 該当する融資制度に定める設備資金および運転資金 |
| 融資限度額 | 7,200万円(別枠) |
| 金利 | 融資後1年毎に直近の業績に応じて変動(0.50~3.25%) |
| 返済期間 | 5年1ヵ月以上20年以内 |
出典:日本政策金融公庫(挑戦支援資本強化特別貸付(資本性ローン))
利用がおすすめの人の特徴は以下の通りです。
- 資金繰りの安定を図りたい人
- 将来的に追加融資を考えている人
新事業活動促進資金
新事業活動促進資金は、新規事業を立ち上げるときに利用できる融資制度です。優れた独自技術やノウハウを活用した新規事業や、経営革新計画や経営力向上計画の認定を受けた事業に活用する資金について利用できます。
新事業活動促進資金の申請に通るためには、技術やノウハウに新規性があるかどうかを第三者の客観的な判断も重要な要素です。
| 対象者 |
|
|---|---|
| 資金の使用用途 | 「該当者」に該当する方が、当該事業を行うために必要とする設備資金および運転資金 |
| 融資限度額 | 7,200万円(うち運転資金4,800万円) |
| 金利 | 基準利率 2.90~4.30% 特別利率A(2.50~3.90%) 特別利率B(2.25~3.65%) 特別利率C(2.00~3.40%) (令和7年10月1日現在、年利%) |
| 返済期間 | 設備資金:20年以内<うち据置期間2年以内> 運転資金:7年以内<うち据置期間2年以内> |
利用がおすすめの人の特徴は以下の通りです。
- 新しく事業を立ち上げる人
- 独自の技術やノウハウを持っている人
地方自治体の制度融資
地方自治体の制度融資は、中小企業や起業家などに対して、地方自治体が提供している融資制度です。各自治体は、中小企業の経営安定化、創業支援、地域経済の発展のために、融資制度を設けています。
例えば、東京都の制度融資では、DXの推進に取り組む方に融資するDX・イノベ・産業育成支援融資(DX)や中小企業が抱える様々な社会課題の解決を支援する社会課題解決融資(社会課題)などがあります。
地方自治体の制度融資は、各自治体のWebページで確認でき、制度融資の対象者は、中小企業者です。地方自治体の制度融資のメリットは、金融機関独自の融資に比べて、低金利であることが多いです。
自分に適している融資制度を探して、申し込みを進めていきましょう。
利用がおすすめの人の特徴は以下の通りです。
- 起業したばかりで信用が低い起業家
- 長期間の返済が可能な借入したい人
起業で融資を受ける際に気をつけるポイント
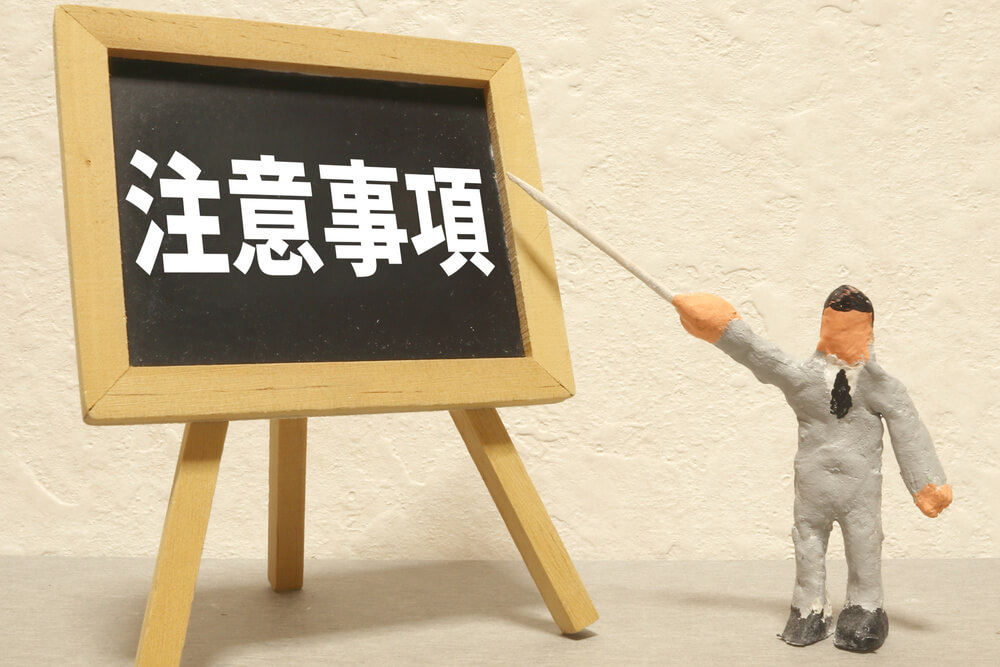
起業で融資を受ける際には、融資を受ける目的をはっきりさせることが大切です。
目的をはっきりさせるためには、事業計画や財務計画を作成し、融資の資金使途や返済方法を明確にしなければなりません。融資の審査をする方も、起業の目的や融資の使い道が不明確な人にお金を貸すことは不安でしょう。
また、審査担当の方は、貸したお金がきちんと戻ってくるかどうかを考えます。融資の審査を通りやすくし、起業の方向性を決めるためにも、融資を受ける目的を決める必要があります。
【重要】起業時の融資の可否を左右する5つの審査基準

起業時に融資を検討する際、金融機関が融資の可否を判断する審査基準を理解しておくことは非常に重要です。
- 【ポイント①】自己資金
- 【ポイント②】創業者のスキルや実績
- 【ポイント③】個人信用情報
- 【ポイント④】事業計画書
- 【ポイント⑤】明確な資金使途
ここでは、融資で特に重要とされる5つの審査基準について詳しく解説します。
【ポイント①】自己資金
自己資金比率とは、起業にあたって準備した自己資金が全体の資金調達に占める割合を指します。
特に金融機関は、自己資金を重視し、多くの場合、最低でも20%以上の自己資金を求めるケースが一般的です。
高い自己資金は、創業者の事業に対する思いや返済能力の証明となり、融資審査において大きなプラス要素となります。逆に自己資金が少ないと、金融機関は返済のリスクが高いと判断します。
そのため、できる限りの自己資金を準備しておくことが融資の審査通過のポイントです。
【ポイント②】創業者のスキルや実績
創業者のスキルや実績は、金融機関が融資を審査する際の重要な判断材料の一つです。
過去の職歴、業界での経験、経営やマーケティング能力、技術的なスキルなど、事業成功の可能性を左右する要素が評価されます。特に同じ業界での実績や過去の成功事例があると、金融機関からの信頼は高まるでしょう。
反対にスキルや実績のない分野での起業の場合、事業失敗による滞納リスクが高いと判断され、融資の審査に悪い影響を与えます。
しかし、必ずしも経験のある分野での起業が必須ではありません。補足資料やパートナーの存在、専門家の支援を示すことで信用力を補強しましょう。
【ポイント③】個人信用情報
個人信用情報は、創業者の過去の借入履歴や返済状況などを示す重要な基準です。
金融機関は、個人の信用情報を通じて、返済能力の有無を判断します。例えば、過去にクレジットカードやローンの延滞、自己破産履歴があると融資の審査が不利になってしまうでしょう。
そのため、個人信用情報に不安がある場合は、各信用情報機関で開示請求を行い、問題があれば改善策を講じてください。
【ポイント④】事業計画書
事業計画書は、起業時の融資審査で重要視される書類の一つです。
金融機関は事業計画書を通じて、事業の実現可能性や収益性、返済能力を見極めるため、事業内容や収支計画、資金繰り、リスク対策、成長戦略などを具体的に記載してください。
事業計画書の内容が曖昧だったり、非現実的な内容の場合は、融資の承認が難しくなるでしょう。
しかし、金融機関を納得させる事業計画書の作成は簡単ではありません。作成が難しい場合は、税理士や中小企業診断士などの専門家のアドバイスを受けるのがおすすめです。
【ポイント⑤】明確な資金使途
融資を受ける際は、調達資金の使途を明確に示さなければなりません。
金融機関は、資金使途が正しいものなのか、合理的かどうかをチェックします。設備投資や運転資金、人件費、広告宣伝費など、使途を経費ごとに細かく分け、どのタイミングでいくら必要なのかを明らかにしてください。
また、明確な資金使途は返済計画を立てやすく、金融機関からの信頼を受けやすくなります。
【手順】起業時に融資を受けるための準備

起業時に融資をスムーズに受けるためには、適切な準備が必要です。
以下の項目を申し込む前に確認・準備しておきましょう。
- 必要書類を用意
- 申し込む融資の要件を確認
- 現実的な事業・返済計画の策定
- 自己資金の用意
- 個人信用情報の確認および問題の解消
ここでは、具体的な準備について解説します。
1.必要書類を用意
融資を申し込む際には、さまざまな書類の提出が求められます。
代表的な必要書類は、以下の通りです。
- 本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード)
- 住民票
- 印鑑証明書
- 履歴事項全部証明書
- 通帳
- 確定申告書
- 法人決算書
- 事業計画書
- 資金繰り計画書
- 見積書
必要書類がない場合、再提出を求められ、審査までに時間がかかってしまいます。申し込む融資によって必要書類が異なるため、事前に確認しておきましょう。
また、必要書類を準備する際は、発行日や有効期限にも注意してください。
2.申し込む融資の要件を確認
起業時に利用できる融資には、さまざまな種類があります。
それぞれ申し込みの要件が異なるため、対象者、融資上限、返済期間や金利、保証人の有無などを事前に確認してください。
制度によっては、創業から一定期間以内に限定されたり、特定の事業者に限定されるなど要件が異なります。自分の事業計画や状況が融資の要件を満たすかどうかを確認しましょう。
3.現実的な事業・計画の策定
多くの融資制度では、事業計画書の提出が求められます。
事業計画書には、事業内容をはじめ、市場分析や競合調査、ターゲット層、売上予測などを具体的に記し、事業の収益性や成長性を示します。返済計画書には、返済期間や毎月の返済額、返済資金の出所を明確に記し、返済能力の有無を証明してください。
融資の審査では、これらの計画が重要視されるため、金融機関が納得できる現実的な事業計画書を作成しましょう。
4.自己資金の用意
融資を申し込む前に自己資金の用意が必要です。
自己資金は、起業に際して創業者が用意した資金を指し、融資金額に対してある程度の割合を持っていることが推奨されます。
例えば、自己資金が多いほど事業参入への意識が伝わり、審査が有利に働きます。一般的に最低20~30%以上の自己資金を用意しておくのが望ましいでしょう。
例えば、1,000万円の融資を受けたい場合は、最低でも200万円の自己資金を用意しておくと安心です。
また、自己資金は融資限度額にも影響します。自己資金が少ないと想定した融資額を得られない可能性があるため、足りない場合は家族からの支援などの利用も検討しましょう。
5.個人信用情報の確認および問題の解消
融資の審査では、創業者の個人信用情報が重要視されます。
過去のローン返済状況やクレジットカードの利用履歴、延滞記録、自己破産歴などがチェックされ、問題があると融資の可否に悪影響を及ぼします。
個人の信用情報は、主に以下3つの信用情報機関に保管されており、インターネットや郵便で開示請求が可能です。
- CIC(シー・アイ・シー)
- JICC(日本信用情報機構)
- KSC(全国銀行個人信用情報センター)
もし、過去の金融事故に関する情報が残っている場合は、状況や改善策を整理し、融資担当者に説明できるように準備しましょう。
融資の審査に落ちてしまった場合の対応

起業する際に融資を申し込んでも、審査に落ちてしまうケースは少なくありません。
しかし、落ちてしまったからと諦める必要はなく、冷静に原因を分析して次の対応を計画することが大切です。審査で落ちた場合に取るべき具体的な対応策は、以下の通りです。
- 落ちた原因を考えて対策を練る
- 6ヶ月以上の期間を空けてから再審査を申し込む
- 融資先の変更を検討する
- 専門家へ相談する
- その他の資金調達方法を検討する
これらの対応を行い、次回の融資に向けた準備を進めましょう。
落ちた原因を考えて対策を練る
融資の審査に落ちたら、まずは原因の分析が必要です。
金融機関は、自己資金の不足、信用情報の問題、事業計画書の不備や収益性の低さ、返済計画の甘さなど、さまざまな視点から審査を行います。それぞれ対応策が異なるため、原因を追求することで再審査を有利に進められます。
例えば、自己資金の不足であれば資金計画の見直し、事業計画書の問題であれば内容の再検討およびブラッシュアップなど、原因に適した対策が再審査での成功につながります。
6ヶ月以上の期間を空けてから再審査を申し込む
審査落ち後は、すぐに再申請をせずに、6ヶ月以上の期間を空けてから申し込みましょう。
多くの金融機関では、審査後のおおよそ6ヶ月間は再審査の申し込みは避けるべきとされています。これは、6ヶ月の間に問題が解決される可能性が低いからです。
そのため、この空白期間は問題の特定と解決に専念する準備期間と捉えておきましょう。期間を空けて再申請することで、ネガティブな情報がリセットされ、改善された情報で良い評価を得られる可能性が高まります。
融資先の変更を検討する
一つの金融機関で審査に落ちたからといって、すべての融資先で同じ結果になるわけではありません。
審査基準は、金融機関や制度ごとに異なるため、融資先によっては審査通過の可能性は秘めています。
検討すべき代表的な融資先は、以下の通りです。
- 都市銀行
- 地方銀行
- 信用金庫・信用組合
- 日本政策金融公庫
それぞれ条件や得意分野が異なるため、事業内容に合った金融機関への変更を検討するのも効果的です。例えば、地域密着型の信用金庫は地元企業の支援に積極的です。
複数の金融機関の特徴を比較し、視野を広げることが融資成功の可能性を広げます。
専門家へ相談する
融資審査に落ちる原因の特定や対策に自信がない場合は、専門家への相談が有効です。
中小企業診断士や公認会計士、税理士、創業支援を行う地方自治体や商工会議所の窓口、起業の窓口には、融資申請に詳しいプロが在籍しています。原因の特定から事業計画のブラッシュアップ、資金繰りの改善方法、信用情報の対策など、具体的なアドバイスを受けられます。
多くの融資申請に携わってきたプロだからこそ分かるアドバイスの活用は、融資成功につながる有効な手段です。
その他の資金調達方法を検討する
金融機関からの融資が難しい場合は、他の資金調達方法も検討すべきです。
例えば、クラウドファンディングやエンジェル投資家からの出資、国や地方自治体が行う補助金や女性の活用、家族や知人からの借入といった資金調達方法があります。
これらは、融資と異なる基準や条件で資金調達が可能なため、資金繰りの幅を広げます。必要な金額や用途、返済計画に合わせて複数の方法を検討しましょう。
融資以外の資金調達方法

起業する際に融資を借りようとしても、審査に落ちる場合があります。審査に落ちると、資金が少なく起業ができないと考える方も多いでしょう。
審査に落ちた方に向けて、融資以外の資金調達の方法を4つ紹介します。
- 自己資金を使う
- 出資を受ける
- 借入をする
- 補助金や助成金を受ける
下記の表ではメリット・デメリットをまとめています。ぜひ参考にしてみてください。
| 資金調達方法 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 自己資金を使う | 融資の利息や返済に関するリスクを回避できる | 自分で資金を貯める必要がある |
| 出資を受ける | 返済不要の資金が受けられる | 経営に対して意見され、思い通りに行かない可能性がある |
| 他者から借入する | 誰でも資金調達ができる可能性がある | 人間関係を壊す可能性がある |
| 補助金や助成金を受ける | 原則返済をする必要がない | 誰でも必ずもらえるわけではない |
自己資金を使う
起業に必要な資金調達方法の1つに、自己資金を使う方法があります。自己資金を使うことで、融資の利息や返済に関するリスクを回避できます。
融資を受ける際に必要な担保や保証人を用意する必要がなく、手続きが簡単になる点もメリットです。自己資金を活用することで、自分の身銭を切っているという感覚から、事業に真剣に取り組めるようになるでしょう。
出資を受ける
出資とは返済不要の資金を受けることです。
出資の種類には主に下記の3つがあります。
- ベンチャーキャピタル
- エンジェル投資家
- 出資型クラウドファンディング
出資を受けるためには、事業が成長する見込みがないといけません。
ベンチャーキャピタルやエンジェル投資家は、事業投資として行っているため、成長性や将来性がないと判断された場合は、出資してもらえません。ベンチャーキャピタルやエンジェル投資家から出資してもらえると、経営のアドバイスをもらえるのも大きなメリットです。
出資型クラウドファンディングは金融機関と異なり、商品やサービスに共感してもらえると、ネット上で拡散し、資金調達が早くできます。しかし、ネット上に情報が残るため、商品を真似される可能性があるでしょう。
借入する
起業する際の資金を集める1つの方法として、他者から借入する方法があります。借入をする場合、家族や知り合いに依頼する人もいるでしょう。家族や知り合いから借入する場合、銀行と異なり誰でも資金調達できる可能性があります。
しかし、金の切れ目は縁の切れ目と言うように、人間関係が壊れてしまうことも考えられます。家族や知り合いから借入を行う際も、きちんと契約をかわし、決められた通りに返済するなど人間関係が壊れないようにしましょう。
補助金や助成金を受ける
国や地方自治体が行っている補助金・助成金を利用することも、資金調達の方法です。融資はお金をもらったわけではなく借りている状態であるため、必ず返済しなければならず、経営を圧迫する可能性があります。
しかし補助金や助成金を上手く使えば、返済の心配がなく経営を圧迫することもありません。
補助金や助成金は下記の通りです。
補助金や助成金によって、申請の条件が異なるため、利用できるのかどうか確認した上で、申請しましょう。
自己資金なしでも起業できる?【結論】起業できます

結論から言うと、自己資金なしでも起業はできます。初期費用がほとんど必要ない事業やパソコンがあればできる事業の場合、自己資金は必要ありません。
しかし、店舗や事務所を借りた事業をする場合は、まとまった資金が必要になり、自己資金がないと難しいでしょう。店舗や事務所を借りた事業を行いたい場合にはきちんと自己資金を用意しましょう。
今回紹介した融資制度は、自己資金要件がない制度もあり、自己資金なしでも申請要件を満たすことはできますが、実際に融資を受けるのは困難な場合がほとんどです。融資を受けるためには自己資金を準備しておきましょう。
【まとめ】自己資金が少ない場合は融資を受けて資金集めを
今回は、起業時に受けられる融資制度や融資を受ける際のポイントなどについて解説しました。起業する際に、自己資金が少ない場合は融資を受けて資金を集めましょう。
融資によって申請できる条件が異なるため、条件に適しているかどうか判断した上で手続きを行ってください。
会社の銀行口座(法人口座)はGMOあおぞらネット銀行がおすすめ!

画像引用元:GMOあおぞらネット銀行
会社設立時にネットバンクで銀行口座を開設するなら、GMOあおぞらネット銀行がおすすめです。
手間なくスピーディーに口座開設できる点が強みで、口座開設手続きは印鑑レス・ペーパーレス・郵送レスで行うことができます。また、条件を満たせば最短即日で口座を開設できます。
振込手数料は同行宛て無料に加え、他行宛てでも一律143円/件(税込)(※)と低価格で、さらに設立1年未満のお客さまであれば、他行宛て振込手数料が月20回まで無料です。
創業期のお悩みを解決するため、外部企業と提携してさまざまなサービスを紹介するビジネスサポートも行っており、会社運営の面でも強い味方になるでしょう。ぜひGMOあおぞらネット銀行をご利用ください。
(※)2025年8月1日より
起業や開業、独立に興味を持ったら、まずは「起業の窓口」に登録してみよう!
「起業の窓口」では、起業に必要なノウハウや成功者のインタビューなど、さまざまなコンテンツを完全無料で提供しています。
会員特典として、起業・経営支援のプロ「V-Spirits」が監修するオリジナル冊子『会社設立完全ガイド』を無料プレゼント。さらに、V-Spritsによる1時間の無料起業相談や、GMOインターネットグループが展開するビジネスの立ち上げや拡大に役立つ各種サービスをおトクな特典付きでご紹介します。
あなたの夢の実現を全力でサポートします!
- 記事監修
-
- 中野 裕哲 HIROAKI NAKANO
- 起業コンサルタント(R)、経営コンサルタント、税理士、特定社会保険労務士、行政書士、サーティファイドファイナンシャルプランナー・CFP(R)、1 級FP 技能士。 V-Spiritsグループ創業者。東京池袋を本拠に全国の起業家・経営者さんを応援!「あの起業本」の著者。著書16冊、累計20万部超。経済産業 省後援「DREAMGATE」で11年連続相談件数日本一。
GMOインターネットグループ株式会社はGMOあおぞらネット銀行株式会社を所属銀行とする銀行代理業として、円普通預金の受入れを内容とする契約の締結の媒介を行います。
銀行代理業許可番号:関東財務局長(銀代)第335号
- ※本記事は、起業の窓口編集部が専門家の監修または独自調査(アンケート)に基づいて制作したものです。
- ※掲載している情報は、記事公開時点の法令・税制・商品・サービス等に基づくものであり、将来的に変更される可能性があります。
- ※アンケート調査に関する記述は、特定の調査対象者からの回答結果および編集部の見解を含んでおり、内容の正確性・完全性を保証するものではありません。
- ※記事の内容は一般的な情報提供を目的としており、すべての方に当てはまるものではありません。個人の状況に応じた具体的な助言が必要な場合は、専門家にご相談ください。
- ※情報の利用や判断、実施については、ご自身の責任で行っていただきますようお願いいたします。
- ※本記事に掲載された内容の転載・複製はご遠慮いただき、引用の際は必ず出典をご明記ください。



 シェア
シェア