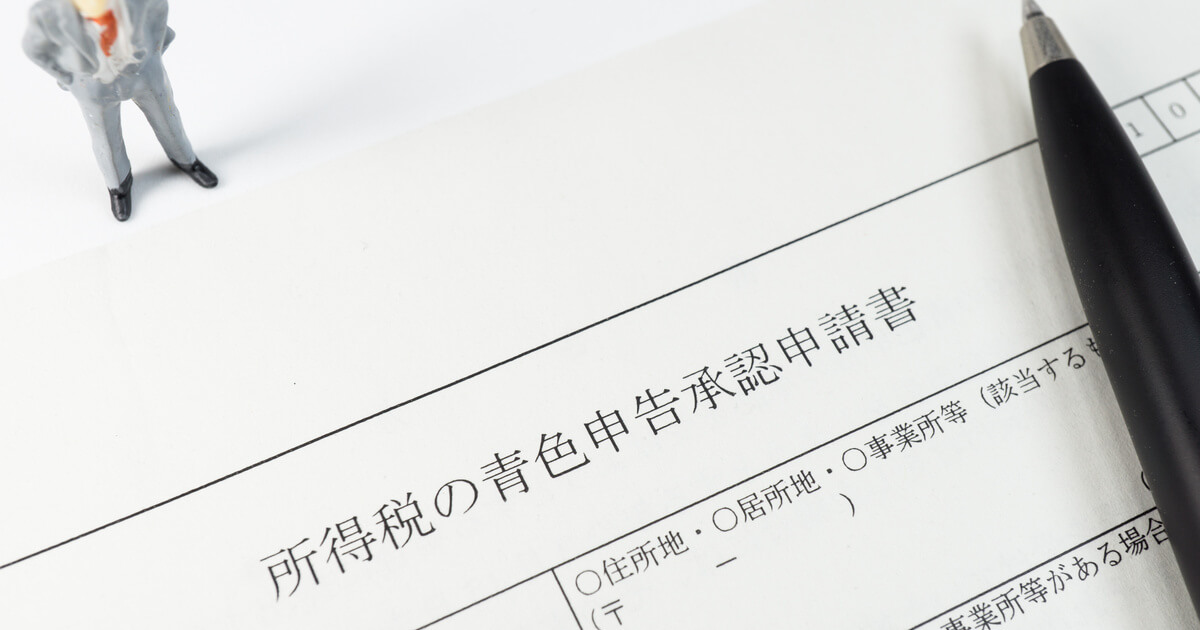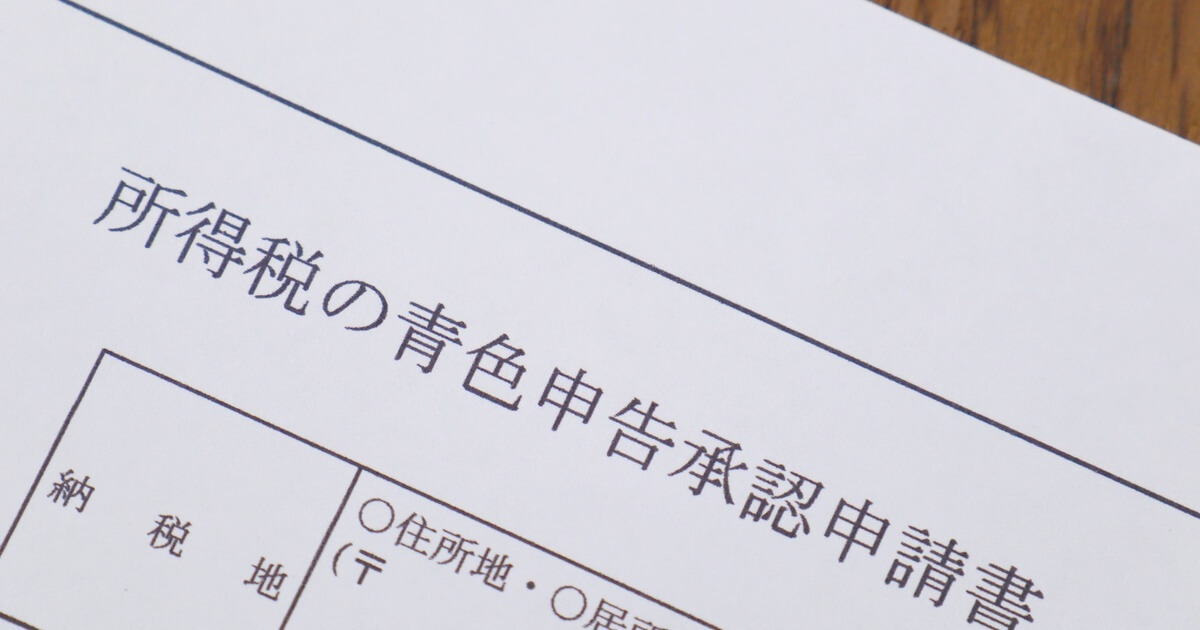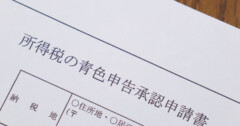個人事業主の手取りの目安|年収別の手取りや計算方法 【早見表付き】

個人事業主の手取りは、年収や経費の計上方法によって大きく変わります。
青色申告と白色申告では控除額の違いにより税負担に差が生じるため、どちらを選択するかが手取り額を左右する重要なポイントです。
また、個人事業主は国民健康保険料や国民年金保険料なども自ら全額負担する必要があり、会社員とは異なる支出構造となっています。税金の計算方法を理解し、適切な節税対策を講じることが、手取りを最大化するための鍵を握ります。
この記事では、個人事業主の手取りの目安や計算方法、節税テクニックなどを早見表を交えて解説します。
- 【この記事のまとめ】
- 売上500万円の個人事業主の手取り収入は、経費次第で異なります。税金としては、所得税と住民税を合計最大約73万円支払います。
- 節税対策として、青色申告やiDeCoの利用、経費の見直しなどが効果的で、これらは手取りを増やすための重要な手段です。
- 個人事業主は国民健康保険や国民年金なども全額自費で負担するため、会社員よりも支払いが多くなる可能性があります。
2025年分(令和7年分)の所得税等の確定申告期間は2026年2月16日(月)から3月16日(月)です。
「起業の窓口」では、青色申告や白色申告の基礎知識、手続きの流れ、節税のコツなどを詳しく解説しています。
ぜひ、「確定申告」に関する他の記事もご覧ください。
2024年11月1日より、フリーランス保護法が施行されます。
組織に所属せずに働くフリーランスが安心して働ける環境を整備するために、フリーランスと企業などとの発注事業者間の取引の適正化(契約書等により取引条件を明示する)が主な目的です。
詳しくは次の記事をご覧ください。フリーランス保護法の概要、制定された背景や具体的な内容などを解説しています。
【年収(青色申告特別控除前の事業所得)別】個人事業主が払う税金と手取りの目安

ここでは、個人事業主が払う税金と手取りの目安を年収別に解説していきます。
国民健康保険料と国民年金保険料は、地域や年齢、扶養状況によって異なるため、平均的な額に基づいて記載しています。扶養親族や配偶者はないものとしています。
青色申告特別控除前の事業所得300万円の手取り
| 青色申告(65万円控除) | 白色申告 | |
|---|---|---|
| 所得税 | 約7万円 | 約10万円 |
| 住民税 | 約15万円 | 約21万円 |
| 個人事業税 | 約5,000円 | 約5,000円 |
| 国民年金保険料 | 約20万円 | 約20万円 |
| 国民健康保険料 | 約24万円 | 約30万円 |
| 手取り金額 | 約230万円 | 約220万円 |
青色申告の場合、青色申告特別控除前の事業所得300万円の手取りは約230万円となります。一方、白色申告は約220万円で、青色申告よりも10万円ほど少なくなります。
青色申告特別控除前の事業所得400万円の手取り
| 青色申告(65万円控除) | 白色申告 | |
|---|---|---|
| 所得税 | 約14万円 | 約20万円 |
| 住民税 | 約24万円 | 約30万円 |
| 個人事業税 | 約5万5,000円 | 約5万5,000円 |
| 国民年金保険料 | 約20万円 | 約20万円 |
| 国民健康保険料 | 約33万円 | 約40万円 |
| 手取り金額 | 約300万円 | 約290万円 |
青色申告特別控除前の事業所得400万円の個人事業主が青色申告を行った場合、手取りは約300万円になります。白色申告の場合は約290万円で、所得税と住民税の負担が青色申告よりも増えるのが特徴です。
青色申告特別控除前の事業所得500万円の手取り
| 青色申告(65万円控除) | 白色申告 | |
|---|---|---|
| 所得税 | 約23万円 | 約34万円 |
| 住民税 | 約33万円 | 約40万円 |
| 個人事業税 | 約10万円 | 約10万円 |
| 国民年金保険料 | 約20万円 | 約20万円 |
| 国民健康保険料 | 約43万円 | 約49万円 |
| 手取り金額 | 約370万円 | 約350万円 |
青色申告特別控除前の事業所得500万円の個人事業主の場合、青色申告と白色申告ですでに大きな差が生まれています。特に白色申告では、所得税と住民税の支払い負担が大きくなっています。
青色申告特別控除前の事業所得600万円の手取り
| 青色申告(65万円控除) | 白色申告 | |
|---|---|---|
| 所得税 | 約40万円 | 約52万円 |
| 住民税 | 約43万円 | 約48万円 |
| 個人事業税 | 約15万5,000円 | 約15万5,000円 |
| 国民年金保険料 | 約20万円 | 約20万円 |
| 国民健康保険料 | 約52万円 | 約58万円 |
| 手取り金額 | 約430万円 | 約400万円 |
青色申告特別控除前の事業所得600万円の個人事業主が青色申告を選択した場合、手取り金額は約430万円になります。白色申告と比べた場合、青色申告のほうが約30万円高くなっています。
青色申告特別控除前の事業所得700万円の手取り
| 青色申告(65万円控除) | 白色申告 | |
|---|---|---|
| 所得税 | 約58万円 | 約70万円 |
| 住民税 | 約52万円 | 約57万円 |
| 個人事業税 | 約20万5,000円 | 約20万5,000円 |
| 国民年金保険料 | 約20万円 | 約20万円 |
| 国民健康保険料 | 約61万円 | 約68万円 |
| 手取り金額 | 約490万円 | 約460万円 |
青色申告特別控除前の事業所得700万円の個人事業主の手取りは、青色申告で約490万円、白色申告で約460万円となります。所得税と住民税の負担が大きくなるため、節税対策の重要性が増してきます。
青色申告特別控除前の事業所得800万円の手取り
| 青色申告(65万円控除) | 白色申告 | |
|---|---|---|
| 所得税 | 約76万円 | 約88万円 |
| 住民税 | 約60万円 | 約67万円 |
| 個人事業税 | 約25万5,000円 | 約25万5,000円 |
| 国民年金保険料 | 約20万円 | 約20万円 |
| 国民健康保険料 | 約71万円 | 約77万円 |
| 手取り金額 | 約550万円 | 約520万円 |
青色申告特別控除前の事業所得800万円の個人事業主が青色申告を行った場合、手取り金額は約550万円になります。白色申告の場合は約520万円で、所得税と国民健康保険料の負担差が拡大します。
青色申告特別控除前の事業所得900万円の手取り
| 青色申告(65万円控除) | 白色申告 | |
|---|---|---|
| 所得税 | 約95万円 | 約110万円 |
| 住民税 | 約70万円 | 約76万円 |
| 個人事業税 | 約30万5,000円 | 約30万5,000円 |
| 国民年金保険料 | 約20万円 | 約20万円 |
| 国民健康保険料 | 約80万円 | 約86万円 |
| 手取り金額 | 約610万円 | 約580万円 |
青色申告特別控除前の事業所得900万円の個人事業主の手取り金額は、青色申告で約610万円、白色申告で約580万円となります。所得税の負担が100万円近くになるため、節税効果の高い青色申告のメリットが大きくなります。
青色申告特別控除前の事業所得900万円の手取り
| 青色申告(65万円控除) | 白色申告 | |
|---|---|---|
| 所得税 | 約120万円 | 約130万円 |
| 住民税 | 約80万円 | 約86万円 |
| 個人事業税 | 約35万5,000円 | 約35万5,000円 |
| 国民年金保険料 | 約20万円 | 約20万円 |
| 国民健康保険料 | 約85万円 | 約85万円 |
| 手取り金額 | 約660万円 | 約640万円 |
青色申告特別控除前の事業所得1,000万円の個人事業主が青色申告を選択した場合でも、所得税の負担額は120万円程度となります。白色申告に関しては130万円近くとなるため、法人化の検討が必要となってきます。
個人事業主の手取りの計算方法

個人事業主の手取り金額は、売上から経費、税金、社会保険料を差し引いて計算します。
売上-(経費+税金+社会保険料)=個人事業主の手取り金額
手取り金額を正確に把握するには、これらの値を適切に見積もる必要があります。特に、税金の計算基準となる課税所得の算出方法を理解しておくことが重要です。
課税所得は、売上から経費や各種控除を差し引いた金額で、この課税所得に税率を乗じて納税額が決まります。
売上-(経費+仕入れ額+基礎控除+その他各種所得控除)=課税所得
個人事業主が支払う主な税金には、所得税、住民税、個人事業税、消費税などがあり、それぞれ計算方法が異なります。金額や計算方法は以下のとおりです。
| 税金の種類 | 金額 | 計算方法 |
|---|---|---|
| 所得税 | 所得に応じて5~45% | 課税所得×税率-税額控除額 |
| 住民税 | 均等割と所得割 | 課税所得×10%+5,000円 |
| 個人事業税 | 業種に応じて3~5% | 課税所得×業種ごとの税率 |
| 消費税 | 前々年の課税売上が1,000万円を超えた場合に発生 (インボイス登録の場合は1,000万円以下でも発生) | ・原則課税:売上にかかる消費税額-仕入れにかかった消費税額 ・簡易課税:売上にかかる消費税額-(売上にかかる消費税額×みなし仕入率) |
個人事業主の実際の手取り金額を算出したい場合は、これらの計算式を活用してください。
住民税に関しては、自治体によって若干異なる可能性があるため確認が必要です。
収支のバランスを見ながら節税対策に取り組むことで、手取り金額の最大化を図っていきましょう。
個人事業主がするべき節税法7選

ここでは、個人事業主がするべき節税法を7つ紹介します。
青色申告を使う
確定申告をする際に青色申告を利用すれば、節税ができます。
青色申告の特徴は以下のとおりです。
- 最大で65万円の特別控除が受けられる
- 取得金額が30万円未満の固定資産の経費を一括で経費として計上できる
- 青色事業専従者給与に関する届出手続きをしている場合、家族従業員の給料を経費として計上できる
- 3年間赤字を繰り返せる
青色申告は帳簿のつけ方が複雑になるというデメリットがありますが、高い節税効果が見込めるため、手取りを増やしたい個人事業主の方は積極的に利用することをおすすめします。
確定申告を楽にしたいと悩む方へ

質問に答えていくだけで、経理の作業がはじめての方でも簡単に確定申告の書類作成をすることができます!
確定申告を楽にサクッとおこないたい方は、freeeがおすすめです!
計上できる経費を見直す
個人事業主が納める所得税は、収入から経費を差し引いて算出されます。そのため、経費にできる費用が多ければ多いほど、納めるべき税金額が少なくなります。
自宅を事務所として使用している個人事業主の方であれば、家賃や光熱費の一部を経費に計上できる可能性があります。このように、一見個人的な出費に見えるものでも経費として計上できるケースがあるため、見直しを行えば節税につながるかもしれません。
iDeCoに加入する
iDeCoに加入すれば、節税につながります。
iDeCoは課税所得金額から掛け金を全額控除することができ、節税になります。
小規模企業共済に加入する
小規模企業共済は、個人事業主の老後資金を準備する公的な制度です。
掛金は全額所得控除の対象となるため、確定申告時の節税効果が期待できます。
掛金は月額1,000円から7万円まで自由に設定でき、共済金の受取額は掛金総額の80~120%に相当します。将来への備えと節税メリットを同時に得られる点で魅力的です。
所得控除を活用する
個人事業主は、青色申告や基礎控除とは別に、所得控除を利用できます。所得控除にはさまざまな種類があり、活用することができれば節税につながります。
所得税の主な種類は以下のとおりです。
- 雑損控除
- 医療費控除
- 社会保険料控除
- 小規模企業共済掛金控除
- 生命保険料控除
- 地震保険料控除
- 寄付金控除
- 障害者控除
- 配偶者控除
- 配偶者特別控除
- 扶養控除
- 基礎控除など
ふるさと納税を利用する
ふるさと納税は、自治体に寄附を行うことで、所得税と住民税から一定額を控除される制度です。
2,000円を超える寄附金については、所得税と住民税から原則として全額が控除の対象となります。
ふるさと納税の活用は、地方自治体への貢献だけでなく、返礼品が受け取れるというメリットもあります。
ただし、確定申告が必要となるため、寄附先の選定や申告手続きには十分な注意が必要です。
法人化を検討する
一定以上の所得がある場合は、法人化を検討することで節税につながる可能性があります。
例えば、課税所得が500万円だった場合、個人事業主であれば所得税と住民税合わせて税率30%です。しかし、課税所得500万円の法人であれば実行税率を23%程度に抑えられます。
法人化するメリットは多くありますが、状況次第ではデメリットの方が多くなることも想定されるため、総合的に考えて判断することが大切です。
個人事業主が利用できる主な控除

個人事業主は、確定申告の際にさまざまな控除を活用することで、税負担を軽減できます。
ここでは、個人事業主が利用できる主な控除を5つ紹介します。
配偶者控除
配偶者控除は、一定の要件を満たす配偶者がいる場合に受けられる所得控除です。
年間の合計所得金額が48万円以下の配偶者が対象となり、納税者本人の所得に応じて最大38万円の控除が適用されます。
老人控除対象配偶者の場合は、最大48万円の控除を受けられるのが特徴です。配偶者の所得や年齢などが控除条件を満たしているか、十分に確認しておきましょう。
医療費控除
医療費控除は、1年間に支払った医療費が一定額を超えた場合に適用される所得控除制度です。
自己や生計を一にする配偶者、その他の親族のために支払った医療費が対象となります。
控除額は、支払った医療費の合計額から保険金等で補填される金額と10万円を差し引いた金額(最高200万円)です。
領収書の保管や計算明細書の作成が必要となるため、日頃から医療費の記録を整理しておくことが大切です。
社会保険料控除
社会保険料控除は、納税者本人や生計を一にする配偶者等が負担した社会保険料について、その支払額の全額が所得から控除される制度です。
健康保険料や厚生年金保険料、介護保険料、国民年金の保険料などが控除の対象となります。
給与所得者の場合、年末調整で社会保険料控除が適用されますが、個人事業主は確定申告での手続きが必要です。
保険料の支払証明書を添付するなど、適切な申告を心がけましょう。
生命保険料控除
生命保険料控除は、生命保険料や介護医療保険料、個人年金保険料を支払った場合に受けられる所得控除です。
平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に係る控除額の計算方法は、それ以前の契約とは異なるため注意が必要です。
控除額は、各保険料の支払額に応じて所定の計算式で算出し、その合計額(最高12万円)を所得から差し引くことができます。
生命保険料控除の適用を受けるには、確定申告時に支払証明書等の提出が必要となります。保険契約の内容と手続きの要件を事前に確認しておくことが重要です。
小規模企業共済等掛金控除
小規模企業共済等掛金控除は、小規模企業共済法に基づく共済契約の掛金等について、その支払額の全額を所得から控除できる制度です。
小規模企業共済の他、確定拠出年金の掛金や障害者扶養共済制度の掛金なども対象となります。
控除を受けるためには、確定申告書に掛金の支払証明書を添付するか、提示する必要があります。
小規模企業共済等への加入は、将来への備えと節税メリットを兼ね備えた有効な選択肢といえるでしょう。
住宅借入金等特別控除
住宅借入金等特別控除は、住宅ローンを利用して住宅の新築や取得をした場合に受けられる税額控除制度です。
一定の要件を満たす必要がありますが、最長13年間にわたって控除が適用されるのが大きな魅力です。
控除額は住宅ローン等の年末残高を基に計算しますが、消費税率の引き上げに伴い、控除率や控除期間などに経過措置が設けられています。
住宅借入金等特別控除の適用を受ける際は、住宅の登記事項証明書や借入金の年末残高証明書など、必要書類の提出を忘れずに行いましょう。
個人事業主が手取りを増やす方法

ここでは、個人事業主が手取りを増やす方法を4つ紹介します。
案件の量を増やす
個人事業主が手取りを増やす最も直接的な方法は、受注する案件の量を増やすことです。
営業活動を強化し、新規顧客の開拓に注力することで、売上アップを目指しましょう。
ただし、案件の増加に伴い、業務量や労働時間も増えることを考慮する必要があります。自身の体力や生産性を見極め、無理のない範囲で案件を増やしていくことが重要です。
また、案件の獲得と並行して業務の効率化や外注化なども検討し、収益性の向上を図ることが望ましいでしょう。
高単価の案件に挑戦する
案件の単価を引き上げることも、個人事業主の手取りアップに効果的です。
提供するサービスの質を高め、専門性や付加価値を打ち出すことで、高単価案件の獲得を目指します。自身のスキルアップに投資し、市場のニーズを的確に捉えた提案力を養うことがポイントです。
高単価案件にチャレンジするためには、自己PRや営業力の強化も欠かせません。ポートフォリオの充実や実績の積み重ねを通じて、高い評価と信頼を獲得していきましょう。
NISAで資産形成する
NISA(少額投資非課税制度)は、投資による資産形成を税制面から支援する制度です。
NISAで購入した金融商品の配当金や売却益に対しての税金がかかりません。
事業から得た所得の一部をNISAに投資することで、中長期的な資産形成が可能です。
NISAには、年間240万円を上限とする成長投資枠と、年間120万円を上限とするつみたて投資枠の2種類があります。
自身のライフプランや投資目的に合わせて、適切な商品を選択することが重要です。
プロや専門家に相談する
個人事業主が手取りを増やすためには、税務や財務の専門知識が不可欠です。
確定申告の際の節税対策や、資金繰りの改善など、専門的なアドバイスが得られるプロに相談しましょう。
例えば、税理士や公認会計士、中小企業診断士など、事業運営を支援する専門家は数多くいます。
課題に応じて特定の分野に強いプロに依頼すれば、手取りを最大化できるだけではなく、事業課題の解決にも繋がります。
個人事業主の手取りは、年収や経費の計上方法によって大きく変わる
個人事業主の手取りは、売上から必要経費や税金、社会保険料を差し引いて算出します。
青色申告の活用や経費の見直し、各種控除の適用など、さまざまな節税対策を講じることで、手取り金額を最大化することが可能です。
一方で、収入が増えるほど税負担も大きくなるため、高収入の個人事業主は法人化のメリットを検討する必要もあるでしょう。
事業の成長に合わせて、柔軟に対応策を練ることが重要です。また、iDeCoやNISAを活用した資産形成や、専門家に相談しながらの財務管理など、中長期的な視点に立った取り組みも欠かせません。
正しい知識と戦略的な行動で、個人事業主としての財務基盤を着実に強化していきましょう。
「起業の窓口」では、個人事業主の方々に向けて、業務効率化のヒントや成功事例、最新のビジネス情報など、お役立ち情報を提供しています。
ぜひ、「個人事業主」に関する他の記事もご覧ください。
起業や開業、独立に興味を持ったら、まずは「起業の窓口」に登録してみよう!
「起業の窓口」では、起業に必要なノウハウや成功者のインタビューなど、さまざまなコンテンツを完全無料で提供しています。
会員特典として、起業・経営支援のプロ「V-Spirits」が監修するオリジナル冊子『会社設立完全ガイド』を無料プレゼント。さらに、V-Spritsによる1時間の無料起業相談や、GMOインターネットグループが展開するビジネスの立ち上げや拡大に役立つ各種サービスをおトクな特典付きでご紹介します。
あなたの夢の実現を全力でサポートします!
- 記事監修
-
- 中野 裕哲 HIROAKI NAKANO
- 起業コンサルタント(R)、経営コンサルタント、税理士、特定社会保険労務士、行政書士、サーティファイドファイナンシャルプランナー・CFP(R)、1 級FP 技能士。 V-Spiritsグループ創業者。東京池袋を本拠に全国の起業家・経営者さんを応援!「あの起業本」の著者。著書16冊、累計20万部超。経済産業 省後援「DREAMGATE」で11年連続相談件数日本一。
- ※本記事は、起業の窓口編集部が専門家の監修または独自調査(アンケート)に基づいて制作したものです。
- ※掲載している情報は、記事公開時点の法令・税制・商品・サービス等に基づくものであり、将来的に変更される可能性があります。
- ※アンケート調査に関する記述は、特定の調査対象者からの回答結果および編集部の見解を含んでおり、内容の正確性・完全性を保証するものではありません。
- ※記事の内容は一般的な情報提供を目的としており、すべての方に当てはまるものではありません。個人の状況に応じた具体的な助言が必要な場合は、専門家にご相談ください。
- ※情報の利用や判断、実施については、ご自身の責任で行っていただきますようお願いいたします。
- ※本記事に掲載された内容の転載・複製はご遠慮いただき、引用の際は必ず出典をご明記ください。
関連記事
30秒で簡単登録
厳選サービスを特典付きでご紹介



 シェア
シェア