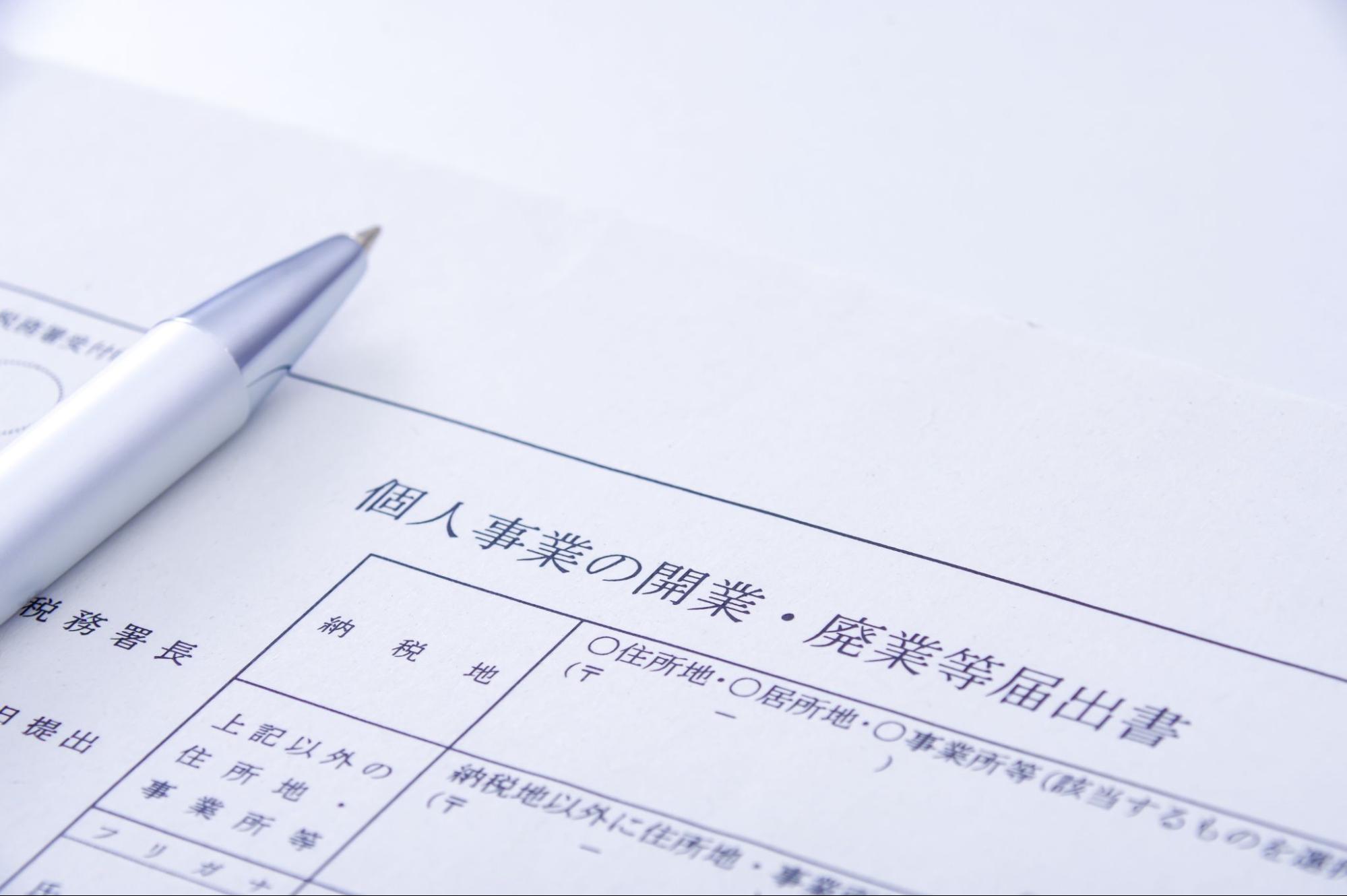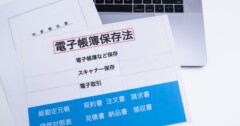創業融資は個人事業主でも可能?受ける方法と必要書類、審査のポイントを解説

個人事業主として今後事業を始めようと考えているなら、創業融資について知っておいて損はありません。融資を受けるにあたっては、融資のメリットや審査のポイントなどを理解しておく必要があるでしょう。
この記事では、個人事業主が創業融資を受ける方法や融資のメリット、審査ポイントなどについて説明します。最後までお読みいただければ、「個人事業主の方が融資を受ける方法」を正しく理解できるでしょう。
- 【この記事のまとめ】
- 個人事業主が創業融資を受けるには、日本政策金融公庫や自治体の制度融資が有効です。無担保で迅速な融資や地域の優遇措置が受けられます。
- 融資のメリットには、資金繰りの安定、返済実績による信用向上、事業の将来設計が挙げられます。長期的な経営を視野に入れるきっかけにもなります。
- 融資審査では、自己資金の状況や事業計画書、信用情報などが重要です。不安があれば、事前に日本政策金融公庫や信用保証協会に相談するのが効果的です。
2024年11月1日より、フリーランス新法(フリーランス保護法、フリーランス保護新法)が施行されます。
組織に所属せずに働くフリーランスが安心して働ける環境を整備するために、フリーランスと企業などとの発注事業者間の取引の適正化(契約書等により取引条件を明示する)が主な目的です。
詳しくは次の記事をご覧ください。フリーランス新法の概要、制定された背景や具体的な内容などを解説しています。
「起業の窓口」では、AIインフルエンサーの茶圓氏とコラボをおこない、AIを活用してビジネスの効率化を図るための貴重な知識を提供しています。
特集ページ「AI×起業」では、最新のAI技術やツールを使った実践的なアプローチを紹介しており、起業家や個人事業主の業務をよりスマートにサポートします。
AIの力で業務の負担を軽減し、ビジネスの成長を加速させたい方に最適な情報が満載です。ぜひご覧ください。
「起業の窓口」の特集ページ「起業家インタビュー」では、実際に成功を収めた起業家たちの貴重なインタビューが充実しています。リアルな体験や苦労、成功までの道のりを通じて、これから起業を目指す方々に向けた実践的なアドバイスを提供しています。
さまざまな分野で活躍する起業家の声を通して、ビジネスのヒントやインスピレーションを得られるコンテンツが満載です。ぜひインタビューを参考にして、自分のビジネスに活かしてみてください。
【基礎知識】創業融資とは

創業融資は、事業の立ち上げ段階で金融機関などから資金を調達する制度です。
ここでは、創業融資の基礎知識として以下を解説します。
- 創業融資の特徴
- 個人事業主と法人の融資の違い
- 創業融資を受けるべきタイミング
それぞれ詳しく見ていきましょう。
創業融資の特徴
創業融資の特徴は、創業初期において事業計画や自己資金などをもとに審査されるため、売上などの実績がない段階で資金調達できる点です。
低金利・長期返済が可能な条件が整っており、起業家が利用しやすい仕組みとなっています。資金が必要な創業時に、事業計画の内容と将来への見通しをもとに融資を受けられるメリットがあります。
原則として日本政策金融公庫や民間金融機関、自治体の制度融資を利用でき、中でも日本政策金融公庫の創業融資は使いやすく、多くの起業家に利用されている制度です。
運転資金や設備資金など、起業に不可欠な資金の調達方法として幅広く認知されています。
個人事業主と法人の融資の違い
創業融資において、個人事業主と法人で審査基準が重視される点は同様ですが、保証条件や信用力などで審査傾向に差が出る可能性があります。
審査の本質は事業計画や資金用途、返済能力など事業の中身であり、事業の形態よりも内容や経験、自己資金、信用情報が重視されます。そのため、審査条件や融資の可能性は個人・法人どちらでもほぼ同等です。
また、法人の場合、無担保・無保証人の融資なら、法人が破産しても、連帯保証人でない代表者個人は返済責任を負いません。個人事業主の場合も同様です。
また、法人は社会的信用やブランド価値で有利になる場合もあるため、大規模な資金調達や成長性を求めるのであれば法人化するメリットもあります。
創業融資を受けるべきタイミング
創業時期が早いほうが実績なし段階での融資が有利とされることが多いため、早めの申し込みが一つの戦略となりますが、最適なタイミングは事業準備の完成度などと合わせて判断すべきです。
このタイミングで申請すれば、事業計画の内容や将来性で評価されやすく、過去の実績が審査対象にならないため融資審査に有利です。創業後しばらくして実績が十分でない場合、審査ハードルが上がるため、早めの申込が成功の秘訣となります。
具体的には、審査や必要書類の準備、融資実行までの期間を考慮し、事業開始2~3か月前から計画を進めるのが理想です。この時期に事業計画書や返済計画をしっかり準備しておけば、面談もスムーズに進み、自己資金が十分あれば審査通過率も高まります。
融資が事業開始までに行われることで、運転資金や設備投資など必要な資金繰りに余裕を持って、事業をスタートさせることが可能です。
個人事業主が創業融資を受ける方法

個人事業主が創業時に融資を受ける方法について説明します。具体的に個人事業主が融資を受ける方法は以下の2つがあります。
- 【個人事業主が創業時に融資を受ける方法】
-
- 日本政策金融公庫の創業融資
- 自治体の制度融資
日本政策金融公庫
個人事業主が創業時に融資を受ける1つ目の方法は「日本政策金融公庫」の利用です。
日本政策金融公庫は、100%政府が出資する金融機関であり、個人事業主や中小企業など様々な事業を行う方に対して融資制度を提供している特徴があります。
日本政策金融公庫で融資を受ける最大のメリットは、「融資実行までのスピードが早いこと」です。申込から融資実行までの目安はおおよそ1か月程度ですが、申込内容・書類の充実度や担当機関の状況によって前後します。借入期間も長く設定することもでき、返済期間は5年以上、元金の据え置き期間も設定できるため、様々な個人事業主の資金計画に合わせた返済方法を選べます。
融資を受ける際にしっかりと審査をするため、「返済能力を説明するための多くの書類や資料の準備」が必要になります。
自治体の制度融資
自治体の制度融資とは、自治体と銀行や信用金庫といった民間金融機関、公的機関である信用保証協会の三者が協調して行っている融資制度です。
自治体と信用保証協会がバックアップすることで、信用力の低い中小企業や個人事業主でも民間金融機関から融資を受けやすくなります。民間金融機関が創業者向けの融資を行う場合はこの自治体の制度融資を活用するのが一般的です。
地域性を活かした優遇が受けられる場合もあり、地元で創業したい個人事業主の方におすすめする融資制度です。
個人事業主が融資を受けるメリット

個人事業主が融資を受ける際には3つのメリットがあります。
- 【個人事業主が融資を受けるメリット】
-
- 資金繰りが安定する
- 信用金庫や銀行に対して返済実績を作れる
- 事業の将来設計を綿密に練るきっかけになる
ここから詳しく解説していきます。
資金繰りが安定する
個人事業主が融資を受けることで、資金繰りが安定するメリットが考えられます。
融資は、一時的に手元のお金を増やすことができます。融資を受けることで、個人事業主が創業時に必要になるまとまった資金を確保しやすくなります。
資金繰りが悪化していると、お金のことが頭をよぎり事業に支障をきたす可能性もあります。
そんな時に融資を受けることができれば、資金に余裕を持った状態で目先の売上だけに捉われず、長期的な目線で事業運営を行えるでしょう。
信用金庫や銀行に対して返済実績を作れる
信用金庫や銀行などで融資を受けた場合、返済実績を作ることにも繋がります。
特に銀行は、企業の実態が分からない場合や返済期日を守らない人には融資を行いません。返済実績があることで次回の融資希望時にも銀行や信用金庫からの評価が高くなりやすくなり、融資も受けやすくなるでしょう。
また、融資を受けて数年間安定した経営を行っていれば、銀行や信用金庫からの信頼も高まり、将来追加の融資が期待できます。
事業の将来設計を綿密に練るきっかけになる
個人事業主が融資を受けるメリットとして「事業の将来設計を綿密に練るきっかけに繋がる」ということも挙げられます。
「融資を受ける」という行動は、事業計画書作成にあたり将来を見越した計画を立てるため、詳細な将来設計を行います。そのため、目先の利益や売上に捉われず、個人事業主として将来ビジョンや計画を再設定するきっかけになります。
事業計画を作成することで、長期的な事業運営にも必ず役に立ちます。
自己資金を温存できる
個人事業主が融資を受ける大きなメリットは、自己資金を温存できることです。
融資を活用することで、手元の自己資金を切り崩さずに事業運転資金や設備投資資金を確保し、資金繰りに余裕を持たせることができます。これにより、不測の支出や急な資金需要にも対応しやすくなり、安定した事業経営を維持することが可能です。
また、自己資金を温存させることで、事業の成長・拡大に必要な新たな投資機会を逃さずに済むメリットもあります。さらに金融機関からの融資は低金利で借りられる場合が多く、長期返済の設定もできるため、返済負担が分散されやすい点も自己資金に負担をかけないメリットです。
融資を計画的に利用・返済することで、金融機関との関係も良好になり、将来さらなる資金調達がスムーズになります。
無担保・無保証人でも借りられる制度がある
個人事業主が受けられる融資の中には、日本政策金融公庫が提供する「新規開業・スタートアップ支援資金」のように、無担保・無保証でも借りられる制度もあります。
この制度の大きなメリットは、自己所有の不動産を担保に差し入れる必要がなく、連帯保証人を立てる必要もないため、創業者のリスクを大幅に軽減できる点です。
ただし、無担保・無保証人である分、金融機関は借入者の返済能力や事業計画の実現可能性も厳しく審査します。自己資金の一定割合の準備が求められることも多いため、事前に融資を受ける条件を確認しておくことも大切です。
こうした無担保・無保証人の融資制度は、創業者が安心して資金調達できる重要な支援策であり、担保がなかったり、リスクを少なく起業したい起業家に適しています。
創業融資の申請に必要な書類一覧

創業融資の申請には、以下の書類が必要となるため、慌てないためにも事前に準備しておきましょう。
- 借入申込書・創業計画書
- 見積書や契約書などの証憑資料
- 本人確認書類と通帳コピー
- 過去の確定申告書
それぞれ解説します。
借入申込書・創業計画書
借入申込書・創業計画書は、創業融資申請の際に必須の書類です。
申込先金融機関によって様式が異なることがあるため、提出先の指示に沿って準備する必要があります。
借入申込書は、融資の基本情報を記入するもので、申込者の氏名、借入希望額、返済期間、資金用途などを記載します。各金融機関や日本政策金融公庫の窓口やWebサイトから入手可能です。
創業計画書は、事業の目的、経営者の経歴、取り扱う商品・サービス、収支見込みや、今後の事業展望などを記載します。
創業者の事業実現可能性を金融機関に示す役割があり、審査の中心資料となるため、わかりやすく具体的に作成することが重要です。
見積書や契約書などの証憑資料
創業融資の申請にあたり、見積書や契約書などの証憑資料は、資金用途を裏付ける重要な書類として求められます。
特に設備投資や仕入れなど、融資金を使う具体的な目的がある場合は、その費用の根拠を示すために見積書が必要です。さらに、取引先との契約内容を証明する契約書も、事業の信頼性や資金用途の正当性を示すために提出が求められることがあります。
これらの証憑資料が整っていることは金融機関の審査通過に有利に働き、申請者の信用力向上につながります。
加えて、見積書や契約書以外にも許認可証のコピーや納品書、支払証明書など、事業の実態を証明できる各種証憑資料を準備しておくことが望ましいです。
本人確認書類と通帳コピー
本人確認書類と通帳コピーは、創業融資申請の基本書類です。
これらの書類は、審査の透明性を高めるために必要不可欠なものとして、書類不備がないように事前に準備することが大切です。
本人確認書類は、一般的には運転免許証の両面コピーや、パスポートの顔写真ページと住所記載ページのコピーが用いられます。これは、申込者が実在することや申込内容に虚偽がないことを証明するために必要な書類です。
通帳コピーは、事業用または個人用の預金通帳の記帳や取引明細のコピーを提出し、資金の流れや返済能力を金融機関に示すために使われます。
ネットバンキングの明細も紙に印刷して提出するケースが多く、金融機関は通帳の取引履歴を確認し、資金用途の妥当性や安定した資金管理ができているかを審査します。
過去の確定申告書
創業後に創業融資の申請を行う際、個人事業主の収入や経営状況を示すために過去の確定申告書が必要です。
過去2~3期分の確定申告書の提出が求められ、これにより金融機関は事業の安定性や返済能力を評価します。創業前の場合でも確定申告書が必要ないケースもあるため、申し込みをする前に確認しておきましょう。
なお、税務申告がされていないと審査ができず、税務申告の実績が整うまで審査が見送られるケースもあります。
また、直近が会社員であった場合は源泉徴収票の提出が求められる場合もあります。勤務先からの発行となるため、手元にない場合は再発行が必要です。源泉徴収票が用意できない場合、給与明細書や代替書類の提出が求められる場合もあります。
金融機関はこれらの書類を使って、返済能力や信用度を総合的に判断します。
【重要】融資を受ける際に押さえておくべき審査のポイント

融資を受けたくとも、審査に受からなければ意味がありません。ここでは、融資を受ける際に押さえておくべき審査のポイントを5つ説明します。
- 【融資を受ける際に押さえておくべき審査のポイント】
-
- 現在の資産状況
- 事業計画書
- 開業に至るまでの経歴・実績
- 過去の信用情報
- 資金使途
- 自己資金の有無と割合
- 売上予測の妥当性
現在の資産状況
まずは、現在の資産状況を確認することが重要です。
自己資金が多いほど、金融機関としては「計画的に資金を貯められる人材」と判断されます。また、親族からの返済不要な資金支援が得られる場合も自己資金の中に含まれる場合があります。融資を受ける際には自己資金の状況をまずは確認してみましょう。
もし、自己資金が少ない場合、たとえ信用情報に問題がなかったとしても金融機関が難色を示す場合があります。
そのため、融資を受ける前には自己資金をどのくらい用意できるのかを再確認しておきましょう。
事業計画書
事業計画書は融資審査に大きく影響を与える書類です。
また、「なぜ希望する融資額が必要なのか」を示す根拠となる書類でもあります。事業計画書に記載する項目としては、「事業を継続させるだけの目的ではなく、成長させ伸ばしていく方法」を具体的に記入します。
さらに明確な目標や市場調査、競合他社、ターゲット層の選定も事業計画書への記載は必須項目です。個人事業主として収支計画を綿密に立て、説得力のある事業計画書の作成をおすすめします。
「起業の窓口」の特集ページ「AI×起業」では、AIを活用して事業計画書を簡単に作成する方法を紹介!
詳しくは「【できるのか?】ChatGPTを使ってたった1時間で事業計画書を書くアラフォー起業家。《小説「AI起業」シリーズ#01》」をご覧ください。
開業に至るまでの経歴・実績
開業に至るまでの経緯や実績も、融資を受ける際に押さえてほしいポイントの1つです。
開業に至るまでの経緯・実績とは、これまで経験してきた職種の中でアピールできる経歴や実績のことをいいます。また同業他社で3年程度の経歴があるのかどうかも融資審査の大きな判断材料となります。
創業融資の場合でも、事業自体の実績はプラス材料です。事業を進められる場合は、早く進め実績をつくりましょう。
過去の個人信用情報
審査前に確認してほしいポイントが「過去の個人信用情報」です。
過去の個人信用情報とは、クレジットやローン契約、申込履歴などの個人での取引情報のことを意味します。金融機関はJICC(株式会社日本信用情報機構)や全国銀行個人信用情報センター、CIC(株式会社シー・アイ・シー)などの個人信用情報を元に融資の判断材料にしています。
そのため、滞納履歴がある場合やブラックリスト入りしている場合には融資が通過しにくい傾向があります。
資金使途
資金使途も融資を受ける上では重要なポイントです。
資金用途は大きく分けて「設備資金」と「運転資金」の2つがありますが、提示していた資金使途以外の理由で資金を利用した場合には、その後の信用に関わり、一括での返済を求められる可能性も考えられます。
明確な資金使途を説明できるように、融資を受ける前から準備しておく必要があるでしょう。
自己資金の有無と割合
創業融資の審査で重視されるポイントの一つが自己資金の有無と割合です。
自己資金は事業にかける本気度やリスク管理能力の証明となり、融資審査で有利に働きます。特に融資希望額の半分から3分の1程度を自己資金として準備していることが望ましく、多ければ多いほど返済能力の評価も高まります。
金融機関は申請者の預金通帳をさかのぼり、自己資金の入金実績や入金の根拠などをチェックするのが一般的です。他人からの借入は基本的に自己資金とは認められず、贈与かどうかや返済能力の有無も審査されます。
自己資金が十分であれば、金融機関は返済リスクが低いと判断し、審査通過率が上がるため、計画的な資金準備が創業融資を成功させるうえで重要な要素です。
売上予測の妥当性
売上予測の妥当性は、創業融資審査の重要ポイントです。
金融機関は予測された売上が現実的かつ信頼できるかを厳しく評価します。具体的には、市場調査に基づいた以下の根拠ある数字が求められます。
- 競合状況
- 顧客ターゲット
- 過去のデータ
- 市場調査
売上予測は市場全体から自社シェアを割り出すトップダウン方式と、顧客数・単価・購入頻度の積み上げで割り出すボトムアップ方式を用いるのが基本です。予測が過度に楽観的でなく、整合性のある計画を提示すると信頼性を高められます。
さらに売上が予測を下回った場合のリスク対策や具体的な対応策も計画に盛り込むことで、融資担当者に安心感を与えられます。
【注意】融資実行後の注意点
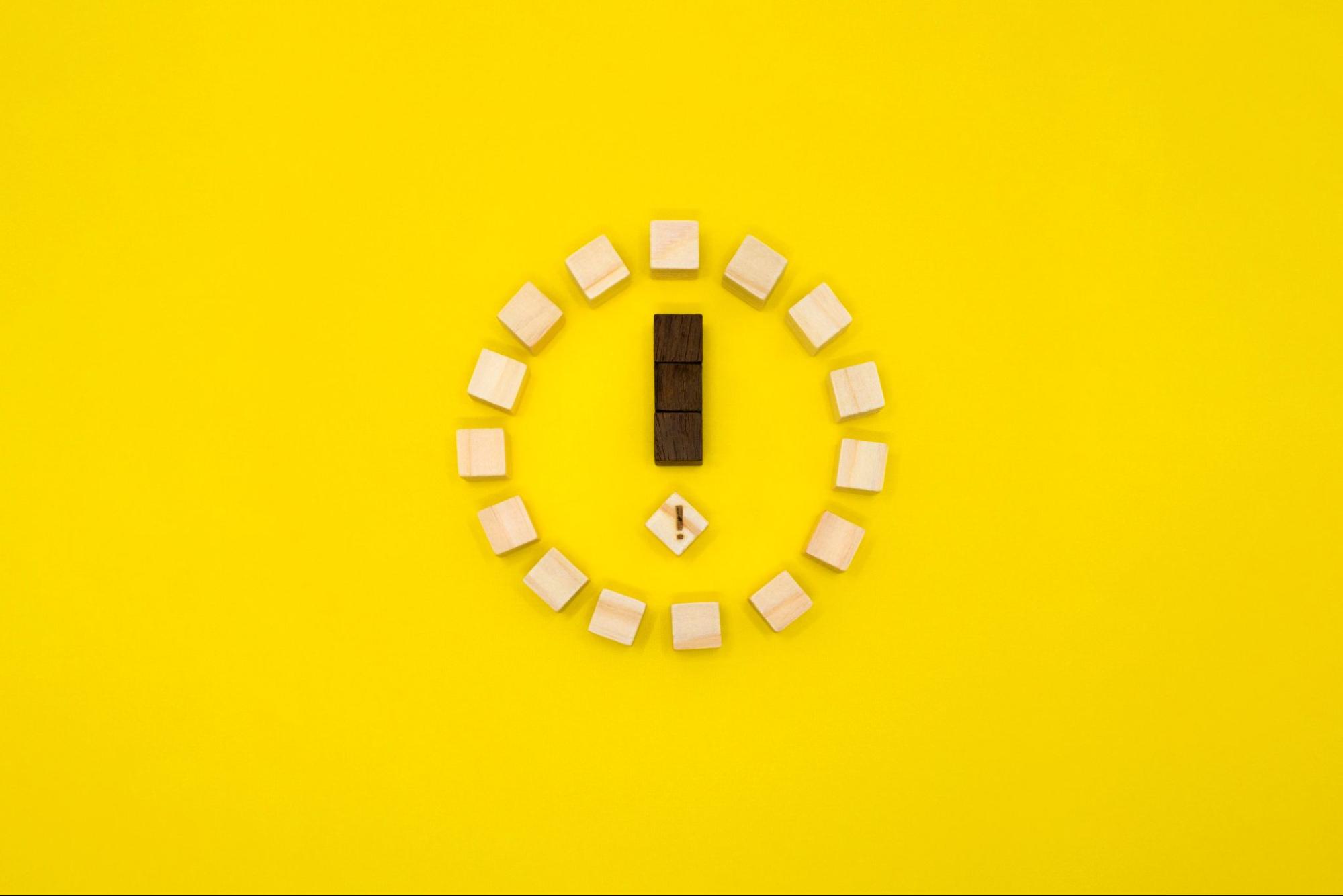
創業融資を受けた後は、以下に注意する必要があります。
- 資金使途の管理を徹底する
- 返済スケジュールの把握と資金繰りの見直し
- 次回の借入に向けた信用構築
それぞれのポイントを解説します。
資金使途の管理を徹底する
創業融資を受けたあとは、資金使途の管理を徹底することが重要です。
融資を受けた資金は、申請時に示した使い方に沿って正しく使わなければならず、運転資金や設備投資など用途ごとに分けて管理することで不正利用を防げます。特に設備資金は見積書等で根拠を示した内容に基づき使用し、使途違反は返済停止や一括返済を要求されるリスクにつながります。
明確な資金使途計画に基づき支出の証拠として領収書や契約書などを整理し、金融機関の問い合わせに備えることも大切です。
返済スケジュールの把握と資金繰りの見直し
融資実行後は、返済スケジュールを正確に把握し、計画的な返済を行う必要があります。
返済遅延は信用低下の原因となり、今後の資金調達や事業運営に支障をきたすため、月々の返済額や返済期日をしっかり把握しましょう。また、売上の変動や不測の事態に備えて定期的に資金繰りを見直し、必要に応じて支出抑制や追加資金調達を検討することも重要です。
資金繰り表を活用するなど、客観的な現状把握を行い、適切に経営改善を図りましょう。
次回の借入に向けた信用構築
融資を受けた後は、きちんと返済を続けることで金融機関からの信頼を築くことが重要です。
返済の遅延や未払いがないことは、将来の追加融資やよりよい条件での借入を受けるための基礎となります。また、経営状況や資金使途についても透明性を保ち、金融機関と良好な関係を維持することが次回融資成功へのポイントです。
定期的な報告や相談を怠らず、問題があれば早期に共有して対策を講じる姿勢が、良好な関係維持と金融機関からの評価向上につながります。
【結論】融資申請前に不安を感じた場合は相談をするのがベスト

個人事業主の方が創業融資を申請する際、不安を感じることは少なくありません。
そのような場合、税理士だけでなく日本政策金融公庫や信用保証協会、自治体の窓口などに相談することが大切です。一人で悩まずに相談することで、融資申請の準備や審査通過のコツを得られ、安心して手続きに臨むことができます。
創業融資は実績のない個人事業主にとってはハードルが高い面もありますが、日本政策金融公庫や自治体の制度を上手に活用すれば、目標額の融資を得られる可能性は十分にあります。重要なのは、焦らずに事業計画や長期的な経営方針を綿密に準備することです。
この記事を参考に、しっかりと準備をしてから創業融資の利用を検討してください。
「起業の窓口」では、個人事業主の方々に向けて、業務効率化のヒントや成功事例、最新のビジネス情報など、お役立ち情報を提供しています。
ぜひ、「個人事業主」に関する他の記事もご覧ください。
会社の銀行口座(法人口座)はGMOあおぞらネット銀行がおすすめ!

画像引用元:GMOあおぞらネット銀行
会社設立時にネットバンクで銀行口座を開設するなら、GMOあおぞらネット銀行がおすすめです。
手間なくスピーディーに口座開設できる点が強みで、口座開設手続きは印鑑レス・ペーパーレス・郵送レスで行うことができます。また、条件を満たせば最短即日で口座を開設できます。
振込手数料は同行宛て無料に加え、他行宛てでも一律143円/件(税込)(※)と低価格で、さらに設立1年未満のお客さまであれば、他行宛て振込手数料が月20回まで無料です。
創業期のお悩みを解決するため、外部企業と提携してさまざまなサービスを紹介するビジネスサポートも行っており、会社運営の面でも強い味方になるでしょう。ぜひGMOあおぞらネット銀行をご利用ください。
(※)2025年8月1日より
起業や開業、独立に興味を持ったら、まずは「起業の窓口」に登録してみよう!
「起業の窓口」では、起業に必要なノウハウや成功者のインタビューなど、さまざまなコンテンツを完全無料で提供しています。
会員特典として、起業・経営支援のプロ「V-Spirits」が監修するオリジナル冊子『会社設立完全ガイド』を無料プレゼント。さらに、V-Spritsによる1時間の無料起業相談や、GMOインターネットグループが展開するビジネスの立ち上げや拡大に役立つ各種サービスをおトクな特典付きでご紹介します。
あなたの夢の実現を全力でサポートします!
- 記事監修
-
- 中野 裕哲 HIROAKI NAKANO
- 起業コンサルタント(R)、経営コンサルタント、税理士、特定社会保険労務士、行政書士、サーティファイドファイナンシャルプランナー・CFP(R)、1 級FP 技能士。 V-Spiritsグループ創業者。東京池袋を本拠に全国の起業家・経営者さんを応援!「あの起業本」の著者。著書16冊、累計20万部超。経済産業 省後援「DREAMGATE」で11年連続相談件数日本一。
GMOインターネットグループ株式会社はGMOあおぞらネット銀行株式会社を所属銀行とする銀行代理業として、円普通預金の受入れを内容とする契約の締結の媒介を行います。
銀行代理業許可番号:関東財務局長(銀代)第335号
- ※本記事は、起業の窓口編集部が専門家の監修または独自調査(アンケート)に基づいて制作したものです。
- ※掲載している情報は、記事公開時点の法令・税制・商品・サービス等に基づくものであり、将来的に変更される可能性があります。
- ※アンケート調査に関する記述は、特定の調査対象者からの回答結果および編集部の見解を含んでおり、内容の正確性・完全性を保証するものではありません。
- ※記事の内容は一般的な情報提供を目的としており、すべての方に当てはまるものではありません。個人の状況に応じた具体的な助言が必要な場合は、専門家にご相談ください。
- ※情報の利用や判断、実施については、ご自身の責任で行っていただきますようお願いいたします。
- ※本記事に掲載された内容の転載・複製はご遠慮いただき、引用の際は必ず出典をご明記ください。
関連記事
- 起業・創業の新着記事
- 起業・創業の人気記事ランキング
- タグリスト
- AI×起業
- AI×起業特集はこちら
- 起業家インタビュー
- 起業家インタビュー一覧はこちら
- 監修者・執筆者一覧
- 監修者・執筆者一覧はこちら



 シェア
シェア