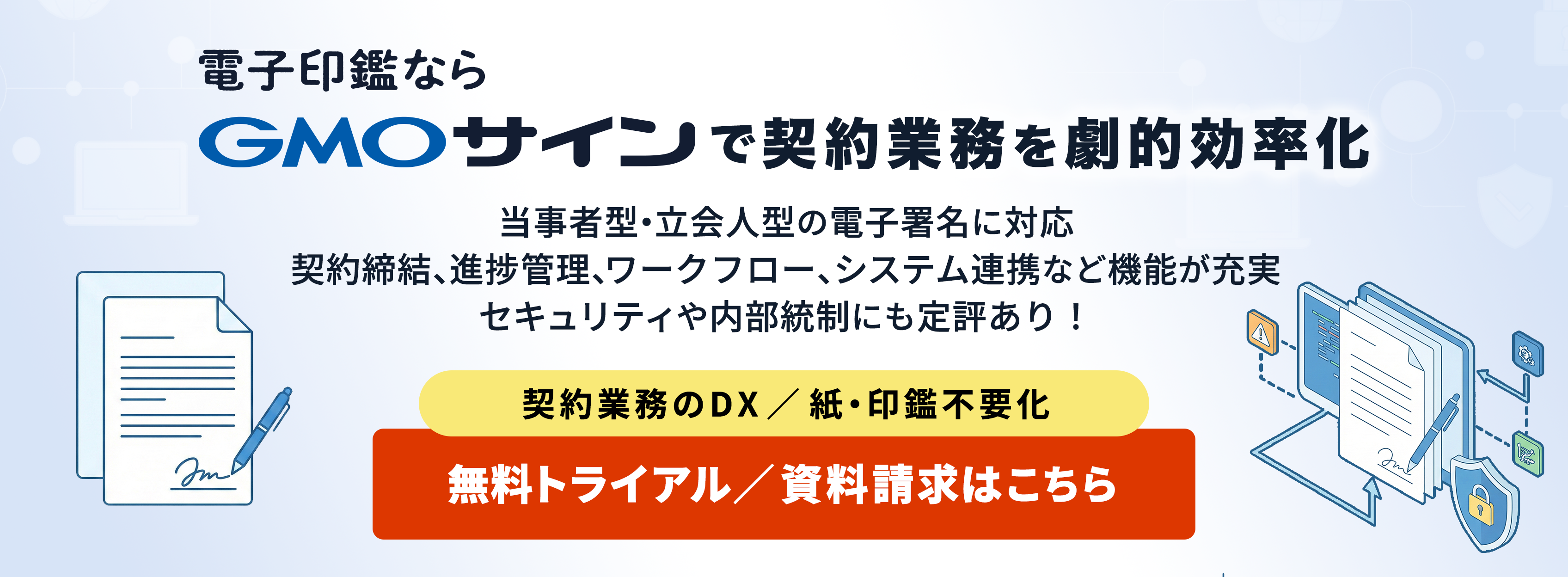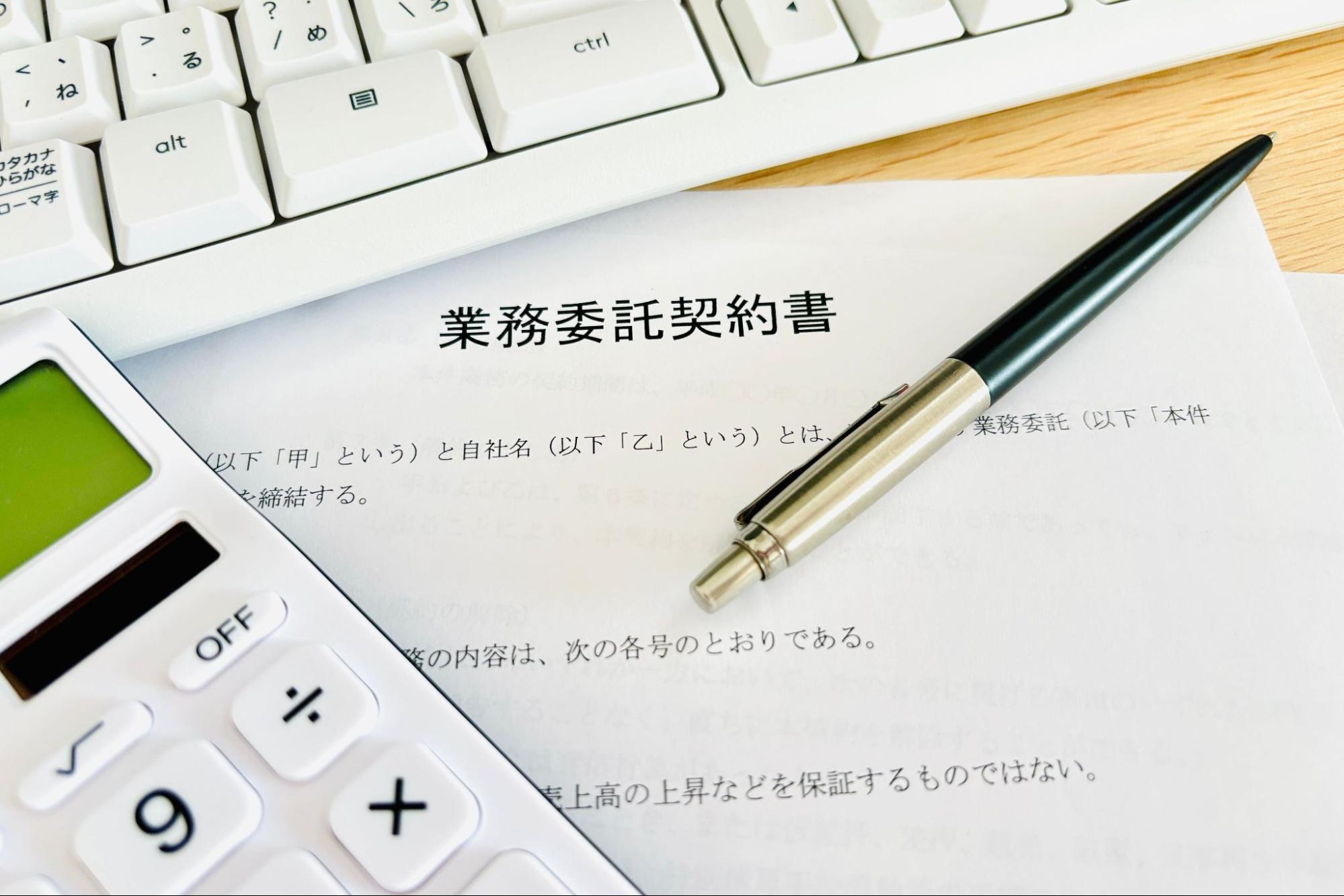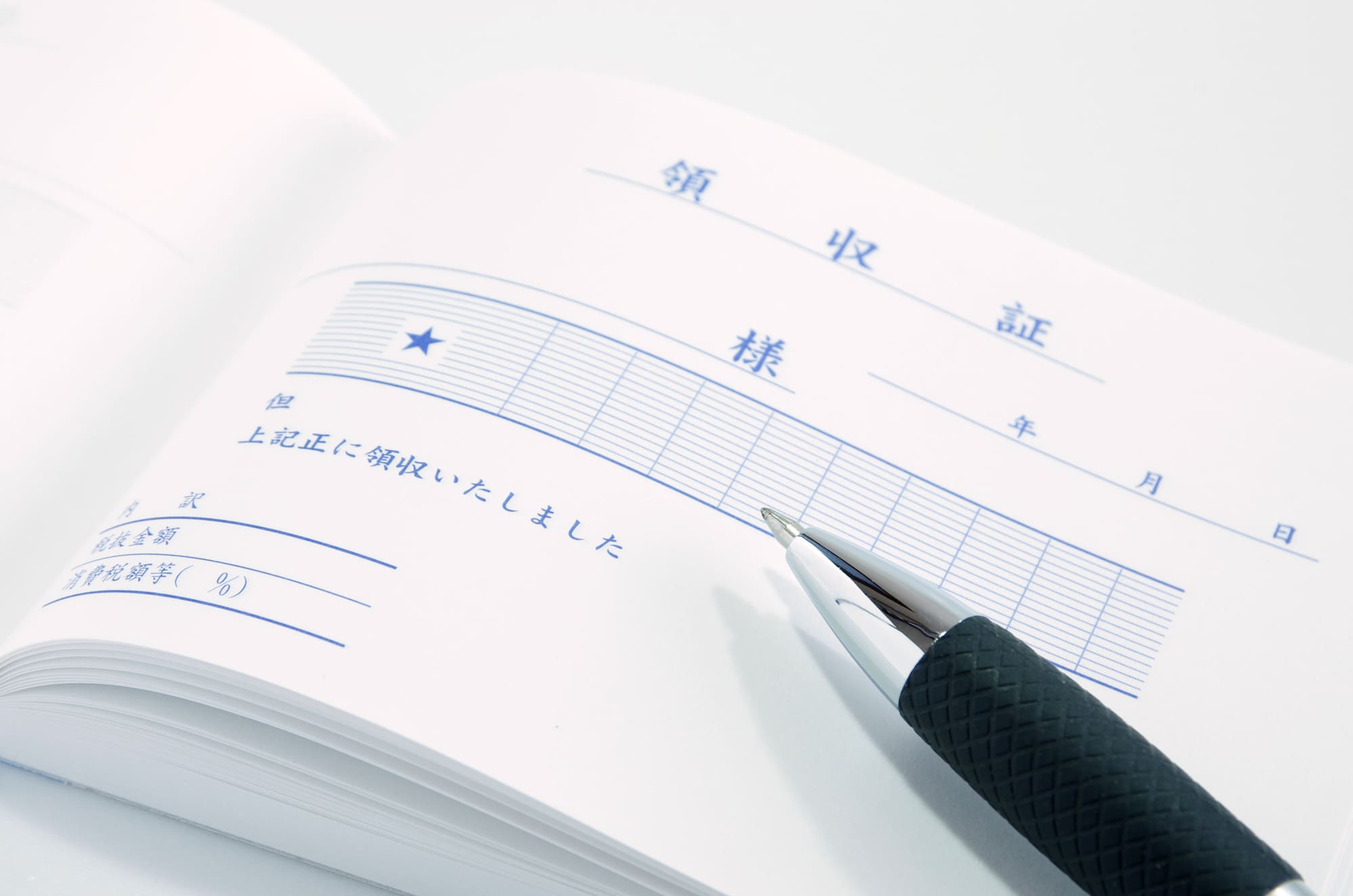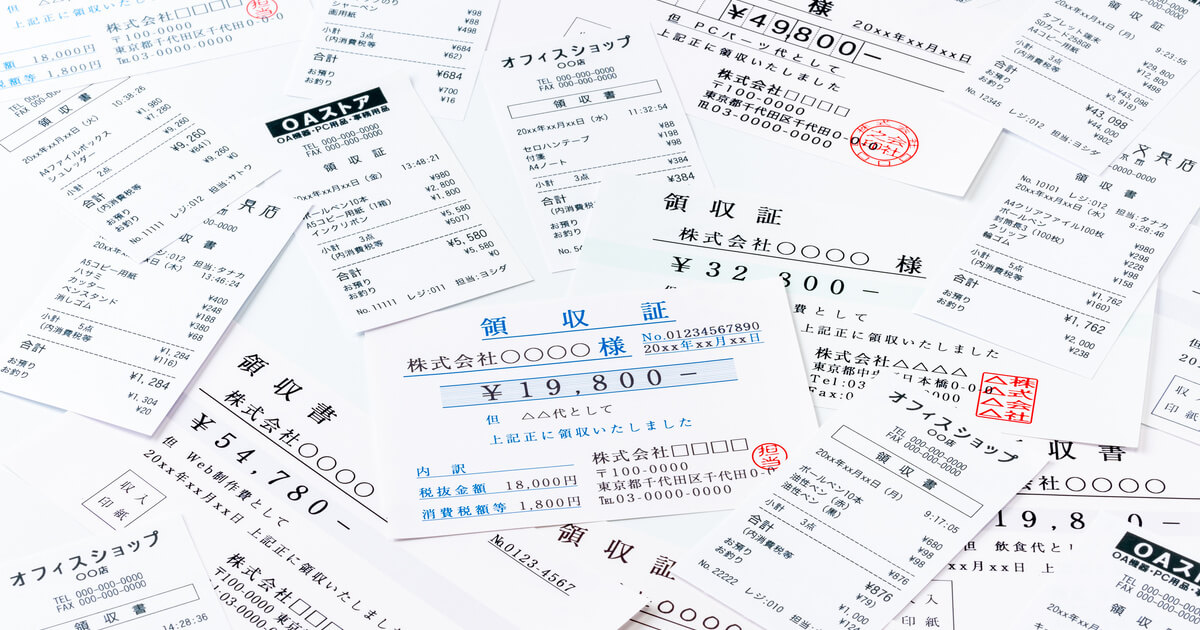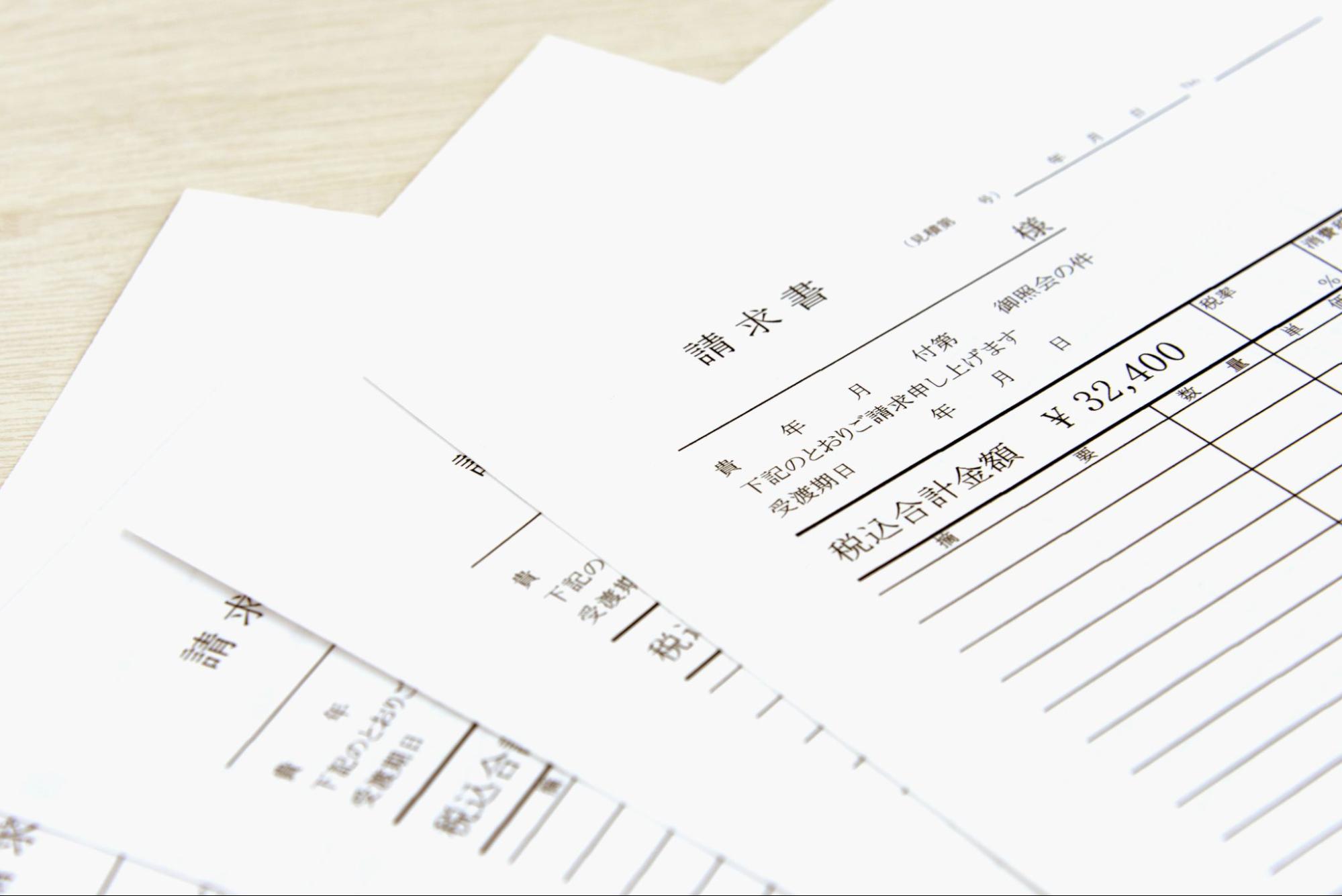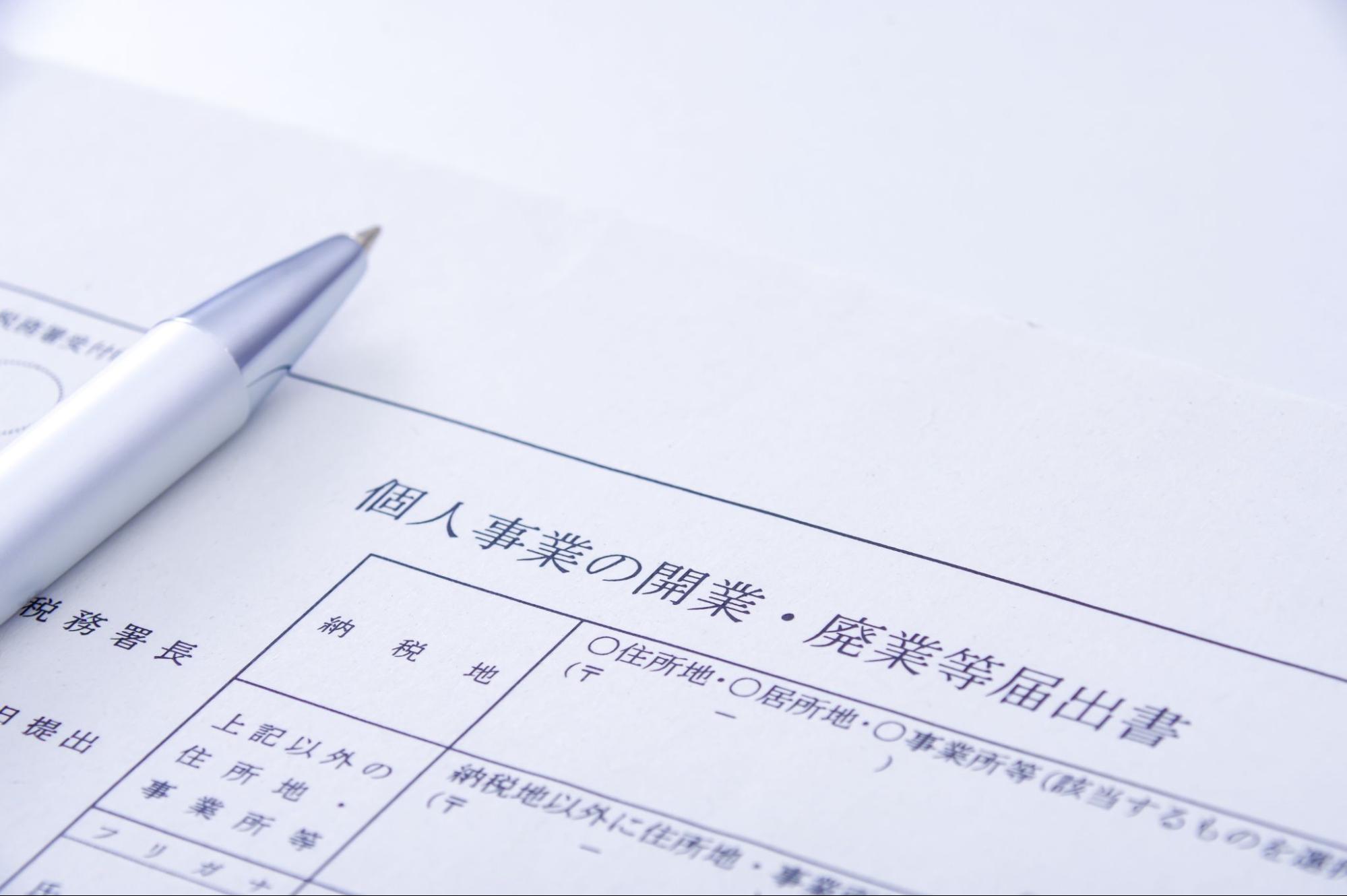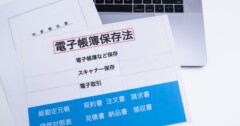印鑑は契約書に必要?契約に使用する種類と押印する位置を解説

印鑑は契約書に不要なのか必要なのか、判断しかねる場面もあるのではないでしょうか。
結論からいうと、契約書における印鑑は必要な場面と不要な場面があるため、状況によって使い分けることが重要です。
この記事では、契約書における印鑑の必要性、契約に使用する印鑑の種類や押印する位置、押印が必要な契約締結の方式について解説します。
- 【この記事のまとめ】
- 契約書に印鑑は必ずしも必要ではありませんが、雇用契約や不動産売買契約など、多くの契約で使われることが一般的です。
- 契約書に押印する際、使用する印鑑の種類は自由ですが、契約の重要性や取引額によって適切な印鑑を用意することが推奨されます。
- 印鑑がない場合は自筆署名や電子印鑑で代用可能ですが、銀行手続きや大きな取引では実物の印鑑が求められる場合もあります。
印鑑は契約書に不要?必要?【結論】必ずしも必要ではない

はじめに、契約書における印鑑の必要性について解説します。
印鑑は契約書で使用するもの
印鑑は契約書で使用するため、用意しておいて損はありません。例えば、印鑑が必要となる場面には次のようなものがあります。
- 雇用契約
- 業務委託契約
- 商品売買契約
- 自動車売買契約
- 不動産売買契約
- 賃貸借契約
- ローン契約
例えば、企業が従業員を雇用する際に必要となる雇用契約や、外部事業者に業務を委託する際に必要となる業務委託契約などで使用します。
また、商品の購入・販売に関する商品売買契約をはじめ、自動車売買契約や不動産売買契約など、特定商品の売買にも印鑑が求められることが多いです。
その他、アパートやマンションなどの不動産を賃貸する際に必要となる賃貸借契約やローン契約など、信用を担保とする契約においても印鑑が必要となります。
契約書の押印はどの印鑑でもOK
契約書の押印に法的に定められた印鑑の種類はありませんが、実務上は会社実印・代表者印など信頼性の高い印鑑が使用されるのが一般的です。シャチハタやゴム印など変形の可能性があるものは契約書への押印としては認められないことが多いので注意が必要です。
押印のない契約書も効力はある
契約書によっては、押印がない場合でも法的効力を発揮します。
ただし、押印のない契約書を作成するとトラブルになることもあり、特に口約束をした場合などは後から「言った」「言わない」と争いになる可能性もあります。
一方、相手が契約違反をした場合、契約書に書かれていて同意も行われていた場合は契約書の内容と照合し、どちらに責任があるのかを追及できます。
手元にない場合は自筆署名も可
印鑑が手元にない場合は、自筆の署名で代用可能です。
また、最近では電子契約も進み、印鑑を電子データで送る電子印鑑での代用も可能です。単なる印影画像を貼り付けた電子印鑑は法的効力が弱く、重要契約では認められません。法的効力を持つのは電子署名法に基づく「電子署名(タイムスタンプ付)」を備えた電子契約サービスです。
ただし、銀行での手続きでは実物の印鑑が必要となる他、自動車売買契約や不動産売買契約など、取引金額が大きい場合は印鑑が求められる場合もあります。
忘れた場合は契約そのものが締結できない状況となることもあるため、最低限の印鑑は揃えておくのが賢明です。
契約に使用する印鑑の種類

契約に使用する印鑑は複数あります。ここでは、その中でも特に使用する機会が多い印鑑の種類を紹介します。
会社実印(代表者印)
会社実印(代表者印)は、会社や代表者の肩書が彫られた印鑑です。
会社実印は法務局に登録された印鑑で、重要な契約や登記に使用されます。通常の社内契約書では角印や認印を用いることもありますが、対外的な重要契約では会社実印を使うのが一般的です。
企業が持つ印鑑のなかでも特に重要な印鑑となるため、起業する際にはまず会社実印(代表者印)を作成するのが良いでしょう。
基本的に契約書や、法的な手続きに使用します。代表者が決裁した証として使用するため、厳重に管理する必要があります。
銀行印
銀行印は、銀行に届け出をした印鑑を指します。銀行口座の開設や窓口での出金などで必要となり、会社実印(代表者印)とは別途で作成して登録するのが一般的です。
ATMやネットバンキングの普及で銀行印を使用するケースは減っているものの、銀行の窓口で手続きをする際に必要となるため、銀行に行く際は持参するのが良いでしょう。
ただし、銀行窓口での出金には通帳と銀行印が必要ですが、本人確認書類を求められる場合もあります。また、持参する際は紛失や盗難には十分に気を付けましょう。
角印・認印
角印・認印は、会社名が刻印された印鑑を指します。正しくは「社印」と呼ばれる印鑑ですが、形状が四角いことから角印と呼ばれるのが一般的です。
ビジネス文書で使用する角印・認印は、契約書や見積書、請求書や領収書などで使用します。
ただし、会社実印(代表者印)は印鑑登録するものの社印は印鑑登録しないため、法的効力は低くあくまでも日常業務で使用する印鑑です。
ゴム印
ゴム印は、住所などの情報が刻印された印鑑を指します。正しくは「住所印」と呼ばれる印鑑ですが、素材がゴムであることからゴム印と呼ばれるのが一般的です。
ゴム印もビジネス文書で使用する頻度が多い印鑑で、住所を記載したい場合や郵送物に宛名を記載したい場合などに使用します。
会社実印(代表者印)のように契約を締結する印鑑ではないため、あくまでも業務効率化のためのツールとして使用される印鑑です。
【重要】契約で押印する印鑑の位置

押印する印鑑の位置は、契約する内容によって変わるため注意が必要です。ここでは、契約で押印する印鑑の位置について解説します。
押印
押印は最もスタンダードな押印方法で、主に契約締結などで使用します。押印の位置は、記名押印方式・署名捺印方式のいずれであっても氏名(名称)の右側部分が一般的です。
記名欄・署名欄への押印は、契約締結に向けた当事者の合意を示すものであるため、印鑑を通じて両者が同意した証拠となります。
最近では電子印鑑で押印するケースも増えており、データ上で契約書を取り交わし、電子印鑑を押印する場面も多くあります。
契印
契印は契約書が複数ページある場合の押印方法で、製本後に各ページにまたがって行う押印を指します。押印の位置は、ページが重なっている見開き部分に行うのが一般的です。
契印は、契約書のページが「正しく連続していること」「差し替え・抜き取りがないこと」の証明となり、契約書全体が当事者によって承認されていることを示します。
ただし、数十ページ・数百ページある場合はすべてのページに押印するのが大変なため、製本した契約書をテープで袋とじにし、テープと紙面にまたがる形で押印することも可能です。
消印
消印は収入印紙が使用済みであることを証明する押印方法で、収入印紙と紙面にまたがって行う押印を指します。押印の位置は、貼付された収入印紙の半分部分に行うのが一般的です。
消印は収入印紙の再使用を防ぐために行うもので、請負契約書や不動産売買契約書などで使用されます。
ただし、当事者全員が消印を行う必要はありません。また、記名欄・署名欄に押印した印鑑と別の印鑑を使用しても問題ないため、比較的形式は自由です。
捨印
捨印は契約締結後に誤りが判明した場合の押印方法で、契約書の冒頭に行う押印を指します。押印の位置は、契約書冒頭の上部余白部分に行うのが一般的です。
捨印は契約などで間違いを訂正するために行うもので、訂正内容とともに記載して行います。
ただし、捨印は原本を所有する相手に一方的に訂正の権限を与えることになるため、重要な条項などを書き換えられる可能性がある点に注意が必要です。
訂正印
訂正印は契約締結後に文言を訂正する際の押印方法で、修正する箇所に行う押印を指します。押印の位置は、修正箇所に上書きする形で行うのが一般的です。
訂正印は契約などの内容を修正するために行うもので、誤りとなる文言を二重線で削除し、追記する文言があれば一緒に記載します。
場合によっては「〇文字削除」「〇文字追加」など、削除・追加した文字数を合わせて記載することが求められる場合もあるため、変更後の内容を明確にしつつ押印しましょう。
止印
止印は契約書本文の末尾に行う押印方法で、契約書の条文が不正に削除・追記されることを防ぐために行われます。ただし、信用できる相手であれば省略も可能です。
また、当事者全員が止印を行う必要はありません。記名欄・署名欄に押印した印鑑と同じ印鑑を使用するのが原則となります。
割印
割印は、複数部作成された契約書が同一のものであることを示すもので、契約書の枚数に応じて行います。
契約書が2部以上ある場合は、同じ内容の契約書であることの証明として割印が必要です。
押印が必要な契約締結の方式

押印が必要な契約締結の方式には、いくつかの方法があります。ここでは、押印が必要な契約締結の方式について解説します。
記名押印
記名押印とは、署名以外の方法で当事者の氏名(名称)を記載して印鑑を押印することを指します。
記名押印は法人の契約締結に使用され、事前にパソコンで作成した契約書に当事者の会社名・代表者名・住所を印字しておき、当日に押印のみを行うケースが一般的です。
署名捺印
署名捺印とは、自署で当事者の氏名(名称)を記載して印鑑を捺印することを指します。
署名捺印は重要な契約で使用され、押印だけではなく署名の効果も加わるため、より明確に契約を成立させたい場合に適した締結方法です。
なお、押印部分には「二段の推定(契約を巡って紛争が起き、契約書が民事訴訟において証拠として提出される場合に、その契約書が証拠になるかを判断する際に用いる考え方)」の効果が発生し、署名部分には「文書の真正な成立の推定」の効果が発生します。
署名部分は民事訴訟法228条4項で定められており、法的効力も強いです。
サイン
外国では、日本のような印鑑ではなくサイン方式が一般的となっています。海外では印鑑に関する制度が存在しないため、記名押印方式や署名捺印方式による契約締結も難しいです。
そのため、海外企業と契約する際はサインが基本となります。
ただし、そのサインが本人の自署によるものであることは別途で確認する必要があるため、サイン証明書などのやり取りも交えて契約締結を行うのが賢明です。
契約書は電子印鑑でも可能

契約書は印鑑の押印により合意が認められるものですが、電子印鑑でも対応可能です。
電子印鑑とは、文字通りデータ上の印鑑であり、パソコンで作成した契約書に印鑑データを押印することで契約が可能となります。
印鑑はさまざまな契約で使用しますが、内容次第では同意があれば口約束でも可能です。しかし、口約束ではトラブルに発展する可能性もあるため、印鑑による押印が推奨されています。
一方で書面による契約はお互いに書類を作成・確認・郵送する手間があるため、業務効率化を考える場合は電子印鑑が有効といえるでしょう。
電子印鑑の作成を考えている場合は、GMOサインにお任せください。
誰でも簡単操作で契約を電子化でき、パソコンだけではなくスマホアプリにも対応。使い方はもちろん実用化における課題解決も、手厚い電話サポートで対応いたします。
また、標準機能が豊富であり、他社ではオプション追加が必要な機能も無料で使えるため、抜群に使い勝手が良い点も魅力です。
契約書に利用できる電子印鑑の主な種類

契約書の電子化が進むなかで、電子印鑑も重要な役割を担っています。
しかし、電子印鑑には種類があり、それぞれ法的効力や利用目的が異なります。
契約書に利用できる電子印鑑の主な種類は、以下の通りです。
- 実在する印鑑をスキャンして画像に変換した電子印鑑
- 識別情報(タイムスタンプ)が含まれた電子印鑑
ここでは、契約書に利用される主な電子印鑑の種類について詳しく解説します。
実在する印鑑をスキャンして画像に変換した電子印鑑
このタイプの電子印鑑は、実際の印鑑をスキャンして画像データ化したもので、手軽に作成できるのが特長です。
まず、実在する印鑑を紙に押印します。押印された紙をスキャナーで読み込み、画像編集ソフトでデータ化することで、PDFやWordなどの電子文書に貼り付けて使用できます。主に社内の内部資料や承認印などに用いられます。
画像編集ソフトの使用スキルさえあれば、簡単に作成でき、費用もほとんどかからない点がメリットです。
ただし、スキャンして作成した電子印鑑はセキュリティ面でのリスクがあります。誰でも改ざんが可能なため、法的な証拠能力が弱く、重要な契約書などの社外向けの文書への使用には向きません。
また、画像編集ソフトで文字をベースにした電子印鑑も簡単に作成可能ですが、印影をスキャンした電子印鑑と同様に社内の内部資料向けです。
識別情報(タイムスタンプ)が含まれた電子印鑑
電子印鑑には、識別情報(タイムスタンプ)が含まれた種類もあります。
見た目は、スキャンして作成した電子印鑑や文字をベースに作成した電子印鑑と同様ですが、識別情報(タイムスタンプ)などのデータが組み込まれています。単なる印影画像ではなく、押印した日時や使用者の識別情報が付加されており、改ざん防止や本人証明の機能を持つ電子印鑑です。
法的効力の高さが特徴で、契約書などの社外向け文書にも適しているため、従来の印鑑と同様に使えます。
ただし、識別情報が含まれた電子印鑑は、有料の専門サービスによって発行されることが一般的で、導入には一定の費用がかかります。
費用はサービスごとに異なるため、セキュリティの高さなどを基準に選ぶとよいでしょう。特に電子帳簿保存法の要件に準拠しているかどうかが、重要な判断基準です。
契約書に電子印鑑を使用するメリット
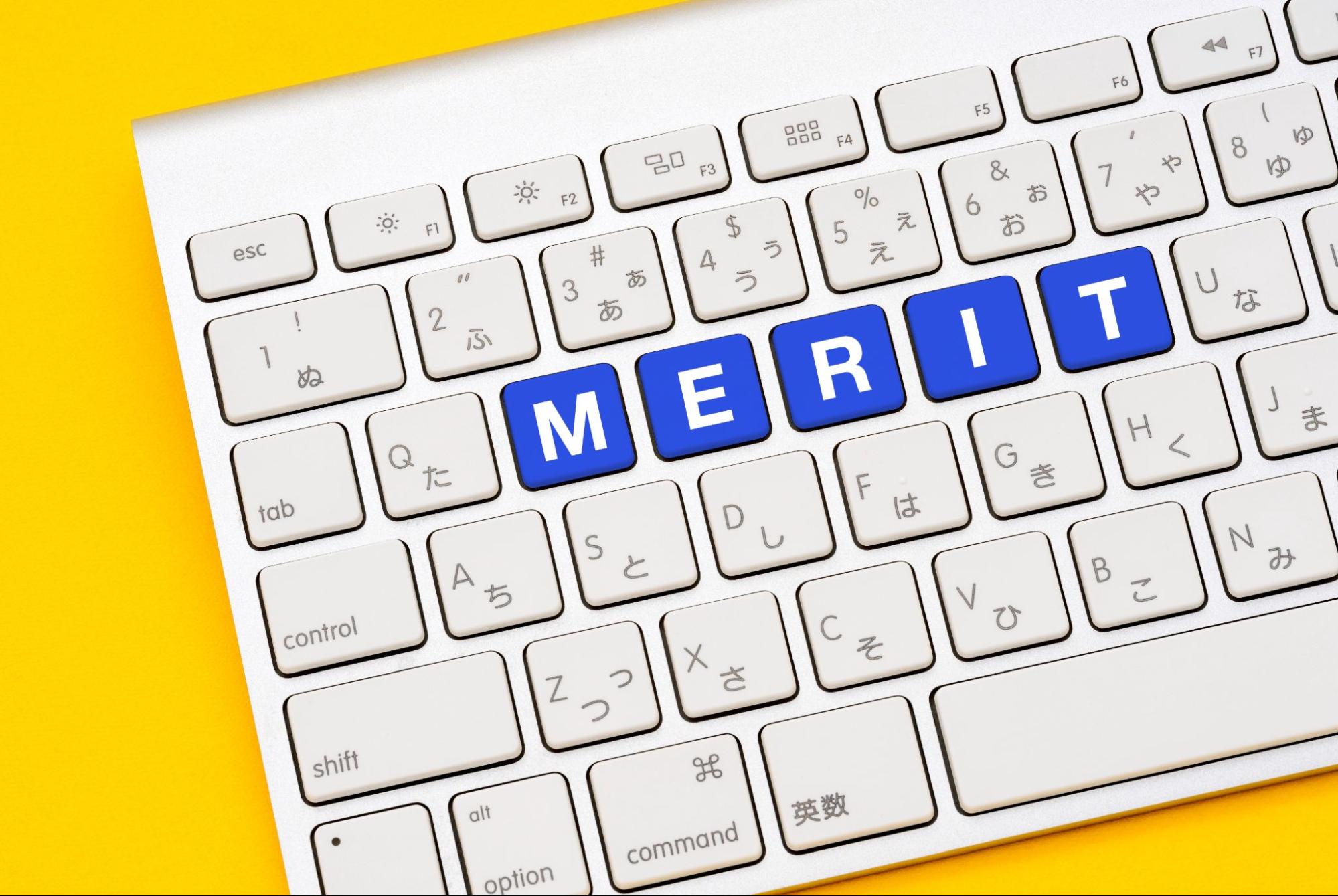
電子印鑑の導入は、業務効率化と利便性の向上に大きく貢献します。
従来の紙への押印よりも、さまざまなメリットを得られるでしょう。
契約書に電子印鑑を使用する主なメリットは、以下の通りです。
- 押印の手間を削減できる
- 書類の整理が簡単
- 取引の簡略化が可能
- コスト削減に貢献できる
- リモートワークなど社外にいても対応できる
- 紛失・破損のリスクがない
ここでは、契約書に電子印鑑を使う具体的なメリットについて詳しく解説します。
押印の手間を削減できる
従来の紙の契約書では、印鑑を押すために担当者が保管場所に出向いたり、貸出の手続きが必要なケースもありました。
また、契約書が複数部あった場合は、対応に時間がかかることも少なくありません。
しかし、電子印鑑を使用することで、パソコンからワンクリックで押印できるため、移動や手続きが不要になります。複数部の契約書であっても、迅速に押印できるため、作業負担の軽減にもつながります。
電子印鑑の導入は、業務のスピードアップにつながり、契約締結までの時間を短縮できる点が大きなメリットです。
書類の整理が簡単
契約書への印鑑を電子印鑑に変えることで、すべての書類は電子データとして管理されます。
つまり、契約書を保管する物理的なスペースが不要です。データ上で管理された書類は、検索や共有が瞬時に行えるため、業務効率化にもつながるでしょう。
また、紙の契約書では紛失や劣化のリスクがありましたが、電子化によってこれらの問題を防止可能です。さらに、電子データ化された契約書をクラウド上に保存すれば、万が一のバックアップ対策にもなります。
取引の簡略化が可能
紙の契約書では、切手や封筒の用意、郵送手続きなど、押印以外にもさまざまな対応が必要でした。
一方、電子印鑑によって電子化された契約書は、物理的な書類のやり取りが不要になり、データ上で契約が完結するため、取引の簡略化が可能です。
例えば、複数の関係者が関わる契約では、遠隔地にいる人からの押印には、往復の郵送などの手間がかかっていました。しかし、電子印鑑であれば、各自が遠隔地から押印できるため、意思決定の促進や業務効率の向上につながります。
コスト削減に貢献できる
電子印鑑によって契約書をデータ化することで、コスト削減につながります。
従来の紙の契約書では、紙代、インク代、郵送費、保管費など、さまざまな経費がかかっていましたが、電子印鑑の導入によって、これらのコストを大幅に削減可能です。
また、書類の整理や郵送手続きなどにかかる時間も削減できるため、業務効率化が進み、人件費の削減にもつながります。
リモートワークなど社外にいても対応できる
契約書に電子印鑑を利用するメリットとして、使用場所が限定されない点が挙げられます。
従来の印鑑の場合、社内にいなければ使用できないケースが一般的です。
しかし、近年は働き方の多様化により、自宅や外出先から契約業務を行うケースが増えています。
そのようなシーンでも、電子印鑑であればどこからでも押印が可能なため、リモートワークでの契約業務も滞りません。物理的な印鑑を持ち歩く必要がなくなり、スムーズな業務継続を実現してくれるでしょう。
紛失・破損のリスクがない
紙の契約書や物理的な印鑑には、紛失や盗難、破損のリスクがありました。
例えば、物理的な印鑑の場合、使用された後に保管場所へ戻されないと、行方が分からなくなってしまうケースも珍しくありません。
しかし、電子印鑑は電子データとして管理されるため、紛失するリスクは著しく低いといえるでしょう。
また、電子印鑑やデータ化された契約書を管理システムによって、アクセス制限や権限設定をかければ、不正使用や改ざんを防止できます。このようなセキュリティ対策は、企業のコンプライアンス強化にもつながります。
【注意】契約書に電子印鑑を使用するデメリット

契約書への電子印鑑の導入には、業務効率化などのメリットがある一方で、いくつかデメリットやリスクが存在します。
- セキュリティ面のリスクがある
- 作成する手間がかかる
- コストがかかる
ここでは、契約書に電子印鑑を使用するデメリットについて詳しく解説します。デメリットを理解したうえで、導入を検討しましょう。
セキュリティ面のリスクがある
電子印鑑は電子データであるため、性質上、第三者による不正利用や偽造などセキュリティ面でのリスクがあります。
スキャンしただけの電子印鑑は容易にコピーや改ざんされ、契約書の信頼性を損なう恐れがあります。また、不正アクセスによるデータの流失や改変も懸念されるため、十分なセキュリティ対策が必要です。
適切なアクセス管理と暗号化、さらに識別情報(タイムスタンプ)と併用しなければ法的トラブルにつながるリスクが高まります。
作成する手間がかかる
電子印鑑の導入には、作成の手間がかかります。
特に識別情報(タイムスタンプ)が付加された電子印鑑は、管理システムの設定、電子署名の付与など、作成から運用までに一定の準備と手間が必要です。
特にセキュリティ面を強化する場合は、社内での取り扱いルールの周知や教育も欠かせません。
単純な画像化した電子印鑑とは異なり、運用負担が増えることを前提にした検討が必要です。
コストがかかる
電子印鑑の導入には、一定のコストがかかります。
特に、識別情報(タイムスタンプ)を含んだ信頼性の高い電子印鑑の場合、有料サービスを利用するのが一般的です。多くは月額料金、さらに利用ごとの費用が発生します。
また、導入時には初期設定の費用や管理体制の構築費用がかかるケースもあるでしょう。加えて、技術的なトラブルに対応できるように、システム保守費用も考慮しなければいけません。
紙の契約書に比べてコスト面での負担を感じる企業もあるため、費用対効果を検証しましょう。
電子印鑑の作成方法
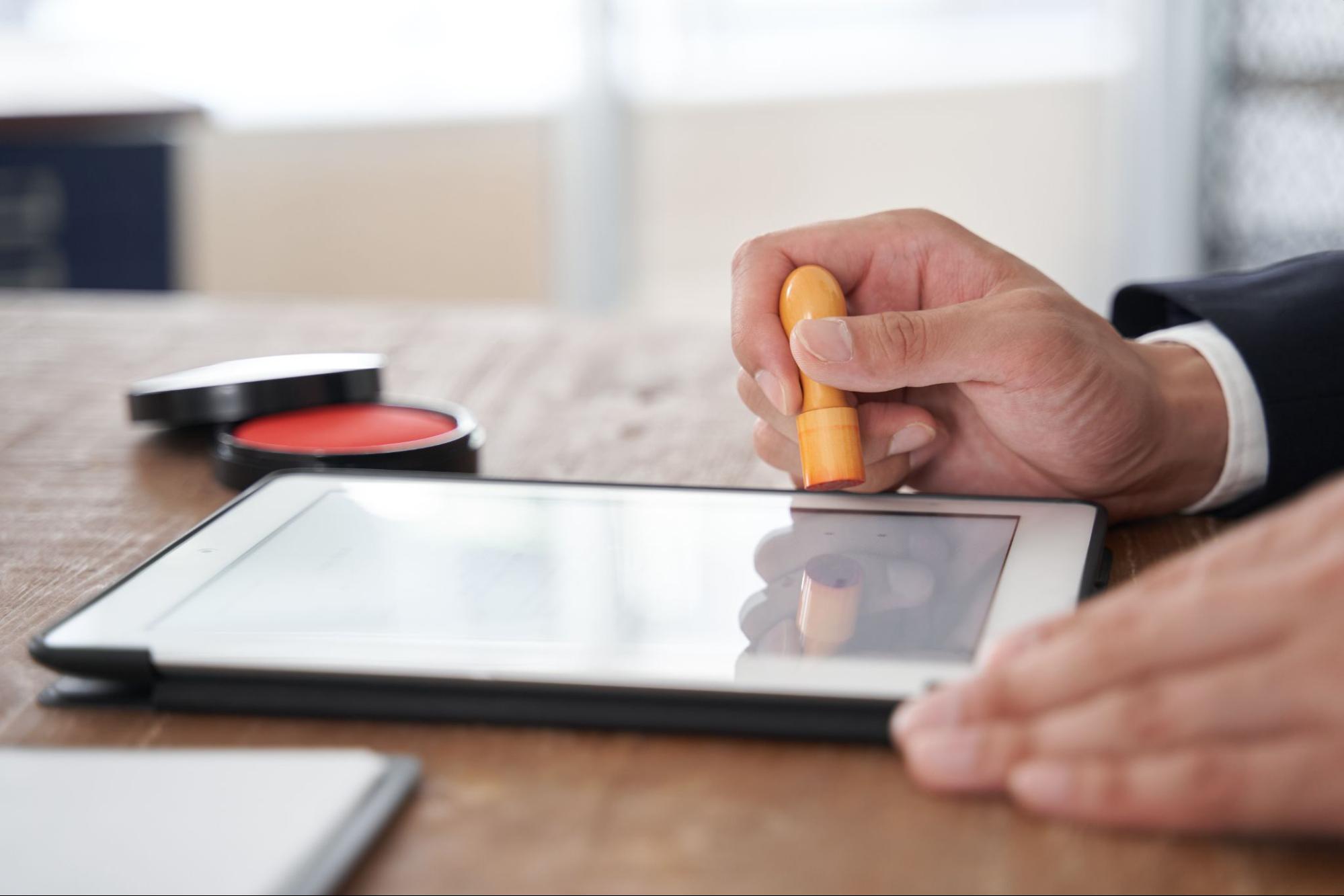
電子印鑑の主な作成方法は、以下の3つです。
- 【無料】所有する印鑑の画像をスキャンして作成
- 【無料】ソフトウェアを使って印鑑風画像を作成
- 【有料】電子印鑑サービスで作成
ここでは、代表的な3つの作成方法について解説します。
【無料】所有する印鑑の画像をスキャンして作成
最も手軽な作成方法は、所有する印鑑の画像を使用します。
具体的な作成方法は、以下の通りです。
- 所有する印鑑を紙に押す
- スキャナーで画像データとして読み取る(スマホのカメラでの撮影も可)
- 画像編集ソフトで不要な余白を切り取る
- 透過画像(PNGなど)として保存
完成した透過画像をPDFやWordファイルなどの電子文書に貼り付けて使用できます。
ただし、無料で簡単に作成できる反面、画像データは複製や改ざんのリスクが高いため、契約書へ使用した場合は証明力が低くなる点に注意が必要です。社内資料や簡易的な承認用途に向いています。
【無料】ソフトウェアを使って印鑑風画像を作成
インターネット上のサービスやソフトウェアを使い、文字だけで印鑑風の電子印鑑を作成する方法もあります。
例えば、インターネット上のサービスであれば、用意された書体や枠のデザイン、サイズを選び、文字を入力するだけで電子印鑑の作成が可能です。作成された画像はダウンロードすれば電子文書に利用できます。
複雑な操作もなく簡単に作成できるため、特別な機器や知識は不要です。
ただし、印鑑風画像の電子印鑑も不正利用を防ぐ仕組みがなく、法的効力はありません。そのため、重要な契約書での使用は避けるべきでしょう。
【有料】電子印鑑サービスで作成
安全性と信頼性を求める場合は、有料の電子印鑑サービスや電子契約のプラットフォームの利用が推奨されます。
これらのサービスでは、電子印鑑の提供に加え、電子署名やタイムスタンプが付与されるため、契約書の信頼性を高めます。
また、サービスによっては、専用のクラウド管理システムで電子契約書を一括管理できるほか、オンラインでの承認作業も可能です。
導入には月額や利用ごとに費用が発生しますが、安全に重要書類を管理できるメリットがあります。
電子印鑑および電子契約の導入を考えている場合は、GMOサインがおすすめです。
国際的な電子商取引保証規準に基づく審査に合格し、トップレベルのセキュリティが担保されているため、重要な契約でも安心して利用できます。
また、パソコンだけでなくスマホアプリにも対応し、出張先や外出先、リモートワークでも契約業務が滞る心配がありません。
契約書の印鑑に関するよくある質問

ここでは、契約書の印鑑に関するよくある質問に回答します。
Q.印鑑がない場合、拇印でも大丈夫ですか?
A.契約書への押印は、実印などと同様の意思表示として有効です。
印鑑を忘れた場合の代替手段として用いられます。
ただし、拇印は正式な印鑑に比べて証明力がやや劣るため、特に重要な契約の場合は、署名(直筆サイン)と組み合わせて本人の意思を正確に示すことが望ましいです。
Q.契約書に押印する場合、印鑑証明は必要ですか?
A.一般的に契約書に押印する場合、印鑑証明の添付は必要ありません。
印鑑証明は、主に不動産の売買契約や遺産相続のように、法律上特に本人確認を厳密に求められる取引に使われます。
そのため、重要性の低い契約書では、本人の署名または認印(朱肉を使った印鑑)で十分であり、印鑑証明まで求められることは少ないでしょう。むしろ印鑑証明を用いると手続きが複雑になるため、不要な場合は使わずに済ませることが一般的です。
なお、取引相手から実印の押印や印鑑証明を求められた場合は、その重要度やリスクに応じて対応を検討するとよいでしょう。
Q.契約印にゴム印は使えますか?
A.契約書の押印にゴム印を使うことは、あまり推奨できません。
ゴム印は簡単に複製や改ざんが可能で、正式な印鑑としての証明力が低いためです。
一般的に契約書には、朱肉を使う認印や実印が用いられます。ゴム印は、回覧や郵便物の受領印など、日常的で正式な証明を必要としないシーンでの使用が適しています。
ただし、契約相手との合意や社内ルールによっては、ゴム印を補助的に用いるケースもありますが、証明力の低さからも、重要な契約書での使用は避けるべきです。
Q.押印のない契約書は無効ですか?
A.押印がなくても、当事者間の同意があれば、契約書は基本的に有効です。
押印は、互いが契約内容に同意したことを証明する一つの手段に過ぎません。例えば、本人の署名(直筆サイン)があれば、押印の代わりとして契約が認められます。
ただし、商習慣や取引先の要望として押印が求められる場合が多く、信頼性の向上やトラブルを防止するためには押印を行うことが望ましいです。
Q.押し間違いはどうすればいい?
A.契約書で押し間違いをしてしまった場合は、適切な対応が必要です。
例えば、押す場所を間違えた場合は、その箇所を二重線で打ち消し、同じ印鑑を被せるように押印します。その後、正しい場所へ印鑑を押印してください。
ただし、間違いの内容が多い場合や複雑な修正が必要な場合は、新しい契約書を作成する方が、トラブル回避のために望ましいです。
まとめ
印鑑はさまざまな契約で使用しますが、契約自体は両者の同意があれば口約束でも成立します。
しかし、印鑑はもちろん契約書を作成しておかないと後々トラブルに発展する可能性があるため、契約内容を含めて書面で明記しておくことが重要です。
GMOオフィスサポートの会社設立印鑑セットでは、法人登記に利用する代表印・銀行印・角印・印鑑ケース・捺印マット・朱肉・電子印影などをセットでご提供しています。
また、GMOサインでは電子印鑑の作成が簡単に行えるため、印鑑の押印・捺印作業を効率化したい場合は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
法人登記やその手続の流れについて、下記の記事で詳しく解説しています。
- 記事監修
-
- 中野 裕哲 HIROAKI NAKANO
- 起業コンサルタント(R)、経営コンサルタント、税理士、特定社会保険労務士、行政書士、サーティファイドファイナンシャルプランナー・CFP(R)、1 級FP 技能士。 V-Spiritsグループ創業者。東京池袋を本拠に全国の起業家・経営者さんを応援!「あの起業本」の著者。著書16冊、累計20万部超。経済産業 省後援「DREAMGATE」で11年連続相談件数日本一。
- ※本記事は、起業の窓口編集部が専門家の監修または独自調査(アンケート)に基づいて制作したものです。
- ※掲載している情報は、記事公開時点の法令・税制・商品・サービス等に基づくものであり、将来的に変更される可能性があります。
- ※アンケート調査に関する記述は、特定の調査対象者からの回答結果および編集部の見解を含んでおり、内容の正確性・完全性を保証するものではありません。
- ※記事の内容は一般的な情報提供を目的としており、すべての方に当てはまるものではありません。個人の状況に応じた具体的な助言が必要な場合は、専門家にご相談ください。
- ※情報の利用や判断、実施については、ご自身の責任で行っていただきますようお願いいたします。
- ※本記事に掲載された内容の転載・複製はご遠慮いただき、引用の際は必ず出典をご明記ください。



 シェア
シェア