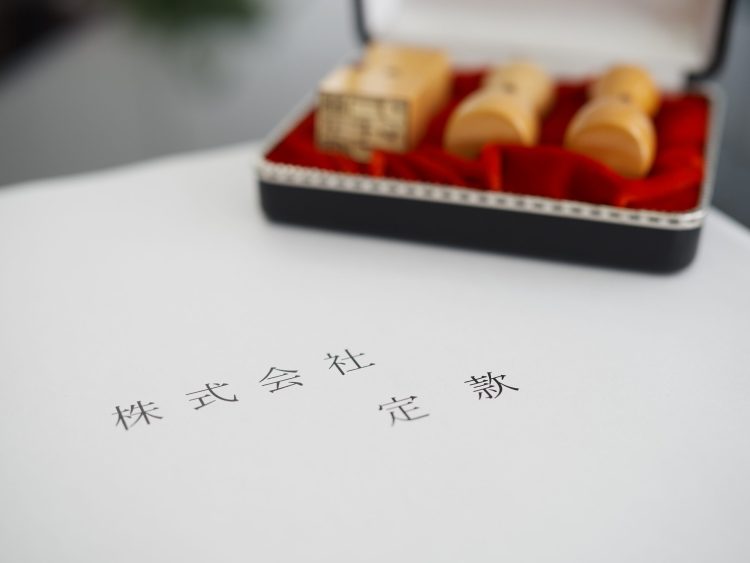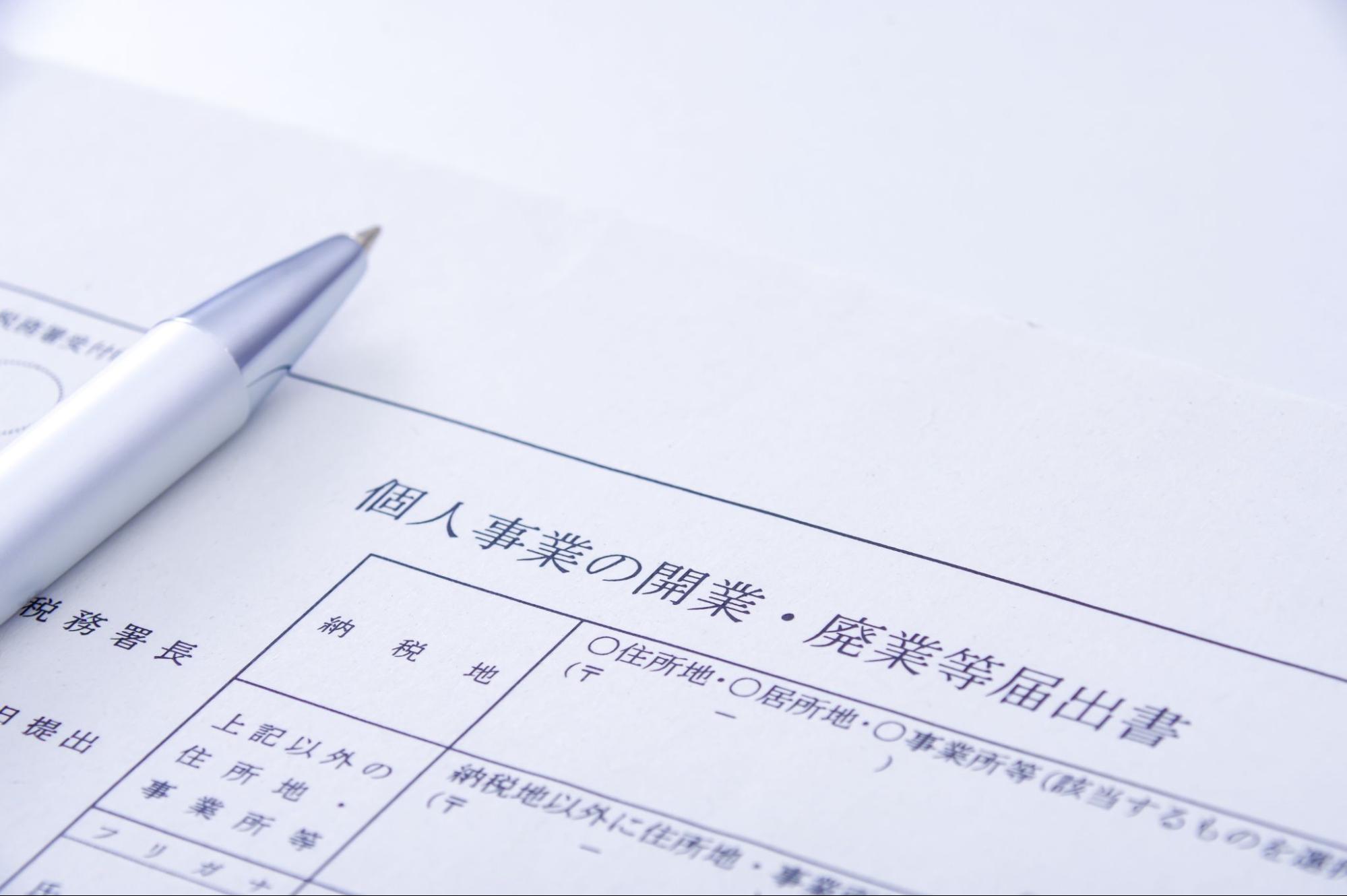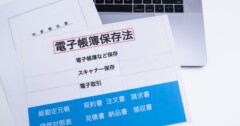会社の種類は全部で4つ!それぞれの特徴や設立方法、メリット・デメリットを解説!
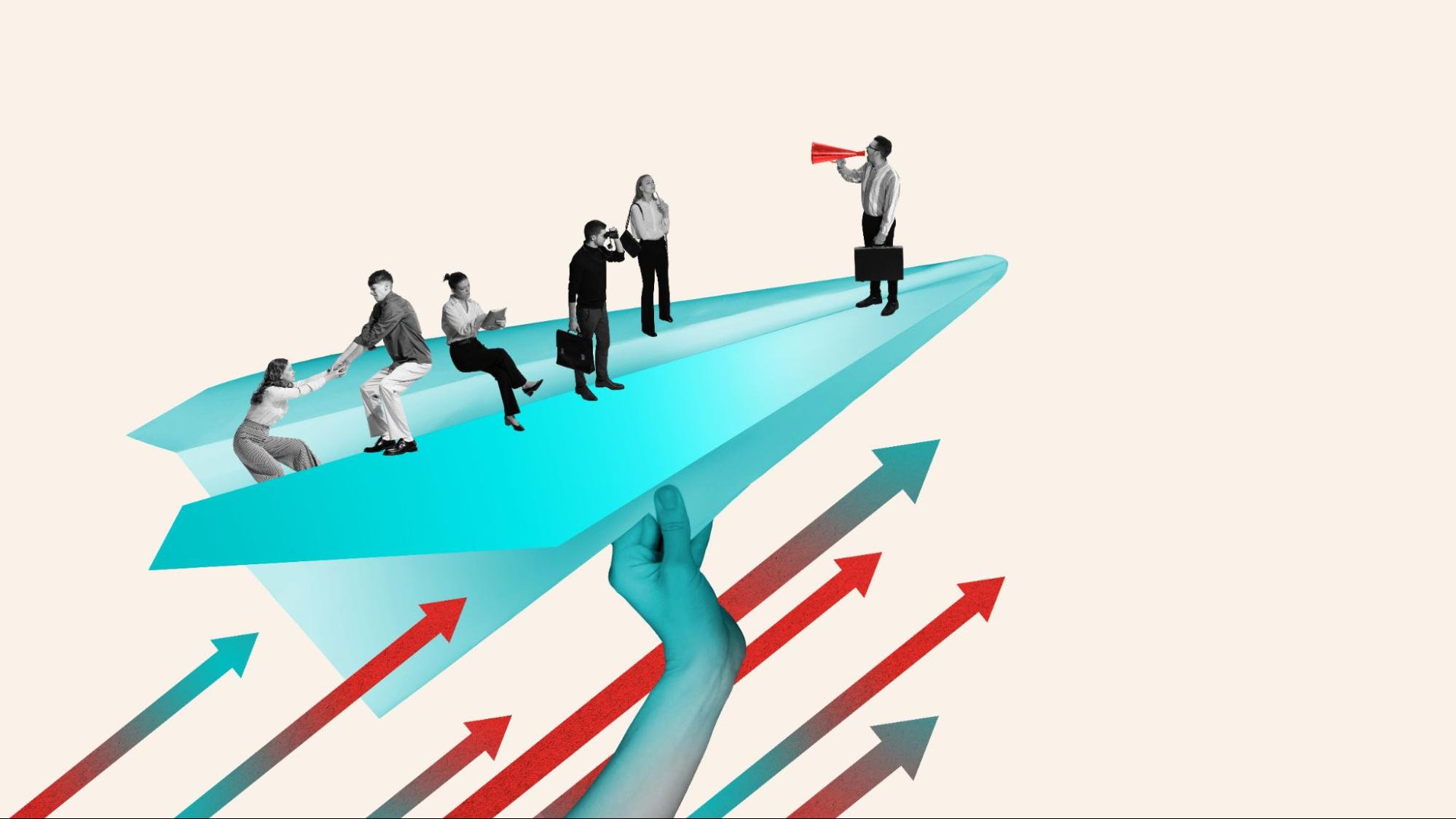
起業する際に最初に検討すべき重要なポイントの一つは、どの会社形態を選択するかです。
会社形態にはさまざまな種類があり、それぞれに独自の特徴やメリット・デメリットが存在します。この記事では、主要な4つの会社形態に焦点を当て、特徴やポイントを詳しく紹介します。
これから起業を目指す方は、ぜひお役立てください。
- 【この記事のまとめ】
- 現在設立できる会社の種類は「株式会社」、「合同会社」、「合資会社」、「合名会社」の4つです。それぞれ異なる責任範囲や資金調達方法があるため、起業時には目的に合った会社形態を慎重に選ぶことが重要です。
- 株式会社は株主から資金を調達し、経営者が事業を運営する形態です。有限責任社員のみで構成され、株主の責任は出資金に限られます。経営者は株主総会で選ばれ、透明性の高い運営が求められます。
- 合同会社は出資者全員が有限責任社員で構成され、利益の配分が自由に決められます。設立コストが低く、経営の自由度も高いですが、社会的知名度が低く、資金調達に制約があることがデメリットです。
「起業の窓口」では、AIインフルエンサーの茶圓氏とコラボをおこない、AIを活用してビジネスの効率化を図るための貴重な知識を提供しています。
特集ページ「AI×起業」では、最新のAI技術やツールを使った実践的なアプローチを紹介しており、起業家や個人事業主の業務をよりスマートにサポートします。
AIの力で業務の負担を軽減し、ビジネスの成長を加速させたい方に最適な情報が満載です。ぜひご覧ください。
「起業の窓口」の特集ページ「起業家インタビュー」では、実際に成功を収めた起業家たちの貴重なインタビューが充実しています。リアルな体験や苦労、成功までの道のりを通じて、これから起業を目指す方々に向けた実践的なアドバイスを提供しています。
さまざまな分野で活躍する起業家の声を通して、ビジネスのヒントやインスピレーションを得られるコンテンツが満載です。ぜひインタビューを参考にして、自分のビジネスに活かしてみてください。
会社形態の基礎知識

会社形態にはいくつかの種類があり、それぞれ特徴や運営の仕組みが異なっています。
ここでは、法人と個人事業主の違いや法人化のタイミング、メリット・デメリットについて基礎的な知識を解説します。
法人と個人事業主の違い
法人と個人事業主の違いについて以下の表にまとめています。
| 個人事業主 | 法人 | |
|---|---|---|
| 税金 | 所得税(最高税率45%の累進課税※住民税等を除く) | 法人税(国税の標準税率15%~23.2%。※実効税率は地方税等含め約30%前後) |
| 事業開始手続き | 税務署に「開業届」を提出するだけで手続きも費用も簡単 | 法務局への法人登記が必要。書類準備や資本金も必要。手間と費用がかかる |
| 事業主の責任範囲 | 無限責任(全財産で責任を負う) | 有限責任(出資額の範囲内で責任を負う) |
| 社会保険加入義務 | なし※一定要件で従業員は加入義務ari | あり |
| 手続きの複雑さ | シンプル | 複雑 |
法人と個人事業主の大きな違いは「法的な主体の存在」と「責任範囲」にあります。
法人は会社という独立した法的主体であり、有限責任であり、会社の借金や責任は法人自身が負い、出資者の責任は出資額の範囲内に限定されるのが特徴です。
一方、個人事業主は事業主本体がすべての責任を負う無限責任となります。
税制面では法人は所得に対して法人税が課され、利益が一定以上になると個人事業主に比べて節税メリットがあります。
法人化するタイミングの目安
法人化するタイミングの目安は、主に事業の利益が増え、税負担の軽減効果が見込める段階です。
一般的には、個人事業主の所得がそれぞれの状況に応じた一定額を超えた段階で法人化を検討することが多いとされています。ただし、具体的な金額基準は法律で定められているわけではなく、事業規模や経費、さらには生活費としていくら必要かといった状況によって判断が分かれます。さらに、取引拡大のために社会的信用が必要になった場合や、従業員を雇用し、経営体制を整える必要が出てきた場合も法人化の適切なタイミングです。
一方で、利益が少なく、法人設立や維持にかかるコストや手間が負担になる場合は、個人事業主のまま事業を続ける方が得策です。
したがって、税制面のメリットと事業規模の成長・信用確保のバランスを見て、法人化のタイミングを判断する必要があります。
法人化による主なメリットとデメリット
法人化による主なメリットとデメリットを以下の表にまとめています。
| メリット | デメリット |
|---|---|
|
|
このように法人化は節税や信用面のメリットが大きいですが、設立・維持コストや手続きの複雑化といったデメリットもあります。
事業の状況や成長計画を踏まえて判断することが重要です。
会社の種類は全部で4種類!

現在、設立できる会社は「株式会社」、「合同会社」、「合資会社」、「合名会社」の4種類があります。
| 株式会社 | 合同会社 | 合資会社 | 合名会社 | |
|---|---|---|---|---|
| 責任の範囲 | 有限責任社員のみ | 有限責任社員のみ | 有限責任社員、無限責任社員 | 無限責任社員のみ |
| 資金調達 | 公開市場で株式の発行・売買が可能 | 社員からのみ資金調達が可能 | 社員からのみ資金調達が可能 | 社員からのみ資金調達が可能 |
| 組織の運営 | 株主総会・取締役会制度に基づく組織運営 | 社員間の合意に基づく組織運営 | 社員間の合意に基づく組織運営 | 社員間の合意に基づく組織運営 |
| 決算公告義務 | 公告義務がある | 公告義務がない | 公告義務がない | 公告義務がない |
それぞれの会社には異なる特徴があるため、起業するときには業種や目的に合わせて、適切な形を慎重に選択することが重要です。
ここでは、4つの会社の特徴を詳しく紹介します。
株式会社
株式会社は、株主から資金を調達して別の経営者が事業を運営し、得た利益を出資者に分配する会社形態です。株式会社の株主は、有限責任社員のみで構成されています。
したがって、株式会社が倒産しても株主は出資金の範囲内で責任を負うだけです。
株式会社の経営者は、株主総会で株主によって選ばれます。
経営者の代表者は、代表取締役と呼ばれます。2006年に施行された会社法では、経営者(取締役)は最低1名以上であればよいとされています。
合同会社
合同会社は、2006年の会社法によって導入された会社形態です。
株式会社との共通点は、出資者が有限責任社員のみで構成されていることです。合同会社では、株主である経営者たちが一体となって会社を運営し、利益の配分も自由に行うことができます。
例として、Apple Japan合同会社や合同会社アマゾンジャパンなどが合同会社として知られています。ただし、企業の法人形態は組織再編等により変更される場合があるため、最新情報の確認が必要です。合同会社は、アメリカのLLC(Limited Liability Company)を参考に作られたといわれ、日本版のLLCとも呼ばれています。
実際、アメリカのLLCも出資者が責任を制限され、自身が経営者となるか外部の者に経営を委託することができる点で、日本の合同会社と似ています。
合資会社
合資会社は、有限責任社員と無限責任社員からなる会社形態です。有限責任社員は資本を出資し、無限責任社員が経営を担当します。有限社員は通常、経営には関与しません。
有限責任社員は資本を出資し、無限責任社員が経営を担当します。有限社員は通常、経営には関与しません。
そのため、合資会社を設立するには、最低でも有限責任社員1名と無限責任社員1名が必要です。
経営者である無限責任社員は、会社が倒産した場合には自身の財産にまで責任が及ぶ可能性があります。
合名会社
合名会社は、無限責任社員のみで構成される会社形態であり、最低でも1人以上の無限責任社員で設立できます。
合名会社は、人々が出資し合い、全ての出資者が経営者となる点で株式会社とは異なります。
イメージとしては、個人事業主が集まって形成された組織のようなものです。
全ての出資者が無限責任社員であるため、会社の危機は出資者自身の資産にも影響を及ぼす可能性があります。
株式会社を設立するメリット・デメリット

目的に合わせた会社をするためには、会社ごとのメリットやデメリットを理解することが重要です。
ここでは、株式会社のメリットとデメリットを紹介します。
メリット
株式会社の出資者(株主)は、有限責任により責任範囲が限定されるため、出資のハードルが低くなります。
株式発行や転換社債などによる資金調達が容易だといえるでしょう。
デメリット
株式会社を設立する際のデメリットとして、費用がかかることが挙げられます。設立には登録免許税、定款認証の費用、定款の収入印紙代、会社印の作成費用が必要です。
株式会社では役員の任期ごとに登記申請手続きを行う必要があり、そのたびに登録免許税がかかります。
また、株主総会の開催や決算書の開示など法律で定められた手続きが必要です。
手続きをするための社内工数や外注費用の負担は、デメリットととらえられるでしょう。
株式会社の設立手続きの流れ

株式会社設立手続きの流れは以下の通りです。
| ステップ | 説明 |
|---|---|
| 1.会社の基本事項を決定 | 商号、事業目的、本店所在地、資本金、発起人、役員、事業年度などを決める。 |
| 2.定款の作成と認証 | 会社のルールをまとめた定款を作成し、公証人役場で認証を受けます。電子定款利用で印紙代4万円が不要になりコスト削減が可能。 |
| 3.資本金の払い込み | 発起人が銀行口座に資本金を払い込み、その証明書類を準備する。資金が確実に用意されたことを証明する重要な手続き。 |
| 4.登記申請 | 法務局に必要書類を提出して登記申請を行う。申請受理後、約1~2週間で法人設立が完了し、会社が法的に認められる。 |
| 5.法人番号取得・届出 | 登記完了後に法人番号が割り当てられ、税務署や年金事務所、市区町村役場に法人設立の届出をする。 |
| 6.社会保険・労働保険の手続き | 従業員がいる場合、社会保険や労働保険の加入手続きを行う。 |
4までの手順を踏むことで、法律的に有効な株式会社の設立となり、事業を開始できるようになります。
株式会社の設立には手続きや書類の準備や手間がかかるため、専門家の助言を得ることも検討するとよいでしょう。
株式会社の設立にかかる費用と時間
株式会社の設立にかかる費用は、登録免許税(最低15万円)、定款認証手数料(約1.5万~5万円)、定款の収入印紙代(紙の場合4万円)が基本であり、合計で約20〜24万円程度が目安です。司法書士など専門家に依頼する場合は、さらに報酬が加算されます。
内訳は以下の通りです。
- 定款の収入印紙代
- 定款認証手数料
- 定款謄本手数料
- 登録免許税
- 印鑑作成費用
- 印鑑登録手数料
なお、司法書士など専門家に手続きを依頼する場合は別途報酬が必要です。
設立にかかる時間は定款認証から登記申請完了まで約1〜2週間が目安で、書類準備や申請のスムーズさによって変動します。
設立後も税務署や年金事務所などへの届出が必要です。
株式会社に向いているビジネスモデルの特徴
株式会社に向いているビジネスモデルの特徴は、スケールの拡大や外部資金調達を前提とした事業です。
特に資本金を投入して設備投資や人材採用を行い、継続的な成長が見込めるITサービスやサブスクリプションモデルのような継続的な収益基盤があるビジネスに向いています。また、社会的信用が重要な取引先との関係構築や複数の出資者を迎える場合も株式会社が適しています。
加えて、利益を分配しやすい体制を整えやすく、事業継承や株式公開を視野に入れた長期的展望のあるビジネスにも最適です。
このため、成長見込みがあり信用力を活かしたい事業に適しているといえます。
合同会社を設立するメリット・デメリット

合同会社の設立には、特定のメリットとデメリットが存在します。社員の立場から見ると、出資者全員の責任範囲が有限である点や設立コストの低さなど、メリットがあります。
一方で、まだ社会的知名度が低く、資金調達方法に制約があるというデメリットもあります。
ここでは、合同会社のメリットとデメリットを紹介します。
メリット
合同会社設立のメリットは、出資者全員の責任範囲が有限であり、合資会社や合名会社と比べて無限に責任を負うことがありません。また、合同会社の設立コストは株式会社よりも安く抑えられます。
合同会社では定款認証が不要なため、5万円の定款認証費用を節約できます。さらに、登録免許税も6万円で済ませられます(株式会社では最低15万円)。
その他のメリットは以下の通りです。
- 利益の配分が自由に決められる。
- 組織運営の自由度が高く、株式会社に比べて柔軟に経営できる。
- 法律上の制約が比較的少なく、例えば決算書の公表義務がない。
合同会社は一般的に小規模な会社であり、社員数や債権者数も少ない傾向があります。そのため、社員や債権者の保護よりも経営の自由度が重視されます。
デメリット
合同会社の主なデメリットは、社会的知名度が低く新株発行や株式上場ができないため、資金調達方法が株式会社と比べて限られていることです。
この点については、合資会社や合名会社も同等に存在するデメリットといえるでしょう。
合同会社の設立手続きの流れ
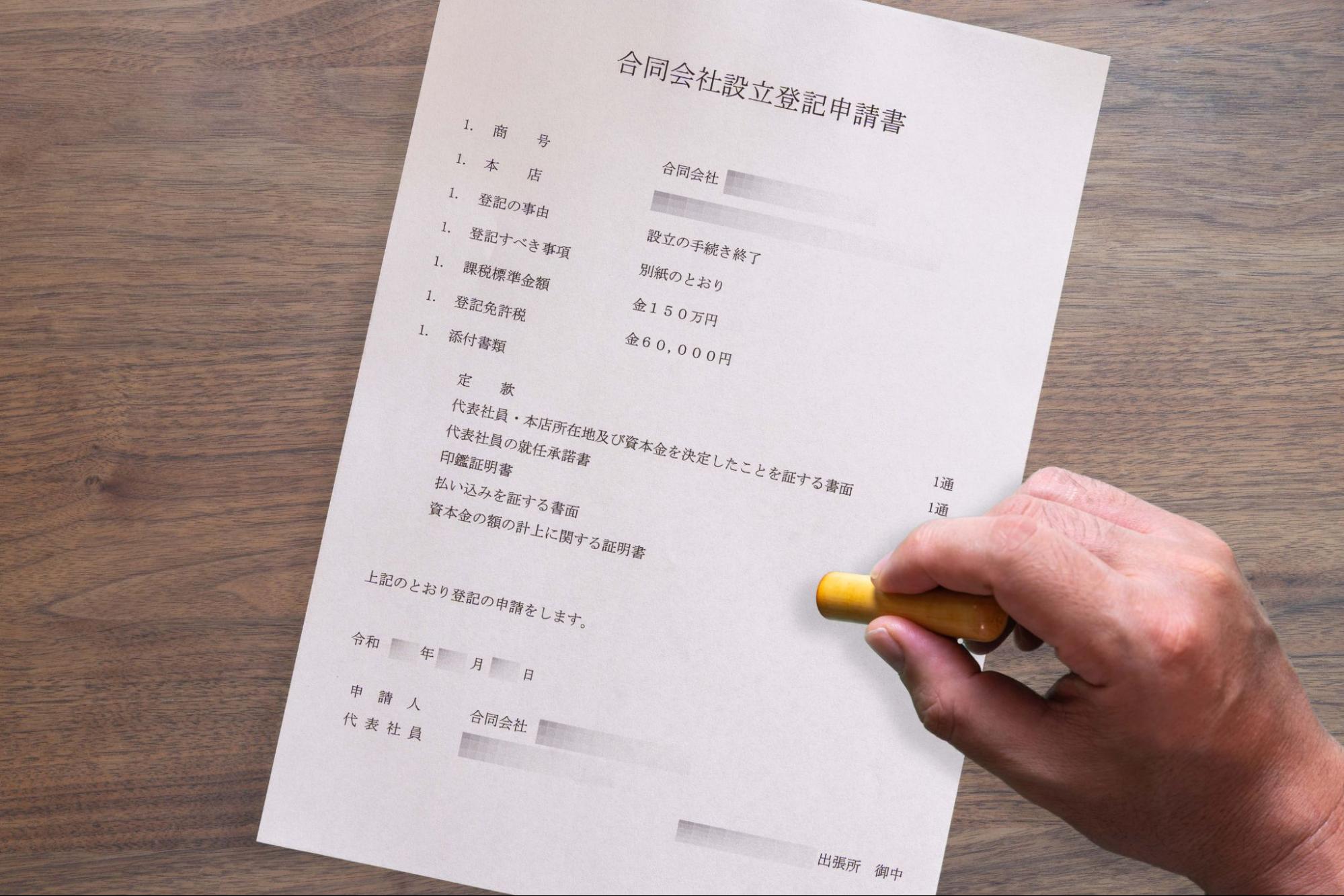
合同会社設立手続きの流れは以下の通りです。
| ステップ | 説明 |
|---|---|
| 1.会社の基本事項を決定 | 商号、所在地、事業内容、資本金、社員など会社の基本情報を決める。 |
| 2.法人用の実印を作成 | 会社の実印を作成する。登記申請時に必要なため、余裕を持って準備する。 |
| 3.定款を作成 | 会社運営のルールを定めた定款を作成する。合同会社は公証人役場での認証が不要で、電子定款によって収入印紙代を節約できる。 |
| 4.資本金の払い込み | 決めた資本金を代表社員の個人口座に払い込み、払込証明書を作成する。 |
| 5.登記申請書類の作成 | 定款、印鑑届出書、代表社員の印鑑登録証明書、払込証明書、合同会社設立登記申請書などの必要書類を準備してまとめる。 |
| 6.法務局に登記申請 | 管轄の法務局に設立登記申請を行い、登記が完了すると法人格が取得され合同会社として正式に設立となる。 |
この流れで登記が完了すれば、法人格を取得して事業開始が可能です。
株式会社に比べると手続きは簡単であるものの、さまざまな書類や手続きが必要となるため、専門家への相談もおすすめです。
合同会社の設立にかかる費用と時間
合同会社の設立にかかる費用は、合計で約10万円が目安です。
内訳は以下の通りです。
- 定款の収入印紙代
- 登録免許税
- 印鑑作成費用
専門家に手続きを依頼する場合は別途報酬がかかることもあります。
株式会社と異なり、定款認証手数料が不要なため、設立費用を大幅に抑えられます。設立にかかる時間は、登記申請から完了まで約2~3週間で、書類の準備状況や申請のスムーズさによって変動します。
設立後には税務署や年金事務所などへの各種手続きも必要です。
合同会社に向いている業種・事業形態
合同会社に向いている業種・事業形態は、設立費用や運営コストを抑えたい小規模事業に最適です。
特にコンサルティングやデザイン事務所、IT関連、クリエイティブ産業など、資金を多く必要としない業種に向いています。また、飲食店や美容サロン、小売業、不動産管理業、学習塾などのBtoC事業も適しています。
合同会社は経営の自由度が高く、出資者全員が経営に参画できるため、少人数の共同経営にも最適です。一方で、業種や事業形態により、社会的信用度は株式会社に比べると低く見られる傾向にあるため、信用性が重要なBtoB事業には不向きな場合もあります。
合資会社を設立するメリット・デメリット

合資会社の設立には定款認証の手続きや費用が不要であり、登録免許税も比較的低いため、経済的なメリットがあります。
一方で、無限責任社員が会社の債務に対して無制限に責任を負う、個人的信用に過度に依存する可能性があるというデメリットも存在します。
ここでは、合資会社のメリットとデメリットを紹介します。
メリット
合資会社を設立する際の登録免許税は6万円ですが、定款認証の手続きや費用は必要ありません。この点は株式会社と比べた場合にメリットといえます。
合資会社は無限責任社員と有限責任社員によって構成されるため、資金を調達したい事業家(経営者)が自ら無限責任を負いながら資金を集めやすくなります。
出資者にとっても、自身の責任範囲を限定しながら利益の分配を期待できる点がメリットです。
デメリット
合資会社の主なデメリットは、無限責任社員が会社の債務に対して無制限に責任を負わなければならないことです。
また、会社の運営においては無限責任社員の個人的信用に過度に依存する傾向が見られることもデメリットとして考えられます。
合資会社の設立手続きの流れ
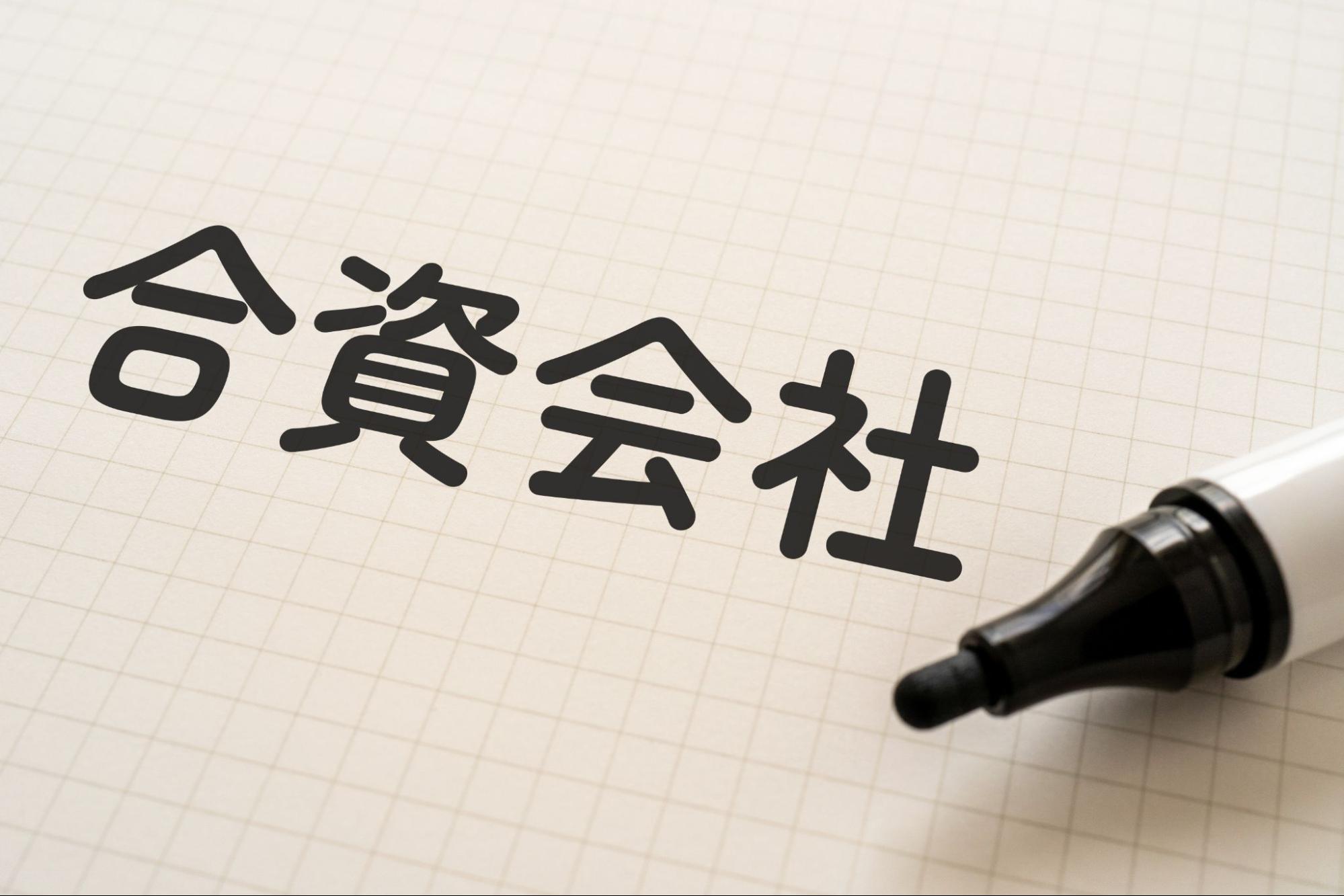
合資会社の設立手続きの流れは以下の通りです。
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| 1.会社の基本事項を決定 | 商号、所在地、事業内容、出資者、代表社員など会社の基本情報を決める。 |
| 2.法人用の実印を作成 | 登記申請に必要となるため、会社の実印を作成する。 |
| 3.定款を作成 | 会社運営のルールを定めた定款を作成する。 |
| 4.資本金の払い込み | 有限責任社員が資本金を払い込み、その証明書を作成する。 |
| 5.登記申請書類の作成 | 定款、登記申請書、払込証明書、出資者の印鑑証明書、代表社員就任承諾書、印鑑届出書など必要書類を揃える。 |
| 6.法務局に登記申請 | 管轄の法務局で登記申請を行い、登記が完了すれば法人格を取得して合資会社の設立が完了する。 |
合資会社は無限責任社員がいるため、責任範囲や経営の仕組みを明確にして設立することが重要です。
手続きは合同会社と似ていますが、責任形態や出資の違いを理解したうえで進める必要があります。
設立にかかる費用と期間
合資会社の設立にかかる費用は、約10万円程度が目安です。
これは主に登録免許税が6万円、定款に貼る収入印紙代が4万円で構成されており、合同会社や合名会社と同様に定款認証が不要なため、株式会社に比べて設立費用を抑えられます。
設立にかかる期間は、登記申請から完了まで約2~3週間で、書類の準備状況や登記申請のスムーズさによっても変わってきます。
設立した後は、税務署や年金事務所などへの各種届出も必要です。
どのような事業に向いているか
合資会社は、無限責任社員と有限責任社員の両方で構成され、家族経営や信頼できる少人数での経営に向いています。
資本金の最低額がなく現物出資も可能なため、伝統的な地場産業や専門技術、サービス業に適しています。例えば、酒造や旅館経営、タオル製造など、長く続き伝統産業に多く採用されているのが特徴です。
社内の関係が親密で、経営資質や人的絆が重要視されるため、経営者と出資者の役割分担が明確な起業に適しています。
また、設立コストが低く定款の自由度も高いため、少人数での起業や地域密着型の事業に向く法人形態です。
合名会社を設立するメリット・デメリット

合名会社の設立には定款認証の手続きや費用が不要であり、登録免許税も比較的低いため、経済的なメリットがあります。
しかし、すべての出資者が無限責任社員として会社の債務に無制限に責任を負わなければならないデメリットもあります。
ここでは、合名会社のメリットとデメリットを紹介します。
メリット
合名会社を設立する際の登録免許税は、6万円という比較的低い金額で済みます。
また、合名会社の設立には定款認証の手続きや費用が不要です。この点は、株式会社と比較しての明確なメリットといえます。
設立費用を抑えることができるため、起業や事業展開の初期費用を削減できます。
定款認証の手続きが不要なため、設立手続きが簡便に行える点も魅力です。
デメリット
合名会社の主なデメリットは、すべての出資者が無限責任社員として会社の債務に無制限に責任を負わなければならない点です。
つまり、出資者は個人の財産が会社の債務に拘束されるリスクを負うことになります。
もし会社が借金や債務不履行などの問題に直面した場合、出資者は自身の財産を差し出さなければならず、個人の資産や財産が危険にさらされる可能性があります。
合名会社の設立手続きの流れ

合名会社の設立手続きの流れは以下の通りです。
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| 1.会社の基本事項を決定 | 商号に「合名会社」を含み、所在地、事業目的、社員、資本金などの基本情報を決める。 |
| 2.類似商号調査を行う | 全社員が無限責任を負う重い法的責任を伴うため、商号のトラブルによるリスクを回避するため。 |
| 3.法人用の実印を作成 | 法人用の実印を作成する。 |
| 4.定款を作成。 | 会社の運営ルールを定めた定款を作成。複数部作成し、法務局への提出用に準備する。公証人の認証は不要。 |
| 5.資本金の払い込み | 全社員が無限責任社員のため、必ずしも資本金を払い込まなくてもよい。 |
| 6.登記申請書類の作成 | 設立登記申請書、定款、資本金の払込証明書、社員全員の印鑑証明書、印鑑届出書、代表社員の就任承諾書などを用意する。 |
| 7.法務局に登記申請 | 準備した書類を管轄の法務局に提出し、登記申請を行う。登記完了後に法人格を取得し、合名会社が正式に成立する。 |
合名会社は社員全員が無限責任を負う形態となるため、設立の各段階で社員間の合意や責任範囲の確認を十分に行うことが重要です。
流れに沿って手続きを進めることで、法的トラブルを避け、スムーズな会社設立が可能となります。
設立にかかる費用と期間
合名会社の設立にかかる費用は、約10万円程度が目安です。
主に登録免許税6万円と定款に貼る収入印紙代4万円で約10万円ほどで、定款認証手数料が不要となるため、株式会社に比べて設立費用を抑えられます。また、実印作成費用や専門家に依頼する費用が別途かかる場合もあるため注意しましょう。
設立にかかる期間は、登記申請から完了まで約2~3週間が標準的で、書類準備の状況や申請のスムーズさによって変動があります。
設立後には税務署や年金事務所への届出が必要です。
合名会社が向いているケース
合名会社が向いているケースは、社員全員が経営に深く関わり、意思決定をスピーディーに行いたい場合に適しています。
合名会社は社員全員が無限責任を負うため、経営に対する責任感が強く、社員間の信頼関係が重要です。また、業務執行権や代表権が社員全員にあるため、各自が積極的に経営に参加でき、自由度の高い経営スタイルを望むケースにも向いています。
例えば、複数の個人事業主が共同で営む専門職や技術者のグループ、地域密着型の小規模サービス業、伝統的な手工業などです。一方で、規模の大きな資金調達や株式発行を必要とする事業には向いていません。
なお、合名会社は設立費用が低く設立のハードルも低いため、新規参入が比較的容易な点も、小規模事業やスタートアップに適した理由です。
【重要】株式会社と合同会社の違い

会社を設立する場合には、株式会社との比較をする必要があるため知識が必要です。
ここでは、株式会社と合同会社の主な違いを紹介します。
設立費用
合同会社の設立費用は株式会社よりも低く、最低でも約10万円から始めることができます。一方、株式会社の設立には最低でも24万円以上の費用が必要です。
収入印紙代は電子定款で免除できますが、残りの20万円は必ず支払う必要があります。
小規模で始めたい場合には、株式会社の設立費用は負担が大きいといえるでしょう。
経営の自由度
経営の自由度においても株式会社と合同会社には差があります。
合同会社は、株式会社に比べて組織運営の自由度が高いです。合同会社では、利益の配分や経営方針の決定を自由に行うことができます。
一方、株式会社は株主総会などの手続きや決定プロセスが複雑であり、組織の決定に時間がかかることがあります。
対外的な信用力
株式会社は一般的な会社形態であり、社会的な信用力が高い傾向があります。
株式会社という形態に慣れ親しんでいるため、ビジネスパートナーや金融機関などからの信用を得やすいです。
一方、合同会社は比較的新しい会社形態であるため、知名度や信用獲得が課題となる場合があります。合同会社としての信用を築くためには、事業実績や信頼性の向上が重要です。
決算公告義務
株式会社では、決算書の一部を公告する義務があります。
一方、合同会社には決算公告義務がないため、秘匿性やプライバシー保護につながります。
株式会社は公開性が高い一方、合同会社は非公開性が高いという違いがあります。
【結論】自分に合うスタイルの会社で起業を成功させよう
会社形態にはそれぞれ特徴やメリット・デメリットがあり、目的やビジネススタイルによって適した選択が異なります。
株式会社は資金調達力が高く、大規模事業や成長を目指す場合に適しています。一方で、組織運営の自由度については合同会社の方が柔軟です。一方、合同会社は設立コストが低く、少人数での柔軟な経営を希望するスタートアップや小規模事業に向いています。
合資会社は無限責任社員と有限責任社員からなるため、経営と資金調達の役割が分担され、信頼できる少人数の事業に最適です。合名会社は社員全員が無限責任を負う責任感の強い経営が必要で、密接な信頼関係を持つ小規模な専門職グループや伝統的な事業に向いています。
各会社形態の特徴やメリット、デメリットを十分に理解し、自身のビジネスの目的や将来計画に合った会社形態を選択することが起業成功のカギとなります。
会社の銀行口座(法人口座)はGMOあおぞらネット銀行がおすすめ!

画像引用元:GMOあおぞらネット銀行
会社設立時にネットバンクで銀行口座を開設するなら、GMOあおぞらネット銀行がおすすめです。
手間なくスピーディーに口座開設できる点が強みで、口座開設手続きは印鑑レス・ペーパーレス・郵送レスで行うことができます。また、条件を満たせば最短即日で口座を開設できます。
振込手数料は同行宛て無料に加え、他行宛てでも一律143円/件(税込)(※)と低価格で、さらに設立1年未満のお客さまであれば、他行宛て振込手数料が月20回まで無料です。
創業期のお悩みを解決するため、外部企業と提携してさまざまなサービスを紹介するビジネスサポートも行っており、会社運営の面でも強い味方になるでしょう。
ぜひGMOあおぞらネット銀行をご利用ください。
(※)2025年8月1日より
起業や開業、独立に興味を持ったら、まずは「起業の窓口」に登録してみよう!
「起業の窓口」では、起業に必要なノウハウや成功者のインタビューなど、さまざまなコンテンツを完全無料で提供しています。
会員特典として、起業・経営支援のプロ「V-Spirits」が監修するオリジナル冊子『会社設立完全ガイド』を無料プレゼント。さらに、V-Spritsによる1時間の無料起業相談や、GMOインターネットグループが展開するビジネスの立ち上げや拡大に役立つ各種サービスをおトクな特典付きでご紹介します。
あなたの夢の実現を全力でサポートします!
- 記事監修
-
- 中野 裕哲 HIROAKI NAKANO
- 起業コンサルタント(R)、経営コンサルタント、税理士、特定社会保険労務士、行政書士、サーティファイドファイナンシャルプランナー・CFP(R)、1 級FP 技能士。 V-Spiritsグループ創業者。東京池袋を本拠に全国の起業家・経営者さんを応援!「あの起業本」の著者。著書16冊、累計20万部超。経済産業 省後援「DREAMGATE」で11年連続相談件数日本一。
GMOインターネットグループ株式会社はGMOあおぞらネット銀行株式会社を所属銀行とする銀行代理業として、円普通預金の受入れを内容とする契約の締結の媒介を行います。
銀行代理業許可番号:関東財務局長(銀代)第335号
- ※本記事は、起業の窓口編集部が専門家の監修または独自調査(アンケート)に基づいて制作したものです。
- ※掲載している情報は、記事公開時点の法令・税制・商品・サービス等に基づくものであり、将来的に変更される可能性があります。
- ※アンケート調査に関する記述は、特定の調査対象者からの回答結果および編集部の見解を含んでおり、内容の正確性・完全性を保証するものではありません。
- ※記事の内容は一般的な情報提供を目的としており、すべての方に当てはまるものではありません。個人の状況に応じた具体的な助言が必要な場合は、専門家にご相談ください。
- ※情報の利用や判断、実施については、ご自身の責任で行っていただきますようお願いいたします。
- ※本記事に掲載された内容の転載・複製はご遠慮いただき、引用の際は必ず出典をご明記ください。



 シェア
シェア