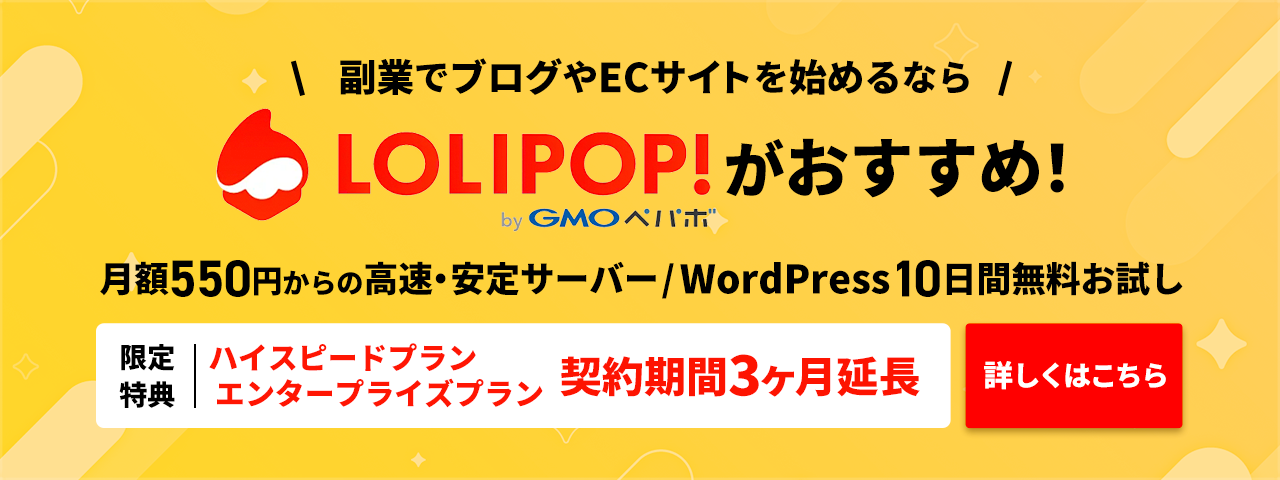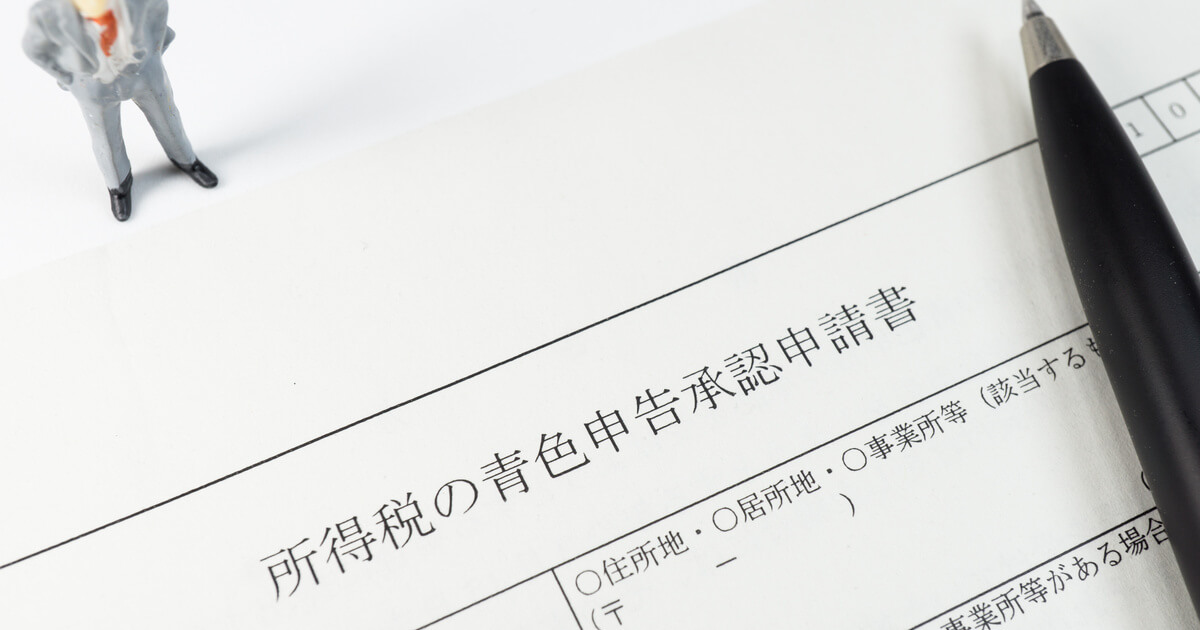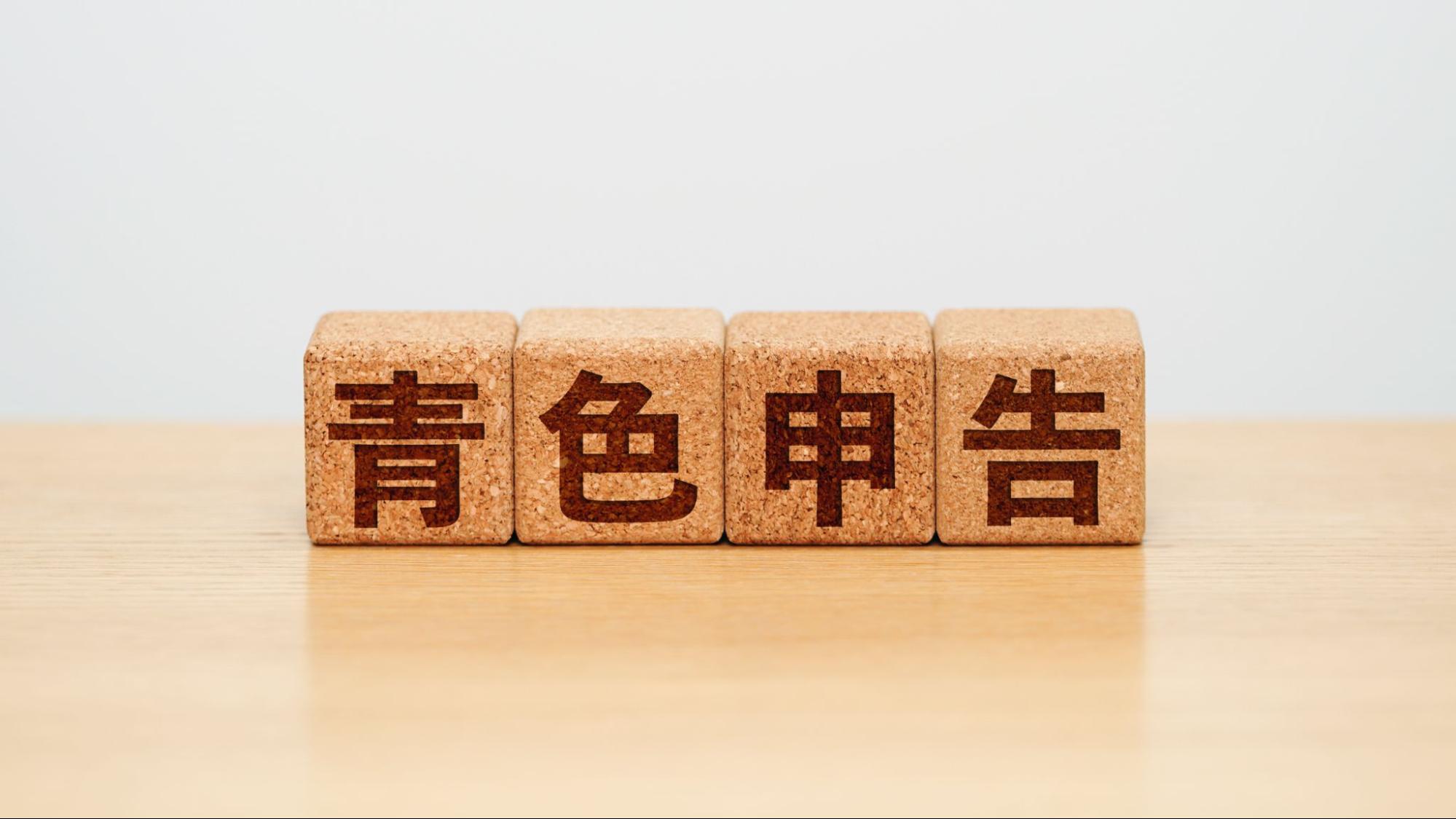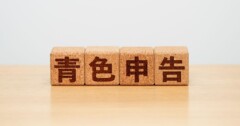副業で損しないための源泉徴収表の基本|確定申告で還付金をもらう方法と計算式、よくある質問まで
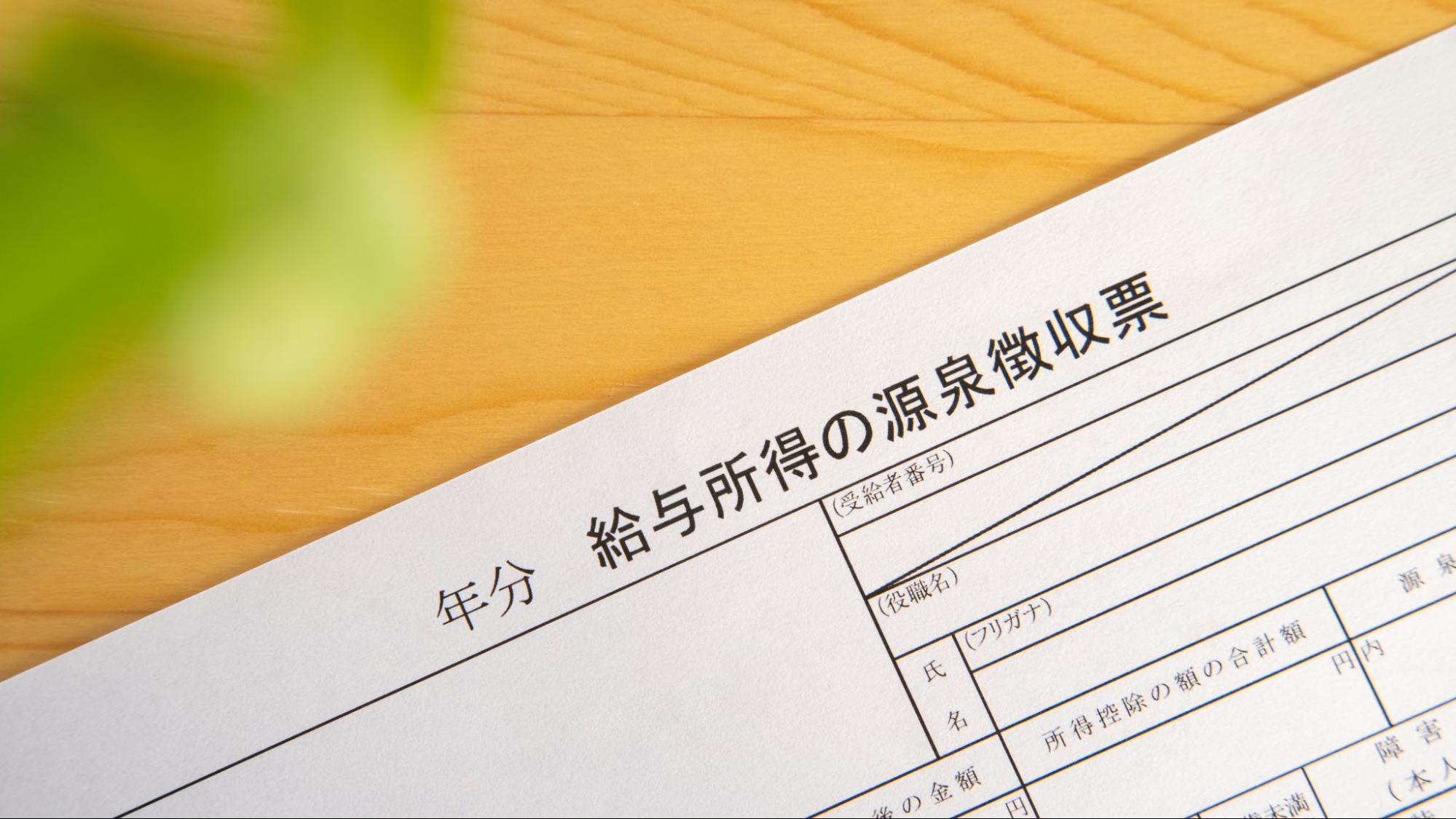
源泉徴収とは、給与を支払う法人および個人が所定の金額を差し引き、受け取る人に代わって納税する制度のことです。
副業するからには、それら源泉徴収について知っておくことが必要となるでしょう。
この記事では、源泉徴収の基本知識や対応方法、注意点、見方について解説し、よくある質問を紹介します。
副業の源泉徴収について知りたい人は、ぜひ参考にしてみてください。
- 【この記事のまとめ】
- 副業する人が知っておきたい源泉徴収とは、給与を支払う法人および個人が所定の金額を差し引き、受け取る人に代わって納税する制度のこと
- 源泉徴収票がある場合は、給与所得・雑所得・株取引ごとに対応が必要となる
- 副業する場合は、源泉徴収票を受け取った際の対応方法や注意点、見方について知っておかないと税金の面でトラブルになりやすい
源泉徴収とは?【結論:あらかじめ税金が差し引かれる制度】
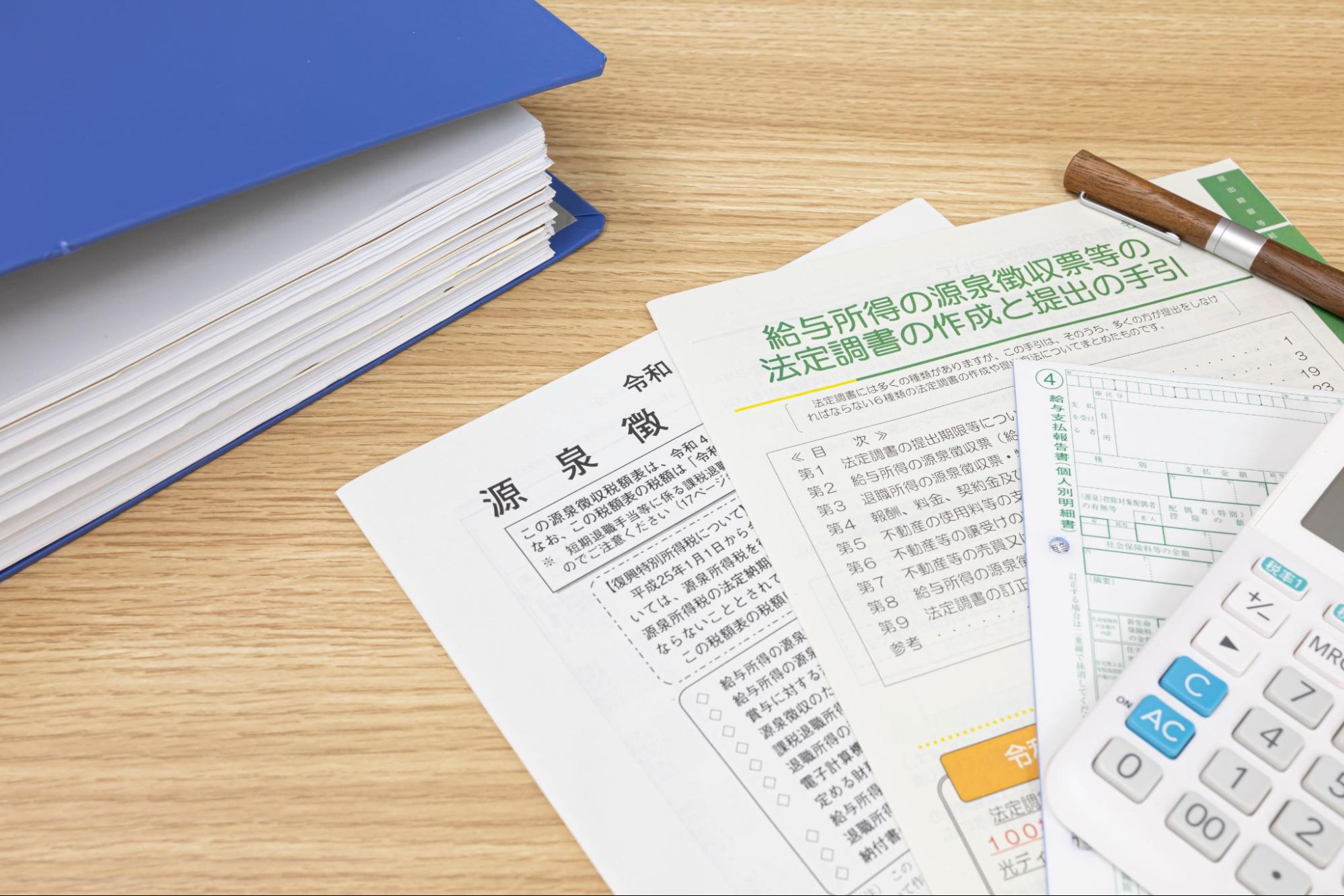
副業する人は、源泉徴収が何を意味するのか知っておくことが重要です。
ここでは、源泉徴収について詳しく解説します。
源泉徴収の意味と目的をわかりやすく解説【仕組み・メリット】
源泉徴収は、給与を支払う法人および個人が所得税を差し引き、受け取る人に代わって納税する制度のことです。
副業などで本業とは別の仕事をすると職場から源泉徴収票が送られてくるため、必要に応じて確定申告を行ったり重要書類を保管したりします。
源泉徴収票とは、法人および個人が支払った給与の金額や天引きした所得税額などが記載された書類のことで、確定申告などに使用します。
副業で1年間に20万円を超えるの給与収入を得た人は、源泉徴収票の他に確定申告書類を作成して管轄の税務署に提出し、所得税を確定させることが必要です。
フリーランスだと源泉徴収されないなど例外もありますが、給与所得者の場合は源泉徴収票に従って確定申告を行うことが求められるでしょう。
源泉徴収については、以下の記事でも解説しています。
源泉徴収の計算式とは?【給与・報酬別に紹介】
フリーランスの場合、源泉徴収の計算は100万円以下と100万円以上で変わるため、注意が必要です。
源泉徴収額の計算方法は、以下となります。
- 100万円以下の場合:支払金額×10.21%
- 100万円以上の場合:(支払金額-100万円)×20.42%+102,100円
100万円以下の場合は支払金額×10.21%で計算するのに対して、100万円以上の場合は(支払金額-100万円)×20.42%+102,100円で計算します。
仮に20万円の収入があった場合、20万円×10.21%=2万420円が源泉徴収額です。
120万円の収入があった場合は、(120万円-100万円)×20.42%+102,100円=14万2,940円が源泉徴収額です。
以上のように収入に応じて源泉徴収額が変動するため、どれくらい稼いだのかについては自分自身で把握しておくのが良いでしょう。
副業は源泉徴収の対象?【報酬の種類によって異なる】
副業における源泉徴収の対象には、以下のようなものがあります。
- 弁護士、公認会計士、司法書士等の特定の資格を持つ人などに支払う報酬・料金
- 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬
- プロ野球選手、プロサッカー選手、プロテニス選手、モデルや外交員などに支払う報酬・料金
- 映画、演劇その他芸能(音楽、舞踊、漫才等)、テレビジョン放送等の出演等の報酬・料金や芸能プロダクションを営む個人に支払う報酬・料金
- ホテル、旅館などで行われる宴会等において、客に対して接待等を行うことを業務とするいわゆるバンケットホステス・コンパニオンやバー、キャバレーなどに勤めるホステスなどに支払う報酬・料金
- プロ野球選手の契約金など、役務の提供を約することにより一時に支払う契約金
- 広告宣伝のための賞金や馬主に支払う競馬の賞金
国税庁からの引用となるためややわかりにくいですが、以上の項目が源泉徴収の対象となるため、どのような場面で源泉徴収されるのかを確認しておくと安心です。
源泉徴収の対象となりやすい具体的な副業職種【対象職種と報酬パターン例】
国税庁が定める「報酬・料金等」に含まれる仕事をしている場合、報酬支払者(クライアント)側で源泉徴収が行われます。特に以下の職種で副業をしている方は、報酬から税金が天引きされている可能性が高いため、請求書や支払明細を確認しましょう。
- Webライター・作家(原稿料)
- デザイナー・イラストレーター(デザイン料・挿絵料)
- エンジニア・プログラマー(技術指導料など契約形態による)
- 講演家・講師(講演料)
- モデル・コンパニオン(出演料)
- スポーツ選手・コーチ(指導料など)
- 弁護士・税理士・会計士などの有資格者
クラウドソーシングサイトなどを通じて仕事をしている場合も、システム上で源泉徴収されているケースがあります。手取り額が想定より少ない場合は、源泉徴収税額(通常10.21%)が引かれていないか確認してください。
支払調書と源泉徴収票の違いとは?【役割・発行元・用途の違い】
源泉徴収票と支払調書の違いは、以下の通りです。
- 源泉徴収票:事業者が雇用契約を結んだ従業員に対して発行する書類
- 支払調書:税務署に対して提出する書類
源泉徴収票と支払調書は似た性質を持つ書類ですが、従業員の給与に対して作成する書類か、取引先の報酬に対して作成する書類かそれぞれ目的が違うため、ご注意ください。
年末調整と源泉徴収の違いを簡単に整理【仕組みと手続きの流れ】
源泉徴収と年末調整の違いは、以下の通りです。
- 源泉徴収:給与や報酬から所定の金額を差し引き、従業員や業務委託先に代わって納税する仕組み
- 年末調整:毎月の給与から源泉徴収した所得税の金額と本来徴収すべき1年分の所得税額との差分を調整する仕組み
源泉徴収と年末調整も似た性質を持つ仕組みですが、従業員に代わって納税する仕組みなのか、差分を調整する仕組みなのかが違うため、注意しましょう。
源泉徴収票の対応方法【副業でも必ず確認を】

源泉徴収票の対応方法は給与所得・雑所得・株取引で変わるため、注意が必要です。
ここでは、源泉徴収票の対応方法について詳しく解説します。
副業の「20万円ルール」は「売上」ではなく「所得(利益)」で判断!
「副業で20万円稼いだら確定申告が必要」とよく言われますが、この20万円とは銀行に振り込まれた金額(収入)のことではありません。「収入(売上)」から「必要経費」を差し引いた「所得(利益)」のことを指します。
計算式:収入(売上)-必要経費=所得
例えば、副業のWebデザインで年間30万円の売上があったとしても、パソコン購入費やソフト代などの経費が15万円かかっていた場合、所得は15万円となります。
売上30万円-経費15万円=所得15万円
この場合、所得が20万円以下のため、所得税の確定申告は原則不要となります(ただし、住民税の申告は必要です)。
源泉徴収されている場合、所得が20万円以下であっても確定申告をすることで、払いすぎた税金(源泉徴収税額)が戻ってくる(還付される)可能性が高いため、シミュレーションしてみることをおすすめします。
副業が「給与所得」の場合の注意点
副業で得た収入が給与所得で、合計額が20万円を超えている場合で計算の結果納税が発生する場合は確定申告が必要です。
確定申告では、本業と副業の給与所得を合算し、所得税を再計算します。
毎年2月16日〜3月15日が確定申告期間となるため、勤め先から受け取った源泉徴収票を持参し、必要な情報を確定申告書類に転記してください。
なお、以下に該当する人は確定申告の必要はありません。
- 各種の所得金額(給与所得や退職所得を除く)の合計金額が20万円以下の場合
- 本業と副業の給与所得から所得控除(基礎控除や医療費控除など)の合計金額を引いた額が年間150万円以下の場合
副業が「雑所得(フリーランス・業務委託)」の場合の注意点
副業で得た収入が雑所得で、経費を引いた額が20万円を超えた場合も確定申告が必要です。
確定申告では、本業で受け取った源泉徴収票と年間の収入の集計(手元にあれば副業で受け取った支払調書)をもとに、手続きを行います。
なお、収入が事業所得に該当する人で青色申告の承認を受けて人は以下の優遇措置を利用できるため、忘れずに確認しておきましょう。
- 青色申告特別控除
- 30万円未満の少額減価償却資産の特例
- 純損失の繰り越し・繰り戻し
- 損益通算
雑所得と事業所得は、どちらに該当するかについて明確な基準はありませんが、副業で得る収入は事業所得ではなく雑所得に該当することがほとんどであるため、要注意です。
本業の労働時間外で働く人は、雑所得として考えます。暗号資産やFX取引で得た収入も雑所得として処理すると良いでしょう。
副業が「株式投資」の場合の源泉徴収と確定申告
株取引によって利益を得た場合は、他の所得と分離して税額を計算しなければいけません。
株取引で譲渡所得や配当所得を得ている場合や取引口座が一般口座、源泉徴収なしの特定口座である場合は確定申告が必要となります。
一方、株取引で損失が生じた場合、利益が出たものの20万円以下だった場合は確定申告が不要となります。
また、源泉徴収ありの特定口座で優遇措置を適用したい場合は確定申告が必須となるため、注意が必要です。
源泉徴収票に関する3つの注意点【もらえない・なくす・期限切れ】

源泉徴収票では、いくつか注意が必要です。
ここでは、源泉徴収票の注意点について詳しく解説します。
確定申告期間が限られる
確定申告期間が限られる点には、注意が必要です。
副業で1年間に20万円を超えるの所得を得た場合は確定申告が必要となりますが、確定申告できる期間は毎年2月16日〜3月15日と決められています。
確定申告が必要な場合は、必ず期限内に申告するようにしてください。
確定申告期間を過ぎていた場合は、ペナルティとして納税額が加算されることがありますが、故意に手続きしなかった場合は追徴課税が課せられます。
追徴課税の主な種類は、以下の通りです。
- 過少申告加算税
- 無申告加算税
- 不納付加算税
- 重加算税
- 延滞税
確定申告を忘れていた場合に課せられる可能性があるのは、無申告加算税と延滞税となります。
一方で故意に申告する金額を変えたり、申告せずにいたりすると過少申告加算税や無申告加算税、不納付加算税の他、重加算税が課せられることもあります。
確定申告が必要な人は、必ず確定申告期間内に手続きを済ませましょう。
なくさないようにする
源泉徴収票はなくすことがあるため、必ずなくさないようにしてください。
一度なくしてしまうと確定申告書類の作成が困難になる他、新たに発行してもらう必要も出てくるなど、手間がかかってしまいます。
受け取った源泉徴収票は、大切に保管しましょう。
もらえないことがある
源泉徴収票はもらえないことがあるため、その際は必ず確認するようにしましょう。
もしもらえないようなら職場の所在地を管轄する税務署に、源泉徴収票不交付の届出書を提出して相談します。
退職などで状況が複雑化している場合は、専門家に相談してみてください。
源泉徴収票の見方【どこをチェックすればいい?】

源泉徴収票には複数の金額が記載されているため、見方を知っておくと理解しやすいです。
源泉徴収票に記載されている金額には、以下のようなものがあります。
- 支払金額
- 給与所得控除後の金額
- 所得控除の額の合計額
- 源泉徴収税額
源泉徴収票を受け取ったら真っ先に確認しておきたいのが、以上4点の項目です。収入金額と所得金額は別物となるため、各金額についてよく確認しておくことが求められます。
自分の報酬からいくら引かれている?計算シミュレーション
副業(原稿料やデザイン料など)の場合、源泉徴収税額は原則として以下の計算式で求められます。
1回の支払金額が100万円以下の場合:支払金額×10.21%
1回の支払金額が100万円超の場合:(支払金額-100万円)× 20.42%+10万2,100円
【例:副業で5万円の報酬を得た場合】
計算:50,000円×10.21%=5,105円
手取り額:50,000円-5,105円=44,895円
この天引きされた「5,105円」は、あなたが前払いした所得税です。年間のトータルの税金を計算した結果、払いすぎていれば確定申告によって戻ってきます。
副業の源泉徴収のよくある質問(FAQ)

副業する際は、源泉徴収に関する疑問を解消しておくと安心です。
ここでは、副業の源泉徴収のよくある質問について詳しく解説します。
「収入」と「所得」はどう違いますか?【計算方法と控除の考え方】
「収入」は売上の合計、「所得」は売上から経費を引いた利益です。 確定申告が必要かどうかの「20万円の壁」は、「収入」ではなく「所得(収入ー経費)」で判断します。経費を正しく計上することで、確定申告が不要になる場合もあります。
源泉徴収票はいつ・どこから届く?【受け取りタイミングと確認方法】
源泉徴収票は、勤務先で受け取るか退職後は住所に送られてくるのが一般的です。
基本的には年間最後の給与支払い日、または退職後1カ月以内に発行されます。
源泉徴収されたら確定申告は不要?【例外と注意点まとめ】
源泉徴収されている人のうち、年末調整を受けている人は確定申告は不要ですが、副業など本業とは別に収入を得た人で、1年間の収入が20万円を超える人で納税が発生する場合は確定申告が必要となります。
一般的に納税の有無に応じて確定申告すべきかが変わるため、注意が必要です。
源泉徴収義務者については、以下の記事でも解説しています。
源泉徴収された状態で確定申告するとどうなる?【還付・追加納税のパターン】
源泉徴収された分を加味して確定申告すると、以下のどちらかとなります。
- 源泉徴収され過ぎた金額が戻ってくる
- 所得税の不足分が発生することがある
一般的には源泉徴収され過ぎた金額が戻ってくるため、還付金を受け取ることが可能です。
一方で、源泉徴収税額が少ない場合は所得税の不足分が発生することがあるため、その場合は不足分を納税します。
本業と副業を別々に確定申告することは可能?【申告は合算が原則・例外あり】
確定申告は、1年間の所得に対して納税額を計算して申告し、納税する一連の手続きとなるため、本業と副業を別で確定申告できません。
副業による所得は所得税の課税対象となるため、本業による所得と合算して申告します。
収入が20万円以下の場合は申告しなくても構いませんが、20万円を超えているにもかかわらず申告しないのは問題となるため、忘れずにご申告ください。
ダブルワークなど、いくつかの仕事を掛け持ちしている人も合算して確定申告が必要です。
本業の会社で、副業分の源泉徴収票もまとめて年末調整できますか?【原則NG・できるケース】
いいえ、できません。 年末調整は「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している1社(本業)でしか行えません。副業先から発行された源泉徴収票は、本業の源泉徴収票と合わせて、ご自身で確定申告を行う必要があります。
副業の収入が20万円以下なら、源泉徴収されていても放置していいですか?【申告不要の条件と落とし穴】
放置すると損をする可能性があります。 所得税の確定申告義務はありませんが、源泉徴収(天引き)されている場合、確定申告をすることで払いすぎた税金が「還付金」として戻ってくる可能性が高いです。また、所得税の申告が不要でも、住民税の申告は別途必要になるケースがほとんどです。
源泉徴収票が送られてこない場合はどうすればいいですか?【再発行依頼と確認手順】
まずは副業先に発行を依頼しましょう。 法律上、支払者は発行義務があります。それでも発行されない場合は、給与明細や支払調書、通帳の入金記録などを基に金額を集計し、税務署に相談してください。場合によっては「源泉徴収票不交付の届出書」を提出することになります。
確定申告を楽にしたいと悩む方へ

質問に答えていくだけで、経理の作業がはじめての方でも簡単に確定申告の書類作成をすることができます!
確定申告を楽にサクッとおこないたい方は、freeeがおすすめです!
副業ではお金に関する手続きが必要となる場合が。事前に確認を
副業を行う際、源泉徴収されることがあります。
源泉徴収は給与を支払う法人および個人が所定の金額を差し引き、受け取る人に代わって納税する制度のことです。
最近は本業の他に仕事をする人も多いため、少なくとも源泉徴収に関する情報は覚えておいて損はありません。むしろ、税金面でのトラブルを回避するためにも知っておきましょう。
当記事で解説した内容は源泉徴収に関するものがメインでしたが、副業では他にもお金に関する手続きが必要となる場合があります。情報を調べてから挑戦するようにしましょう。
スキマ時間を有効活用!副業に興味を持ったら、まずは「起業の窓口」に登録してみよう
副業で収入アップを考えている方も多いと思いますが「時間がない」と感じて諦めている方も多いのではないでしょうか。しかし、スキマ時間を上手く利用して副業をすることで、本業とは異なる収入源を持つことが可能です。
起業の窓口では、スキマ時間に手軽に始められるおすすめの副業やメール、SNS、AIを活用した副業、必要なノウハウなど、さまざまなコンテンツを無料でご提供。また、GMOインターネットグループが展開する副業に役立つ各種サービスをおトクな特典付きでご紹介しています。
副業から起業を目指す人にもオススメです。
- 記事監修
-
- 中野 裕哲 HIROAKI NAKANO
- 起業コンサルタント(R)、経営コンサルタント、税理士、特定社会保険労務士、行政書士、サーティファイドファイナンシャルプランナー・CFP(R)、1 級FP 技能士。 V-Spiritsグループ創業者。東京池袋を本拠に全国の起業家・経営者さんを応援!「あの起業本」の著者。著書16冊、累計20万部超。経済産業 省後援「DREAMGATE」で11年連続相談件数日本一。
- ※本記事は、起業の窓口編集部が専門家の監修または独自調査(アンケート)に基づいて制作したものです。
- ※掲載している情報は、記事公開時点の法令・税制・商品・サービス等に基づくものであり、将来的に変更される可能性があります。
- ※アンケート調査に関する記述は、特定の調査対象者からの回答結果および編集部の見解を含んでおり、内容の正確性・完全性を保証するものではありません。
- ※記事の内容は一般的な情報提供を目的としており、すべての方に当てはまるものではありません。個人の状況に応じた具体的な助言が必要な場合は、専門家にご相談ください。
- ※情報の利用や判断、実施については、ご自身の責任で行っていただきますようお願いいたします。
- ※本記事に掲載された内容の転載・複製はご遠慮いただき、引用の際は必ず出典をご明記ください。



 シェア
シェア