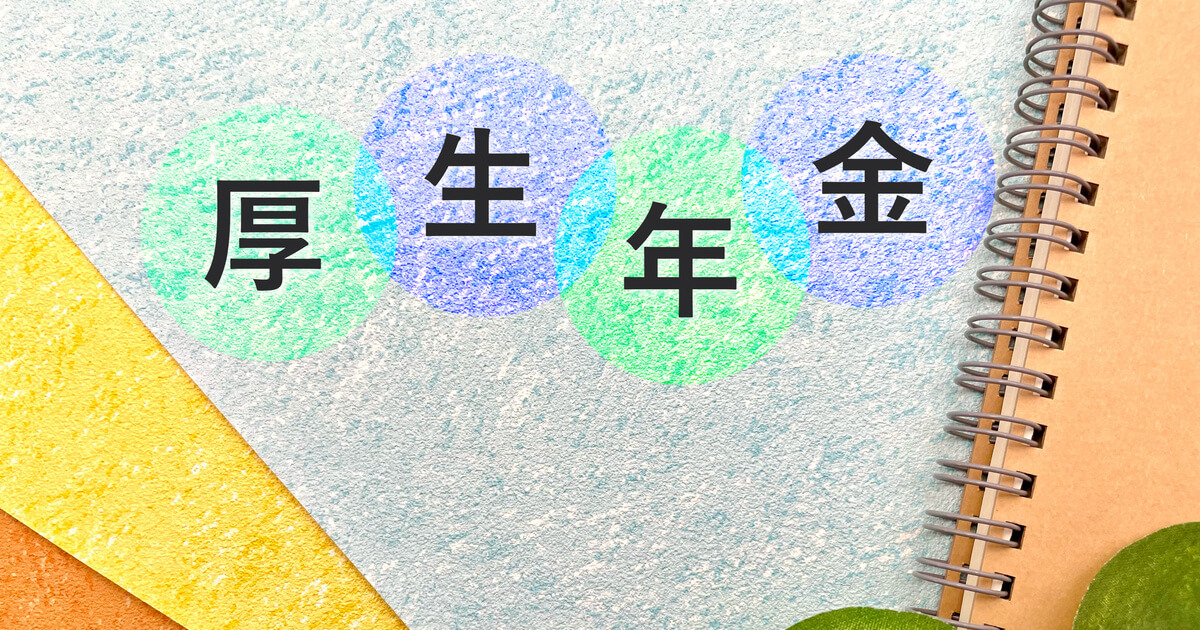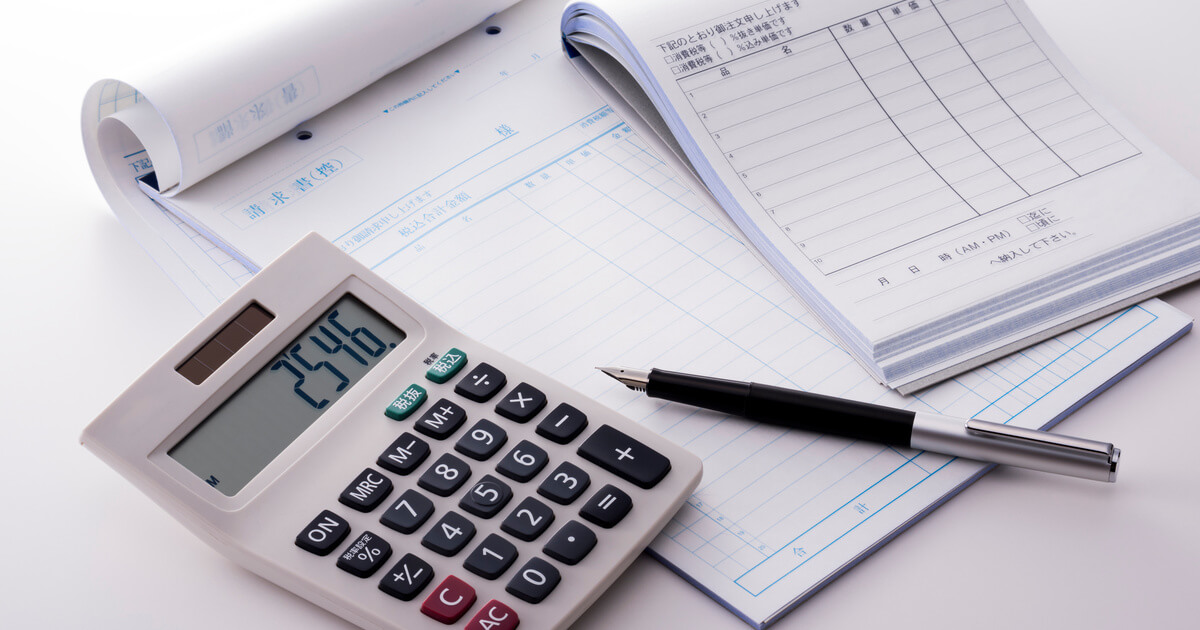フリーランスが加入する健康保険とは?国保の加入方法や注意点について詳しく解説

フリーランスが加入できる健康保険には、国民健康保険や国民健康保険組合、会社で加入していた保険の任意継続、扶養家族に入るという4つの選択肢があります。
国民健康保険が一般的ですが、加入するには会社を退職後、14日以内にお住まいの市区役所または町村役場に届出を提出しなければなりません。
さらに、加入には健康保険資格喪失証明書をはじめ、退職証明書もしくは雇用保険の離職票、マイナンバーカード(個人番号カード)や運転免許証などの本人確認書類が必要です。
この記事では、フリーランスが加入する健康保険、国民健康保険と会社員の健康保険の違い、国民健康保険に加入する流れ、加入時に必要なもの、注意点について詳しく解説します。
- 【この記事のまとめ】
- フリーランスが加入できる健康保険には、国民健康保険、任意継続、国民健康保険組合、扶養家族に入るなどの選択肢があります。
- 国民健康保険は都道府県や市町村が運営し、収入や世帯構成に基づき保険料が算出されます。手続きは退職後14日以内に必要書類を揃えて行います。
- 任意継続は退職後20日以内に手続きが必要で、保険料は全額自己負担です。扶養家族に入る場合、年収などの条件を満たせば保険料を支払わずに済みます。
2024年11月1日より、フリーランス保護法が施行されます。
組織に所属せずに働くフリーランスが安心して働ける環境を整備するために、フリーランスと企業などとの発注事業者間の取引の適正化(契約書等により取引条件を明示する)が主な目的です。
詳しくは次の記事をご覧ください。フリーランス保護法の概要、制定された背景や具体的な内容などを解説しています。
「起業の窓口」では、AIインフルエンサーの茶圓氏とコラボをおこない、AIを活用してビジネスの効率化を図るための貴重な知識を提供しています。
特集ページ「AI×起業」では、最新のAI技術やツールを使った実践的なアプローチを紹介しており、起業家や個人事業主の業務をよりスマートにサポートします。
AIの力で業務の負担を軽減し、ビジネスの成長を加速させたい方に最適な情報が満載です。ぜひご覧ください。
フリーランスが加入できる健康保険の種類

ここでは、フリーランスが加入できる健康保険の種類について解説します。
国民健康保険
フリーランスが加入する健康保険は、国民健康保険が一般的です。国民健康保険は都道府県や市町村が運営し、加入者全員が均等に負担を分担します。
保険料は収入をはじめ、世帯構成や住んでいる地域に基づいて算出され、病気やけがで医療機関を利用した際は自己負担が軽減される仕組みです。
任意継続
フリーランスは、会社で加入していた全国健康保険協会や健康保険組合の健康保険を任意で継続できます。退職後に検討すべき健康保険としては、有力候補のひとつとなるでしょう。
任意継続を行うには、資格喪失日から20日以内に手続きを済ませる必要があります。保険を継続できる期間は、最長2年間と有限です。
また、保険料の全額が自己負担になります。在職中は保険料の半分を会社が支払っていましたが、退職後はすべて自己負担になるため注意が必要です。
さらに、納付期限を過ぎると翌日には保険資格を失ってしまうため、期限内の支払いは厳守しましょう。
一見するとデメリットが多く見える任意継続ですが、手続き自体は非常にシンプルです。退職後の一時的な健康保険としては、良い選択肢のひとつといえるでしょう。
国民健康保険組合
フリーランスは国民健康保険組合への加入も可能です。加入できる業種は限られますが、加入可能な組合がいくつか存在します。
国民健康保険組合は業種や事業所の所在地によって加入できるものが異なり、条件や保険料の計算方法もさまざまです。
業種別の国民健康保険組合には特有のメリットがあります。
例えば、文芸美術国民健康保険組合には、国内に住む文芸、美術、著作などの芸術活動に従事する人々やその家族が加入できます。
▼文芸美術国民健康保険組合
| 加入者 | 保険料 |
|---|---|
| 組合員 | 月額25,700円(内訳:医療分19,900円 後期高齢者支援金分5,800円)/人 |
| 家族 | 月額15,400円(内訳:医療分9,600円 後期高齢者支援金分5,800円)/人 |
| 介護保険料 | 月額 5,700円/人 |
なお、法人の加入はできません。
また、美容業界に特化した東京美容国民健康保険組合は、東京都内で美容関連の業務を行う個人事業主、従業員、家族が加入できます。
▼東京美容国民健康保険組合
| 加入者 | 保険料 |
|---|---|
| 事業主組合員 | 月額20,000円(均等制)/人 |
| 従業員組合員 | 月額14,500円(均等制)/人 |
| 家族 | 月額9,500円(人頭割~組合員・世帯主負担)/人 ※未就学児は月額6,000円/人 |
| 介護保険料 | 組合員:月額 23,000円(均等制)/人 従業員:月額17,500円(均等制)/人 家族:月額12,500円(人頭割~組合員・世帯主負担)/人 |
東京美容国民健康保険組合は、美容業界で唯一の国民健康保険組合です。
それぞれの健康保険組合に関する詳しい情報は、公式ホームページから確認できます。適切な健康保険組合を見つけることで、国民健康保険よりも保険料を抑えられる場合があります。
扶養家族に入る
フリーランスは、家族が加入する健康保険の扶養家族に入れます。
健康保険の扶養家族として認められた場合、追加の保険料を支払わず健康保険の恩恵を受けることが可能です。
しかし、年収が130万円未満、扶養する家族の年収の半分未満である、共同生計を営んでいるなどの条件もあります。
扶養家族は健康保険料の節約だけでなく、万一の病気や怪我にも対応できます。加入条件を満たしているのであれば、検討すべき健康保険のひとつです。
国民健康保険と会社員の健康保険の違い

国民健康保険と会社員の健康保険の違いは以下の通りです。
| 国民健康保険 | 会社員の健康保険 | |
|---|---|---|
| 保険料の負担割合 | 加入者が全額負担 | 会社と折半 |
| 医療費の自己負担 | 3割(6歳未満および70~74歳は原則2割、75歳以上は原則1割) | |
| 傷病手当金・出産手当金 | なし | あり |
| 保険料の算出方法 | 前年度の所得に応じて算出 | 一定期間の給与等の平均額に応じて算出 |
| 扶養 | 扶養の概念がない | 条件を満たせば配偶者や子どもを被扶養者にできる(扶養人数が増えても保険料は一定) |
| 保険料の支払い方法 | 自分で支払う | 給与から天引き |
フリーランスが加入できる国民健康保険は、加入者が保険料の全額を自己負担しなければなりません。
また、国民健康保険には被扶養者の概念がないため、加入者全員に保険料が課されるのが特徴です。
一方、会社員の健康保険に関しては、会社と従業員が保険料を折半で支払います。配偶者や子ども等を被扶養者にできるほか、出産手当金や傷病手当金の制度があります。
フリーランスが加入する公的年金制度
日本の公的年金制度は、国民年金と厚生年金の2部階層です。フリーランスは国民年金にのみ加入し、会社員や公務員は国民年金に加えて厚生年金にも加入しています。
公的年金の保障は以下の通りです。
- 65歳から受け取れる老齢年金
- 被保険者の死亡時に遺族が受け取る遺族年金
- 障害を持つ場合に受け取れる障害年金
しかし、フリーランスは厚生年金の保障を受けられません。
会社員と比べると将来的に受け取れる年金額に差が出ますが、付加年金や国民年金基金といった制度を利用すれば年金額を増やせます。
付加年金として毎月400円の付加保険料を支払うことで、将来の年金額を200円×納付月数だけ増額できます。
国民年金基金については、月額で最高68,000円までの掛金を納めることで、より多くの年金の受け取りが可能です。
国民年金基金は、フリーランスのライフプランに合わせて年金額や受取期間を調整でき、支払った掛金は社会保険料控除の対象になります。
フリーランスが加入する公的介護保険
フリーランスは40歳を迎えると、公的介護保険へ加入しなければなりません。40歳から64歳までは第2号被保険者として分類され、65歳以上では第1号被保険者に切り替わります。
保険料は国民健康保険と一緒に徴収され、全額自己負担が必要です。
公的介護保険は、被保険者が将来的に介護が必要になった場合に支援を受けられます。その際は原則として、1割負担で介護サービスの利用が可能です。
国民健康保険に加入する際の流れ
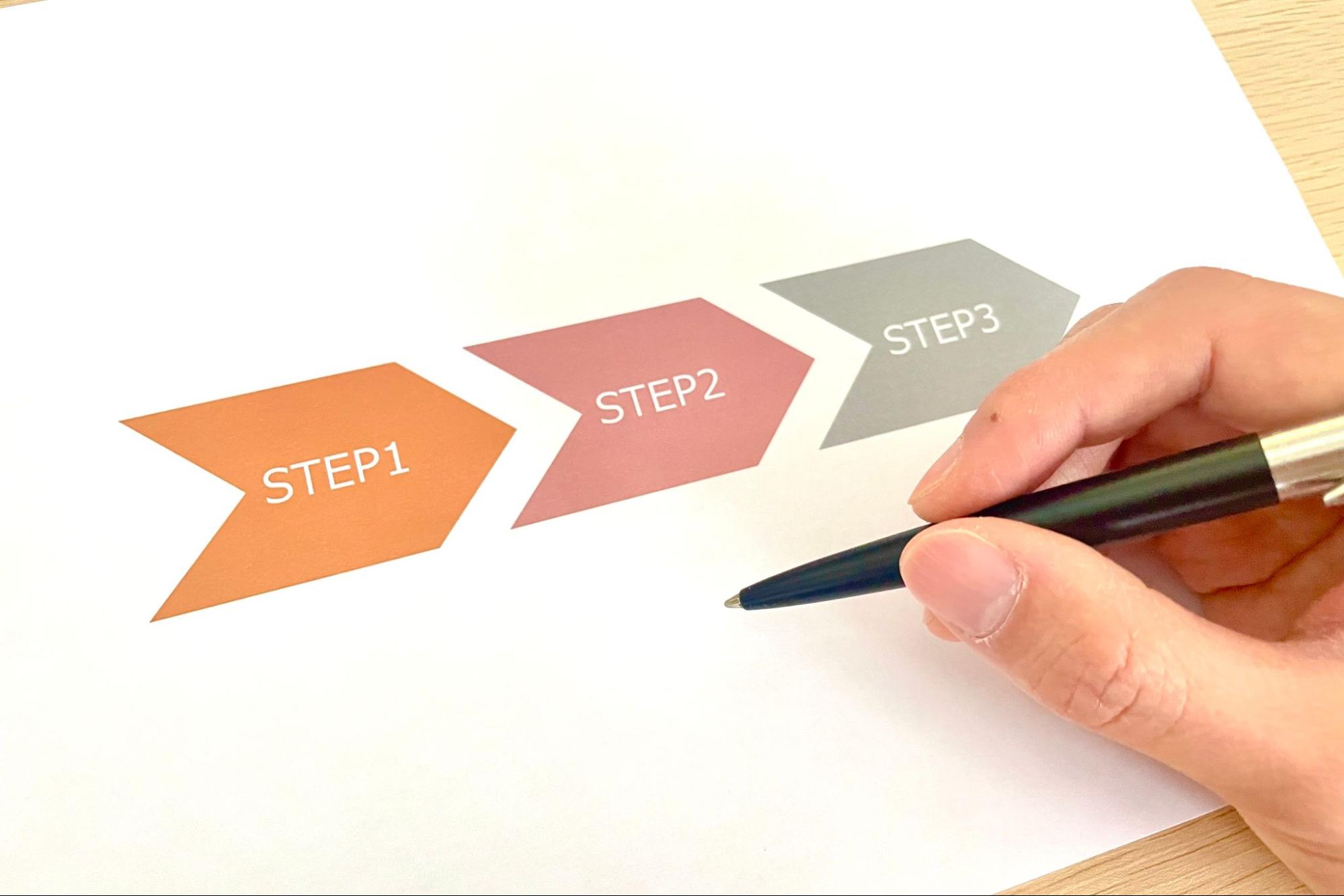
ここでは、国民健康保険に加入する際の流れについて解説します。
会社員を退職後、世帯主が14日以内に届出
会社員を退職した後は、世帯主が14日以内に社会保険から国民健康保険に切り替える手続きを済ませる必要があります。
国民健康保険の加入手続きには、健康保険資格喪失証明書の提出が必要です。証明書は、国民健康保険へ加入するすべての人々を含めなければなりません。
ただし、退職した本人だけが国民健康保険に加入する場合は、退職証明書や雇用保険の離職票など、退職日が明記された書類で申請が可能です。
異なる世帯から申請する場合は、世帯主の印鑑を持参しましょう。
提出先は住まいの役所にある保険年金課
国民健康保険への切り替えは、会社の健康保険を脱退した後に、地域の区役所や市役所の保険業務窓口で届出を行います。
手続きは脱退後14日以内に行う必要があり、世帯主が手続きしなければなりません。
事情により世帯主が手続きを行えない場合は代理人でも届出を行えますが、その場合は世帯主の委任状が必要です。
健康保険資格喪失証明書は、雇用先や健康保険組合からのみ取得できます。市役所や区役所では発行されないため、退職時に入手しておきましょう。
さらに、扶養家族がいる場合といない場合で必要な書類が異なります。スムーズな手続きを実現させるためにも、事前に準備を整えておくことが大切です。
国民健康保険の加入で必要なもの
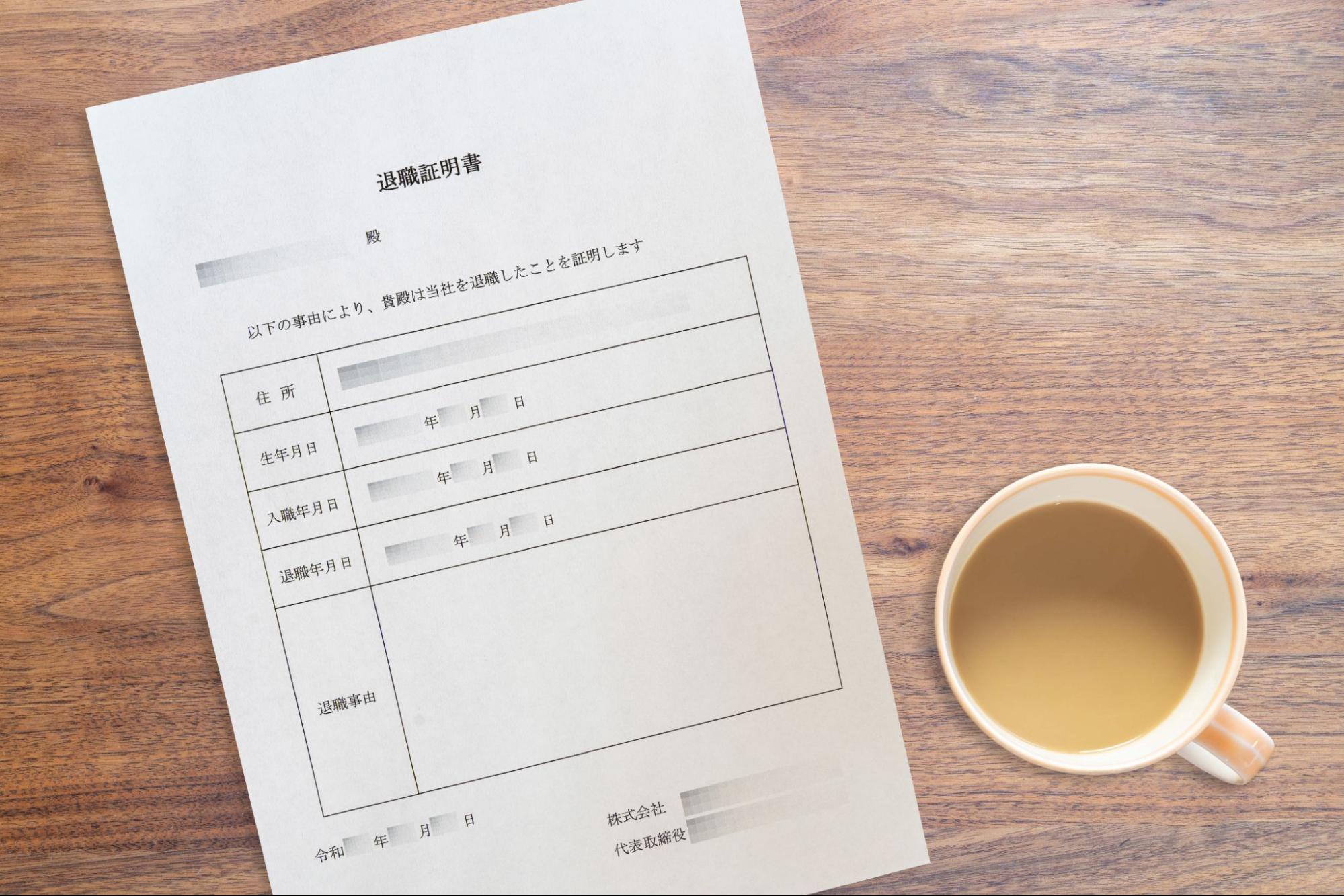
ここでは、国民健康保険の加入で必要なものについて解説します。
健康保険資格喪失証明書
フリーランスが国民健康保険へ切り替える際は、健康保険資格喪失証明書の提出が必要です。
健康保険資格喪失証明書は、会社の健康保険の被保険者が国民健康保険に加入するために、資格喪失と被扶養者でなくなった日付を証明する書類になります。
提出する際は、扶養家族を含め、国民健康保険に加入するすべての人の分が必要です。
退職証明書もしくは雇用保険の離職票
フリーランスが国民健康保険に加入する際は、誰が国民健康保険に加入するのか明確にする必要があります。
会社を退職した本人のみが加入する場合は、退職証明書もしくは雇用保険の離職票など、退職した日付が確認できる書類を用意すれば申請が可能です。
個人番号カードや運転免許証などの本人確認書類
フリーランスが国民健康保険に加入する手続きには、申請者本人の本人確認書類の提出が必要です。
- マイナンバーカード(個人番号カード)
- 運転免許証
- 運転経歴証明書
- パスポート
上記の写真付き証明書からひとつを選んで提出します。これらが手元にない場合は、以下から2つを選んで提出しましょう。
- 保険証
- 年金手帳
- 学生証
提出が必要な書類をすべて揃えたら、退職後から14日以内に提出してください。
フリーランスが国民健康保険に加入する注意点

ここでは、フリーランスが国民健康保険に加入する際の注意点について解説します。
退職日から期間が空くと遡って請求される
フリーランスは退職後すぐに国民健康保険へ加入することになります。退職日から期間が空いてしまうと、遡って加入する必要があります。
退職日を明確にするために、健康保険資格喪失証明書の用意が必要です。退職日を確実に証明できる状態を整えておきましょう。
また、健康保険資格喪失証明書があれば、退職翌日からの加入が認められます。
退職したらすみやかに手続きを進められるよう、準備を済ませておきましょう。
国民健康保険の追加加入手続きは自治体で確認を
国民健康保険へ加入する際に、世帯のなかですでに国民健康保険に加入している人がいる場合は、自治体に手続き方法を確認しましょう。
なお、期限は加入者の退職後14日以内です。14日以内に必要書類が揃わない場合は、市役所に連絡しておきましょう。
手続き中は医療費が10割負担になる
フリーランスが国民健康保険に加入する際、手続き中はまだ国民健康保険に加入していることが証明できない状況で、医療費が原則10割負担になります。(後日申請することで負担したうちの自己負担部分を超える金額は還付を受けることができます。)
公的な健康保険制度に加入している場合、支払いが必要な医療費は一部(通常は3割)のみですが、加入していない場合、窓口では医療費全額を自己負担しなければいけません。
場合によっては高額な医療費がかかる可能性があるため、国民健康保険の加入手続きはスムーズに済ませましょう。
国民健康保険料などは経費ではなく社会保険料控除扱い
国民健康保険料などは経費として計上できません。社会保険料控除の対象となるため、申告を間違えないように注意してください。
国民健康保険料を経費として扱ってしまうと、所得が正しい数値になりません。税額にも影響が出るため、経費として計上すると根本的な修正が必要になります。
フリーランスは事業関連の出費を経費として計上できますが、経費に該当する支出を判断するためには専門知識が必要です。
保険料を含む経費と混同しやすい支出は少なくないため、誤って扱わないよう注意しましょう。常に適切な会計処理を心がけることが大切です。
「起業の窓口」では、フリーランスの方々に向けて、業務効率化のヒントや成功事例、最新のビジネス情報など、お役立ち情報を提供しています。
ぜひ、「フリーランス」に関する他の記事もご覧ください。
起業や開業、独立に興味を持ったら、まずは「起業の窓口」に登録してみよう!
「起業の窓口」では、起業に必要なノウハウや成功者のインタビューなど、さまざまなコンテンツを完全無料で提供しています。
会員特典として、起業・経営支援のプロ「V-Spirits」が監修するオリジナル冊子『会社設立完全ガイド』を無料プレゼント。さらに、V-Spritsによる1時間の無料起業相談や、GMOインターネットグループが展開するビジネスの立ち上げや拡大に役立つ各種サービスをおトクな特典付きでご紹介します。
あなたの夢の実現を全力でサポートします!
- 記事監修
-
- 中野 裕哲 HIROAKI NAKANO
- 起業コンサルタント(R)、経営コンサルタント、税理士、特定社会保険労務士、行政書士、サーティファイドファイナンシャルプランナー・CFP(R)、1 級FP 技能士。 V-Spiritsグループ創業者。東京池袋を本拠に全国の起業家・経営者さんを応援!「あの起業本」の著者。著書16冊、累計20万部超。経済産業 省後援「DREAMGATE」で11年連続相談件数日本一。
- ※本記事は、起業の窓口編集部が専門家の監修または独自調査(アンケート)に基づいて制作したものです。
- ※掲載している情報は、記事公開時点の法令・税制・商品・サービス等に基づくものであり、将来的に変更される可能性があります。
- ※アンケート調査に関する記述は、特定の調査対象者からの回答結果および編集部の見解を含んでおり、内容の正確性・完全性を保証するものではありません。
- ※記事の内容は一般的な情報提供を目的としており、すべての方に当てはまるものではありません。個人の状況に応じた具体的な助言が必要な場合は、専門家にご相談ください。
- ※情報の利用や判断、実施については、ご自身の責任で行っていただきますようお願いいたします。
- ※本記事に掲載された内容の転載・複製はご遠慮いただき、引用の際は必ず出典をご明記ください。



 シェア
シェア