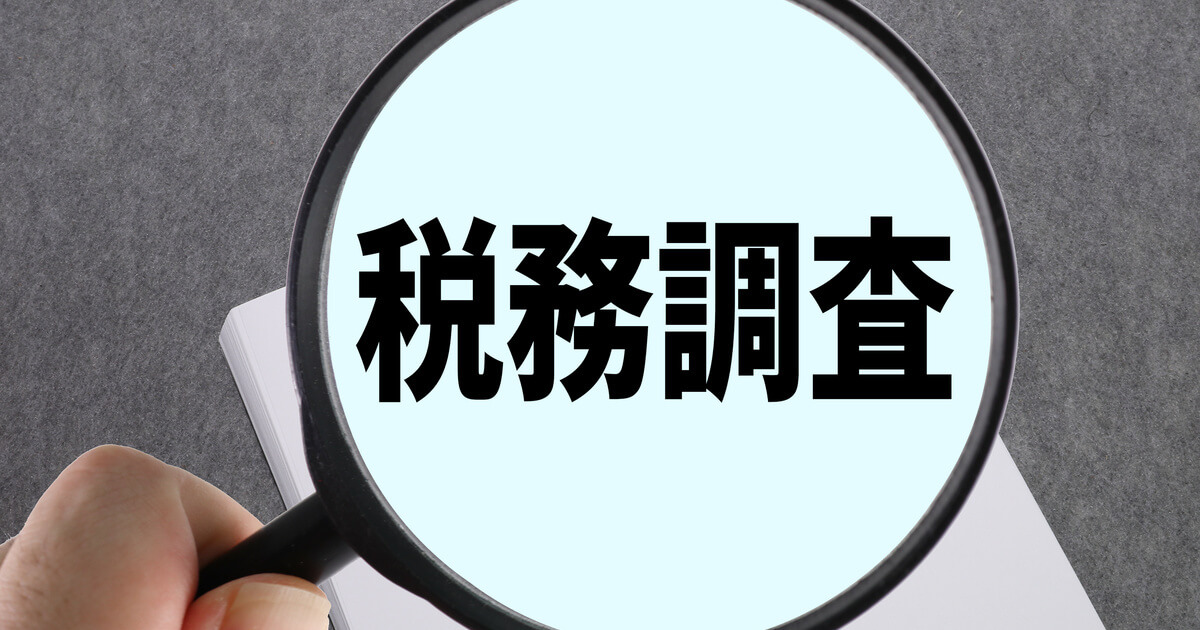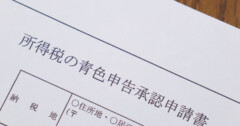【個人事業主向け】車の経費計上完全ガイド!可能となる条件や節税戦略について解説

個人事業主は業務で車を使用する場合に、かかった費用を経費として計上することができます。
ただし、事業とプライベートで車を兼用して使っている場合は按分して正しく経費を計上しなければなりません。車の購入にかかった費用に関しても、一部を除きすべてを一気に計上できるわけではなく、減価償却を行う必要があります。
車の経費計上で失敗したり、損をしたりしないためにも、経費について正しい知識を持っておきましょう。
この記事では、個人事業主向けに車の経費を計上する方法や条件、注意点を紹介します。
- 【この記事のまとめ】
- 個人事業主が車関連の支出を経費にできる条件や計上する方法を紹介しています。
- 車の経費を計上する際は記録をして証明できるようにしておく必要があります。
- 車を活用した節税方法としてリースの活用や自家用車の事業転用などがあります。
2025年分(令和7年分)の所得税等の確定申告期間は2026年2月16日(月)から3月16日(月)です。
「起業の窓口」では、確定申告の方法、青色申告や白色申告の基礎知識、手続きの流れ、節税のコツなどを詳しく解説しています。
ぜひ、「確定申告」に関する他の記事もご覧ください。
2024年11月1日より、フリーランス保護法が施行されます。
組織に所属せずに働くフリーランスが安心して働ける環境を整備するために、フリーランスと企業などとの発注事業者間の取引の適正化(契約書等により取引条件を明示する)が主な目的です。
詳しくは次の記事をご覧ください。フリーランス保護法の概要、制定された背景や具体的な内容などを解説しています。
「起業の窓口」では、AIインフルエンサーの茶圓氏とコラボをおこない、AIを活用してビジネスの効率化を図るための貴重な知識を提供しています。
特集ページ「AI×起業」では、最新のAI技術やツールを使った実践的なアプローチを紹介しており、起業家や個人事業主の業務をよりスマートにサポートします。
AIの力で業務の負担を軽減し、ビジネスの成長を加速させたい方に最適な情報が満載です。ぜひご覧ください。
個人事業主が車関連の支出を経費にできる条件

個人事業主が車関連の支出を経費にするためには条件があります。
ここでは、どのような場合に車関連の支出を経費にできるか解説します。
事業での使用目的
個人事業主が車関連の支出を経費にする条件は、車を事業目的に使用することです。
事業のために使用する車であれば、そこにかかった費用はすべて経費として計上できます。例えば、車を出張サービスや配達サービス、新規顧客開拓のための訪問などです。他にも、仕事の打ち合わせや取引先訪問、商品の運搬、顧客訪問などに使う場合も経費になります。
「車種やメーカーで経費にできる・できない」という区分はなく、常識の範囲内であれば、高級車でも通常の車と同じように経費にできます。一方、プライベートで使用するために車を購入している場合、経費としての計上はできないため、注意が必要です。
車の名義と所有形態
個人事業主が事業に車を使い、そこでかかった費用を経費にするのであれば、本人名義にするのが望ましいでしょう。
ただし、車の名義が本人ではなくても、同一生計にある親族が所有する車であれば、経費として認められます。同一生計にない場合は家族や親族であっても、経費として認められないため、注意しましょう。
また、車の所有形態は車を事業に使っていることが証明できれば、個人名義でもリースローンでもかまいません。ローンを利用して車を購入し、名義人がローン会社になっている場合も経費として計上できます。
プライベート使用との区分
個人事業主が経費として計上できるのは、事業用に車を使った場合にかかる費用のみであり、プライベートに使用してかかった費用は対象外です。
そのため、事業用とプライベートで併用して車を使用する場合は、「家事按分」をしなければなりません。家事按分とは、事業用とプライベートで使っている割合を計算し、事業で使っている費用のみを経費として計上することです。
家事按分に明確な計算方法はありませんが、事業に使用した日数や走行距離などから家事按分するのが一般的となっています。
例えば、車にかかった費用が10万円だったとします。
事業に使った走行距離が700km、プライベートで使った走行距離が300kmだった場合の割合は7:3です。このケースだと7万円を経費として計上できます。
車の購入費を経費計上する方法

車の購入にかかった費用を経費計上する場合、減価償却を行うのが一般的です。
ここでは、減価償却の基本や一括償却できるケース、中古車を購入した場合の計上方法を詳しく解説します。
減価償却の基本
個人事業主が事業のために車を購入した場合、購入にかかる費用を減価償却して経費にできます。
減価償却とは、固定資産の取得にかかった費用について、全額をその年の経費とせず、耐用年数に応じて配分を行うための方法です。車の耐用年数は車の種類や状態によって異なり、新車を購入する場合は乗用車の場合は6年となります。
なお、減価償却には以下2つの方法があります。
- 定額法:耐用年数の期間中毎年同じ金額を減価償却する
- 定率法:未償却残高に対して一定の割合をかけて減価償却する
定額法は簡単な計算で安定した経費計上を行う場合、定率法は初年度に多くの経費を計上し、短期的に節税効果を狙いたい場合におすすめです。
個人事業主は一般的に定額法は誰でも利用できしますが、定率法は税務署に届けることによって選択できます。
個人事業主が減価償却するやり方や計算方法は、以下の記事でも詳しく解説していますので、あわせてご参照ください。
中古車の購入
中古車を購入する場合、減価償却の計算方法は新車と異なる点に注意が必要です。中古車の耐用年数は以下の計算式で求めることができます。
中古車の耐用年数:(法定耐用年数-経過年数)+(経過年数×0.2%)
仮に4年落ちの中古車を購入する場合、計算式に当てはめると以下になります。
(法定耐用年数6年-経過年数4年)+(経過年数4年×0.2%)=2. 8年
です。小数点は切り捨てとなるため、最終的な耐用年数は2年となります。新車に比べると中古車の方が耐用年数が短いため、節税効果が高いといえるでしょう。
一括償却と少額減価償却資産の特例
車の耐用年数が2年の減価償却資産について、定率法を用いる場合は1年で一括償却していいというルールがあります。そのため、耐用年数が2年になる4年落ちの中古車では購入年度に一括で経費計上が可能です。
また、青色申告を受けている個人事業主は、少額減価償却資産の特例によって、30万円未満で取得した中古車については一括償却ができます。
少額減価償却資産の特例では、年間300万円までが限度額となっているため、複数の資産に対して適用させる場合は上限に注意が必要です。
車関連の経費として計上できる項目

車関連の経費として計上できる項目には、維持費や税金、保険料などがあります。
ここでは、それぞれの項目について解説します。
維持費(ガソリン代、駐車場代、車検代など)
車の維持にかかる費用は「車両費」として経費計上できます。
車両費は、以下のような費用が該当します。
- ガソリン代
- ETC代
- 駐車場代
- 車検代
- 修理費
- 洗車代
- タイヤやバッテリ-などのパーツ代
ガソリン代やETC代などは旅費交通費として計上することも可能です。
車をプライベート用と事業用に使っている場合は、それぞれの支払いについて家事按分が必要となります。
なお、車の購入にかかる費用については車両費ではなく、「車両運搬具」として計上します。車両運搬具にはカーナビや納車にかかった費用なども含まれます。
税金(自動車税、自動車重量税など)
車にかかる税金は「租税公課」として計上できます。
車にかかる税金として自動車税があります。自動車税とは、毎年4月1日時点で車検証上の所有者にかかる税金のことです。ローンを組んで車を購入した場合は、車検証に記載される使用者が税金を納める必要があります。
自動車税は排気量によって変わりますが、軽自動車は一律です。個人事業主も日常的に業務に車を使っている場合は、自動車税をそのまま経費にできます。ただし、自動車税の納付が遅れたことで発生する加算金や延滞金は計上できません。
また、車の新規登録や車検を実施する際にかかる自動車重量税も経費として計上できます。
保険料(自動車保険、自賠責保険)
車にかかる自動車保険や自賠責保険などの保険料も、「損害保険料」として計上できます。
自賠責保険は車の所有者に対して加入を義務付けている保険です。自賠責保険は車の購入時と車検時に支払います。車検時は車検料に自賠責保険料が含まれていることも多いため、自賠責保険の保険料は別途計算して損害保険料として計上するのがよいでしょう。
一方、自動車保険とはドライバーが任意で加入する保険のことを指します。任意保険の保険料も経費として計上できますが、2年以上にわたる保険料を一括で払った場合は、期間ごとに按分しなければなりません。
例えば、契約期間3年間で18万円の任意保険料を支払った場合、計上できるのは1年目6万円、2年目6万円、3年目6万円となります。
車の経費計上における注意点
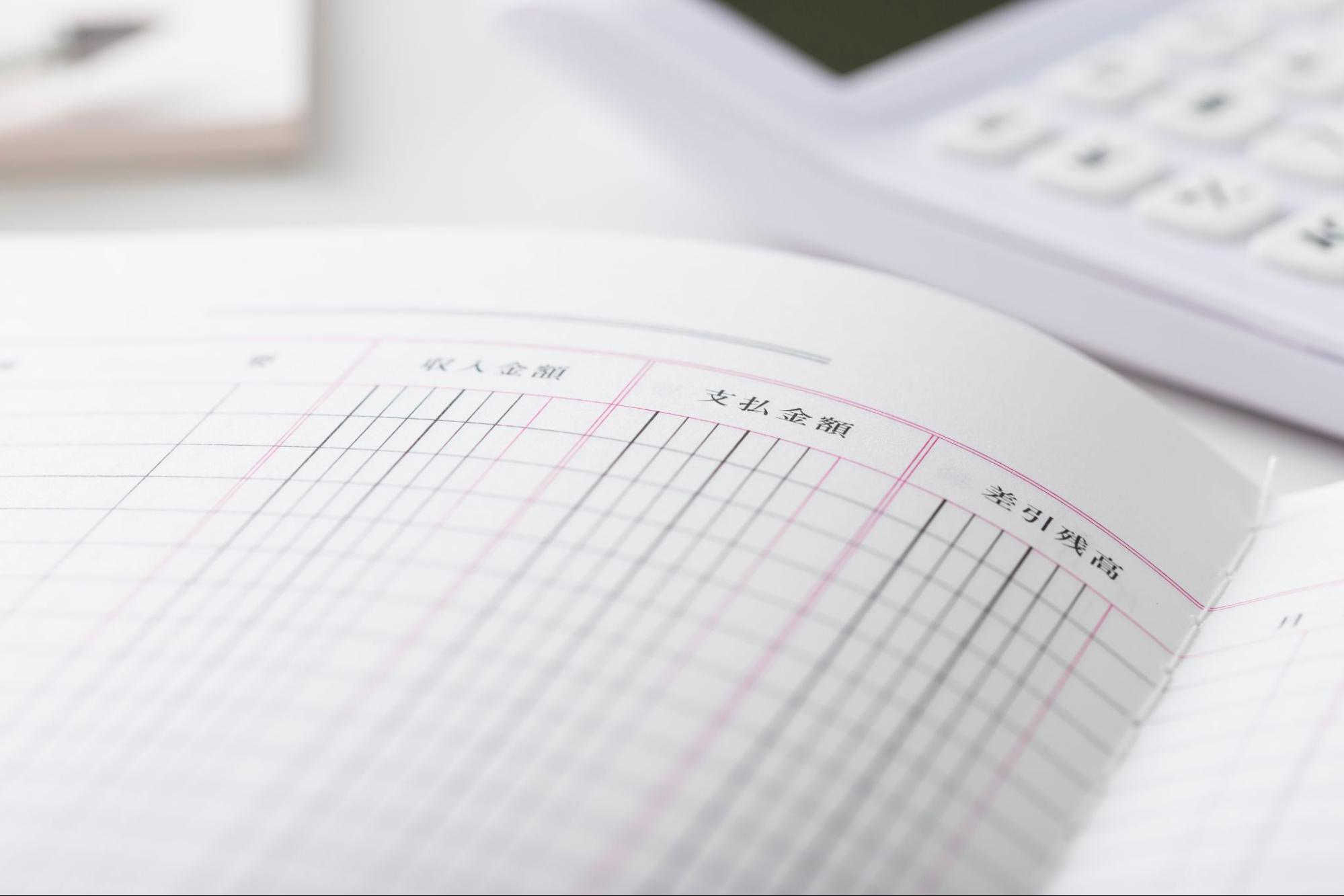
個人事業主が車の支出を経費にする場合、どのようなことに注意したらよいのでしょうか。
ここでは、車の経費計上における注意点を解説します。
経費の証明と記録の重要性
車の支出を経費にするためには、支払いを証明する記録や証拠が必要です。
一般的には領収書やレシートが証拠書類として認められるため、経費に関連する支出がある場合は受け取って保管しましょう。領収書やレシートがない場合、契約書や請求書、納品書、預金通帳なども経費の証明になります。
なお、確定申告の際に領収書やレシートの提出は不要です。これらの書類は税務調査が入った際に、証拠として提示するために保存して置いておく必要があります。書類を保管しておく必要がある期間は、青色申告だと7年間、白色申告だと5年間です。
青色申告と白色申告の違い
青色申告は複式簿記を条件に最大65万円の控除が受けられる一方、白色申告は単式簿記で簡易な手続きができる代わりに税制上の優遇措置がないという違いがあります。
また、白色申告は少額減価償却資産が10万円未満であるのに対し、青色申告は30万円未満であることも違いです。さらに青色申告は赤字が3年間繰り越せることや、家族への給料を経費にできるメリットもあります。
赤字が繰り越せるため、車の経費が多くかかって赤字になった場合、翌年に引き続き節税できます。
例えば、1年目に50万円の赤字が発生して2年目に100万円の黒字になった場合に、2年目と1年目の所得を合算できるため、2年目の課税所得が50万円になるというものです。所得税や住民税は課税所得が増えるほど納める金額も多くなるため、課税所得が減ることによって節税できます。
青色申告と白色申告の違いや切り替えのタイミングは以下の記事でも詳しく解説していますので、あわせてご参照ください。
なお、青色申告で確定申告を行うためには、青色申告の手続きを行う必要があります。
確定申告を楽にしたいと悩む方へ

質問に答えていくだけで、経理の作業がはじめての方でも簡単に確定申告の書類作成をすることができます!
確定申告を楽にサクッとおこないたい方は、freeeがおすすめです!
車を活用した節税戦略

車を活用した節税方法として、リース活用や自家用車の事業転用があります。
ここでは、それぞれの特徴やメリット、デメリットを解説します。
リース活用のメリットとデメリット
個人事業主は車を購入するよりも、リースを活用した方が節税になるケースがあります。
なぜなら、車の購入にかかった費用は減価償却が必要ですが、リースの場合は月々かかるリース料を一括で経費計上できるためです。税金や自賠責保険だけでなく、任意保険に加入する諸費用やメンテナンスなどもリース料に含まれるものもあるため、経費の計算を簡単にできるメリットもあります。
一方、リース契約をすると期間中に中途解約ができない点に注意しましょう。解約すると高額の違約金が発生したり、残りの期間のリースを一括で支払ったりしなければならないケースもあります。
このようなリスクを下げるためにも、契約期間や途中解約のルールを事前に確認しておきましょう。
特に事業を始めたばかりの場合はリース料の支払いが滞る可能性もあるため、契約期間の選べる範囲が広いカーリース会社をおすすめします。
自家用車の事業転用による節税効果
車で節税したい場合に、自家用車がある場合は社用車として事業転用することも方法の一つです。
新たに車の購入資金を準備する必要はなく、個人事業主であれば必要な手続きも少なくて済みます。自家用を業務用として使うことで、事業に関連する支払いなら経費として計上できるため、課税所得も減ります。課税所得が減ると、所得税や住民税などの納付額も減り、節税につながるでしょう。
特に「車の購入資金がない」「事業用で車を使う機会が多くない」という場合はおすすめです。
その際、車の帳簿価額は購入時のものではなく、取得金額から自家用として使っていた分の減価償却費相当分を差し引いた金額にする必要があります。
車の経費を適切に計上して節税を
この記事では、個人事業主向けに車にかかる費用を経費にするコツや注意点、ポイントをお伝えしました。
事業用として車を使う場合、かかった費用はすべて経費として計上できます。「何の支払いが経費になるのか」を理解し、領収書やレシートを保管して記録しましょう。
プライベートと併用する場合は、按分にも注意し、税務署から指摘があった場合に説明できるようにしておく必要もあります。
ぜひ本記事を参考に、車の経費を適切に計上して節税を目指しましょう。
「起業の窓口」では、個人事業主の方々に向けて、業務効率化のヒントや成功事例、最新のビジネス情報など、お役立ち情報を提供しています。
ぜひ、「個人事業主」に関する他の記事もご覧ください。
起業や開業、独立に興味を持ったら、まずは「起業の窓口」に登録してみよう!
「起業の窓口」では、起業に必要なノウハウや成功者のインタビューなど、さまざまなコンテンツを完全無料で提供しています。
会員特典として、起業・経営支援のプロ「V-Spirits」が監修するオリジナル冊子『会社設立完全ガイド』を無料プレゼント。さらに、V-Spritsによる1時間の無料起業相談や、GMOインターネットグループが展開するビジネスの立ち上げや拡大に役立つ各種サービスをおトクな特典付きでご紹介します。
あなたの夢の実現を全力でサポートします!
- 記事監修
-
- 中野 裕哲 HIROAKI NAKANO
- 起業コンサルタント(R)、経営コンサルタント、税理士、特定社会保険労務士、行政書士、サーティファイドファイナンシャルプランナー・CFP(R)、1 級FP 技能士。 V-Spiritsグループ創業者。東京池袋を本拠に全国の起業家・経営者さんを応援!「あの起業本」の著者。著書16冊、累計20万部超。経済産業 省後援「DREAMGATE」で11年連続相談件数日本一。
- ※本記事は、起業の窓口編集部が専門家の監修または独自調査(アンケート)に基づいて制作したものです。
- ※掲載している情報は、記事公開時点の法令・税制・商品・サービス等に基づくものであり、将来的に変更される可能性があります。
- ※アンケート調査に関する記述は、特定の調査対象者からの回答結果および編集部の見解を含んでおり、内容の正確性・完全性を保証するものではありません。
- ※記事の内容は一般的な情報提供を目的としており、すべての方に当てはまるものではありません。個人の状況に応じた具体的な助言が必要な場合は、専門家にご相談ください。
- ※情報の利用や判断、実施については、ご自身の責任で行っていただきますようお願いいたします。
- ※本記事に掲載された内容の転載・複製はご遠慮いただき、引用の際は必ず出典をご明記ください。



 シェア
シェア