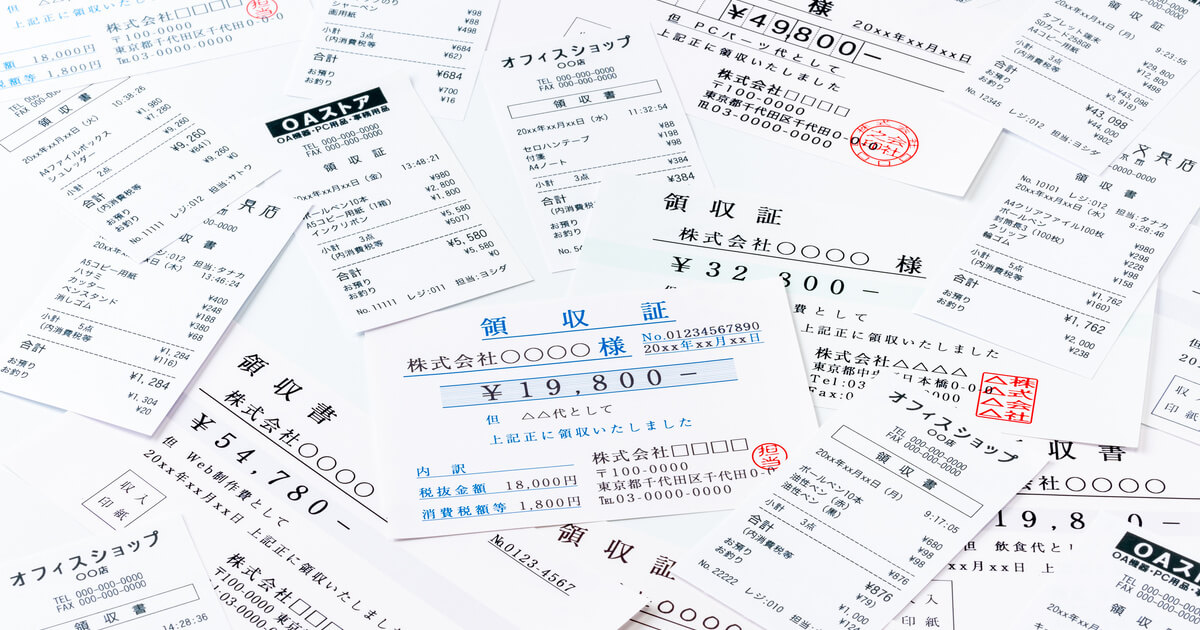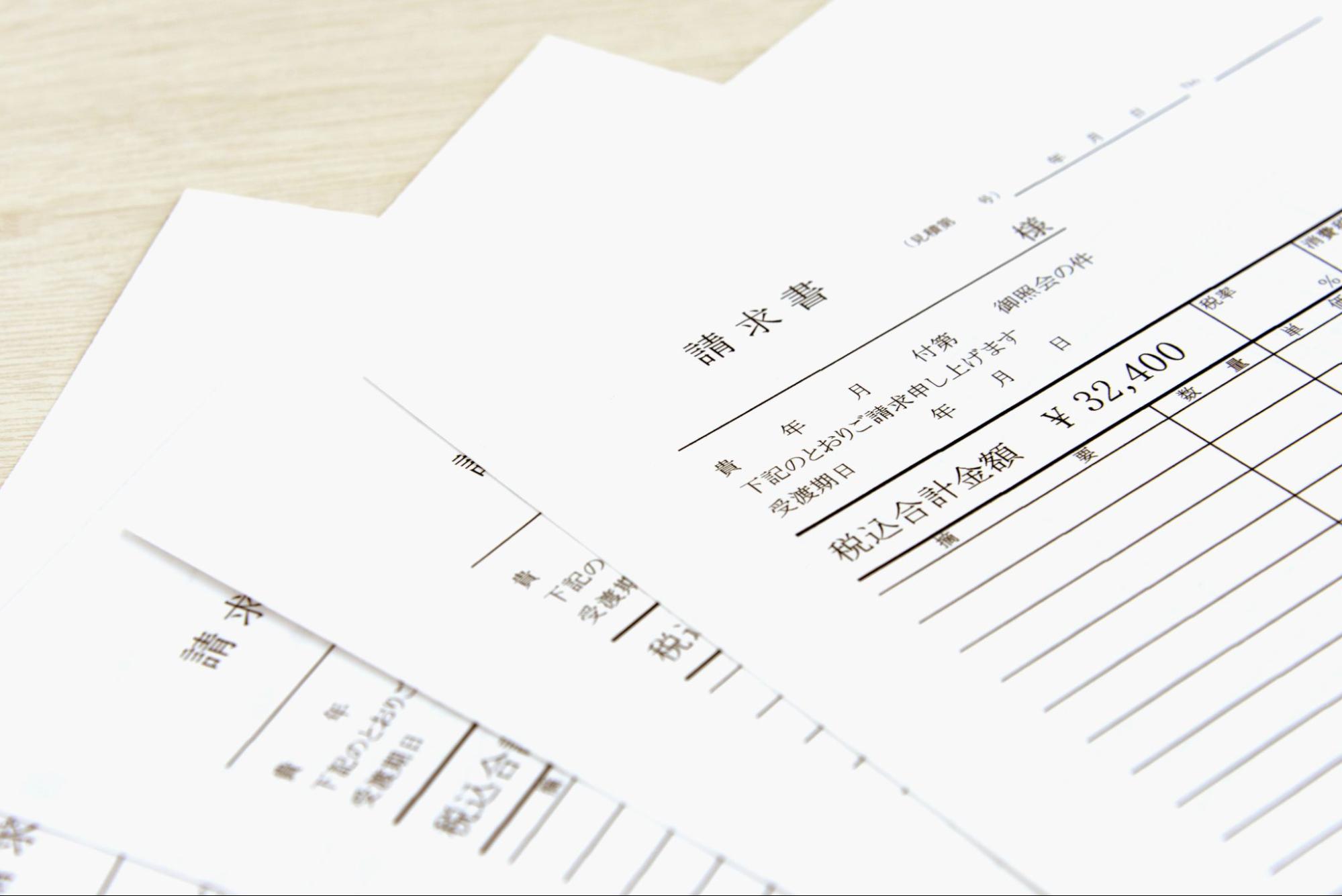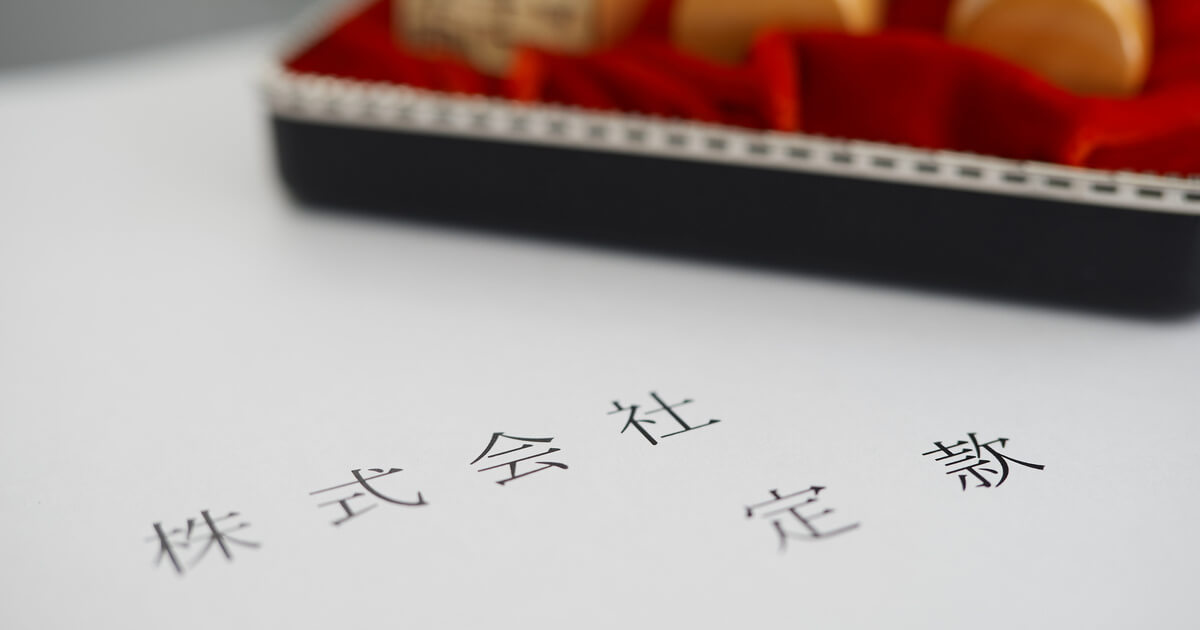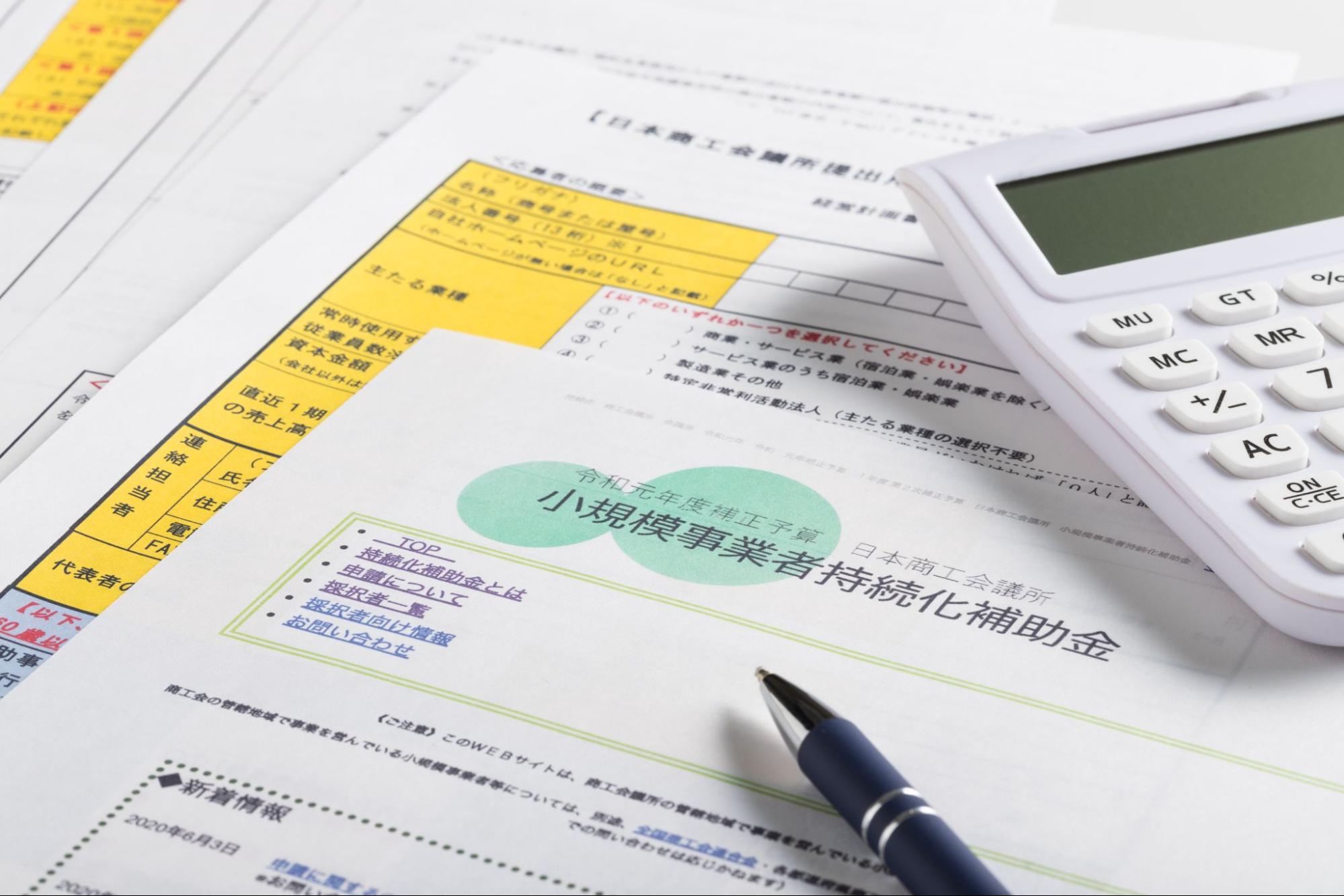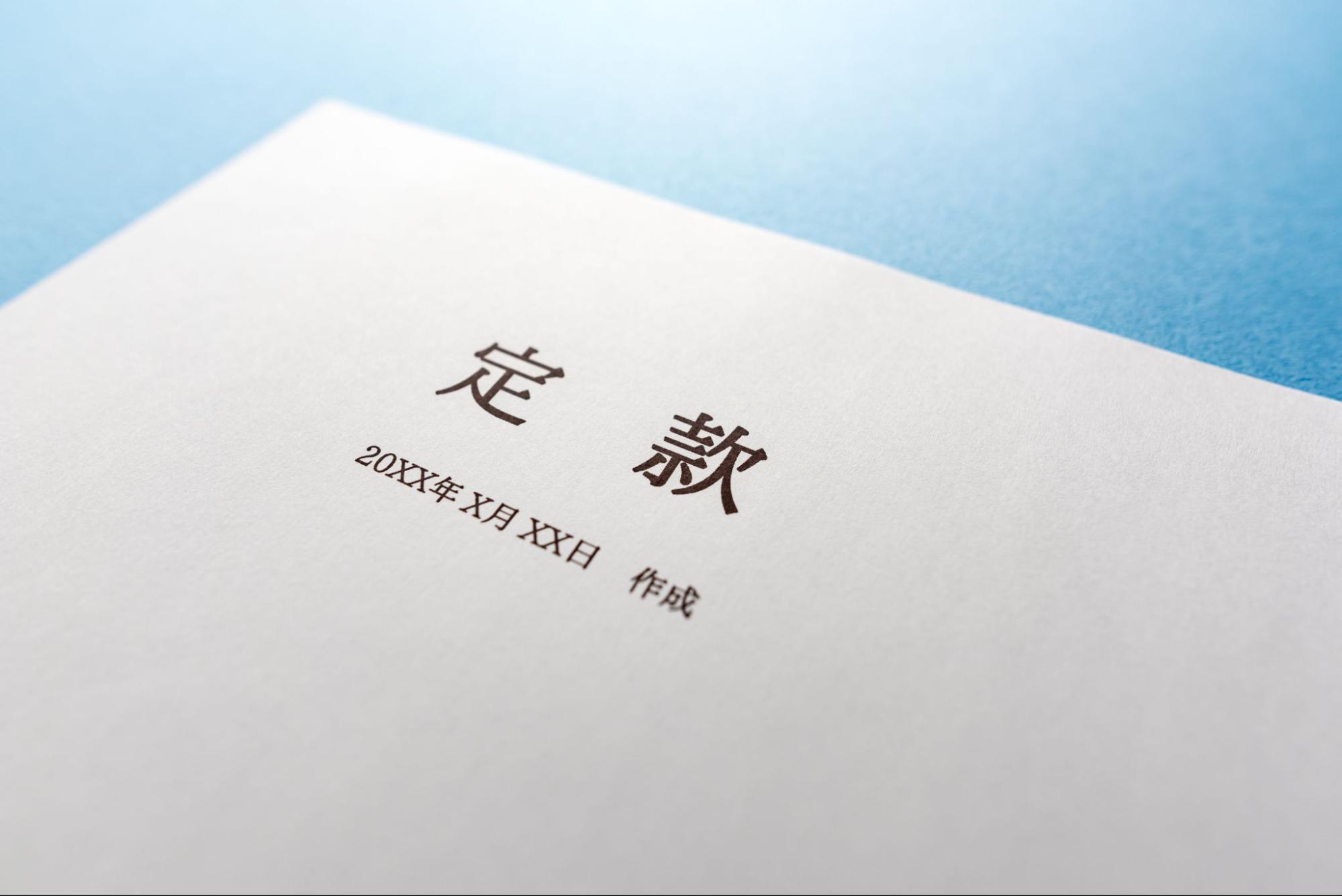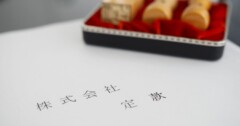合同会社設立時に印鑑は必要?融資や取引のための法人印鑑の種類と注意点

合同会社を設立する際、印鑑は必要なのかと疑問に思う方は多いのではないでしょうか。
2021年の商業登記規則の改正以降、合同会社の設立登記では印鑑の提出が任意となり、電子定款やオンライン申請の普及によって印鑑不要のケースも増えています。
しかし、銀行口座の開設や融資、各種契約書への押印など、会社運営には法人印鑑が必要とされる場面が多く存在します。
特に「会社実印」「銀行印」「角印」といった法人印鑑の種類や使い分けを理解しておくことは、スムーズな事業スタートに欠かせません。
印鑑に関する正しい知識を身につけ、デジタル化の波にも対応できる準備を整えておきましょう。
- 【この記事のまとめ】
- 合同会社設立時に印鑑は必須ではありません。2021年以降、オンラインでの登記申請では印鑑の提出が任意となりました。ただし、書面申請では印鑑が必要です。
- 業務や取引での印鑑の利用が推奨されます。契約や金融機関との取引で印鑑が求められるため、設立時に使用しなくても印鑑を事前に準備しておくと便利です。
- 法人印鑑の種類と用途を把握することが重要です。必要な法人印鑑は、会社実印、銀行印、角印の3種類があり、それぞれ異なる用途で使用されます。
GMOオフィスサポートでは、会社設立時に必要な代表印や銀行印などの印鑑セットを販売しております。最短で2営業日以内に発送しますので、急いで作りたい方にもおすすめです。
「起業の窓口」では、AIインフルエンサーの茶圓氏とコラボをおこない、AIを活用してビジネスの効率化を図るための貴重な知識を提供しています。
特集ページ「AI×起業」では、最新のAI技術やツールを使った実践的なアプローチを紹介しており、起業家や個人事業主の業務をよりスマートにサポートします。
AIの力で業務の負担を軽減し、ビジネスの成長を加速させたい方に最適な情報が満載です。ぜひご覧ください。
「起業の窓口」の特集ページ「起業家インタビュー」では、実際に成功を収めた起業家たちの貴重なインタビューが充実しています。リアルな体験や苦労、成功までの道のりを通じて、これから起業を目指す方々に向けた実践的なアドバイスを提供しています。
さまざまな分野で活躍する起業家の声を通して、ビジネスのヒントやインスピレーションを得られるコンテンツが満載です。ぜひインタビューを参考にして、自分のビジネスに活かしてみてください。
印鑑は合同会社設立時に必要?

はじめに、合同会社設立時に印鑑は必要なのかについて解説します。
2021年から登記所への印鑑提出は任意
2021年に行われた商業登記規則改正により、法人設立をオンラインで申請する場合は登記所への印鑑提出が任意となりました。
原則、印鑑の提出が任意となったため、登記所へ提出しても提出しなくても大丈夫です。当然ながら、未提出時のペナルティもありません。
そのため、2021年以降に合同会社を設立する場合は、登記所への印鑑提出は基本的に必要ないと認識しておいて良いでしょう。
オンラインで登記申請する場合は不要
オンラインで合同会社の登記申請を行う場合、印鑑は不要です。
一般的にオンラインで申請する場合は、定款をPDF形式に変換して電子定款として添付するだけで登記できるため、定款を含めてすべての添付書類に電子署名できれば印鑑は不要となります。
電子定款で登記する場合は収入印紙も不要となるため、印鑑代だけでなく収入印紙代も節約できるのがメリットです。
書面で登記申請する場合は必要
書面で合同会社の登記申請を行う場合は印鑑が必要です。
一般的に書面で申請する場合は、申請用紙の必要箇所に印鑑を押印してから提出するため、書面申請に限り印鑑が必要となります。
申請用紙で登記する場合は郵送の他、本社所在地を管轄する法務局へ直接出向かなくてはいけない場合もあるため、やや負担がかかるのがデメリットです。
取引で求められる場合もある
合同会社設立時の印鑑提出は不要ですが、会社同士の契約や企業間での取引においては印鑑が必要となる場面もあります。
他にも、以下の取引で印鑑が求められることがあります。
- 会社同士の契約時
- 企業間での取引時
- 金融機関への融資申込・契約時
契約時や取引時だけでなく、金融機関から融資を受ける場合には印鑑が求められるケースは少なくありません。
そのため、合同会社設立時には使用しなかったとしても、その他の場面に備えて印鑑は作成しておくことを推奨します。
合同会社設立時に必要な法人印鑑の種類

印鑑は合同会社設立時には不要ですが、その他の場面で必要となるため事前に作成しておくことを推奨します。ここでは、合同会社設立時に必要な法人印鑑の種類について解説します。
会社実印
会社実印とは、法人が所在する地域を管轄する法務局に登録する印鑑のことで、法務局に印鑑を持参して窓口で印鑑登録申請を行うと登録できます。
会社実印は丸い形状で外側に会社名、内側に役職名(代表者印)を彫るのが一般的で、契約書類作成や法人登記申請などで使用します。
代表者印
代表者印とは、経営者が企業の代表者として体外的に使用する印鑑のことで、会社実印と同じ立ち位置にある印鑑となります。
会社実印と同義となるため丸い形状で外側に会社名、内側に役職名(代表者印)を彫るのが一般的で、用途は会社実印とほぼ同様です。
銀行印
銀行印とは、取引のある金融機関に届け出る印鑑のことで、会社の銀行口座の出金や小切手・手形の振り出しなどに使用する印鑑となります。
形状は丸く、外側に会社名、内側に「銀行之印」と彫られたものを使用するのが一般的で、会社実印をそのまま銀行印として提出することも可能です。
角印
角印とは、会社名を彫刻した四角い形状の印鑑のことで、取引で発生した領収書や請求書の発行などに使用する印鑑です。
形状は四角く、会社印や社印と呼ばれるのが一般的で、企業が日常的に使用する印鑑となります。
しかし、会社実印のように法務局に届け出る必要がない印鑑であるため、公的な書類には使用しないのが一般的です。
法人印鑑の具体的な使用シーン

会社設立後、法人印鑑は事業運営のさまざまな場面で不可欠です。銀行口座の開設や契約書の締結、融資申請、行政手続きなど、会社の公式な意思を示す重要な役割を担います。
ここでは具体的な使用シーンを4つに分け、各場面での印鑑の役割を解説します。
銀行口座開設時
合同会社の法人口座を開設する際、金融機関への届出印として法人印鑑が必要です。金融機関は、口座名義人である法人の意思確認と不正利用を防止するため、届出印の登録を求めます。
具体的には、口座開設申込書への押印や、その後の取引で使う手形・小切手の振り出しなどに銀行印を使用します。一般的に、会社の代表者印とは別に銀行印を作成することが推奨されます。
これは、最も重要な実印の紛失や盗難、摩耗のリスクを分散させるためです。会社の資産を管理する重要な手続きであるため、信頼性の高い銀行印をあらかじめ準備しておきましょう。
契約書や請求書への押印
合同会社の事業運営において、取引先との契約書や請求書など、日常的な書類への押印は頻繁に発生します。
契約書や請求書への押印は、会社としての正式な意思表示であることを証明し、契約の信用性を高めるために重要です。
例えば、業務委託契約書や不動産賃貸借契約書といった重要書類には、法務局に登録した会社実印(代表者印)を使用します。
一方で、請求書や見積書、領収書など日常的に発行する書類には、認印としての役割を持つ角印を使うのが一般的です。
用途に応じて印鑑を使い分けることで、業務の効率化と印鑑の適切な管理ができます。
融資申請時
金融機関から融資を受ける際、法人印鑑の押印が求められる場合が多いです。
これは、会社として正式な申し込みであることを証明するものであり、申請に不可欠な要件となっているためです。
例えば、金銭消費貸借契約書には、法務局に登録された会社実印の押印が必要な場合が多いです。
資金調達は会社の成長に直結する重要な活動のため、手続きをスムーズに進めるには会社実印の準備が欠かせません。
印鑑関連の準備と手続き

合同会社の設立には、法人印鑑に関する準備と手続きが欠かせません。
ここでは、印鑑作成の手順や費用相場、電子定款での取り扱い、登記や印鑑証明書の取得タイミングなど、一連の準備と手続きについて具体的に解説します。
印鑑作成の手順と費用相場
合同会社設立では、会社名が確定したら法人印鑑を作成します。設立後の手続きを円滑に進めるため、事前に準備しておくことが重要です。
- 代表者印・銀行印・角印など、必要な印鑑の種類を決める
- チタンや黒水牛といった印鑑の素材やサイズを選ぶ
- オンラインショップや実店舗の専門業者に注文する
費用相場は素材や品質により異なりますが、代表者印・銀行印・角印の3本セットで1万円前後が一般的です。
注文から受け取りまでは1週間程度かかる場合もあるため、登記申請などのスケジュールを考慮し、余裕を持って手配しましょう。
電子定款作成時の印鑑の取り扱い
電子定款で合同会社を設立する場合、定款自体への押印は不要です。
これは、紙の定款と異なり、電子署名によって本人の証明を行うためで、4万円の収入印紙代が不要になるという利点があります。
しかし、法人印鑑そのものが不要になるわけではありません。
会社設立後の法人口座の開設や取引先との契約締結など、事業運営のさまざまな場面で法人印鑑の押印が求められます。
電子定款を利用する場合でも、設立手続きと並行して法人印鑑を準備しておくことが不可欠です。
登記申請と印鑑証明書の取得タイミング
合同会社の設立登記を申請する際、同時に代表者印(会社実印)を法務局へ登録します。この印鑑登録が完了すると、印鑑証明書の発行に必要な「印鑑カード」が交付されます。
印鑑証明書は、金融機関での融資手続きや不動産契約など、会社の信用を証明する重要な場面で提出を求められる書類です。
多くの場合、発行から3ヶ月以内のものを求められるため、登記完了後、実際に必要となる手続きの直前に取得するのが最適なタイミングです。
手続きの遅延を防ぐためにも、登記申請から印鑑証明書の取得までの一連の流れを事前に把握しておきましょう。
印鑑と電子化の関係

政府主導のデジタル化により、日本の印鑑文化は転換期を迎えています。電子契約が普及する今、従来の印鑑と電子署名の違いを理解することが重要です。
ここでは、両者の法的な違いや、法改正がもたらす印鑑文化の今後の展望について解説します。
電子署名・デジタル契約との違い
電子署名と電子印鑑は、デジタル文書で利用される点で似ていますが、その仕組みや法的効力は大きく異なります。
電子署名は、電子署名法に基づき「誰が作成したか」「改ざんされていないか」を証明する仕組みそのものを指します。
一方、電子印鑑は印影を画像データ化したものであり、それ単体では法的な証明力が限定的です。両者の主な違いは以下の通りです。
| 項目 | 電子署名 | 電子印鑑(印影データ) |
|---|---|---|
| 法的根拠 | 電子署名法 | 法的な定義はない |
| 作成者の証明 | 電子証明書により厳格に担保 | 複製の容易さから証明は困難 |
| 非改ざん性の証明 | 改ざんを検知する技術的仕組みあり | 基本的に機能はない |
重要な契約など、法的な信頼性が求められる場面では、電子署名法に準拠した電子署名が不可欠です。
印鑑文化の今後と法改正の影響
政府主導のデジタル化推進や法改正により、日本の印鑑文化は大きな転換期を迎えています。行政手続きにおける押印義務の見直しが進み、多くの書類で脱ハンコが実現しました。
脱ハンコの実現により、業務効率化やペーパーレス化が促進され、民間企業においても電子契約サービスの導入が加速しています。
しかし、法人印鑑が完全に不要になるわけではありません。例えば、法人の設立登記や金融機関との一部の取引、不動産契約など、依然として実印と印鑑証明書が求められる重要な場面は残っています。
今後、デジタル化の流れはさらに進むと予測されますが、当面は従来の印鑑と電子署名を事業内容や取引に応じて適切に使い分けるハイブリッドな運用が求められるでしょう。
印鑑の管理と紛失時の対応

法人印鑑は会社の信用に関わるため、紛失や盗難、悪用といったリスク管理が不可欠です。日頃の管理を徹底し、万が一の事態に備えることが重要です。
ここでは、具体的な保管ルールから紛失時の対応手順、悪用防止策までを解説します。
印鑑の保管方法と管理ルール
法人印鑑は会社の信用を左右する重要な物品のため、厳重な保管と明確な管理ルールの設定が不可欠です。
紛失や盗難、不正使用といったリスクを防ぐため、物理的な安全確保と組織的な運用体制の両面から対策を講じます。
具体的には、社内で「印章管理規程」を定め、以下のようなルールを設けることが有効です。
- 印鑑の保管: 代表者印は耐火金庫や貸金庫、銀行印なども施錠可能な場所で厳重に保管する
- 管理責任者の指定: 印鑑の種類ごとに管理責任者を定め、責任の所在を明確にする
- 使用ルールの徹底: 使用時の申請・承認フローを定め、押印履歴を管理台帳で記録する
こうした保管と管理のルールを徹底することが、会社の安全な運営につながります。
紛失時の対応と再発行の流れ
万が一、法人印鑑を紛失した場合は、悪用を防ぐために迅速な対応が求められます。落ち着いて以下の手順で手続きを進めましょう。
- 警察への届出: まず、最寄りの警察署や交番へ遺失届を提出し、盗難が疑われる場合は盗難届を提出する
- 失効手続き: 代表者印(会社実印)は法務局で、銀行印は取引金融機関で失効手続きを行う
- 改印(再発行): 新しい印鑑を作成し、法務局や金融機関で改印手続きを行う
関係各所への連絡: 契約中の取引先など、関係各所へ事情を説明し、トラブルを未然に防ぎます。紛失した印鑑の種類によって手順が異なるため、事前に流れを確認しておくことが重要です。
第三者による悪用リスクと防止策
法人印鑑は第三者に悪用されると、会社に甚大な損害をもたらすリスクがあるため、徹底した防止策が必要です。
勝手に契約を締結されたり、預金を引き出されたりする危険を防ぐには、日頃からの対策が欠かせません。具体的な防止策としては、以下の点が挙げられます。
- 印鑑の使い分け: 代表者印と銀行印を兼用せず、別々に作成・保管してリスクを分散させる
- 印鑑と重要書類の分別保管: 実印と印鑑証明書、銀行印と通帳は必ず別の場所に保管する
- 複製されにくい印鑑の作成: 偽造防止のため、複雑な書体(篆書体や印相体など)を選ぶ
これらの対策を講じることで、第三者による悪用のリスクを大幅に低減できます。
合同会社の設立の手続きと流れ

合同会社の設立を考えている場合は、設立の手続きと流れを把握しておくことが重要です。ここでは、合同会社の設立の手続きと流れについて解説します。
基本事項を決定する
合同会社を設立する場合は、基本事項を決定するところから始めます。
- 会社名
- 所在地
- 資本金
- 事業目的
- 事業年度
基本事項は「具体的に何を決める」と定められているわけではありませんが、上記のような基本的な要素から決めていくのが一般的です。
例えば、会社名は企業のアイデンティティとなるだけでなく、世間に認識してもらうための重要な要素となる他、所在地や資本金も今後の経営を左右する要素となるでしょう。
そのため、各基本事項は設立段階で細かく設定しておくのが理想です。
許認可で財産要件のある事業については要件を満たす金額の設定が必要となります。
他にも、あらかじめ決めておいた方が今後の経営がスムーズになるため、合同会社設立時にはある程度の基本事項を決定しておきましょう。
定款を作成する
合同会社を設立する際は、定款の作成が必要です。
定款とは、わかりやすくいうと「会社の基本的なルールを定めた書類」のことで、一般的には会社法によって定款に記載すべき事項などについて定められています。
合同会社の場合は社員となる人物が作成し、他の社員の署名または記名押印を行うことで作成でき、1人で設立する場合は自身の署名または記名押印で作成できます。
なお、定款に記載する事項には次のものが必要です。
- 商号・住所などの基本事項
- 社員の氏名や名称などの情報
- 社員の出資目的及び価額の評価標準
- 全社員を有限責任社員とする旨
その他、持分譲渡に関する要件や業務執行に関する社員の選任方法、業務の決定方法、代表する社員の指名または互選の規定、存続期間または解散事由などを記載します。
別途で、業務執行社員の人数や報酬などについて任意で記載すれば定款の作成は完了です。
印鑑を注文する
合同会社を設立する際は、印鑑はあったほうがよいでしょう。
印鑑の提出は合同会社設立時に限り任意となっていますが、契約や取引で使用する印鑑が複数あるため、時間があるときに印鑑を注文しておくことが重要です。
前述の通り、合同会社には主に「会社実印(代表者印)」「銀行印」「角印」の3つの印鑑が必要となるため、今後必要となりそうな印鑑を含め注文しておきましょう。
出資を履行する
資本金の価額が決定したら、実際に出資を行います。
合同会社を設立する発起人の金融機関口座に振り込みましょう。
出資を行ったら、通帳の出資を確認できるページと表紙・裏表紙をコピーして、払込証明書を作成してください。払い込みに問題がなければ、合同会社の設立完了です。
登記申請する
最後に、法務局に登記申請を行いましょう。
設立登記の申請手続きは省略できないため合同会社の代表者が法務局に設立登記のための申請書を提出します。
事前に作成した「会社実印(代表者印)」「銀行印」「角印」を準備し、法務局に次の書類を作成すれば登記申請が可能です。
- 合同会社設立登記申請書
- 定款
- 印鑑届出書
- 代表社員の印鑑登録証明書
- 業務執行社員の一致を証する書面
- 出資の払い込み及び給付を証する書面
- 資本金の価額が法令に則って計上されたことを証する書面
代理人が登記申請をする場合は、その権限を証する書面も持参してください。上記の書類に不備がなければ合同会社の設立が完了し、会社組織として運営可能です。
ただし、印鑑など事前に準備しておくべきものが揃っていないと手続きに遅れが生じるため、あらかじめ用意すべきものを把握しておくことを推奨します。
合同会社の印鑑作成の注意点

合同会社で印鑑を作成する際は、いくつかの注意が必要です。ここでは、合同会社の印鑑作成の注意点について解説します。
代表取締役印ではなく代表社員之印と刻印
合同会社の印鑑を作成する際は、代表取締役印ではなく代表社員之印と刻印しましょう。
株式会社の代表者印を作成する場合は「代表取締役之印」と表記するのが一般的ですが、合同会社の場合は「代表社員之印」と表記するのが一般的です。
印鑑を専門業者に依頼する場合は「株式会社ではなく合同会社」と伝え、代表取締役の文言は使用しないようにしましょう。
把握しやすく偽造されにくい書体
合同会社の印鑑を作成する際は、把握しやすく偽造されにくい書体を選びましょう。
印鑑の刻印は把握しやすさを重視すると単調になり、偽造されにくさを重視すると複雑になるため、視認しやすく簡単には真似できないものを作成する必要があります。
印鑑の専門業者ではどちらの要件も満たした印鑑の作成が可能なため、業者に相談するのがおすすめです。
1辺1cm以上3cm以下の正方形
合同会社で使用する会社実印(代表者印)は、1辺1cm以上3cm以下の正方形に収めなければいけません。
形状に規制はないものの、直径1.8cmの丸印がよく使用されているため、作成時に迷った場合は他の企業の印鑑を参考にすると良いでしょう。
ただし、刻印に入れる文字数に比例して印鑑のサイズも2.1cm〜2.4cmと大きくなるため、どれくらいの文字数を入れるのかも検討しなければいけません。
その他、普段の業務で使用する印鑑は形状やサイズの条件もないため、使用しやすいものを選びましょう。
ゴム印やシャチハタ印は不可
公的な書類に使用する印鑑は、ゴム印やシャチハタ印は認められていません。
通常業務でゴム印やシャチハタ印を使用する分には問題ありませんが、公的な手続きにおいては簡易的な印鑑は拒否されるため、その他の法人印鑑を別途作成しておきましょう。
ただし、平時の業務であっても契約や取引の内容によってはゴム印やシャチハタ印が認められないケースもあるため、場面ごとに使い分けることが重要となるでしょう。
印鑑の兼用は避ける
合同会社に限らず、印鑑の兼用は避けましょう。
例えば、会社実印(代表者印)と銀行印の兼用や、その他の印鑑と角印の兼用は危険です。同じ印鑑を兼用すると偽造や盗難のリスクがあるため、別々での作成・保管を推奨します。
万が一の際にも印鑑の兼用を行っていると「どの印鑑を使用したか」を失念し、各種手続きに問題が生じることもあるかもしれません。
そのため、印鑑の兼用はしないようにしてください。
合同会社の印鑑に関するよくある質問

合同会社の設立にあたり、印鑑に関する疑問は多く生じます。実印は必要なのか、電子契約で代替できるのかなど、よくある質問にQ&A形式で回答します。
合同会社でも実印は必要?
合同会社においても会社実印(代表者印)は必要です。特に、法務局へ書面で設立登記を申請する際には、会社実印の届出が必須となります。
また、登記申請時には代表社員個人の実印と印鑑証明書も求められるため、事前に準備しなければなりません。
設立後も、金融機関からの融資契約や不動産の売買契約、その他重要な契約を締結する場面で、会社の正式な意思決定を示すものとして会社実印の押印と印鑑証明書の提出が求められます。
合同会社の設立手続きと、その後の円滑な事業運営において会社実印は不可欠な役割を担っているため、必ず作成しましょう。
電子契約サービスを使えば印鑑は不要?
電子契約サービスを導入すれば契約書への押印は不要になりますが、法人印鑑が完全に不要になるわけではありません。
電子契約は電子署名法に基づき、電子署名によって契約の有効性を担保するため、物理的な押印作業は発生しません。
しかし、法人口座を開設する際の銀行印の届出や、一部の行政手続き、書面での契約を希望する取引先とのやり取りなど、依然として法人印鑑が必要となる場面は多く残っています。
そのため、業務のデジタル化を進める一方で、こうした押印文化が残る実務にも対応できるよう、法人印鑑一式(実印、銀行印、角印)は準備しておくべきです。
個人名義の銀行印は会社用に使える?
個人名義の銀行印を会社の法人口座用として使うことはできません。会社は個人とは別人格の法人であるため、会社の財産と個人の財産は明確に分けて管理する必要があります。
金融機関で法人口座を開設する際には、法人名義で作成された会社用の銀行印の届出が必要です。一般的に、会社の銀行印は外枠に会社名、内枠に「銀行之印」と彫刻されたものを使用します。
もし個人の印鑑を流用すると、資産管理が不明瞭になるので、必ず法人専用の銀行印を作成しましょう。
角印と実印は兼用できる?
法律上、サイズの規定を満たしていれば角印を会社実印として登録することは可能ですが、リスク管理の観点から兼用は絶対に避けるべきです。
実印は会社の最も重要な意思決定に使用するもので、厳重な管理が必要です。
一方、角印は請求書や見積書など日常業務で頻繁に使うため、紛失や盗難、印影を偽造されるリスクが実印に比べて格段に高まります。
万が一、兼用している印鑑が悪用された場合、会社に甚大な損害をもたらす契約を勝手に結ばれる危険性があります。
こうしたリスクを分散させるためにも、必ず実印と角印は別の印鑑として作成し、管理してください。
合同会社の設立にはGMOオフィスサポート
合同会社設立時、印鑑の提出は2021年の法改正で任意となり、オンライン申請では不要です。しかし、銀行口座の開設や融資、契約書への押印など、事業運営では法人印鑑が必要な場面が多く存在します。
必要な印鑑は主に「会社実印(代表者印)」「銀行印」「角印」の3つで、各種手続きの際に提出が求められることもあります。
そのため、合同会社設立時の印鑑の提出は任意であっても、後々のことを考えると事前に作成しておいた方が良いでしょう。
GMOオフィスサポートでは、会社設立印鑑セットを提供しています。
法人登記に利用する会社実印(代表社員)・銀行印・角印の他、印鑑ケースや捺印マット、朱肉や電子印影などもセットで提供しています。
ぜひこの機会に、お気軽にお問い合わせくださいませ。
法人登記やその手続の流れについて、下記の記事で詳しく解説しています。
起業や独立を考えている方に朗報
起業・経営のプロ監修のオリジナル冊子『会社設立完全ガイド』を無料でプレゼント!
「起業の窓口」では、起業に必要なノウハウや成功者のインタビュー、経理や会計の基礎知識など、さまざまなコンテンツを完全無料で提供しています。また、GMOインターネットグループが展開するビジネスの立ち上げや拡大に役立つ各種サービスをおトクな特典付きでご紹介しています。
会社設立や資金調達などのノウハウが詰まった『会社設立完全ガイド』をGETして、夢の実現への一歩を踏み出してみませんか?
- 記事監修
-
- 中野 裕哲 HIROAKI NAKANO
- 起業コンサルタント(R)、経営コンサルタント、税理士、特定社会保険労務士、行政書士、サーティファイドファイナンシャルプランナー・CFP(R)、1 級FP 技能士。 V-Spiritsグループ創業者。東京池袋を本拠に全国の起業家・経営者さんを応援!「あの起業本」の著者。著書16冊、累計20万部超。経済産業 省後援「DREAMGATE」で11年連続相談件数日本一。
- ※本記事は、起業の窓口編集部が専門家の監修または独自調査(アンケート)に基づいて制作したものです。
- ※掲載している情報は、記事公開時点の法令・税制・商品・サービス等に基づくものであり、将来的に変更される可能性があります。
- ※アンケート調査に関する記述は、特定の調査対象者からの回答結果および編集部の見解を含んでおり、内容の正確性・完全性を保証するものではありません。
- ※記事の内容は一般的な情報提供を目的としており、すべての方に当てはまるものではありません。個人の状況に応じた具体的な助言が必要な場合は、専門家にご相談ください。
- ※情報の利用や判断、実施については、ご自身の責任で行っていただきますようお願いいたします。
- ※本記事に掲載された内容の転載・複製はご遠慮いただき、引用の際は必ず出典をご明記ください。



 シェア
シェア