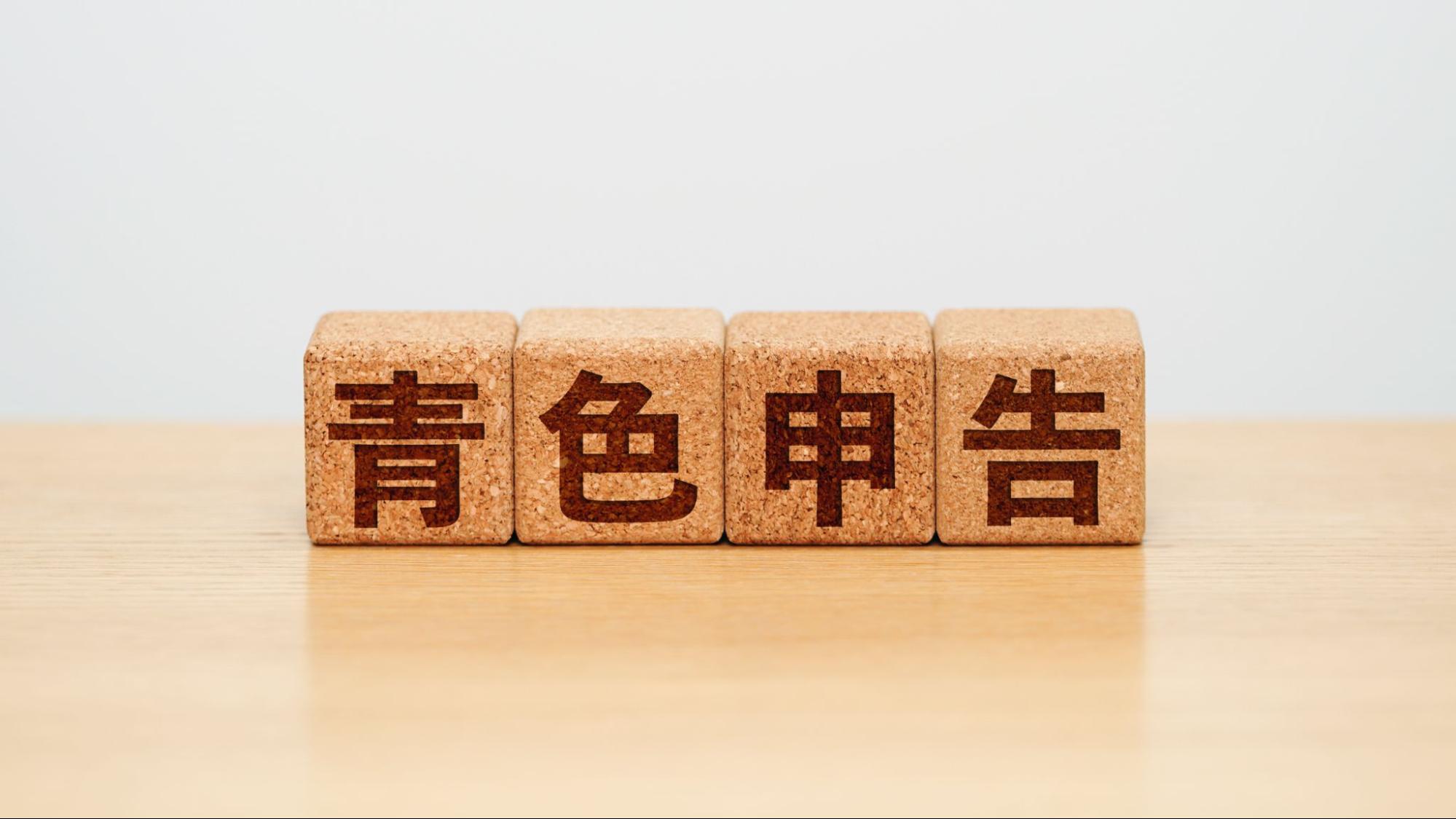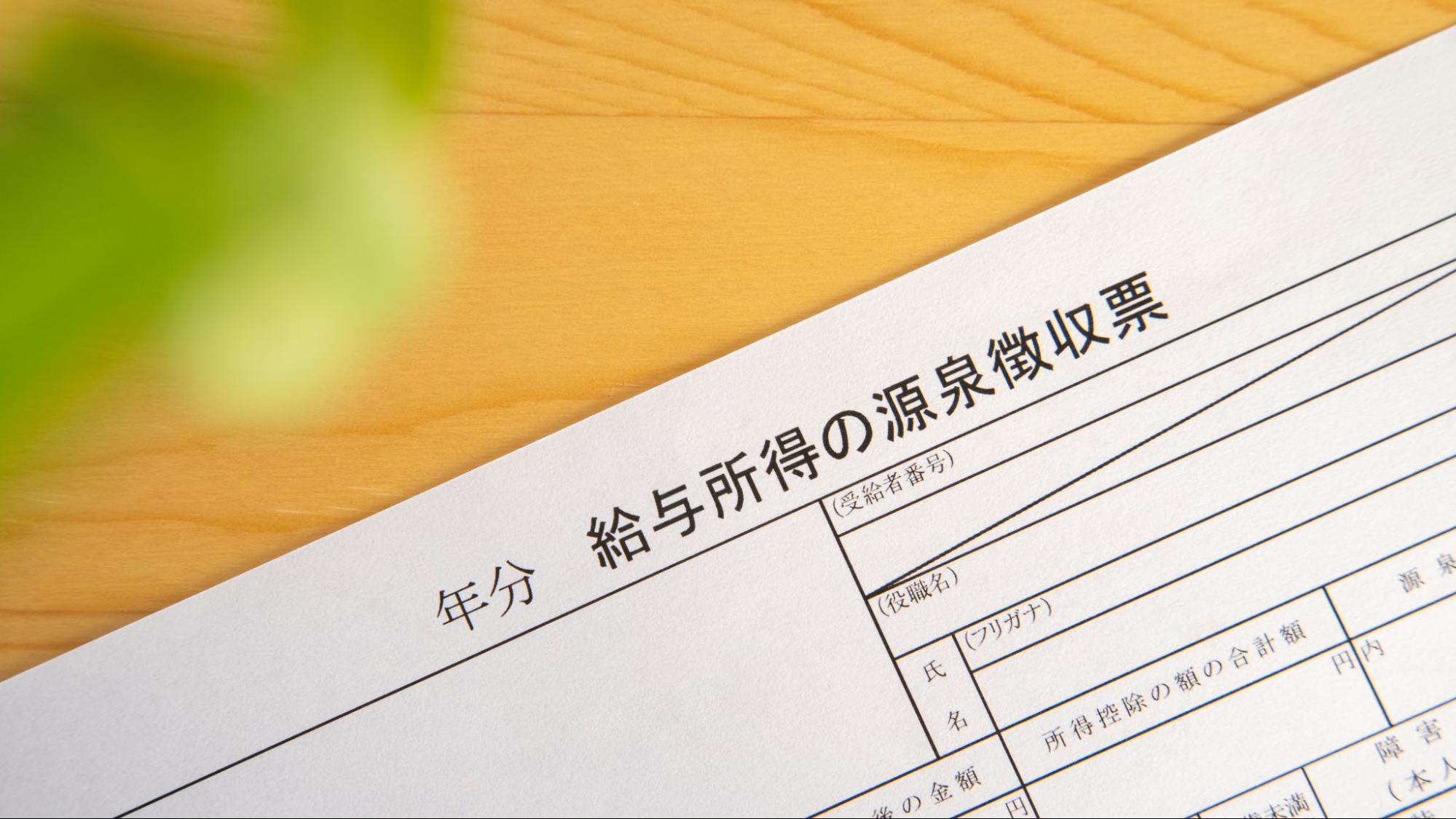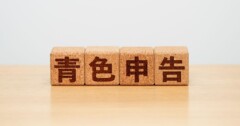メール副業の実態とは?詐欺被害の防ぎ方や収入を増やすコツ

メール副業は、その名の通りメールを使って稼ぐ方法で、相談に乗るものから営業まで、さまざまな仕事内容があります。
スマホがあれば始められる手軽さが魅力ですが、一方で詐欺のリスクもあるため注意しなければなりません。
メール副業で失敗しないためには、メリットやリスクを正しく理解することが大切です。この記事では、メール副業の実態や詐欺被害を防ぐ方法、収入を増やすコツなどを紹介します。
- 【この記事のまとめ】
- メール副業はメールを通じて収入を得る仕事で、場所や時間を選ばないメリットがあります。
- メール副業には営業や文章作成、カウンセラーなど、さまざまな種類があります。
- しかし、詐欺も多くあるため信頼できる会社やサイト選びが大切です。
2024年11月1日より、フリーランス保護法が施行されます。
組織に所属せずに働くフリーランスが安心して働ける環境を整備するために、フリーランスと企業などとの発注事業者間の取引の適正化(契約書等により取引条件を明示する)が主な目的です。
詳しくは次の記事をご覧ください。フリーランス保護法の概要、制定された背景や具体的な内容などを解説しています。
メール副業とは

メール副業とは、メールやオンラインのコミュニケーションツールを利用して収入を得る副業です。
スマホを使って空いた時間にできることから、時間や場所が制限されやすい会社員や主婦に特に人気があります。
メール副業は2000年代にかけてインターネットが普及し、メールが使えるようになった時代から存在しています。
近年になってメール副業が話題になる機会が増えたのは、2018年に政府が働き方改革の一環として、副業を積極的に推進するようになったのが一つのきっかけです。
さらにSNSの普及もメール副業の発展を促し、種類も多様化しています。
一方で、メール副業を始める方をターゲットにした詐欺も増えている現状があります。詐欺に巻き込まれると経済的な損失だけでなく、知らない間に犯罪に巻き込まれるリスクもあるため注意が必要です。
メール副業で成功するためにも、メール副業のメリットやリスクを十分に把握しておきましょう。
メール副業の特徴

ここでは、メール副業の特徴を解説します。
主なメール副業の種類
メール副業の主な種類と特徴は以下の通りです。
| メール副業の種類 | 特徴 |
|---|---|
| メールオペレーター | オンライン通販や求人サイトなど、Web事業を展開している企業のオペレーター業務です。商品に関する問い合わせや詳細な内容について、メールでやりとりを行います。電話が苦手な人でもできるため人気の副業です。 |
| メール営業 | リストに基づいて個人や企業に営業メールを送る仕事です。営業の文面作成が必要となる場合もあるため、営業経験がある方に向いています。情報収集やリスト作成を同時に依頼されるケースもあります。 |
| メール文章作成 | 企業の商品概要やサービスに関する文章を作成し、メールやDMで送信する仕事です。顧客の興味を惹くセールスコピーやアピールポイントを、文章にまとめる必要があります。 |
| メールカウンセラー | メールを通じて心の悩みや問題を抱える人を支援する仕事です。相談者と直接会うことなく、メールを通じた文章で悩み相談に応じます。電話と違って伝えたい内容をじっくりと考えられます。 |
| メールアンケート | 企業から依頼のあったアンケートに答えて謝礼をもらう仕事です。簡単なアンケートであれば、1件につき数分から数十分で回答できます。 |
メール副業には、スキルがなくても始められる仕事もあれば、営業やキャッチコピー作成のように一定のスキルが求められる仕事もあります。
メール副業を始める際は、自分が持っているスキルや興味に合ったものを選ぶのがよいでしょう。
メール副業のメリット
メール副業のメリットは、時間と場所を選ばないことや初期コストを抑えられることです。基本的にメールを使った副業は、パソコンやスマホがあればどこでも行うことができます。
そのため、「スキマ時間を利用して副収入を増やしたい」「収入を増やしたいけど子育てが忙しくて外にいけない」という方にも最適です。
また、メール副業の多くは特別な設備や道具が必要なく初期コストがかからないため、お金がなくても気軽に始められます。
ランニングコストについても、インターネット環境とスマホの維持費のみで、店舗を用意する必要もありません。
さらに、業務内容によってはライティングやコミュニケーション能力、営業の知識などが向上するメリットもあります。
知識やスキルを高めることで、効率よく稼げる副業が見つかる可能性が高まるでしょう。
メール副業で高収入を得るコツ

メール副業で高収入を得るためには工夫が必要です。ここでは、メール副業で高収入を得るためのコツを紹介します。
効率的な時間管理と作業スケジュール
メール副業は一般的に数をこなせばこなすほど収入も増えるため、高収入を得るためには時間管理と作業スケジュールの調整が重要です。
時間管理や作業時間の確保のためには、時間ブロックの活用をおすすめします。時間ブロックとは、1日を一定のブロックに分け、それぞれの時間帯に特定のタスクを振り分ける時間管理方法です。
例えば、「平日の21時から22時まではメール副業に割り当てる」と決めておくと、どれだけ忙しくても副業に時間を回すことができるようになります。
時間ブロックを活用することで、集中力を持続したり効率的に作業を進められたりするなどのメリットもあります。
メール副業はいつでもどこでもできる一方、ある程度のルールを決めておかないと手をつけなくなる可能性もあるため、副業で成果を出すためにも時間管理は徹底しましょう。
また、本業の合間や休憩時間を有効に活用することも収入を増やすためのコツです。1日の中でどれくらい副業に使える時間があるかを、まずは確認してみましょう。
複数のメール副業を組み合わせる
メール副業で収入を増やすためには、複数のメール副業を組み合わせるのもコツです。
例えば、メールアンケートを始める場合は1つのアンケートサイトだけでなく、複数のアンケートサイトに登録することで案件を増やせます。
他にも、休日はメールカウンセラーの副業を行い、本業がある日はスキマ時間を使って営業メールの作成を行うなど、異なるタイプのメール副業を組み合わせるのもよいでしょう。
異なるメール副業を同時進行することで、スキルの相乗効果も期待できます。
また、複数の副業を組み合わせることは収入増加だけでなく、リスクを分散できるという点もメリットです。一つの副業の受注がなくなっても、他の副業があれば副業収入がいきなりゼロにはなりません。
ただし、複数のメール副業を組み合わせる場合は、それぞれの副業が雑にならないように注意する必要があります。
メール副業による税金と確定申告の方法

メール副業で収入を得た場合所得金額によっては、確定申告をして税金を納める必要があります。ここでは、メール副業による税金と確定申告の方法を解説します。
副業収入の税金の基本知識
副業収入が発生した場合、所得に応じて所得税と住民税を納める義務があります。
所得は収入から経費を差し引いた額のことです。年間に100万円の収入があり経費が50万円かかっている場合、年間の所得は50万円になります。
所得税は年間の所得に基づき、5~45%の累進課税が適用されます。所得が多くなるほど税率も高くなるため、副業収入が多くなるほど納める所得税も増える仕組みです。
また、所得税とは別に復興特別所得税が別途2.1%かかります。復興特別所得税は東日本大震災からの復興を目的とした創設された税金で、2037年12月31日まで上乗せされて徴収されます。
一方、住民税は、一定以上の所得のある人に均等にかかる均等割と所得に応じて課税される所得割、一部の自治体では森林環境税やみどり税といった均等割に上乗せされ課税される税目で構成されています。均等割は一律ですが、所得割額は、課税総所得に対し税率10%が課税されます。
給与所得者は給料から所得税や住民税が差し引かれますが、メール副業の収入については自身で確定申告し所得税がある場合は納税しなければなりません。合わせて住民税がある場合で個人納付を選択した場合は、自ら納税しなければなりません。
確定申告を楽にしたいと悩む方へ

質問に答えていくだけで、経理の作業がはじめての方でも簡単に確定申告の書類作成をすることができます!
確定申告を楽にサクッとおこないたい方は、freeeがおすすめです!
確定申告の必要性と方法
メール副業で所得が発生した場合、所得額によっては確定申告を行って所得税を納付しなければなりません。
確定申告は、1年間の所得から所得税を計算して税務署に申告・納税する手続きです。前年の所得に対して、基本的に2月16日~3月15日までの間に手続きを行います。
確定申告は、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を利用してオンラインで行うことも可能です。ちなみに給与所得者の場合は、副業の年間所得が20万円以下だと確定申告は不要です。
しかし、確定申告の必要がなくても住民税の申告は行わなければなりません。
確定申告を行うと申告内容が税務署から市区町村に通知されるため手続きは不要ですが、確定申告をしない場合は市区町村で住民税の手続きを行う必要があります。
そのため、年間所得が20万円以下でも確定申告をした方が良いでしょう。副業で収入を得た場合の確定申告については、以下の記事でも詳しく解説しています。
メール副業詐欺の実態と対策

メール副業を始める場合は、副業詐欺に注意が必要です。ここでは、メール副業詐欺の実態と対策を解説します。
よくある詐欺の手口
メール副業詐欺でよくある手口は、副業を始める際に登録料や教材費などが請求されるケースです。登録料や教材費ではなく、「ポイント購入が必要」という言葉で課金を促される場合もあります。
基本的にメール副業であれば、高額な登録料や教材費が発生することはありません。お金を稼ぐために始めたにもかかわらず、高額な登録料や教材費の発生によって損失を抱えるリスクがあります。
また、詐欺師に個人情報を渡してしまうことで、個人情報が流出して二次被害に遭う可能性もあるため注意が必要です。
個人情報の流出により、勝手に有料サービスに登録されたり高額な請求がきたりなど、特殊詐欺に使われるリスクもあります。
チャットレディについて
チャットレディのメール副業も、副業詐欺に巻き込まれやすいため注意が必要です。
チャットレディとは、メールやライブチャットサービスを利用して男性とコミュニケーションを取って報酬を得る仕事です。
基本的にはメール1通あたりの単価が決められており、画像や動画を送ると、さらに報酬が増える仕組みとなっています。
詐欺師は、「メールのやりとりだけで稼げる」「簡単に高収入が得られる」などの甘い言葉で興味を引こうとします。
詐欺師が運営しているチャットレディのサイトに登録すると、個人情報が悪用されたり、報酬が払われなかったりなどのトラブルにつながる可能性があるため注意しましょう。
また、システムトラブルや文字化けなどを理由に金銭を請求されるようなケースもあります。
詐欺被害を防ぐには
メール副業の詐欺に遭わないためにも、「誰でも稼げる」「すぐに高収入が得られる」などの簡単に稼げるという話は疑いましょう。
誰でも簡単に高収入を得られる副業はありません。このような副業は詐欺に遭うだけでなく、闇バイトに加担することで大きな犯罪に巻き込まれるリスクもあります。
怪しいと思ったら、登録を考えているサイト運営者の会社名や所在地などを事前に調べ、実績があるかどうかを確認しましょう。
インターネット上で、サイトや運営会社の口コミやレビューなどをチェックしておくことが大切です。
被害にあった場合の対処法
メール副業の詐欺に遭った場合は、警察相談専用電話(#9110)や消費者庁が設置する消費者ホットライン(188)で相談しましょう。
相談内容に応じて具体的な対策を教えてもらうことができ、地方公共団体が設置している消費生活センター等を紹介してもらうことができます。
また、クーリングオフが可能な場合は早急に手続きを行いましょう。クレジットカードで料金を支払っている場合なら、チャージバックで返金してもらえるケースがあります。
被害にあったことが明確な場合は、最寄りの警察署に相談して被害届を提出しましょう。
なお、詐欺師に返金請求を行う場合は、弁護士に相談するのが一般的です。
まとめ
この記事では、メール副業の実態や詐欺被害の防ぎ方、収入を増やすコツを解説しました。
メール副業は空いた時間で気軽に副業できるというメリットがある一方、副業詐欺に巻き込まれるなどのリスクもあるため注意が必要です。
実際に始める際は、メール副業を募集している会社の評判や実績を十分に調べたうえで、十分に検討してから判断しましょう。
また、メール副業で詐欺被害に遭った場合は被害内容に応じて、消費者ホットラインや警察、弁護士などに早めに相談することも大切です。
スキマ時間を有効活用!副業に興味を持ったら、まずは「起業の窓口」に登録してみよう
副業で収入アップを考えている方も多いと思いますが「時間がない」と感じて諦めている方も多いのではないでしょうか。しかし、スキマ時間を上手く利用して副業をすることで、本業とは異なる収入源を持つことが可能です。
起業の窓口では、スキマ時間に手軽に始められるおすすめの副業やメール、SNS、AIを活用した副業、必要なノウハウなど、さまざまなコンテンツを無料でご提供。また、GMOインターネットグループが展開する副業に役立つ各種サービスをおトクな特典付きでご紹介しています。
副業から起業を目指す人にもオススメです。
- 記事監修
-
- 中野 裕哲 HIROAKI NAKANO
- 起業コンサルタント(R)、経営コンサルタント、税理士、特定社会保険労務士、行政書士、サーティファイドファイナンシャルプランナー・CFP(R)、1 級FP 技能士。 V-Spiritsグループ創業者。東京池袋を本拠に全国の起業家・経営者さんを応援!「あの起業本」の著者。著書16冊、累計20万部超。経済産業 省後援「DREAMGATE」で11年連続相談件数日本一。
- ※本記事は、起業の窓口編集部が専門家の監修のもとに制作したものです。
- ※掲載している情報は、記事の公開・更新時点における商品・サービス、法令、税制に基づいており、将来これらは変更される可能性があります。
- ※記事内容の利用・実施については、ご自身の責任と判断でお願いいたします。
- ※本記事は一般的な情報提供を目的としております。個人の状況に応じた具体的な助言が必要な場合は、専門家にご相談ください。



 シェア
シェア