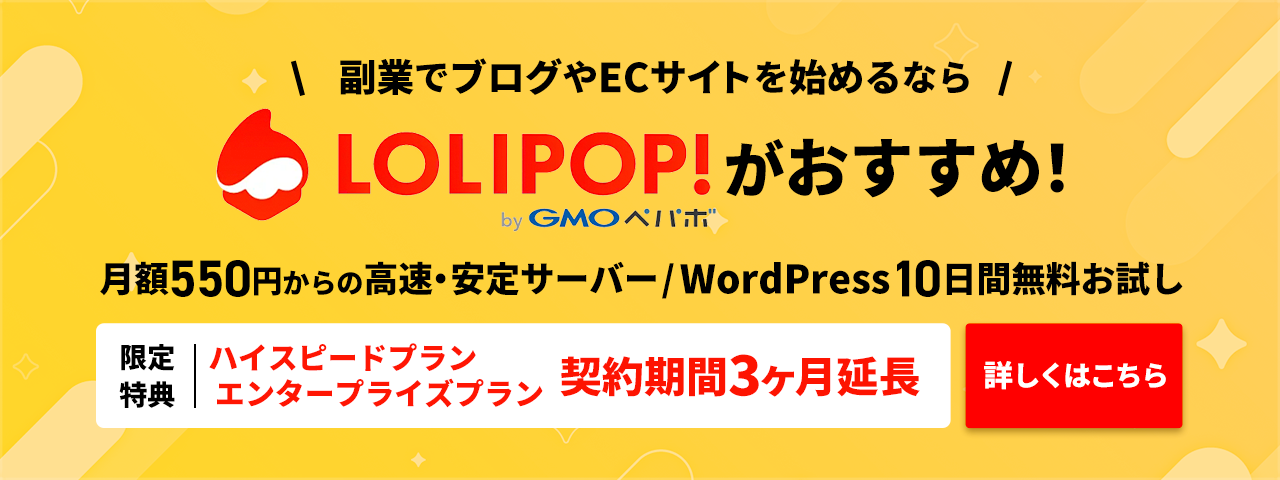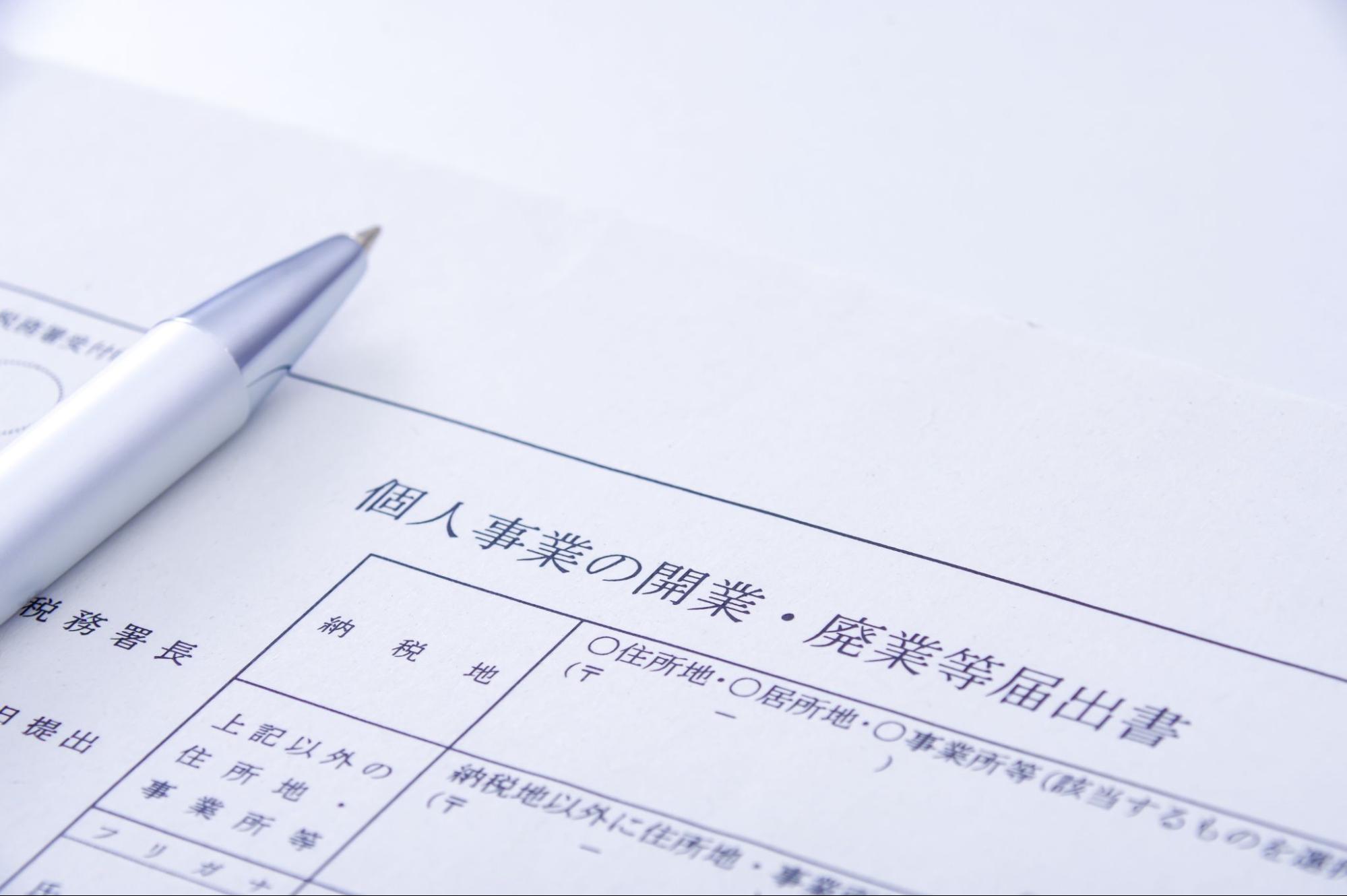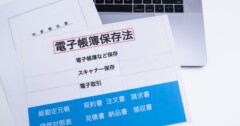スタートアップでも必要?ゼロトラスト環境の構築

スタートアップ企業は、限られたリソースの中で効果的なセキュリティ対策を講じる必要があります。
ゼロトラスト環境を構築することによって強固なセキュリティ体制を実現できますが、具体的な内容や導入方法がわからないという方も多いのではないでしょうか。
この記事では、スタートアップ企業におけるゼロトラスト環境の構築について詳しく解説します。
- 【この記事のまとめ】
- ゼロトラスト環境は、内部・外部問わず全てのアクセスを検証し、社内からの不正アクセスにも対応できる強固なセキュリティを提供します。
- ゼロトラストを実現するためには、「Never trust, always verify」の原則を遵守し、強力な認証やネットワークセグメンテーション、データ保護などの要件を満たすことが必要です。
- タートアップ企業がゼロトラストを導入することで、セキュリティリスクの最小化、クラウドサービスやリモートワークの安全な活用、コスト効率や生産性の向上が期待できます。
ゼロトラストセキュリティとは

ゼロトラストセキュリティは、従来のセキュリティモデルとは異なるアプローチを取る概念です。
ここでは、ゼロトラストセキュリティについて詳しく解説します。
ゼロトラストの定義と従来のセキュリティモデルとの違い
ゼロトラストセキュリティは、「信頼できるものは何もない」という前提に基づくセキュリティモデルです。
従来の境界型セキュリティが社内ネットワークを信頼し、外部からの脅威のみを想定していたのに対し、ゼロトラストでは内部・外部を問わずすべてのアクセスを検証します。
このアプローチにより、社内からの不正アクセスや内部脅威にも対応できるため、より包括的なセキュリティ対策が可能です。
また、クラウドサービスやリモートワークの普及により、従来の境界型セキュリティでは対応が難しくなっている現状にも適しています。
ゼロトラストが注目される背景と現代のセキュリティ課題
ゼロトラストが注目される背景には、デジタルトランスフォーメーション(DX)の加速があります。
クラウドサービスの利用拡大やリモートワークの普及により、従来の境界型セキュリティでは対応が困難な状況が増えています。また、サイバー攻撃の高度化や内部不正の増加も大きな要因です。
これらの脅威に対して、ゼロトラストは「すべてを信頼しない」という前提で、常に認証と認可を行うことで、より強固なセキュリティを実現します
ゼロトラストの基本原則と構成要素

ゼロトラストを実現するには、いくつかの重要な原則と要素があります。
ここでは、ゼロトラストの基本原則と構成要素について解説します。
「Never trust, always verify」の原則
ゼロトラストの基本原則は「Never trust, always verify(決して信頼せず、常に検証する)」です。この原則に基づき、すべてのアクセスに対して認証と認可を行います。
具体的には、ユーザー、デバイス、ネットワーク、アプリケーションなど、すべての要素を信頼せず、常に検証を行います。
この取り組みにより、内部からの不正アクセスや外部からの攻撃に対して、より強固な防御を実現することが可能です。
ゼロトラストを実現する7つの要件
ゼロトラスト環境を構築するには、様々な要件を満たすことが求められます。
ゼロトラストを実現するための7つの要件は、以下の通りです。
- 強力な認証:多要素認証などの導入
- デバイス制御:デバイスの健全性確認
- ネットワークセグメンテーション:必要最小限のアクセス制御
- アプリケーション制御:アプリケーションレベルでのアクセス管理
- データ保護:暗号化やアクセス制御の徹底
- 可視化と分析:ログ収集と異常検知
- 自動化と継続的な監視:セキュリティポリシーの自動適用と常時監視
これらの要件を満たすことで、包括的なゼロトラスト環境を構築できます。
しかし、ゼロトラストの実装は一朝一夕に行えるわけではなく、組織の規模やニーズに応じて段階的に導入し、継続的に改善していくことが重要です。
また、技術的な対策だけでなく、従業員の教育や組織文化の変革も同時に進める必要があります。
ゼロトラストは単なるセキュリティ対策ではなく、組織全体のデジタルトランスフォーメーションの一環として捉えることが、成功への鍵となるでしょう。
スタートアップ企業がゼロトラストを導入するメリット

スタートアップ企業にとって、ゼロトラストの導入には多くのメリットがあります。
ここでは、スタートアップ企業がゼロトラストを導入するメリットについて詳しく解説します。
セキュリティリスクの最小化と事業継続性の向上
ゼロトラストの導入により、スタートアップ企業は包括的なセキュリティ対策を実現できます。
従来の境界型セキュリティでは見落とされがちだった内部脅威にも対応できるため、セキュリティリスクを大幅に低減できます。
また、常時監視と認証により不正アクセスや情報漏洩のリスクを最小限に抑えられ、セキュリティインシデントによる事業中断のリスクを軽減し、事業継続性を向上させることが可能です。
クラウドサービスとリモートワークの安全な活用
スタートアップ企業にとって、クラウドサービスやリモートワークの活用は効率的な事業運営に欠かせません。
ゼロトラストは、場所やデバイスを問わず安全なアクセスを可能にするため、これらの新しい働き方を安全に導入できます。
クラウドサービスの利用においても、ゼロトラストの原則に基づいた認証と認可により、データの保護と安全なアクセスを実現できます。
スタートアップ企業は柔軟な働き方を維持しながら、セキュリティを強化することが可能です。
コスト効率と生産性の向上
ゼロトラストの導入は、長期的にはコスト削減につながります。従来の境界型セキュリティでは、複数のセキュリティ製品を導入・管理する必要がありましたが、ゼロトラストでは統合的なアプローチが可能です。
また、クラウドベースのゼロトラストソリューションを利用することで、初期投資を抑えつつ、スケーラブルなセキュリティ対策を実現できます。
さらに、セキュリティ強化により、インシデント対応にかかるコストや時間を削減し、生産性の向上にもつながります。
ゼロトラスト導入のステップ

ゼロトラストの導入は段階的に進めることが重要です。
ここでは、ゼロトラスト導入のステップについて詳しく解説します。
現状分析とゼロトラスト戦略の策定
ゼロトラスト導入の第一歩は、組織の現状を正確に把握し、明確な戦略を立てることです。この段階では、現在のセキュリティ状況を綿密に分析し、保護すべき重要資産やセキュリティギャップを特定します。
ネットワーク構成、アクセス制御ポリシー、データフロー、ユーザー権限など、多岐にわたる要素を調査することが重要です。
分析結果に基づいて、組織の業務プロセスやリスク許容度を考慮しながら、包括的なゼロトラスト戦略を策定します。
この戦略には、短期・中期・長期の目標や具体的な実装計画を盛り込み、同時に経営陣の理解と支持を得ることも不可欠です。
さらに、ゼロトラスト導入に伴う課題を予測し、事前に対策を検討することでスムーズな導入が可能となります。
ID認証基盤の整備と多要素認証の導入
ゼロトラストの基盤となるのは、強力なID認証システムです。
すべてのユーザーとデバイスを一元管理する統合的なID管理システムを構築することで、アクセス権限の管理が容易になり、セキュリティリスクを大幅に低減できます。
次に、多要素認証(MFA)を導入します。MFAは、知識情報(パスワードなど)、所持情報(スマートフォンなど)、生体情報(指紋など)の中から2つ以上を組み合わせて認証を行う方式です。
ただし、MFAの導入に際しては、セキュリティの強化とユーザーの利便性のバランスを取ることが重要です。
例えば、シングルサインオン(SSO)と組み合わせることで、セキュリティを高めつつ、ユーザーの負担を軽減することができます。
デバイスセキュリティとエンドポイント保護の強化
ゼロトラストの原則に基づき、すべてのデバイスを潜在的な脅威とみなし、厳格な管理を行います。
デバイス管理(MDM)を通じて、デバイスのOSやアプリケーションの更新状況、セキュリティ設定などを一元管理し、脆弱性を最小限に抑えます。
さらに、最新のAIや機械学習(ML)を活用したエンドポイント保護ソフトウェアを導入し、マルウェア対策や不正アクセス検知を強化することで、未知の脅威にすることが可能です。
加えて、デバイスの検証プロセスを確立し、リソースへのアクセスを許可する前に、デバイスが組織のセキュリティ要件を満たしているかを確認します。
ネットワークセグメンテーションとマイクロセグメンテーションの実装
ネットワークセグメンテーションは、ゼロトラストを構築するうえでの重要な要素です。
ネットワークを論理的に分割しアクセス制御を細分化することで、攻撃者の横方向の移動を制限し、被害の拡大を防ぐことができます。
さらに進んだマイクロセグメンテーションでは、個々のワークロードやアプリケーションレベルでセグメント化を行うため、より細かな粒度でのアクセス制御が可能となり、セキュリティをさらに強化できます。
これらの技術を実装することで、「最小権限の原則」を実現し、ゼロトラストの重要な要素を満たすことが可能です。
データ保護とアクセス制御の最適化
ゼロトラストにおいて、データ保護は最も重要な要素の一つです。
まず、組織内のデータを分類し重要度評価を行います。そのうえで、重要なデータには適切な暗号化を施し、それぞれに適切な保護レベルを設定します。
データへのアクセスは厳密に制御し、必要最小限の権限のみを付与することが重要です。ロールベースアクセス制御(RBAC)や属性ベースアクセス制御(ABAC)などの高度なアクセス制御メカニズムを活用します。
これらの対策により、データの機密性、完全性、可用性を確保し、ゼロトラストの原則に基づいたデータ保護を実現できます。
ゼロトラスト導入の課題と対策

ゼロトラストの導入には、いくつかの課題が存在します。
ここでは、ゼロトラスト導入の課題と対策について解説します。
従業員の理解と協力を得るための教育と啓発
ゼロトラストの導入には、従業員の理解と協力が不可欠です。多くの従業員にとって、常時認証や厳格なアクセス制御は煩わしく感じられる可能性があります。
この課題に対しては、定期的な教育と啓発活動が効果的です。ゼロトラストの必要性や利点を分かりやすく説明し、セキュリティ意識の向上を図ります。
また、導入初期は段階的にポリシーを適用し、従業員が徐々に慣れていけるよう配慮することも重要です。
導入検討、まずは基盤となる認証・認可(IDaaS)から
ゼロトラストの全面的な導入は、多くの企業にとって大きな変革となります。
したがって、まずは基盤となる認証・認可システム、特にIDaaS(Identity as a Service)の導入から始めることをおすすめします。
IDaaSを導入することで、統合的なID管理と多要素認証を実現でき、ゼロトラストの重要な要素を満たしつつ、段階的な導入が可能です。
また、クラウドベースのIDaaSを利用することで、初期投資を抑えつつ、スケーラブルな認証基盤を構築できます。
既存システムとの統合と段階的な移行計画
多くの企業では、既存のシステムやアプリケーションが存在します。これらをゼロトラスト環境に統合することは、技術的にも運用面でも課題となります。
この課題に対しては、段階的な移行計画を立てることが重要です。
まず、重要度の高いシステムや新規システムからゼロトラストを適用し、徐々に範囲を広げていきます。
また、APIやシングルサインオン(SSO)技術を活用し、既存システムとの連携を図ることで、スムーズな統合を実現できます。
セキュリティに関するご相談なら「GMOセキュリティ24」へ!
セキュリティ対策が重要と分かっていても何からすべきなのか、自社の課題に対して何が最適なのか不安がつきものです。
「GMOセキュリティ24」では24時間、漏洩やサイトリスク診断や相談が無料できます。
気軽にご利用いただけるサービスなので、セキュリティ対策の手始めとしてぜひご活用ください!
「GMOセキュリティ24」はこちら。
- 記事監修
-

- GMOグローバルサイン株式会社は、ヨーロッパで初めてWebTrustを取得した認証局です。2006年にGMOインターネットグループに加わり、政府レベルのセキュリティを世界展開。電子証明書市場のリーディングカンパニーとして積極的な活動を行い、電子署名業界および学術界の専門家から構成される国際団体「クラウド署名コンソーシアム」に加盟し、国際的な法規制を遵守したクラウド上の電子署名の実施におけるオープンな標準規格の決定に参加しています。
GMOグローバルサイン株式会社
https://www.globalsign.com/
- ※本記事は、起業の窓口編集部が専門家の監修または独自調査(アンケート)に基づいて制作したものです。
- ※掲載している情報は、記事公開時点の法令・税制・商品・サービス等に基づくものであり、将来的に変更される可能性があります。
- ※アンケート調査に関する記述は、特定の調査対象者からの回答結果および編集部の見解を含んでおり、内容の正確性・完全性を保証するものではありません。
- ※記事の内容は一般的な情報提供を目的としており、すべての方に当てはまるものではありません。個人の状況に応じた具体的な助言が必要な場合は、専門家にご相談ください。
- ※情報の利用や判断、実施については、ご自身の責任で行っていただきますようお願いいたします。
- ※本記事に掲載された内容の転載・複製はご遠慮いただき、引用の際は必ず出典をご明記ください。



 シェア
シェア