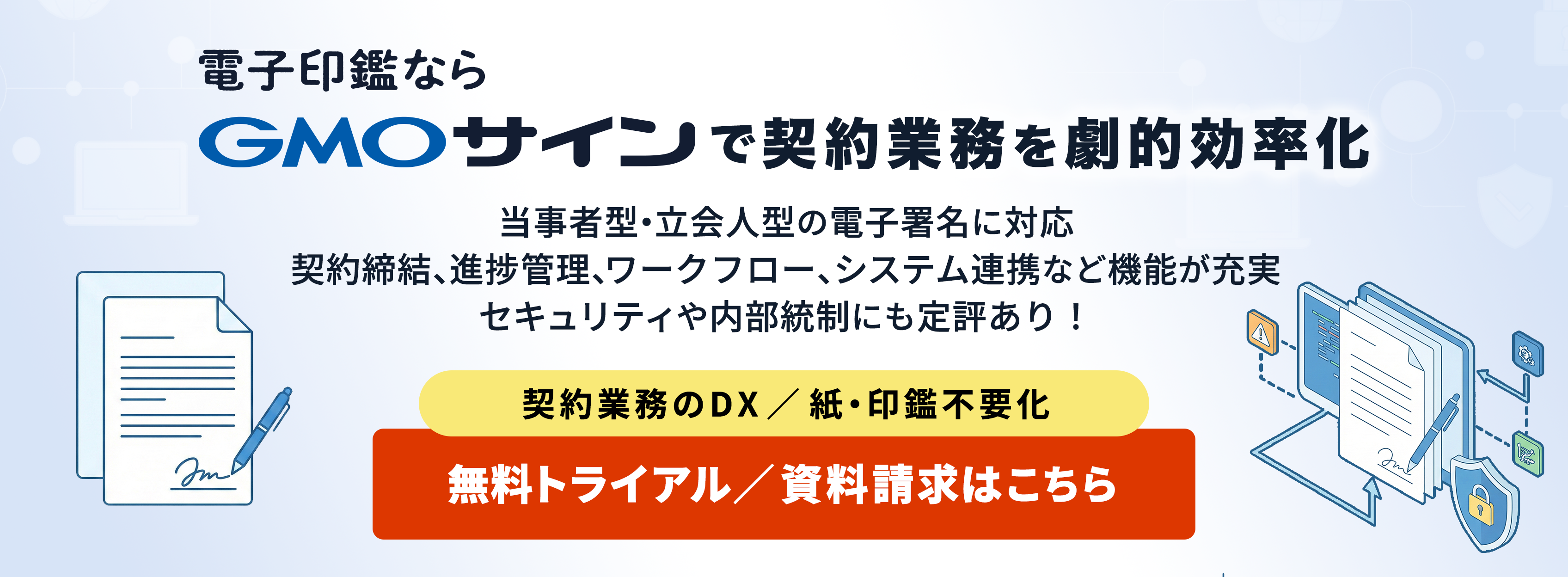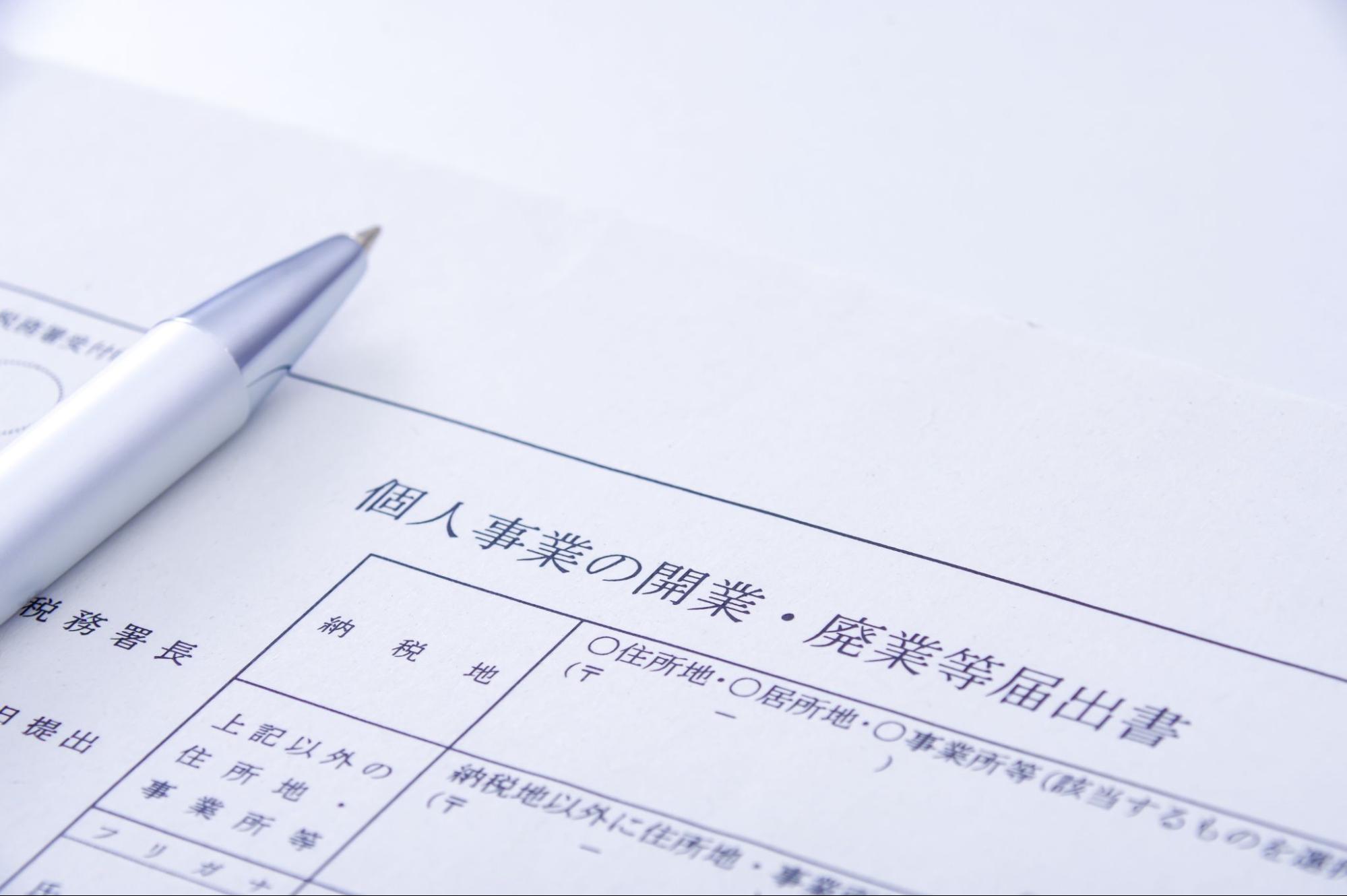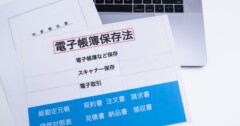電子契約に法的効力は本当にある?電子署名法や証拠力・導入ポイントについて解説
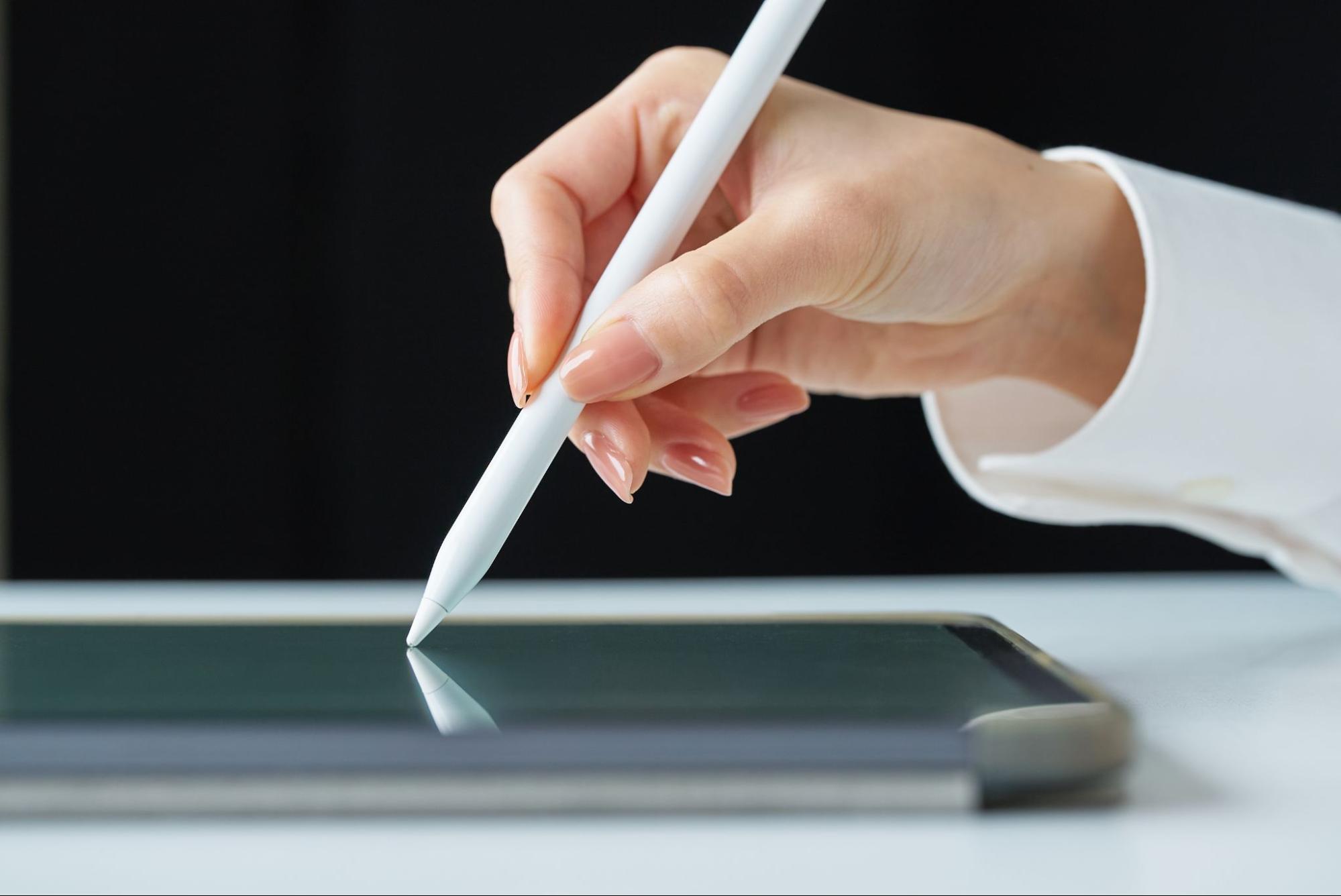
ペーパーレス化が進む今、「電子契約に法的効力は本当にあるのだろうか?」という疑問をお持ちではないでしょうか。
結論から言えば、電子署名法に基づき、電子契約にも紙の契約書と同等の法的効力が認められています。
しかし、その効力を確実に担保するには、電子署名の仕組みや関連法規を正しく理解し、適切な方法で導入・運用することが不可欠です。
この記事では、電子契約の法的効力の根拠や証拠力、具体的な導入ポイント、そして注意点まで解説します。
- 【この記事のまとめ】
- 電子契約は電子署名法により紙の契約と同等の法的効力が認められています。本人確認や改ざん防止を担保することで、安心して利用できる仕組みです。
- 電子契約には当事者型や立会人型などの方式があり、信頼性や利便性に応じて選択が必要です。保存には電子帳簿保存法の要件遵守も求められます。
- 書面交付が義務付けられる契約など一部では電子契約が使えません。導入時は法令確認と社内体制の整備を行い、安全で効率的な運用を実現することが重要です。
電子契約の基本知識

電子契約を導入するにあたっては、まず基本的な仕組みを理解することが重要です。
ここでは、電子契約が「そもそもどのようなものか」という定義から、従来の紙や口頭契約との違い、そして近年注目される背景までを分かりやすく解説します。
電子契約とは何か
電子契約とは、紙の契約書を使用せず、デジタルデータ上で契約手続きを完結させる仕組みを指します。
パソコンやスマートフォンを通じて契約内容を確認し、電子署名やタイムスタンプを付与することで法的に有効な契約が成立します。
データとして管理できるため、書類の保管コストを削減し、紛失や改ざんのリスクを抑えられる点も大きなメリットです。
また、電子署名法によって契約当事者の同意と本人性が担保されており、紙の契約と同様に法的効力が認められます。
働き方の多様化が進む現在、電子契約は業務の効率化とコンプライアンス強化を実現する有効な手段として企業に広がっています。
紙の契約・口頭契約との違い
紙の契約や口頭契約と比べ、電子契約は手間やコストを大きく削減でき、証拠性にも優れています。以下の表で、それぞれの特徴と違いを分かりやすく比較します。
| 比較項目 | 紙の契約 | 口頭契約 | 電子契約 |
|---|---|---|---|
| 契約の方法 | 書面に署名や押印を行い締結 | 口頭での合意により成立 | 電子署名や認証システムで締結 |
| 印紙税 | 契約内容に応じて印紙税が必要 | 不要 | 不要 |
| 証拠力 | 書面があれば一定の証拠力をもつ | 証拠が残りにくく、後で確認が困難 | 署名データや通信記録が残り証拠として有効 |
| 作業負担 | 印刷・押印・郵送・保管の手間が多い | 手続きは簡単だが記録管理が難しい | オンラインで確認から締結まで完結し効率的 |
| コスト | 印紙代・紙代・郵送費・保管費用が発生 | 費用は発生しないが信用性が低い | 印紙税不要でコスト削減が可能 |
| セキュリティ | 紛失や改ざんのリスクがある | 記録が残らずリスクが高い | 電子認証で改ざん防止が可能 |
デジタル化が進む現在、紙や口頭に比べて確実性・効率性ともに優れた電子契約を導入する企業が急増しています。
業務のスピード化とセキュリティを両立できる点が、電子契約が選ばれる大きな理由の一つです。
電子契約が注目される背景
電子契約が急速に注目されている背景には、DX推進やリモートワークの普及が挙げられます。
紙の書類をやり取りする必要がなく、契約のやりとりを短時間で完結できるため、業務スピードと生産性が大幅に向上します。
さらに、コロナ禍を契機に非対面で安全に契約を結べる手段としても需要が高まりました。電子署名法の改正やクラウドサービスの進化により、セキュリティ面での信頼性も向上しています。
これらの社会的・技術的な変化を受け、電子契約は企業にとって欠かせないビジネスインフラとして注目されています。
【重要】電子契約の法的効力の根拠
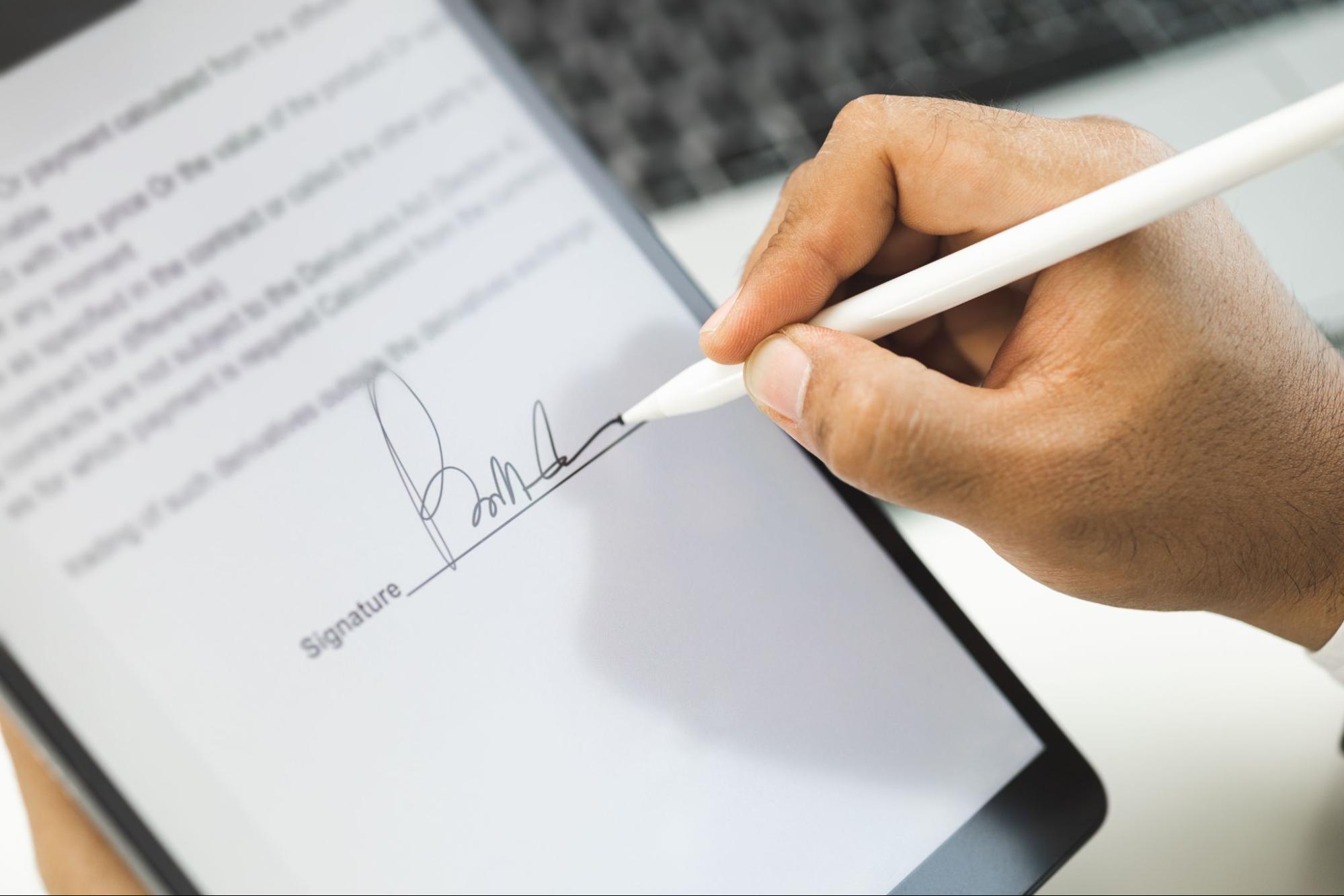
電子契約の法的効力を理解するためには、法律上どのように根拠づけられているかを知ることが重要です。
ここでは、これら3つの根拠をもとに、電子契約が法的に有効とされる理由を分かりやすく解説します。
電子署名法による効力の定義
電子契約の法的効力は、電子署名法によって明確に規定されています。
同法第2条で電子署名の定義を示し、第3条では「本人による電子署名が付された電磁的記録は、真正に成立したものと推定する」とされています。
この規定により、電子署名が付与された契約データは、署名や押印を伴う紙の契約書と同等の証拠力を有すると扱われます。
したがって、契約の存在や内容を争う場面でも、電子署名法に基づく証拠として強く認められる仕組みとなっています。
契約自由の原則と電子契約の位置づけ
民法第522条第2項では、「法令に特別の定めがある場合を除いて、契約の成立に書面や方式を要しない」と規定されています。
そのため、当事者は口頭でも書面でも自由に契約方式を選択でき、電子契約も同様に法的拘束力をもつ契約形態と位置づけられています。
つまり、法令で書面が必須とされる一部の契約を除き、電子署名を用いた契約データは有効に成立し、企業は業務効率やコスト面を考慮して最適な方法を採用可能です。
政府・省庁の公式見解
電子契約の法的有効性については、政府が複数の公的資料で明確に示しています。
総務省・法務省・経済産業省は2020年7月17日付で「利用者の指示に基づきサービス提供事業者自身の署名鍵により暗号化等を行う電子契約サービスに関するQ&A」を共同で発表し、クラウド型の電子契約サービスも条件を満たせば電子署名法に定める電子署名として扱われると明記しました。
この文書では、利用者の指示に基づきサービス提供事業者が署名を行う場合でも、本人確認と改ざん防止の仕組みが正しく機能していれば法的に問題ないと説明しています。
さらに、デジタル庁もその方針を引き継ぎ、2024年には運用基準を更新しました。これにより、電子契約が安心して利用できる環境が国の制度として整備されています。
電子契約の方式と特徴
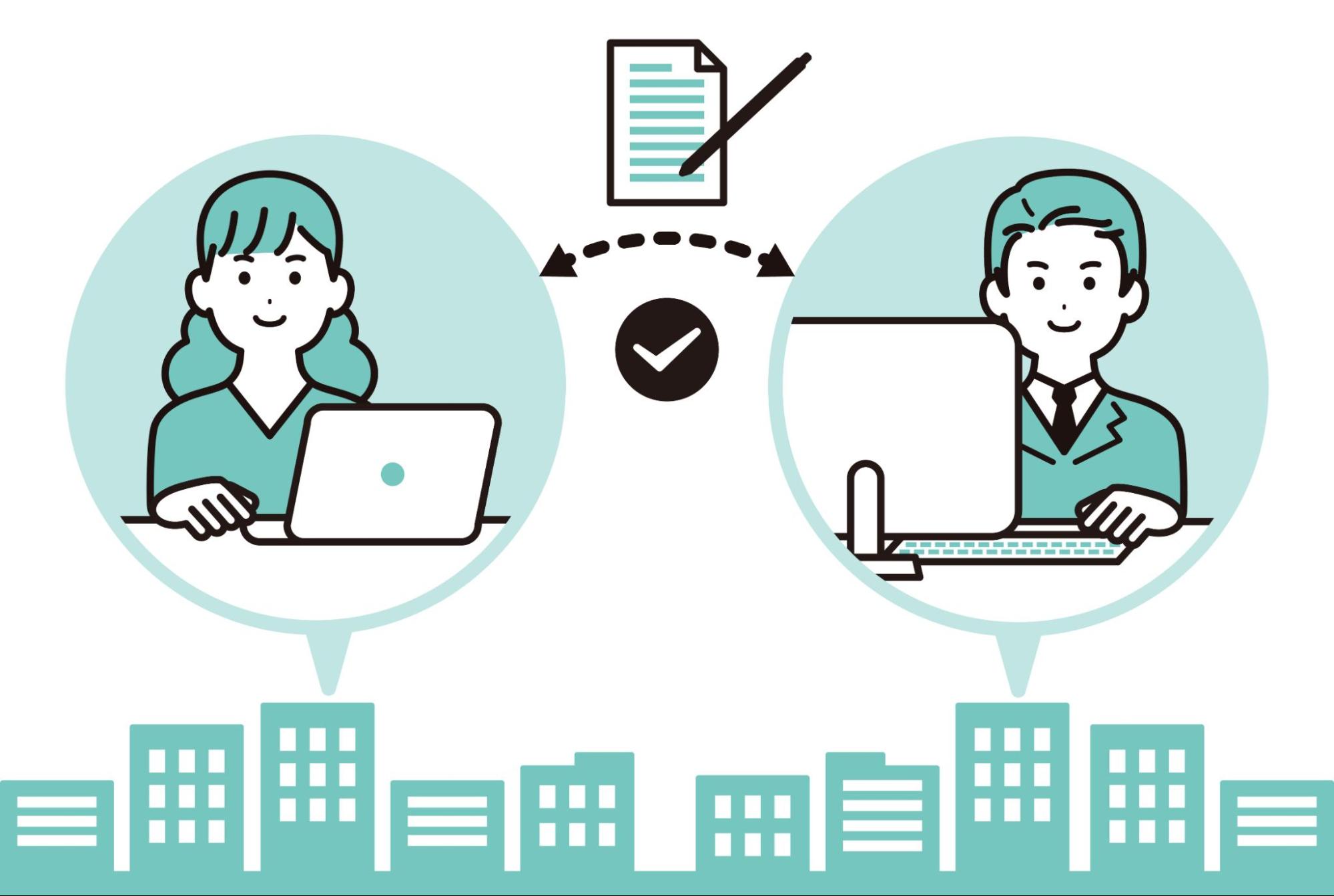
電子契約にはいくつかの方式があり、契約内容や目的によって使い分けることが大切です。ここでは、「当事者型」「立会人型」「簡易方式」それぞれの方式と特徴をわかりやすく整理して解説します。
当事者型
当事者型電子契約は、契約当事者が直接電子証明書を取得し、自ら電子署名を行う方式です。電子署名法第2条第1項の要件を満たすため、最も高い法的信頼性をもちます。
第三者機関による厳格な本人確認を経て電子証明書が発行され、本人性と改ざん防止が確実に担保されます。
主な特徴は以下の通りです。
- 電子証明書の事前取得が必要(手続きに数日から数週間を要する)
- 電子署名法第3条の推定効により高い証拠力を持つ
- 第三者機関による厳格な本人確認が行われる
- 暗号化技術により改ざんや偽造のリスクが極めて低い
確実性を重視する重要な契約において、当事者型は最適な選択肢といえるでしょう。
立会人型
立会人型電子契約は、第三者事業者が契約当事者に代わって電子署名を行う方式です。
2020年の政府見解により、一定の要件を満たす場合は電子署名法上の電子署名に該当することが明確化されました。利用者は電子証明書の取得が不要で、メール認証などによる本人確認のみで利用できます。
主な特徴は以下の通りです。
- 事前の電子証明書取得が不要で導入が簡単
- メール認証やSMS認証による本人確認を実施
- クラウドサービスとして提供され、操作が直感的
- 契約締結までの時間を大幅に短縮可能
業務効率と利便性を重視する企業にとって、立会人型は実用的な方式として広く採用されています。
簡易方式のリスク
簡易方式とは、電子署名を伴わない単純な電子サインのみで契約を締結する方式を指します。
手軽に利用できる反面、法的な証拠力が限定的で、紛争時に契約の有効性を証明できないリスクがあります。電子署名法の推定効が適用されないため、裁判などでは不利になる可能性が高くなります。
主なリスクは以下の通りです。
- 本人確認が不十分で成りすましの危険性がある
- 電子署名法第3条の推定効が適用されない
- 契約内容の改ざんを検出できない場合がある
- 紛争時に契約の存在や内容を立証しづらい
重要な契約においては、簡易方式ではなく電子署名法に準拠した当事者型や立会人型の採用を強く推奨します。
保存と管理のポイント

電子契約の契約書は紙の原本と異なり、電子データとして長期間保管し、必要に応じて内容をすぐに確認できる状態を維持しなければなりません。
ここでは、電子契約を安全かつ確実に管理するための保存要件や、実務で役立つ運用のポイントを解説します。
電子帳簿保存法と保存要件
電子契約を締結した場合、その契約データは電子帳簿保存法上「電子取引」として保存が義務づけられています。
同法は紙の書類を電子化して保存するための特例法であり、2024年1月からは電子データの保存が完全に義務化されました。
保存要件には、データが正しい形で保たれているかを示す「真実性の確保」と、必要なときに内容を確認できる「可視性の確保」の2つがあります。
例えば、タイムスタンプの付与や、訂正・削除履歴を残せるシステムを利用することが推奨されています。
契約書を電子で締結した場合、法人税法および会社法に準じて7年間(または事業年度+7年)の保存が必要となるため、法的要件を満たす環境での保管が求められます。
真正性・原本性をどう担保するか
電子契約を長期にわたり安全に保持するためには、データの「真正性」と「原本性」を確保する仕組みが欠かせません。
真正性とは、契約データが改ざんされていない状態を意味し、電子署名やタイムスタンプを付与することで信頼性を維持できます。
原本性は、紙の原本と同等の効力を示す概念で、署名情報や署名証明書が記録されていることが条件です。これらを満たすためには、改ざん防止機能を備えた電子契約システムの利用が不可欠です。
さらに、クラウド上のデータは定期的にバックアップを取り、アクセス権限を制限して管理することで、法的効力を損なわずに安全な運用が実現します。
実務での保管フロー例
電子契約の保管では、締結後のデータ管理と継続的な監視が欠かせません。
まず、電子署名・タイムスタンプを付与した契約データをシステムにアップロードし、以下のルールで保存・管理します。
- 保存期間:法人税法・電子帳簿保存法の基準により7年以上
- アクセス権限:担当者と管理責任者に限定
- 定期点検:半年〜1年に一度、表示・検索の可否を確認
- バックアップ:別サーバーまたはクラウドで二重保存
これらを遵守することで、法的要件をクリアしつつ、実務上の紛失や改ざんリスクを大きく軽減できます。
【注意】電子契約が使えないケース

電子契約は多くの場面で活用できますが、法令や業界ルールにより利用できないケースも存在します。ここでは、代表的な使えないケースを解説します。
書面交付義務がある取引
電子契約は幅広い分野で利用できますが、法令で「書面の交付」が義務づけられている取引では電子化が認められていません。
これは、消費者保護や契約トラブル防止のため、契約内容を紙で明確に交付する必要があるためです。代表的な取引例は以下の通りです。
- 特定商取引法に基づく取引(訪問販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引、特定継続的役務提供、訪問購入など)
- 労働契約に関する労働条件通知書や派遣就業条件明示書
- 宅地建物取引業法に基づく重要事項説明書や媒介契約書
- 下請法における発注書・受領書(いわゆる3条書面)
- 割賦販売法・貸金業法で定められる契約締結前交付書面
これらの書面は、交付内容を相手が直接確認し、理解したうえで契約判断を行えるようにする目的があります。
電子契約を導入する前に、該当する取引が書面交付義務の対象かを必ず確認し、法令違反を防ぐ運用を行いましょう。
不動産登記・遺言など要式行為
電子契約は多くの取引で認められていますが、法律によって特定の形式が求められる「要式行為」には対応できません。
要式行為とは、契約の有効性を確保するために、署名・押印や公証など特定の方式が義務づけられている行為を指します。代表的な例は以下の通りです。
- 不動産登記の申請
- 公正証書遺言の作成
- 事業用定期借地契約
- 任意後見契約書
これらは、当事者の意思確認や公的な立証が不可欠なため、現行法上は電子データでは法的効力を持ちません。
法改正によって将来的に電子化の範囲が拡大する見込みはありますが、現時点では紙の書面による手続きが必要な分野として扱われています。
業種や契約内容による制限
電子契約は多くの分野で認められていますが、業種や契約内容によっては法規制や業界ルール上の制限が残っています。
特に消費者保護や信頼性を重視する分野では、電子化の対象外とされる契約が存在します。代表的な例は以下の通りです。
- 金融や保険:一部は紙での契約が必須
- 医療・介護:書面による本人確認や説明義務が必要
- 建設・下請関連:電子化には相手方の承諾が必要
- 行政・公共分野:提出形式が限定されている
このように、電子契約の導入にあたっては、関係法令や監督官庁のガイドラインを確認することが不可欠です。
実務で安心して導入するために

電子契約を安全に導入するには、本人確認の精度確保、社内体制の整備、監査対応までを一貫して構築することが重要です。
ここでは、企業が安心して電子契約を導入・運用するための実務対応策を解説します。
本人確認・多要素認証の仕組み
電子契約の安全性を確保するために、本人確認と多要素認証の仕組みを適切に導入する必要があります。
本人確認が不十分だと、第三者によるなりすましや不正な契約締結のリスクが生じるため、信頼性の高い認証手段を採用しなければなりません。
代表的な方法として、メールアドレスとSMS認証を組み合わせた二要素認証や、電子証明書を用いた厳格な本人確認があります。
当事者型の電子契約では、認証局が発行する電子証明書を使い、立会人型では複数の認証手段を組み合わせることが一般的です。
社内規程・稟議との組み合わせ
電子契約を効果的に運用するには、社内規程の整備と稟議フローとの連携が不可欠です。
電子署名管理規程を策定し、契約締結権限者と手続きフローを明確化することで、無秩序な契約締結を防止できます。
また、電子契約システムに稟議機能を組み込むと、社内承認と契約締結を一元化でき、業務効率が飛躍的に向上します。
例えば、申請者が上長・法務部・決裁者の順に承認を得た後、自動的に相手方へ送信される設定にすれば、二重入力の手間がなくなり、締結までのスピードも短縮可能です。
監査・コンプライアンス対応例
電子契約システムには、誰がいつ何をしたかという操作履歴が自動的に記録されるため、監査やコンプライアンス対応において大きなメリットがあります。
紙の契約書では改ざんや日付の遡及のリスクがありますが、電子契約ならタイムスタンプや電子署名により、契約締結の正確な記録を技術的に保証できます。
さらに、契約データを一元管理できるため、監査時の証跡提出がスムーズになり、法令遵守の状況を明確に示すことが可能です。
企業の内部統制を強化するためには、契約プロセスの透明性を高め、不正行為を防ぐ仕組みを整えることが重要です。
【結論】まとめ
電子契約は電子署名法により、適切な電子署名が付与されていれば、紙の契約書と同等の法的効力を持つと認められています。
ただし、その効力を確実に担保するには、契約方式の選択や保存要件の遵守が不可欠です。
また、一部には電子契約が使えない取引も存在するため、導入前に自社の契約内容を確認することが重要です。
電子契約の仕組みを正しく理解し、安全で効率的な運用を行うと、企業の信頼性向上と業務効率化の双方を実現できます。
- ※本記事は、起業の窓口編集部が専門家の監修または独自調査(アンケート)に基づいて制作したものです。
- ※掲載している情報は、記事公開時点の法令・税制・商品・サービス等に基づくものであり、将来的に変更される可能性があります。
- ※アンケート調査に関する記述は、特定の調査対象者からの回答結果および編集部の見解を含んでおり、内容の正確性・完全性を保証するものではありません。
- ※記事の内容は一般的な情報提供を目的としており、すべての方に当てはまるものではありません。個人の状況に応じた具体的な助言が必要な場合は、専門家にご相談ください。
- ※情報の利用や判断、実施については、ご自身の責任で行っていただきますようお願いいたします。
- ※本記事に掲載された内容の転載・複製はご遠慮いただき、引用の際は必ず出典をご明記ください。



 シェア
シェア