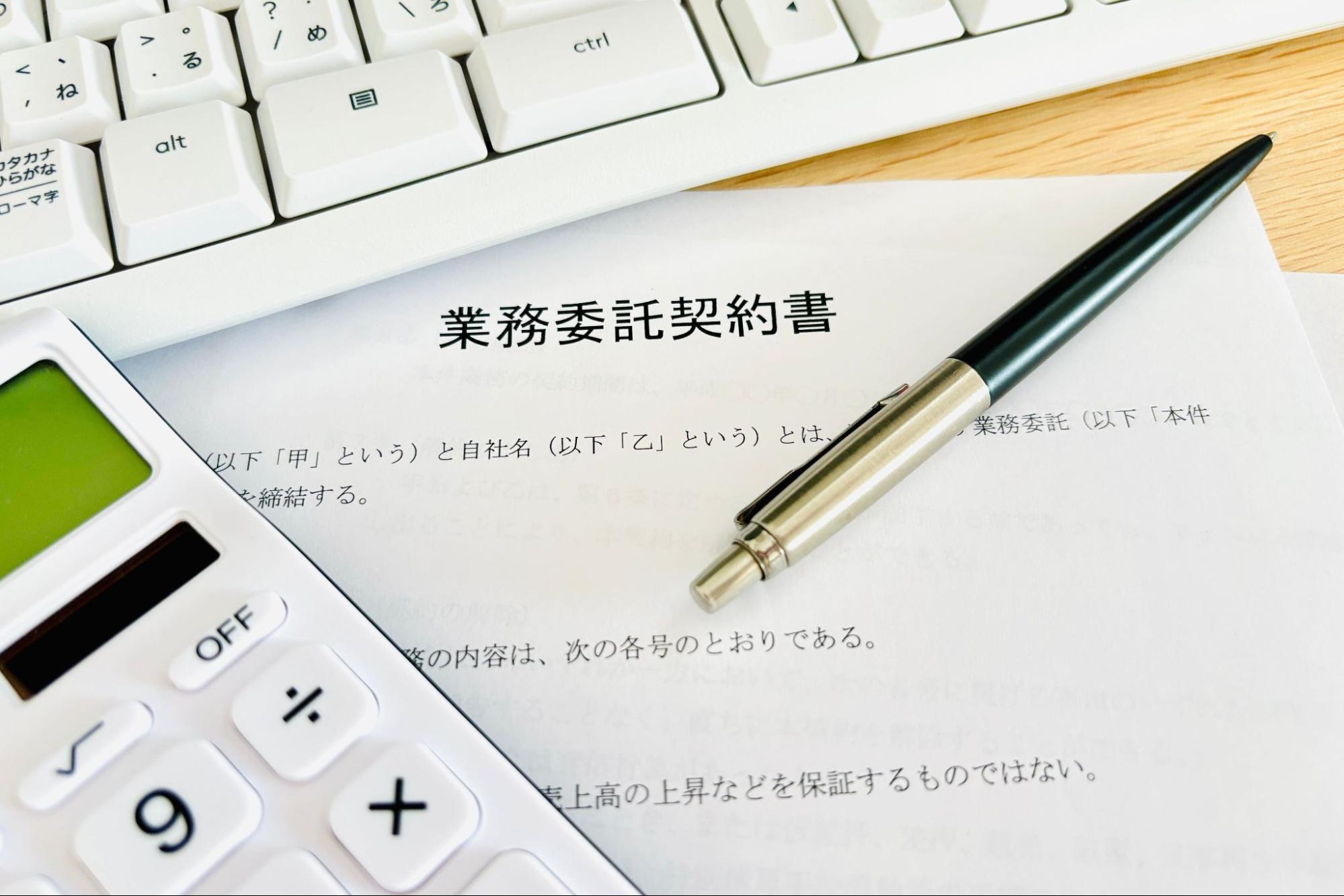フリーランスのための労災保険完全ガイド!令和6年11月から特別加入制度が適用拡大!

「フリーランスは、仕事中のケガでも補償が受けられないの?」という不安を感じたことはないでしょうか。
これまでの労災保険は、基本的に「雇われて働く人」が対象で、業務中に事故やケガをしても、フリーランスは補償を受けられないケースがほとんどでした。
しかし、2024年11月から労災保険の「特別加入制度」がフリーランスにも拡大されました。
これにより、企業から業務委託を受けて働くすべてのフリーランスが、業務中や通勤中の事故に備えられるようになります。
この記事では、労災保険の特別加入制度の内容や対象者、補償内容、加入方法、民間保険との違いなどをわかりやすく紹介します。
- 【この記事のまとめ】
- 22024年11月から、すべての業務委託型フリーランスが労災保険に特別加入できるようになり、業務中や通勤中の事故に備えられるようになります。
- 加入には特別加入団体を通じた申請が必要で、保険料は全額自己負担です。給付基礎日額に応じて補償額と保険料が変動します。
- 労災保険は業務災害に特化しており、業務外のリスクには民間保険の併用が有効です。補償内容の違いを把握し、重複や漏れを防ぎましょう。
2024年11月1日より、フリーランス保護法が施行されます。
組織に所属せずに働くフリーランスが安心して働ける環境を整備するために、フリーランスと企業などとの発注事業者間の取引の適正化(契約書等により取引条件を明示する)が主な目的です。
詳しくは次の記事をご覧ください。フリーランス保護法の概要、制定された背景や具体的な内容などを解説しています。
2024年11月からフリーランスも対象に。労災保険の特別加入制度とは?

2024年11月より、フリーランスも労災保険の特別加入制度の対象となりました。ここでは、特別加入制度の具体的な内容や背景について詳しく解説します。
労災保険とは
労災保険は、仕事中や通勤中に発生したケガや病気、さらには死亡に対して、治療費や休業補償、障害が残った場合の給付、遺族への補償など、幅広いサポートを提供する公的な保険制度です。
これまでフリーランスは対象外となることが多く、業務中のリスクに十分備えられない課題がありました。
しかし、働き方が多様化し、フリーランスとして活動する人が増加したため、より多くの働き手が安心して仕事に取り組めるよう、制度の見直しが進められました。
特別加入制度の概要
特別加入制度は、会社に雇用されていない自営業者やフリーランスなど、通常は労災保険の対象外となる人々が一定の条件を満たす場合に、労災保険へ任意で加入できる仕組みです。
2024年11月からは、従来一部の業種に限られていた特別加入の対象が大幅に拡大され、企業等から業務委託を受けて働く全業種のフリーランスも対象となりました。
これにより、フリーランスも業務中や通勤中の事故や病気に対して、労働者と同様の補償を受けられるようになります。保険料は給付基礎日額に基づき、原則0.3%の料率で計算され、全額自己負担です。
加入手続きは、特別加入団体を通じて行う必要があります。新制度の導入で、フリーランスの安全と安心が大きく向上することが期待されています。
フリーランスが対象となる背景
フリーランスが特別加入制度の対象となった背景には、働き方の多様化とフリーランス人口の増加が挙げられます。
これまでの労災保険制度は、伝統的な雇用関係を前提としていたため、企業と雇用契約を結ばないフリーランスは補償の対象外でした。
しかし、近年はITやクリエイティブ分野をはじめ、幅広い業種でフリーランスとして働く人が増え、業務中の事故や病気に対するセーフティネットの必要性が高まっています。
こうした社会的な要請を受け、2024年11月からは「フリーランス・事業者間取引適正化等法」に基づき、企業等から業務委託を受ける全てのフリーランスが特別加入できるよう法改正が行われました。
参考:フリーランスとして業務を行う方・フリーランスの方に業務を委託する事業者の方等へ
労災保険特別加入の給付内容

次に、労災保険特別加入制度で労災保険の加入者になった場合、どのようなケースで保険(補償)が給付されるのか解説します。
療養(補償)等給付
療養(補償)等給付は、仕事または通勤によるケガや病気により療養するケースです。
労災病院や労災指定病院などにおいて、必要な治療を無料で受けることが可能です。それ以外の医療機関で治療を受けた場合、治療に要した費用が支給されます。
休業(補償)等給付
休業(補償)等給付は、仕事または通勤によるケガや病気による療養のために労働をすることができず、それが原因で賃金を受けられないケースです。
休業4日目以降、休業1日につき給付基礎日額の60%(特別支給金20%と合わせて80%)が支給されます。
障害(補償)等給付
障害(補償)等給付は、障害(補償)等年金と障害(補償)等一時金の2種類があります。
障害(補償)等年金は、仕事または通勤によるケガや病気の状態が安定し、治療してもこれ以上改善しない状態(「治ゆ(症状固定)」と言います。)となり、障害等級第1級から第7級までに該当する障害が残ったケースです。1年あたり給付基礎日額の313日分(第1級)~131日分(第7級)が支給されます。
障害(補償)等一時金は、仕事または通勤によるケガや病気が治ゆ(症状固定)した後に、障害等級第8級から第14級までに該当する障害が残ったケースです。給付基礎日額503日分(第8級)~56日分(第14級)が支給されます。
傷病(補償)等年金
傷病(補償)等年金は、仕事または通勤によるケガや病気が療養開始後1年6ヵ月を経過した日または同日後に傷病が治癒(症状固定)していないこと、かつ、傷病による障害の程度が傷病等級に該当する場合に1年あたり給付基礎日額313日分(第1級)~245日分(第3級)が支給されます。
遺族(補償)等給付
遺族(補償)等給付は、遺族(補償)等年金と遺族(補償)等一時金の2種類です。
遺族(補償)等年金は、仕事もしくは通勤が原因で死亡したケースです。被災した特別加入者(労働者)の死亡当時にその収入によって生計を維持されていたといったような所定の要件を満たした配偶者等の遺族に支給されます。遺族の人数に応じ、1年あたり給付基礎日額の245日(4人以上)~153日(1人)分を支給します。
遺族(補償)等一時金は、①遺族(補償)等年金を受ける遺族がいない、②年金を受けている方が失権し、かつ、他に年金を受けられる者がない場合であり、既に支給された年金の合計額が給付基礎日額の1,000日分に満たないケースです。
①の場合は給付基礎日額の1,000日分、②の場合は1,000日分から既に支給した年金の合計額を引いた金額が支給されます。
葬祭料等(葬祭給付)
葬祭料等(葬祭給付)は、仕事または通勤が原因で死亡した方の葬祭を行うケースです。
31万5,000円に、給付基礎日額30日分を加えた金額または給付基礎日額60日分のうち、いずれか高いほうの金額が支給されます。
労災保険特別加入の保険料

フリーランスが労災保険に特別加入する場合、保険料の仕組みや支払い方法を理解しておくことが重要です。
ここでは、給付基礎日額の選び方や具体的な保険料の計算方法、支払いの流れについて詳しく解説します。
給付基礎日額の選択肢と保険料の計算方法
フリーランスが労災保険に特別加入する際、最初に決めるのが「給付基礎日額」です。これは自身の年間収入をもとに日割りで設定する金額で、3,500円から25,000円まで16段階から選択できます。
給付基礎日額は、休業補償や障害給付などの支給額の基準となり、選ぶ金額が高いほど保険料は上がりますが、補償内容も手厚くなります。
保険料の具体的な計算式は、以下の通りです。
- 保険料算定基礎額=給付基礎日額×365
- 年間保険料=保険料算定基礎額×1,000分の3
給付基礎日額の選択は毎年見直しが可能なため、収入や生活状況に合わせて柔軟に設定できます。
保険料の支払い方法とスケジュール
労災保険の特別加入における保険料の支払い方法は、加入団体によって異なりますが、主に振込・クレジットカード決済・コンビニ決済が選択できます。
振込は最も一般的で、銀行や郵便局から指定口座へ送金する方法です。支払い期限までに確実に納付する必要があり、振込手数料は基本的に自己負担となります。
保険料の納付スケジュールは、年度ごとの一括払いが基本です。年度は4月から翌年3月までで、途中加入の場合は加入月から3月までの月割り計算となります。
口座振替による年3回の分割払いが選択できる場合もありますが、初年度や途中加入時は一括払いとなるケースが多いです。
支払い方法やスケジュールは加入団体によって異なるため、詳細は必ず事前に確認してください。
特別加入制度の対象となるフリーランスの条件

2024年11月から、労災保険特別加入制度の対象となるフリーランスの範囲が大きく広がりました。ここでは、対象となる具体的な業種や働き方、そして加入条件について解説します。
対象となる業種や働き方の具体例
労災保険特別加入制度の対象となるフリーランスの範囲の大幅な拡大により、従来は一部の職種に限られていた特別加入が、企業等から業務委託を受けて働くすべてのフリーランスに認められています。
例えば、以下のような分野のフリーランスが対象です。
- ITエンジニア
- デザイナー
- カメラマン
- コンサルタント
- ライター
- 翻訳者
- インストラクター
- 研究者
BtoBの業務委託だけでなく、同種の業務を消費者から受託している場合も含まれます。
ただし、消費者からのみ業務を受託する場合や、企業から委託された業務と異なる内容の仕事を消費者から受けている場合は対象外です。
従業員の有無による影響
特別加入制度を利用する際、従業員の有無は大きなポイントになります。従業員を雇用していないフリーランスや一人親方は、自身の判断で特別加入できます。
一方で、従業員を雇用している場合は「中小事業主」としての条件を満たす必要があります。業種ごとに雇用できる従業員数の上限が定められており、これを超えると特別加入の対象外となります。
具体的な上限は以下の通りです。
| 業種 | 雇用できる従業員数の上限 |
|---|---|
| 金融業・保険業・不動産業・小売業 | 50人以下 |
| 卸売業・サービス業 | 100人以下 |
| 上記以外の業種 | 300人以下 |
また、従業員を常時雇用している場合は、その従業員も労災保険へ加入させる義務があります。
従業員の雇用形態や人数によって、特別加入の可否や手続きが変わるため、自身の働き方と照らし合わせて確認しましょう。
労災保険に特別加入する方法

フリーランスの労災保険に特別加入する方法には、決まった手続きが存在します。ここでは、特別加入団体の選び方や申請の流れ、注意点について解説します。
特別加入団体を通じた申請手続き
フリーランスが労災保険に特別加入するには、必ず「特別加入団体」を通じて申請する必要があり、個人で直接労働基準監督署に申し込むことはできません。
特別加入団体には、すでに都道府県労働局長の承認を受けている団体を利用する方法と、新たに団体を立ち上げて申請する方法がありますが、既存の団体を選ぶ方法が一般的です。
団体はフリーランスを「労働者」とみなし、団体自体が「事業主」として申請を代行します。
加入希望者は、自身の業種や職種に合った団体を選び、団体の案内に従って必要書類を準備し、加入手続きを進めます。
団体ごとに申請方法や必要書類が異なる場合があるため、事前に詳細を確認し、スムーズな手続きを心がけましょう。
必要書類と申請の流れ
特別加入の申請には、事前に必要書類を揃え、正しい流れで手続きを進めることが重要です。主な必要書類は以下の通りです。
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 収入証明書
- 業務内容を証明する書類
- 業務委託契約書の写し(必要な場合)
- 特別加入申請書
- 誓約書
- 預金口座振替依頼書
- 住所や事業所所在地の証明書類(公共料金領収書、銀行の残高証明書など)
申請の流れは次の通りです。
- 特別加入団体を選び、問い合わせを行う
- 必要書類を入手し、記入・準備する
- 特別加入団体へ書類を提出する
- 保険料を納付する
- 団体が内容を審査し、労働局へ申請
- 承認後、特別加入者証が発行される
事前の準備と正確な手続きがスムーズな加入のポイントです。
加入時の注意点とよくあるミス
労災保険の特別加入時には、いくつかの注意点とよくあるミスがあります。まず、特別加入は任意であり、自分で手続きをしなければ補償は始まりません。
補償開始は申請翌日以降となるため、事故発生後の遡及加入は認められません。申請時には下記の点に注意しましょう。
- 保険料や諸費用は全額自己負担となる
- 一部の業務では健康診断の受診が必要
- 保証対象は「業務災害」「通勤災害」に限定される
よくあるミスは次の通りです。
- 必要書類の不備や記入漏れ
- 本人確認書類や証明書類の有効期限切れ
- 業務内容や収入証明の不足
- 自身の業務が団体の対象外であることに気付かず申請
事前にチェックや準備を行い、トラブルを防止しましょう。
他の保険制度との比較と併用のポイント

他の保険制度には、健康保険や民間の保険、所得補償保険、賠償責任保険などがあり、それぞれ補償範囲や役割が異なります。
ここでは、公的労災保険とその他の保険制度の違いや、併用する際のポイントについて解説します。
労災保険と健康保険の違いは?
労災働保険と健康保険は、補償範囲や給付内容、自己負担の有無などに明確な違いがあります。
労災保険は業務災害や通勤災害に対して手厚い補償を行い、治療費は全額補償される一方、健康保険は業務外の病気やケガを対象とし、医療費の一部が自己負担となります。
業務中や通勤中の事故は必ず労災保険を優先して利用しましょう。
民間の保険との違い
フリーランスが加入できる労災保険には、公的な労災保険特別加入と民間の保険(上乗せ保険や傷害保険)があります。
両者には補償内容や保険料、適用範囲に大きな違いがあります。主な違いは以下の通りです。
| 比較項目 | 公的労災保険(特別加入) | 民間の労災保険・傷害保険 |
|---|---|---|
| 補償範囲 | 勤務中・通勤中のみ | 日常生活も含め幅広く設計できる |
| 補償金額 | 治療費全額補償、休業補償も高め | 掛け金に応じた保険金、上限あり |
| 保険料 | 比較的安い | 高額になる場合が多い |
| 補償期間 | 治癒まで全額補償 | 通院・入院に数などに上限あり |
| 柔軟性 | プランは限定的 | 補償内容を自由に設計できる |
公的労災保険は、業務中や通勤中の事故・病気に対して、比較的安価な保険料で手厚い補償を受けられます。
一方、民間の保険は保険料が高くなる傾向があるものの、日常生活や業務外のリスクもカバーでき、補償内容を柔軟に設計できる点が特徴です。
所得補償保険や賠償責任保険との違いと併用法
所得補償保険や賠償責任保険は、労災保険と補償範囲や目的が異なります。
労災保険は業務中や通勤中の事故・病気に限定されますが、所得補償保険は病気やケガで働けなくなった際の収入減を幅広く補償します。
賠償責任保険は、業務上の過失による損害賠償リスクに備えるものです。
| 保険の種類 | 主な補償範囲・特徴 |
|---|---|
| 労災保険 | 業務中・通勤中のケガや病気、死亡を補償 |
| 所得補償保険 | 病気やケガで働けなくなった場合の収入減を補償(業務外も対象) |
| 賠償責任保険 | 業務上の過失による損害賠償責任を補償 |
労災保険、所得補償保険、賠償責任保険は併用が可能です。
例えば、労災保険で業務中の事故に備えつつ、所得補償保険で私生活や業務外のリスクもカバーできます。また、賠償責任保険を加えることで、万が一の損害賠償請求にも対応できます。
ただし、補償内容が重複する場合もあるため、加入時には各保険の内容や免責期間、保険金額をよく確認し、バランスよく組み合わせましょう。
フリーランス向け保険選びで失敗しないためのチェックポイント

フリーランスが保険選びで失敗しないためには、補償範囲や支払い条件などを事前にしっかり確認することが重要です。
ここでは、フリーランスが安心して働くために押さえておきたい保険選びのチェックポイントを解説します。
補償対象の確認(業務中/業務外の線引き)
フリーランスが保険を選ぶ際、まず確認すべきは補償対象の範囲です。
労災保険特別加入は業務中や通勤中の事故・病気のみが対象で、例えばクライアント先での作業中や移動中の事故は補償されますが、プライベートでのケガは対象外です。
一方、民間保険は業務外の事故や日常生活のリスクもカバーできる場合があります。
| 労災保険の種類 | 補償対象範囲の例 |
|---|---|
| 労災保険特別加入 | ・クライアント先での作業中 ・打ち合わせ帰りの事故 ・業務関連の移動中 など |
| 民間保険 | ・自宅作業中の転倒 ・プライベート旅行中のケガ ・業務外の病気 など |
業務の線引きが曖昧なケース(自宅作業中の事故など)は、労災認定のハードルが高いため、民間保険との併用が効果的です。
契約前には「業務の定義」を明文化した規約を確認し、補償の隙間を埋める設計が必要です。
支払い条件・免責の有無
保険選びで見落としがちなのが「支払い条件」と「免責事項」です。労災保険特別加入の場合、保険料は給付基礎日額×365×0.3%で算出され、全額自己負担です。
一方、民間保険では「免責期間(最初の30日は補償対象外)」や「既往症の除外」など、条件が細かく設定される傾向にあります。
主なチェックポイントは以下の通りです。
- 支払い条件:保険金の支払い基準(日額制/一時金制)
- 免責事項:危険な作業中の事故/飲酒運転関連のケガ/自然災害時の損害
- 更新条件:年齢制限/健康状態の告知義務
特に、フリーランス向けの賠償責任保険では「過失割合による減額」が適用される場合があるため、免責条項の有無を必ず確認しましょう。
労災保険特別加入に関するよくある質問

労災保険特別加入については、申請方法や補償内容、手続きの流れなど多くの疑問が寄せられます。ここでは、よくある質問とそのポイントを分かりやすく解説します。
加入対象となるか不安な場合の相談先は?
労災保険特別加入の対象になるか不安な場合は、専門機関へ相談すると安心して手続きを進められます。主な相談先は以下の通りです。
| 相談先 | 内容・特徴 |
|---|---|
| 特別加入団体 | 連合フリーランス労働保険センターやみんなの労働保険組合など、全国対応の団体で制度や手続きの相談が可能 |
| 労働保険事務組合 | 経営管理協会や商工会議所など、事務委託を通じて中小事業主や個人事業主も相談・申請可能 |
| 労働基準監督署・労働局 | 最寄りの監督署や労働局で、制度の詳細や自身が対象となるか直接確認できる |
| 厚生労働省の公式相談窓口 | 労働保険相談ダイヤル(0570−006031)で一般的な質問や制度全体の案内を受けられる |
これらの窓口では、事業内容や働き方に基づく加入可否や手続き方法を丁寧に案内しています。不明点があれば早めに相談し、スムーズな加入を目指しましょう。
加入後に内容変更はできる?
労災保険特別加入後も、内容の変更は可能です。
例えば、給付基礎日額の変更や、住所・氏名・業務内容の修正などは、年度更新時や必要に応じて「特別加入に関する変更届」を提出することで対応できます。
ただし、給付基礎日額の変更は原則として保険年度(4月~翌年3月)の切り替え時のみ可能で、年度途中の変更はできません。
また、管轄地域を超えた住所変更の場合は、一度脱退し再加入が必要なケースもあります。
変更手続きは、加入している特別加入団体のマイページや窓口から申請できるため、内容に変更が生じた場合は速やかに手続きを行いましょう。
安心・安全に働くために、労災保険の特別加入を検討しよう
2024年11月から、フリーランスも労災保険の特別加入が可能になり、仕事中や通勤中のケガや病気、死亡時に幅広い補償を受けられます。業務中の事故や病気によるリスクから保護され、安心して仕事に専念できる環境を整えることができるでしょう。
「起業の窓口」では、フリーランスの方々に向けて、業務効率化のヒントや成功事例、最新のビジネス情報など、お役立ち情報を提供しています。
ぜひ、「フリーランス」に関する他の記事もご覧ください。
起業や開業、独立に興味を持ったら、まずは「起業の窓口」に登録してみよう!
「起業の窓口」では、起業に必要なノウハウや成功者のインタビューなど、さまざまなコンテンツを完全無料で提供しています。
会員特典として、起業・経営支援のプロ「V-Spirits」が監修するオリジナル冊子『会社設立完全ガイド』を無料プレゼント。さらに、V-Spritsによる1時間の無料起業相談や、GMOインターネットグループが展開するビジネスの立ち上げや拡大に役立つ各種サービスをおトクな特典付きでご紹介します。
あなたの夢の実現を全力でサポートします!
- 記事監修
-
- 中野 裕哲 HIROAKI NAKANO
- 起業コンサルタント(R)、経営コンサルタント、税理士、特定社会保険労務士、行政書士、サーティファイドファイナンシャルプランナー・CFP(R)、1 級FP 技能士。 V-Spiritsグループ創業者。東京池袋を本拠に全国の起業家・経営者さんを応援!「あの起業本」の著者。著書16冊、累計20万部超。経済産業 省後援「DREAMGATE」で11年連続相談件数日本一。
- ※本記事は、起業の窓口編集部が専門家の監修または独自調査(アンケート)に基づいて制作したものです。
- ※掲載している情報は、記事公開時点の法令・税制・商品・サービス等に基づくものであり、将来的に変更される可能性があります。
- ※アンケート調査に関する記述は、特定の調査対象者からの回答結果および編集部の見解を含んでおり、内容の正確性・完全性を保証するものではありません。
- ※記事の内容は一般的な情報提供を目的としており、すべての方に当てはまるものではありません。個人の状況に応じた具体的な助言が必要な場合は、専門家にご相談ください。
- ※情報の利用や判断、実施については、ご自身の責任で行っていただきますようお願いいたします。
- ※本記事に掲載された内容の転載・複製はご遠慮いただき、引用の際は必ず出典をご明記ください。



 シェア
シェア