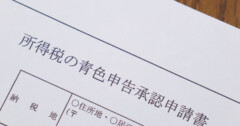法人の印鑑証明書の取得方法をわかりやすく解説!料金や必要書類、注意点
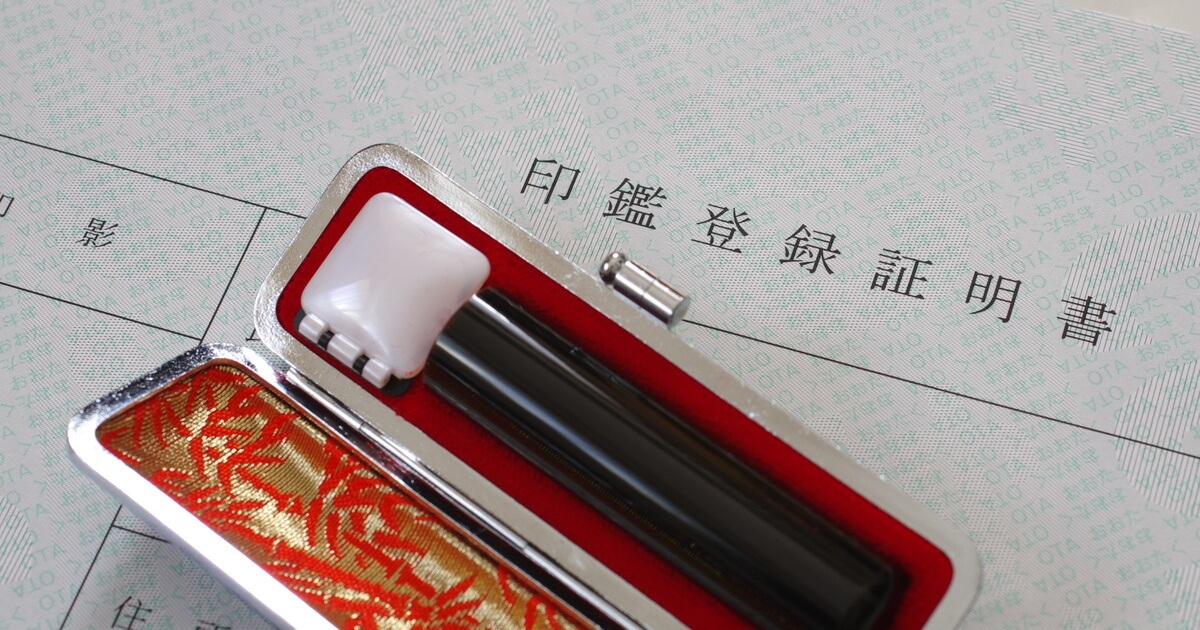
「法人の印鑑証明書はどうやって取得するの?」という疑問がある方もいるでしょう。
法人の印鑑証明とは、登録された法人の実印(代表者印)が正式なものであると証明することです。
印鑑証明書は金融機関での口座開設や重要な契約締結など、さまざまな場面で必要となる重要書類であり、印鑑カードがあれば窓口や証明書発行請求機で即日取得できます。
ただし、印鑑証明書の登録には、実印のサイズに制約があるほか、取得は印鑑カードがなければ代表者本人でも取得できないなど、事前に把握しておくべき注意点があります。
本記事では、法人の印鑑証明書の取得方法、取得に必要な印鑑カードの管理方法、手数料や受付時間などの実務的な情報について解説します。
- 【この記事のまとめ】
- 印鑑証明書の取得には、一般的に500円の手数料が必要です。料金は、窓口や郵送、オンライン申請など、取得方法によって異なります。
- 印鑑証明書は、法人の信頼性を証明する重要な書類で、不動産取引や契約時など、さまざまな場面で必要とされます。
- 印鑑証明書を取得するためには、法務局で印鑑登録を行う必要があります。
- 印鑑証明書の取得方法は、法務局の窓口、オンライン、郵送の3つです。用途や状況に応じて最適な方法を選択しましょう。
法人の印鑑証明とは?

法人の印鑑証明とは、登録された法人の実印(代表者印)が正式なものであると証明することです。
法人設立時に法務局へ代表者印を登録すると、その印鑑が会社の正式な実印として認められ、必要に応じて印鑑証明書を発行できます。
印鑑証明書は、金融機関での法人口座開設、不動産売買契約、融資申込み、重要な取引契約の締結など、さまざまな場面で提出が求められます。
- ▼印鑑証明書に記載されているもの
-
- 登録された印鑑の印影
- 会社の商号
- 本店所在地
- 代表者の氏名と生年月日など
取引先が、印鑑証明書の有効期限を「発行から○ヶ月以内」と定めているケースが多いため、使用目的に応じて取得時期を慎重に調整しましょう。
古い証明書は提出先によっては効力を失うため、重要な契約の際は必ず新しいものを準備する必要があります。
印鑑カードとは?
印鑑カードとは、法人の印鑑証明書を取得する際に必要となる、法務局が発行する特別なカードのことです。
法人は、法人設立後に代表者印の登録と同時に印鑑カード交付申請書を法務局に提出することで、印鑑カードを取得できます。
このカードがなければ、たとえ代表者本人であっても印鑑証明書の発行は受けられないため、金庫などで厳重に管理しましょう。
印鑑カードを紛失した場合は、速やかに廃止届を提出する必要があります。廃止届には印鑑カード交付申請書(再交付用)や法務局に届け出ていた代表印などが必要です。手続きは、代表者本人または廃止届や申請書の委任状欄に記載された代理人が法務局の窓口で行います。
代表者が交代した場合でも印鑑カードをそのまま引き継ぐことは可能です。しかし、セキュリティの観点から新しいカードへの切り替えを検討することをおすすめします。
印鑑証明書の料金はいくら?

法人の印鑑証明書を取得する際には、料金が発生します。この料金は全国一律です。
一般的にかかる手数料は、以下の通りです。
| 申請方法 | 手数料 | 窓口申請・窓口受取 | 500円 |
|---|---|
| 郵送申請・郵送受取 | 500円 |
| オンライン申請・窓口受取 | 420円 |
| オンライン申請・郵送受取 | 450円 |
※郵送申請、郵送受取の場合、郵送用と返送用の切手代が別途必要です。
※参考:法務省|登記手数料について
法人の印鑑証明書はどんなときに必要?

法人の印鑑証明書は、企業経営において多岐にわたる場面で必要とされます。
たとえば、不動産の購入や売却、銀行融資の申し込み、大きな取引の契約締結時など、法人としての正式な意思表示が必要な場面で提出が求められます。
法人の信頼性を高め、公的な取引においても正確性を保証するために、印鑑証明書は不可欠な書類です。
【結論】印鑑証明書を取得するには印鑑登録が必要

印鑑証明書を取得するには、まず印鑑登録が必要です。印鑑登録とは、法人が使用する印鑑を法務局に届け出て、公式に認められた印鑑として登録することを意味します。この登録を行うことで初めて、印鑑証明書の発行が可能になるのです。
印鑑登録をするには、法務局にて以下の4つのステップで申請を行います。
| ステップ1.印鑑届書の提出 |
|
|---|---|
| ステップ2.印鑑カードの交付申請 |
|
| ステップ3.印鑑カードの受け取り | – |
| ステップ4.印鑑証明書の取得 |
|
委任状に代表者の実印を押印してあれば、代理人の申請でも登録可能です。ただし、法務局に登録する印鑑は、「1cm以上、3cm以内」の正方形に収めなければいけない規定があります。この範囲に収まっていないと実印としての登録ができないため、注意しましょう。
印鑑カードは会社設立時に必須ではありませんが、印鑑証明書の取得には必要です。そのため、印鑑登録と同時に交付申請書を記入して取得しておくと便利です。なお、印鑑カードの交付申請は郵送でもできます。
【重要】印鑑証明書の取得方法

ここでは、印鑑証明書の取得方法について解説します。
法務局の窓口
法人の印鑑証明書は、法務局の窓口で取得できます。
法務局の窓口では、印鑑登録後、法人代表者自身が手数料を支払い、印鑑証明書を受け取ることが一般的です。
窓口での手続きは、直接質問ができ、不明点をその場で解決できるため、安心して手続きを進められます。法務局の場所と営業時間を事前に確認しておきましょう。
一般的には、以下の時間であれば対応してもらえます。
| 窓口取扱時間 | 月~金 午前8時30分~午後5時 |
|---|
※令和6年1月4日から働き方改革推進により窓口対応時間が変更されています
窓口で印鑑証明書を受け取る際に必要なものと、受け取りにかかる日数は以下の通りです。
| 受け取りに必要なもの |
|
|---|---|
| 受け取りにかかる日数 | 最短即時 |
法人登記やその手続きの流れについて、下記の記事で詳しく解説しています。
法務局の証明書発行請求機
法務局に設置されている証明書発行請求機を利用すると、窓口での待ち時間を避けて効率的に印鑑証明書を取得できます。
証明書発行請求機の基本的な操作方法は以下の通りです。
- ▼証明書発行請求機の操作方法
-
- 印鑑カードを証明書発行請求機に挿入する
- タッチパネル画面の案内に従って必要事項を入力する
- 整理券を発行する
- 窓口で収入印紙を購入して提出する
証明書発行請求機は、窓口の受付時間内で利用でき、手数料は1通500円です。発行までの所要時間は数分程度と短く、急ぎで証明書が必要な場合に便利です。
ただし、機械の故障や定期メンテナンスで使用できない場合もあるため、余裕を持って取得することをおすすめします。
また、印鑑証明書を受け取る際には印鑑カードが必要になるため、忘れずに持参しましょう。
オンライン
近年では、オンラインを利用して印鑑証明書を取得する方法も増えています。
オンラインでの取得は、法人代表者が直接窓口に行かなくても、インターネットを通じて申請から支払い、証明書の受け取りまでができるため、時間や場所を選ばずに手続きを行えます。
しかし、この方法を利用するには、事前に法務省が提供するシステムにアクセスし、必要な準備を行う必要があります。また、オンラインでの手続きが可能な自治体かどうかも確認が必要です。
一般的には、以下の手順で受け取ります。
- 申請用総合ソフトをダウンロードし、申請書を作成する
- インターネットバンキングにて手数料を支払う
- 郵送または法務局の窓口で印鑑証明を受け取る
また、受け取りに必要なものと日数については、それぞれ以下の通りです。
| 受け取りに必要なもの |
|
|---|---|
| 受け取りにかかる日数 | 1-3営業日
※事前に法人の電子証明書を取得しておく必要があります。 |
郵送
また、印鑑証明の取得方法として郵送を利用することもできます。
郵送での申請は、必要な書類を郵送し、証明書を自宅や事務所に直接送ってもらう方法です。この場合、事前に必要書類の準備と、手数料を郵便局などで購入した収入印紙で支払う必要があります。
時間的な余裕を持って申請することで、直接窓口に行くことなく手続きを完了させることが可能です。
一般的には、以下の手順で受け取ります。
- 法務省のホームページから印鑑証明書交付申請書をダウンロード、印刷・記入する
- 500円の収入印紙、印鑑カードと、切手を貼りつけた返信用封筒を同封し郵送する
- 印鑑カードと印鑑証明書が返送される
郵送で印鑑証明書を受け取る際に必要なものと、受け取りにかかる日数は以下の通りです。
| 受け取りに必要なもの |
|
|---|---|
| 受け取りにかかる日数 | 3-5営業日 |
【注意】法人が印鑑証明書を取得する際に確認すべきこと

法人の印鑑証明書を取得する際は、実印の規格や必要な書類など、事前に確認すべき重要なポイントがいくつかあります。
以下の注意点を把握することで、トラブルなくスムーズに手続きを進められます。
実印には大きさの制約がある
法人の実印として登録できる印鑑には、一辺が1cm以上3cm以内の正方形に収まるサイズという明確な規定があります。
この範囲を超える印鑑は登録申請の段階で拒否されるため、印鑑作成時には十分な注意が必要です。
一般的に、法人実印は直径1.8cm〜2.1cmの丸印が多く、外側に会社名、内側に代表取締役印などの肩書きが二重の円で彫刻されています。
材質については特に制限はありませんが、ゴム印やシャチハタなど変形しやすいものは認められていません。
- ▼法人実印の素材として人気があるもの
- チタン
- 黒水牛
- オランダ水牛
- 薩摩本柘
- 彩樺
長年の使用により印影が不鮮明になったり、印面が欠けたりした場合は、速やかに改印手続きを行い、新しい実印を登録し直す必要があります。
改印の際は、古い印鑑の廃止届と新しい印鑑の登録申請を同時に行います。手続き期間中は印鑑証明書を取得できないため注意が必要です。
印鑑証明書の発行には印鑑カードが必要
印鑑証明書を取得するためには、必ず印鑑カードの提示が求められます。このカードなしでは発行手続きを進められません。
たとえ代表者本人が運転免許証などの本人確認書類を持参して窓口に出向いても、印鑑カードがなければ証明書の発行は受けられません。
従業員や司法書士などの代理人に取得を依頼する場合も、必ず印鑑カードを預ける必要があります。
万が一印鑑カードを紛失した場合は、第三者による悪用を防ぐため直ちに法務局へ連絡し、カードの廃止手続きを行いましょう。
印鑑カードの管理責任者を明確にし、使用記録を残すなど、組織的な管理体制を構築することが重要です。
印鑑証明書の申請には手数料がかかる
法人の印鑑証明書を取得する際は、1通につき420円〜500円の手数料がかかります。
この手数料は、窓口・郵送申請、オンライン申請(郵送・窓口)など、取得方法によって異なります。
| 申請方法 | 手数料(改定前の料金※) |
|---|---|
| 窓口・郵送申請 | 500円(450円) |
| オンライン申請(郵送受け取り) | 450円(410円) |
| オンライン申請(窓口受け取り) | 420円(390円) |
※2025年4月1日から印鑑証明書の発行手数料が変更
複数枚必要な場合は枚数分の手数料がかかります。たとえば、窓口で5通取得する場合は、「500円 × 5通」で合計2,500円の支払いとなります。
支払い方法は取得場所により異なり、窓口や証明書発行請求機では現金払いが基本です。
オンライン申請の場合は、インターネットバンキングやペイジーでの電子納付が利用できます。
法人の印鑑証明書に関するよくある質問

印鑑証明書の取得に関して、多くの方が気になる疑問や不安について詳しく解説します。
印鑑カードを紛失した際はどうする?
印鑑カードを紛失した場合は直ちに管轄の法務局へ連絡し、その後速やかに廃止届を提出する必要があります。
廃止届には会社の登記簿謄本や代表者の印鑑、本人確認書類などが必要です。
手続きは、代表者本人または委任状を持った代理人が法務局の窓口で行います。廃止処理の完了までにかかる時間は約30分程度です。
廃止手続きと同時に新しい印鑑カードの交付申請を行えば、その日のうちに新しいカードを受け取れます。
紛失に気付いた時点で既に第三者に悪用されている可能性もあるため、取引先への連絡や銀行口座の確認など、被害の有無を速やかにチェックすることが重要です。
印鑑証明書の取得には何日かかる?
印鑑証明書は即日発行が原則であり、法務局の窓口や証明書発行請求機を利用すれば、申請から数分程度で受け取れます。
混雑時でも、30分程度で取得できるのが一般的です。
オンライン申請の場合は、申請データの送信後、窓口受取なら1〜3営業日、郵送受取なら3〜5営業日程度で手元に届きます。
年度末や月末などの繁忙期は窓口が混雑し、通常より時間がかかる場合があるため注意が必要です。
急ぎで必要な場合は、朝一番や昼休み明けなど比較的空いている時間帯を狙うか、証明書発行請求機の利用をおすすめします。
印鑑証明書の取得は社長しかできない?
印鑑証明書は、代表者(社長)本人でなくても、印鑑カードを持参すれば誰でも申請して受け取れます。
従業員、秘書、司法書士など、委任状なしで代理人が取得できる点が大きな特徴です。
これは、印鑑カード自体が本人確認の役割を果たしているためです。印鑑カードさえあれば、手続きが完了します。
印鑑カードは会社の重要な財産であるため、信頼できる担当者のみに預けることが大切です。
代理人に依頼する際は、必要枚数と使用目的を明確に伝え、受け取った証明書の枚数を必ず確認してもらいましょう。カードの受け渡しは手渡しを原則とし、郵送は紛失リスクが高いため避けるべきです。
印鑑証明書を請求する際に使う印鑑は?
印鑑証明書の請求時には、印鑑の押印は必要ありません。印鑑カードの提示のみで手続きが完了します。
法務局の窓口で申請書を記入する際や、証明書発行請求機を操作する際も、印鑑を使用する場面はありません。
実印はあくまで契約書などの重要書類に押印するためのものであり、証明書取得の際には持参する必要はありません。
ただし、印鑑を届け出た代表者の生年月日の記入(証明書発行請求機の場合は入力)が必要となります。代理人が取得する場合はあらかじめ確認しておきましょう。
ただし、特別な申請を行う場合は実印の押印が求められることがあります。印鑑カードの再発行や改印手続きなど、特別な申請を行う場合は、実印の押印が求められることがあります。
通常の印鑑証明書取得であれば、印鑑カードと手数料のみ準備すれば問題ありません。
印鑑証明書を請求する際の受付時間は?
法務局の窓口受付時間は、平日の午前8時半〜午後5時までとなっており、土日祝日および年末年始は休業です。
証明書発行請求機も同じ時間帯での利用となりますが、昼休み時間(12時〜13時頃)も稼働しているため便利です。
ただし、月末や年度末は特に混雑するため、16時以降の来局は避けた方がよいでしょう。
法人の印鑑証明書はコンビニで取得できる?
個人の印鑑証明書とは異なり、法人の印鑑証明書はコンビニでは取得できません。法務局の窓口、証明書発行請求機、郵送、オンライン申請でのみ取得可能です。
法人の印鑑証明書は法務局が管理・発行している一方、個人の印鑑証明書は住民票がある市区町村が管理・発行しており、根本的にシステムが異なります。
個人の印鑑証明書はマイナンバーカードを利用したコンビニ交付サービスが普及していますが、法人の証明書はこのサービスに対応していません。
デジタル化の推進により、将来的には法人の証明書もコンビニで取得できるようになる可能性はありますが、現時点では実現の見通しは立っていません。
急ぎで必要な場合は、最寄りの法務局の証明書発行請求機を利用するか、オンライン申請で事前に手続きを済ませておくことをおすすめします。
印鑑証明書の取得をスムーズに進める方法は?
印鑑証明書の取得を効率化するには、オンライン申請システムの活用が最も効果的な方法です。
事前に「申請用総合ソフト」をパソコンにインストールし、必要事項を登録しておけば、2回目以降は簡単に申請できます。
証明書発行請求機を利用する場合は、混雑を避けるため、午前中の早い時間帯や14時〜15時頃に利用することをおすすめします。
定期的に必要となる企業は年間スケジュールを立てて計画的に取得し、常に数通ストックしておくとよいでしょう。
法人の印鑑証明にGMOオフィスサポートの印鑑セット
法人の印鑑証明書は、企業活動を行う上で欠かせない重要な書類です。印鑑証明の料金や取得方法、必要性について理解することで、スムーズに手続きを進めることができます。
窓口、オンライン、郵送での取得など、様々な方法があるため、状況に応じて最適な方法を選びましょう。法人としての責任と信頼性を高めるためにも、正確な手続きを行い、必要な書類を適切に管理することが求められます。
GMOオフィスサポートでは、法人登記に利用する代表印と銀行印・角印・印鑑ケース・捺印マット・朱肉・電子印影などセットで提供しています。
| ツゲ製7点セット | 黒水牛製7点セット | ゴム印3点セット |
|---|---|---|
| 15,000円 | 18,000円 | 6,500円 |
| 代表印、銀行印、角印、印鑑ケース、朱肉、捺印マット、電子印影データ | 代表印、銀行印、角印、印鑑ケース、朱肉、捺印マット、電子印影データ | ゴム印4行、ケース、スタンプ台 |
※入金確認後、2営業日以内に発送
ご自身の用途に合わせて、印鑑を選んでみてください。事業用印鑑を準備することは、事業の正式なスタートを切るための大切な一歩ともいえます。
会社の銀行口座(法人口座)はGMOあおぞらネット銀行がおすすめ!

画像引用元:GMOあおぞらネット銀行
会社設立時にネットバンクで銀行口座を開設するなら、GMOあおぞらネット銀行がおすすめです。
手間なくスピーディーに口座開設できる点が強みで、口座開設手続きは印鑑レス・ペーパーレス・郵送レスで行うことができます。また、条件を満たせば最短即日で口座を開設できます。
振込手数料は同行宛て無料に加え、他行宛てでも一律143円/件(税込)(※)と低価格で、さらに設立1年未満のお客さまであれば、他行宛て振込手数料が月20回まで無料です。
創業期のお悩みを解決するため、外部企業と提携してさまざまなサービスを紹介するビジネスサポートも行っており、会社運営の面でも強い味方になるでしょう。ぜひGMOあおぞらネット銀行をご利用ください。
(※)2025年8月1日より
起業や開業、独立に興味を持ったら、まずは「起業の窓口」に登録してみよう!
「起業の窓口」では、起業に必要なノウハウや成功者のインタビューなど、さまざまなコンテンツを完全無料で提供しています。
会員特典として、起業・経営支援のプロ「V-Spirits」が監修するオリジナル冊子『会社設立完全ガイド』を無料プレゼント。さらに、V-Spritsによる1時間の無料起業相談や、GMOインターネットグループが展開するビジネスの立ち上げや拡大に役立つ各種サービスをおトクな特典付きでご紹介します。
あなたの夢の実現を全力でサポートします!
- 記事監修
-
- 中野 裕哲 HIROAKI NAKANO
- 起業コンサルタント(R)、経営コンサルタント、税理士、特定社会保険労務士、行政書士、サーティファイドファイナンシャルプランナー・CFP(R)、1 級FP 技能士。 V-Spiritsグループ創業者。東京池袋を本拠に全国の起業家・経営者さんを応援!「あの起業本」の著者。著書16冊、累計20万部超。経済産業 省後援「DREAMGATE」で11年連続相談件数日本一。
GMOインターネットグループ株式会社はGMOあおぞらネット銀行株式会社を所属銀行とする銀行代理業として、円普通預金の受入れを内容とする契約の締結の媒介を行います。
銀行代理業許可番号:関東財務局長(銀代)第335号
- ※本記事は、起業の窓口編集部が専門家の監修または独自調査(アンケート)に基づいて制作したものです。
- ※掲載している情報は、記事公開時点の法令・税制・商品・サービス等に基づくものであり、将来的に変更される可能性があります。
- ※アンケート調査に関する記述は、特定の調査対象者からの回答結果および編集部の見解を含んでおり、内容の正確性・完全性を保証するものではありません。
- ※記事の内容は一般的な情報提供を目的としており、すべての方に当てはまるものではありません。個人の状況に応じた具体的な助言が必要な場合は、専門家にご相談ください。
- ※情報の利用や判断、実施については、ご自身の責任で行っていただきますようお願いいたします。
- ※本記事に掲載された内容の転載・複製はご遠慮いただき、引用の際は必ず出典をご明記ください。



 シェア
シェア