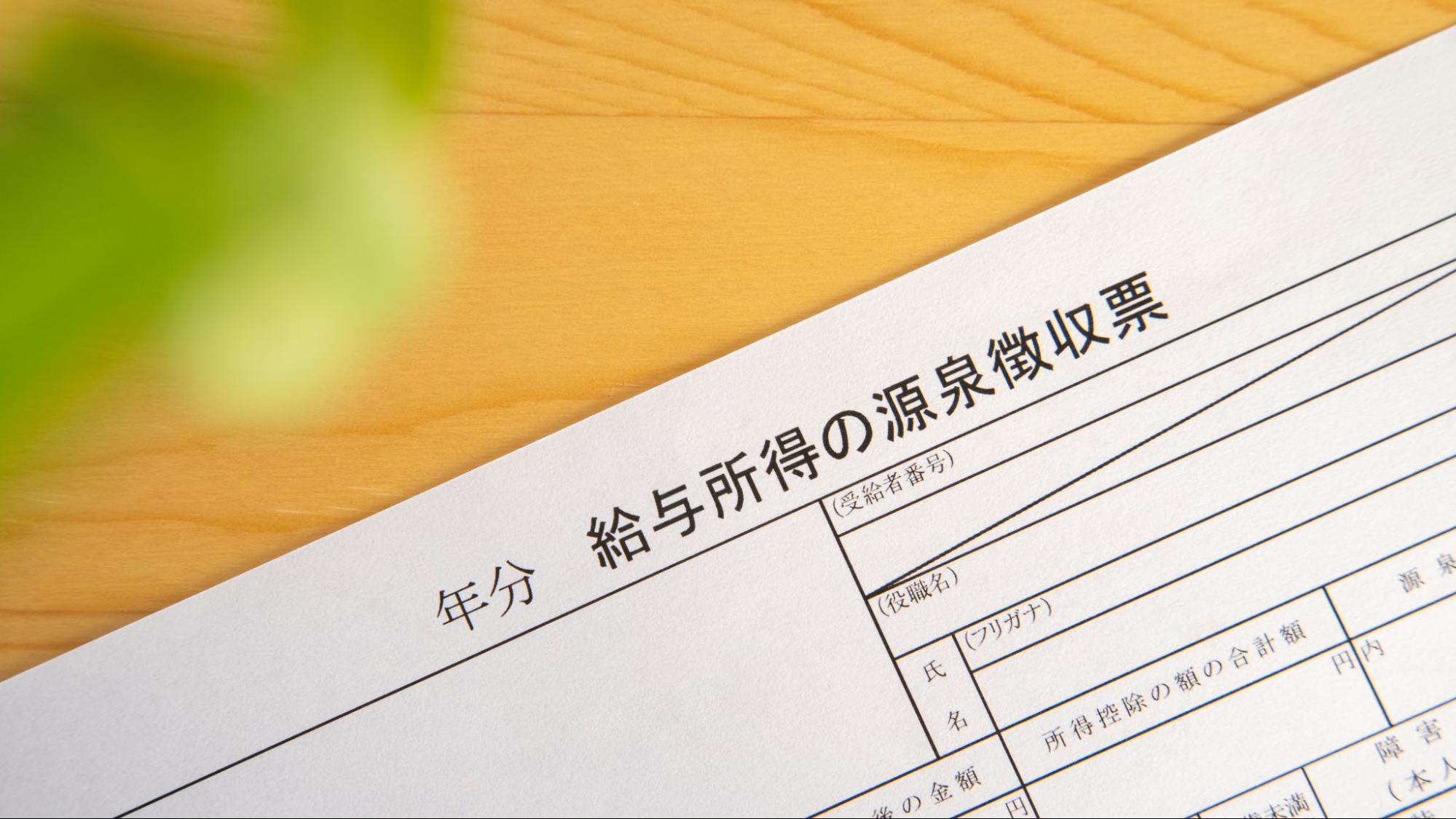予定納税額の確認方法とは?適切なステップで納税額を把握しよう

所得税の納付額が一定以上に達する見込みがある場合、税務署から所得税を先払いする予定納税の通知書が届きます。
予定納税の通知書を受け取ったら、期日までに税金を納めなければなりません。納付が遅れると延滞税が発生するため、税金を納められるように資金を用意しておく必要があります。
一方、予定納税はすべての人が対象になるわけではないため、通知書が届かないからといって不安になることはありません。
予定納税で慌てないためにも、制度について正しく理解しておくことが大切です。この記事では、予定納税額の確認方法や注意点、トラブルや対処法を紹介します。
- 【この記事のまとめ】
- 予定納税とは、前年度の所得税額が一定基準を上回る場合に、その年の所得税の一部をあらかじめ納付する制度です。
- 予定納税は予定納税基準額の1/3を年間2回に分けて納付するのが一般的です。
- 予定納税を期日までにしないと延滞税のペナルティを課せられる場合があります。
予定納税額とは

予定納税額とは、前年の所得税の金額が一定額以上に達した場合に、前払いしなければならない所得税の額のことです。
確定申告のタイミングで一度に多額の税金を納めるのではなく、分割して納税できるため、金銭的な負担を軽減できるメリットがあります。
ここでは、予定納税が必要な人とスケジュールを解説します。
予定納税が必要な人
予定納税を行う必要があるのは、前年分の所得に対する納税額が15万円以上の人です。
納税額15万円というのは、所得税および復興所得税の税金を合算した金額であり、住民税は含まれていません。
予定納税額の計算は原則として、前年の申告納税額を予定納税基準額とし、基準額の2/3を予定納税として納めます。
また、予定納税基準額の計算では、前年の退職所得や譲渡所得などの一時所得は計算に含めません。
個人事業主やフリーランスとして働いている方が、確定申告時に税金を15万円以上納めていると、翌年は予定納税の可能性が高いです。
一方、会社に勤めて給料をもらっている給与所得者は、給料から所得税が源泉徴収されているため、予定納税の対象外となります。
予定納税のスケジュール
予定納税のスケジュールは、第1期の納付期限が7月1日~7月31日、第2期の納付期限が11月1日~11月30日で、それぞれ予定納税基準額の1/3を納めます。
予定納税の通知書は、6月15日までに税務署から通知されます。この通知書に予定納税額や納税に関する手続きなどが記載されているため、通知が届いたら確認しましょう。
ちなみに、予定納税額は前年度の所得税額から計算した金額であるため、今年度の所得額が大きく減少すると、所得に対して予定納税で多くの税金を納めることになります。
この場合、確定申告で還付手続きを行うことによって納めすぎた所得税が還付されます。
また、今年度の所得額が大幅に減少することが予想されている場合は、「減額申請」という特例措置を利用し、予定納税額を減らすことも可能です。
予定納税額を確認する方法

予定納税で慌てないためにも、早めに予定納税額を確認しておきましょう。ここでは、予定納税額を確認する方法を紹介します。
通知書で確認する方法
予定納税額は、税務署から送られてくる予定納税等の通知書で確認できます。通知書は毎年6月15日までに送付され、前年分の納税分に基づく予定納税額が記載されています。
通知書の右側に第1期分と第2期分の予定納税額が記載されているため、税金を期日までに納められるように資金を用意しておきましょう。
予定納税等の通知書には、予定納税基準額も記載されています。基本的に予定納税は予定納税基準額の2/3であるため、納税額が前年と同じ場合は確定申告時に残りの1/3を納める必要があります。
e-Taxを利用した確認方法
e-Taxで予定納税額を確認することもできます。予定納税額の確認手順は、以下の通りです。
- e-Taxにログイン
- 通知書等メニューを選択
- 予定納税等通知書を確認
令和5年1月以降、申請書作成の際に「この申告書に係る通知等がある場合、e-Taxによる通知を希望する」を選択すると、予定納税額の通知はe-Taxで行われます。
この場合は、予定納税等の通知書が届かないため注意しましょう。
確定申告書から確認する方法
予定納税額は確定申告書から確認することもできます。
事業所得、不動産所得、給与所得のみの場合は、所得税の確定申告書Bの45欄が予定納税基準です。
なお、分離課税の所得、譲渡所得、一時所得、雑所得などがある場合は、所得と源泉徴収額を控除して計算した金額と、その金額に対する復興特別所得税の合計額が予定納税基準額となります。
確定申告書Bの45欄が、そのまま予定納税基準額になるとは限らないという点に注意が必要です。
確定申告を楽にしたいと悩む方へ

質問に答えていくだけで、経理の作業がはじめての方でも簡単に確定申告の書類作成をすることができます!
確定申告を楽にサクッとおこないたい方は、freeeがおすすめです!
予定納税額に関するトラブルと対処法

予定納税額に関するトラブルが発生した場合は、速やかに対応しましょう。ここでは、予定納税額に関するトラブルと対処法を解説します。
通知書が届かない場合の対応
予定納税額の通知書は例年6月中旬頃に送付されますが、その時期に届かない場合は以下の原因が考えられます。
- 予定納税基準額が15万円未満
- e-Taxでの通知を希望している
- 以前に納付書を使わない手段で予定納税している
まずは確定申告書類を確認して、予定納税基準額が15万円以上でないか確認しましょう。
予定納税基準額が15万円以上の場合は、e-Taxに通知が届いている可能性があります。e-Taxにログインして予定納税額の通知が来ていないか確認しましょう。
また、以前の確定申告や予定申告で納付書を使わずに納税していた場合、予定納税の納付書は送られなくなります。
具体的には、口座振替、クレジットカード納付、コンビニ納付、インターネットバンキングによる納付です。
予定納税が必要な方は、通知書が届いていなくても、期日までに税金を納めなければなりません。
納付期限を過ぎると延滞税が発生するため、期日までに通知書が届いていない場合は、予定納税額を調べる必要があります。
紛失した場合の再発行手続き
予定納税額の通知書を紛失してしまい、納税額がわからなくなってしまった場合は、税務署に通知書を再発行してもらえるケースがあります。
まずは管轄の税務署に連絡し、「予定納税額の通知書を再発行できるか」「再発行には何が必要か」などを確認しましょう。その際は、本人確認書類や納税者番号を用意しておくとスムーズです。
振替で予定納税している場合は、期日になると指定の口座から引き落とされます。振替納税を選択している場合は、引き落としが行われていないか確認しましょう。
予定納税は第1期が7月1日~7月31日となっており、予定納税額の通知書が届く6月中旬から時間的な余裕がありません。慌てないためにも、紛失に気づいた時点で早めに再発行の手続きをしましょう。
計算ミスや変更があった場合
予定納税が間違っている場合は、予定納税基準額を算出する確定申告そのものに誤りがあるため、修正申告を行う必要があります。
修正申告を行う際は、税務署または国税庁のWebサイトから修正申告書をダウンロードし、必要事項を記入したら、管轄の税務署に持参もしくはe-Taxで提出しましょう。
また、今年度の所得が前年度よりも大幅に減少する可能性があり、納税額を減らしたい場合は予定納税の減額申請ができます。減額申請の対象となるのは以下に該当する方です。
- 廃業、休業、失業した場合
- 業績不振で所得が明らかに少なくなる場合
- 災害、盗難、横領で資産に損害を受けた場合
- 所得税額が下がる見込みの場合
減額申請の手続きは、予定納税額の減額申請書を税務署の窓口または国税庁のWebページからダウンロードし、管轄の税務署に提出します。
減額申請の理由だけでなく、申告納税見積額等の計算も記入が必要です。
副収入がある人が知っておくべき注意点

予定納税は個人事業主や法人だけでなく、副収入がある給与所得者にも関係があります。ここでは、副収入がある人が知っておくべきことを解説します。
副業収入と予定納税の関係
給与所得がある正社員やアルバイトの場合、給料から所得税が源泉徴収されるため、通常は予定納税の対象になりません。
源泉徴収とは、所得が発生する際にその所得から一定の税額をあらかじめ差し引いて納税する制度のことです。給与所得者は会社が源泉徴収をするため、自身で所得税の計算をする必要がありません。
しかし、給与所得以外に副業収入があり、副業の年間所得に対する予定納税基準額が15万円以上の場合は予定納税が必要です。
給与所得の源泉徴収はあくまでも会社が支払う給料を基準とした徴収であり、副業に関する収入は含まれていません。なお、給与所得者は副業収入が年間20万円を超える場合に確定申告が必要です。
源泉徴収されている場合の影響
個人事業主やフリーランスが報酬を受け取る際、報酬が源泉徴収されている場合は、前年度の所得税額が15万円以上でも予定納税の対象にならない場合があります。
その理由は、申告納税額は所得税額から源泉徴収税額を差し引いた金額であるためです。
例えば、所得税額が17万円でも10万円が源泉徴収されている場合、申告納税額は7万円になるため予定納税が不要となります。
個人事業主やフリーランスが源泉徴収されるケースは、原稿料や講演料、専門職の報酬を受け取るなどがあります。
ちなみに、給与所得者の場合は所得税の過不足について会社が年末調整を行って調整しますが、個人事業主やフリーランスは年末調整がありません。
そのため、源泉徴収されている所得がある場合は、確定申告を行って所得税の過不足を自身で計算する必要があります。
源泉徴収の仕組みや計算方法、納付方法などは、以下の記事でも詳しく解説しているので、あわせてご参照ください。
確定申告時に注意すべきポイント
給与所得者が副業を辞めたなどの理由で副業所得が年間20万円以下になっても、予定納税している場合は必ず確定申告をしましょう。
なぜなら、予定納税で納付した所得金額が今年度の所得税額よりも多かった場合は、確定申告時に還付を受けることができるためです。
例えば、今年度に予定納税で20万円を納めたとします。実際の所得税額が0円だった場合、確定申告を行うことで納めた20万円が還付されます。
還付は自動的に行われるものではなく、自身が確定申告をして手続きをする必要があります。確定申告をしないままでいると、受け取れる還付金がもらえないため注意しましょう。
まとめ
この記事では、予定納税額の概要や確認方法、注意点を解説しました。
予定納税は、確定申告の時に納める所得税や復興特別所得税を先に分散して納める制度です。年間の所得税を一度に納める必要がないため、納税者には資金繰りの負担を軽減できるメリットがあります。
予定納税額は、通知書や確定申告書類で確認できます。通知書は6月中旬頃に送られますが、e-Taxの場合はe-Taxに通知が届く点に注意しましょう。
また、期日まで予定納税をしないと延滞税のペナルティを課せられる可能性があるため、早めに予定納税がないか確認しておくことも大切です。
起業や開業、独立に興味を持ったら、まずは「起業の窓口」に登録してみよう!
「起業の窓口」では、起業に必要なノウハウや成功者のインタビューなど、さまざまなコンテンツを完全無料で提供しています。
会員特典として、起業・経営支援のプロ「V-Spirits」が監修するオリジナル冊子『会社設立完全ガイド』を無料プレゼント。さらに、V-Spritsによる1時間の無料起業相談や、GMOインターネットグループが展開するビジネスの立ち上げや拡大に役立つ各種サービスをおトクな特典付きでご紹介します。
あなたの夢の実現を全力でサポートします!
- 記事監修
-
- 中野 裕哲 HIROAKI NAKANO
- 起業コンサルタント(R)、経営コンサルタント、税理士、特定社会保険労務士、行政書士、サーティファイドファイナンシャルプランナー・CFP(R)、1 級FP 技能士。 V-Spiritsグループ創業者。東京池袋を本拠に全国の起業家・経営者さんを応援!「あの起業本」の著者。著書16冊、累計20万部超。経済産業 省後援「DREAMGATE」で11年連続相談件数日本一。
- ※本記事は、起業の窓口編集部が専門家の監修または独自調査(アンケート)に基づいて制作したものです。
- ※掲載している情報は、記事公開時点の法令・税制・商品・サービス等に基づくものであり、将来的に変更される可能性があります。
- ※アンケート調査に関する記述は、特定の調査対象者からの回答結果および編集部の見解を含んでおり、内容の正確性・完全性を保証するものではありません。
- ※記事の内容は一般的な情報提供を目的としており、すべての方に当てはまるものではありません。個人の状況に応じた具体的な助言が必要な場合は、専門家にご相談ください。
- ※情報の利用や判断、実施については、ご自身の責任で行っていただきますようお願いいたします。
- ※本記事に掲載された内容の転載・複製はご遠慮いただき、引用の際は必ず出典をご明記ください。



 シェア
シェア