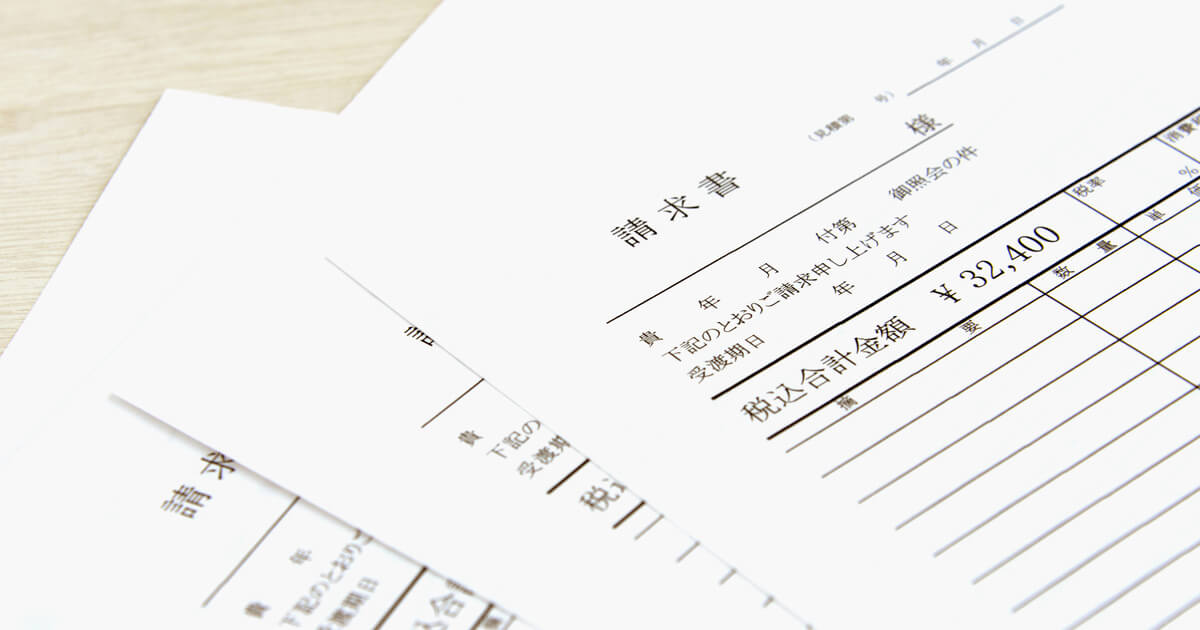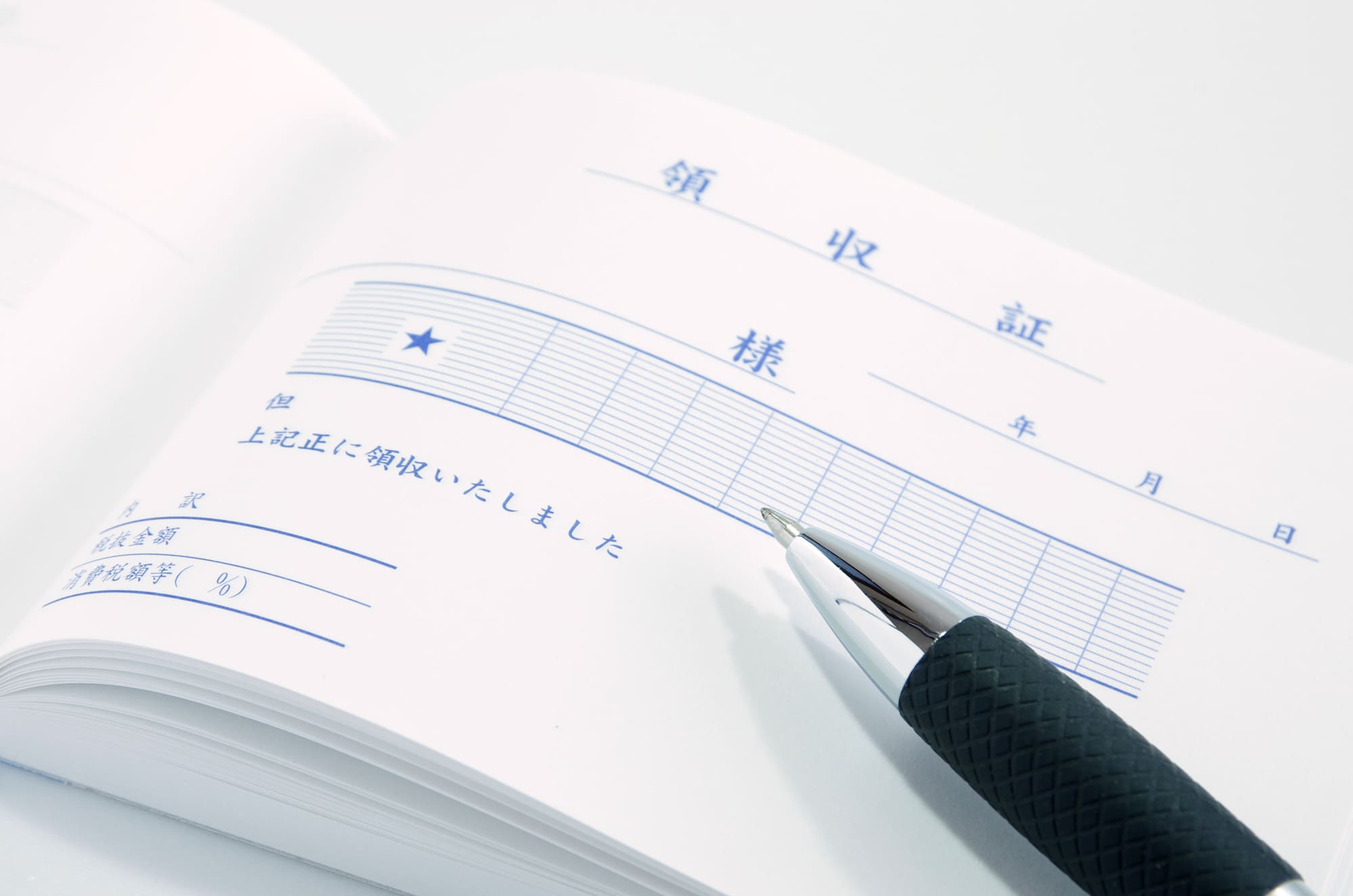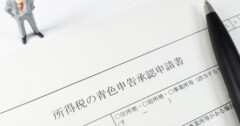請求書に印鑑は必要?押し方や注意点、電子印鑑について詳しく解説

「請求書に印鑑は必要なの?」「どの種類の印鑑を使えばいいか分からない」という疑問を抱えている方も多いでしょう。
結論から言えば、請求書への印鑑押印は法的に必須ではなく、インボイス制度においても印鑑は不要です。
実際には日本の商慣習として印鑑を押すことが一般的であり、取引先との信頼関係構築や書類の信頼性向上のために多くの企業が継続して使用しています。
しかし、印鑑の種類によって効力が異なり、実印・銀行印・角印の使い分けを誤ると、信頼性や業務効率の低下を招く可能性があるため注意が必要です。
この記事では、請求書への押印の必要性、請求書に使用する印鑑の種類と選び方、適切な押印方法と注意点について解説します。
- 【この記事のまとめ】
- 請求書への印鑑は法律上必須ではありませんが、ビジネス慣習として信頼性や文書の正式性を高める役割を果たします。
- 請求書に押印がない場合でも法的効力は維持されますが、改ざん防止やトラブル回避の観点から押印が推奨されます。
- 押印には認印や角印が一般的で、デジタル化の進展によりPDFのデジタル印鑑の活用も増えています。
【結論】請求書に印鑑は必ずしも必要ではない!
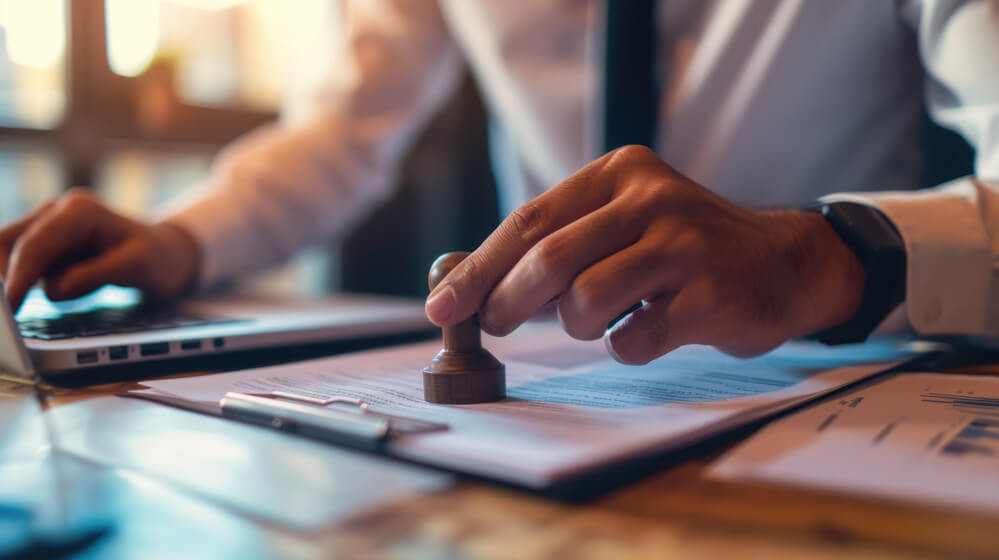
請求書への押印は、法律で明確に義務付けられているわけではありません。
とはいえビジネスの慣習として、押印があると文書の正式性や真実性を示すことができ、取引の信頼性を高めることができます。
そのため、請求書に印鑑があるかどうかは、多くの企業や個人事業主にとって重要な意味を持つのです。
適格請求書(インボイス)に印鑑は不要
2023年10月から始まったインボイス制度において、適格請求書に印鑑の押印は法的に義務付けられていません。
取引年月日や取引内容、登録番号、税率ごとの消費税額など、必要な記載事項さえ満たしていれば有効な請求書として認められます。
これは従来の請求書においても同様で、民法上、契約の成立に印鑑は必須要件ではないのです。
ただし、日本の商慣習として印鑑を押すことが一般的であり、取引先によっては押印を求められるケースも少なくありません。
印鑑があることで書類の信頼性が高まり、改ざん防止の効果も期待できるため、多くの企業が継続して使用しています。
特に大手企業や官公庁との取引では、社内規定により押印を必須としている場合があるため、事前に確認しておくことが大切です。
請求書への押印の必要性
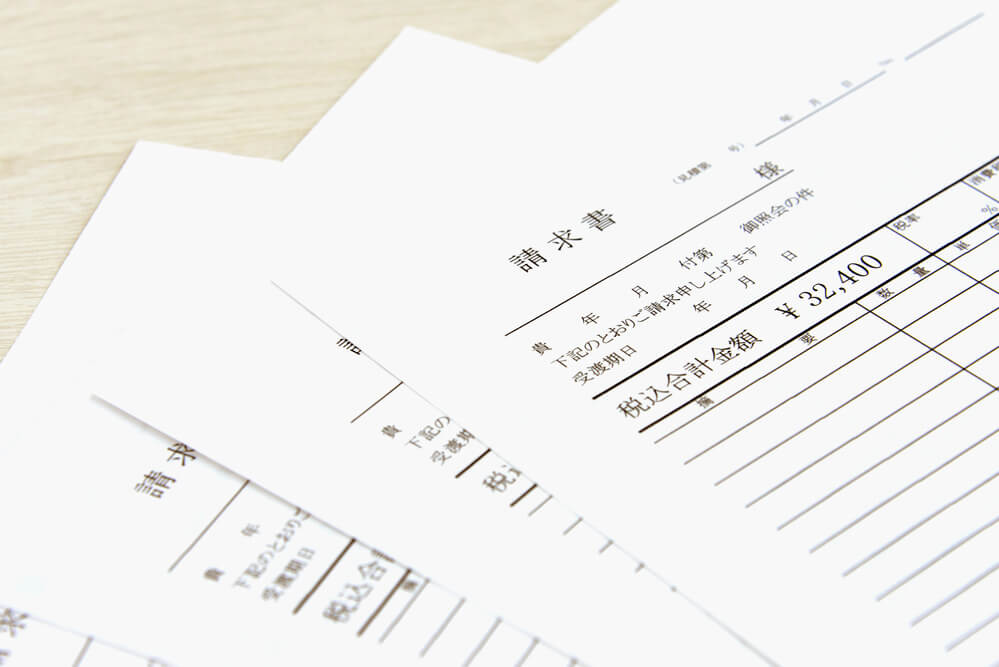
先述したように、請求書への押印は法律などで義務付けられているものではありません。
しかし、以下のような理由から必要性が高いといえます。
- 偽造を防げる
- 信頼性が増す
- 支払いトラブルを回避できる
それぞれ具体的に見ていきましょう。
偽造を防げる
請求書に印鑑を押すもっとも大きな理由は、偽造や改ざんを防ぐためです。
印鑑はその個体ごとに独特な印影を持つため、文書が正式なものであることの証明となります。これにより、不正な改ざんや偽造のリスクを低減させることができます。
信頼性が増す
押印された請求書は、取引の正当性や誠実さを示す証拠となります。
印鑑は取引の当事者が文書の内容を確認し、同意した証として機能するためです。その結果、取引関係の信頼性が高まり、ビジネスを円滑に進行する一助となるでしょう。
押印がない請求書の効力は?
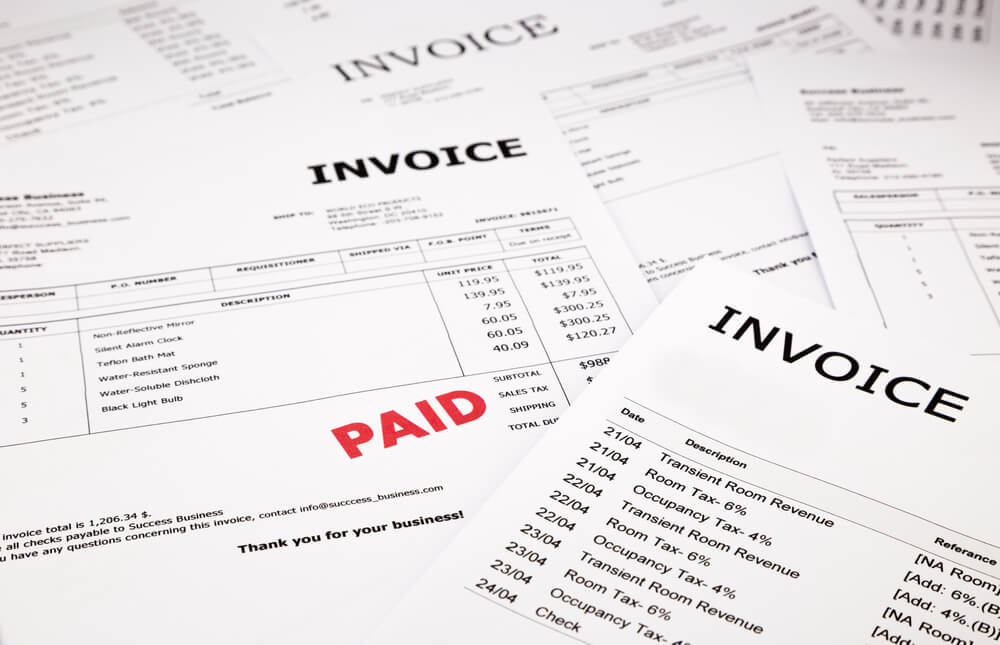
では、押印がない請求書の効力についてはどうなのでしょうか。法律上、商習慣上のそれぞれの観点から見ていきましょう。
法律上の効力
日本の法律では、請求書に印鑑を押すことを義務付けていないため、押印がない請求書も原則として有効です。
民事訴訟法では、書面による契約の成立について、「当事者が署名または記名押印した書面は真正に成立したものと推定する」と規定されています。しかし、これはあくまでも任意規定であり、印鑑がなくても契約は成立します。ただし、印鑑のコピーやスキャンは真正な押印と認められない場合があり、注意が必要です。
しかし、押印がない場合、その文書の真実性や正式性を証明する他の方法が求められることがあります。具体的には、メールのやり取りや電子証明書などが用いられるケースが一般的です。
商習慣上の効力
ビジネスの実務では、押印がない請求書に対する扱いが異なる場合があります。長い間にわたる商習慣や業界の慣例により、印鑑を要求する場合が多いです。
一部の企業では、押印のない請求書を受け付けてもらえない場合もあるので、あらかじめ取引先との合意や会社の規定に基づいて判断する必要があります。
【注意】請求書への印鑑の押し方と注意点

ここからは、請求書への印鑑の押し方を説明していきます。特に決まったルールはないものの、以下の点に注意しましょう。
- 押印場所
- 印鑑の種類
- 押印の仕方
押印場所
請求書に印鑑を押す場所は、通常、文書の末尾や指定された欄になります。
明確な場所が指定されていない場合は、請求内容や合意内容が確認できる部分の近くに押印することが一般的です。会社名や住所にかかるように押印することで、改ざんリスクを軽減できます。
空白部分に押印する場合は、他の記載事項と重ならないように注意しましょう。
印鑑の種類
請求書に使用する印鑑には、実印、銀行印、認印などがありますが、請求書の場合は認印や社印が用いられることが多いです。請求内容の重要性や正式性に応じて、適切な印鑑を選びましょう。
もちろんシャチハタでも構いませんが、インクの色が薄くならないようにくれぐれも注意してください。なお、角印の方がフォーマルな印象を与えられるのでおすすめです。
押印の仕方
押印時には、印影がはっきりと残るように注意しましょう。不鮮明な印影は文書の正式性を損ねる原因となるため、印鑑は直接紙に押すか、印鑑台を使用してきれいに押すことが望ましいです。
二度押しも避けるのが無難なので、印影が薄くならないように気をつけてください。基本的には、朱肉は朱色のものを使用しましょう。
請求書に押す印鑑の種類

請求書に使用される印鑑には複数の種類があり、それぞれ役割や効力が異なります。適切な印鑑を選択することで、書類の信頼性を高め、取引先との信頼関係構築にも繋がります。
実印(丸印)
実印は法務局に登録された会社の代表者印であり、印鑑として位置付けられています。直径1.8cm〜2.1cm程度の丸形で、会社名と代表者の肩書きが彫刻されているのが一般的です。
重要な契約書や公的書類に使用されることが多く、請求書への押印は稀です。
実印を請求書に使用すると、紛失や偽造のリスクが高まるため、日常的な業務では避けるべきといえます。高額取引や特別な契約条件がある場合に限定することが賢明です。
銀行印
銀行印はその名前の通り、銀行口座の開設や手形・小切手の発行時に使用する印鑑です。実印より一回り小さい1.6cm〜1.8cm程度のサイズが一般的となっています。
振込先口座と同じ銀行に登録している印鑑を押すことで、取引の信頼性を高める効果もあります。
請求書への押印に銀行印を使用する企業もありますが、請求書などの取引書類に押印するのは一般的ではありません。
万が一の紛失や盗難に備えて、実印や角印とは別に保管することが推奨されています。
角印
角印は会社の認印として最も頻繁に使用される印鑑で、請求書や見積書、納品書などの日常的な書類に押印されます。正方形の形状で、一辺が2.1cm〜2.4cm程度のサイズが標準的です。
角印には会社名のみが彫刻されており、代表者名は含まれないため、複数の部署で共有して使用できる利便性があります。
法務局への登録は不要で、必要に応じて複数作成しても問題ありません。
請求書への押印は角印で十分とする企業が大半を占めており、業務効率の観点からも最適な選択といえるでしょう。印影が鮮明で、会社名がはっきりと読み取れるものを選ぶことが重要です。
個人事業主やフリーランスは丸形の印鑑が一般的

個人事業主やフリーランスの場合、請求書には個人名の丸形印鑑を使用するのが一般的です。
法人のような角印は使用せず、直径1.2cm〜1.8cm程度の認印で対応する方が多くなっています。
屋号がある場合は、屋号と個人名を組み合わせた印鑑を作成することも可能ですが、必須ではありません。
実印として市区町村に登録している印鑑は、重要書類のみに使用し、請求書には別の認印を用意することをおすすめします。
なお、シャチハタなどの浸透印はインクが薄れやすく改ざんの恐れもあるため、朱肉を使用する印鑑が望ましいといえるでしょう。
取引先によっては印鑑の種類を指定される場合もあるため、事前に確認しておくと安心です。
【重要】電子請求書には電子印鑑の利用が便利

電子請求書の普及に伴い、PDFファイルに押印できる電子印鑑の需要が急速に高まっています。
電子印鑑を利用することで、物理的な印鑑を押してスキャンする手間が省け、請求書作成から送付までの業務を大幅に効率化できるのです。
電子印鑑には、印影を画像化しただけの簡易型と、電子証明書を付与したデジタル印鑑の2種類があります。
| 電子印鑑の種類 | 特徴 |
| 簡易型 | 印影をスキャンまたは作成した画像データで、電子文書に貼り付けて使用する簡易的な電子印鑑 |
| デジタル印鑑 | タイムスタンプや識別情報が記録され、押印日時と押印者を証明できる高度な電子印鑑 |
電子署名付きのデジタル印鑑は改ざん防止機能を持ち、紙の書類への押印と同様の法的効力が認められています。一方、単なる画像データの電子印鑑は効力が限定的です。
初期費用や月額料金が発生するサービスもありますが、印紙税の削減や保管スペースの削減など、長期的なメリットに期待できます。
クラウド型の請求書発行システムと連携すれば、請求業務全体のデジタル化も実現可能です。
ただし、取引先が電子印鑑を受け入れているか事前に確認し、必要に応じて紙の請求書も併用する柔軟な対応が求められます。
電子印鑑を利用するメリット・デメリット

電子印鑑の導入を検討する際は、メリットとデメリットを正しく理解した上で、自社の業務形態や取引先の状況に適しているか慎重に判断することが重要です。
ここでは、電子印鑑の具体的な利点と注意点について詳しく解説します。
電子印鑑のメリット
電子印鑑の最大のメリットは、請求書の作成から取引先への送付までの一連の作業時間を短縮し、業務効率を向上させられる点にあります。
従来は文書を印刷し、押印してからスキャンしてPDF化するという複数の工程が必要でしたが、電子印鑑であればパソコンの画面上で全ての作業が完結するのです。
印紙税も不要となるため、コスト削減の効果にも期待できます。
また、物理的な書類の保管スペースが不要となり、クラウド上で管理することで検索機能を使って過去の請求書を瞬時に見つけ出せるようになります。
環境への配慮という観点からも、ペーパーレス化は企業の社会的責任を果たす取り組みといえるでしょう。
- ▼電子印鑑のメリット
-
- 請求書作成の作業時間を短縮できる
- コスト削減効果に期待できる
- 書類管理の効率化に繋がる
- ペーパーレス化が実現する
- 押印のための出社が不要になる
電子印鑑のデメリット
電子印鑑の導入には、初期のシステム構築費用や従業員への操作教育にかかるコスト、さらに運用ルールの策定など、相応の準備期間と投資が必要となります。
デジタル化が進んでいない取引先では、従来通りの紙の請求書を求められることも少なくありません。
簡易的な画像印鑑は複製が容易であるため、なりすましや改ざんのリスクが物理印鑑より高くなる可能性があり、セキュリティ対策を十分に講じる必要があります。
法的効力を持つデジタル印鑑の場合は、電子証明書の取得費用や年間更新料も必要です。これらの課題を踏まえ、段階的な導入計画を立てることが成功への鍵となります。
- ▼電子印鑑のデメリット
-
- システム構築費用や従業員教育コストが発生する
- 従来の紙書類が必要になることがある
- 十分なセキュリティ対策が求められる
- デジタル印鑑は電子証明書の取得・更新費用が必要になる
電子印鑑の作成方法

電子印鑑を作成する方法は複数あり、予算や必要とする機能に応じて選択できます。以下、代表的な作成方法とそれぞれの特徴について解説します。
印章のスキャン
最も簡単で低コストの方法は、既存の物理的な印鑑を白紙に押印し、スキャナーやスマートフォンのカメラで読み取って画像データ化する方法です。
スキャンした画像は背景を透過処理し、PNG形式で保存します。
解像度は300dpi以上に設定することで、印影の細部まで鮮明に再現でき、実際の押印と見分けがつかないクオリティを実現できます。
ただし、この方法で作成した電子印鑑は単なる画像データであり、複製や改ざんが容易で法的効力が限定的である点には注意が必要です。
社内文書や簡易的な確認書類には適していますが、重要な契約書類への使用は避けるべきといえます。
Excel・Word
Microsoft OfficeのExcelやWordに搭載されている図形描画機能を活用すれば、追加費用なしでオリジナルの電子印鑑を作成できます。
円形や四角形の図形を組み合わせ、テキストボックスで会社名や氏名を入力して微調整すれば完成です。印影を撮影・スキャンしてExcelやWordで編集する方法もあります。
作成した印鑑は図形として保存しておけば、必要なときにコピー&ペーストで簡単に文書に挿入できます。
WordやExcelのマクロ機能を使えば、ワンクリックで定位置に印鑑を配置する自動化も実現できるため、業務効率化にも繋がるでしょう。
フリーソフト
インターネット上には、無料で利用できる電子印鑑作成サービスが多数提供されています。ブラウザ上で名前を入力するだけで印鑑画像を生成できる手軽さが魅力です。
- ▼フリーソフトの一例
-
- Web印鑑
- 印鑑透過
- 電子三文判
- クリックスタンパー
- くいっくはんこ
書体は篆書体、古印体、行書体など伝統的なものから選択でき、印鑑のサイズや枠の太さ、色の濃淡まで細かくカスタマイズできるサービスもあります。
作成したデータはPNG形式で保存され、背景が透過処理されているため使いやすい点が特徴です。
ただし、無料サービスで作成した印鑑は誰でも同じものを作成できてしまうため、セキュリティ面での信頼性は低く、重要書類への使用は推奨されません。
識別情報の付与サービス
高度なセキュリティと法的効力を求める企業には、電子証明書やタイムスタンプなどの識別情報を付与できる有料サービスの利用が適しています。
PKI技術を使用した電子署名機能により、押印者の身元証明と文書の改ざん防止を同時に実現できるのです。押印日時や押印者情報については暗号化されて記録されます。
これらのサービスで作成されたデジタル印鑑は、法的な証拠能力も認められているため、契約書などの重要文書に最適です。
初期費用は数万円、月額料金は数千円程度かかりますが、投資に見合う価値があるといえるでしょう。
GMOグローバルサインが提供する「GMOサイン」では、電子署名法に準拠した電子印鑑機能を搭載し、契約印タイプと実印タイプの両方の電子署名に対応しています。
無料のお試しプランもご用意していますので、電子印鑑の導入をご検討の際は、ぜひ「GMOサイン」のご利用をご検討ください。
請求書の印鑑に関してよくある質問
ここからは、請求書の印鑑に関して、よくある質問に回答していきます。
PDFの請求書に印鑑は必要?
デジタル化が進む中で、PDF形式の請求書の使用が増えています。法律上はPDFの請求書に印鑑を押す必要はありませんが、受け取り側の要望に応じてデジタル印鑑を使用する場合があります。
請求書の認印はシャチハタでも大丈夫?
シャチハタ印は、正式な文書には適さないとされる場合が多いです。しかし、請求書に関しては、使用する企業や業界によって異なりますので、取引先の了承を得ることが重要です。
請求書には角印と丸印のどちらを使うべき?
請求書に使用する印鑑の形状は、特に定められていません。一般的には、認印や社印が用いられ、その形状は企業や個人の好みによります。
ただし、形状によって印象が変わるため、取引の内容や相手との関係性を考慮して選択することが望ましいです。
請求書に訂正印を使っても大丈夫?
一般的な文書の記載ミスを訂正する際は訂正印を使いがちですが、請求書の金額や取引内容など重要事項については訂正印は使用しません。
訂正印を使用することで、請求書そのものの信頼性が損なわれる可能性があるため、訂正箇所が多い場合や金額に関わる重要な部分に誤りがある場合は、新たに請求書を作り直しましょう。
訂正の経緯を記録として残しておけば、後々のトラブル防止にも繋がるため、変更履歴の管理は重要なポイントとなります。
印鑑を押す位置を間違えたらどうなる?
請求書における印鑑の押印位置は一般的に会社名の右側か書類の右下部分とされていますが、多少位置がずれても法的効力に影響はありません。
重要なのは印影が鮮明で会社名が読み取れることです。
万が一、印影が不鮮明になったり上下逆さまに押してしまったりした場合は、その横に改めて正しく押印し直すか、新しい請求書を作成することをおすすめします。
複数の印鑑を押す必要がある場合は、上下左右のバランスを考慮し、見た目にも整然とした配置を心がけることで書類の信頼性が高まります。
【まとめ】請求書の印鑑は法的に不要でも実務では重要な役割を果たす
請求書への印鑑押印は法的義務ではありませんが、日本の商慣習として定着しており、角印を使用することで業務効率と安全性のバランスを保てます。
電子印鑑を導入すれば、請求書作成から送付までの時間を短縮でき、印紙税の削減やテレワーク対応など多くのメリットを享受できます。
ただし、取引先のデジタル化状況やセキュリティ対策を考慮し、物理印鑑と電子印鑑を適切に使い分けることが重要です。
GMOオフィスサポートでは、法人登記に利用する代表印と銀行印・角印・印鑑ケース・捺印マット・朱肉・電子印影などセットで提供しています。
| ツゲ製7点セット | 黒水牛製7点セット | ゴム印3点セット |
| 15,000円 | 18,000円 | 6,500円 |
| 代表印、銀行印、角印、印鑑ケース、朱肉、捺印マット、電子印影データ | 代表印、銀行印、角印、印鑑ケース、朱肉、捺印マット、電子印影データ | ゴム印4行、ケース、スタンプ台 |
※入金確認後、2営業日以内に発送
ご自身の用途に合わせて、印鑑を選んでみてください。事業用印鑑を準備することは、事業の正式なスタートを切るための大切な一歩ともいえます。
起業や開業、独立に興味を持ったら、まずは「起業の窓口」に登録してみよう!
「起業の窓口」では、起業に必要なノウハウや成功者のインタビューなど、さまざまなコンテンツを完全無料で提供しています。
会員特典として、起業・経営支援のプロ「V-Spirits」が監修するオリジナル冊子『会社設立完全ガイド』を無料プレゼント。さらに、V-Spritsによる1時間の無料起業相談や、GMOインターネットグループが展開するビジネスの立ち上げや拡大に役立つ各種サービスをおトクな特典付きでご紹介します。
あなたの夢の実現を全力でサポートします!
- 記事監修
-
- 中野 裕哲 HIROAKI NAKANO
- 起業コンサルタント(R)、経営コンサルタント、税理士、特定社会保険労務士、行政書士、サーティファイドファイナンシャルプランナー・CFP(R)、1 級FP 技能士。 V-Spiritsグループ創業者。東京池袋を本拠に全国の起業家・経営者さんを応援!「あの起業本」の著者。著書16冊、累計20万部超。経済産業 省後援「DREAMGATE」で11年連続相談件数日本一。
- ※本記事は、起業の窓口編集部が専門家の監修または独自調査(アンケート)に基づいて制作したものです。
- ※掲載している情報は、記事公開時点の法令・税制・商品・サービス等に基づくものであり、将来的に変更される可能性があります。
- ※アンケート調査に関する記述は、特定の調査対象者からの回答結果および編集部の見解を含んでおり、内容の正確性・完全性を保証するものではありません。
- ※記事の内容は一般的な情報提供を目的としており、すべての方に当てはまるものではありません。個人の状況に応じた具体的な助言が必要な場合は、専門家にご相談ください。
- ※情報の利用や判断、実施については、ご自身の責任で行っていただきますようお願いいたします。
- ※本記事に掲載された内容の転載・複製はご遠慮いただき、引用の際は必ず出典をご明記ください。



 シェア
シェア