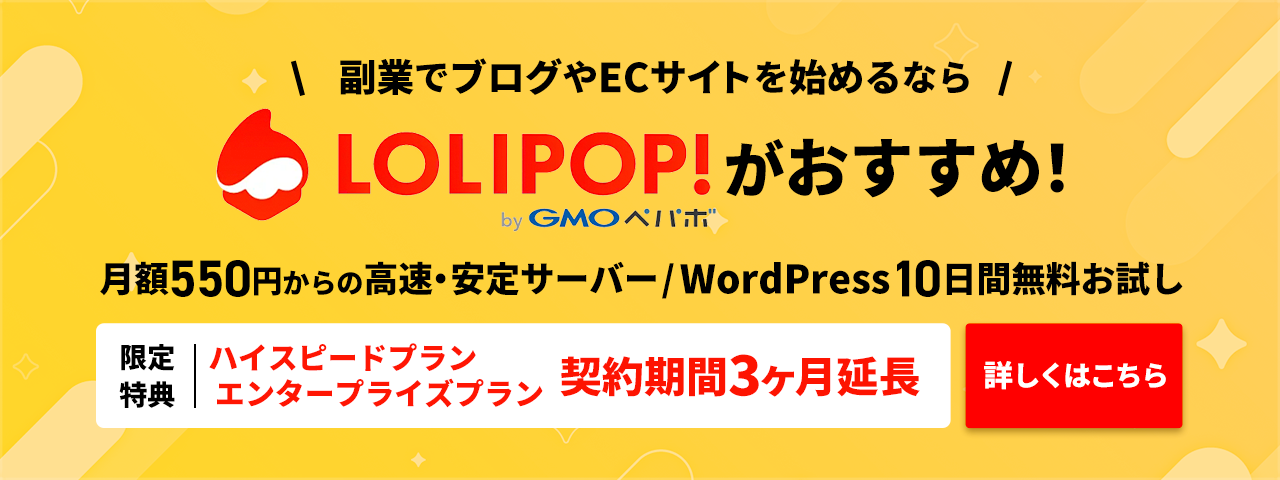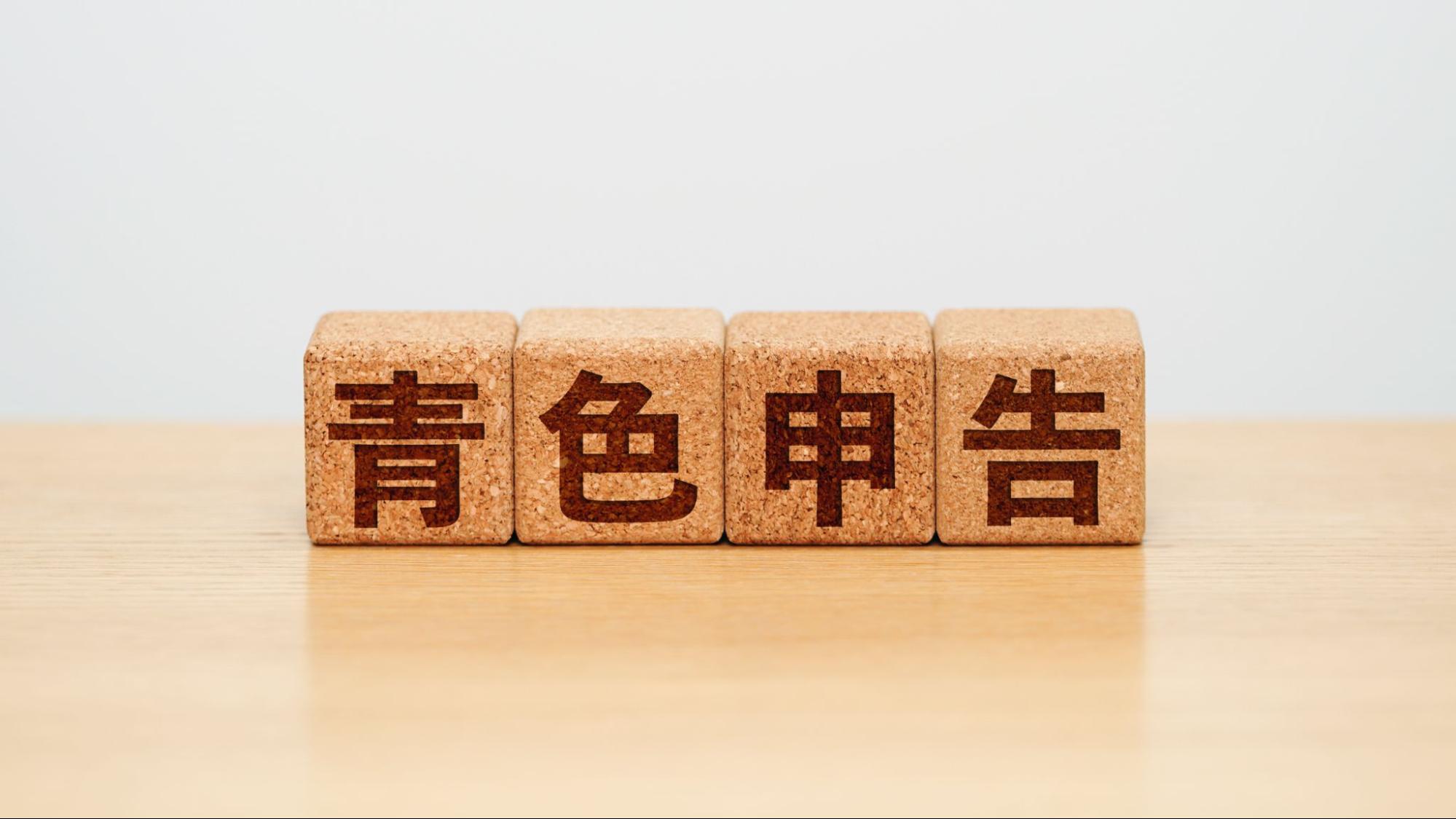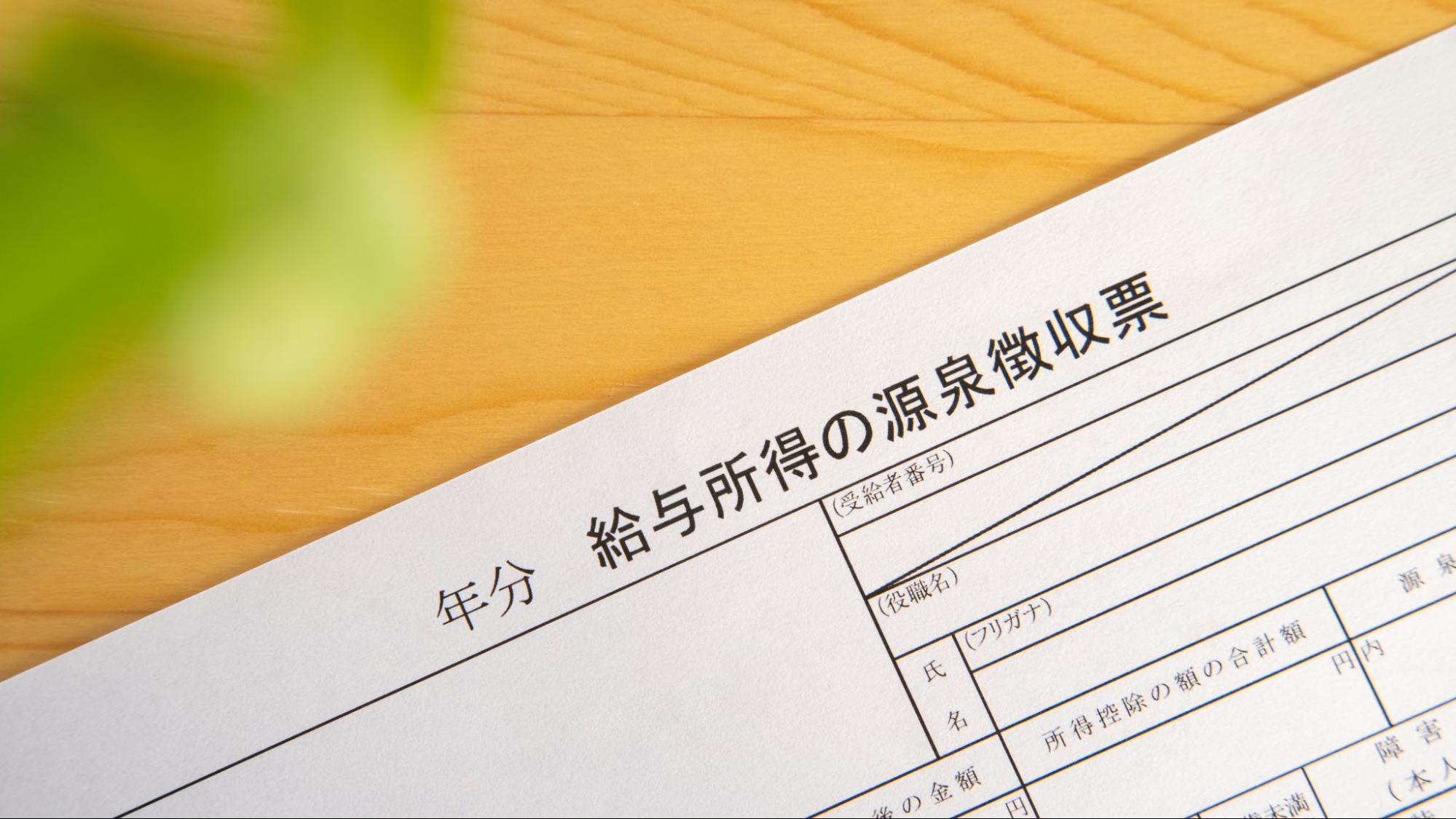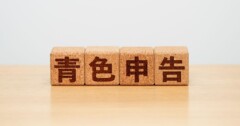不動産投資で副収入を得る!副業禁止の会社員でもOKな理由と稼ぐための注意点

不動産投資は、副業禁止規定がある企業でも資産運用として認められるケースが多いため、副業として高い人気があります。
この記事では、不動産投資が許容される理由や注意点、具体的なメリットについて解説します。適切な準備と計画を行い、不動産投資を成功に導くためのポイントを押さえましょう。
- 【この記事のまとめ】
- 不動産投資は資産運用とみなされるため、副業禁止規定がある企業でも許容される場合があります。
- 不動産投資は手間が少なく本業に集中できる点や、ローンを活用して少ない自己資金で始められる点が魅力です。
- 事前に就業規則を確認し、本業に支障がない範囲で行うことが重要です。
副業禁止でも不動産投資がOKな理由は?
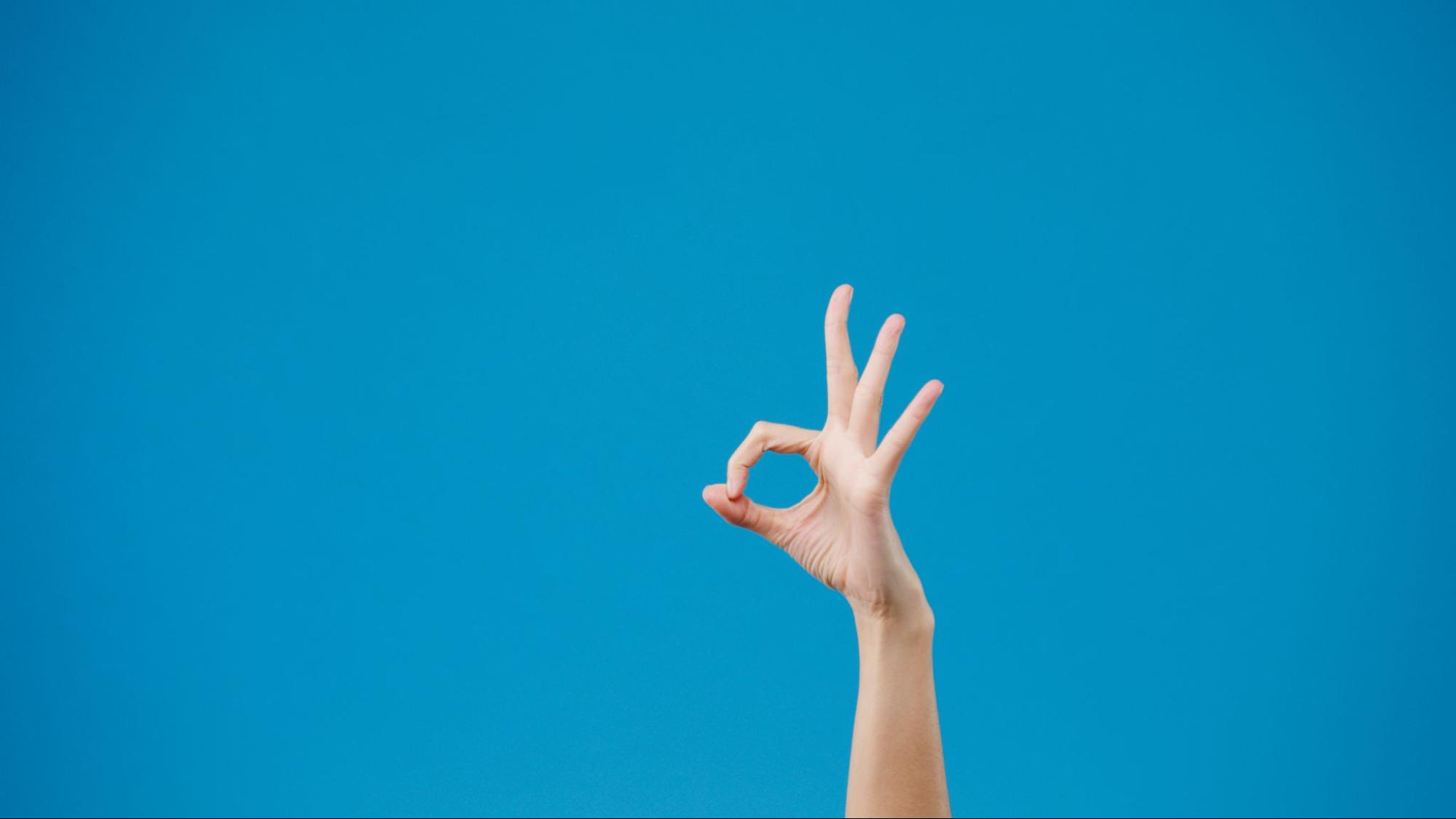
副業禁止規定がある企業でも、不動産投資は許容されるケースがあります。ここでは、不動産投資が副業と区別される理由について解説します。
副業ではなく資産運用と判断される
副業禁止規定に抵触しない理由は、不動産投資が一般的に資産運用とみなされるためです。不動産投資は株式や投資信託と同様、個人の資産を増やすための運用手段と位置づけられています。
特に、物件を購入して賃貸収入を得る形態の場合、日常的な労働を伴わないため『労働による収入』ではなく、『資産からの収益』として扱われます。
やむを得ない事情の場合がある
副業禁止の規定がある場合でも不動産投資が許容される理由の一つに、やむを得ない事情の場合がある点が挙げられます。
例えば、親族から不動産を相続した場合や、所有している物件を賃貸に出さざるを得ない状況など、本人の意思とは関係なく不動産収入が発生するケースがあります。
収益を得ることが主目的ではなく、資産の管理や維持が目的と見なされるため、副業には該当しないと判断されることが多いです。
本業に悪影響を及ぼすリスクが低い
本業に悪影響を及ぼすリスクが低い点も、不動産投資が副業禁止規定に抵触しない理由の一つです。
不動産投資は、管理業務を専門の不動産管理会社に委託することで、日常的な労働や時間的負担を大幅に軽減できます。
投資家自身が直接関与する時間が少なく、本業の勤務時間やパフォーマンスに影響を与える可能性が低いと判断されます。
また、不動産投資は基本的に長期的な資産運用であり、短期的な成果を求めるものではありません。この特性から、本業との両立が比較的容易である点も評価されています。
本業の情報漏洩リスクが低い
不動産投資は、物件の購入や管理を通じて収益を得る仕組みであるため、本業で扱う機密情報や取引先データを利用する必要がありません。
そのため、競業避止義務や情報漏洩の懸念が少なく、会社側も問題視しにくいです。
さらに、不動産投資の多くは管理会社に運営を委託するため、投資家自身が積極的に関与する場面は限られます。
これらの特性により、本業との接点がほとんどなく、情報漏洩につながるリスクを最小限に抑えることが可能です。
副業の不動産投資が問題になるケース

不動産投資は副業として多くのメリットがありますが、場合によっては問題視されることもあります。ここでは、不動産投資が副業として問題になる具体的なケースについて解説します。
事業的規模で行っている
不動産投資が副業として問題視されるケースの一つが、事業的規模で行っている場合です。
具体的には、所有する物件の数が多くなり、管理や運営に日常的な労働が必要となると、副業ではなく事業とみなされる可能性があります。
例えば、5棟10室以上の物件を所有している場合は、税法上も事業的規模と判断されることが一般的です。
事業的規模になると、本業に影響を及ぼすリスクが高まり、会社の就業規則に抵触する可能性があります。
また、管理業務が増えることで本業のパフォーマンス低下や時間的な負担が懸念されます。不動産投資を始める際は、規模を慎重に計画し、本業とのバランスを保つことが重要です。
銀行員や公務員は注意が必要
銀行員や公務員が不動産投資を行う際には、特に注意が必要です。
銀行員の場合、業務上インサイダー情報や機密情報に触れる機会が多いため、金融商品取引や不動産投資を含む副業が厳しく制限されることがあります。
一部の金融機関では、相続などの特別な事情を除いて、不動産投資自体を禁止しているケースもあるため注意が必要です。
一方、公務員は国家公務員法や地方公務員法により、副業が原則禁止されていますが、不動産投資は一定の条件を満たせば認められる場合があります。
具体的には、以下のような条件が挙げられます。
- 5棟10室未満
- 年間家賃収入500万円未満
- 管理業務を委託している
基準を超えると副業とみなされる可能性が高く処分の対象となる場合もあるため、事前に規定を確認し慎重に対応することが重要です。
不動産関連の副業の種類

不動産関連の副業には、以下のような多様な選択肢があります。
- 不動産投資
- 不動産仲介
- 土地活用
不動産投資は、アパートやマンションを購入し、賃貸物件として運用する方法です。家賃収入を得ることで安定した収益が期待でき、資産形成にもつながります。
不動産仲介は、売り手と買い手、または貸し手と借り手を仲介する仕事です。
宅建士の資格があれば独立して行うことも可能ですが、不動産会社と業務委託契約を結べば宅建業免許がなくても始められます。一般的に報酬は歩合制で、成果次第で高収入が期待できます。
土地活用は、余った土地を活用してアパート経営やコインパーキング運営などを行う方法です。初期投資額に応じてさまざまな形態が選べるため、自分の状況に合わせた運用が可能です。
不動産関連の副業には、それぞれ異なるメリットやリスクがあるため、自分に合った方法を慎重に選ぶことが重要です。
副業で不動産投資がおすすめの理由

不動産投資は、手間が少なく本業に集中できる点や、ローンを活用して始められる点など、多くのメリットがあります。
また、節税効果や資産の分散、不測の事態への備えといった側面でも魅力的な選択肢です。ここでは、不動産投資が副業としておすすめされる具体的な理由について詳しく解説します。
手間がかからないため本業に集中できる
不動産投資は、管理業務を管理会社に委託することで、オーナー自身が日常的に物件運営に関与する必要性が少なく手間を大幅に削減できます。
例えば、入居者の募集や契約手続き、家賃の回収、退去時の対応などの煩雑な業務をすべて管理会社が代行してくれるため、本業に専念しやすい環境を作ることが可能です。
また、不動産投資は株式やFXのように値動きを追う必要がなく、長期的な運用が基本となるため心理的な負担も軽減されます。
不動産投資は本業との両立を図りたい会社員や、忙しい方にとって理想的な副業といえるでしょう。
ローンを組んで購入できる
不動産投資が副業としておすすめの理由として、ローンを活用して物件を購入できる点が挙げられます。
不動産投資ローンは、物件そのものが担保となるため、自己資金が少なくても始められるのが特徴です。
特に、安定した収入がある会社員は金融機関からの信用度が高く、有利な条件で融資を受けられる可能性があります。
さらに、ローンを活用することでレバレッジ効果が働き、少ない元手で大きな資産を運用することが可能です。
例えば、家賃収入でローン返済を行いながら、将来的には資産形成や老後の備えとして活用できます。ただし、無理のない返済計画を立てることが重要です。
資産を分散できる
株式や投資信託などの金融商品と異なり、不動産は実物資産であり、経済の変動やインフレの影響を受けにくい特性があります。
この特性により、リスクを分散しながら安定した収益を得ることが可能です。
さらに、不動産は長期的な資産形成に適しており、家賃収入や将来的な売却益を通じて収益を得られる点が魅力です。
本業の収入が金融市場の影響を受けやすい場合でも、不動産投資による収益がリスクヘッジとして機能します。
ただし、物件選びや地域の市場動向を慎重に見極めることが成功の鍵となります。適切な計画を立てることで、効率的な資産運用が実現できるでしょう。
不測の事態に備えられる団体信用生命保険
不動産投資では、ローンを組む際に加入が求められることが多い団体信用生命保険(団信)が、不測の事態への備えとして大きなメリットとなります。
団信は、ローン契約者が死亡や高度障害になった場合に、残りのローン残高を保険会社が肩代わりする仕組みです。
これにより、家族に経済的負担を残さず物件を資産として引き継ぐことが可能になります。
また、最近では病気やケガによる就業不能状態をカバーする特約付きの団信もあり、リスク管理の幅が広がっています。
不動産投資は長期的な運用が基本ですが、このような保険制度を活用することで、予期せぬ事態にも対応できる安心感を得られる点が魅力です。
なお団体信用生命保険料は金利に含まれる場合もありますので、銀行に確認しましょう。
副業で不動産投資をする際のポイント

不動産投資を副業として始める際には、成功させるために押さえておくべきポイントがいくつかあります。
ここでは、不動産投資を始める際に注意すべき具体的なポイントについて詳しく解説します。
信頼して任せられる業者を探す
不動産投資を成功させるためには、信頼できる業者を見つけることが重要です。物件選びや管理業務をサポートしてくれる業者は、投資のパートナーとして非常に重要な役割を果たします。
信頼できる業者を選ぶポイントは以下の通りです。
- 実績や評判を確認する
- 提案内容の具体性と透明性を確認する
- コミュニケーション能力を評価する
- 不動産やリスクについて正確な情報を教えてくれる
業者の実績や評判を確認し、過去の取引事例や顧客からの評価を参考にしましょう。また、提案内容が具体的で透明性があるかどうかも判断基準となります。
さらに、業者とのコミュニケーションも重要です。質問に対して丁寧に答えてくれるか、投資家の立場に立ったアドバイスを提供してくれるかを見極めましょう。
信頼できる業者は、不動産市場の動向やリスクについても正確な情報を提供してくれるため、安心して任せられます。
忘れずに確定申告を行う
不動産投資で得た収入は、確定申告が必要になります。
家賃収入や賃貸経営による利益が発生した場合、必要経費を差し引いた不動産所得が20万円を超える場合には計算の結果納税が発生すれば確定申告することが義務付けられています。
例えば、管理費や修繕費、ローンの利息などは経費として計上可能です。これにより、所得を抑えることが可能です。
確定申告は毎年2月16日から3月15日までに行う必要があります。必要書類を事前に準備し、正確な申告を行うことでトラブルを防ぎ、節税効果を最大限に活用しましょう。
不明点がある場合は、税理士のサポートを受けるのも一つの方法です。
確定申告を楽にしたいと悩む方へ

質問に答えていくだけで、経理の作業がはじめての方でも簡単に確定申告の書類作成をすることができます!
確定申告を楽にサクッとおこないたい方は、freeeがおすすめです!
事前に就業規則を確認しておく
不動産投資を副業として始める際には、必ず所属する会社の就業規則を確認しましょう。
多くの企業では、副業禁止規定や競業避止義務が設けられており、これに違反すると懲戒処分や契約解除のリスクがあります。
特に、不動産投資が事業的規模とみなされる場合や、本業に悪影響を及ぼす可能性がある場合は注意が必要です。
不明点があれば、上司や人事担当者に相談し、許可を得ることでトラブルを未然に防ぐことができます。
本業に支障がない範囲に留める
本業は収入の基盤であり、契約上の義務を果たすことが最優先です。不動産投資を副業として行う際には、本業に支障をきたさない範囲で取り組みましょう。
例えば、物件の管理業務やトラブル対応などに時間を取られ、本業の勤務態度や成果が低下すると、職場での信頼を損ねる可能性があります。
管理業務は信頼できる管理会社に委託し、自分の関与を最小限に抑える工夫が必要です。
スケジュール管理を徹底し、本業の勤務時間外や休日を有効活用して副業に取り組むことが推奨されます。
さらに、不動産投資の規模を拡大する際には、本業とのバランスを見極めながら慎重に計画を立てることが成功の鍵となります。
不動産投資することを伝えておく
副業禁止規定のある企業では、不動産投資が資産運用として認められる場合でも、事前に報告し許可を得ることでトラブルを防ぐことができます。
黙って進めると、後から問題視される可能性があるため注意が必要です。
また、不動産投資を報告することで、会社側から具体的なルールや制限について説明を受けられるため、安心して副業を進められます。
特に、規模の拡大や管理業務の負担が増える場合には、本業への影響が懸念されるため、透明性を保つことが信頼関係を維持するポイントです。
適切な準備と計画が不動産投資の成功の秘訣
不動産投資は、副業禁止規定がある企業でも資産運用として認められることが多い魅力的な選択肢です。手間が少なく、節税効果や資産分散のメリットがありますが、以下の点に注意が必要です。
- 事業的規模での運営は避ける
- 就業規則を確認し、必要に応じて会社に報告する
- 必要な場合確定申告を忘れずに行う
- 本業に支障をきたさない範囲で取り組む
適切な準備と計画を行い、リスクを理解しながら取り組むことで、不動産投資を成功に導くことができるでしょう。
スキマ時間を有効活用!副業に興味を持ったら、まずは「起業の窓口」に登録してみよう
副業で収入アップを考えている方も多いと思いますが「時間がない」と感じて諦めている方も多いのではないでしょうか。しかし、スキマ時間を上手く利用して副業をすることで、本業とは異なる収入源を持つことが可能です。
起業の窓口では、スキマ時間に手軽に始められるおすすめの副業やメール、SNS、AIを活用した副業、必要なノウハウなど、さまざまなコンテンツを無料でご提供。また、GMOインターネットグループが展開する副業に役立つ各種サービスをおトクな特典付きでご紹介しています。
副業から起業を目指す人にもオススメです。
- 記事監修
-
- 中野 裕哲 HIROAKI NAKANO
- 起業コンサルタント(R)、経営コンサルタント、税理士、特定社会保険労務士、行政書士、サーティファイドファイナンシャルプランナー・CFP(R)、1 級FP 技能士。 V-Spiritsグループ創業者。東京池袋を本拠に全国の起業家・経営者さんを応援!「あの起業本」の著者。著書16冊、累計20万部超。経済産業 省後援「DREAMGATE」で11年連続相談件数日本一。
- ※本記事は、起業の窓口編集部が専門家の監修または独自調査(アンケート)に基づいて制作したものです。
- ※掲載している情報は、記事公開時点の法令・税制・商品・サービス等に基づくものであり、将来的に変更される可能性があります。
- ※アンケート調査に関する記述は、特定の調査対象者からの回答結果および編集部の見解を含んでおり、内容の正確性・完全性を保証するものではありません。
- ※記事の内容は一般的な情報提供を目的としており、すべての方に当てはまるものではありません。個人の状況に応じた具体的な助言が必要な場合は、専門家にご相談ください。
- ※情報の利用や判断、実施については、ご自身の責任で行っていただきますようお願いいたします。
- ※本記事に掲載された内容の転載・複製はご遠慮いただき、引用の際は必ず出典をご明記ください。



 シェア
シェア