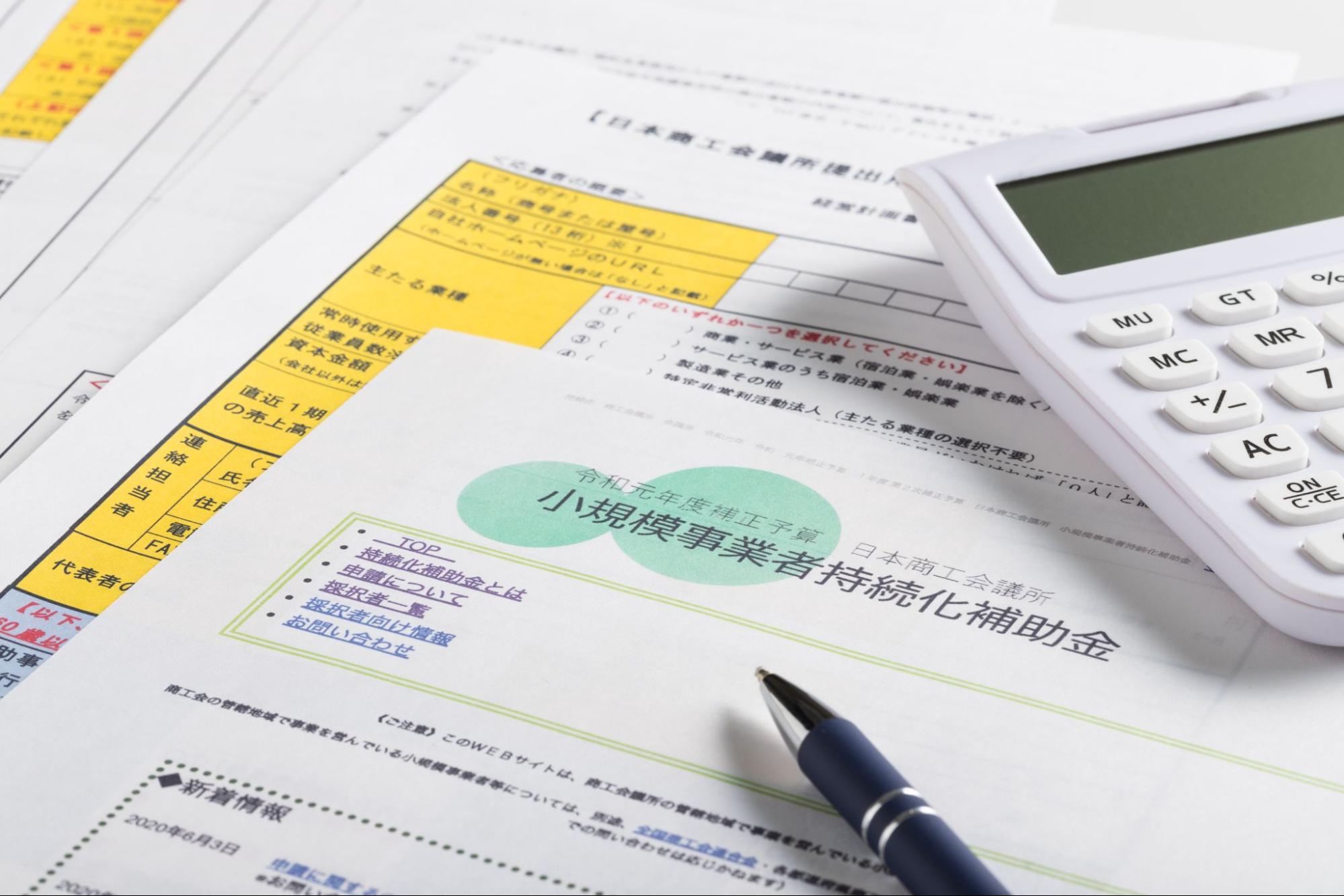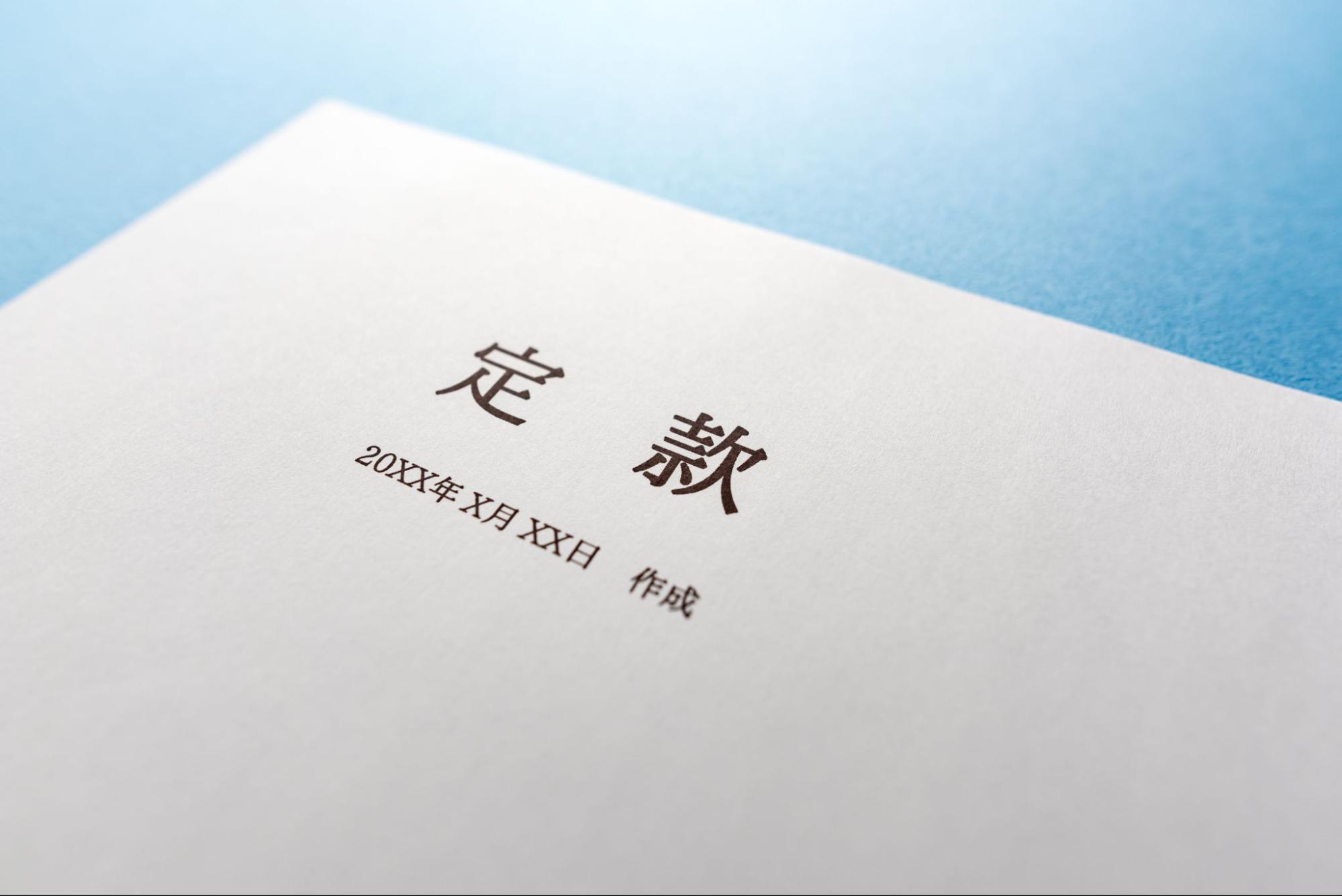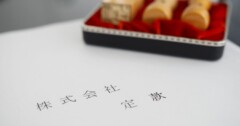法人税の計算方法|法人税率とは?税率やシミュレーションを徹底解説

本記事では、法人税とはどのように計算されるのか、計算方法から実際にシミュレーションを行った金額、そのほか節税対策の考え方まで詳しく説明していきます。
- 【この記事のまとめ】
- 法人税は企業の収益に対する税金で、利益は売上から原価や費用を引いて算出されます。税務調整後に法人税が課せられます。
- 法人税は4ステップで計算します。利益を算出し課税所得を算出、法人税率を確認し、納税額を求める流れが重要です。
- 法人税率は資本金や所得により異なり、中小企業には優遇措置があります。各企業の条件を確認することが重要です。
確定申告を楽にしたいと悩む方へ

質問に答えていくだけで、経理の作業がはじめての方でも簡単に確定申告の書類作成をすることができます!
確定申告を楽にサクッとおこないたい方は、freeeがおすすめです!
法人税とは?法人にかかる税金の種類

法人の事業活動によって生じる税金には、主に次のような種類があります。
- 法人税
- 地方法人税
- 法人住民税
- 法人事業税
- 特別法人事業税
- 消費税
これらの税金の詳細を1つずつ詳しく解説します。
1.法人税
法人税とは、法人の所得に対して国に納める税金のことです。
法人の所得金額は、収益にあたる益金から、費用にあたる損金を差し引いて算出します。
法人税の税率は以下のとおりです。
| 区分 | 適用関係(開始事業年度) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 平28.4.1以後 | 平30.4.1以後 | 平31.4.1以後 | 令4.4.1以後 | ||
| 年800万円以下の部分 | 下記以外の法人 | 15% | 15% | 15% | 15% |
| 適用除外事業者 | 19% | 19% | |||
| 年800万円超の部分 | 23.40% | 23.20% | 23.20% | 23.20% | |
2024年12月時点の法人税率は、23.20%となっています。ただし、年800万円以下の所得金額部分については、15%の軽減税率が適用されます。
国の財政状況や経済情勢などを踏まえて、法人税率は変動してきました。直近では、法人の「稼ぐ力」を高めるため、課税ベースの拡大と税率引き下げが行われています。
法人税は国の重要な財源の1つであり、その税率は経済政策と密接に関係しています。
2.地方法人税
地方法人税は、平成26年度の税制改正によって創設された税金で、法人住民税の一部として国税化されたものです。
法人税と混同されがちですが、地方法人税と法人税は異なる税金なので注意が必要です。法人税は国の財政収入となるのに対し、地方法人税は地方交付税の原資となり、地方団体の財源として活用されます。
地方法人税は、地域間の税源偏在の是正や財政力格差の縮小を目的としているのです。
地方法人税の税率は現在10.3%で、令和元年10月1日以後に開始する事業年度から適用されています。
3.法人住民税
法人住民税は、都道府県と市町村が法人に課す税金で、法人等が事務所や事業所を置く地域の会費的な性質を持っています。
法人住民税は個人にかかる住民税と似ており、法人等の所在地の都道府県と市町村に納めます。「法人税割」と「均等割」の2種類があり、それぞれ税額の計算方法が異なります。
- 法人税割:法人税額を基準に、一定の税率をかけて計算
- 均等割:法人の資本金等の額や従業員数に応じて決定
4.法人事業税
法人事業税は、法人等の事業活動に対して都道府県が課す税金です。
法人が事業活動を行う際に、都道府県から受ける行政サービスの対価と位置付けられています。
法人の業種や所得等に応じて、「付加価値割」「資本割」「所得割」「収入割」の計4種類の税目があります。
各事業年度の所得金額や収入金額、従業員への給与総額などを課税標準として、それぞれの税率を乗じて税額を計算します。
- 付加価値割:各事業年度の付加価値額を課税標準として計算
- 資本割:法人の資本金等の額を課税標準として計算
- 所得割:法人の各事業年度の所得を課税標準として計算
- 収入割:各事業年度の収入金額を課税標準として計算
法人事業税の税率は業種によって異なり、例えば電気供給業やガス供給業では収入金額が課税標準となるなど、それぞれの特性に応じた課税方式が採られています。
5.特別法人事業税
特別法人事業税は、令和元年10月1日以後に開始する事業年度から導入された税金で、法人事業税の一部が分離独立したものです。
特別法人事業税の課税標準は、法人事業税の所得割と収入割の税額を基準として計算します。計算式は以下のとおりです。
法人事業税の所得割額×特別法人事業税の税率=特別法人事業税額
税率は法人の種類によって異なり、外形標準課税の対象法人では260%、それ以外の法人では37%などと定められています。
申告や納付の手続きは、法人事業税と一体で行います。
6.消費税
消費税は、国税と地方税からなる税金で、商品の販売やサービスの提供など、幅広い取引に対して課税されます。
最終的には消費者が負担し、納税義務は事業者が負います。仕入税額控除の仕組みにより、各取引段階で二重に税金がかかることはありません。
消費税の標準税率は10%(消費税7.8%、地方消費税2.2%)ですが、一部の取引には8%の軽減税率が適用されます。
課税事業者は、取引ごとの消費税を集計し、確定申告および納付を行う必要があります。
法人税の税率

法人税の税率は、企業の資本金や所得に応じて変動し、主に次の区分に応じて制定されています。
普通法人の税率
普通法人とは、法人税法上で規定されているもので、株式会社や有限会社、合同会社などが含まれます。
| 資本金 | 所得金額 | 法人税率 |
|---|---|---|
| 1億円超の普通法人 | – | 23.20% |
| 1億円以下の普通法人 | 年800万円以下の部分 | 15.00% |
| 年800万円以上の部分 | 23.20% |
資本金が1億円以上の普通法人では所得金額にかかわらず一律23.20%です。一方資本金1億円以下の場合、800万円以下の所得までは15%、それ以上からは23.20%が課せられます。
また、上記の表は平成31年4月1日以降に事業を開始した普通法人に当てはまり、それ以前に開業している企業に関しては税率が異なります。それ以前の税率については、国税庁のサイトで確認しましょう。
普通法人以外の税率
普通法人に当てはまらない、協同組合や公益法人、特定の医療法人はそれぞれ以下の税率が充てられます。
| 対象 | 所得金額 | 法人税率 |
|---|---|---|
| 協同組合 | 年800万円以下の部分 | 15.00% |
| 年800万円以上の部分 | 19.00% | |
| 公益法人 | 年800万円以下の部分 | 15.00% |
| 年800万円以上の部分 | 23.20% | |
| 人格のない社団 | 年800万円以下の部分 | 15.00% |
| 年800万円以上の部分 | 23.20% | |
| 特定の医療法人 | 年800万円以下の部分 | 15.00% |
| 年800万円以上の部分 | 19.00% |
※公益法人や人格のない社団については、収益事業から生じた所得にのみ課税されます。
協同組合や特定の医療法人は、連結親法人である場合などで税率は異なります。公益法人では、公益法人とみなされていない団体などの場合は税率が異なります。また、企業によっては適用除外事業者として認定されている場合もあります。
企業がどの区分に属するか不明の方は、国税庁の電話相談窓口もあるため、そちらで確認するとよいでしょう。
法人税の計算方法

法人税の仕組みは複雑です。まずは、法人税の計算方法を確認しましょう。
次の4つのステップで説明していきます。
- 利益を計算する
- 課税所得を算出する
- 法人税率を確認する
- 納税額を算出する
1.利益を計算する
企業が事業活動をして得た実際の儲けのことを利益といいます。利益額の計算では、各事業年度の収益から費用を差し引いた金額を算出します。差し引く費用は、商品仕入れなどの原価、販売までにかかった人件費や広告費、家賃などです。
収益から費用を引いた額が会計上の利益となります。期中に会計処理を積み重ね、最終的に損益計算書で会計上の利益額を表します。
2.課税所得を算出する
次に、法人税にかかる所得を確認します。課税所得は、益金から損金を差し引いて算出します。益金、損金とは、法人税法に基づいて事業年度ごとの会計上の利益を調整したものです。
具体的には、益金は商品やサービス提供の収益、株や土地などの譲渡益など、損金は商品の原価や販売費、管理費などを指します。ここで注意しておきたいのが、利益を割り出す上で行った会計と法人税計算のために行った会計では数字が異なる点です。これは公平性を保った税金を徴収するため、法律に則って調整を行うために違いが出ます。
3.法人税率を確認する
続いて、法人税率を確認します。法人税率は、事業内容や利益、資本金によって各企業で異なります。15%以下、もしくは23.20%の税率が当てはまります。
中小企業の場合には法人税の軽減措置があり、資本金が1億円以下や他社との関係性など条件を満たした場合に適用されます。その他、協同組合の場合では税率がやや低くなり、課税所得が800万円以上の場合、19%となっています。
どの税率が適用となるかは、国税庁のサイトで調べるなどしてチェックしましょう。
4.納税額を算出する
最後に、算出した課税所得と法人税率を掛け合わせて、納税額を算出します。益金が3,000万円で損金が1,000万円の企業の場合で、具体的に計算してみます。
益金3,000万円から損金1,000万円を引いて、課税所得は2,000万円です。この2,000万円のうち、800万円の部分までの法人税率は15%、残りの1,200万円の法人税率は23.20%で計算します。120万円と278.4万円を足して398.4万円です。
結果、納税額は398.4万円ということになります。
法人税のシミュレーション

事業を行う中で、「実際に今、会社にかかっている法人税がいくらぐらいか知りたい」「これからどのくらいの利益を出したら法人税が加算されるのか把握したい」ということもあるでしょう。
インターネット上では、以下のようなざっくりとした金額を算出してくれるWebサイトがあります。
資本金と利益額を入力するだけで、法人税などをシミュレーションして計算します。参考までに使用してみてください。
資本金:1,000万以下
繰越欠損金:0円
税引前当期純利益:500万円
法人税:75万円
ほか
地方法人税:77,200円
法人事業税:264,400円
法人住民税:122,500円
資本金:1億円以下
繰越欠損金:0円
税引前当期純利益:1000万円
法人税:166万4,000円
ほか
地方法人税:171,300円
法人事業税:674,000円
法人住民税:296,400円
法人税が課税される法人と課税されない法人

法人の目的や特性により、法人税が軽減されたり、課税されなかったりする法人があります。条件は以下のとおりです。
法人税が課税される法人
普通法人や協同組合などは、原則法人税が課税されます。ただし、条件により法人税は軽減されています。
普通法人とは、株式会社・有限会社・医療法人・相互会社・企業組合・日本銀行などです。協同組合には、農業協同組合・信用金庫・労働者協同組合などが当てはまります。
| 普通法人 | 原則法人税が課税されますが、 中小法人(資本金1億円以下)は税率が軽減されます |
|---|---|
| 協同組合 | 原則法人税が課税されますが、 税率が軽減されます |
法人税が課税されない法人
公共法人や公益法人、人格のない社団などは、収益事業を除き法人税が課税されません。公共法人とは地方公共団体・金融公庫・事業団など、公益法人とは・財団法人・宗教法人・学校法人・社会福祉法人などが挙げられます。
また、人格のない社団とはPTA・同窓会・実行委員会などで、法律上の法人ではありませんが税法上では法人とみなされる団体です。
| 公共法人 | 非課税です |
|---|---|
| 公益法人 | 原則法人税は課税されませんが、 収益事業から生じた法人税には課税されます |
| 人格のない社団 | 原則法人税は課税されませんが、 収益事業から生じた法人税には課税されます |
法人税の対象期間と申告期限

法人税は、法人の事業年度ごとに計算し納付します。
事業年度とは、法人の決算期間のことで、定款で自由に決められます。
個人事業主の場合は暦年(1月1日〜12月31日)が原則ですが、法人は1年以内の任意の期間を設定できるのです。
ただし、決算事務の負担を避けるため、繁忙期と重ならないよう設定する必要場合があります。事業年度終了日の翌日から2ヶ月以内が申告の期限となります。
法人税は、中間申告と確定申告に分けて納付するのが基本です。
中間申告の納付期限は事業年度開始から6ヶ月経過した日から2ヶ月以内、確定申告は事業年度終了の翌日から2ヶ月以内です。前事業年度の税額が20万円以下の場合や設立初年度は、中間申告が免除されます。
申告期限の延長を希望する場合は、定款で「事業年度終了後3ヶ月以内に定時株主総会を開催する」と定め、所轄税務署に申請すれば1ヶ月の延長が認められます。
ただし、納付期限は延長されないので、見込み税額を期限内に納付する必要があります。期限内に納付しなかった場合、利子税が発生するため注意が必要です。
法人税の納付が遅れた場合のペナルティ

ここでは、法人税の納付が遅れたり申告に不備があったりした場合のペナルティについて解説します。
延滞税が発生する
法人税の納付期限を過ぎると、完納するまでの期間に応じて延滞税が課されます。
延滞税とは、納付遅延に対する一種の利息のようなものです。
納付期限から2ヶ月以内に完納すれば、年7.3%または延滞税特例基準割合+1%のどちらか低い方の割合で計算されます。
しかし、2ヶ月を超えると、年14.6%または延滞税特例基準割合+7.3%のいずれか低い方の高税率となるため、少しでも早く納付することが大切です。
納付すべき税額に延滞税の割合と延滞日数をかけ、それを365(年間日数)で割ると、延滞税額が算出されます。
納付が遅れるほど、延滞税の負担が増大する点に注意が必要です。
各種加算税が課される
法人税の申告漏れや申告内容の不備などがあると、ペナルティとして加算税が課されます。
加算税には、過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税、重加算税の4種類があります。
| 名称 | 課税要件 | 課税割合 |
|---|---|---|
| 過少申告加算税 | 期限内申告について、修正申告・更正があった場合 | 10%・15% |
| 無申告加算税 | 1:期限後申告・決定があった場合 2:期限後申告・決定について、修正申告・更正があった場合 |
15%・20%・30% |
| 不納付加算税 | 源泉徴収等による国税について、法定納期限後に納付・納税の告知があった場合 | 10% |
| 重加算税 | 仮装隠蔽行為があった場合 | 35%・40% |
引用:加算税の概要|財務省
申告漏れや申告内容の不備があった場合、ペナルティとして加算税が課される可能性があります。
また、申告内容に故意の隠蔽や仮装があった場合は、ペナルティがさらに重くなります。
差し押さえのリスクがある
上記のペナルティを課されても納税に応じない場合、再三の督促の後、法人の財産が差し押さえられるリスクがあります。
差し押さえられた不動産や動産、債権などは現金化され、滞納している法人税の支払いに充てられます。事業継続への影響も大きいため、絶対に避けなければなりません。
また、申告や納付の遅れなどを繰り返していると、青色申告の承認取り消しを受ける恐れもあります。メリットの多い青色申告を失うことで、節税面での不利益が生じてしまいます。
これらのペナルティを受けないためには、余裕を持った資金繰りや期限管理を徹底することが大切です。
法人税の節税方法

法人税の節税には、さまざまな手法があります。ここでは、経費計上や制度の活用など、代表的な節税方法を7つ紹介します。
損金を増やす
損金は、会社の資産を減らす原価や費用、損失です。益金から損金を差し引いたものが法人税の課税所得となるため、損益を増やすことが課税所得を減らすことに繋がります。
実際にかかった費用のすべてが損金として認められるわけではないため、損金として計上できるものをもれなく計上することが節税対策で重要となってきます。
例えば、必要な備品を購入したり、接待交際費や役員への報酬を損金として計上したりする、中小企業倒産防止共済制度(経営セーフティ共済)を活用するなどの方法です。
益金を減らす、つまり会社の売上を調整するということはもちろんNGですが、損金を漏れなく計上するということは重要なポイントです。
特別控除を利用する
特別控除の仕組みを活用すれば、法人税の負担が軽くなります。特別控除とは、本来納めるべき法人税の金額から一定の金額を控除できる特例で、条件を満たす法人に対して適用されます。
特別控除には、中小企業投資促進税制、中小企業経営強化税制、商業・サービス・農林産業活性化税制、中小企業防災・減災投資促進税制、所得拡大税制など、さまざまな税制が存在します。
活用できる控除がないか確認しておきましょう。また制度の活用には、青色申告が必要など複数の条件が含まれているため、よく内容を確認しておくことも大切です。
法人税の軽減措置を利用する
中小法人に対して、法人税の軽減措置が利用できます。条件としては、資本が1億円以下で資本金5億円以上の法人と支配関係がない中小法人が対象です。
法人税が所得の800万円以下の部分について、本来なら15%のところを19%で計算されます。軽減税率に加えて、貸倒引当金や欠損金関係、留保金課税などの部分に関して中小法人向けの税制があり、さまざまな軽減措置を受けることができます。
従業員の家を社宅にする
会社が社宅を借り上げ、従業員に貸し出すことで節税効果が期待できます。会社が支払う家賃と、従業員から受け取る賃料との差額を、会社の経費として計上できるのです。
ただし、社宅とするためには、物件の賃貸契約を会社名義で結び、従業員からも適正な賃料を受け取る必要があります。賃料が無料や著しく低額だと、現物支給として課税対象となるため注意が必要です。
一方、従業員にとっても家賃負担が軽減されるメリットがあります。福利厚生の充実は、優秀な人材の確保にも繋がるでしょう。
旅費日当を支給する
出張の際、宿泊費や交通費以外にかかる食事代や雑費などを旅費日当として支給し、経費計上することで節税効果があります。
個人事業主の場合、事業主本人の旅費日当は経費にできませんが、法人であれば経営者の分も計上可能です。
ただし、旅費日当の支給額は、社内規程に基づき妥当な金額に設定する必要があります。規程から著しく乖離した支給は、経費としての正当性を問われる恐れがあるのです。
適切な金額の旅費日当であれば、会社は経費算入でき、経営者は非課税で受け取れます。出張旅費規程を整備したうえで、旅費日当の活用を図りましょう。
赤字を繰り越す
法人税の計算上、赤字が発生した場合、青色申告を行っていれば最長10年間の繰越が可能です。翌期以降に黒字となった際、過去の赤字と相殺することで、法人税の節税に繋げられるのです。
さらに一定の条件を満たせば、前期が黒字で当期が赤字の場合、前期に遡って赤字と相殺し、法人税の還付を受けられる制度もあります。これは、「欠損金の繰戻しによる還付」と呼ばれるものです。
ただし、赤字であっても法人住民税の均等割は課税されてしまいます。赤字を出さないよう、業績改善に努めることが重要といえます。
中小企業倒産防止共済制度に加入する
中小企業倒産防止共済は、取引先の倒産に備える共済制度です。掛金の支払いを損金算入でき、節税に寄与します。
共済に加入していれば、取引先が倒産した際、無担保・無保証で掛金の10倍(上限8,000万円)まで即座に借入できます。売掛金の回収が困難になっても、資金繰りの安定化を図れるのです。
掛金は月額5,000円から20万円の間で設定でき、掛金総額が800万円に達するまで積み立てられます。余剰資金の運用先としても効果的です。
節税メリットを享受しつつ、万一の際の資金調達手段を確保しておきましょう。
まとめ

法人税は企業の所得に対する税金で、法人住民税や法人事業税などと一緒に納税する必要があります。
計算方法は複雑ですが、利益の算出、課税所得の計算、税率の確認、納税額の算出という4つのステップに分けて理解するのが有効です。
法人税率は企業の資本金や所得によって異なり、中小企業には軽減措置が設けられています。シミュレーションで概算額を把握しつつ、節税対策にも取り組みましょう。
損金算入の活用、特別控除制度の利用、赤字繰越の適用など、さまざまな節税手法があります。
納税額を適正に保つためにも、税理士など専門家のアドバイスを受けながら、計画的に納税を進めることが大切です。
確定申告を楽にしたいと悩む方へ

質問に答えていくだけで、経理の作業がはじめての方でも簡単に確定申告の書類作成をすることができます!
確定申告を楽にサクッとおこないたい方は、freeeがおすすめです!
起業や独立を考えている方に朗報
起業・経営のプロ監修のオリジナル冊子『会社設立完全ガイド』を無料でプレゼント!
「起業の窓口」では、起業に必要なノウハウや成功者のインタビュー、経理や会計の基礎知識など、さまざまなコンテンツを完全無料で提供しています。また、GMOインターネットグループが展開するビジネスの立ち上げや拡大に役立つ各種サービスをおトクな特典付きでご紹介しています。
会社設立や資金調達などのノウハウが詰まった『会社設立完全ガイド』をGETして、夢の実現への一歩を踏み出してみませんか?
- 記事監修
-
- 中野 裕哲 HIROAKI NAKANO
- 起業コンサルタント(R)、経営コンサルタント、税理士、特定社会保険労務士、行政書士、サーティファイドファイナンシャルプランナー・CFP(R)、1 級FP 技能士。 V-Spiritsグループ創業者。東京池袋を本拠に全国の起業家・経営者さんを応援!「あの起業本」の著者。著書16冊、累計20万部超。経済産業 省後援「DREAMGATE」で11年連続相談件数日本一。
- ※本記事は、起業の窓口編集部が専門家の監修または独自調査(アンケート)に基づいて制作したものです。
- ※掲載している情報は、記事公開時点の法令・税制・商品・サービス等に基づくものであり、将来的に変更される可能性があります。
- ※アンケート調査に関する記述は、特定の調査対象者からの回答結果および編集部の見解を含んでおり、内容の正確性・完全性を保証するものではありません。
- ※記事の内容は一般的な情報提供を目的としており、すべての方に当てはまるものではありません。個人の状況に応じた具体的な助言が必要な場合は、専門家にご相談ください。
- ※情報の利用や判断、実施については、ご自身の責任で行っていただきますようお願いいたします。
- ※本記事に掲載された内容の転載・複製はご遠慮いただき、引用の際は必ず出典をご明記ください。
関連記事
- 会社設立・法人化の新着記事
- 会社設立・法人化の人気記事ランキング
- タグリスト
- AI×起業
- AI×起業特集はこちら
- 起業家インタビュー
- 起業家インタビュー一覧はこちら
- 監修者・執筆者一覧
- 監修者・執筆者一覧はこちら
30秒で簡単登録
厳選サービスを特典付きでご紹介



 シェア
シェア