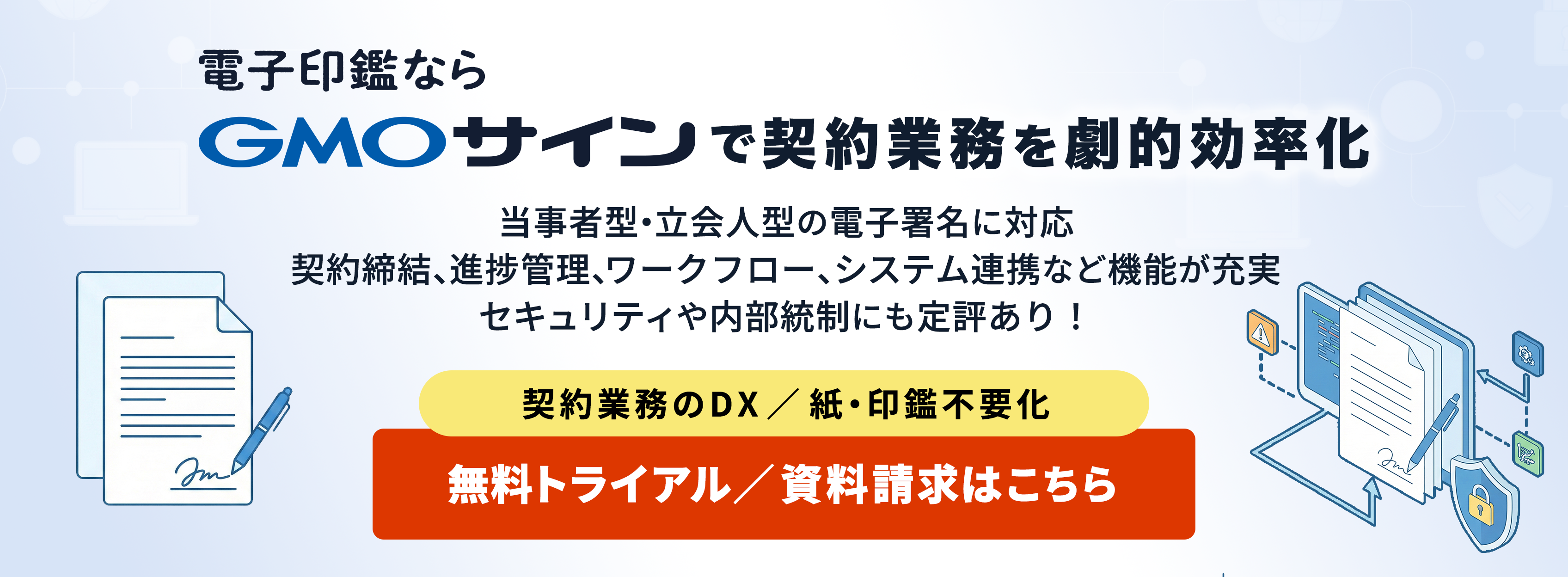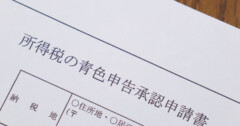印紙税を削減するには?コストカットの具体例や電子契約のメリット・デメリットを解説

印紙税は、契約書や領収書など特定の文書に課される国税ですが、その仕組みや課税対象となる文書、税額の計算方法は複雑で分かりにくい部分があります。
この記事では、印紙税の基本的な概要から、課税文書に該当する書類の種類や収入印紙の金額、そして印紙税の節約方法までを分かりやすく解説しています。
電子契約の普及に伴い印紙税の負担を減らす方法も増えているため、最新の対応策も含めて理解を深めましょう。
- 【この記事のまとめ】
- 印紙税とは契約書や領収書などの文書に課せられる国税です。
- 課税文書の種類や記載された金額によって、収入印紙の金額が異なります。
- 課税文書の印紙税を削減するには、電子データ化が最も効果的な方法です。
【重要】印紙税とは

印紙税とは、契約書や領収書などの「課税文書」に対して課される国税の一つです。
これらの文書を作成する際に必要な収入印紙を貼付し、その分の税金を納付する義務があります。印紙税は、契約の当事者が経済的利益を得ることを理由に課され、適正な納税を促すことで経済活動の透明性を保つ役割を持っています。
収入印紙が必要な課税文書
収入印紙の貼付が義務付けられている文書は、印紙税法に定められた課税文書に該当するものです。
主に、不動産売買契約書や請負契約書、金銭消費貸借契約書、運送契約書、約束手形など20種類の文書が対象です。これらの文書は、契約金額や内容に応じて収入印紙の税額が変わります。
収入印紙の金額
収入印紙の金額は、文書の種類や記載された契約金額によって異なります。
例えば、不動産売買契約書の場合、契約金額が1万円未満は非課税ですが、1万円以上10万円以下なら200円、1,000万円を超えると2万円、さらに高額になると数十万円に達するケースもあります。
金額は印紙税額の一覧表で定められており、契約の内容や金額によって適切な収入印紙を貼る必要があります。
課税文書に該当しなければ収入印紙は不要
すべての契約書が収入印紙の対象となるわけではありません。
課税文書に該当しなければ、収入印紙の貼付は不要です。
国税庁によって、以下の文書が非課税文書として定められています。
- 課税物件表内の非課税文書欄に該当する文書
- 国・地方公共団体・印紙税法別表第二に掲げるものが作成した文書
- 印紙税法別表第三に記載される文書を、該当する人物が作成した場合
- 特別の法律により非課税とされる文書
引用:国税庁(印紙税の手引)
また、電子契約のように、紙の課税文書を作成しない契約形態では印紙税の課税対象外となり、結果として印紙税の負担軽減が可能です。
【手順】課税文書の印紙税を削減するための方法

課税文書にかかる印紙税はさまざまな方法で削減可能です。
- 契約書や領収書を電子データ化する
- 契約金額と消費税額を分けて記載する(第1号・2号・17号文書)
- 契約期間を3ヶ月以内にして非課税要件を満たす(第7号文書)
- 契約書のコピーで対応する
- 印紙税を相手方に負担させる
- 契約書を作成しない
- 海外で契約する
- 金券ショップで収入印紙を買う
特に電子契約の導入や契約書の記載方法の工夫、管理方法など、実務で取り組みやすい節税策が多数あります。
ここでは、課税文書の印紙税を削減する方法を詳しく解説します。
なお、文書の種類によって適用の可否が分かれるため、国税庁の「No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで」と「No.7141 印紙税額の一覧表(その2)第5号文書から第20号文書まで」をご覧ください。
契約書や領収書を電子データ化する
電子契約や契約書の電子データ化は、収入印紙の貼付が不要となる最も効果的な印紙税の削減方法です。
紙の契約書が不要になるため印紙代のみならず、紙・郵送費・保管コストも削減できます。
電子契約は法的にも有効で、国税庁も認めているため安心して活用できます。
契約金額と消費税額を分けて記載する(第1号・2号・17号文書)
契約書の記載金額を税込一括ではなく、税抜金額と消費税額等に分けて書くことで印紙税の金額を節約できる場合があります。
例えば、契約金額が1,000万円の場合、税込1,100万円と書くより税抜1,000万円、消費税100万円と分けて記載したほうが印紙税を低く抑えられます。
ただし、第1号、第2号、第17号の課税文書にのみ適用可能です。
契約期間を3ヶ月以内にして非課税要件を満たす(第7号文書)
第7号文書の継続的取引の基本となる契約書は、契約期間が3ヶ月以内かつ更新の定めがなければ非課税となります。
例えば、契約期間を短く設定し、更新条項を記載しなければ印紙税が不要です。
ただし、頻繁な契約更新が必要となるため長期契約には不向きです。
契約書のコピーで対応する
契約書の原本には収入印紙が必要ですが、単なる写し(コピー)には印紙税は課されません。
契約当事者が原本1通に印紙を貼り、関係者にはコピーを配布することで印紙代の削減が可能です。
ただし、コピーに「原本と相違なし」などの証明書きがある場合は課税の対象になるため注意が必要です。
印紙税を相手方に負担させる
法律上、印紙税の負担者は定められていないため、契約交渉により相手方に印紙代の負担を求めることが可能です。
一般的には双方が各々の契約書に貼付しますが、交渉次第で印紙税負担を調整できます。ただし、下請法等の適用がある場合は慎重な対応が求められます。
契約書を作成しない
契約は口頭でも成立するため、契約書を作らなければ印紙税は発生しません。
しかし、書面のない契約は証拠不足となるリスクがあり、トラブル防止や信頼性確保の観点から通常は推奨されません。
海外で契約する
印紙税は国内で作成された文書に課されるため、契約の最終締結を海外で行うと印紙税は不要となります。
海外での契約締結は節税策として有効ですが、法的効果や実務面の影響を十分検討したうえで実施すべきです。
金券ショップで収入印紙を買う
金券ショップでは収入印紙を1〜2%割引で購入できることがあり、わずかな節約につながります。
ただし、高額印紙の在庫不足や偽物のリスクがあるため、信頼できる店舗を選ぶことが重要です。
急ぎの場合は郵便局など正規の販売窓口を利用しましょう。
印紙税の削減以外にもある電子契約のメリット

電子契約は印紙税の削減だけでなく、以下のようなさまざまなメリットがあります。
- 契約業務の効率化ができる
- 印刷・郵送コストを削減できる
- 管理が楽になる
- 社内にいなくても契約業務を行える
- コンプライアンス強化も可能
ここでは、電子契約によって得られる印紙税の削減以外のメリットについて解説します。
契約業務の効率化ができる
電子契約は契約の作成、署名、送信、保管といった全てのプロセスをオンラインで完結できるため、紙の契約書に比べて大幅に作業時間を短縮できます。
押印や郵送の手間がなくなり、担当者の工数削減が可能です。
また、契約の修正や再送付も迅速に行えるため、業務の停滞を防ぎ、迅速な意思決定をサポートします。
印刷・郵送コストを削減できる
紙の契約書では印刷費や封筒代、郵送費などのコストがかかりますが、電子契約を利用すればこれらの物理的なコストをゼロにできます。
多くの契約書を遠隔地とやり取りする企業にとっては郵送費の削減効果が特に大きく、経費削減に直結するでしょう。
また、契約書の保管場所や管理コストも削減でき、オフィススペースの有効活用にも寄与します。
管理が楽になる
電子契約システムには契約書の検索、分類、保存機能が備わっており、紙の書類管理に比べて効率的に契約情報を管理できます。
また、契約履歴や締結状況がリアルタイムで把握できるほか、再発行や確認作業も簡単に行え、紛失リスクがほぼなくなります。クラウドによる一元管理が標準化されているため、複数拠点での契約管理もスムーズです。
社内にいなくても契約業務を行える
電子契約は、インターネット環境さえあれば、リモートワーク中や出張先、自宅などどこからでも契約を締結できます。
押印のための出社が不要になり、業務の柔軟性が大幅に向上します。特に昨今の働き方の多様化に対応でき、緊急時でも即時に契約を締結できるためビジネスチャンスを逃しません。
コンプライアンス強化も可能
電子契約では、タイムスタンプや電子署名により契約書の改ざん防止と真正性の担保が可能です。
契約締結履歴や操作ログの記録が付与されるため、内部統制や監査対応が容易になります。
また、アクセス権限管理や高度な暗号化技術により情報漏洩リスクも低減され、法令遵守や企業の信頼性向上に役立ちます。
【注意】電子契約のデメリット
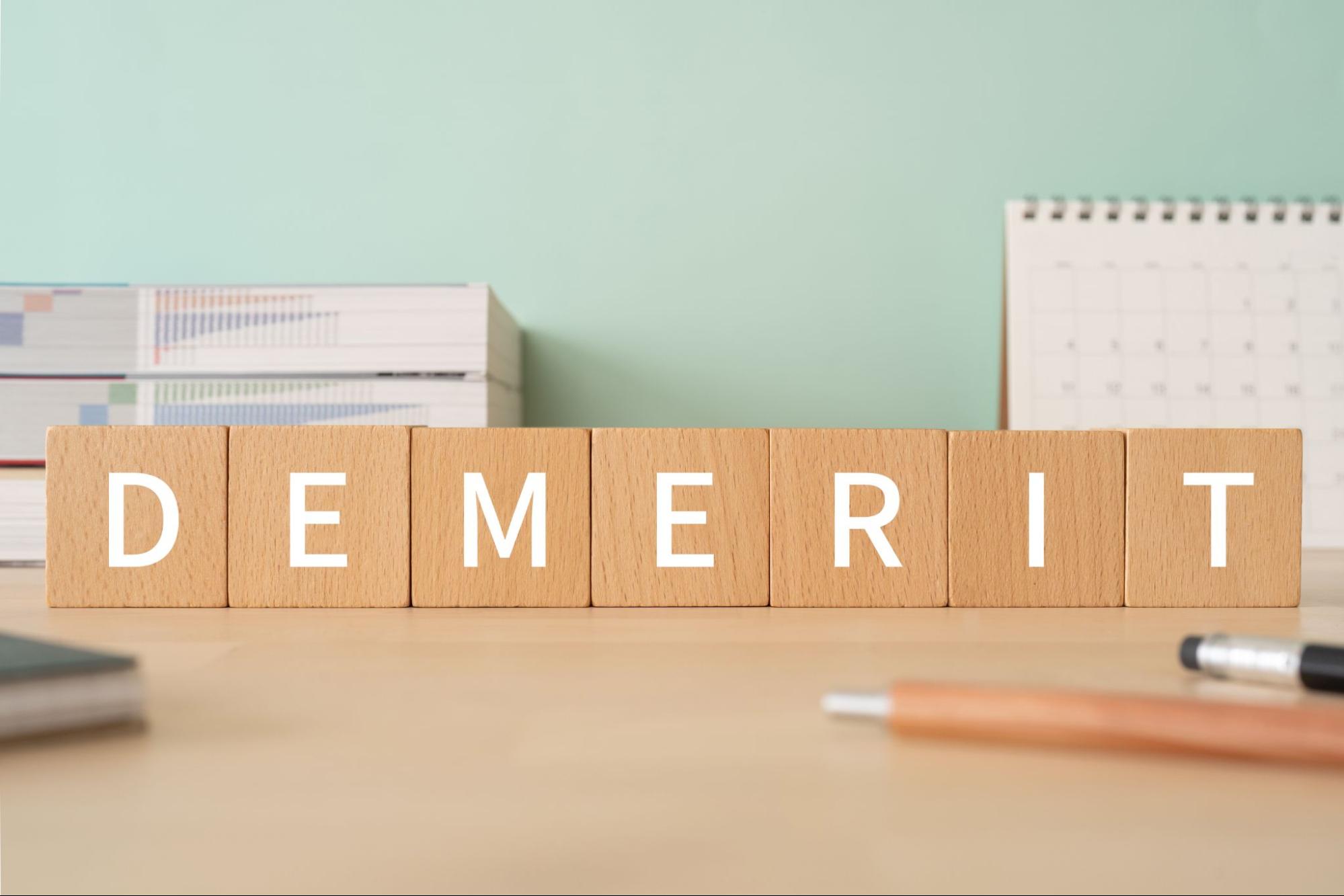
電子契約は多くのメリットがありますが、一方で運用上の制約やコスト面の課題も存在します。
- 契約の種類によっては対応できない
- 契約締結日のバックデートができない
- システムのランニングコストが発生する
導入前にこれらのデメリットを理解し、適切な対策や対応を検討することが成功のポイントとなります。
契約の種類によっては対応できない
電子契約はすべての契約に対応しているわけではありません。
特に法律で書面交付が義務づけられている契約や公的手続きに使う文書など、一部の契約書類は電子データ化が認められていない場合があります。
例えば、事業用定期借地権設定契約・任意後見契約・企業担保権の設定又は変更を目的とする契約・農地又は採草放牧地の賃貸借契約は、電子契約が認められていません。
契約締結日のバックデートができない
電子契約では、契約締結日を後から遡った変更(バックデート)ができません。
これは契約の真正性や証拠力を保つために重要なルールです。
そのため、契約書の締結日を任意に操作したい場合や過去の日付を記載する必要がある契約には電子契約は適していません。
システムのランニングコストが発生する
電子契約の利用には、契約管理システムやサービスの利用料といったランニングコストが継続的に発生します。
中長期的に見れば紙の契約書にかかる印刷・郵送費等より割安になるケースが多いものの、初期導入時や小規模事業では負担に感じることもあります。
費用対効果を見極め、適切なサービスを選びましょう。
印紙税に関するよくある質問

ここでは、印紙税に関するよくある質問に回答します。
Q.収入印紙を貼り忘れた場合は?
A.契約書などに必要な収入印紙を貼り忘れると、追徴課税や罰則の対象になることがあります。
発見した場合は、遅れて貼ることや、不足分を追加で貼付する必要があります。
税務調査によって発覚した場合、過少申告加算税などが課せられる場合もあるため注意しておきましょう。
Q.収入印紙を多く貼ってしまった場合は?
A.収入印紙を多く貼ってしまった場合は、状況によって対応が異なります。
例えば、収入印紙を使用していなかったり、非課税文書に貼り付けてしまった場合は、郵便局の窓口で交換が可能です。
一方、課税文書へ収入印紙を多く貼ってしまった場合は、税務署での手続きが必要になります。
Q.領収書を分割すれば印紙税を削減できる?
A.領収書を複数に分割することで印紙税の削減が可能です。
例えば、9万円の領収書には200円の収入印紙が必要ですが、3枚に分割すればそれぞれが非課税となります。
ただし、経理上の問題で受け取り側から分割を断られる可能性があるため注意してください。
Q.電子契約にすると本当に印紙税は不要?
A.電子契約は、印紙税の課税対象外となるため収入印紙は不要です。
そのため、作成したPDFファイルをメールに添付したり、電子契約システムによる締結によって印紙税の削減が可能です。
Q.印紙税は契約の当事者どちらが負担する?
A.印紙税の負担者は、法律で定められていません。
一般的には契約書の取り決めや商習慣に従い、当事者間で協議のうえ決定します。負担を相手に負わせたい場合は、その旨を契約書に明記しておくとよいでしょう。印紙税の削減を目指すなら、電子契約サービスのGMOサインの導入がおすすめです。
GMOサインは月額8,800円(税込9,680円)で、電子契約に関する基本機能とともに、差込文書一括送信や閲覧制限、ワークフロー機能など多彩な機能を提供し、業務の効率化を強力にサポートします。
また、電子署名法に準拠したサービスで法的な安全性も確保されており、証明書付きの電子契約が可能なため印紙税は不要です。さらに、導入後は使い方動画やサポート、導入支援など充実したフォローがあり、初めての電子契約でも安心して利用できます。
印紙税の節約だけでなく、紙の印刷・郵送コストの削減や契約業務の迅速化も見込めるため、コスト削減と業務効率化を同時に実現したい方に適しています。
まとめ
印紙税は契約書や領収書など特定の文書に対して課される国税であり、経済取引の透明性確保に重要な役割を果たしています。
課税対象となる文書は印紙税法で定められた20種類の課税文書に限られ、その種類や契約金額に応じて収入印紙の金額が異なります。すべての契約書に収入印紙が必要なわけではなく、非課税とされる文書や電子契約の利用により負担軽減も可能です。
さらに、電子契約には印紙税節約以外に業務効率化やコスト削減、管理の簡単化、場所を問わない契約の柔軟性、コンプライアンス強化といった多くのメリットがあり、企業の業務改革に貢献します。
ただし一部契約には電子データ化できない制約やコストも存在するため、導入時には注意が必要です。
- ※本記事は、起業の窓口編集部が専門家の監修または独自調査(アンケート)に基づいて制作したものです。
- ※掲載している情報は、記事公開時点の法令・税制・商品・サービス等に基づくものであり、将来的に変更される可能性があります。
- ※アンケート調査に関する記述は、特定の調査対象者からの回答結果および編集部の見解を含んでおり、内容の正確性・完全性を保証するものではありません。
- ※記事の内容は一般的な情報提供を目的としており、すべての方に当てはまるものではありません。個人の状況に応じた具体的な助言が必要な場合は、専門家にご相談ください。
- ※情報の利用や判断、実施については、ご自身の責任で行っていただきますようお願いいたします。
- ※本記事に掲載された内容の転載・複製はご遠慮いただき、引用の際は必ず出典をご明記ください。



 シェア
シェア