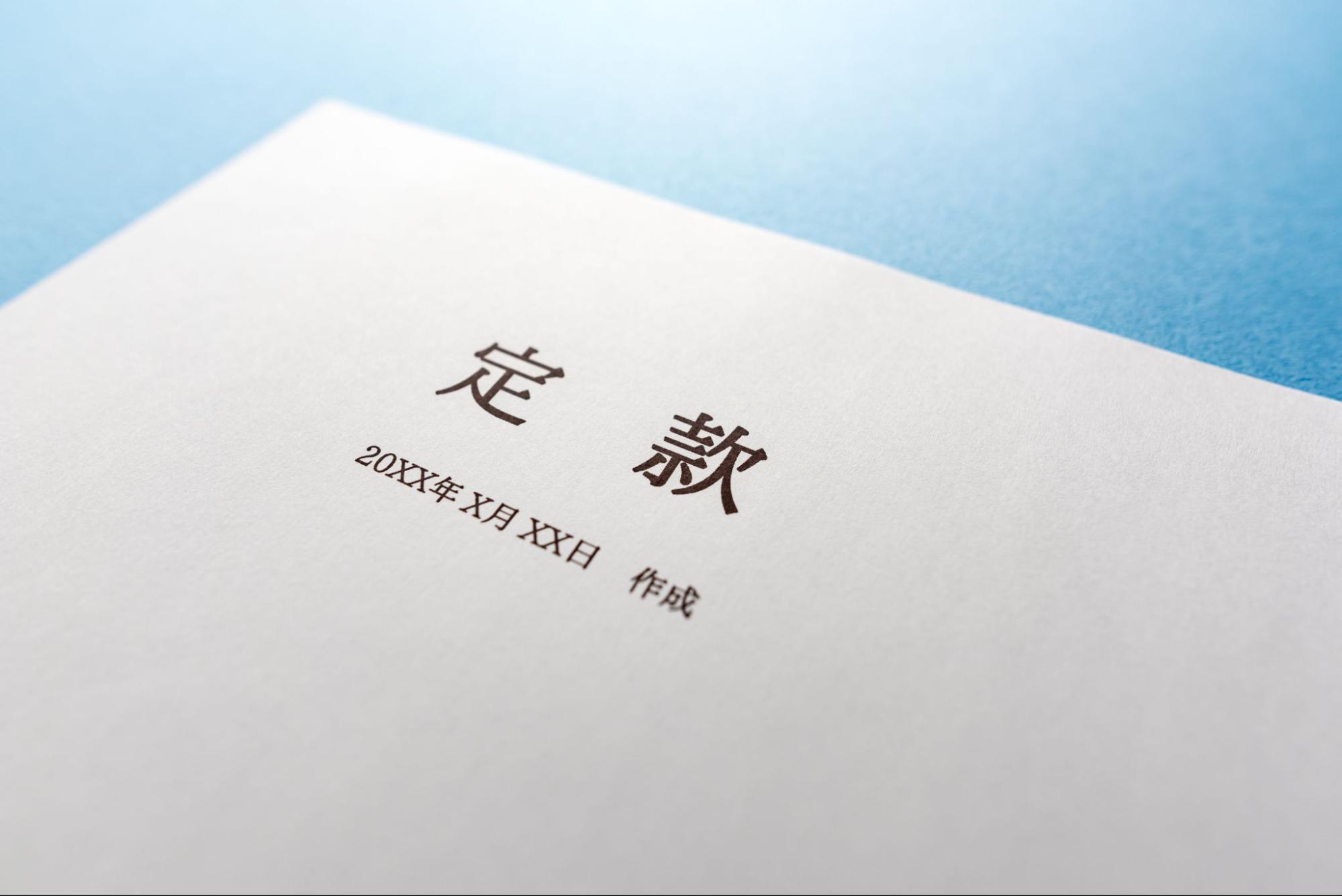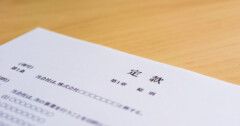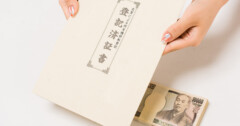【2026年最新】会社設立時に活用できる補助金まとめ|基礎知識から活用メリット・主要制度まで紹介
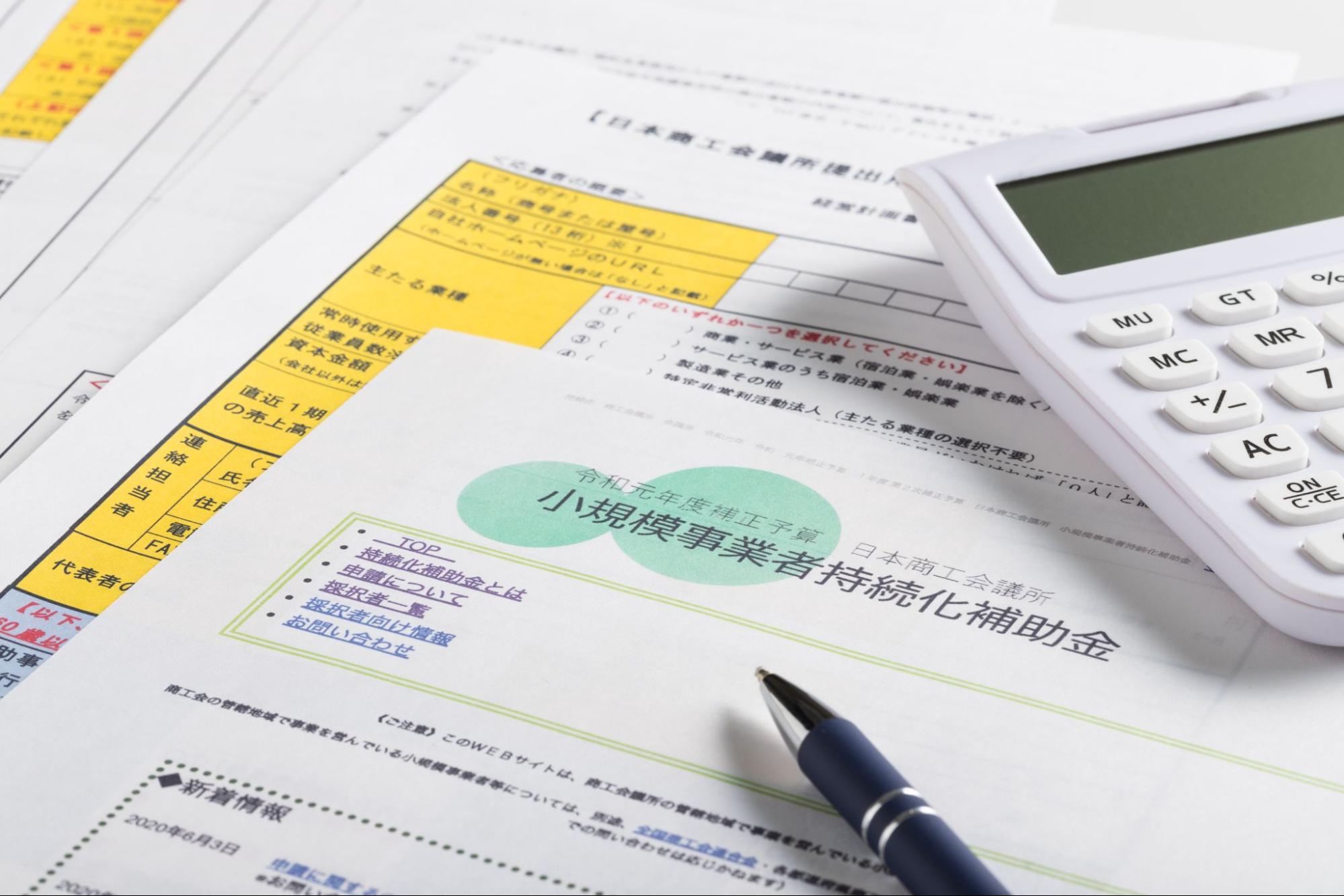
会社設立や起業の際には、資金調達が大きな課題となります。
そのようなシーンで頼りになるのが、国や地方自治体が事業者を支援するために提供する補助金制度です。補助金は返済不要で事業の立ち上げや拡大に必要な資金を確保できるため、多くの起業家や中小企業にとって強力なサポートとなります。
この記事では、補助金の基本的な仕組みや目的、対象者、そして助成金との違いについて分かりやすく解説します。また、会社設立時に補助金を利用するメリットやデメリット、代表的な補助金制度も紹介し、これから起業を考える方が適切に制度を利用できるようサポートします。
- 【この記事のまとめ】
- 補助金は返済不要であり、採択を受ければ会社設立後の大きなサポートになります。
- 補助金の申請によって、事業計画の見直しができるメリットがあります。
- 補助金の申請時には、書類作成の時間や審査通過、入金されるタイミングの遅さに注意が必要です。
【前提確認】補助金とは?

補助金とは、国や地方自治体が特定の政策目標を達成するために、事業者に対して資金の一部を給付する制度です。
返済の必要がなく、事業の立ち上げや拡大、設備投資、販路開拓などの支援を受けられます。ただし、目的に沿った使い道に限られ、適切な報告と実績の提出が求められます。
目的
補助金の主な目的は、国や地域の政策目標に沿った経済活動を促進することです。
例えば、中小企業の生産性向上、地域の産業振興、環境に配慮した事業展開、DX化の推進などが挙げられます。補助金を通じて、事業者が取り組みたいが資金面で難しいプロジェクトを後押しし、社会全体の発展につなげることを狙いとしています。
対象者
補助金の対象者は、募集要項によって異なりますが、一般的には個人事業主、中小企業、小規模事業者などが該当します。
業種や従業員数、設立年数などの条件が設定されることが多く、例えば設立5年以内の法人や従業員20人以下の事業者など、支援を必要としている層を対象としています。
正確な対象要件は、各補助金の公募要領で確認しましょう。
財源
補助金の財源は、主に税金です。
国や地方自治体が国民から集めた税収をもとに、公共の利益を目的として支出されます。
そのため、補助金の使い道には透明性と適正性が求められ、不正利用や目的外の使用が発覚した場合には、返還命令や法的措置がとられる可能性があります。補助金は無償ではあるものの、公的資金であるという意識が重要です。
助成金との違い
補助金と助成金はともに返済不要の支援金ですが、目的や審査方法に違いがあります。
助成金は厚生労働省が管轄し、雇用保険料を財源としており、主に雇用の維持・拡大や職場環境の改善を目的としています。要件を満たせば原則として支給されるため、審査は比較的通りやすいです。
一方、補助金は経済産業省などが出し、税金を財源とし、政策に沿った事業提案の中から採択される仕組みのため、競争率が高く、審査も厳しい傾向にあります。
【重要】会社設立時に補助金を利用するメリット

会社設立時の補助金利用には、以下のようなメリットがあります。
- 原則返済の義務がない
- 会社設立時に足りない資金を補える
- 大きな補助を受けられる場合もある
- 事業計画の見直しができる
ここでは、会社設立時に補助金を利用するメリットについて解説します。
原則返済の義務がない
補助金には原則として返済の義務がありません。
会社設立時の資金調達において借入のような返済負担や利息が生じず、リスクを抑えた資金調達方法として非常に有効です。
特に創業期は資金繰りが厳しいため、返済不要の補助金は資金計画に安心感をもたらします。また、不正受給や目的外の使用がなければ返還請求をされることもないため、適切に活用すれば大きなメリットとなります。
会社設立時に足りない資金を補える
会社を設立する際は、事業開始に必要な資金が自己資金だけでは不足することが多いです。
補助金は不足分を補う重要な資金源となり、設備投資や宣伝費、ITツール導入費用など、多様な費用に充てられます。資金の一部を補助金でまかなうことで、本来ならば融資などで調達しなければならないコストや手間を軽減でき、事業運営により集中できます。
大きな補助を受けられる場合もある
補助金には数百万円から数千万円、場合によっては数億円規模の支援が受けられるものもあります。
特にものづくり補助金や事業再構築補助金などは大規模な設備投資や事業転換を支援し、会社設立直後の成長段階でも活用可能です。
こうした大きな補助を受けることで、初期の資本金以上の投資が可能となり、競争力強化や新たな市場開拓につながります。
事業計画の見直しができる
補助金申請には通常、詳細な事業計画書が必要です。
そのため、申請準備の過程で自社の事業内容や将来展望を改めて整理し、事業計画を見直す良い機会となります。計画を見直すことで不足点や課題に気づきやすくなり、より実効性の高い経営戦略を立てられるようになるでしょう。
補助金申請を通じて事業の方向性を明確にできるのは、大きなメリットの一つです。
【注意】会社設立時に補助金を利用するデメリット
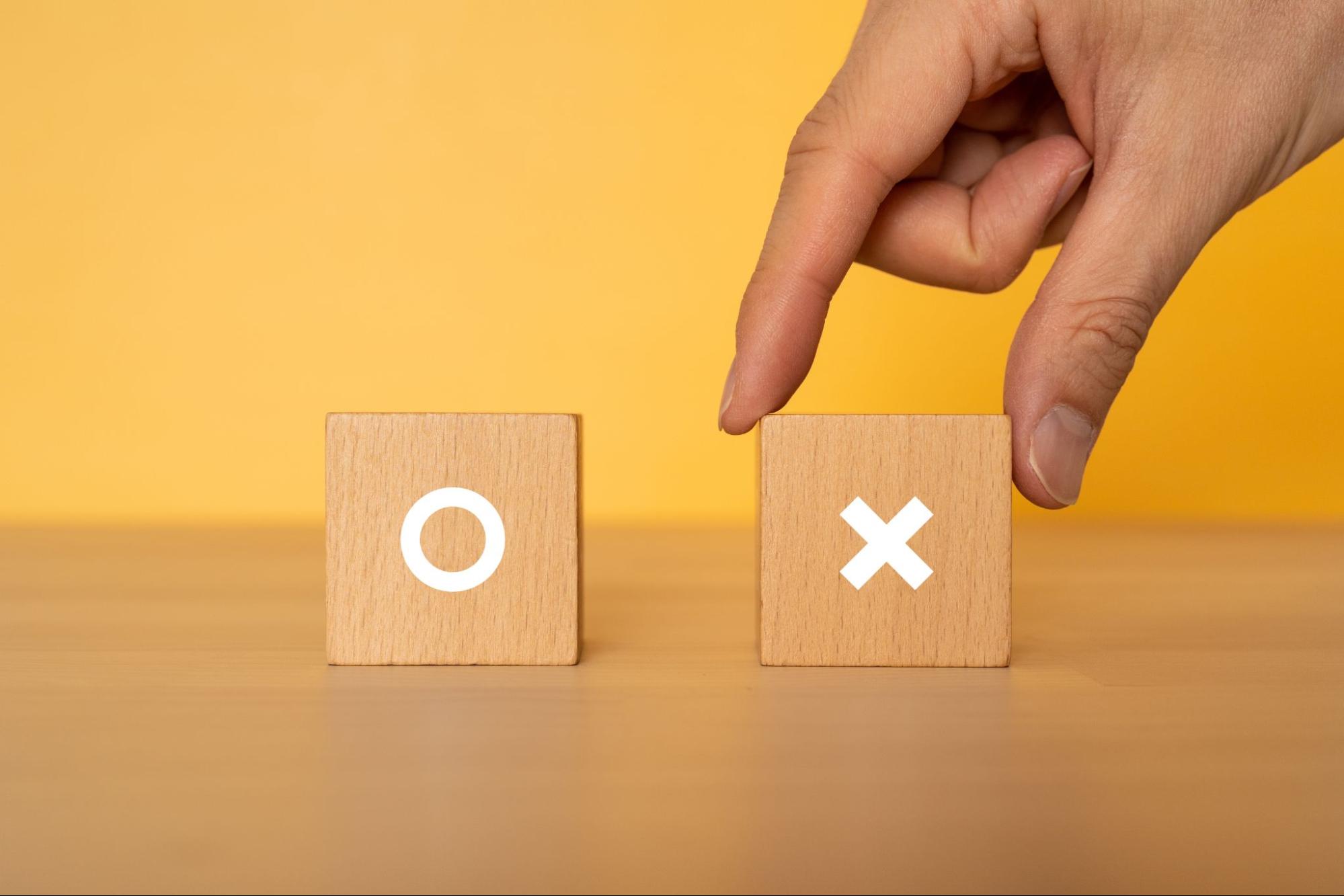
会社設立時の補助金利用にはメリットがある一方でデメリットも存在します。
- 申請に必要な書類作成に手間がかかる
- 審査に通らなければ支給されない
- 入金されるタイミングが遅い
ここでは、会社設立時に補助金を利用するデメリットについて解説します。
申請に必要な書類作成に手間がかかる
補助金の申請には詳細な書類作成が求められます。
事業計画書をはじめ、申請書類全般の作成には時間と労力がかかり、初めて取り組む場合は数十時間、場合によっては2週間以上費やすケースも珍しくありません。
手続きの準備によって本業がおろそかになるリスクがあるほか、専門的な知識が必要なため外部の専門家に依頼するケースも増えています。
審査に通らなければ支給されない
補助金は申請すれば必ずもらえるわけではなく、厳しい審査に通過する必要があります。
書類内容の充実度や事業の実効性、要件の適合性などが評価され、審査に落ちると一切支給されません。
特に大規模な補助金の場合は競争率も高く、採択率が30%前後にとどまることもあります。そのため、審査に落ちるリスクを考慮し、申請準備に十分な時間と労力をかける必要があります。
入金されるタイミングが遅い
補助金は原則として事業実施後、報告書提出や審査を経てから支給される後払い方式が一般的です。
そのため、申請後すぐに資金が入金されるわけではなく、入金までに数ヶ月かかることもあります。
会社設立時の資金として補助金を計画する場合、補助金支給までの期間中は、自己資金や融資などで資金繰りを行う必要があり、資金計画を綿密に立てることが重要です。
会社設立の前後に使える補助金6選
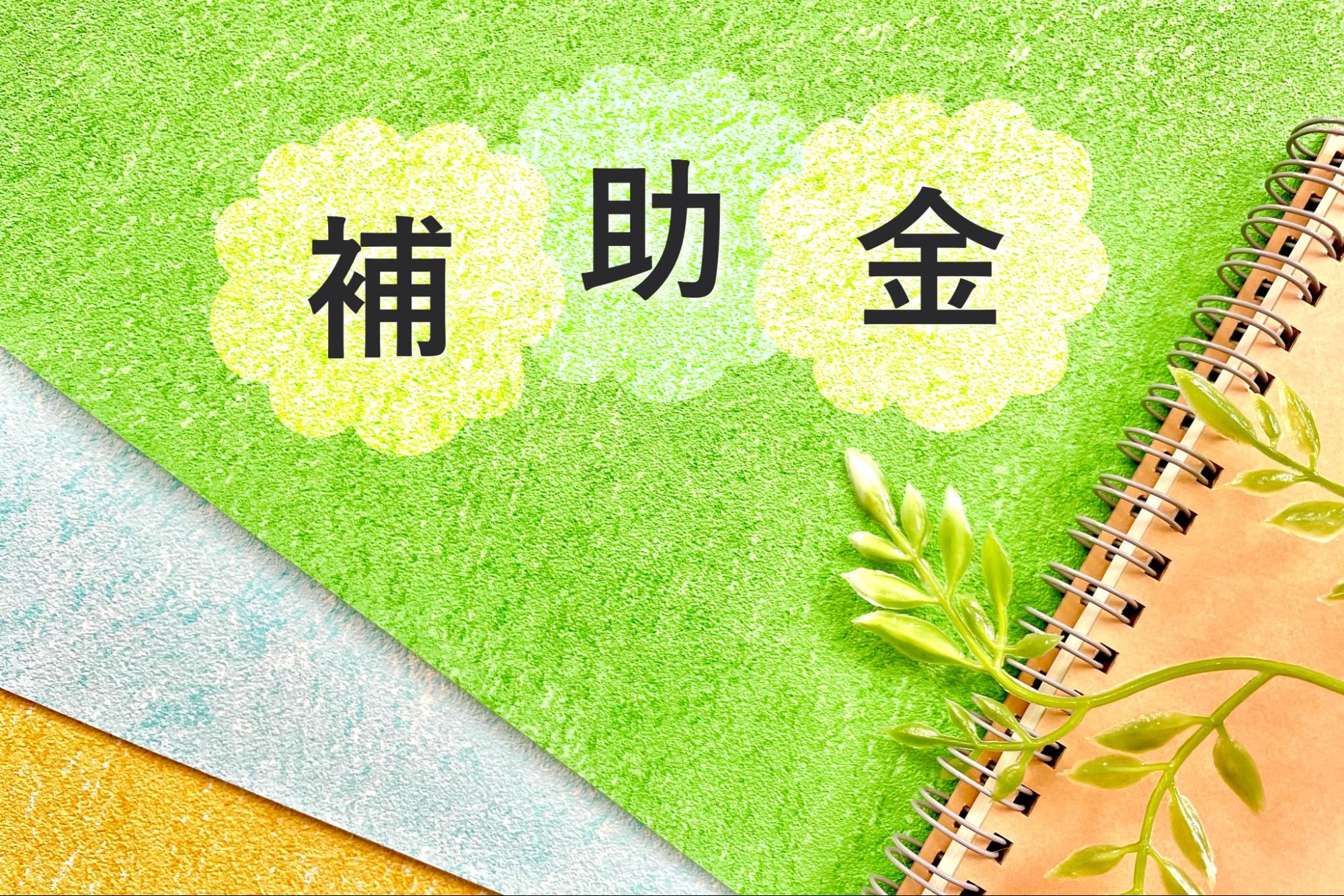
会社設立の前後には、多様な補助金制度を活用することで資金面の支援を受けることが可能です。
特に以下6つの補助金は、会社設立時に検討すべき制度です。
- 小規模事業者持続化補助金
- ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金
- IT導入補助金
- 中小企業省力化投資補助金
- 事業再構築補助金
- 事業承継・M&A補助金
ただし、補助金ごとに対象や条件、補助内容が異なるため、自社の状況に合ったものを選んで申請を検討しましょう。
小規模事業者持続化補助金
小規模事業者持続化補助金は、従業員数が商業・サービス業で5人以下、製造業などで20人以下の小規模事業者を対象に、販路開拓や業務効率化など経営の持続的発展を支援する補助金です。
| 申請枠 | 補助率 | 補助上限 | インボイス特例 |
|---|---|---|---|
| 通常枠 | 2/3 | 50万円 | 50万円を上乗せ |
| 賃金引上げ枠 | 2/3 ※赤字事業者は3/4 |
200万円 | |
| 卒業枠 | 2/3 | 200万円 | |
| 後継者支援枠 | 2/3 | 200万円 | |
| 創業枠 | 2/3 | 200万円 |
出典:小規模事業者持続化補助金
広告宣伝費、店舗改装費、新商品開発費などが対象経費となり、補助上限額は通常50万円、賃金引上げや創業枠など特定要件を満たす場合は最大200万円まで拡大されます。
また、免税事業者から適格請求書発行事業者へと転換する小規模事業者に対するインボイス特例を設けており、要件を満たせば補助上限額が一律50万円上乗せされます。
ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金
ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金は、通称「ものづくり補助金」として知られ、中小企業や小規模事業者を対象に、革新的な製品やサービスの開発、海外需要開拓に対して支援する補助金です。
| 申請枠 | 補助率 | 補助上限 |
|---|---|---|
| 製品・サービス高付加価値化枠 | 中小企業:1/2 小規模企業・小規模事業者および再生事業者:2/3 |
従業員5人以下:750万円 従業員6~20人:1,000万円 従業員21~50人:1,500万円 51人以上:2,500万円 |
| グローバル枠 | 中小企業:1/2 小規模企業・小規模事業者:2/3 |
3,000万円 |
出典:ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(第 21次公募要領概要版)
大規模な設備投資や技術導入費用が対象となり、補助額は数百万円から最大で数千万円規模まで多様です。会社の成長期に大きな投資を必要とする際に活用しやすい制度です。
IT導入補助金
IT導入補助金は、中小企業・小規模事業者が業務効率化やDX化を進めるためにITツールの導入費用を支援する補助金です。
| 申請枠 | 補助率 | 補助上限 |
|---|---|---|
| 通常枠 | 1/2(地域別最低賃金+50円以内で雇用する従業員が全体の30%以上の場合は2/3) | 450万円 |
| インボイス枠(インボイス対応類型) | 中小企業:3/4 小規模事業者:4/5 補助額が50万円超~350万円以下の部分:2/3 |
350万円 |
| インボイス枠(電子取引類型) | 中小企業・小規模事業者:2/3 その他の事業者:1/2 |
350万円 |
| セキュリティ対策推進枠 | 中小企業・小規模事業者:2/3 その他の事業者:1/2 |
100万円 |
| 複数社連携IT導入枠 | 対象経費によって異なる | 3,000万円 |
出典:IT補助金2025
主に在庫管理システムや決済ソフト、ハードウェア、インボイス制度に対応した受発注システム、ネットワーク監視システムなどが補助の対象となります。
また、申請枠によって補助率と補助上限が異なります。例えば通常枠の場合、補助上限は通常450万円です。
なお、導入を希望するITツールは事務局登録済みのものである必要があり、IT導入支援事業者と連携して申請します。
中小企業省力化投資補助金
省力化投資補助金は、中小企業の省力化投資を促進することを目的とした補助金です。
| 申請枠 | 補助率 | 補助上限 |
|---|---|---|
| カタログ注文型 | 1/2 | 従業員5名以下:200万円(300万円) 従業員6~20名以下:500万円(750万円) 従業員21名以上:1,000万円(1,500万円) ※()内は賃上げ要件を満たした場合 |
| 一般型 | 中小企業(補助額1,500万円まで):1/2(2/3) 中小企業(補助額1,500万円超の部分):1/3 小規模企業者・小規模事業者・再生事業者(補助額1,500万円まで):2/3 小規模企業者・小規模事業者・再生事業者(補助額1,500万円超の部分):1/3 |
従業員5名以下:750万円(1,000万円) 従業員6~20名以下:1,500万円(2,000万円) 従業員21~50名:3,000万円(4,000万円) 従業員:51~100名:5,000万円(6,500万円) 従業員100名以上:8,000万円(1億円) ※()内は大幅な賃上げを行う場合 |
出典:中小企業省力化投資補助金
主にIoTやロボットなど自動化機器の導入費用が補助対象です。投資によって生産性の向上やコスト削減を図りたい事業者に向いています。
特にカタログ注文型では、カタログ掲載の製品から自社の業務に合ったものを選べるため、比較的簡単に省力化投資を実現できるでしょう。
事業再構築補助金
事業再構築補助金は、成長分野進出や業態変更、新規事業開始など事業再構築を支援するための補助金です。
| 申請枠 | 補助率 | 補助上限 |
|---|---|---|
| 成長分野進出枠(通常類型) | 中小企業者等:1/2(2/3) 中堅企業等:1/3(1/2) ※()内は短期に大規模な賃上げを行う場合 |
従業員20名以下:1,500万円(2,000万円) 従業員21~50名:3,000万円(4,000万円) 従業員51~100名:4,000万円(5,000万円) 従業員101人以上:6,000万円(7,000万円) ※()内は短期に大規模な賃上げを行う場合 |
| 成長分野進出枠(GX進出類型) | 中小企業者等:1/2(2/3) 中堅企業等:1/3(1/2) ※()内は短期に大規模な賃上げを行う場合 |
従業員20名以下:3,000万円(4,000万円) 従業員21~50名:5,000万円(6,000万円) 従業員51~100名:7,000万円(8,000万円) 従業員101人以上:8,000万円(1億円) ※()内は短期に大規模な賃上げを行う場合 |
| コロナ回復加速化枠(最低賃金類型) | 中小企業者等:3/4(2/3) 中堅企業等:2/3(1/2) ※()内はコロナが影響した債務の借り換えを行っていない場合 |
従業員20名以下:500万円 従業員6~20名:1,000万円 従業員21名以上:1,500万円 |
補助上限は数千万円から最大で数億円に及ぶこともあり、会社設立後の大きな飛躍や事業転換期に活用されます。
ただし、申請には厳格な要件があり、設立したばかりの新しい会社の場合は採択されるのが難しいでしょう。
事業承継・M&A補助金
事業承継・M&A補助金は、中小企業の事業承継及びM&Aの促進を目的とした補助金で、後継者不足などの問題を抱える企業に対し、事業承継に必要な専門家活用費用や設備投資費用を補助します。
| 申請枠 | 補助率 | 補助上限 |
|---|---|---|
| 事業承継促進 | 小規模事業者:2/3 その他の企業:1/2 |
800万円(1,000万円) ※()内は補助事業期間に一定の賃上げを行う場合 |
| 専門家活用 | 買い手支援類型(Ⅰ型):2/3 売り手支援類型(Ⅱ型):2/3(1/2) ※()内は一定の要件を満たす場合 |
600万円 |
| 廃業・再チャレンジ | 2/3 ※併用申請の場合は他申請枠の補助率に従う |
150万円 |
| PMI推進 | 1/2 | 150万円 |
例えば、先代の経営者から事業を引き継ぎ、後継者が経営の安定化や新たな成長戦略を実現するために利用されるケースなどに利用されます。
まとめ
補助金は、会社設立時や事業拡大において非常に有用な資金調達手段のひとつです。返済の義務がなく、事業の推進に必要な資金を確保できるため、経営の安定化や成長加速に大きく寄与します。
一方で、申請には詳細な事業計画の策定や多くの書類作成が必要であり、審査を通過しなければ支給されないリスクもあります。
また、補助金の支給は原則事業実施後となるため、入金までの資金繰りを計画的に行うことも重要です。
各補助金の特徴や対象条件を理解し、自社の状況に最適な制度を活用することで、会社設立時の負担を軽減し、成功への一歩を踏み出しましょう。
- ※本記事は、起業の窓口編集部が専門家の監修または独自調査(アンケート)に基づいて制作したものです。
- ※掲載している情報は、記事公開時点の法令・税制・商品・サービス等に基づくものであり、将来的に変更される可能性があります。
- ※アンケート調査に関する記述は、特定の調査対象者からの回答結果および編集部の見解を含んでおり、内容の正確性・完全性を保証するものではありません。
- ※記事の内容は一般的な情報提供を目的としており、すべての方に当てはまるものではありません。個人の状況に応じた具体的な助言が必要な場合は、専門家にご相談ください。
- ※情報の利用や判断、実施については、ご自身の責任で行っていただきますようお願いいたします。
- ※本記事に掲載された内容の転載・複製はご遠慮いただき、引用の際は必ず出典をご明記ください。



 シェア
シェア