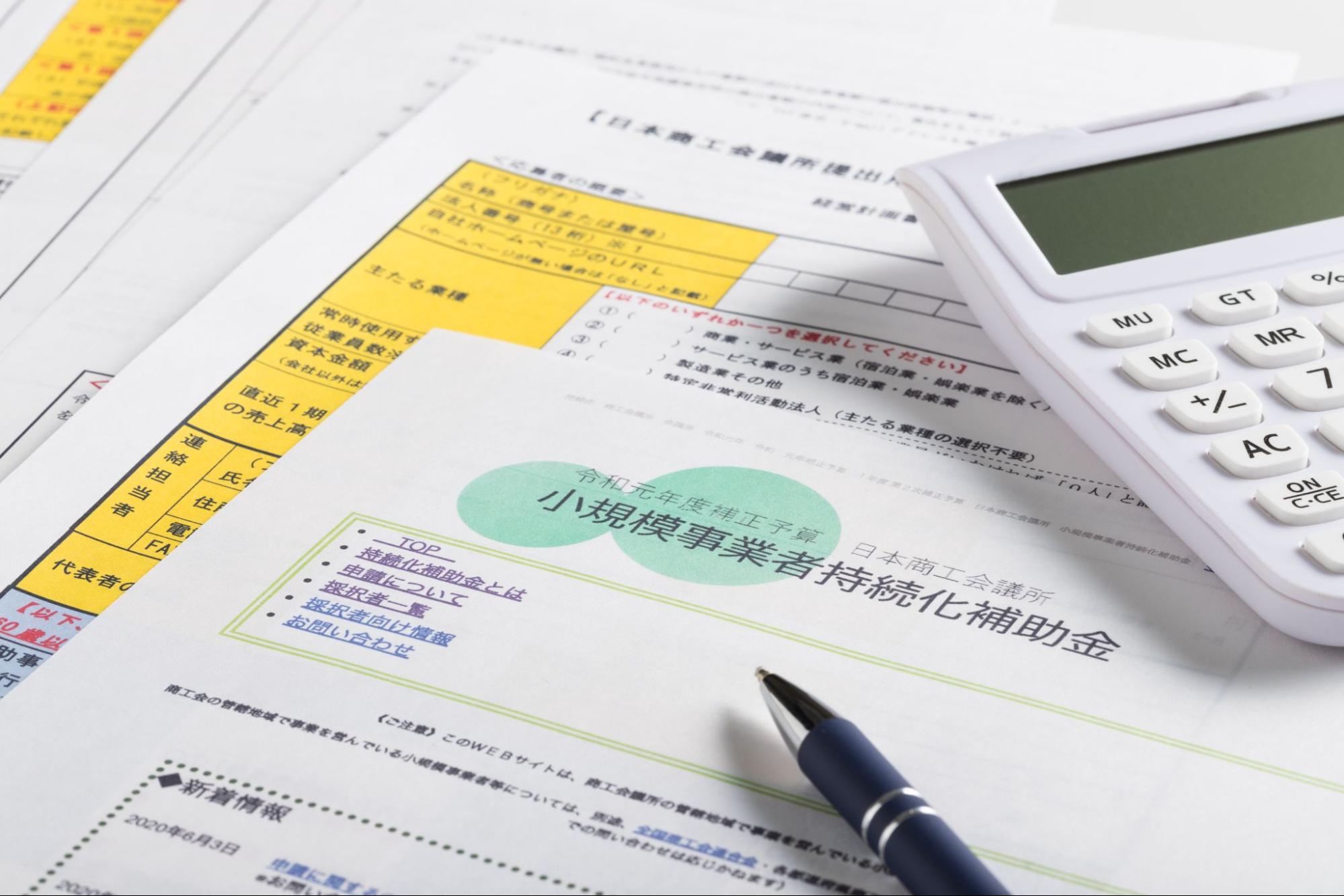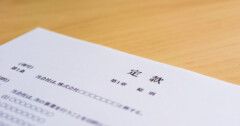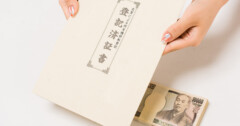電子定款とは?紙定款との違いやメリット・デメリット、作成手順をわかりやすく解説
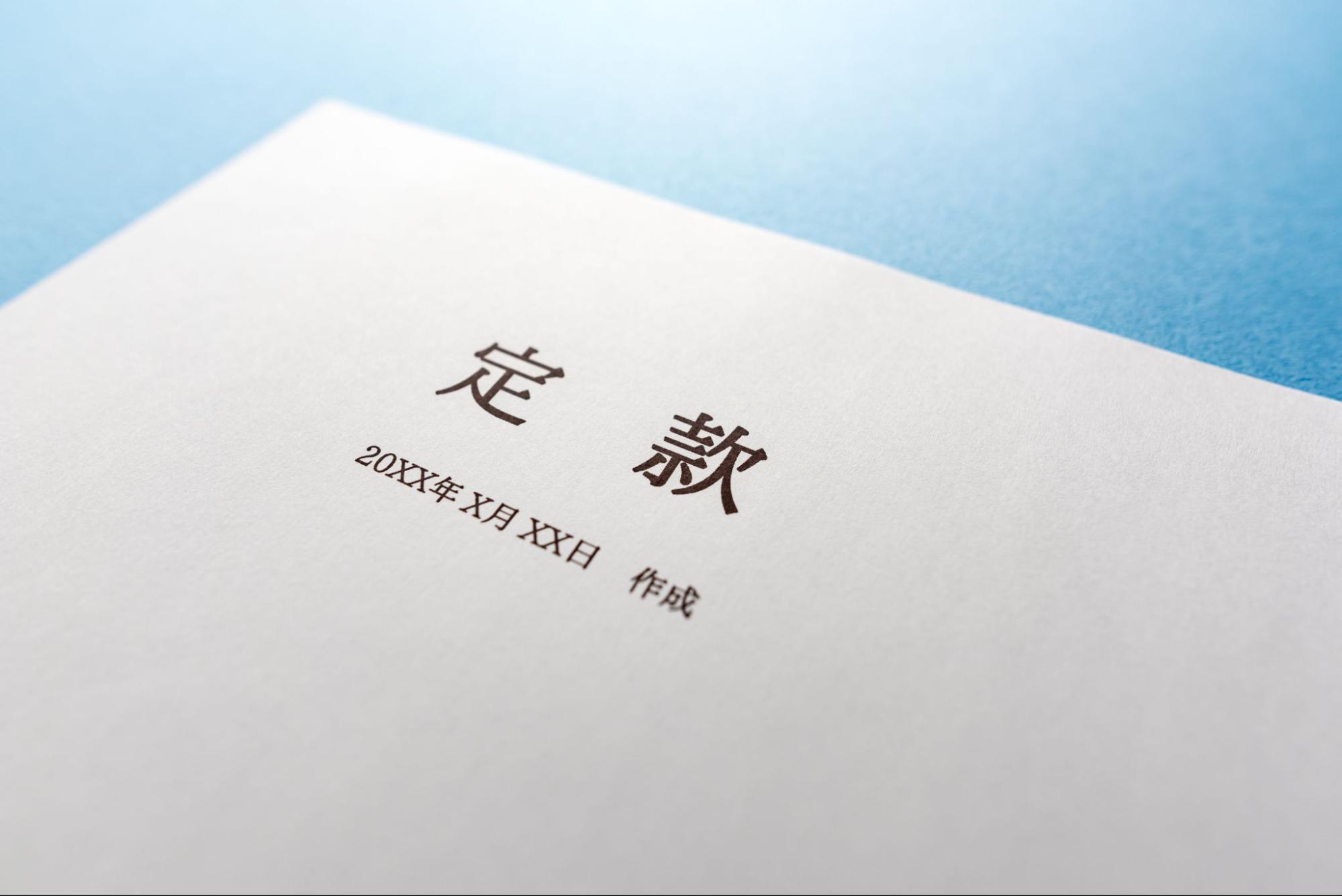
会社設立に欠かせない定款は、これまで紙の書類で作成・認証されてきましたが、近年では電子化が進み電子定款が主流となっています。
電子定款とは、定款をPDF形式の電子データとして作成し、電子署名を施したもので、印紙税節約や手続きの効率化といった大きなメリットがあります。
この記事では、電子定款の基本的な役割や紙の定款との違い、メリット・デメリット、作成から認証までの具体的な手順をわかりやすく解説します。
- 【この記事のまとめ】
- 電子定款は従来の紙の文書ではなく、PDF形式の電子データとして作成して電子署名を付与したものです。
- 電子定款は、従来の紙の定款にかかる4万円の印紙税を節約できます。
- オンライン申請が可能なため、効率的な定款作成が可能です。
【重要】電子定款とは
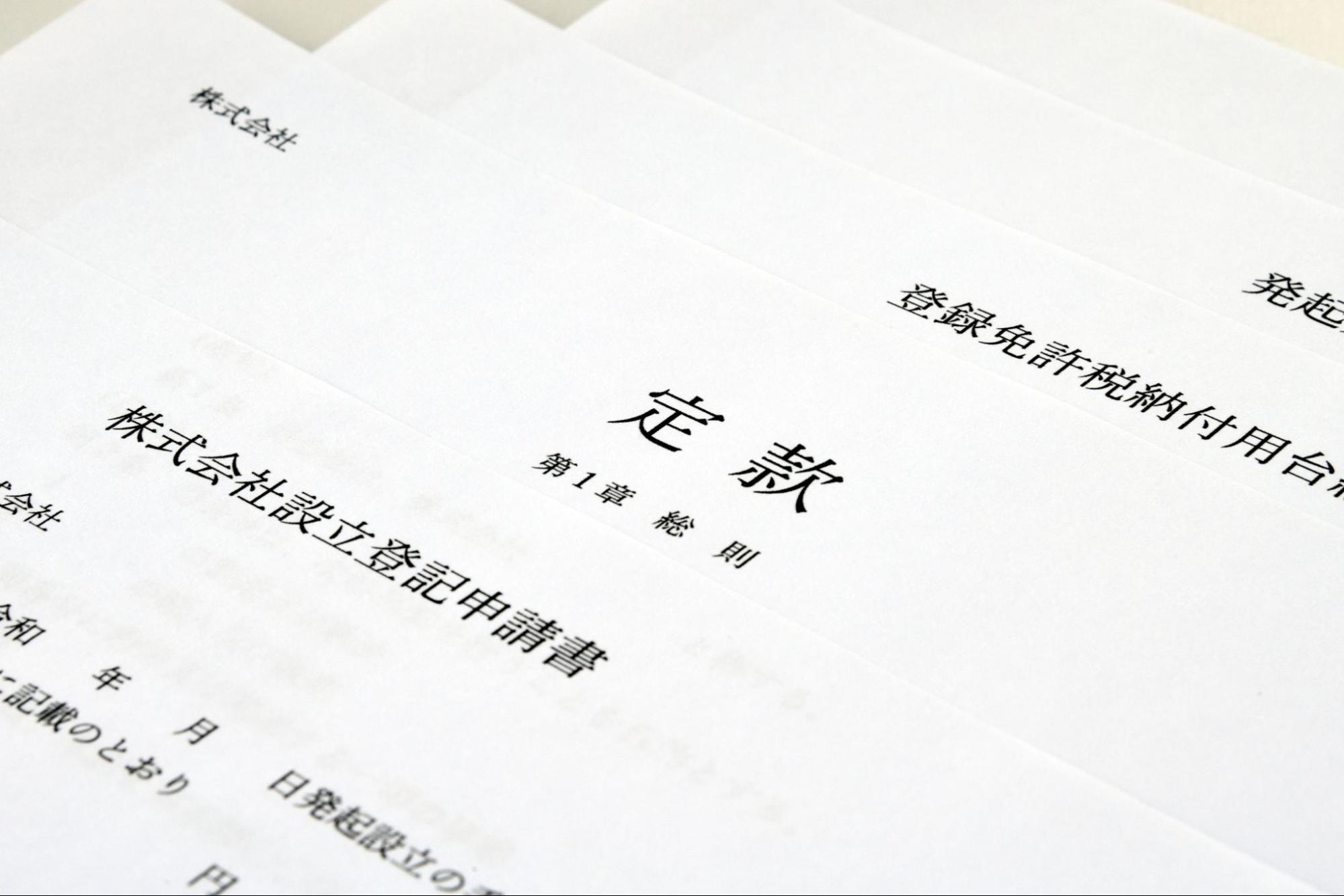
電子定款とは、会社設立の際に必要な定款を紙の文書ではなくPDF形式の電子データとして作成し、電子署名を施したものを指します。
定款は会社の基本ルールや目的、組織運営の原則を定めた重要な書類であり、電子データ化により、印紙税4万円の節約が可能です。
なお、電子定款も紙の定款と同様に法的効力を持ち、公証役場での認証手続きが必要であるため、正確な作成と手続きが求められます。
電子定款の役割
電子定款の役割は、会社設立の基盤となる基本規則を法的効力を持つ形で定めることにあります。
会社の目的や組織形態、業務執行の方法などが明文化され、社内外の関係者に対して会社運営の根拠を示すことが可能です。
また、電子定款により印紙税の負担軽減ができるため、コスト面でも経営者にとって大きなメリットをもたらします。さらに、電子署名を用いることで文書の改ざん防止や信頼性の向上にも寄与しています。
電子定款と紙の定款の違い
電子定款と紙の定款の最大の違いは、印紙税の有無と作成・認証の方法にあります。
紙の定款は印紙税4万円が課される一方、電子定款はPDF化して電子署名を行うことで、印紙税が課されません。
ただし、電子定款の作成には専用のPDF作成ソフトや電子証明書、ICカードリーダーなどの機器が必要で、作成手順がやや複雑です。また、認証手続きもオンラインで申し込みを行い、公証役場での受け取りが必要となる点で異なります。
そのほか、電子定款は改ざんリスクが低いため安全性が高いことも特徴です。
電子定款を利用するメリット

電子定款を利用する主なメリットは、以下の通りです。
- 印紙代の4万円が不要になる
- 作成や保存、提出の効率化が可能
- オンライン申請で全国どこからでも手続きが可能
初期費用となる印紙税の4万円を削減できるほか、作成から保存、提出までをオンライン申請が可能なため、紙の定款に比べて管理が容易です。
ここでは、電子定款を利用するメリットを解説します。
印紙代の4万円が不要になる
電子定款の最大のメリットは、収入印紙代の4万円が発生しない点です。
紙の定款は印紙税法の対象となるため、認証時に4万円の収入印紙を貼付する必要がありますが、電子定款は電子データであるため印紙税の対象外となります。
この節約効果は会社設立時の初期費用削減に大きく貢献し、特に資金に余裕のない起業家にとって大きなメリットになるでしょう。
ただし、電子定款作成に必要なソフトや機器の購入費用と比較して、本当にコスト面でのメリットがあるかは事前に検討が必要です
作成や保存、提出の効率化が可能
電子定款は、作成から提出、保存までを一貫して電子データで行えるため、手続きの効率化が図れます。
定款を専用ソフトで作成後、PDF化して電子署名を付与するだけで認証申請が可能で、印刷や押印の手間が不要です。
また、電子データとして保存できるため、紛失や破損のリスクが低く、必要なときにすぐに取り出せます。長期的な管理においても、紙文書よりも検索性やバックアップの面で優れており、会社運営のデジタル化にも貢献します。
オンライン申請で全国どこからでも手続きが可能
電子定款は、法務省の登記・供託オンライン申請システムを通じて全国の公証役場に申請できるため、居住地にかかわらず手続きが可能です。
特に地方在住者や希望する公証役場が遠方にある場合でも、物理的な移動が不要で済み、時間や交通費の節約になります。
ただし、認証後の電子定款データは公証役場に直接出向いて受け取る必要がある点には注意が必要です。
【注意】電子定款を利用するデメリット

電子定款はコスト削減や効率向上に優れた方法ですが、一方で注意すべきデメリットも存在します。
- 機器や専用ソフトの準備が必要
- 修正や変更の際は再申請に費用がかかる
これらのデメリットを理解したうえで、利用を判断しましょう。
ここでは、電子定款を利用するデメリットを解説します。
機器や専用ソフトの準備が必要
電子定款の作成には、複数の機器やソフトウェアの準備が必要です。
- 電子証明書付きのマイナンバーカード
- 文章作成ソフト(Microsoft Wordなど)
- 電子署名ソフト(Adobe Acrobatなど)
- ICカードリーダライタ
専用機器やソフトウェアの準備には費用と手間がかかるため、初めて電子定款を利用する場合は導入コストが負担になることがあります。
特にソフトの利用料金や機器購入費用が印紙代の節約額を上回ることもあるため、事前に総合的なコストを比較検討しましょう。
修正や変更の際は再申請に費用がかかる
電子定款は一度オンラインで認証申請を行うと、その後の内容修正や変更ができません。
もし修正が必要となった場合は、電子定款を新たに作成し再申請しなければならず、その際に公証役場への再認証手数料が1万5,000円から5万円程度発生します。さらにデータ保存手数料もかかります。
無駄なコストを抑えるためにも、認証申請前に内容を十分に確認しましょう。
【手順】電子定款の作成から認証までの流れ

電子定款の作成から公証役場での認証までの一般的な流れは、以下の通りです。
- 定款の作成とPDF化
- ICカードリーダライタで電子証明書付きマイナンバーカードを読み込む
- PDFにした定款に電子署名を付ける
- オンライン申請システムで申請者情報を登録
- 公証役場の予約を取る
- 必要なものを準備のうえ公証役場へ受け取りに行く
ここでは、電子定款の作成と認証に必要な準備と手続きの流れを詳しく解説します。
必要な機器や環境
電子定款を作成するためには、以下の機器が必要です。
- PDFファイルの作成が可能な文書作成ソフト(例:Microsoft Wordなど)
- 電子証明書付きのマイナンバーカード
- ICカードリーダライタ
- 電子署名が可能なPDF作成ソフト(例:Adobe Acrobat)
また、申請はオンラインで行うため、安定したインターネット環境も整えておきましょう。
定款の作成とPDF化
まず会社の基本事項を盛り込んだ定款をMicrosoft Wordなどの文書作成ソフトで作成し、内容に誤りがないか慎重に確認します。
特に「絶対的記載事項」は、定款に必ず記載しないといけません。
以下の項目の漏れがないかを確認しておきましょう。
- 事業目的
- 商号
- 本店所在地
- 出資額
- 発起人の氏名および住所
なお、作成した定款はPDF形式で保存します。
記載内容に不安があれば、メールやFAXで公証役場にデータを送付し、事前確認してもらうことも可能です。
ICカードリーダライタで電子証明書付きマイナンバーカードを読み込む
PDFデータに電子署名を付けるための準備を行います。
ICカードリーダライタでマイナンバーカードに内蔵された電子証明書を読み込んでください。
なお、ICカードリーダライタは、3,000円~5,000円程度で販売されているため、電子定款を作成する際は事前に購入しておきましょう。
PDFにした定款に電子署名を付ける
読み込んだ電子証明書を利用して、PDF化した定款に電子署名を付与します。
署名が付けられた電子定款は法的効力を持ち、変更や改ざんの防止が可能です。
また、署名付与には専用のプラグインソフトを使うケースが一般的です。
オンライン申請システムで申請者情報を登録
PDFデータに電子署名を付与させたら、認証手続きが必要です。
まずは法務省の登記・供託オンライン申請システムで、利用者情報を登録します。
登録後、申請用総合ソフトをダウンロード・インストールして、電子署名付きの電子定款ファイルをアップロードしてください。
公証役場の予約を取る
電子定款の認証は公証役場で行うため、事前に電話やWebで予約を取る必要があります。
予約が取れたら、当日に向けて必要書類や持ち物を再度確認しましょう。
必要なものを準備のうえ公証役場へ受け取りに行く
予約日に公証役場へ赴き、認証済みの電子定款を受け取ります。
その際に必要なものは、以下の通りです。
- USBメモリなどの記録媒体
- 印刷した電子定款
- 発起人の印鑑証明書
- 電子署名を行った発起人以外の委任状
- 認証手数料(1万5,000円~5万円)
- 本人確認書類
- 印鑑
定款データを受け取れば、電子定款の認証手続きは完了です。
電子定款の作成が難しければ専門家への依頼がおすすめ

電子定款の作成は、専用機器やソフトの準備、細かな法律知識が必要なため、初めての方には難しい場合があります。
そのような場合は、司法書士や行政書士、税理士といった専門家への依頼がおすすめです。
専門家に依頼すれば、定款の作成から電子署名、申請手続きまでスムーズかつ正確に進められるため、手続きのミスや手間を大幅に減らせます。
また、専門知識が必要な複雑なケースでも安心して任せられるため、起業準備に集中できるメリットもあります。費用はかかりますが、時間や労力を節約し、安心して会社設立を進めたい方には非常に有効な選択肢です。
電子定款に関するよくある質問

ここでは、電子定款に関するよくある質問に回答します。
Q.電子定款を作成する際にマイナンバーカードは必要ですか?
A.電子定款の作成には、原則マイナンバーカードが必要です。
マイナンバーカードには電子署名を行うための電子証明書が付随しており、作成には欠かせません。
ただし、住民基本台帳カードを取得している場合は一部代用可能な場合もありますが、新規発行は終了しているため、マイナンバーカードの取得が現実的です。
Q.電子定款は合同会社でも必要ですか?
A.合同会社の設立では、定款の認証手続き自体が不要なため、電子定款の認証も必要ありません。
しかし、電子定款による作成や管理の利便性を考慮して活用するケースはあります。特に電子データでの管理を希望する場合は電子定款を利用しても問題ありませんが、法的義務としては必要ありません。
Q.電子定款の認証にはどのくらい時間がかかりますか?
A.電子定款の認証手続き自体は、オンライン申請後、通常は数日以内に完了します。
ただし、公証役場での認証は予約制であり、混雑状況や予約の取りやすさにより変動します。そのため、オンライン申請の受付から公証役場での認証受け取りまで、全体で1週間~2週間程度を見ておくとよいでしょう。
Q.電子定款の内容を後から変更したい場合はどうすればいいですか?
A.電子定款は一度オンラインで申請すると、その後内容の修正ができません。
変更が必要な場合は、新たに電子定款を作成し、再度認証申請を行う必要があります。この際に公証役場の認証手数料などの追加費用が発生します。
そのため、申請前に内容を十分に確認し、ミスがないように注意することが重要です。
まとめ
電子定款は、会社設立に欠かせない定款を電子データとして作成する方法です。
電子データ化によって、印紙税4万円を節約できます。さらに、書類の作成から提出、保存までをオンラインで効率的に行えるため、時間やコストの大幅な削減につながります。
一方で、機器やソフトの準備が必要であることや、申請後の修正が難しい点には注意が必要です。
初めて電子定款を利用する場合や手続きに不安がある場合は、専門家に相談・依頼するとより安心して進められるでしょう。
- ※本記事は、起業の窓口編集部が専門家の監修または独自調査(アンケート)に基づいて制作したものです。
- ※掲載している情報は、記事公開時点の法令・税制・商品・サービス等に基づくものであり、将来的に変更される可能性があります。
- ※アンケート調査に関する記述は、特定の調査対象者からの回答結果および編集部の見解を含んでおり、内容の正確性・完全性を保証するものではありません。
- ※記事の内容は一般的な情報提供を目的としており、すべての方に当てはまるものではありません。個人の状況に応じた具体的な助言が必要な場合は、専門家にご相談ください。
- ※情報の利用や判断、実施については、ご自身の責任で行っていただきますようお願いいたします。
- ※本記事に掲載された内容の転載・複製はご遠慮いただき、引用の際は必ず出典をご明記ください。



 シェア
シェア